船場の丁稚どん──山片蟠桃補遺(4) [山片蟠桃補遺]

一説に、船場はもともと着船場(ちゃくせんば)、つまり船着き場のことだったとあります(牧村史陽『大阪ことば事典』)。この説にしたがうと、着船場の着がとれて船場になったわけです。たしかに「せんば」という特殊な読み方は、そんなところに由来するのかもしれません。
さて、今回は香村菊雄の『船場ものがたり』 に沿って、話を進めていきましょう。
まず、船場の範囲ですが、それは土佐堀川と東横堀川、そしていまは埋められてしまった西横堀川と長堀川に囲まれた東西に長い長方形の地域でした。昔の大阪は堀川がめぐらされた水の都だったことがわかります。これは物資が水路で運ばれたためですね。
町は碁盤上に形成され、南北に筋、東西に通(とおり)が走っています。江戸時代の町名は、北から南に、北浜、内北浜、今橋、高麗橋、伏見町、道修町(どしょうまち)、平野町、淡路町、瓦町、備後町、安土町、本町、南本町、唐物(からもん)町、北久太郎町、南久太郎町、北久宝寺町、南久宝寺町、博労町、順慶町、安堂寺町、塩町となっていました。だいたい1丁目から5丁目までありました。
町は「ちょう」ではなく「まち」と読みます。いまも残っている町名もあるし、残っていない町名もありますが、その名前をみていると、なんとなく町の由来や扱っている商品がわかってくるから不思議です。
ほかにちいさな町もあります。北浜の東側、土佐堀川に面しているのが大川町(おおかわちょう)です。「ちょう」と読む例外。ここはいまも昔も住友の拠点です。そして、その一本通りを南にはいったところにあるのが、われらが蟠桃の勤めていた升屋のある梶木町(かじきまち)ですね。
船場を横切って通りは城に向かっています。縦の筋として有名なのは、何といっても御堂筋ですね。御堂筋には北御堂(西本願寺)と南御堂(東本願寺)が立っています。だから、御堂筋というわけです。明治以降、御堂筋は大幅に拡張されました。堺筋も同じです。
船場の町をつくったのは、豊臣秀吉です。大坂城築城にあわせて、堺や伏見、平野、伊勢などから商人を呼び寄せて、あきないをさせたといいます。
しかし、秀吉の時代は短く、大坂夏の陣の落城で船場も焼け野原になりました。それを立てなおしたのが徳川幕府です。大坂城は再築され、新たな堀川がつくられ、商業優遇措置がとられ、船場は復興します。
徳川幕府は商人に自由な活動、自由な生活を認めていたわけではありません。むしろ、些細な部分まで統制がおよんでいたというべきでしょう。商人には、生活態度、着る物、持ち物、食事、建物、乗り物にいたるまで、制限が課されていました。基本はぜいたく禁止令です。これに違反した淀屋辰五郎は身代を取り潰されました。ばかばかしいほどの法令ですが、徳川期に、この法令は意外ときいて、船場の商人はぜいたくを慎み、富の蓄積にはげむことになります。
ぜいたく禁止は、けちとしまつの精神へと結実し、商家には上から下までその精神がしみついていきます。
商家の構成は、旦さんを筆頭に、それを補佐する大番頭、その下に番頭、手代がいて、一番下が丁稚です。もちろん、家の中では御寮人(ごりょんさん、若奥さん)が大きな力をもっていて、女衆(おなごし、下女)をまとめるとともに、家内に何かと気を配っています。
丁稚は7、8年修行して、17か18で手代見習になります。それから二十歳をすぎて、番頭の娘や、時に主人に見込まれたときにはいとさん(お嬢さん)を嫁にもらったりして、30そこそこで番頭になるわけです。
番頭になると、別家を認められ、いわば支店のようなものをまかせられることもあります。別家しないで残り、大番頭に進む者もでてきます。蟠桃が選んだのは、この道ですね。主人が幼かったため、蟠桃は実質的に升屋の経営者となり、倒産寸前だった升屋を立てなおすことになります。
ところで、丁稚の話です。丁稚の1日はどんなふうだったのでしょう。
丁稚は商家ではたらく、だいたい10歳から17歳くらいまでの男の子で、番頭や手代に呼び捨てにされ、休む間もなくこきつかわれます。縁故採用が基本です。蟠桃の場合も、おじさんが升屋の番頭を務めていました。
お目見えの日は、店の者に丁稚の呼び名で紹介され、つづいて家族や女衆にも紹介され、ごりょんさんから木綿縞の着物、下着、前垂や草履などをもらいます。女中頭からは箱膳を渡され、食器や箸をもらい、そのしまい方を教わります。掃除の仕方や寝る場所、その他こまごまとしたことを教えてくれるのは先輩の丁稚です。
やっかいなのは船場のことばです。播州のいなかからやってきた蟠桃は、最初、聞き慣れないことばに、ずいぶんとまどったと思いますが、徐々に慣れてきたことでしょう。たとえば、船場では出かけるときに「いて参じます」といわねばならず、それにたいして「はよ、お帰り」ということばが返ってきます。船場では、いまの漫才やコントのようなことばはけっして使わず、なめらかな浄瑠璃のようなことばで、丁寧語の「ござります」や「ござりまへん」がよく用いられていました。
播州にくらべ、船場のことばはやわらかい。ずけずけした言い方はしません。それにどことなくユーモアや皮肉、しゃれも含まれています。蟠桃が番頭である自分に引っ掛けて、一度だけ蟠桃と名乗ったのは、こうしたしゃれ心をきかせたためでしょう。それが、いまでは山片蟠桃という堅苦しい名前になって通用しているのですから、泉下の升屋小右衛門(こえもん、略称、升小)も苦笑いしていることでしょう。
ちなみに香村菊雄によると、谷崎潤一郎が『細雪』でくり広げていることばは、昭和10年代のもので、船場ことばとしては、ずいぶん崩れていて、チャンポン船場弁になっているといいます。
話がちょっと脇にそれてしまいましたが、『船場ものがたり』のえがく丁稚の一日はコマネズミのようにすぎていきます。
いまの時間で朝5時ごろ起きると、自分のふとんをあげ、店の着物に着替え、顔を洗うと、すぐに表の掃除です。終わったら夏なら外に水をまきます。つづいて、店の間にはたきをかけ、隅から隅まで拭き掃除をします。硯の水を替え、たばこ盆を掃除し、灰吹きを洗い、火鉢の灰の処理、花瓶の水の取り替えと目まぐるしく仕事をしたあと、やっと朝食です。早飯早糞が原則。そのあと、仕事にとりかかります。職種によって、その作業はさまざま。升屋のような米仲買にはどんな仕事が待ち受けていたのでしょう。ことこまかな仕事が休む間もなく次々に押し寄せたにちがいありません。
雑用もまたきりがありませんでした。買い物や洗濯物の片づけなど、女衆の手伝いもやらされたかもしれません。いとさんやこいさんの雑用、おえさん(年配のごりょんさん)の仕事、それにだんさんのお供もあったでしょう。「それはもう連続的に、あれやこれやの雑用私用が、よくもこれだけあるものと思うほどあるのであった」と香村菊雄も書いています。
それでいて、給金はなし。番頭さんの言では、店は「金もうけの秘訣を教えてくれはるのに、一文の月謝も取りはらん。あべこべに、ここでは三度の御飯もただで食べさしてくれはる」という理屈になります。
明治の終わりになっても、尋常小学校を出て10歳のころからすぐに丁稚として船場の店に勤める人は多かったようです。松下幸之助もそのひとりでした。「ぼくの場合は(丁稚時代の)生活体験がそのままぼくの人生観をかたちづくってくれたような感じがします」と語っています。
ですから、丁稚の仕事は、学校とはまるで無縁のようにみえて、じつはそれ自体が実地の商業学校だったのです。
すると、蟠桃もまた学校とは無縁だったかというと、そうではありません。むしろ、かれは徳川時代の高等学府ともいえる懐徳堂で学んでいるのです。どうして、そんなことが可能だったのでしょう。そこには升屋主人、二代目平右衛門の考えが強く作用しています。
升屋文書はいま大阪大学の懐徳堂研究センターに預けられ、解読が進められているところです。ですから、これからさまざまな資料がでてくる可能性がありますが、いまのところ升屋平右衛門の考えは推測の域をでません。おそらく平右衛門はこれから商家の経営を担う者には、学問が必要だと考えていたのでしょう。蟠桃はお気に入りの丁稚でした。そのため、平右衛門は蟠桃を懐徳堂で学ばせることにしたのです。丁稚としては破格の扱いです。
当時、大坂を代表する豪商は鴻池ですが、香村菊雄によると、鴻池の3代目善右衛門宗利は、享保17年(1732)におよそ次のような家訓を遺しているそうです。長いので、現代語訳でそのポイントだけを列記しておきます。
「身持ちのよくない者は不適格とみなして、一族相談のうえ追放し、他に相続人を立てること」
「親類や縁者に対しても、金銭を融通することを堅く禁じる」
「本家に多くの子がいた場合でも、先祖から譲り渡された全財産は嫡子に相続させること」
「毎月相談日を決めて万事相談せよ。一存で片付けず、意見一致の上解決すること」
「代々出入りのお大名には、相変わらずご用をつとめなくてはならぬが、新規に出入りを求められて、気軽にお貸しすることはならぬ」
「本業以外の商売に手を出すな」
「当主一族は子や孫までもよく読書すべし。良い先生がいらっしゃれば、家の方へお呼びして講義していただき、手代どもも聴講を受けること。学問も業務以外の勤めと心がけよ」
「別家の手代と本家の手代が、商売向きのことで、内々に打ち合わせることを禁じる」
「気づいたことは、相談のうえ、本家当主に上申して実行せよ。お互いにたしなみ、常に家のためになることをよく考えて油断なく勤めること」
「殺生を楽しむことは堅く禁じる」
「当主はじめ、分家、その子孫の者たちも、成人して遊興で素行を乱すことのないよう」
船場では、鴻池の教訓は、鴻池だけではなく商家全般の教訓として受け止められていたと思われます。特徴的なのは、本業以外の商売に手を出すなとしているところかもしれません。いかにも堅実な姿勢がみてとれます。それと、学問を重視していることですね。実際、鴻池は懐徳堂の運営を支えています。
升屋平右衛門が鴻池の影響を受けたこともじゅうぶんに考えられます。鴻池に見習って、学問がだいじだと思うようになっていたのでしょう。平右衛門もまた懐徳堂の支援者でした。そこで、子飼いの蟠桃を懐徳堂に通わせることになります。
平右衛門には嫡男がいませんでした。生まれた男子は早世し、長女はすでに嫁入りし、いま家には次女のなさしか残っていません。このころ、なさは10歳足らずだったのではないでしょうか。平右衛門の頭には、ひょっとしたら蟠桃をいずれ聟にという思いもかすめたかもしれません。その思いが蟠桃の懐徳堂通いにつながったとみるのは、ちょっとうがちすぎでしょうか。
実際には、4年後、平右衛門は甥っ子を養子に迎えることにしました。このとき養子になった平治郎は15歳。12歳か13歳だったなさと、いずれ結婚することになっています。平治郎が升屋の養子になったとき、蟠桃は17歳です。小説なら、この三者の関係がどんなふうだったか、空想がふくらむところです。
ところが、平治郎を養子に迎えた直後、平右衛門に嫡男、平蔵が生まれたことが、事態を複雑にします。母親は誰だったのでしょう。ぼくなどは、平蔵はおめかけさんから生まれた子どもではないかと疑ってしまいますが、げすの勘ぐりかもしれません。
5年後、平右衛門は亡くなり、平治郎が升屋の家督を継ぎます。しかし、しばらくするうちに升屋は倒産の危機に見舞われます。そのとき、24歳の蟠桃は22歳の平治郎を追放し、8歳の平蔵を擁して、升屋を立てなおすことになるのです。背景に何があったのか。このあたりも興味がつきないところですね。いずれにせよ、手代の蟠桃が経営手腕を発揮するのはこのときからです。
ハラリ『ホモ・デウス』(まとめ) [本]

1 神の人へ
ベストセラーになったハラリの『サピエンス全史』は、ホモ・サピエンス(賢い人)と呼ばれる現世人類が、これまでどのような歴史を歩んできたのかをふり返ったものだった。これにたいし、同じ著者による本書は、その人類がホモ・デウス(神の人)に進化しつつあることを示そうとしている。
最初に著者は、これまで人類につきまとった悩みは、飢餓と疫病と戦争だったと書いている。しかし三千年紀(紀元2001〜3000)にはいったいま、人類はこれまでのそうした悩みを克服しつつあるという。
ほとんどの国では、実際に飢え死にする人は少なくなった。むしろ、過食のほうが飢饉よりもはるかに深刻な問題になりつつある。
疫病や感染症にたいしても、20世紀の医療は空前の成果を挙げた。ペストや天然痘、インフルエンザはもはや脅威ではなくなり、エイズやエボラ出血熱などの新たな感染症にも対処できるようになった。
これからも新たな病原菌が出現する可能性はあるが、けっして悲観するにはおよばない。「自然界の感染症の前に人類がなす術もなく立ち尽くしていた時代は、おそらく過ぎ去った」と著者はいう。
20世紀後半以降、大きな戦争はまれになった。核兵器が戦争の恐怖を思い起こさせるいっぽう、わざわざ戦争をして土地や資源を奪い取る必要もなくなったからだ。国を豊かにするには、戦争より交易のほうが有効であることを人類は学んだ。
サイバー戦争やテロがおこる可能性は残っている。だが、それによって大規模な世界戦争が発生することはまずない、と著者は断言する。
飢饉と疫病と戦争をもはや自然や神のせいにするわけにはいかない。「私たちの力をもってすれば、状況を改善し、苦しみの発生をさらに減らすことは十分可能なのだ」
人類の活動が地球の生態系を破壊し、ひいては人類そのものを危険にさらしつつあることは否定しがたい。だが、それでも、人類は止まることなく、さらなる進化をめざそうとするだろう。その方向を著者はホモ・サピエンスからホモ・デウス(神の人)への進化と名づけている。
これからの人類のプロジェクトのひとつは、不死への戦いである。
人間はいまや生命を技術的に処理しうるようになった。がんやアルツハイマー病はまだ克服されていないが、結核がそうだったように、それが克服されるのも時間の問題だ。腎臓や網膜や心臓も移植できるようになっている。
遺伝子工学や再生医療、ナノテクノロジーの発達はめざましい。20世紀に人類は平均寿命を40歳から70歳に伸ばしたが、21世紀にはそれがさらに伸びる可能性がある。
「死との戦いは今後1世紀間の最重要プロジェクトとなる可能性が依然として高い」。科学界と経済界はそれを応援し、不死を売り物にする大きな市場が生まれることはまちがいないだろう、と著者は予測する。
もうひとつの人類のプロジェクトは、幸福の増進である。
1人あたりGDPが増え、自動車、冷蔵庫、エアコン、洗濯機、テレビ、コンピューターなどの商品が普及し、教育、医療、福祉が充実しても、かならずしも幸福度が増大するとはかぎらない。そのことは先進諸国での自殺率の高さをみてもわかる。GDPはかならずしも幸福度の指数ではない。
幸福度は物質的要素だけではなく、心理的なものや身体的な感覚によっても支えられている。どんなに社会が豊かになっても、そこに不安や緊張、不快感、憂鬱な気分が広がっていけば、人は幸福を感じないだろう。
快感と至福は幸福をもたらす原動力である。だが、それは長続きしない。人は心地よい感覚の再現を求めて、どこまでも前に歩みつづけようとする本性をもっている。そこで、「世界中の幸福レベルを上げるためには、人間の生化学的作用を操作する必要がある」と、著者は主張する。
いまでは向精神薬や興奮剤が、憂鬱になったり気分の落ちこんだりしたときに、ごくふつうに用いられるようになった。こうした薬は病人だけではなく、注意力散漫の子どもや前線の兵士にも処方されているという。
だが、そうした薬も、使い方を誤れば、犯罪の原因にもなる。
さらに次の段階にいたれば、脳に電気的な刺激を与えたり、遺伝子を操作したりして、人間の活動をコントロールすることも可能になるだろう。
そこまでして、人間は幸福すなわち快感を求めるべきだろうか。
ブッダは快感への渇望滅却こそがだいじだと唱えた。しかし、資本主義はあくまでも快感を追求しつづける。それによって「毎年、より優れた鎮痛剤や新しい味のアイスクリーム、より快適なマットレス、より中毒性の高いスマートフォン用ゲームが生みだされ、私たちはバスが来るのを待つ間、一瞬たりとも退屈に苦しまないで済むようになる」。
著者は人間の本性からみて、ブッダよりも資本主義に軍配を上げる。
人類はどこに向かおうとしているのか。「人間は幸福と不死を求めることで、じつは自らを神にアップグレードしようとしている」。
そのための手段となるのが生物工学、サイボーグ工学、非有機的な人工知能(AI)の開発だ。これらは人間をアップグレードするテクノロジーである。
21世紀中に人間はホモ・サピエンス(賢い人)からホモ・デウス(神の人、ないし超人)に進化する、と著者は断言する。これは人が不死と幸福を追求しつつ、そのための超能力をもつことを意味している。
進化のスピードは上がっている。それはだれにも止められない。
〈現代の経済は、生き残るためには絶え間なく無限に成長し続ける必要がある。もし成長が止まるようなことがあれば、経済は居心地のよい平衡状態に落ち着いたりはせず、粉々に砕けてしまう。〉
遺伝子工学によって、人類はこれまでにない、より健康で美しく賢い子孫をつくりだす可能性をもつようになった。生殖にあたって、欠陥のあるミトコンドリアDNAを交換することももはや不可能ではない。デザイナーベビーの誕生もSFの世界ではなくなっている。
地球のすべての人が不死と至福と神性を手に入れるというわけではないが、そうした方向への挑戦はとどまることはないだろう、と著者はいう。
ここで、おもしろいのは、著者が、そのいっぽうで、人間至上主義は同時に人類の凋落への危険性をはらんでいるとみていることだ。
絶頂と絶望のあいだを綱渡りしてみせるのが、ハラリの思考の特徴である。それでも、あくまでも絶頂に賭けるところに、かれが受ける秘密があるのかもしれない。
とはいえ、ここまで読んで、ぼく自身は国家と資本主義による人間の統制がますます進展するように感じて、すこし憂鬱になる。あるいはホモ・デウスがホモ・サピエンスを支配する未来がやってくるのだろうか。
2 人間とは何か
著者の方法がおもしろいのは、生物学(動物学)と歴史学を融合しながら、人類史を俯瞰的に見渡そうとしていることである。
第1部「ホモ・サピエンスが世界を征服する」の冒頭、著者は、われわれの毎日の生活のなかで、ライオンやオオカミやトラは、動物園を除けば、もはやおとぎ話やアニメの世界にしか存在せず、実際に「この世界に住んでいるのは、主に人間とその家畜なのだ」と指摘している。
〈合計するとおよそ20万頭のオオカミが依然として地球上を歩き回っているが、飼い馴らされた犬の数は4億頭を上回る。世界には4万頭のライオンがいるのに対して、飼い猫は6億頭を数える。アフリカスイギュウは90万頭だが、家畜の牛は15億頭、ペンギンは5000万羽だが、ニワトリは200億羽に達する。〉
この具体的な指摘には、なるほどと思わず納得してしまう。
過去7万年間、ホモ・サピエンスは地球の生態系に、じつに大きな変化をもたらしてきた。マンモスなど大型動物を絶滅に追いこんだのはホモ・サピエンスの仕業である。
狩猟採集の世界では、アニミズムが人と動物との対話をもたらしていた。それどころか、人間はみずからの祖先をヘビやトカゲなどの動物と考えていた。つまり、人間は動物の一種にすぎないと思われていたのだ。
しかし、いまでは動物はヒトより劣った存在とみなされるようになった。これは農業革命のもたらした意識変革である。農業革命は家畜をもたらした。「今日、大型動物の9割以上が家畜化されている」
家畜の身になってみれば、人に守られ、育てられる家畜の運命は悲しいものだ。たとえば、イノシシの遺伝子を引き継いだブタは、さまざまな欲求や感覚や情動をもっている。にもかかわらず、かれらは食肉としてしか評価されず、その目的に沿ってだいじに育てられる。
ここで、アルゴリズムという用語が登場する。
アルゴリズムというのは、いまはやりのコンピューター用語だ。
人を含む動物は身体をもち、その身体を感覚や情動や欲求にもとづいて動かしている。その動きはアルゴリズムにしたがっている、と著者は考えている。
「アルゴリズムとは、計算をし、問題を解決し、決定に至るための、一連の秩序だったステップのことをいう」
つまり、アルゴリズムとは欲求の実現に向けての段取りや計算といってよいだろう。
人を含め、すべての動物は、感覚や情動や欲求をもち、アルゴリズムに沿って行動する。ブタにはブタの、人には人のアルゴリズムがある。
親子の情動的な絆は人もブタも変わらない。にもかかわらず、人は子ブタや子牛を生後すぐに母親から引き離して、もっぱら食肉として育てる。
有神論の宗教が、こうした行動を正当化した、と著者はいう。
古代ユダヤ教では、子羊や子牛が神のいけにえとしてささげられた。ほとんどの宗教は、神だけではなく人間をも神聖視している。魂をもつのは人間だけであり、動物には魂がなく、人のために存在していると解された。
こうして神は作物や家畜を守り、人は神に収穫をささげるという構図ができあがった。
動物たちにも共感を示したのはジャイナ教と仏教、ヒンドゥー教である。どんなものも殺してはならないと教えた。とはいえ、こうしたインドの宗教も、牛の乳をしぼったり、その力を利用したりすることまでは禁じなかった。
農業革命は経済革命であるとともに宗教革命でもあったという。動物は感覚のある生き物から、ただの資産へと降格された。そして国家が成立すると、国家は征服した人間集団を資産として扱うようになる。人間による人間の差別も発生した。
そして、その後の科学革命と産業革命が、人間至上主義を生みだす。人間は神に代わって自然を動かし管理する存在になった。
人間がこの世界でいちばん強力な種であることはまちがいない。だが、力のある種の生命が、ほかの種の生命より貴重かどうかは、じつはわからない、と著者はいう。
人間には魂があるが、動物には魂がないという説はあやしい。
ダーウィンの進化論がいまでも恐れられるのは、ダーウィンが魂が存在しないことを立証したからだという著者の見方はおもしろい。ここでは、神を信じないが、人間至上主義には懐疑的という著者の考え方が垣間見られる。
進化論は人が分割できない不変かつ不滅の個からなるという信念をしりぞけた。ダーウィンは、あらゆる生物学的存在は、小さく単純な部分からできた複雑な器官の集合であり、それは徐々に進化したものだと考えた。進化論によれば、永遠不滅の魂なるものはどこにも存在しない。
動物とちがって人間には心があるという言い方にたいしても、著者は反論する。
〈心は魂とは完全に別物だ。心は神秘的な不滅のものではない。目や脳のような器官でもない。心は、苦痛や快楽、怒り、愛といった主観的経験の流れだ。これらの精神的な経験は、感覚や情動や思考が連結して形作っている。感覚や情動や思考は、一瞬湧き起こったかと思えば、たちまち消える。……永久不変の魂とは違い、心は多くの部分を持ち、たえず変化しており、それが不滅だと考える理由はまったくない。〉
ロボットやコンピューターに心や意識はない。こうした装置は何も感じないし、何も渇望しない。あらかじめ入力されたデータにもとづいて、動くだけだ。
いっぽう人を含む動物には感覚と情動がある。人間も動物も感覚と情動にもとづいてデータを処理し、行動する。ここには無意識のアルゴリズムが潜んでいる。
問題は心や意識とは何かということだ。
これが意外と解明されていない。
船場という場所 [山片蟠桃補遺]

[1830年代の大阪。大阪くらしの今昔館で]
引きつづき、中沢新一の『大阪アースダイバー』を読んでいます。
ナニワの商人にはミトコンドリア性が強かった。権力に取りこまれても、おいそれとは服従しなかった、と中沢は書いています。ここでいうミトコンドリア性とは、生命力の源といってもよいでしょう。
商人の世界ではゼニが絶大な威力をもちます。それは合理主義、自由な発想をもたらしますが、いっぽうでは殺伐とした競争社会を生みだします。
しかし、どうやら船場には、この殺伐さを防ぐ文化のようなものが形成されていた、と中沢はいいます。それを象徴するのが暖簾です。暖簾は古さと信用をあらわします。商品は暖簾に守られることによって、えげつないゼニを稼ぐための手段ではなく、いわば信用に包まれた価値になります。
大阪人はこってりしているというより、むしろあっさりしているのではないか、と中沢はいいます。それは商品のもつ性格からきています。
商品は売れたら、それでいわば縁切りになって、一サイクルが完了します。それからまた次のサイクルがはじまるわけで、いつまでもこってりとこだわるのは大阪人らしくないというわけです。にもかかわらず、大阪人はむきだしのゼニよりも信用をだいじにしました。
信用はおカネをベースにしていますから、じつに合理的です。しかし、それが単に合理的ではなく、信仰の域にまで達していたのが、ナニワ商人の特徴だった、と中沢はいいます。
「ナニワ商人は、この信用の空間を絶対に信仰し、信仰にはずれた行為は、厳に自分に禁じた」
ナニワでは、土地の取引にあたって「手金」なども取りませんでした。「口約束」で「手打」が完了。取引の多くも「手形」でおこなわれました。
手形も単に便宜上の発明ではなかったといいます。手形を交わすことは、お互いが信用の約束を交わすことにほかなりませんでした。
「ここには信用の空間への律儀な信仰が、確固として保ち続けられた」
ですから、船場というのは、単なる商業地域ではなく、商業道徳の信仰空間だったわけです。
船場では恋愛は御法度だったといいます。恋愛を暖簾のなかにもちこまない。たしかに、これも商業道徳のひとつにちがいありません。どろどろの恋愛が暖簾のなかにはいってくると、近松門左衛門の『女殺油地獄(おんなごろしあぶらのじごく)』になってしまいますものね。
しかし、船場に愛情がなかったわけではありません。そこには「クールに洗練された、デリケートな愛情の世界が、静かに形成されていった」と中沢は書いています。それを表現したのが谷崎潤一郎の『細雪』だったというわけでしょう。
とはいえ、暖簾の外では、ナニワ商人のエネルギーが奔放だったことも忘れてはなりません。そこからは遊び人のぼんぼんの世界が広がっていきます。
商家は一種の修行の場だったといいます。丁稚は船場道場で商人道の修行に励んだと、中沢は書いています。その丁稚を鍛え上げるのが若い番頭の役割でした。
「船場には、生まれたばかりの時期の、日本の資本主義の思想が、巨大なフォークロアの集積体として、番頭から弟子へと伝えられてきた」というわけです。
その哲学の根本は「商人がゼニを正しく動かす思想を忘れないでいれば、商人道は社会を豊かに富ませていく、この世でいちばん重要な仕事となる」というものだった、と中沢は書いています。
蟠桃の思想を育んだのが、船場での丁稚奉公だったことはまちがいないでしょう。それはいったいどういうものだったのでしょう。
香村菊雄に『船場ものがたり』という名著があります。著者は船場育ちで、この本で、いまはない船場の様子を再現しようとしています。
これを読めば、時代はかなり下るとはいえ、蟠桃が13歳から修行した船場がどういう場所だったかを、もう少し接近してつかめるのではないでしょうか。そんな期待をもって、この本を読みはじめました。
中沢新一『大阪アースダイバー』 から──山片蟠桃補遺(2) [山片蟠桃補遺]
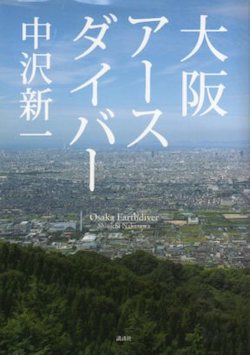
山片蟠桃の勤める升屋は梶木町、いまの北浜4丁目にありましたが、ここはいうまでもなく、船場に位置していました。
そこで、たまたまぼくの手元にあった中沢新一の『大阪アースダイバー』をぱらぱらとめくりながら、船場とはどういうところかを考えてみようというわけです。ぼく自身は実家に帰るとき、大阪を通り過ぎるだけで、一度も大阪暮らしをしたことがないので、残念ながら船場といっても、なかなか実感がわかないのが実情です。
この本のオビには「南方と半島からの『海民』が先住民と出会い、砂州の上に融通無碍な商いの都が誕生・発展する」と書かれています。
こんなふうに五千年の歴史をわずか2行に圧縮して説明されても、想像力の乏しいぼくなどは何のこっちゃと思ってしまうのですが、とりあえずはるか昔、海からやってきた海民が砂州に築いた商都、それが大阪だと理解しておきましょう。人類学は時間軸がめちゃくちゃ長くて、しかもそれがときどき入り乱れるので、読むほうは混乱してしまいます。
それはともかく、本書のあとがきでも、中沢は「大阪という存在を全体性において考えるには、やはり中核は船場であるように思います」と書いています。船場があってこそ、キタやミナミが成立するわけですね(もっともそのへそは上町台地の四天王寺というわけですが)。
第2部「ナニワの生成」を読んでみました。
そもそも商人とは何かというところから中沢からはじめています。古代人は物にはタマ(魂)が宿っていると考えていました。商人はその物を「無縁」の場に持ちだすことによって、物からタマを切り離します。それによって、物の属人的な関係を破壊し、物をカネで買える商品に変えてしまうのです。
古代は物にタマが宿っていたといわれると、なるほどそうだったのかなと思ってしまいます。だから、物をもらうということ、物をあげるということ、物を返すということはたいへん重いことだったのですね。
物からタマが切り離されると、物は人間的な関係を失って軽くなり、一定のルールのもとに(つまりおカネのやりとりで)、自由に交換されるようになります。その仲立ちをしたのが商人ですね。中沢は「商人は、人と物とを『無縁』にする原理にしたがって生きようとした、最初の近代人である」という言い方をしています。
しかし、商人があらわれたからといって「商品世界」が誕生するわけではありませんね。ぼくにいわせれば、人びとが何もかもおカネに頼って暮らすようになるのが「商品世界」です。人びとはおカネを稼ぐためにはたらかねばなりません。そして、その世界は近代においては、ひとつの世界システムに組みこまれていくのです。
古代、中世、近代と区別すれば、中世はいわば、古代社会から近代商品世界にいたる過渡期にあたります。江戸時代は近世と呼ばれますが、中世から近代への橋渡し、いわば近代の入り口にあたるわけです。
おっと、本からはずれてしまいましたが、ナニワは水底から生まれてきた、と中沢は書いています。淀川の運んだ土砂が砂州をつくり、そこに海民=商人と芸人(クグツ)がやってきます。
ナニワが海だったなんて信じられないという向きにたいして、中沢はいかに大阪に島のつく地名が多いかを挙げています。中之島、堂島、福島、網島、都島、田島、北島、出来島、姫島……。みんな島だったんです。
古代、この地は「ナニワ八十島」と呼ばれていました。ナニワとはナルニワ。すなわち、水底からごぼごぼと生まれてくる島々のことを指していたというのが、中沢説です。
ナニワは砂州から生まれた都市です。そこは無縁の地でした。無縁とは共同体と共同体の隙間を指しています。
そこで商人の誕生です。商人は海民から発生した、と中沢はいいます。商品はそもそも流れていくものです。
それと同時に商品にはもともと神への供え物という意味があって、ナニワ八十島の海民は、朝廷に海産物の贄(にえ)を献上していたというのです。中世にいたり、こうした海民(供御人)が余った海産物を売るようになったのが、市場のはじまりです。そうした市場は無縁の空間である砂州や河原につくられました。このあたりは網野史学が横溢していますね。
「商人は『無縁』の原理から発生した、新種の人間として歴史に登場した」と、中沢は書いています。しかし、贈与や愛情のような人間どうしのつながりではなく、信用と交換という計算づくで動いている商人には、どこか無気味で、合理性の怪物のようなイメージがつきまとっていました。
商人が集まって見世を出すと、町場が生まれます。そうした商人の同業組合が「座」となります。油座や魚座、藍座、薬座、酒麹座などの座。これは村の共同体とは異なる自由な商人連合の組合組織です。それは地縁や血縁から切り離された、いわば信頼関係にもとづく新たな組織でした。そのような座がはじめてつくられたのが船場という場所だった、と中沢はいいます。
その船場という場所に、われわれは立っています。そして、ここは神爪村と無縁になった少年、山片蟠桃がほうり込まれた最先端の道場だったともいえます。
そこがどんな場所だったのか、『大阪アースダイバー』をもう少し読んでみることにしましょう。
山片蟠桃補遺(1) [山片蟠桃補遺]
2013年にトランスビューから『蟠桃の夢』という本を出版してから、なんとなくもやもやしたものがわだかまっていました。
この本はもともとぼくのホームページ(いまは閉鎖)に連載していた「蟠桃」を4分の1程度にダイジェストしたものなのですが、やはりできるなら全体を復元したいという気持ちがあります。

そこで単行本とは別に私家版の電子書籍をつくろうかと思い立ったわけですが、そこで問題があることがわかりました。
オリジナル版は400字にして、約1500枚あります。これをそのまま収録すると、その4分の1はどうしても単行本と重なってしまうのです。それを避けるには、ある程度は書きなおす必要があるのですが、そのエネルギーがはたしてあるかどうか。そこで考えあぐねてしまいました。
蟠桃の『夢の代』やその他の草稿をもう一度読みなおすのも、ちょっとしんどい気がします。蟠桃にからむ人たち、たとえば中井竹山や履軒、麻田剛立、その他大勢のことももっと研究するとなると、それこそ気が遠くなりそうです。
しかし、ひまといえば、ひまなので、ぼちぼちやってもいいかなと思いはじめています。もっとも、しろうと仕事なので、はたしてどこまで行けるかはわかりません。ぼく自身、もう蟠桃の亡くなった年に近づいています。
このあいだ、93歳の父と会うため、3カ月ぶりにいなか(高砂市)に帰りました。その途中、蟠桃ゆかりの大阪を訪れ、高砂では蟠桃の生まれた村、神爪にも寄ってきました。
まず蟠桃といえば懐徳堂ですね。
その史跡が大阪の船場、今橋にあります。

蟠桃の勤めていた升屋は愛日小学校になり、その愛日小学校も廃校になって、いまは淀屋橋三井ビルになっています。梶木町(いまは北浜)の升屋から尼ヶ崎町(今橋)の懐徳堂までは、歩いて3、4分の距離でした。

住友が経営していた銅座の跡。いまは愛珠幼稚園になっています。

仙台藩の蔵屋敷は中之島の公会堂あたりにありました。

堂島の米会所跡。ここも蟠桃ゆかりの地です。

それから、蟠桃の生まれ故郷に。神爪(兵庫県高砂市)です。このあたりもマンションが増えました。

加古川からの疎水が流れています。

生石神社(石の宝殿)の一の鳥居。蟠桃の生まれた家はこの近くにありました。

蟠桃ゆかりの覚正寺。

ここには村人によってつくられた蟠桃の墓が移設されています。

そして、高砂の十輪寺。蟠桃とは関係なし。ここにはうちの墓があります。母の墓参りです。

寺内には遠縁の故加藤三七子さんの歌碑が立てられています。
春愁の昨日死にたく今日生きたく。

さて、山片蟠桃については、ほぼ書き尽くした気もするのですが、これからは遠近法で、もう一度アプローチしてみようかと思うようになりました。それをあわよくば自主制作の電子版にするのが、ぼくの夢です。
ところで、山片蟠桃ってだれと思われる方には、拙ブログの次のページをどうぞ。6年前、高砂コミュニティセンターでの講演です。
https://kimugoq.blog.ss-blog.jp/2013-11-17
この本はもともとぼくのホームページ(いまは閉鎖)に連載していた「蟠桃」を4分の1程度にダイジェストしたものなのですが、やはりできるなら全体を復元したいという気持ちがあります。

そこで単行本とは別に私家版の電子書籍をつくろうかと思い立ったわけですが、そこで問題があることがわかりました。
オリジナル版は400字にして、約1500枚あります。これをそのまま収録すると、その4分の1はどうしても単行本と重なってしまうのです。それを避けるには、ある程度は書きなおす必要があるのですが、そのエネルギーがはたしてあるかどうか。そこで考えあぐねてしまいました。
蟠桃の『夢の代』やその他の草稿をもう一度読みなおすのも、ちょっとしんどい気がします。蟠桃にからむ人たち、たとえば中井竹山や履軒、麻田剛立、その他大勢のことももっと研究するとなると、それこそ気が遠くなりそうです。
しかし、ひまといえば、ひまなので、ぼちぼちやってもいいかなと思いはじめています。もっとも、しろうと仕事なので、はたしてどこまで行けるかはわかりません。ぼく自身、もう蟠桃の亡くなった年に近づいています。
このあいだ、93歳の父と会うため、3カ月ぶりにいなか(高砂市)に帰りました。その途中、蟠桃ゆかりの大阪を訪れ、高砂では蟠桃の生まれた村、神爪にも寄ってきました。
まず蟠桃といえば懐徳堂ですね。
その史跡が大阪の船場、今橋にあります。

蟠桃の勤めていた升屋は愛日小学校になり、その愛日小学校も廃校になって、いまは淀屋橋三井ビルになっています。梶木町(いまは北浜)の升屋から尼ヶ崎町(今橋)の懐徳堂までは、歩いて3、4分の距離でした。

住友が経営していた銅座の跡。いまは愛珠幼稚園になっています。

仙台藩の蔵屋敷は中之島の公会堂あたりにありました。

堂島の米会所跡。ここも蟠桃ゆかりの地です。

それから、蟠桃の生まれ故郷に。神爪(兵庫県高砂市)です。このあたりもマンションが増えました。

加古川からの疎水が流れています。

生石神社(石の宝殿)の一の鳥居。蟠桃の生まれた家はこの近くにありました。

蟠桃ゆかりの覚正寺。

ここには村人によってつくられた蟠桃の墓が移設されています。

そして、高砂の十輪寺。蟠桃とは関係なし。ここにはうちの墓があります。母の墓参りです。

寺内には遠縁の故加藤三七子さんの歌碑が立てられています。
春愁の昨日死にたく今日生きたく。

さて、山片蟠桃については、ほぼ書き尽くした気もするのですが、これからは遠近法で、もう一度アプローチしてみようかと思うようになりました。それをあわよくば自主制作の電子版にするのが、ぼくの夢です。
ところで、山片蟠桃ってだれと思われる方には、拙ブログの次のページをどうぞ。6年前、高砂コミュニティセンターでの講演です。
https://kimugoq.blog.ss-blog.jp/2013-11-17



