本格的な流行は秋から──速水融『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』散読(2) [本]

1918年4月、日本でも巨大インフルエンザの先触れとなる小流行がはじまった。インフルエンザの流行は毎年のことなので、このときはだれもがさほど気にしなかった。
むしろ話題になったのは台湾に巡業中の大相撲の力士がインフルエンザらしきものに感染し、3人が死亡したことである。38度から40度の発熱があり、5日ほどで快方に向かうのが、インフルエンザの一般的な症状だった。新聞は台湾北部の基隆(キールン)と対岸の香港にそうした熱病の流行がみられると報じている。
日本国内では、5月初旬、横須賀軍港で軍艦「周防」に150名余の患者が発生した。中旬には保土ケ谷の富士瓦斯紡績工場で多数の工員が感染。そのころ東京市内でもぼつぼつ患者がではじめている。
このときのインフルエンザは、相撲の力士が数多く感染し、夏場所の休場者が多かったため、「角力(すもう)風邪」と呼ばれるほどだった。
6月から7月になると、近衛師団を含め、東京、仙台、金沢、松本、弘前、青森など、軍の各連隊で4000人以上の感染者がでた。感染率は非常に高かったが、死者はほとんど出ていない。
6月に衛戍(えいじゅ)病院[陸軍病院]に収容されたインフルエンザ患者数は3万人以上、海軍病院もほぼ同様だった。しかし、流行はこれでほぼ収まり、7月下旬には収束に向かっている。
日本で本格的な流行がはじまったのは、それから2カ月後、1918年9月下旬になってからである。
春が先触れにすぎなかったとすれば、このときの本格的な流行を第1波としてもよいだろう。もちろんこれを第2波と理解してもよいのだが、ここではこれを第1波と解釈して話を進めることにする。何せ、先触れとこのときとでは、感染者も死者も桁違いに数がちがいすぎるからである。
名古屋の『新愛知』(現在の中日新聞の前身)は、9月20日に日紡大垣工場で感冒が発生したと伝えている。さらに9月26日には大津の歩兵第9連隊に400名の患者が発生したと報じた。
10月12日の『読売新聞』には、山口県厚狭郡高千帆小学校(現山陽小野田市)の児童60名が39度以上の高熱を発し、鼻血を出しているという記事が掲載されている。
各地の新聞をみると、10月半ば以降、全国でインフルエンザ患者が増え、死者が続出したことが判明する。滋賀県や愛媛県、京都市でも、小中学校児童が数多く感染し、学校が閉鎖された。西日本からはじまった流行は、短期間のうちに、東日本、北日本に広がったとみられる。
本書には、全国の様子が事細かに追跡されているが、ここでは大阪・東京近辺だけに話を限ることにしよう。
大阪市内では10月29日に多くの小学校が休校となり、市電運転手2000人のうち450人が欠勤したことが報じられている。
同じころ、京都では西陣の職人の欠勤が相次ぎ、病院の看護婦の過半が感染し、治療に困難をきたしていた。11月にはいると、死者数は急速に増える。その大半が20歳から40歳までの壮年男女だった。
死者の増加により、大阪市では火葬場が混乱し、遺体が処理しきれなくなった。11月5日には大阪市内の全小学校が休校となった。
大阪市内の死者は11月12日がピークで419人に達した。なかでも学校教員の死者が多かった。
火葬場の混乱は神戸でも同様で、遺体が処理しきれず、棺桶が放置されるままになっていた。
京都、大阪、神戸でも、インフルエンザは10月20日ごろから流行しはじめ、11月半ばまでの約1カ月間、猛威をふるったとみてよいだろう。そして、12月になって少し落ち着いたあと、ふたたび1919年2月ごろからぶり返し、2月末、ようやく小康状態になった。
東京では、10月24日の各紙が流行性感冒の襲来を告げている。青山師範学校や小石川の女子師範学校も休校となっていた。
10月25日、内務省は全国に「西班牙(スペイン)風邪」に注意するよう警告をうながし、各地で「適当な処置を講じられたし」と伝えている。とくにはっきりとした指針は示されなかった。
東京市内では、インフルエンザの流行により、学校の休校が増え、遠足が中止になった。職場の欠勤者も多くなり、交通機関や通信に影響がではじめた。死者が目立つようになるのは、11月にはいってからである。砂村、町屋、桐ヶ谷、落合の火葬場は満杯となった。
11月5日には劇作家の島村抱月が、仕事場にしていた牛込の芸術倶楽部でインフルエンザのため死亡した。そして、翌年1月には恋人の松井須磨子が後追い自殺をするという悲劇を生むことになる。
11月になると、東京朝日新聞や都新聞などが、感冒による死者が増えていると報じるようになる。インフルエンザはすでに10月からはじまっていた。著者は「むしろ、新聞各紙が何も書かなかったことに作為を感じる」として、政府による何らかの情報統制があったことを示唆している。
11月下旬になると、流行は下火になった。都新聞は11月上旬に1日平均230−40人あった東京市内の死者数が、下旬には150−60人に減ったと伝えている。
10月以来、猖獗(しょうけつ)を極めたインフルエンザは東京でも12月にはいっていったん落ち着いたかにみえた。しかし、年があらたまると、ふたたび再燃する。より重大なのは、インフルエンザから肺炎に進み、亡くなる人が増えたことである。1月下旬には「盛り返した流行性感冒」といったような記事が数多くみられる。
2月3日の東京朝日新聞は、最近2週間で東京府下で1300名が死亡したと伝えている。各病院は満杯となり、新たな「入院は皆お断り」という状態だった。都新聞は、感染者の年齢が15歳から40歳であること、看護婦が払底していることを報じている。
こうした事態に東京府、東京市は「何をすべきかわからなかった、というのが実相であろう」と著者はコメントしている。警視庁当局はなすすべなく「茫然として居る」と、当時の時事新報も断じていた。
東京市長は2月5日に告諭を発し、室内や身体の清潔維持、人混みを避けること、うがいの励行、患者の隔離を奨励している。病院に行けない細民に無料の治療券を配布したり、医薬の給付をおこなったりもしている。しかし、劇場や映画館などの閉鎖はおこなわなかった。
著者は1918年秋から翌年春にかけての、この第1波(「前流行」)に関して、こんなふうにまとめている。
〈嵐のように襲来した「前流行」は、公式統計だけでも2116.8万人の罹患者、25.7万人以上の死亡者を出し、約半年にわたって暴れまわった後、いずかたともなく消えてしまった。春の到来という季節上の変化もあったろうし、多くの人が罹患し、ウイルスへの免疫抗体を持つようになった結果かもしれない。何せ病原体さえ分からなかった当時のことなので、予防や治療の結果でなかったことだけは確かである。用いられた薬も、中には肺炎の予防・治療に効くものもあったかもしれないが、流行性感冒そのものには無力だった。むしろ死亡者がこれだけで済んだのが幸運だったと考えてもいいだろう。〉
日本での第1波(「前流行」)の感染率は、国民全体の38%と、きわめて高かった。これにたいし、死亡率は12.1パーミル、すなわち1.21%となぜか低かった。人混みに出るな、手洗い、うがいをせよ、衣類・寝具を日光消毒せよといった注意を励行したことが案外きいたかもしれない、と著者も認めている。
「しかし、どこかに潜んだウイルスは、次の出番を静かに待っていたのである」。第2波が到来するのは必至だった。
第2波はくるのか──速水融『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』散読(1) [本]

100年前のパンデミックに関連して、少し前に本ブログで、ジョン・バリーの『グレート・インフルエンザ』の内容を紹介した。
だが、『グレート・インフルエンザ』には、日本のことは書かれていない。
はたして、あのとき日本ではどのようなことがおこっていたのか。
それを知りたくなり、ようやく本の貸し出しをしてくれるようになった図書館で、この本を借りてみた。次の予約がはいっているので、2週間以内に返却しなければならない。詳しくは読めないが、気になったところだけでもと思い、メモをとりはじめた。
夏になって、2月以来の新型コロナウイルス騒動は、ようやく一段落した感があるが、心配なのははたしてことし秋から冬にかけての第2波があるのかどうかということだ。
スペイン風邪と呼ばれることが多かった約100年前のインフルエンザ(当時の言い方では流行性感冒)と、今回の新型コロナを同等にみるわけにはいかない。インフルエンザとコロナはちがうかもしれない。それでも、かつての記録は何かの参考になるはずだ。
1918(大正7)年から20(大正8)年にかけて、日本の状況はどうだったのか。
当時は大日本帝国の時代である。帝国は内地と外地に分かれていた。内地の人口は1920年で約5600万人。加えて、日本が台湾と朝鮮を植民地とし、樺太を領有し、関東州を租借していたことを頭にいれておく必要がある。満州国が誕生するのは、もう少し後の1932年だ。
有名な歴史人口学者である著者は、100年前のインフルエンザをいちおう「スペイン・インフルエンザ」と呼んでいる。とはいえ、前にも書いたように、このときのインフルエンザの発生地は、スペインではなく、アメリカのカンザス州だったと思われる。時期はおそらく1918年1月。主に第1次世界大戦中の兵士の移動によって、全世界に広がった。2年にわたって猛威をふるい、そのときの死者は最低限で見積もっても4000万ないし5000万人といわれる。
もちろん、インフルエンザは日本にもやってきた。著者はそのときの日本での流行を3期にわけてふり返っている。すなわち、
(1)1918年4月─7月(先触れ)
(2)1918年秋─1919年春(前流行)=第1波
(3)1919年暮─1920年春(後流行)=第2波
日本でインフルエンザの本格的流行がはじまるのは1918年秋からである。その年の4月から7月にかけても先触れがある。『グレート・インフルエンザ』のジョン・バリーによると、このときのインフルエンザ・ウイルスは5月に上海に到着していたという。だから、これを第1波としてもよいのだが、1918年春から夏にかけての流行は例年とさほど変わらず、死者数も急増したわけではない。
そこで、ここでは1918年秋からの本格的流行を第1波とし、春の流行は先触れと理解しておくことにしよう。先触れから2、3カ月後、本格的な第1波がやってくる。
インフルエンザの大流行は第1波だけでは収まらなかった。第1波の流行から7カ月後、おそれていた第2波がはじまる。先触れから数えれば、このとき日本は約2年にわたって、インフルエンザの波に2度、数え方によっては3度襲われたことになる。
内務省の資料では、日本内地における第1波の患者は2116万8398人、死者は25万7363人、第2波の患者は241万2097人、死者12万7666人となっている。合計すると、患者2358万495人、死者38万5029人となる。
第1波にくらべて、第2波の患者数はずっと少ないが、患者にたいする死者の割合は第2波のほうがずっと高かった。
いずれにせよ、この内務省の資料にもとづいて、日本でのスペイン・インフルエンザによる死者数は約38万5000人という数字がまかり通っていた。
だが、著者はこの死者数は過小評価だと明言する。統計上の不備があるうえに、隠れた死者数があるからだ。そこで、著者は例年と比較した超過死亡者数をもとに、スペイン・インフルエンザによる死者数を割りだし、それを月別、男女別、主要都市別、道府県、内地・外地にわけて、新たに計算しなおしている。
その手法を紹介するのはやめておく。詳しい統計を示すのもわずらわしい。著者が計算しなおした1918年から20年にかけてのインフルエンザによる死者数だけを以下に示しておく。
日本内地 45万3452人
樺太 3749人
朝鮮 23万4164人
台湾 4万8866人
総計 74万231人
なお、このかん帝国内の人口は減っておらず、むしろ増えている。出生率が死亡率よりはるかに高かったからである。インフルエンザの流行は日本の人口を減少させるものではなかった。とはいえ、内地だけでも45万人以上が亡くなったというのは、やはりこのインフルエンザがただごとではなかったことをうかがわせる。
歴史はくり返すわけではない。歴史を知るのは同じことをくり返さないためである。そして、できれば善きことを学ぶためである。
だが、自然災害だけはくり返しやってくる。おそらく、今回のパンデミックも第2波、場合によっては第3波がやってくるだろう。
それにどう対応するか。
100年前、日本で何がおこっていたのかを、本書から学ぶなら、何らかの教訓が得られるかもしれない。
以下はその簡単なまとめである。
フーコーの壮絶な闘い──エリボン『ミシェル・フーコー伝』から(3) [われらの時代]
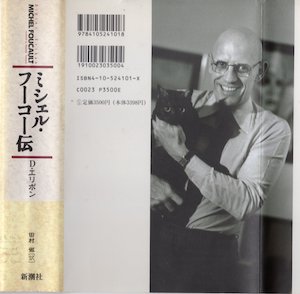
1971年5月、『許しがたきもの』というパンフレットが発行される。その裏表紙には、こう書かれていた。
〈許しがたきものは、裁判所、ポリ公、病院、収容施設、学校、兵役、新聞雑誌、テレビ、国家〉
このパンフレットを出版したのは「刑務所調査集団(GIP)」という団体で、その提唱者はミシェル・フーコーだった。
この年、2月8日、パリ・モンパルナス駅下の聖ベルナール礼拝堂で、刑務所調査集団の発足を告げる集会が開かれた。
フーコーは声明を読み上げる。
〈毎日のわれわれの生活にたいして、警察による碁盤目状の警備網が引き締められている。市中の通りで、国道で。外国人や若者のまわりでは、思想言論の罪というものがまたもや姿を見せてきた。……刑務所とは何かを、われわれは知らせたいと思う。すなわち誰がそこへ行くのか、そこでは何が起こっているのか、囚人の生活は、また看守の生活はどうなっているのか。〉
こうして、フーコーを中心として、刑務所の調査がはじまったのだ。68年5月以降の抗議活動は、警察による多くの左翼活動家の逮捕をもたらしていた。だが、フーコーが問題としたのは政治犯だけではない。普通犯もまた社会システムの犠牲なのではないかと考えていた。
刑務所ではいったい何がおこなわれているのか。そもそも犯罪とは、犯人とは何なのか。フーコーにとって、刑務所調査集団による調査は、1970年代はじめの大事業となった。フーコーのパートナー、ダニエル・ドゥフェールは、地下組織「プロレタリア左派」(毛沢東派)に属するようになっていたが、かれを含め、党派には関係なく、多くの人がこの団体に加わって調査に協力した。
1971年12月にはトゥールのネイ中央刑務所で、反抗する囚人たちを看守が激しく弾圧する事件がおきた。リールやニーム、ナンシーなどでも、囚人の暴動が発生し、治安機動隊が投入された。共産党系の新聞は、行政当局にこうした「やくざ連中」に厳しく対処するよう求めていた。
しかし、1972年1月18日、調査集団は当局による弾圧を批判し、法務省への申し入れをおこなおうとした。フーコーやサルトル、クロード・モーリヤック、ジル・ドゥルーズなど数十人が集まり、法務省にはいろうとするが、機動隊がそれを排除した。3日後、セバストポール大通りでは千人近くのデモがくり広げられた。
刑務所調査集団は大きな成功を収めた。さまざまな行動が展開されただけではない。刑務所の実態をあばく本も出版される。だが、1970年代半ばになると運動は分裂し、しだいに崩壊していく。
その間、コレージュ・ド・フランスでの講義もつづけられている。フーコーのテーマは刑務所調査集団の活動と無縁ではない。
桜井哲夫の『フーコー』によれば、各年の講義内容は次のようなものだった。
(1)1970─71年「知への意志」
最終的な目標は、現代社会の規範を正当化している学問体系の諸関係をあばきだすことだ。今年度は19世紀フランスの刑罰、処罰精神治療について、当時の文書を素材として検討する。
(2)1971─72年「刑罰理論と刑罰制度」
19世紀フランスの刑罰制度の研究。中世の審問と近代の試験との関係。
(3)1972─73年「処罰社会」
19世紀前半の殺人者ピエール・リヴィエールの回想記の分析。古典主義時代から19世紀までの刑罰の諸段階。
(4)1973─74年「精神治療の権力」
18世紀から19世紀にかけて狂気と精神医学はどうのうな関係にあったか。
(5)1974─75年「異常者」
異常者という概念はどのようにしてつくられのか。
1976年の講義は休講となるが、講義はその後も毎年つづく。講義のほかにセミナーもあった。だが、とりあえず75年までの講義内容をこうして並べてみただけでも、フーコーのコレージュ・ド・フランスでの講義が、刑務所調査集団の政治活動といかにつながっていたかがわかるだろう。
輝かしい社会の裏面には隠された部分があって、それは社会から排除され、隠蔽され、隔離され、時に抹殺されている。その象徴となるのが犯罪であり、犯罪者なのだった。時の社会を成り立たせている知と権力の実相は、隠されている部分によって逆照射されなければ、ほんとうの姿がみえてこない。こういう発想はいかにも68年の思想を引き継いでいたといえるかもしれない。
フーコーの仕事はまとめられて、1975年の著書『監視と処罰──監獄の誕生』(1977年の日本語訳では『監獄の誕生──監視と処罰』)となる。この本のなかで、フーコーはジェレミー・ベンサムが設計したパノプティコン、すなわち「一望監視装置」について、長々と説明する。パノプティコンは優秀な監獄装置にとどまらず、現代にも拡張されていく「権力の眼」なのだった。
だが、ぼくが追うのは70年代はじめのころまでのフーコーだ。そのあとの華々しい活躍については、ごく簡単に触れるにとどめよう。
何はともあれ、エリボンの「伝記」をもう少し読み進めてみる。
70年代はじめには、フーコーの生活はすっかり変わってしまった、とエリボンは書いている。フーコーは万人周知の人物、闘士になっていた。その交際範囲、活動範囲も拡大している。
71年11月27日にフーコーは、これまで論難してきたサルトルとはじめて話を交わしている。この日はパリのアラブ人街で、ある事件をきっかけに人種差別反対の集会とデモがおこなわれていた。
72年12月16日の抗議活動にも加わっている。アルジェリア人労働者のモハメド・ディアブが警察署のなかで死んだことに抗議するためだ。このときもフーコーは逮捕され、真夜中に釈放されている。しかし、数日後、新聞に報道されて、大きな反響を呼んだ。
フーコーはいかなる政治組織にも加盟しない。党や知識人が大衆を領導するという考え方はまちがっていると思っている。政治運動に加わるのは、あくまでも個人としてだ。つれあいのダニエル・ドゥフェールが毛沢東派の新聞『人民の大義』にかかわっているため、かれの出る集会にはためらわず参加し、発言はする。しかし、フーコー自身は毛沢東主義者ではなく、むしろ極左の形式主義に批判的だった。
毛沢東派のリーダー、ピエール・ヴィクトール(本名ベニー・レヴィ)との対談では、裁判という装置について語りながら、毛沢東派の人民裁判という考え方には同意できないと話している。
フーコーは解放通信社(APL)とも発足当初から関係をもっている。この通信社は、闘争や運動に関するニュースを集めて、広く伝えていた。1973年に発刊された左派の新聞『リベラシオン』はサルトルが主筆を務めていたが、フーコーはこれにも参加している。
だが、新聞は次第に右翼と同じようにイデオロギーに満ちた左翼キャンペーンを張るようになり、内紛も激しくなって、真実を語ることを旨とするフーコーは落胆を隠せなくなる。70年代半ば、極左主義の時代は終わった。
刑務所調査集団もすでに解散している。毛沢東派のプロレタリア左派も73年10月には、ひそかに解散した。
しかし、フーコーは終わらなかった。サルトルの模索する政治革命とは一線を画した、個別の政治活動がつづく。道は分かれる。1977年11月、テロリズムに反対するフーコーは、ドゥルーズともたもとをわかった。ボードリヤールは『フーコーを忘れること』という本を書く。
1975年には、俳優のイヴ・モンタンやレジス・ドブレとともに、スペインのマドリードにおもむき、フランコ政権が11名の男女に死刑判決を下したことに抗議する。武装警官がかれらを排除し、無理やりパリ行きの飛行機に乗せた。だが、その後もスペインの政治犯を守るための抗議活動をつづけている。
1975年から84年にかけて、フーコーは実に多くの声明文に署名する。不正の告発をためらわなかった。
1975年の『監獄の誕生』から1年半後、フーコーは『性の歴史』を刊行しはじめる。
「問題は、人間の性現象についての言説を支えている〈権力=知=快楽〉という体制を、その機能と存在理由において明確にすることである」と、フーコーは書く。
この本は6巻を予定されている。だが、実際に執筆されたのは4巻分で、生前には3巻しか出版されない。プランも大きく変更され、中世から近代に向かうはずが、初期キリスト教、さらにはギリシア・ローマまでさかのぼり、そこで途絶えた。
フーコーの政治活動はつづく。1977年には東欧諸国の反体制派を支援した。サルトルとはしばしば連携している。
1979年にはベトナムのボート・ピープルを支援する運動に加わった。80年にサルトルが亡くなったときは、葬儀に参加し、霊柩車のあとをモンパルナス墓地まで歩いた。
1978年にはイランのテヘランを2度にわたって訪れ、何本もイランのルポを書いた。パリではホメイニとも会った。翌年、ホメイニがイランに帰国し、イラン革命がおこると、革命を支持したフーコーはメディアから猛烈に叩かれる。
1981年、フランスではミッテランが大統領選で勝利し、社会主義政権が誕生する。フーコーは裁判や移民問題、死刑廃止について、政権に期待を寄せる。だが、政権との関係はすぐに悪化する。フーコーは、ミッテラン政権がポーランドでの軍事政権樹立による反体制派弾圧を黙認していると批判する。「ポーランドの民衆の闘いと連帯しなければならない」とフーコーは訴える。82年にはワルシャワを訪れ、軍人や知識人、学生と会っている。
1970年以降、アメリカには講演のためよく出かけていた。とりわけ頻繁に行くようになったのが75年以降である。スタンフォードでもバークレーでも、フーコーの講演があると聞くと、多くの学生が集まり、階段教室はすぐにすし詰めとなった。だが、アメリカ訪問も1983年秋のバークレーが最後となる。
フーコーがニューヨークやサンフランシスコが好きだったのは、フランスとちがって、ここでは年齢とは関係なく、公然と同性愛が認められていたからである。フーコーにとって、カリフォルニアは日当たりのよいすばらしい楽園だった。だが、その楽園にエイズという災厄が襲いかかる。
1984年6月25日、フーコーはエイズのため、パリのサルペトリエール病院で死去する。享年58歳。その直前、8年ぶりに「性の歴史」の第2巻『快楽の活用』と第3巻『自己への配慮』が出版された。
フーコーが亡くなったとき、吉本隆明はこう記している。
〈ミシェル・フーコーが死んだ。現存する世界最大の思想家の死であった。……
わたしたちはフーコーに、ロシア的なマルクス主義とまったく独立に、はじめて世界を認識する方法を見つけだした思想家をみて、心を動かされ、その展開を見つめてきた。だが、勝手な思い込みを言わしてもらえば、フーコーはじぶんの啓示した世界認識の方法の意味のおおきさを、じぶんでおそれるかのように、個別的な分野の具体的な歴史の追究に転じたようにおもわれる。かれのあとに、ロシア的なマルクス主義に張りあう力をもち、それにまったく独立な世界認識の方法を見つけだすことはできない。あるのはたくさんの思想の破片だけだ。
摂理や決定論や信念の体系とかかわりない世界認識の統一的な方法がありうることを、はじめて啓示したミシェル・フーコーの最初の一撃を、わたしたちはながく忘れることはないであろう。〉
最高学府の教授に──エリボン『ミシェル・フーコー伝』から(2) [われらの時代]
1966年、『言葉と物』がベストセラーになるなか、フーコーはフランス中部のクレルモン大学から出向するかたちで、チュニジアのチュニス大学に赴任し、学生に哲学を教えることになった。チュニジアには2年半滞在することになる。
このころの最大関心事は『知の考古学』の執筆である。フーコーは必死になって書いた。原稿が完成したときが、チュニジアを去る時である。
『知の考古学』は難解である。歴史分析を人間至上主義的にではなく、考古学的におこなう方法を探った著作といえるかもしれない。ここでいう考古学とは出土品などの研究によって、人類の活動を探るというのではない。言説のかたまりを「思考のひそかな動き」としてとらえ記述することを指している。
フーコーにとって、歴史は連続したものではなく、断絶したものと考えられていた。歴史分析では、解釈主義もまた避けなければならない。「語られたことを、それがまさしく語られた限りにおいて記述する」のが考古学の方法なのだ。それは構造主義とは異なる。常に人が見ていながら実際には見えていないものを見えるようにすることが求められる。ぼくなどには、よく理解できないけれど、フーコーはそんなふうに思考を重ねている。
マルクス主義の発展史観や人間礼賛の進歩主義、近代化論は否定され、歴史と現在をとらえる新たな視座が模索されているようにみえる。
パリでは68年5月に、いわゆる五月革命が発生した。だが、このときフーコーはパリに数日間いたものの、五月革命にはほとんど立ち会っていない。衝撃を受けたのは、むしろアルジェリアでのできごとだった。
1967年6月、中東では「六日戦争」(第3次中東戦争)が発生した。イスラエルがエジプト、ヨルダン、シリアを攻撃し、ヨルダン川西岸、ガザ地区、シナイ半島、ゴラン高原を占領していた。
こうしたなか、チュニスでは反ユダヤ人暴動が発生する。ユダヤ人の住む地区で火災がおき、200近いユダヤ人の小さな商店が略奪にあい、シナゴーグが破壊された。左翼急進主義の学生たちも「パレスチナの兄弟」のために立ち上がり、この暴動に手を貸した。フーコーはこの暴動に嫌悪を隠さない。
このときフーコーは師のカンギレムに「マルクス主義が、この事態に対して機会(そして用語)を提供できたというのは、いかなる歴史の策略(ないし愚劣さ)なのか、と思っています」という手紙を送っている。
学生活動家たちは、その後も日和見的な政府を批判する姿勢を強めていった。アメリカのハンフリー副大統領がチュニジアを訪問したときには、暴力的な抗議活動を引きおこした。
しかし、1968年3月から6月にかけて、多くの学生が政府によって逮捕され、投獄され拷問されるのをみるにつけ、フーコーはいてもたってもいられなくなる。学生たちを守る側に立つようになった。
フーコーは68年5月のパリではなく、3月のチュニジアで、生々しい政治と権力の問題にぶつかったのだ。好ましからざる人物になりつつあったフーコーに、チュニジアの警察は早くフランスに帰国するよう脅しをかけた。それでもかれは、学生の裁判を見守るため、ぎりぎりまでチュニジアにとどまった。
1968年10月にチュニスへの出向期限が切れたため、フーコーは年末にフランスに戻ってくる。ソルボンヌ大学の教授になる話もあったが、それは実現しない。パリ郊外にある新設のヴァンセンヌ大学で哲学を教えることが決まった。
五月革命に参加しなかったフーコーは、このころ右派のドゴール派とさえみられていた。だが、ヴァンセンヌの正教授となったフーコーは、講師陣として自分のまわりに左派の哲学者たちを集めた。
パリではまだ五月革命の余熱が残っている。1969年1月、サンルイ高等中学校の生徒たちが集会で五月革命の記録映画を上映しようとしたところ、当局から妨害を受けた。抗議する学生たちを警察が排除する。開校早々のヴァンセンヌでも、それに同調して、バリケードが築かれた。真夜中、警察との攻防戦がくり広げられる。フーコーは学生たちとともに逮捕され、1日拘束された。
フーコーは警察による鎮圧行動を激烈に批判する。そのあと、ヴァンセンヌでは集会とデモ、共産党系と新左翼の乱闘、新左翼どうしの内ゲバがくり返される日々がつづいた。
そのなかでもフーコーは講義をつづける。「性の言説」、「形而上学の終わり」、「生にかんする諸学の認識論」、ニーチェについて。受講する学生は多い。多すぎて、まともな授業ができなほどだ。
1970年1月、文部大臣がマルクス・レーニン主義的傾向の強いヴァンセンヌの哲学科学生には、教員資格の証明書を与えないと言明する。フーコーは猛烈に抗議する。ヴァンセンヌではまたも学生たちが建物を占拠し、それを警察が排除するというくり返しがつづく。
フーコーはヴァンセンヌに2年間とどまった。かれにとっては、政治と暴力の季節、波瀾万丈の2年間だった。
1970年4月、フーコーは師のジャン・イポリットの後任として、フランスの最高学府、コレージュ・ド・フランスの教授に就任することが決まった。だが、ヴァンセンヌでの経験は、かれをすっかり戦闘的知識人に変えていた。
エリボンはいう。
〈1969年以後フーコーは、戦闘的知識人の形象そのものを一身に具現しはじめる。こうして作りあげられるのは、誰しもが知っているあのフーコー、デモ行進と声明文の人フーコー、《闘争》と《批判》の人フーコーであって、その闘争と批判は、コレージュ・ド・フランスの講座教授の肩書のおかげで、いっそう大きな力と確固たるものが与えられていく。〉
フーコーがコレージュ・ド・フランスの一員に迎えられるにあたっては、ジョルジュ・デュメジルやジャン・イポリット、フェルナン・ブローデルをはじめとする多くの学者の支援があった。
教授への選出にさいし、フーコーは『狂気の歴史』、『臨床医学の誕生』、『言葉と物』から最近の『知の考古学』にいたる、みずからの研究業績を説明し、さらにこれからの講義計画を提示している。それにもとづいて、コレージュの教授会は念入りな審査のすえ、フーコーをコレージュの教授にふさわしいと認め、文部大臣もそれを承認したのである。
1970年12月2日、フーコーはコレージュ・ド・フランスの大講堂で、最初の講義をおこなう。この日、コレージュのあるカルチェ・ラタン地区は、相変わらず戒厳令下におかれ、保安機動隊が厳しい規制を敷いていた。だが、フーコーの講義には何百人もの人が押し寄せ、古い講堂はすし詰め状態になった。聴衆のなかには、クロード・レヴィストロース、フェルナン・ブローデル、フランソワ・ジャコブ、ジル・ドゥルーズなどの顔もみられる。
70年12月の開講講義でフーコーはおよそ次のように語っている。
われわれの文明ほど言説に敬意を示した文明はほかにない。しかし、ロゴス尊重の下には、一種の恐れが隠れている。そのため、この社会では言説の無秩序な噴出を避けるための拘束システムがつくられている。それが禁止とタブー(人はどんなことを言ってもいいわけではない)であり、分割と拒否(狂人の話は聞くな)であり、さらに「禁止を正当化し、狂人を規定する」真理なるものの枠組みがつくられている。言説にはほかにもさまざまな制限原理が設けられている。少なくともこの秩序の仮面を可視化しなければならない、とフーコーはいう。
哲学の語る真理を批判的、また系譜学的に解体すること。狂気や性現象についての言説、文学や宗教、倫理、生物学、医学、政治、法律に関する言説もまた検証されなければならない。
フーコーの講義はまだはじまったばかりだ。講義は1970年以降、かれが亡くなる1984年までつづけられることになる。
エリボンはその講義の様子をとらえた1975年のあるルポを紹介している。
〈フーコーは講義の舞台につかつかと威勢よく、水に飛び込む人のように入ってくると、人々の体を跨いで越えながら教卓の椅子にたどりつき、数々のテープレコーダーを押しやって自分の書類を置き、上着を脱いで、電気スタンドをともし、時速100キロといった調子で発進する。声は力強く、よく届き、ラウドスピーカーで中継されている。……座席は300なのに500人もがすし詰めになっていて、ほとんどすき間がない。猫1匹たりとも脚の置き場があるまい。〉
フーコーの講義は一コマ2時間で、年に十数回おこなわれた。公開講義なので、誰でも聞くことができる。授業料もない代わりに試験や学位授与もない。コレージュはいわば国立の市民大学なのである。
そのため立錐の余地もないほど大勢の人が押し寄せ、教卓には山のようにテープレコーダがセットされていた。参加者は講義のあと、それを必死になって回収するのだ。これをみても、ただちに理解できないにせよ、いかにフーコーの講義が人気だったかがわかる。



