あのころフーコーは──D・エリボン『ミシェル・フーコー伝』から(1) [われらの時代]
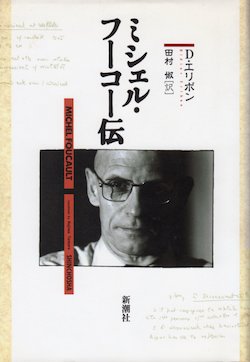
ディディエ・エリボンの『ミシェル・フーコー伝』 から、あのころのフーコーの様子をたどってみる。
ミシェル・フーコーは1926年10月にフランス西部の都市ポワチエに生まれた。父は名声高い外科医で、母も地所や農場、牧場をもっていた。裕福な家庭だったといえよう。
聖スタニスラス中学に入学した1940年9月ごろ、町はドイツ軍によって占領されていた。フーコーは43年6月、バカロレア(大学入学資格試験)に合格するが、医学の道には進まず、文科を選ぶ。
戦争が終わった45年秋にパリに出て、アンリ4世高等中学校で入試の準備をし、46年秋に高等師範学校に入学する。しかし、孤独と同性愛に苦しみ、48年には自殺未遂をおこしている。
フーコーの代表作、『狂気の歴史』(1961)や『性の歴史』(1976〜84)は、みずからの個人史を歴史的に掘り下げた作品だとみる向きもある。
1950年には、高等師範の教師ルイ・アルチュセールに倣って、フランス共産党に入党している(しかし、3年で離党)。この年、教授資格試験に失敗するが、気を取り直して勉学にはげみ、翌年、見事に合格をはたした。
新しい教授資格者はどこかの高等中学で教職につかねばならないが、フーコーは高校教師の道を選ばず、チエール財団で研究をつづけた。だが、この財団の寮でも、同性愛関係でもめごとをおこし、追い出されるようにして、1952年にフランス北部にあるリール大学の助手となった。
リール大学に赴任して、心理学を教えるようになっても、フーコーはこの町に定住しない。毎週、駅近くの小ホテルに宿泊して、2、3日授業をおこなっては、パリに戻る生活をつづけている。このころ、専門の心理学研究を深めながら、ニーチェを読みはじめている。1955年にはスウェーデンのウプサラに向かう。ウプサラのフランス会館館長となるのだ。
ウプサラでは3年間すごしている。ここでの仕事は、フランス語とフランス文化を紹介することだ。ウプサラのフランス会館で、フーコーは週に6時間授業をした。多くの生徒はそれについて行けず、脱落していった。にもかかわらず、フーコーの仕事ぶりは熱意にあふれていた。アルベール・カミュやロラン・バルトをはじめ多くの講師陣がやってきた。
公務は繁忙をきわめた。そのかたわら、フーコーはウプサラの大図書館で資料の山を読みふけり、博士論文の執筆に着手する。その成果が1961年に『狂気の歴史』となって、出版されることになる。
フーコーは1958年にウプサラを離れ、いったんパリに戻ってからワルシャワに行き、ワルシャワ大学のフランス文明センターの仕事を引き受ける。だが、それも1年しかつづかない。
フランス外務省とかけあって今度はドイツに行こうとする。1959年から60年にかけ、フーコーはハンブルクのフランス文化学院で、フランス語の授業をするが、多くの時間は大学図書館で過ごしていた。膨大な量の博士論文『狂気の歴史』の仕上げに取りかかっていたのだ。
フランスに戻ったフーコーはその論文を出版する(当時のタイトルは『狂気と非理性』)。論文は1961年5月のソルボンヌ大学での公開審査を経て優秀と判断され、文学博士の学位を得る。フーコーは1962年秋にフランス中部にあるクレルモン大学の正教授に昇格することになった。
1960年秋から66年春までフーコーはクレルモンとパリのあいだを往復していた。哲学科の聴講者は全体で30人ほどだった。
このころのフーコーはどちらかというと左翼だが、政治参加にはそれほど積極的ではなく、70年代のような急進派ではなかった。
1963年からは、『言葉と物』の原型となる講義をはじめている。エリボンによれば、そのころフーコーは革命を準備していたわけでも、バリケードに思いをいたしていたわけでもなかった。むしろ、激しい反共産主義の姿勢を示していた。共産党を脱退し、ポーランドで暮らして以来、フーコーは共産主義を思い起こさせるものに猛烈な敵意をいだいていたという。
1963年には東京の日仏学院院長に任命されるという話があった。しかし、クレルモン大学の学部長が文部省に強く訴えて、話は立ち消えになった。モーリス・パンゲではなく、フーコーが日仏学院に来ていたら、また別の展開があったかもしれない。
そのころ、フーコーは大学で心理学を教えることに飽き飽きしはじめていた。ソルボンヌ大学に移る計画はうまく行かない。1965年には2カ月間ブラジルに滞在した。66年にはチュニジアのチュニス大学に出向することになる。そのころ、パリでは『言葉と物』が出版され、増刷を重ねていた。
以上はまえおき。
それ以降、70年代はじめごろまでを、エリボンの『ミシェル・フーコー伝』に沿って、少し詳しくみていくのが、われらの時代のテーマである。
といっても、このころ日本ではフーコーはほとんど知られていない。1970年に来日したときも、メディアはほとんど注目しなかった。構造主義の登場で、サルトルはフランスでは凋落していたのに、日本はまだサルトルの時代だった。日本でフーコーが注目されるようになるのは70年後半からである。
しかし、ここではその心理的時差を縮めて、われわれと同時代の生のフーコーを追っていくことにしよう。
まず1966年4月にガリマール社から出版された『言葉と物』が大ヒットしたことを取りあげるべきだろう。
この本の序章では、ベラスケスの絵画「侍女たち」が取りあげられていた。これはいちばん最後につけ加えられた原稿だったという。だが、それまで読んだことのないような、鋭い文学的ともいえる絵画の構造的分析が読者を引きつけ、本は「菓子パンのように」売れて、増刷に次ぐ増刷となった。難解な哲学書がこれほど売れるのはまれなことだった。
フーコーは早くからサルトルやメルロポンティの「人間学」を批判していた。「人間学」の幻想に異議を申し立てていた。神の死とともに人間は絶対者となるわけではなく、絶対者としての人間もまた終わる、とフーコーは宣言した。
この本のサブタイトルは「人文科学の考古学」となっている。フーコーは16世紀初頭から数世紀にわたる知の形式を追っている。
フーコーによれば、おのおのの時代には、あらゆる科学的な言説を可能にする知の格子のようなものがあって、こうした「歴史的な先験的認識」をフーコーはエピステーメーと呼ぶ。
どのような学問も何らかのエピステーメーのなかで深められ、同時代の学問と結びついている。フーコーはまず古典主義の時代に発展した一般文法、富の分析、博物学を取りあげる。そして、それらが19世紀には、比較文法、経済学、生物学へと変成していくことを指摘する。人間を認識対象とみるなら、ここでとらえられているのは、話す人間、働く人間、生きる人間である。
古典主義のエピステーメーの特徴は、いわば表象の分析である。一般文法では、言語の内的メカニズムが解明れる。富の分析では、富と貨幣の関係が取りあげられる。そして博物学ではさまざまな分類がなされる。
これにたいし、19世紀のエピステーメーがめざすのは深層の分析である。比較文法では言語とは何かが問われ、経済学では価値の源泉が問われ、生物学では目に見えない生命の根源が問われる。
ルネサンス以後の古典主義時代において主役となったのは、神のもとで生きる人間だった。とはいえ、その世界は神によってつくられていた。
しかし、19世紀になると、世界をかたちづくるのは無限なる神ではなく、有限なる人間だという思想が強く打ちだされる。そして、世界の深層を発見するのも、また神ではなく、有限なる(命の限られた)人間なのだということになる。
だが、はたしてそうなのか。フーコーはその「人間」なるものに疑問をいだく。神なき近代の個としての「人間」もまた幻想ではないのか。
人間を疑うなかで、フーコーが導きの糸とするのは、精神分析学や文化人類学、さらには言語学である。こうした反科学は「人文諸科学のなかでその実証性をつくり、さらにつくりなおすあの人間をたえず解体することをやめない」とフーコーはいう。
『言葉と物』の末尾は、あまりにも有名である。
〈人間は、われわれの思考の考古学によってその日付の新しさが容易に示されるような発明にすぎぬ。そしておそらくその終焉は間近いのだ。〉
この謎のことばは大きな波紋を広げていった。
『言葉と物』が出版された1966年には、構造主義論争が燃え盛っていた。『構造人類学』の著者レヴィストロースは、1962年に『野生の思考』を出版し、サルトルを手厳しく批判していた。フーコーもまたサルトルを「最後のヘーゲル哲学者であり、最後のマルクス主義者」と断じていた。そこで、かれも構造主義の陣営に加わったとみなされるようになる。
反撃がはじまった。共産党のマルクス主義者は、フーコーはニーチェ・イデオロギーに染まっており、かれの考え方は未来への客観的な道を隠蔽するものだと批判した。サルトルもまた、フーコーが歴史を拒否し、マルクス主義を排除しているとみなしていた。
だが、人びとがこぞって『言葉と物』を読んだのは、「人間の死」という強烈なテーゼにひかれたからだけではない。マルクス主義とは異なる新たな世界解釈を待ち望んでいたからにちがいない。問われているのは「近代」だった。
フーコーは当初、構造主義者と呼ばれることに異論を唱えていない。だが、次第に構造主義というレッテルを拒絶するようになる。構造主義と一線を画すために『言葉と物』とは別の本を書きたいと思った。それが1969年に出版される『知の考古学』となって結実するのだ、とエリボンは書いている。
儒教の変容と国学運動──『丸山眞男講義録[第七冊]』を読む(6) [われらの時代]
長々とまとめてきたが、今回が最後である。
近世儒教の核心が宋学、とりわけ朱子学なのはまちがいないが、日本では18世紀ごろから、この核心である朱子学からの偏差、ないし逸脱が大きくなってくる。その代表者が古学派の伊藤仁斎であり、古文辞学派の荻生徂徠だった、と丸山は述べている。
いっぽう、儒教そのものは、18世紀半ば以降、藩校や庶民の学校がつくられて、通俗化されるかたちで、社会的に普及していくことになる。
そして、幕藩体制の流動化とともに、儒教イデオロギーは近代的自然科学の方法と接合(たとえば三浦梅園や山片蟠桃)したり、国際法規範を受容(たとえば横井小楠)したりする方向へと変型されていく。
丸山は、その変型のパターンを三類型にわけている。その区分けは難解でよくわからないが、ぼく流に勝手に解釈すれば、古学、国学、尊皇思想への変型として理解できるのではないかと思う。
いずれにせよ、江戸の半ばごろから朱子学は大きな変容をとげようとしていた。その変容がどのようなものであったかを、丸山は少し立ち入ってみていこうとしている。
ひとつは理気二元論の修正である。貝原益軒は朱子学の理先気後説に疑問を唱え、陽明学に近い立場をとるようになった。伊藤仁斎は朱子学とは逆に気が先にあって理が後にあるという説を唱えた。理よりも気を重視する立場である。
さらに朱子学では「天理を存して仁欲を滅尽す」というが、江戸儒教ではむしろ人欲や功利に高い意義が認められていた。山鹿素行は欲こそが理性の源という考え方を示している。
仁もまた仏教的な慈悲や恩などの心情的契機と結びついた。
政治においても、実際の効果(功利)が重視されるようになる。それがもっとも強く押しだされるのが徂徠学である。儒教は統治術としてとらえられ、個人道徳は統治に役立つかぎり、存在意義を認められる。徂徠の弟子、太宰春台は儒教規範の外面性を主張した。
さらに統治における非合理的契機の重視がみられるようになる。すなわち、徳治をおこなうには民の人情を把握すべし、あるいは時勢をみよ、というように。ここからは古道にしたがうのではなく、リアルな政治認識をもてという主張がでてくる。
いにしえと今とでは時勢がことなるというのは、歴史的相対主義につながる。貝原益軒は、古今を通じて変わらぬ自然法としての「綱常倫理」と状況によって変化する「礼法制度」とは区別しなければならないという考えを打ちだす。さらに熊沢蕃山にいたっては、道と法を区別せよと主張する。相対的な法を絶対的なものと混同すれば、教条主義が生ずるという。水土という風土的契機を強調したのも蕃山だ。
徂徠は「聖人の道」を絶対化した反面、歴史意識を重視した。歴史を知るには、その時代の言語と制度を理解しなければならない。歴史の変遷を無視し、一定の価値基準に立って外から歴史を裁断する方法は、歴史を私物化することになるというのが、徂徠から導かれる教訓だ、と丸山はいう。
「普遍妥当的な『道』も具体的な歴史的条件の変化や地理的・風土的カルチュアの相違を無視しては、空虚な観念論に陥る」といった認識は、「現代の当面している問題や矛盾に直接に対決し、現代の必要に応じた解決の提示への途を開いた」。
それが蕃山、徂徠、春台の開いた制度論・機構論の方法である。それは海保青陵や本多利明、佐藤信淵などにも継承された。
とはいえ、こうした経験的観察の方法も、江戸時代においては歴史的所与をなりゆきとして、ありのままに肯定する現実主義に陥りやすい、と丸山はいう。幕府の武家政治はそのまま是認されがちだった。丸山によれば、江戸時代の「自由思想家」は、しばしば「泰平の世」の賛美をくり返している。
富永仲基は儒・仏・神の三教を批判し、「加上」説を唱えた。それによって、思想のダイナミックな発展をとらえたが、ここからは「今」にたいするいかなる批判も、また未来へ向かっての実践的行動も出てこない、と丸山はいう。それは平賀源内とて同じである。源内には辛辣な社会批判はあるが、その発想は儒教の範疇を出ていないと論じている。
丸山が注目するのは山県大弐の『柳子新論』である。かれは古代日本の王政をたたえ、幕府政治のもとではそれが失われたとして、王政復古を唱える。大弐は崎門学派から尊王論を継承し、徂徠学派から制度論的発想を受け継いで、両者を結合した。これは聖人の途に依拠しながら、幕府の政治を批判した、きわめて稀な例だった。
ここからは国学の話になる。「日本の原型の方法的自覚・復元をテコにして、儒仏その他、一切の外来イデオロギーの異端性を暴露せんとしたのが国学運動にほかならない」と、丸山は述べる。
その思想は反幕的ではなく、むしろ保守的だった。国学の論理は「文学芸術を基盤とし美的価値に依拠するいわば非政治的なナショナリズム」であって、儒仏のみならず、その後も外来の普遍主義を排撃するもっとも協力な論理として今日まで継承されている、と丸山はいう。
国学運動の意義。それは、ひとつに従来政治的価値に従属していた学問・芸術に自律的創造性が与えられ、人間性の自己主張が登場するようになったこと。さらに、鎖国によって閉じこめられていた精神生活の底に沈殿していた原型的思考が発酵し、外的な思想を空虚なものとして突き崩していったこと。そして、国学運動が江戸後期の儒教の変型とあいまって、日本主義なるものを醸成していったこと。
国学運動の源泉は(1)契沖らに代表される歌学の革新、(2)山崎闇斎の開いた垂加神道と尊皇主義(日本中華論)、(3)日本の古典への古学、古文辞学の適用に求められる、と丸山はまとめている。
国学には歌学と記紀というふたつのジャンルがあり、いずれも日本の原型的思考方法を探る試みだった。その志向性を示すのが、宣長の「漢意(からごころ)」にたいする「大和意(やまとごころ)」という言い方である。
個の自覚をうながすこうした発想は、日本の古道を絶対化する方向に走るため、いっぽうで偏狭な日本主義に陥るが、「他面では、世界像を儒教的なそれから解放した」と、丸山は指摘する。それにより、儒教は規範を外から押しつける説教万能主義、人情を切り捨てる偽善とみられるようになった。
国学は自然のままの「真心」を尊重する。しかし、その真心とは何かをめぐって、国学者の意見は割れた。真淵にとって、真心とは「直き心」であって、『万葉集』で読まれているような率直、素朴な古代精神を指していた。いっぽう宣長は真淵の「ますらをぶり」にたいし、「たをやめぶり」にかえって人の「真心」をみいだすことになる。
宣長にみられるのは、修身や治国平天下から歌の心を切り離そうとする志向である。そこからは倫理的・政治的価値から独立した「もののあはれ」という芸術独自の価値基準が生まれてくる。
宣長は『源氏物語』を、儒者のように淫乱の書とは読まなかった。勧善懲悪的な見方から切り離して、よろずのことを心のままに記した物語としてとらえたのである。人の情(こころ)にかなう「物のあはれ」がえがかれていることこそ物語の真骨頂なのだ、と宣長はいう。
しかし、国学はひとつのディレンマをかかえていた。国学にとって、古道は古代の天皇の道である。だが、もういっぽうで、倫理的・政治的価値基準から解放された芸術的精神でもあった。こうしたちがいが、日本主義と文人主義の分裂となってあらわれてくる。たとえば平田篤胤には日本主義の傾向が強いし、上田秋成は文人主義に傾いている。
宣長の政治思想はどのようなものであったか。
宣長は德治主義の正統性を批判する。それは規範と制度によって人民の教化をはかるものだが、しょせん人情には適合せず、現実には建前だけで空転する。德治主義は、権力への野心をもつ者が権力の簒奪を合理化するイデオロギーにすぎない、とまで宣長はいう。
宣長は儒教の規範主義的判断を否定し、善悪の彼岸に立って、天皇の正統性と皇統の連続性を主張した。
宣長にとって政治とは、自然の感情のまま敬虔に権威に奉仕することにほかならなかった。
「政治的なるものを服従者の立場と倫理にすべて還元するのが宣長の基本的な政治的思考態度である」と丸山はいう。上からの治国平天下の道を説く儒者の政治論は空虚で無意味である。
宣長によれば、人民、行政官僚、摂政関白、将軍を含め、すべての者が上級の権威に無条件に奉仕することが、政治であり、まつりごとなのである。
天皇はこれら下級者に政治を委任し(しらしめ)、まつりごとをきこしめすことによって、日本に君臨する。臣下も万民も、天皇の御心を心として従うならば、上と下とがよく和合して、天下はめでたく治まる、と宣長は考えていた。けっして幕府否定論ではない。
平田篤胤らの学派は、こうした宣長の思想を変型し、天皇親政の復古イデオロギーを唱えることになる。
いっぽう、国学には一種の汎美主義、すなわち美的価値によって世界を包摂する傾向がある、と丸山はいう。汎美主義に立つと、リアルな政治的思考は、さかしらで、不潔な打算と感じられるようになる。ここからは、政治はわが事にあらずという静寂主義的な(無関心な)態度も生まれてくる(それは現実の政治をそのまま認める態度でもある)。
その反対に汎美主義からは激情的なファナティシズムが生まれ、それはしばしばラジカルな政治行動として爆発する。その政治行動には政治目標や戦略・戦術がまったく欠落しており、慟哭とか恋闕といったロマン的感情にもとづいて非政治的な政治行動がなされることになる。
国学の斬新さは、儒教や仏教の教学を学問の領域から放逐し、古代言語と文献学の追体験的方法によって獲得される歴史的知識だけに確実な学問的認識を限局しようとしたところにあった、と丸山はいう。没理性的・没批判的な「事実」信仰、あるいは日本古代神話についての無批判的な文献信仰があったにせよ、国学の画期的な意義は否定できない。
「師の説になづむな」という学問的態度を説いた宣長の懐疑的・批判的精神は、新たな学問的認識の地平を切り開いた。しかし、宣長の国学精神は、同時に歴史的・政治的現実を絶対的に肯定するアイロニーとも表裏一体をなしていたのだ、と丸山はまとめている。
こうして東大での丸山の最終講義は終わった。
日本には次々と新しい思想が押し寄せてくる。それは新たな火山灰となって積み重なっていく。しかし、その底には思想の古層があり、さらに外来の仏教や儒教がもたらした分厚い蓄積もあり、さらには国学によって再発見された独自の層も沈殿していることを丸山は教えようとしていた。
近世儒教の核心が宋学、とりわけ朱子学なのはまちがいないが、日本では18世紀ごろから、この核心である朱子学からの偏差、ないし逸脱が大きくなってくる。その代表者が古学派の伊藤仁斎であり、古文辞学派の荻生徂徠だった、と丸山は述べている。
いっぽう、儒教そのものは、18世紀半ば以降、藩校や庶民の学校がつくられて、通俗化されるかたちで、社会的に普及していくことになる。
そして、幕藩体制の流動化とともに、儒教イデオロギーは近代的自然科学の方法と接合(たとえば三浦梅園や山片蟠桃)したり、国際法規範を受容(たとえば横井小楠)したりする方向へと変型されていく。
丸山は、その変型のパターンを三類型にわけている。その区分けは難解でよくわからないが、ぼく流に勝手に解釈すれば、古学、国学、尊皇思想への変型として理解できるのではないかと思う。
いずれにせよ、江戸の半ばごろから朱子学は大きな変容をとげようとしていた。その変容がどのようなものであったかを、丸山は少し立ち入ってみていこうとしている。
ひとつは理気二元論の修正である。貝原益軒は朱子学の理先気後説に疑問を唱え、陽明学に近い立場をとるようになった。伊藤仁斎は朱子学とは逆に気が先にあって理が後にあるという説を唱えた。理よりも気を重視する立場である。
さらに朱子学では「天理を存して仁欲を滅尽す」というが、江戸儒教ではむしろ人欲や功利に高い意義が認められていた。山鹿素行は欲こそが理性の源という考え方を示している。
仁もまた仏教的な慈悲や恩などの心情的契機と結びついた。
政治においても、実際の効果(功利)が重視されるようになる。それがもっとも強く押しだされるのが徂徠学である。儒教は統治術としてとらえられ、個人道徳は統治に役立つかぎり、存在意義を認められる。徂徠の弟子、太宰春台は儒教規範の外面性を主張した。
さらに統治における非合理的契機の重視がみられるようになる。すなわち、徳治をおこなうには民の人情を把握すべし、あるいは時勢をみよ、というように。ここからは古道にしたがうのではなく、リアルな政治認識をもてという主張がでてくる。
いにしえと今とでは時勢がことなるというのは、歴史的相対主義につながる。貝原益軒は、古今を通じて変わらぬ自然法としての「綱常倫理」と状況によって変化する「礼法制度」とは区別しなければならないという考えを打ちだす。さらに熊沢蕃山にいたっては、道と法を区別せよと主張する。相対的な法を絶対的なものと混同すれば、教条主義が生ずるという。水土という風土的契機を強調したのも蕃山だ。
徂徠は「聖人の道」を絶対化した反面、歴史意識を重視した。歴史を知るには、その時代の言語と制度を理解しなければならない。歴史の変遷を無視し、一定の価値基準に立って外から歴史を裁断する方法は、歴史を私物化することになるというのが、徂徠から導かれる教訓だ、と丸山はいう。
「普遍妥当的な『道』も具体的な歴史的条件の変化や地理的・風土的カルチュアの相違を無視しては、空虚な観念論に陥る」といった認識は、「現代の当面している問題や矛盾に直接に対決し、現代の必要に応じた解決の提示への途を開いた」。
それが蕃山、徂徠、春台の開いた制度論・機構論の方法である。それは海保青陵や本多利明、佐藤信淵などにも継承された。
とはいえ、こうした経験的観察の方法も、江戸時代においては歴史的所与をなりゆきとして、ありのままに肯定する現実主義に陥りやすい、と丸山はいう。幕府の武家政治はそのまま是認されがちだった。丸山によれば、江戸時代の「自由思想家」は、しばしば「泰平の世」の賛美をくり返している。
富永仲基は儒・仏・神の三教を批判し、「加上」説を唱えた。それによって、思想のダイナミックな発展をとらえたが、ここからは「今」にたいするいかなる批判も、また未来へ向かっての実践的行動も出てこない、と丸山はいう。それは平賀源内とて同じである。源内には辛辣な社会批判はあるが、その発想は儒教の範疇を出ていないと論じている。
丸山が注目するのは山県大弐の『柳子新論』である。かれは古代日本の王政をたたえ、幕府政治のもとではそれが失われたとして、王政復古を唱える。大弐は崎門学派から尊王論を継承し、徂徠学派から制度論的発想を受け継いで、両者を結合した。これは聖人の途に依拠しながら、幕府の政治を批判した、きわめて稀な例だった。
ここからは国学の話になる。「日本の原型の方法的自覚・復元をテコにして、儒仏その他、一切の外来イデオロギーの異端性を暴露せんとしたのが国学運動にほかならない」と、丸山は述べる。
その思想は反幕的ではなく、むしろ保守的だった。国学の論理は「文学芸術を基盤とし美的価値に依拠するいわば非政治的なナショナリズム」であって、儒仏のみならず、その後も外来の普遍主義を排撃するもっとも協力な論理として今日まで継承されている、と丸山はいう。
国学運動の意義。それは、ひとつに従来政治的価値に従属していた学問・芸術に自律的創造性が与えられ、人間性の自己主張が登場するようになったこと。さらに、鎖国によって閉じこめられていた精神生活の底に沈殿していた原型的思考が発酵し、外的な思想を空虚なものとして突き崩していったこと。そして、国学運動が江戸後期の儒教の変型とあいまって、日本主義なるものを醸成していったこと。
国学運動の源泉は(1)契沖らに代表される歌学の革新、(2)山崎闇斎の開いた垂加神道と尊皇主義(日本中華論)、(3)日本の古典への古学、古文辞学の適用に求められる、と丸山はまとめている。
国学には歌学と記紀というふたつのジャンルがあり、いずれも日本の原型的思考方法を探る試みだった。その志向性を示すのが、宣長の「漢意(からごころ)」にたいする「大和意(やまとごころ)」という言い方である。
個の自覚をうながすこうした発想は、日本の古道を絶対化する方向に走るため、いっぽうで偏狭な日本主義に陥るが、「他面では、世界像を儒教的なそれから解放した」と、丸山は指摘する。それにより、儒教は規範を外から押しつける説教万能主義、人情を切り捨てる偽善とみられるようになった。
国学は自然のままの「真心」を尊重する。しかし、その真心とは何かをめぐって、国学者の意見は割れた。真淵にとって、真心とは「直き心」であって、『万葉集』で読まれているような率直、素朴な古代精神を指していた。いっぽう宣長は真淵の「ますらをぶり」にたいし、「たをやめぶり」にかえって人の「真心」をみいだすことになる。
宣長にみられるのは、修身や治国平天下から歌の心を切り離そうとする志向である。そこからは倫理的・政治的価値から独立した「もののあはれ」という芸術独自の価値基準が生まれてくる。
宣長は『源氏物語』を、儒者のように淫乱の書とは読まなかった。勧善懲悪的な見方から切り離して、よろずのことを心のままに記した物語としてとらえたのである。人の情(こころ)にかなう「物のあはれ」がえがかれていることこそ物語の真骨頂なのだ、と宣長はいう。
しかし、国学はひとつのディレンマをかかえていた。国学にとって、古道は古代の天皇の道である。だが、もういっぽうで、倫理的・政治的価値基準から解放された芸術的精神でもあった。こうしたちがいが、日本主義と文人主義の分裂となってあらわれてくる。たとえば平田篤胤には日本主義の傾向が強いし、上田秋成は文人主義に傾いている。
宣長の政治思想はどのようなものであったか。
宣長は德治主義の正統性を批判する。それは規範と制度によって人民の教化をはかるものだが、しょせん人情には適合せず、現実には建前だけで空転する。德治主義は、権力への野心をもつ者が権力の簒奪を合理化するイデオロギーにすぎない、とまで宣長はいう。
宣長は儒教の規範主義的判断を否定し、善悪の彼岸に立って、天皇の正統性と皇統の連続性を主張した。
宣長にとって政治とは、自然の感情のまま敬虔に権威に奉仕することにほかならなかった。
「政治的なるものを服従者の立場と倫理にすべて還元するのが宣長の基本的な政治的思考態度である」と丸山はいう。上からの治国平天下の道を説く儒者の政治論は空虚で無意味である。
宣長によれば、人民、行政官僚、摂政関白、将軍を含め、すべての者が上級の権威に無条件に奉仕することが、政治であり、まつりごとなのである。
天皇はこれら下級者に政治を委任し(しらしめ)、まつりごとをきこしめすことによって、日本に君臨する。臣下も万民も、天皇の御心を心として従うならば、上と下とがよく和合して、天下はめでたく治まる、と宣長は考えていた。けっして幕府否定論ではない。
平田篤胤らの学派は、こうした宣長の思想を変型し、天皇親政の復古イデオロギーを唱えることになる。
いっぽう、国学には一種の汎美主義、すなわち美的価値によって世界を包摂する傾向がある、と丸山はいう。汎美主義に立つと、リアルな政治的思考は、さかしらで、不潔な打算と感じられるようになる。ここからは、政治はわが事にあらずという静寂主義的な(無関心な)態度も生まれてくる(それは現実の政治をそのまま認める態度でもある)。
その反対に汎美主義からは激情的なファナティシズムが生まれ、それはしばしばラジカルな政治行動として爆発する。その政治行動には政治目標や戦略・戦術がまったく欠落しており、慟哭とか恋闕といったロマン的感情にもとづいて非政治的な政治行動がなされることになる。
国学の斬新さは、儒教や仏教の教学を学問の領域から放逐し、古代言語と文献学の追体験的方法によって獲得される歴史的知識だけに確実な学問的認識を限局しようとしたところにあった、と丸山はいう。没理性的・没批判的な「事実」信仰、あるいは日本古代神話についての無批判的な文献信仰があったにせよ、国学の画期的な意義は否定できない。
「師の説になづむな」という学問的態度を説いた宣長の懐疑的・批判的精神は、新たな学問的認識の地平を切り開いた。しかし、宣長の国学精神は、同時に歴史的・政治的現実を絶対的に肯定するアイロニーとも表裏一体をなしていたのだ、と丸山はまとめている。
こうして東大での丸山の最終講義は終わった。
日本には次々と新しい思想が押し寄せてくる。それは新たな火山灰となって積み重なっていく。しかし、その底には思想の古層があり、さらに外来の仏教や儒教がもたらした分厚い蓄積もあり、さらには国学によって再発見された独自の層も沈殿していることを丸山は教えようとしていた。
新型コロナをめぐるケネス・ルオフ氏(ポートランド州立大学教授)の論考 [雑記]

5月21日付の日本経済新聞に『国民の天皇』の著者として知られるケネス・ルオフ氏の論考が掲載されました。これは50日ほど前の拙訳をダイジェストしたものです。
消えてしまうのもおしいので、4月7日に訳出したそのオリジナル版をここに紹介しておきます。
市場システム以上に公益に配慮を
ケネス・ルオフ(ポートランド州立大学歴史学教授)
この原稿を書いている米国には現在パンデミックが押し寄せており、私の住んでいるオレゴン州ポートランドも例外ではないが、かろうじて最悪の事態は免れそうな気配だ。このような危機的状況において、何よりもだいじなのは、自分たちの基本的な価値感を確認することである。しかし、どのような価値感が真に重要か、あるいはそうでないかをあきらかにしなければならない。重要なのは全般的な公共福祉を推進することであって、「純粋市場」の力を信奉することではない。
ウイルスは世界中で、だれもがそれに直面していることを思い起こさせてくれた。それだけではない。現に社会には公益があること、だれもがコミュニティと責任という感覚を分かちあっていることをも教えてくれた。それは、国内的、国際的なレベルを問わない。もし公益がないなら、医療従事者がパンデミックを抑えようとして、懸命に努力することなどありえないだろう。いまの時点で、パンデミックを市場の力にまかせるべきだと言う人が数多くいるとは思えない。
とはいえ、この四十年間、先進国ではできるかぎり何もかも市場にまかせるべきだという考え方が主流になっており、それ以外は事実上あまり顧みられてこなかった。新自由主義を採用したどの国でも、公益の領域は縮小していた。
新自由主義は国によって異なる現れ方をしてきた。米国では、次のような公益分野が取り消されたり周辺においやられたりしている。精神疾患の治療、豊かな国ではとうぜんなさるべき水準の科学的調査、だれにとっても手の届く高等教育、公園やレクリエーション施設、広義のインフラストラクチャー、公衆衛生など。そうした分野に必要となる適切な資金が削られているのだ。以上はごく一部の例にすぎない。だが、それだけでも公益が周縁においやられているという感は否めない。
オレゴン州で、公益を圧縮する動きがあらわになったのは、1990年の州法案5が可決されてからである。この法案は財産にもとづいて支払われる教育税に限度を設けるもので、そのころ新自由主義が支配的になりつつあった米国では、税制見直しの波が各地をおおっていた。
日本人は新自由主義によって国の公益から押しだされた部分を何とか維持しているといえるだろう。それは日本が幸いにも米国や英国、西欧諸国ほどには新自由主義を取り入れなかったためである。それでも新自由主義は日本でも公益の領域を減少させてきた。
その間、社会経済的な不平等は次第に深刻さを増していた。純粋市場なるものにすべてを委ねるべきだと主張した人たちは、2007−2008年の金融危機以降におきた景気悪化を自分たちの責任としてとらえようとせず、むしろリベラルすぎるオバマ政権の大きな政府による「救済措置」に非難の矢を向けた。とはいえ、その救済措置は、そもそも直近のブッシュ政権の政策を引き継いだものだったのである。
しかし、すべては純粋市場まかせという王様は、今やまさに裸の王様なのだ。トランプ大統領に督促されて、共和党支配の上院は2兆ドルの経済救済対策を満場一致で可決した。市場への不介入を信条とするある下院議員は、下院でこの救済措置を阻止しようとしたが、民主、共和両党からも変人扱いされるほどだった。
私自身の立場を明らかにしておこう。私は各国政府が世界経済システムの崩壊を防ぐために努力していることに反対しているわけではない。また、資本主義に反対しているわけでもない。
しかし、アメリカ社会のあらゆる領域に行き渡っている市場こそすべてという考え方、実際には市場の私物化にだまされないようにすべきだと考えている。というのも、連邦準備銀行による2兆円の経済措置をはじめとして、市場への大幅介入という基本的な対策自体が、市場こそすべてという観念が神話にすぎないことを示しているからである。
市場が働けば働くほど社会全体がよくなるという考え方は間違っている。願わくば、そのことを世界中の人々が認識してほしいものだ。
医療関係者が必要とする個人防御具(PPE)が絶望的に不足している惨状を市場が魔法の力で解決してくれるわけではないことを、われわれは学びつつある。市場はそれでも事態の改善にそれなりの役割を果たすかもしれない。しかし、市場だけでは公益を提供することができない。
いったんこのウイルスを克服しても(次にやってくる公衆衛生上の脅威に備えることも含めて)、ほかにも市場の力だけにまかせておくべきではない社会の分野があるということを覚えておかなければならない。公益の範囲をふたたびいかに拡大していくかを、もう一度考え直す必要がある。自分たち自身の歴史を振り返ってみても、それは資本主義を廃止しなくてもできることなのである。
近世儒教とその批判──『丸山眞男講義録[第七冊]』を読む(5) [われらの時代]
丸山はこう述べている。
『論語』が日本にもたらされたのは応神天皇のときとされ、それ以来、儒教は日本の歴史とともにあった。聖徳太子の十七条憲法には、儒教の影響が強い。律令時代の制度もそうだ。しかし、平安時代にはいると、思想界は圧倒的に仏教の支配下に置かれるようになる。
鎌倉時代にはいると、儒教は復活する。幕府の正統性が求めらるようになったからである。とはいえ、武士全体のエートスは、かならずしも儒教と一致していたわけではない。
中世を通じ、儒教は五山の禅僧によって継承され、その注釈がなされていた。宋学、すなわち朱子学が日本にはいってくるのはそのころだ。
しかし、訓詁学としてではなく、統治のイデオロギーとして儒教が脚光を浴びるのは、戦国大名が登場してからである。家臣団の組織化と領国農民の把握が求められていた。
江戸時代において、儒教、とりわけ朱子学が正統な体制イデオロギーになったといわれるのは、ある意味では正しいし、ある意味では正しくない、と丸山はいう。
家康は藤原惺窩を引見し、林羅山を登用した。同時に政治的秘書役として、僧の天海や崇伝を採用している。江戸時代を通じて、仏教は宗教行事として武士や庶民のあいだに浸透する。
しかし、幕府の政治を武断から文治に転換させるイデオロギー的役割をになったのは儒教だった。君父の道を説く現世思想にほかならなかったからである。
林羅山は朱子学者としてより、一種の物知りとして、4代の将軍に仕えた、と丸山はいう。幕府は教学振興のために儒教を奨励したが、朱子学だけを尊重したわけではなかった。それは6代、7代将軍に新井白石が仕え、8代吉宗に荻生徂徠が重用されたことをみてもわかる。
湯島昌平坂にあった林家の私塾が、公式に幕府の学問所となるのは、松平定信の寛政異学の禁(1790年)以後にすぎない。
17世紀半ばには、熊沢蕃山や山鹿素行が幕府によって排斥されている。だが、これは朱子学以外が禁止されたからではない。そのころ、京都では伊藤仁斎が民間儒者として宋学に代わる古学を提唱し、数千人の門人を集めていたが、幕府はむしろこれを容認している。
朱子学が官学とみなされるのは、18世紀末の寛政の改革においてであり、だからといって、それ以前もそれ以降も、儒教は朱子学しか認められなかったというわけではない。
武家政治はかならずしも儒教の政治理念とは一致しなかった。とはいえ、江戸時代において、儒教は思想や教育の面で大きな影響をおよぼしている。その影響は浄瑠璃や文学などでもみられる。
四書五経は諸藩の藩校だけではなく、寺子屋や塾などでも教えられていた。その意味で、江戸時代において、儒教はもっとも常識化した教えになっていた。しかし、幕藩体制の崩壊とともに、儒教は教育の中心からはずされていくことになる。
そもそも儒教思想とはなんだろう。その始まりから分岐と合流をくり返す数千年にわたる複雑な流れをたどるのは困難である。何がほんとうの儒教であり、何がその逸脱や歪曲であるのかを問うのも、意味がないだろう。だいじなのは、江戸時代において、儒教がどのように受け止められていたかだ、と丸山はいう。
さらに丸山は、儒教は江戸時代には人倫の基本を説いた教科書、あるいは治国平天下の統治原理として受け止められてきたが、たとえば『論語』には、それにとどまらないおもしろさ、いわば人生の知恵が盛りこまれていることにも注目をうながしている。
それはともかく、江戸の儒教は宋学、反宋学的傾向を含めて、ポスト宋学だったとみてよい、と丸山は論じている。儒教がもっとも活発だったのは18世紀中ごろまで。後半期にも寛政の三博士(柴野栗山、古賀精里、尾藤二洲)、天保期の佐藤一斎、大塩中斎がでてくる。
しかし、江戸も後半にはいると、アンチ儒教の国学が登場するし、安藤昌益や三浦梅園、本多利明、佐藤信淵といった儒教からはみだした思想家が活躍しはじめる。
そこで、丸山は儒教がもっとも活発だった18世紀半ばまでの儒教的観念がどういうものだったかを述べている。
基本は「天人相関」の概念だった、と丸山はいう。
天(自然)には一定の法則と秩序がある。そして自然界と社会関係、人間精神とのあいだには、密接な連関がある。これが「天人相関」である。
陰陽五行が万物を生じ、化育させる。天地の運行と社会秩序の再生産とは対応している。いっぽうにおける調和の破壊は、他方の秩序を攪乱させる。天子には、この調和を保つという使命が託されている。
人間道徳の基本は天命にしたがうことである。そのためには五倫、すなわち君臣、父子、夫婦、長幼、朋友の秩序が守られねばならない。これは永遠不変の「自然的秩序」である。
天地が万物を化育するように、徳を積んだ君主は社会のなかに万人を配置し、化育する。それによって、人は五倫を学び、礼的秩序にしたがう。自然界の災厄を防ぎ、宇宙の運動を円滑にするのも為政者の責任である。
人はまず修身を学ばねばならない。大切なのは、家庭のなかで家父長への恭順(孝)を習得することであり、それがやがて政治秩序(君臣の義)を守ることにつながる。
程朱学は天人相関思想を理気論によって基礎づけた、と丸山はいう。そこには太極図説にあらわされる独自の宇宙論的形而上学がある。天理が陰陽五行を通じて万物を化成する。それに形を付与するのが気である。たとえば、種から花が生じ、赤子から人が成長するように。
すべてのものは理と気の結合から成っており、気の作用で差別と運動が生ずる。人間はすぐれた気を受けているから、万物の霊長となる。だが、それでも気質の差があって、それが人品のちがいをもたらす。
丸山は宋学について、さらに詳しく述べているが、頭がこんがらがってきそうなので、そのあたりは省略しよう。
いまは朱子学が天人合一の自然的秩序観をもっていたことを理解しておけばよいだろう。
そこからはまず身分的統治関係を自然とする考え方がでてくる。
天が上にあり地が下にあるのと同様に、君臣の上下が乱れなければ、国はおさまるというわけである。
さらに身分は尊卑という価値判断ともつながっている。聖賢君子による愚民にたいする支配は天命として正当化された。
しかし、上下貴賤の別が永遠不変の道として正当化されるためには、君は君であり、臣は臣であることが求められる。名と実が離反してはならないのだ。君臣関係や家族的秩序が混乱することは避けなければならない。
そこからは名分を正すという発想がでてくる。いかに王権が衰微しようとも、正統な統治者はあくまでも統治者でなければならない。
礼的な秩序は、現実の力関係にしたがうことではなく、正統な王に服従することによって保たれるのである。
幕末にいたって、朱子学のこうした大義名分的な尊王論は、忠誠関係を天皇に移転する役割をはたした。現実にはまったく実力のない天皇を正統な統治者として、大政奉還、王政復古をもたらすことになるのである。
もうひとつ、自然的秩序の論理からは社会的職分の思想がでてくる、と丸山はいう。各人は天から与えられた場を職分として守ることによって、全体的システムの循環が保証されるという倫理意識である。これは一種の社会分業論でもある。ここでは支配被支配の関係よりも社会全体の相互関係の論理が強調されている。
江戸時代は職業選択の自由はなく、与えられた身分と職に応じて、職分を尽くすことが求められた。それは被治者にかぎらない。統治者にとっては、人民に仁政をほどこすことが、その職分とみなされていた。
しかし、概してその倫理は「知足安分」、すなわちおのれの分を知るという消極的態度に停滞しがちだった。そして、身を律して、よき政治をおこなうという統治者の規範は、しばしばゆるみがちだった。
儒教には易姓革命の思想もある。統治者が仁政安民の義務を怠れば、暴君征伐(あるいは禅譲)を正当とするという考え方である。
この革命論を打ちだしたのは孔子ではなく孟子であり、そこには王朝の交替を正当化する意図が含まれている。人民革命が肯定されたわけではない。あくまでも暴君を取り除くことが目的だった。
儒教が理想とするのは、徳ある統治者による仁政である。武力・軍事力の行使、厳しい法と刑による支配は、徳治の理念に反する。
かくて王覇の弁別がなされる。すなわち王道と覇道。徳による仁政が王道だとすれば、軍国主義ないし権力政治が覇道である。
しかし、権力は手段であって、それによって安民仁政が実現することもありうる。権は常道に反する非常手段だが、結果的に道に合する場合もある。時に臨機応変で、事の軽重を判断し、すばやく行動することも重要とされる。
江戸時代においては権道や権謀に相対的に高い価値判断が与えられていた、と丸山はいう。それは覇者を高く評価する考え方にもつながっていた。そのいっぽう、君臣の義を絶対とする思想のもとでは、革命権の主張はむしろ抑えられていた。
皇室と幕府との関係はどうだったのか。王者・覇者の区別は名実論とも結びついていた。すなわち名のみある帝王と、その帝王からの授権にもとづいて実力ある覇者が国主として領土を支配するという関係。この名実論は幕末になって大義名分論へと転化し、攘夷論と化合し、「尊皇斥覇」の思想に発展していくことになる。
攘夷論が、儒教における華夷内外の弁別に由来することはいうまでもない。これは自民族を中心とする国際秩序をさすが、もともと中華思想は、武力・軍事ではなく、礼楽を持つ文化にこそ優越性があるという考え方に根ざしていた。中央の支配者が野蛮な周辺民族に文化の恩恵を授けるという意識が強かった。
しかし、日本では中華思想をそのまま認めるわけにはいかなかった。それを認めれば日本が中国に従属する「東夷」となってしまうからである。そこで日本で「攘夷」が語られるさいには、独特のバイアスがかかってくる、と丸山はいう。
日本を「中華」とするには、中華思想を逆転的に読み替える必要があった。
儒教にはさらに「天下」という独特の概念があった。丸山によれば、「『天下』概念は『国家』概念の上位に立ち、世界=コスモスを意味する」。とはいえ、日本では「天下」は世界ではなく、日本全体のことを指し、「国家」とは藩の呼称にほかならなかった。
とはいえ、天下は基本的に世界概念であり、天下に妥当する道が天道だった。そこからは一視同仁の世界主義が生まれる。
江戸時代には、天下は天下の天下なりということばが頻繁に登場する(山片蟠桃もよく使った)。天下は一人の天下にあらずという意味が含まれている。そこには公共性の概念とともに、独裁政策への批判意識がはたらいている。
逆に天に二日なく、民に二王なしという言い方もある(孟子)。これはいわば一君万民思想であり、日本でもっとも早くから摂取された思想である。「十七条憲法」にもこの表現がある。武家社会の発展とともに、この表現はあまり用いられなくなるが、幕末には尊王論とともに、ふたたび登場してくる。
こうしてみると、儒教思想には両極志向性がある、と丸山はいう。異なった社会的・歴史的文脈におくと、儒教のカテゴリーはいかようにも読むことができるのである。
たとえば、いくら為政者に徳があっても、それだけで仁政がかなうとはかぎらない。君は君たり、臣は臣たりの思想は、君君たらざれば、臣臣たらずということにつながった。さらには君君たらずとも、臣臣たらざるべからずという服従倫理もでてくる。あげくのはてに主君の意に反して行動するのは、かえって主君のためだという考え方も登場する。
時に忠と孝はどちらが優先するのかという矛盾も生じる。大義親を滅すという考え方もあれば、父は天地のあいだの一人だが、君というものは天下に何人もいるという見方もある。
要するに、儒教思想にはこうした両義性が隠されている、と丸山はいう。
儒教は一面、現実政治への批判の武器となりうる。しかし、それでも秩序価値の比重がずっと高かった。
丸山は儒教をこう批判している。
〈[儒教では]秩序の基本的構想自体が、人間の上下関係と親疎関係を基軸とした秩序であって、そうした特殊な人間の秩序づけが秩序一般と等値され、それからの背反は直ちに無秩序──つまりジャングルの法則だけが支配する禽獣世界への転落を意味すると考えられたのである。ここには、普遍的な平等と友愛理念を基盤として、他者との間に関係をとりむすぶこともまた秩序形成であるという考え方、あるいはまた、自他の利害の対立、少くも不一致を社会の出発点とし、そうした特殊利害の間の抗争・妥協・調整のプロセスを通じて、自発的に、いわば下から共同利害が形成されてゆくのも秩序形成の一つのあり方であるという考え方も、はじめから視野の外にあったのである。〉
ここには儒教思想を批判し、民主主義を打ち立てようとする丸山の視座がはっきりと表明されている。
修身斉家治国平天下という道徳主義的な統治思想にたいしても、丸山ははっきりと批判している。
〈修身斉家治国平天下というような道徳と政治を直接的に連続させ、また、統治作用を治者による被治者の人倫への教化と見ることは、政治的認識としてあまりに素朴であるだけでなく、一方で政治権力を無限界に精神的領域に侵入させるとともに、他方で儒教の家族内倫理に現われているように、道徳の領域に強制力を伴う統治関係をもちこむ傾向をうむ。こうして、もっとも悪い場合には、権力的強制を道徳的に粉飾し、逆に道徳から内面性をうばって、これを共同体もしくは集団への順応に堕さしめることになる。〉
そして、問題は、このような秩序観や政治観が、下意識の次元で、いまも残っていることなのである、と丸山は述べている。
『論語』が日本にもたらされたのは応神天皇のときとされ、それ以来、儒教は日本の歴史とともにあった。聖徳太子の十七条憲法には、儒教の影響が強い。律令時代の制度もそうだ。しかし、平安時代にはいると、思想界は圧倒的に仏教の支配下に置かれるようになる。
鎌倉時代にはいると、儒教は復活する。幕府の正統性が求めらるようになったからである。とはいえ、武士全体のエートスは、かならずしも儒教と一致していたわけではない。
中世を通じ、儒教は五山の禅僧によって継承され、その注釈がなされていた。宋学、すなわち朱子学が日本にはいってくるのはそのころだ。
しかし、訓詁学としてではなく、統治のイデオロギーとして儒教が脚光を浴びるのは、戦国大名が登場してからである。家臣団の組織化と領国農民の把握が求められていた。
江戸時代において、儒教、とりわけ朱子学が正統な体制イデオロギーになったといわれるのは、ある意味では正しいし、ある意味では正しくない、と丸山はいう。
家康は藤原惺窩を引見し、林羅山を登用した。同時に政治的秘書役として、僧の天海や崇伝を採用している。江戸時代を通じて、仏教は宗教行事として武士や庶民のあいだに浸透する。
しかし、幕府の政治を武断から文治に転換させるイデオロギー的役割をになったのは儒教だった。君父の道を説く現世思想にほかならなかったからである。
林羅山は朱子学者としてより、一種の物知りとして、4代の将軍に仕えた、と丸山はいう。幕府は教学振興のために儒教を奨励したが、朱子学だけを尊重したわけではなかった。それは6代、7代将軍に新井白石が仕え、8代吉宗に荻生徂徠が重用されたことをみてもわかる。
湯島昌平坂にあった林家の私塾が、公式に幕府の学問所となるのは、松平定信の寛政異学の禁(1790年)以後にすぎない。
17世紀半ばには、熊沢蕃山や山鹿素行が幕府によって排斥されている。だが、これは朱子学以外が禁止されたからではない。そのころ、京都では伊藤仁斎が民間儒者として宋学に代わる古学を提唱し、数千人の門人を集めていたが、幕府はむしろこれを容認している。
朱子学が官学とみなされるのは、18世紀末の寛政の改革においてであり、だからといって、それ以前もそれ以降も、儒教は朱子学しか認められなかったというわけではない。
武家政治はかならずしも儒教の政治理念とは一致しなかった。とはいえ、江戸時代において、儒教は思想や教育の面で大きな影響をおよぼしている。その影響は浄瑠璃や文学などでもみられる。
四書五経は諸藩の藩校だけではなく、寺子屋や塾などでも教えられていた。その意味で、江戸時代において、儒教はもっとも常識化した教えになっていた。しかし、幕藩体制の崩壊とともに、儒教は教育の中心からはずされていくことになる。
そもそも儒教思想とはなんだろう。その始まりから分岐と合流をくり返す数千年にわたる複雑な流れをたどるのは困難である。何がほんとうの儒教であり、何がその逸脱や歪曲であるのかを問うのも、意味がないだろう。だいじなのは、江戸時代において、儒教がどのように受け止められていたかだ、と丸山はいう。
さらに丸山は、儒教は江戸時代には人倫の基本を説いた教科書、あるいは治国平天下の統治原理として受け止められてきたが、たとえば『論語』には、それにとどまらないおもしろさ、いわば人生の知恵が盛りこまれていることにも注目をうながしている。
それはともかく、江戸の儒教は宋学、反宋学的傾向を含めて、ポスト宋学だったとみてよい、と丸山は論じている。儒教がもっとも活発だったのは18世紀中ごろまで。後半期にも寛政の三博士(柴野栗山、古賀精里、尾藤二洲)、天保期の佐藤一斎、大塩中斎がでてくる。
しかし、江戸も後半にはいると、アンチ儒教の国学が登場するし、安藤昌益や三浦梅園、本多利明、佐藤信淵といった儒教からはみだした思想家が活躍しはじめる。
そこで、丸山は儒教がもっとも活発だった18世紀半ばまでの儒教的観念がどういうものだったかを述べている。
基本は「天人相関」の概念だった、と丸山はいう。
天(自然)には一定の法則と秩序がある。そして自然界と社会関係、人間精神とのあいだには、密接な連関がある。これが「天人相関」である。
陰陽五行が万物を生じ、化育させる。天地の運行と社会秩序の再生産とは対応している。いっぽうにおける調和の破壊は、他方の秩序を攪乱させる。天子には、この調和を保つという使命が託されている。
人間道徳の基本は天命にしたがうことである。そのためには五倫、すなわち君臣、父子、夫婦、長幼、朋友の秩序が守られねばならない。これは永遠不変の「自然的秩序」である。
天地が万物を化育するように、徳を積んだ君主は社会のなかに万人を配置し、化育する。それによって、人は五倫を学び、礼的秩序にしたがう。自然界の災厄を防ぎ、宇宙の運動を円滑にするのも為政者の責任である。
人はまず修身を学ばねばならない。大切なのは、家庭のなかで家父長への恭順(孝)を習得することであり、それがやがて政治秩序(君臣の義)を守ることにつながる。
程朱学は天人相関思想を理気論によって基礎づけた、と丸山はいう。そこには太極図説にあらわされる独自の宇宙論的形而上学がある。天理が陰陽五行を通じて万物を化成する。それに形を付与するのが気である。たとえば、種から花が生じ、赤子から人が成長するように。
すべてのものは理と気の結合から成っており、気の作用で差別と運動が生ずる。人間はすぐれた気を受けているから、万物の霊長となる。だが、それでも気質の差があって、それが人品のちがいをもたらす。
丸山は宋学について、さらに詳しく述べているが、頭がこんがらがってきそうなので、そのあたりは省略しよう。
いまは朱子学が天人合一の自然的秩序観をもっていたことを理解しておけばよいだろう。
そこからはまず身分的統治関係を自然とする考え方がでてくる。
天が上にあり地が下にあるのと同様に、君臣の上下が乱れなければ、国はおさまるというわけである。
さらに身分は尊卑という価値判断ともつながっている。聖賢君子による愚民にたいする支配は天命として正当化された。
しかし、上下貴賤の別が永遠不変の道として正当化されるためには、君は君であり、臣は臣であることが求められる。名と実が離反してはならないのだ。君臣関係や家族的秩序が混乱することは避けなければならない。
そこからは名分を正すという発想がでてくる。いかに王権が衰微しようとも、正統な統治者はあくまでも統治者でなければならない。
礼的な秩序は、現実の力関係にしたがうことではなく、正統な王に服従することによって保たれるのである。
幕末にいたって、朱子学のこうした大義名分的な尊王論は、忠誠関係を天皇に移転する役割をはたした。現実にはまったく実力のない天皇を正統な統治者として、大政奉還、王政復古をもたらすことになるのである。
もうひとつ、自然的秩序の論理からは社会的職分の思想がでてくる、と丸山はいう。各人は天から与えられた場を職分として守ることによって、全体的システムの循環が保証されるという倫理意識である。これは一種の社会分業論でもある。ここでは支配被支配の関係よりも社会全体の相互関係の論理が強調されている。
江戸時代は職業選択の自由はなく、与えられた身分と職に応じて、職分を尽くすことが求められた。それは被治者にかぎらない。統治者にとっては、人民に仁政をほどこすことが、その職分とみなされていた。
しかし、概してその倫理は「知足安分」、すなわちおのれの分を知るという消極的態度に停滞しがちだった。そして、身を律して、よき政治をおこなうという統治者の規範は、しばしばゆるみがちだった。
儒教には易姓革命の思想もある。統治者が仁政安民の義務を怠れば、暴君征伐(あるいは禅譲)を正当とするという考え方である。
この革命論を打ちだしたのは孔子ではなく孟子であり、そこには王朝の交替を正当化する意図が含まれている。人民革命が肯定されたわけではない。あくまでも暴君を取り除くことが目的だった。
儒教が理想とするのは、徳ある統治者による仁政である。武力・軍事力の行使、厳しい法と刑による支配は、徳治の理念に反する。
かくて王覇の弁別がなされる。すなわち王道と覇道。徳による仁政が王道だとすれば、軍国主義ないし権力政治が覇道である。
しかし、権力は手段であって、それによって安民仁政が実現することもありうる。権は常道に反する非常手段だが、結果的に道に合する場合もある。時に臨機応変で、事の軽重を判断し、すばやく行動することも重要とされる。
江戸時代においては権道や権謀に相対的に高い価値判断が与えられていた、と丸山はいう。それは覇者を高く評価する考え方にもつながっていた。そのいっぽう、君臣の義を絶対とする思想のもとでは、革命権の主張はむしろ抑えられていた。
皇室と幕府との関係はどうだったのか。王者・覇者の区別は名実論とも結びついていた。すなわち名のみある帝王と、その帝王からの授権にもとづいて実力ある覇者が国主として領土を支配するという関係。この名実論は幕末になって大義名分論へと転化し、攘夷論と化合し、「尊皇斥覇」の思想に発展していくことになる。
攘夷論が、儒教における華夷内外の弁別に由来することはいうまでもない。これは自民族を中心とする国際秩序をさすが、もともと中華思想は、武力・軍事ではなく、礼楽を持つ文化にこそ優越性があるという考え方に根ざしていた。中央の支配者が野蛮な周辺民族に文化の恩恵を授けるという意識が強かった。
しかし、日本では中華思想をそのまま認めるわけにはいかなかった。それを認めれば日本が中国に従属する「東夷」となってしまうからである。そこで日本で「攘夷」が語られるさいには、独特のバイアスがかかってくる、と丸山はいう。
日本を「中華」とするには、中華思想を逆転的に読み替える必要があった。
儒教にはさらに「天下」という独特の概念があった。丸山によれば、「『天下』概念は『国家』概念の上位に立ち、世界=コスモスを意味する」。とはいえ、日本では「天下」は世界ではなく、日本全体のことを指し、「国家」とは藩の呼称にほかならなかった。
とはいえ、天下は基本的に世界概念であり、天下に妥当する道が天道だった。そこからは一視同仁の世界主義が生まれる。
江戸時代には、天下は天下の天下なりということばが頻繁に登場する(山片蟠桃もよく使った)。天下は一人の天下にあらずという意味が含まれている。そこには公共性の概念とともに、独裁政策への批判意識がはたらいている。
逆に天に二日なく、民に二王なしという言い方もある(孟子)。これはいわば一君万民思想であり、日本でもっとも早くから摂取された思想である。「十七条憲法」にもこの表現がある。武家社会の発展とともに、この表現はあまり用いられなくなるが、幕末には尊王論とともに、ふたたび登場してくる。
こうしてみると、儒教思想には両極志向性がある、と丸山はいう。異なった社会的・歴史的文脈におくと、儒教のカテゴリーはいかようにも読むことができるのである。
たとえば、いくら為政者に徳があっても、それだけで仁政がかなうとはかぎらない。君は君たり、臣は臣たりの思想は、君君たらざれば、臣臣たらずということにつながった。さらには君君たらずとも、臣臣たらざるべからずという服従倫理もでてくる。あげくのはてに主君の意に反して行動するのは、かえって主君のためだという考え方も登場する。
時に忠と孝はどちらが優先するのかという矛盾も生じる。大義親を滅すという考え方もあれば、父は天地のあいだの一人だが、君というものは天下に何人もいるという見方もある。
要するに、儒教思想にはこうした両義性が隠されている、と丸山はいう。
儒教は一面、現実政治への批判の武器となりうる。しかし、それでも秩序価値の比重がずっと高かった。
丸山は儒教をこう批判している。
〈[儒教では]秩序の基本的構想自体が、人間の上下関係と親疎関係を基軸とした秩序であって、そうした特殊な人間の秩序づけが秩序一般と等値され、それからの背反は直ちに無秩序──つまりジャングルの法則だけが支配する禽獣世界への転落を意味すると考えられたのである。ここには、普遍的な平等と友愛理念を基盤として、他者との間に関係をとりむすぶこともまた秩序形成であるという考え方、あるいはまた、自他の利害の対立、少くも不一致を社会の出発点とし、そうした特殊利害の間の抗争・妥協・調整のプロセスを通じて、自発的に、いわば下から共同利害が形成されてゆくのも秩序形成の一つのあり方であるという考え方も、はじめから視野の外にあったのである。〉
ここには儒教思想を批判し、民主主義を打ち立てようとする丸山の視座がはっきりと表明されている。
修身斉家治国平天下という道徳主義的な統治思想にたいしても、丸山ははっきりと批判している。
〈修身斉家治国平天下というような道徳と政治を直接的に連続させ、また、統治作用を治者による被治者の人倫への教化と見ることは、政治的認識としてあまりに素朴であるだけでなく、一方で政治権力を無限界に精神的領域に侵入させるとともに、他方で儒教の家族内倫理に現われているように、道徳の領域に強制力を伴う統治関係をもちこむ傾向をうむ。こうして、もっとも悪い場合には、権力的強制を道徳的に粉飾し、逆に道徳から内面性をうばって、これを共同体もしくは集団への順応に堕さしめることになる。〉
そして、問題は、このような秩序観や政治観が、下意識の次元で、いまも残っていることなのである、と丸山は述べている。
江戸という岩盤──『丸山眞男講義録[第七冊]』を読む(4) [われらの時代]
ここから講義は後半にはいり、江戸時代の儒教と国学が論じられることになる。ただし、国学についてはごく簡単にしかふれられない。
まずは導入部として17世紀前後の状況が論じられる。
室町から戦国にかけては混沌の時代だった。ところが1637年の島原の乱の平定、1639年の鎖国令ののち、突如として静謐が訪れる。
すでに荘園制は解体され、郷村を掌握する分国大名領地制が完成していた。戦国大名が終わり、近世大名が生まれようとしていた。
戦国の終わり16世紀半ばに、ポルトガル人とスペイン人が渡来し、南蛮貿易が開始されると、キリシタンが急激に増加した。
日本にとって、幕末の開国が第二の開国だとすれば、16世紀半ばは第一の開国である。
第一の開国は、西欧と日本がはじめて直接に接触するという意味では世界史的な出来事だった。しかし、その時期はヨーロッパはまだ近代開幕期であって、まだアジア世界が優位を保っている。西洋世界が優位に躍り出るのは、それ以降の300年においてである。
16世紀におけるヨーロッパ人のアジア進出には、アジアへの憧れがあふれていた。イエズス会の宣教師たちは、日本人と日本文化の優秀性に強い印象をもつことになる。
いっぽう西欧文明とのはじめての接触は、日本人の世界像に大きな変革をもたらした。これまでは朝鮮、中国、天竺がせいぜいだったのに、南蛮という大きな世界が広がったのである。南蛮からは、鉄砲や火薬に加え、さまざまな道具、テクノロジー、学術、キリスト教がもたらされた。17世紀はじめ、日本人の活動も東南アジアにまで広がっていった。
南蛮文化の流入は、軍事技術に大きな変化をもたらした。だが、戦国の世が終わると、日本は内に閉じこもる伝統的な方向に舵を切っていく。
1549年のザビエル来日以来、イエズス会による布教により、キリスト教が広まる。1579年に全国のキリシタンは13万人を数えていた。1586年、豊臣秀吉は最初の布教禁止令を出し、96年には長崎で26人の殉教者を処刑した。
秀吉の弾圧にもかかわらず、キリシタンの数は増加しつづけ、1600年ごろには30万人以上になっていた。その数は、最盛時は50万人から70万人に達した。
短い布教期間であったにもかかわらず、キリスト教は日本思想史上に、いくつかの重要な観念をもたらした。丸山によれば、それは個人の尊厳の観念、そして人間にとって自由のもつ意味だった。この世の権力や富よりも、個人の魂の救済こそがだいじだという教えは鮮烈な印象を残した。
だが、全国統一をめざす政治指導者は、こうした教えに猜疑と警戒をいだき、やがてキリシタン弾圧に踏み切ることになる。
弾圧は一向一揆にも向けられたが、キリスト教とちがい、一向宗(浄土真宗)自体は禁止されなかった。禁止されたのは、かれらによる集団的武装抵抗である。仏教寺院は権力に屈し、その後、庶民を統制する機関として、権力によって利用されていくことになる。
1637年には、島原・天草の乱が発生する。領主、松倉重政の暴政にたいして、キリシタンの農民が反乱に立ちあがる。そして、ついに松平信綱の率いる幕府軍が出動することになった。幕府軍は12万、これにたいし2万5000の農民が原の古城にたてこもって、2カ月にわたって城を守り抜いた。
幕府はその後、全面的な鎖国令、さらには宗門人別改め寺請制などによるキリシタン統制に踏み切ることになる。幕府は、現世的な政治権力をおびやかす信仰集団の存在を恐れていた。
いっぽう、一向一揆のほうはどうだったろう。
信仰共同体にもとづく一向一揆には、郷村を巻き込んで横に広がっていくダイナミズムがあった。一向一揆は郷村を中心に、地侍や国人を吸収して、荘園領主や守護大名に対抗する勢力に広がっていった。
本願寺は戦国期にはそれ自体巨大な領主権力となっていた。本寺・末寺のヒエラルキーを中核として、事実上の城郭構造をもつ大寺院も生まれていた。だが、こうした仏教勢力も、最終的には統一政権に屈し、行政機構にくみこまれ、檀家制と寺請制に安住することになる。
こうして、宗教、芸術、学問などの普遍主義的価値に依存する文化集団の自立性が奪われ、ギルドや自治都市の独立性も奪われていく。閉じられた幕藩体制の誕生により、現世的な秩序価値が優位となる時代が到来した、と丸山は指摘する。
幕藩体制の統治原理は、どのようなものだったのだろうか。
丸山によれば、幕藩体制は徳川家康が将軍となる1603年に即座に成立したのではなく、17世紀いっぱいを要して、5代将軍綱吉のときにようやく完成されたのだという。
徳川幕府の歴史的意義は、徳川氏が荘園体制を完全に破壊し、大名領国制を凍結することによって、全国統治をなしとげたことだという。全国における徳川氏の所領はほかの大名より圧倒的に多かった。だが、それだけではない。徳川氏には国内の分裂を防ぐにたる政治的リアリズムとイデオロギー的統制という政治技術があった。
江戸時代に反乱らしい反乱はほとんどなかった。これは当時、ヨーロッパが宗教改革とフランス革命の時代だったことを考えてみても、世界史上めずらしいことだ、と丸山はいう。
徳川幕府は成立早々から、幕府にたいする現実的・潜在的敵対勢力を排除することをめざした。
皇室・公家にたいしては、徹底的な非政治化をはかり、寺社を行政組織の末端に組み入れ、城下町に武士を集住させ、商人を町人として都市に閉じこめた。大名にはいつでも改易、所替、移封を命じることのできる権力を保持していた。
とはいえ、現実におこなったことは、戦国大名領国の凍結である。大名は所領をあてがわれた代わりに将軍に忠誠を誓う。幕府の監視下であるにせよ、領国を支配する大名は、それぞれ徴税権、立法権、武装権をもっていた。大名は幕府への納税義務はなかった。だが、幕府からさまざまな公共事業や寺社の増築などを請け負わされていた。
幕府の支配地(天領)は、約700万石であり、全国石高の4分の1を占めていた。これに加えて、幕府は全国主要鉱山といくつかの都市(京都、大坂、長崎)を直轄し、貨幣鋳造権をもっていた。
全国の支配構造は、幕府を中心として、旗本、親藩・譜代大名、外様大名の区分けの上に成り立っている。各大名は参勤交代による出府をしいられていたものの、いちおうは徳川氏から自立した領国を認められている。天領でも領国内でも、在地領主はほとんどいない。城下町に集住する武士は、俸禄によって地位を定められ、帰属する家への奉仕を求められていた。
幕藩体制は戦国状態を凍結化し、非常時臨戦態勢を継続したもので、いわば日常化された総動員体制だったという丸山の解釈はおもしろい。社会全体に相互監視と密偵組織の目が行き届いていた。
とはいえ、天下泰平が長引くにつれ、臨戦態勢の実感は薄れ、消極的保身の態度が蔓延していく。「自発的公共心と連帯性の欠如、いわば受動的なマイ・ホーム精神」が江戸後期の特徴となる、と丸山はいう。
江戸時代で評価すべきは、「文治主義」と「教学振興」である。徳川家康は林羅山を迎え、新興の朱子学をよく講義させた。武家諸法度でも、儒教主義的な統治方針が打ちだされ、諸藩も文教振興に力を入れるようになった。
とはいえ、日本では儒教はけっして正統的なイデオロギーとはならなかった。そのことは家康が僧の天海や崇伝を尊重したことでもあらわれている。仏教も支配の道具として欠かせなかったのだ。
日本で宋学(朱子学)がはやるようになるのは16世紀からである。幕藩体制下では、この近世儒教が統治思想となり、文治政策として展開されていくことになる。
武断体制と、儒教の文治政策のあいだにはしばしば矛盾が生じた。江戸時代には、無礼をはたらいた庶民にたいする切捨御免、さらには仇討ちや決闘も公認されていた。江戸初期には殉死も認められていた。だが、こうした武断体制のなかでも、儒教は次第に浸透していった。
江戸時代の統治原理について、さらに丸山は次のように指摘する。
ひとつは農民、町人、庶民からの武士の隔離である。根本には兵農分離の方針がある。武士と庶民との通婚は禁止され、住居、衣服、言語、作法、帯刀にいたるまで、武士と庶民の生活様式は区別されていた。
武士には存在理由としての名誉と義が与えられる。その存在理由の付与に儒教は大きな役割を果たした。
農民は収奪の対象でしかなかったが、領主は農民を軍事的に支配するだけではなく、温情主義的に臨んだ。勧農が要請され、農民は慈恵の対象となった。
武士階級は、ヒエラルキー的に編成され、すべての行動面で、ことこまかに格式や作法、礼が定型化されている。秩序と安定がこの時代の基本思想だった。
被支配層でもまた階層と身分が適用されていた。
村でも名主・庄屋には苗字帯刀が許され、衣装も一般農民と区別されていた。百姓にも本百姓から水呑百姓にいたる階層と身分があり、商家でも主人、番頭、手代、丁稚の階層と身分があった。それは花柳界でも同じである。
義理、家、名などの倫理は、武士だけでなく、商家をはじめ庶民にも適用された。
上をみれば無数の階層があるが、下にも無限の階層がある。そこで知足安分、すなわち身のほどを知るという精神が生まれる。
丸山はこう記している。
〈いまや神にせよ仏にせよ、超越的な絶対者は否定され、一切の価値は「世間」に内在化している以上、天道とか天理とかいった普遍理念も、君臣・父子・夫婦といった特殊的な身分関係によって構成された具体的秩序を離れてはありえない。そうして、この具体的秩序は「凍結化」の根本要請にしたがって、無限に単純再生産されねばならない。知足安分と天下泰平とは、こうして内面的に連結したのである。これこそ日本史上「保守主義」とよぶにもっともふさわしい体制であった。〉
「集中排除」の精神についても言及している。
集中排除とは喧嘩口論や徒党の禁止を意味する。それだけではない。
「権力・富・尊敬・名誉等が特定の人格・身分・職業に集中することが極力排除される」と丸山はいう。
例えば公家は身分は高いが、俸禄はきわめて低いというように。あるいは大目付は諸侯に命令する権利をもっているが、武家としての家格は低かったとか。大商人は大金持ちだが、その身分はいやしいとみなされていたとか。
こうした集中排除の考え方が江戸時代の安定化に寄与していた、と丸山はいう。
さらに、江戸時代には、祖法墨守、新儀停止の伝統主義もある。しきたりにしたがって行動することが何よりも求められていた。
要するに固定化による安定が、江戸の天下泰平をもたらしていた。
日本の民主主義はこうした保守の岩盤から出発しなければならなかったのである。
まずは導入部として17世紀前後の状況が論じられる。
室町から戦国にかけては混沌の時代だった。ところが1637年の島原の乱の平定、1639年の鎖国令ののち、突如として静謐が訪れる。
すでに荘園制は解体され、郷村を掌握する分国大名領地制が完成していた。戦国大名が終わり、近世大名が生まれようとしていた。
戦国の終わり16世紀半ばに、ポルトガル人とスペイン人が渡来し、南蛮貿易が開始されると、キリシタンが急激に増加した。
日本にとって、幕末の開国が第二の開国だとすれば、16世紀半ばは第一の開国である。
第一の開国は、西欧と日本がはじめて直接に接触するという意味では世界史的な出来事だった。しかし、その時期はヨーロッパはまだ近代開幕期であって、まだアジア世界が優位を保っている。西洋世界が優位に躍り出るのは、それ以降の300年においてである。
16世紀におけるヨーロッパ人のアジア進出には、アジアへの憧れがあふれていた。イエズス会の宣教師たちは、日本人と日本文化の優秀性に強い印象をもつことになる。
いっぽう西欧文明とのはじめての接触は、日本人の世界像に大きな変革をもたらした。これまでは朝鮮、中国、天竺がせいぜいだったのに、南蛮という大きな世界が広がったのである。南蛮からは、鉄砲や火薬に加え、さまざまな道具、テクノロジー、学術、キリスト教がもたらされた。17世紀はじめ、日本人の活動も東南アジアにまで広がっていった。
南蛮文化の流入は、軍事技術に大きな変化をもたらした。だが、戦国の世が終わると、日本は内に閉じこもる伝統的な方向に舵を切っていく。
1549年のザビエル来日以来、イエズス会による布教により、キリスト教が広まる。1579年に全国のキリシタンは13万人を数えていた。1586年、豊臣秀吉は最初の布教禁止令を出し、96年には長崎で26人の殉教者を処刑した。
秀吉の弾圧にもかかわらず、キリシタンの数は増加しつづけ、1600年ごろには30万人以上になっていた。その数は、最盛時は50万人から70万人に達した。
短い布教期間であったにもかかわらず、キリスト教は日本思想史上に、いくつかの重要な観念をもたらした。丸山によれば、それは個人の尊厳の観念、そして人間にとって自由のもつ意味だった。この世の権力や富よりも、個人の魂の救済こそがだいじだという教えは鮮烈な印象を残した。
だが、全国統一をめざす政治指導者は、こうした教えに猜疑と警戒をいだき、やがてキリシタン弾圧に踏み切ることになる。
弾圧は一向一揆にも向けられたが、キリスト教とちがい、一向宗(浄土真宗)自体は禁止されなかった。禁止されたのは、かれらによる集団的武装抵抗である。仏教寺院は権力に屈し、その後、庶民を統制する機関として、権力によって利用されていくことになる。
1637年には、島原・天草の乱が発生する。領主、松倉重政の暴政にたいして、キリシタンの農民が反乱に立ちあがる。そして、ついに松平信綱の率いる幕府軍が出動することになった。幕府軍は12万、これにたいし2万5000の農民が原の古城にたてこもって、2カ月にわたって城を守り抜いた。
幕府はその後、全面的な鎖国令、さらには宗門人別改め寺請制などによるキリシタン統制に踏み切ることになる。幕府は、現世的な政治権力をおびやかす信仰集団の存在を恐れていた。
いっぽう、一向一揆のほうはどうだったろう。
信仰共同体にもとづく一向一揆には、郷村を巻き込んで横に広がっていくダイナミズムがあった。一向一揆は郷村を中心に、地侍や国人を吸収して、荘園領主や守護大名に対抗する勢力に広がっていった。
本願寺は戦国期にはそれ自体巨大な領主権力となっていた。本寺・末寺のヒエラルキーを中核として、事実上の城郭構造をもつ大寺院も生まれていた。だが、こうした仏教勢力も、最終的には統一政権に屈し、行政機構にくみこまれ、檀家制と寺請制に安住することになる。
こうして、宗教、芸術、学問などの普遍主義的価値に依存する文化集団の自立性が奪われ、ギルドや自治都市の独立性も奪われていく。閉じられた幕藩体制の誕生により、現世的な秩序価値が優位となる時代が到来した、と丸山は指摘する。
幕藩体制の統治原理は、どのようなものだったのだろうか。
丸山によれば、幕藩体制は徳川家康が将軍となる1603年に即座に成立したのではなく、17世紀いっぱいを要して、5代将軍綱吉のときにようやく完成されたのだという。
徳川幕府の歴史的意義は、徳川氏が荘園体制を完全に破壊し、大名領国制を凍結することによって、全国統治をなしとげたことだという。全国における徳川氏の所領はほかの大名より圧倒的に多かった。だが、それだけではない。徳川氏には国内の分裂を防ぐにたる政治的リアリズムとイデオロギー的統制という政治技術があった。
江戸時代に反乱らしい反乱はほとんどなかった。これは当時、ヨーロッパが宗教改革とフランス革命の時代だったことを考えてみても、世界史上めずらしいことだ、と丸山はいう。
徳川幕府は成立早々から、幕府にたいする現実的・潜在的敵対勢力を排除することをめざした。
皇室・公家にたいしては、徹底的な非政治化をはかり、寺社を行政組織の末端に組み入れ、城下町に武士を集住させ、商人を町人として都市に閉じこめた。大名にはいつでも改易、所替、移封を命じることのできる権力を保持していた。
とはいえ、現実におこなったことは、戦国大名領国の凍結である。大名は所領をあてがわれた代わりに将軍に忠誠を誓う。幕府の監視下であるにせよ、領国を支配する大名は、それぞれ徴税権、立法権、武装権をもっていた。大名は幕府への納税義務はなかった。だが、幕府からさまざまな公共事業や寺社の増築などを請け負わされていた。
幕府の支配地(天領)は、約700万石であり、全国石高の4分の1を占めていた。これに加えて、幕府は全国主要鉱山といくつかの都市(京都、大坂、長崎)を直轄し、貨幣鋳造権をもっていた。
全国の支配構造は、幕府を中心として、旗本、親藩・譜代大名、外様大名の区分けの上に成り立っている。各大名は参勤交代による出府をしいられていたものの、いちおうは徳川氏から自立した領国を認められている。天領でも領国内でも、在地領主はほとんどいない。城下町に集住する武士は、俸禄によって地位を定められ、帰属する家への奉仕を求められていた。
幕藩体制は戦国状態を凍結化し、非常時臨戦態勢を継続したもので、いわば日常化された総動員体制だったという丸山の解釈はおもしろい。社会全体に相互監視と密偵組織の目が行き届いていた。
とはいえ、天下泰平が長引くにつれ、臨戦態勢の実感は薄れ、消極的保身の態度が蔓延していく。「自発的公共心と連帯性の欠如、いわば受動的なマイ・ホーム精神」が江戸後期の特徴となる、と丸山はいう。
江戸時代で評価すべきは、「文治主義」と「教学振興」である。徳川家康は林羅山を迎え、新興の朱子学をよく講義させた。武家諸法度でも、儒教主義的な統治方針が打ちだされ、諸藩も文教振興に力を入れるようになった。
とはいえ、日本では儒教はけっして正統的なイデオロギーとはならなかった。そのことは家康が僧の天海や崇伝を尊重したことでもあらわれている。仏教も支配の道具として欠かせなかったのだ。
日本で宋学(朱子学)がはやるようになるのは16世紀からである。幕藩体制下では、この近世儒教が統治思想となり、文治政策として展開されていくことになる。
武断体制と、儒教の文治政策のあいだにはしばしば矛盾が生じた。江戸時代には、無礼をはたらいた庶民にたいする切捨御免、さらには仇討ちや決闘も公認されていた。江戸初期には殉死も認められていた。だが、こうした武断体制のなかでも、儒教は次第に浸透していった。
江戸時代の統治原理について、さらに丸山は次のように指摘する。
ひとつは農民、町人、庶民からの武士の隔離である。根本には兵農分離の方針がある。武士と庶民との通婚は禁止され、住居、衣服、言語、作法、帯刀にいたるまで、武士と庶民の生活様式は区別されていた。
武士には存在理由としての名誉と義が与えられる。その存在理由の付与に儒教は大きな役割を果たした。
農民は収奪の対象でしかなかったが、領主は農民を軍事的に支配するだけではなく、温情主義的に臨んだ。勧農が要請され、農民は慈恵の対象となった。
武士階級は、ヒエラルキー的に編成され、すべての行動面で、ことこまかに格式や作法、礼が定型化されている。秩序と安定がこの時代の基本思想だった。
被支配層でもまた階層と身分が適用されていた。
村でも名主・庄屋には苗字帯刀が許され、衣装も一般農民と区別されていた。百姓にも本百姓から水呑百姓にいたる階層と身分があり、商家でも主人、番頭、手代、丁稚の階層と身分があった。それは花柳界でも同じである。
義理、家、名などの倫理は、武士だけでなく、商家をはじめ庶民にも適用された。
上をみれば無数の階層があるが、下にも無限の階層がある。そこで知足安分、すなわち身のほどを知るという精神が生まれる。
丸山はこう記している。
〈いまや神にせよ仏にせよ、超越的な絶対者は否定され、一切の価値は「世間」に内在化している以上、天道とか天理とかいった普遍理念も、君臣・父子・夫婦といった特殊的な身分関係によって構成された具体的秩序を離れてはありえない。そうして、この具体的秩序は「凍結化」の根本要請にしたがって、無限に単純再生産されねばならない。知足安分と天下泰平とは、こうして内面的に連結したのである。これこそ日本史上「保守主義」とよぶにもっともふさわしい体制であった。〉
「集中排除」の精神についても言及している。
集中排除とは喧嘩口論や徒党の禁止を意味する。それだけではない。
「権力・富・尊敬・名誉等が特定の人格・身分・職業に集中することが極力排除される」と丸山はいう。
例えば公家は身分は高いが、俸禄はきわめて低いというように。あるいは大目付は諸侯に命令する権利をもっているが、武家としての家格は低かったとか。大商人は大金持ちだが、その身分はいやしいとみなされていたとか。
こうした集中排除の考え方が江戸時代の安定化に寄与していた、と丸山はいう。
さらに、江戸時代には、祖法墨守、新儀停止の伝統主義もある。しきたりにしたがって行動することが何よりも求められていた。
要するに固定化による安定が、江戸の天下泰平をもたらしていた。
日本の民主主義はこうした保守の岩盤から出発しなければならなかったのである。
政治的観念の「原型」──『丸山眞男講義録[第七冊]』を読む(3) [われらの時代]
紀記は全般的に高度の政治的神話性を帯びている、と丸山はいう。その性格は、皇室統治の正当化というイデオロギー性が強い。だが、そこには儒教以前の発想がひそんでいることも見逃してはならないという。
まず「まつりごと」ということば。まつりごととは、政事=祭事というのが、一般的なとらえ方である。
だが、崇神天皇や垂仁天皇のとき、すでに祭儀と政事は区別されようとしていた。政事と祭事には、ともに奉るという概念がともなう。すなわち奉仕と服従である。しかし、政事=祭事と解するのは危険だ、と丸山は指摘する。
政治とは、まつろはぬものをまつろはしめること、すなわち帰順せぬ者を帰順させることだった。
古事記によれば、アマテラスは天孫のニニギノミコトに、三種の神器(玉・鏡・剣)を渡し、さらに三神(常世思金〈とこよのおもひかね〉、手力男〈たぢからのお〉、天岩戸別〈あまのいわとわけ〉)を配して、こうのたまう。この鏡をわが魂として祭れ。そして常世思金神にしたがって、天の下の政(まつりごと)をするように、と。
よけいな口をはさむと、この三神はまるで、カネと力(戦い)、そして守り(防衛)を象徴しているかのようである。
それはともかく、ここでも祭儀と政事は関連しつつも分離されている。まず祭祀がおこなわれ、その後に政治がなされるのだ、と丸山はいう。
ヤマトタケルの場合は、景行天皇の命を受けて東征するが、まつりごとをなすのは、天皇から職務遂行を委託されたヤマトタケルなのだ。
「この意味で、まさに『政』は第一義的に、上なる政治的権威にたいする政事という職務の奉仕」にほかならない、と丸山は論じる。
ほかに統治にかかわることばとしては、まず「しらす」(「しろしめす」)がある。
イザナギは子のアマテラス、月読(つくよみ、つきよみ)、スサノオに、それぞれ高天原、夜の食国(おすくに)、海原を「しろしめせ」と指示している。のちにアマテラスは孫のニニギノミコトに、この豊葦原の瑞穂の国は、汝のしらす国だと述べ、降臨を命じることになる。
しらすには、単なる領有ではなく、正統な統治という意味が含まれている、と丸山はいう。
統治がらみでは、もうひとつ「きこしめす」(聞く)ということばもある。すなわち臣下の奏上を聞くことが統治である。
さらに「ことむける」、すなわち、こちらに向けるとは、帰順させる、平定するの意味。軍事的な平定、ことむけが終わったあとは、皇孫がしろしめすことになっている。
「まつりごと」は、「ことむける」と「きこしめす」の往来関係のうえに成り立っている。すなわち命令を実施することと、その結果を報告することによって「しろしめす」、すなわち統治が実現する。
この関係について、丸山はこう述べている。
〈しらす、きこしめすはsovereign〔元首〕のreign〔君臨〕の問題であり、まつりごとはgovernment〔政府〕の問題であるといえる。まつりごとは行政幹部のなかで議(はか)られ、君主は「まつりごと」を「きこしめす」地位にあって「あめのした」を「しろしめす」ということになる。〉
この図式が、日本の統治形態の伝統的パターンなのだ。このパターンは、天皇の統治(天皇、貴族)でも、幕府(将軍、老中)でも、各藩レベル(殿様、家老)でも、常に再生産されてきた、と丸山はいう。
こうしたいわば「二重統治」は、卑弥呼と男弟との関係、推古天皇と聖徳太子との関係でも示されている。大化改新以来、日本は中国の制度を取り入れて、天皇親政のタテマエをとるようになるが、それでももともとの統治の「原型」は存続した、と丸山は考えている。
日本では大王(おおきみ)が天皇と呼ばれるようになったのは7世紀初頭の推古朝以降である。さらに奈良朝になると、天皇は万葉歌人によって現人神(あらひとがみ)とうたわれるようになった。
日本の律令制では、太政官という独特の制度が設けられた。これはかたちとしての天皇親政を実現するための最高合議体だった。
しかし、日本では統治機構が整備され、その統制力が強化されるほど、天皇は神聖化され、逆に実質的な政治的決定権から隔離されていく。
こうして、政治体制は次第に藤原氏の摂関時代へと移行していく。「天皇は臣の翼を得て君臨し、臣は……合議で事を決し統治することが天皇への奉仕になる」という関係が生まれる。
天皇は群臣から奉仕される存在となる。それでは天皇自身が奉仕する(まつる)対象はないのか、と丸山は問う。天皇がまつるのは神々である。ここにおいて祭事と政事が関係づけられることになる。
天皇が宮中で行う祭事でもっとも重要なのが祝詞(のりと)。天皇は祭主となって、神と人とを媒介する。
まつられる神は天つ神、国つ神、それに皇室の祖霊である。だが、究極の神が何であるかはあいまいなままだ。
「こうしてまつる主体は特定しているが、まつられる客体は不特定であり、かつ無限に遡及してしまう」と、丸山はいう。
とはいえ、天皇が個人として祭祀と礼拝の対象になったことはない。天皇はけっして宗教的絶対者ではなく、みずからはあくまでも祭祀の統率者にとどまる。
丸山によれば、日本の祭祀の根幹は「共同体の首長が、共同体のために、穀物の豊饒と共同体成員の増殖と繁栄を祝福し、それに関係するさまざまな儀礼」だった。
ヤマト国家を拡大する過程で、大君(おおきみ)が天皇となるのは、そこの中国の「天」の思想が摂取されたからだ、と丸山は解している。
〈元来日本の「原型」では、太陽神は農耕神でこそあれ宇宙の中心ではなく、太陽神優越の観念はなかった。むしろ穀霊信仰という形で、他の氏族との同一面が存在した。しかし皇祖神がアマテラスに特定化されるのに見あって、その農耕神たる太陽神の観念を媒介として、宇宙(天)の中心たる太陽という形而上学的思考が輸入され、それと同時に、前述の太陽神が天皇に連続するという図式を基盤に、天皇を地上の中心者(地無二皇)たらしめる観念的前提となった。〉
こうして天皇は政事の次元を超えた共同体最高の祭祀者となって、政治体制のいかんにかかわらず、存続継承されていくことになる。
これが丸山のえがいた日本の政治の原型、ないし古層といってよい。
まず「まつりごと」ということば。まつりごととは、政事=祭事というのが、一般的なとらえ方である。
だが、崇神天皇や垂仁天皇のとき、すでに祭儀と政事は区別されようとしていた。政事と祭事には、ともに奉るという概念がともなう。すなわち奉仕と服従である。しかし、政事=祭事と解するのは危険だ、と丸山は指摘する。
政治とは、まつろはぬものをまつろはしめること、すなわち帰順せぬ者を帰順させることだった。
古事記によれば、アマテラスは天孫のニニギノミコトに、三種の神器(玉・鏡・剣)を渡し、さらに三神(常世思金〈とこよのおもひかね〉、手力男〈たぢからのお〉、天岩戸別〈あまのいわとわけ〉)を配して、こうのたまう。この鏡をわが魂として祭れ。そして常世思金神にしたがって、天の下の政(まつりごと)をするように、と。
よけいな口をはさむと、この三神はまるで、カネと力(戦い)、そして守り(防衛)を象徴しているかのようである。
それはともかく、ここでも祭儀と政事は関連しつつも分離されている。まず祭祀がおこなわれ、その後に政治がなされるのだ、と丸山はいう。
ヤマトタケルの場合は、景行天皇の命を受けて東征するが、まつりごとをなすのは、天皇から職務遂行を委託されたヤマトタケルなのだ。
「この意味で、まさに『政』は第一義的に、上なる政治的権威にたいする政事という職務の奉仕」にほかならない、と丸山は論じる。
ほかに統治にかかわることばとしては、まず「しらす」(「しろしめす」)がある。
イザナギは子のアマテラス、月読(つくよみ、つきよみ)、スサノオに、それぞれ高天原、夜の食国(おすくに)、海原を「しろしめせ」と指示している。のちにアマテラスは孫のニニギノミコトに、この豊葦原の瑞穂の国は、汝のしらす国だと述べ、降臨を命じることになる。
しらすには、単なる領有ではなく、正統な統治という意味が含まれている、と丸山はいう。
統治がらみでは、もうひとつ「きこしめす」(聞く)ということばもある。すなわち臣下の奏上を聞くことが統治である。
さらに「ことむける」、すなわち、こちらに向けるとは、帰順させる、平定するの意味。軍事的な平定、ことむけが終わったあとは、皇孫がしろしめすことになっている。
「まつりごと」は、「ことむける」と「きこしめす」の往来関係のうえに成り立っている。すなわち命令を実施することと、その結果を報告することによって「しろしめす」、すなわち統治が実現する。
この関係について、丸山はこう述べている。
〈しらす、きこしめすはsovereign〔元首〕のreign〔君臨〕の問題であり、まつりごとはgovernment〔政府〕の問題であるといえる。まつりごとは行政幹部のなかで議(はか)られ、君主は「まつりごと」を「きこしめす」地位にあって「あめのした」を「しろしめす」ということになる。〉
この図式が、日本の統治形態の伝統的パターンなのだ。このパターンは、天皇の統治(天皇、貴族)でも、幕府(将軍、老中)でも、各藩レベル(殿様、家老)でも、常に再生産されてきた、と丸山はいう。
こうしたいわば「二重統治」は、卑弥呼と男弟との関係、推古天皇と聖徳太子との関係でも示されている。大化改新以来、日本は中国の制度を取り入れて、天皇親政のタテマエをとるようになるが、それでももともとの統治の「原型」は存続した、と丸山は考えている。
日本では大王(おおきみ)が天皇と呼ばれるようになったのは7世紀初頭の推古朝以降である。さらに奈良朝になると、天皇は万葉歌人によって現人神(あらひとがみ)とうたわれるようになった。
日本の律令制では、太政官という独特の制度が設けられた。これはかたちとしての天皇親政を実現するための最高合議体だった。
しかし、日本では統治機構が整備され、その統制力が強化されるほど、天皇は神聖化され、逆に実質的な政治的決定権から隔離されていく。
こうして、政治体制は次第に藤原氏の摂関時代へと移行していく。「天皇は臣の翼を得て君臨し、臣は……合議で事を決し統治することが天皇への奉仕になる」という関係が生まれる。
天皇は群臣から奉仕される存在となる。それでは天皇自身が奉仕する(まつる)対象はないのか、と丸山は問う。天皇がまつるのは神々である。ここにおいて祭事と政事が関係づけられることになる。
天皇が宮中で行う祭事でもっとも重要なのが祝詞(のりと)。天皇は祭主となって、神と人とを媒介する。
まつられる神は天つ神、国つ神、それに皇室の祖霊である。だが、究極の神が何であるかはあいまいなままだ。
「こうしてまつる主体は特定しているが、まつられる客体は不特定であり、かつ無限に遡及してしまう」と、丸山はいう。
とはいえ、天皇が個人として祭祀と礼拝の対象になったことはない。天皇はけっして宗教的絶対者ではなく、みずからはあくまでも祭祀の統率者にとどまる。
丸山によれば、日本の祭祀の根幹は「共同体の首長が、共同体のために、穀物の豊饒と共同体成員の増殖と繁栄を祝福し、それに関係するさまざまな儀礼」だった。
ヤマト国家を拡大する過程で、大君(おおきみ)が天皇となるのは、そこの中国の「天」の思想が摂取されたからだ、と丸山は解している。
〈元来日本の「原型」では、太陽神は農耕神でこそあれ宇宙の中心ではなく、太陽神優越の観念はなかった。むしろ穀霊信仰という形で、他の氏族との同一面が存在した。しかし皇祖神がアマテラスに特定化されるのに見あって、その農耕神たる太陽神の観念を媒介として、宇宙(天)の中心たる太陽という形而上学的思考が輸入され、それと同時に、前述の太陽神が天皇に連続するという図式を基盤に、天皇を地上の中心者(地無二皇)たらしめる観念的前提となった。〉
こうして天皇は政事の次元を超えた共同体最高の祭祀者となって、政治体制のいかんにかかわらず、存続継承されていくことになる。
これが丸山のえがいた日本の政治の原型、ないし古層といってよい。
倫理・歴史意識の「原型」──『丸山眞男講義録[第七冊]』を読む(2) [われらの時代]
丸山はこんなふうに話している。
〈日本の思想史は、外来思想の受容と修正の歴史である。ただし「受容」はすぐれて主体的な選択であるから、これを摂取という。つぎつぎに摂取された外来文化は日本の精神構造の内部に層をなし、より新しい層と古い層の間に不断の相互作用が行われる。最下層に沈殿しているものを「原型」とよぶ。〉
その「原型」がどのようなものかを探るのはむずかしい。しかし、大陸由来の儒教や仏教などの語法や観念を除去し、神道や民間伝承などの観念と照らし合わせていくと、そこに固有の思考様式や価値意識を認めることができる。それを再構成して仮設として立てたものが「原型」なのだ、と丸山はいう。
丸山が注目するのは日本の神話である。「神話こそ、環境に意味連関を与える人類文化史上最初の意識的な試みであり、ここにおいて、ある文化圏の根元的な概念のフレームワーク(枠組)を見ることができる」という。その点は、宗教も同じであって、人間は「『宗教』のない世界で生きてゆくことはできない」。神話や宗教があってこそ、人は厳しい環境に対応することができる。
そこで、まず論じられるのが、倫理意識の「原型」についてである。
日本では、タマやカミは、畏るべきものであり、尋常を超えた能力をもつものである。それらは鎮め、遠ざけられねばならない。禍いは神の怒りであり、その怒りは人間が神の掟に背いたために生じ、そうしたたたりや罪は、ハラヒ、キヨメられなければならない。
こうして次第に神々への祭儀が定型化していく。日本では、歴史に記録された最古の時代(紀元3世紀ごろ)に、呪術から祭儀への発展がみられる。聖と俗(ハレとケ)の分化も意識されていた。ハレのさいには、ミソギによって、ケガレ(=罪)を除去しなければならなかった。
日本の祭祀では、呪術的性格が濃厚に残っていた。呪術の世界には、かまどの神とか厠の神といった特定の精霊がかかわっており、それに応じて、祭儀が多様化する。場に応じた行動様式の使い分けは、日本人の特徴でもある。
記紀神話は、高天原系と筑紫系、出雲系の3つの系統からなるが、結局はヤマトの国の成立と統治者の由来を語る物語へと収斂していく。そこには、さまざまな矛盾や撞着がみられる。とはいえ、重視されるのは、特定共同体への服従と献身をあらわすキヨキ心である。
イザナギ神話をみれば、ミソギからはまがごとを起こす悪神と、禍いを直す善神が生まれている。しかし、ふたつの神がミソギから生まれていることをみてもわかるように、善神と悪神は相関的な存在である。善神もたまには悪行をするし、悪神も悪行しかしないわけではない。その意味で、プラグマティックな適応性に富んでいる、と丸山はいう。
古代人にとって、死はケガレと結びついており、人はそこから遠ざかろうとした。日本で仏教が受容されたのは、葬儀を通じてである。それまでも葬儀に相当するものがなかったわけではない。死者がよみがえる、言い換えれば死霊が戻ってこないようにするために、境界を防ぐという発想があった。黄泉の国という水平的空間性にたいし、仏教は地獄、極楽という別世界の概念を導入した。よみがえりの代わりに、死後の救済という観念が移入された。
生成と生殖を賛美する自然的生のオプティズム、死にたいする生の優越が記紀神話をおおっている。悪とは生成と生殖を阻害するものであり、それをなおし、生成力を復元させるのが、直毘霊(なおびのみたま)ということになる。
ナルとウムはともに「生」である。生成作用は神格化される。まず「あしかび」のようなものが神となる。すなわち国常立尊(くにのとこたちのみこと)。それから七代の神がなり、イザナギ、イザナミにいたる。イザナギがイザナミの黄泉の国から戻って生まれた神が、アマテラス、ツクヨミ、スサノオとなる。なるとうむは連続している。つくるという主体性は薄弱である。「なりゆき」と「いきほひ」の世界が生まれる。
「なりゆき」と「いきほひ」は歴史意識の「原型」となる。これが次のテーマだ。
日本には、自然的時間の流れについてのオプティミズムがある。ここは自然的時間の経過において万物が生成活動し、増殖する、成りゆく世界である。自然的時間のなかには勢いがそなわっている。そこで、日本人は「歴史は人間がつくるものであり、歴史的現実や状況はわれわれが起すものというよりは、われわれの外にあるどこからか起ってくるものであり、如何ともすべからざる勢の作用であるという考えに傾きやすい」と、丸山はいう。それが時勢、大勢という観念につながってくる。なりゆき史観は、時勢への追随となってあらわれる。
こうしたなりゆき史観は、古代インドやキリスト教、古代中国思想とは異なる。
丸山によれば、日本の歴史意識の原型は次のようにえがかれる。
「歴史は現在を中心とした、過去から未来への無限の流れである」
「時間を超越した『永遠』も『絶対者』もない。永遠はただ時間における無限の持続である」
「現在は過去の生成(なる=ある)の結果であり、顕現である」
過去は現在によって、はじめて位置づけられる。したがって、原始時代がユートピアとみなされることはない。
未来は「現在からの発射であり、噴出である」。したがって、目的ないし終着点としてのユートピアも存在しない。
そうした思考からは、いくつかの帰結が導かれる、と丸山はいう。
日本人の歴史観は現在中心的であり、過去を規範的に絶対化せず、未来の目標もない。「なりゆき」の時勢史観である。ユートピア思想はほとんどみられず、海外にある地上の模範国をモデルとする傾向が強い。
現世主義的、此岸主義的だが、現世はうつろう世としてとらえられる。「不断に推移転変する時間の流れに乗りながら、つねに現在の瞬間を肯定的に生きる」のが日本人だ。しかし、生の意味は必ずしも肯定的にとらえられていないから、いっぽうでは享楽主義、他方では淡泊に死を選ぶ態度がでてくる。
過去─現在─未来は、血縁の系譜や世代の継承によって象徴的に表現される。氏や家の無窮の連続が、永遠のイメージとして尊重される。
日本ではすでに7世紀ごろから、氏神信仰と血縁系譜を尊ぶ観念が生まれていた。そして、皇室を中心に有力豪族を政治的に統制するためのイデオロギーが整備されていく。神代史においては、アマテラスが皇祖神として位置づけられ、そこに登場する神々が皇室に臣従する有力豪族の祖神として配されていく。
中国の祖先崇拝は、子の父にたいする「孝」というかたちをとって規範化されるが、日本では祖霊が子に宿って、「古きものの死から新しきものの生への流れを通じての継続」が歴史意識をかたちづくる。その典型的な儀式が大嘗祭である。この儀式によって、新天皇は象徴的にはアマテラスの直接の子になる、と丸山は指摘する。
日本の神話では究極の絶対神は存在しない。あるのは天つ神への道筋だけであって、そこにおいて神事がなされる。こうして原初の再生が状況への適応を生み出す。変革は天つ神の意を受けて、おこなわれるのである。これが惟神(かむながら)ということになる。すなわち、天にいます神の思し召すままに改革がなされる。これと同じパターンが明治維新にもみられた、と丸山はいう。
天地初発に立ち返ることが、「タマ」の活力(いきおい)になって、混沌からの再出発と、大胆な改革を可能にする、と丸山はみている。
ちょっと頭をかかえるしかない。

〈日本の思想史は、外来思想の受容と修正の歴史である。ただし「受容」はすぐれて主体的な選択であるから、これを摂取という。つぎつぎに摂取された外来文化は日本の精神構造の内部に層をなし、より新しい層と古い層の間に不断の相互作用が行われる。最下層に沈殿しているものを「原型」とよぶ。〉
その「原型」がどのようなものかを探るのはむずかしい。しかし、大陸由来の儒教や仏教などの語法や観念を除去し、神道や民間伝承などの観念と照らし合わせていくと、そこに固有の思考様式や価値意識を認めることができる。それを再構成して仮設として立てたものが「原型」なのだ、と丸山はいう。
丸山が注目するのは日本の神話である。「神話こそ、環境に意味連関を与える人類文化史上最初の意識的な試みであり、ここにおいて、ある文化圏の根元的な概念のフレームワーク(枠組)を見ることができる」という。その点は、宗教も同じであって、人間は「『宗教』のない世界で生きてゆくことはできない」。神話や宗教があってこそ、人は厳しい環境に対応することができる。
そこで、まず論じられるのが、倫理意識の「原型」についてである。
日本では、タマやカミは、畏るべきものであり、尋常を超えた能力をもつものである。それらは鎮め、遠ざけられねばならない。禍いは神の怒りであり、その怒りは人間が神の掟に背いたために生じ、そうしたたたりや罪は、ハラヒ、キヨメられなければならない。
こうして次第に神々への祭儀が定型化していく。日本では、歴史に記録された最古の時代(紀元3世紀ごろ)に、呪術から祭儀への発展がみられる。聖と俗(ハレとケ)の分化も意識されていた。ハレのさいには、ミソギによって、ケガレ(=罪)を除去しなければならなかった。
日本の祭祀では、呪術的性格が濃厚に残っていた。呪術の世界には、かまどの神とか厠の神といった特定の精霊がかかわっており、それに応じて、祭儀が多様化する。場に応じた行動様式の使い分けは、日本人の特徴でもある。
記紀神話は、高天原系と筑紫系、出雲系の3つの系統からなるが、結局はヤマトの国の成立と統治者の由来を語る物語へと収斂していく。そこには、さまざまな矛盾や撞着がみられる。とはいえ、重視されるのは、特定共同体への服従と献身をあらわすキヨキ心である。
イザナギ神話をみれば、ミソギからはまがごとを起こす悪神と、禍いを直す善神が生まれている。しかし、ふたつの神がミソギから生まれていることをみてもわかるように、善神と悪神は相関的な存在である。善神もたまには悪行をするし、悪神も悪行しかしないわけではない。その意味で、プラグマティックな適応性に富んでいる、と丸山はいう。
古代人にとって、死はケガレと結びついており、人はそこから遠ざかろうとした。日本で仏教が受容されたのは、葬儀を通じてである。それまでも葬儀に相当するものがなかったわけではない。死者がよみがえる、言い換えれば死霊が戻ってこないようにするために、境界を防ぐという発想があった。黄泉の国という水平的空間性にたいし、仏教は地獄、極楽という別世界の概念を導入した。よみがえりの代わりに、死後の救済という観念が移入された。
生成と生殖を賛美する自然的生のオプティズム、死にたいする生の優越が記紀神話をおおっている。悪とは生成と生殖を阻害するものであり、それをなおし、生成力を復元させるのが、直毘霊(なおびのみたま)ということになる。
ナルとウムはともに「生」である。生成作用は神格化される。まず「あしかび」のようなものが神となる。すなわち国常立尊(くにのとこたちのみこと)。それから七代の神がなり、イザナギ、イザナミにいたる。イザナギがイザナミの黄泉の国から戻って生まれた神が、アマテラス、ツクヨミ、スサノオとなる。なるとうむは連続している。つくるという主体性は薄弱である。「なりゆき」と「いきほひ」の世界が生まれる。
「なりゆき」と「いきほひ」は歴史意識の「原型」となる。これが次のテーマだ。
日本には、自然的時間の流れについてのオプティミズムがある。ここは自然的時間の経過において万物が生成活動し、増殖する、成りゆく世界である。自然的時間のなかには勢いがそなわっている。そこで、日本人は「歴史は人間がつくるものであり、歴史的現実や状況はわれわれが起すものというよりは、われわれの外にあるどこからか起ってくるものであり、如何ともすべからざる勢の作用であるという考えに傾きやすい」と、丸山はいう。それが時勢、大勢という観念につながってくる。なりゆき史観は、時勢への追随となってあらわれる。
こうしたなりゆき史観は、古代インドやキリスト教、古代中国思想とは異なる。
丸山によれば、日本の歴史意識の原型は次のようにえがかれる。
「歴史は現在を中心とした、過去から未来への無限の流れである」
「時間を超越した『永遠』も『絶対者』もない。永遠はただ時間における無限の持続である」
「現在は過去の生成(なる=ある)の結果であり、顕現である」
過去は現在によって、はじめて位置づけられる。したがって、原始時代がユートピアとみなされることはない。
未来は「現在からの発射であり、噴出である」。したがって、目的ないし終着点としてのユートピアも存在しない。
そうした思考からは、いくつかの帰結が導かれる、と丸山はいう。
日本人の歴史観は現在中心的であり、過去を規範的に絶対化せず、未来の目標もない。「なりゆき」の時勢史観である。ユートピア思想はほとんどみられず、海外にある地上の模範国をモデルとする傾向が強い。
現世主義的、此岸主義的だが、現世はうつろう世としてとらえられる。「不断に推移転変する時間の流れに乗りながら、つねに現在の瞬間を肯定的に生きる」のが日本人だ。しかし、生の意味は必ずしも肯定的にとらえられていないから、いっぽうでは享楽主義、他方では淡泊に死を選ぶ態度がでてくる。
過去─現在─未来は、血縁の系譜や世代の継承によって象徴的に表現される。氏や家の無窮の連続が、永遠のイメージとして尊重される。
日本ではすでに7世紀ごろから、氏神信仰と血縁系譜を尊ぶ観念が生まれていた。そして、皇室を中心に有力豪族を政治的に統制するためのイデオロギーが整備されていく。神代史においては、アマテラスが皇祖神として位置づけられ、そこに登場する神々が皇室に臣従する有力豪族の祖神として配されていく。
中国の祖先崇拝は、子の父にたいする「孝」というかたちをとって規範化されるが、日本では祖霊が子に宿って、「古きものの死から新しきものの生への流れを通じての継続」が歴史意識をかたちづくる。その典型的な儀式が大嘗祭である。この儀式によって、新天皇は象徴的にはアマテラスの直接の子になる、と丸山は指摘する。
日本の神話では究極の絶対神は存在しない。あるのは天つ神への道筋だけであって、そこにおいて神事がなされる。こうして原初の再生が状況への適応を生み出す。変革は天つ神の意を受けて、おこなわれるのである。これが惟神(かむながら)ということになる。すなわち、天にいます神の思し召すままに改革がなされる。これと同じパターンが明治維新にもみられた、と丸山はいう。
天地初発に立ち返ることが、「タマ」の活力(いきおい)になって、混沌からの再出発と、大胆な改革を可能にする、と丸山はみている。
ちょっと頭をかかえるしかない。

東大での最終講義──『丸山眞男講義録[第七冊]』 を読む(1) [われらの時代]

丸山眞男が東京大学で日本政治思想史を講義したのは、1967年度が最後となった。翌年には「東大紛争」があって、講義が中断されてしまうからである。そのあと長期療養を余儀なくされた丸山は、71年に東大を退職してしまう。
その最後の講義がどのようなものだったのか、ちょっと知りたくなった。
この年、ぼくは早稲田大学に入学したばかりで、受験科目の皮相な知識しかなく、専攻した政治学はおろか日本政治思想史とくれば、まるでちんぷんかんぷんだった。いまでも、むずかしい話はよくわからない。あのころはどんな時代だったのかという懐旧の念だけがぼくを引っぱっている。それで、丸山講義録の最終巻を読んでみる気になった。
講義は1967年10月17日から68年2月1日まで、東大本郷キャンパスの法文1号館21番教室で計24回おこなわれた。授業時間は110分、受講学生は約130名だったという。
この年度のテーマは3つだった。日本の政治意識の原型、近世儒教の政治思想、思想運動としての国学。
ハイレベルなテーマなので、はたしてどこまで本書について行けるか、はなはだ心もとないのだが、ともかくも無手勝流で読むことにする。勝手なまとめなので、内容の正確さは保証しない。
「東洋政治思想史講義」と題されて、可能なかぎり毎年おこなわれる講義は、この年、「日本政治思想史講義」と名を改めた。実際、それまでも日本の政治思想を扱っていたからである。それも、ほとんど明治維新以前、とりわけ江戸時代を対象としていた。
なぜ近代以前だったのか。その理由について、丸山は、制度は代わるけれど、ものの考え方はそれほど変わらないこと、忘れられがちな近代以前を知ることで近代以降を対象化しうること、明治以降の政治外交史は法学部のほかの講座でも扱っているので明治以前を取りあげることにした、などと述べている。
1964年度が仏教思想を中心に古代から室町末まで、65年度が武士のエートスの発展、66年度がキリシタンと初期の江戸儒教を論じたのにたいし、67年度は儒教、国学を含めた江戸の政治思想が主に取りあげられることになっていた。
ところが、実際には、67年度は儒教、国学を含めた江戸の政治思想というより、むしろそれ以前に、講義の大半は日本の政治的思考様式の「原型」を論じることに関心が向けられていることがわかる。これはのちに『忠誠と反逆』(1992)に収められる論文「歴史意識の『古層』」(1972)につながる問題意識だったといえるだろう。
それでは、丸山講義を読ませてもらおう。もっとも粗雑なぼくの頭で理解できるのは、あくまでもわかる部分だけだ。
最初にモンテスキューの『法の精神』についての言及があり、モンテスキューが自然的、地理的条件を重視していることが指摘されている。思想の持続的なパターンには「領土の大小とか空間的位置、気候、土壌などが作用している」と丸山はいう。
もちろん風土だけがすべてではないが、風土の影響は案外大きい。それは人の美意識や宇宙像、自然観にも影響をもたらす。
日本もイギリスも島国だが、日本とイギリスでは思考様式や歴史意識に大きなちがいがある。
イギリスは昔からヨーロッパと一体となって発達し、イギリス人にとって古典といえば、ほかのヨーロッパの国々と同じく、ギリシャ、ローマの古典になっている。その歴史もヨーロッパ全体の歴史と同時性をもっている。
ところが、「日本は中国から影響をうけるが、歴史的同時性はほとんどない」と丸山はいう。仏教が中国に伝来したのは西暦紀元元年前後であるのに、日本への渡来は6世紀となる。中国で宋学(朱子学)が全盛期を迎えたのは12世紀後半なのに、日本で朱子学が全盛となるのは江戸時代の17世紀初期になってからである。つまり日本は「急激な文化的ショックもなく、大陸民族による大規模な征服も、人種混淆も、古代日本(弥生文化)以来、経験していない」のだ。
朝鮮と日本のちがいは、朝鮮が中国と陸続きなのに、日本は海で隔てられていることに由来する。中国からみれば日本は「東夷」の国であり、文明の及ぶ最東端に位置している。
『後漢書』や『魏志倭人伝』には倭国の記録がある。倭国は5世紀半ばまで朝貢国だが、3世紀ごろには、すでに西日本を中心とした古代国家が形成されていた。『日本書記』には、4世紀に新羅に侵攻し、任那に日本府を築いたという記録がある。
丸山はこうコメントする。
〈古代日本は、中国に朝貢しつつ朝鮮の一部を朝貢させるという、独特な位置を占めた。また漢字受容の仕方もちがう。日本はきわめて早くこれを仮名として日本語化した[朝鮮でハングルがつくられたのは15世紀半ばになってからだ]。〉
日本には大陸文明の渡来以前にすでに何かがあり、その上で文化を受容した、と丸山はいう。弥生式以後の日本文化には、人種、言語、領土、生産様式、宗教意識まで含め、いちじるしい連続性と同質性がみられる。それらは自然にできたものとさえ感じられている。
しかし、重要なのは、そのことだけではない。「日本の特異性は、同質性を保ちつつも常に世界最高の文化から刺激を受けつづけてきたこと、高度な大陸文化の適当な刺激を受けつつ、しかも同質性を保った点にある」と丸山はいう。
大陸からの空間的距離があったおかげで、日本は意識的に大陸文化を摂取し、オリジナルな何かを加工して、独自の文化をつくることができた。それは「もっぱら支配層が外国文化を摂取するという形をとり、それが上から下へ、中央から地方へと浸透していった」。
日本の地理的特徴は、日本が「地理的位置において、完全な閉鎖的自足性を維持するにはあまりに高度の外来文明の刺激を受けやすい位置にある」ことだ、と丸山はいう。それは開かれた共同体社会だといってもよい。外にたいしては開かれていながら、内部では閉鎖性が強いのが日本社会の特質である。
内と外の区別は、思考様式の二分化をもたらす。内では共同体モラルによる画一的な思考と行動様式が形成され、外は他者からなる見知らぬよその世界である。そのため日本人のあいだではコスモポリタニズムの感覚が育ちにくい。
日本の思想文化は、外の世界からの文化の摂取と、その修正、同化の歴史といってもよい。摂取によって、土着の内なる等質性は破壊されることなく持続する。古くはいったものは下層に沈殿し、そのうえに外からはいってきたものが積み重なる。外来文化を受容し、修正するパターンが見受けられる。
停滞でもなく、革命的断絶でもなく、だらだらとした変化がつづくのが、日本の思想文化の特徴だ。体制の切れ目がはっきりしない。
たとえば明治維新をみても、新しいものが古いものの上に乗って成長発展していくことがわかる。近代日本においても「伝統的なるものと近代的なるものとは矛盾することなく、むしろ補完しあった」。「それはまた持続性と変化性の逆説的結合ということができる」と、丸山は述べている。
こうしたとらえ方には、さまざまな反論も可能だろう。ウェーバー流の「型」による認識方法に疑問が寄せられてもしかるべきだ。はたして、明治維新をこんなふうにとらえて、納得してしまってもいいのか、という強い懸念も残る。
だが、いまは講義を聴くときだ。
勝手にブックカバーチャレンジ [雑記]
このところSNSで7日間ブックカバーチャレンジというのがはやっているようです。コロナ禍で家に閉じこもるのを余儀なくされているなら、せめて読書の楽しみをみつけようという提案。まことに結構なことです。
ぼくのほうは、まさしく黄昏で、友達がどんどん亡くなって、いよいよ人生の終末期が近づいてきました。思い出だけが新しいと感じる毎日です。
平凡なサラリーマン生活を約35年送りました。そのうち15年が営業関係、20年が書籍編集関係の仕事。無能な編集者でした。
この年になると、恥も外聞もなくなります。自分のつくった本から、勝手にブックカバーを並べてみました。いろいろ思い出はありますが、とくに説明はいらないというので、昔の記念として並べてみました。7冊ということですが、少し増えてしまいました。
斎藤茂男『妻たちの思秋期』(1982年)
斎藤さんの本は「日本の幸福」シリーズで、何冊も出しました。

辺見庸『もの食う人びと』(1994年)
もう一冊エッセイをまとめました。

横川和夫『仮面の家──先生夫婦はなぜ息子を殺したか』(1993年)
横川さんと保坂渉さんの本は何冊も出しました。『かげろうの家』もそうですね。

ロバート・マクナマラ『マクナマラ回顧録──ベトナムの悲劇と教訓』(仲晃訳、1997年)
もう一冊、ベトナムとの対話をまとめた本を出しました。

春名幹男『秘密のファイル──CIAの対日工作』(上下、2000年)

工藤幸雄『ぼくとポーランドについて、など』(1997年)
『乳牛に鞍』という本、翻訳本も出しました。工藤先生の家にはよく出入りさせてもらいました。

小野寺百合子『私の明治・大正・昭和──戦争と平和の八十年』(1990年)
ほかにも何冊か。『バルト海のほとりにて』は改訂版をつくりました。

ノーマン・デイヴィス『ヨーロッパ』(全4巻、別宮貞徳訳、2000年)
『アイルズ』という大著も出しました。

ドン・オーバードーファー『二つのコリア──国際政治の中の朝鮮半島』(菱木一美訳、1998年)
マンスフィールドの本もありましたね。

ポール・ジョンソン『現代史』(全2巻、別宮貞徳訳、1992年)
最初に出したのは『インテレクチュアルズ』(1990年)です。ポール・ジョンソンの本は何冊も出しました。別宮先生は大恩人です。
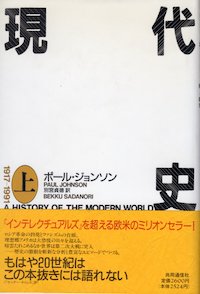
マルク・ド・ヴィリエ『ウォーター──世界水戦争』(鈴木主税訳、2002年)
鈴木先生には、ジェームズ・マンの『米中奔流』や『ウルカヌスの群像』など、多くの本でたいへんお世話になりました。

ケネス・ルオフ『国民の天皇──戦後日本の民主主義と天皇制』(高橋紘監修、木村剛久・福島睦男訳、2003年)

ジョン・バリー『グレート・インフルエンザ』(平澤正夫訳、2005年)
これは傑作です。平澤先生とは『ダムはムダ』という本もつくりました。

もうきりがないですね。このへんでやめておきましょう。みんな懐かしい思い出です。以上、ステイ・ホームの身辺整理でした。それにしても昔の本なのでカバーが汚れてしまっています。
ぼくのほうは、まさしく黄昏で、友達がどんどん亡くなって、いよいよ人生の終末期が近づいてきました。思い出だけが新しいと感じる毎日です。
平凡なサラリーマン生活を約35年送りました。そのうち15年が営業関係、20年が書籍編集関係の仕事。無能な編集者でした。
この年になると、恥も外聞もなくなります。自分のつくった本から、勝手にブックカバーを並べてみました。いろいろ思い出はありますが、とくに説明はいらないというので、昔の記念として並べてみました。7冊ということですが、少し増えてしまいました。
斎藤茂男『妻たちの思秋期』(1982年)
斎藤さんの本は「日本の幸福」シリーズで、何冊も出しました。

辺見庸『もの食う人びと』(1994年)
もう一冊エッセイをまとめました。

横川和夫『仮面の家──先生夫婦はなぜ息子を殺したか』(1993年)
横川さんと保坂渉さんの本は何冊も出しました。『かげろうの家』もそうですね。

ロバート・マクナマラ『マクナマラ回顧録──ベトナムの悲劇と教訓』(仲晃訳、1997年)
もう一冊、ベトナムとの対話をまとめた本を出しました。

春名幹男『秘密のファイル──CIAの対日工作』(上下、2000年)

工藤幸雄『ぼくとポーランドについて、など』(1997年)
『乳牛に鞍』という本、翻訳本も出しました。工藤先生の家にはよく出入りさせてもらいました。

小野寺百合子『私の明治・大正・昭和──戦争と平和の八十年』(1990年)
ほかにも何冊か。『バルト海のほとりにて』は改訂版をつくりました。

ノーマン・デイヴィス『ヨーロッパ』(全4巻、別宮貞徳訳、2000年)
『アイルズ』という大著も出しました。

ドン・オーバードーファー『二つのコリア──国際政治の中の朝鮮半島』(菱木一美訳、1998年)
マンスフィールドの本もありましたね。

ポール・ジョンソン『現代史』(全2巻、別宮貞徳訳、1992年)
最初に出したのは『インテレクチュアルズ』(1990年)です。ポール・ジョンソンの本は何冊も出しました。別宮先生は大恩人です。
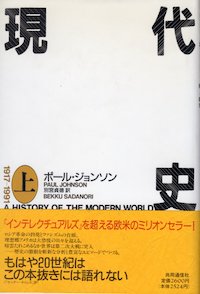
マルク・ド・ヴィリエ『ウォーター──世界水戦争』(鈴木主税訳、2002年)
鈴木先生には、ジェームズ・マンの『米中奔流』や『ウルカヌスの群像』など、多くの本でたいへんお世話になりました。

ケネス・ルオフ『国民の天皇──戦後日本の民主主義と天皇制』(高橋紘監修、木村剛久・福島睦男訳、2003年)

ジョン・バリー『グレート・インフルエンザ』(平澤正夫訳、2005年)
これは傑作です。平澤先生とは『ダムはムダ』という本もつくりました。

もうきりがないですね。このへんでやめておきましょう。みんな懐かしい思い出です。以上、ステイ・ホームの身辺整理でした。それにしても昔の本なのでカバーが汚れてしまっています。
服部龍二『大平正芳』を読む(2) [われらの時代]

1972年7月7日に田中角栄内閣が成立すると、大平正芳は2度目の外相に就任した。田中は日中国交回復を急ぐとの談話を発表し、「外交は大平に任せた」と述べた。
この年2月には、すでにニクソン米大統領が訪中し、米中首脳会談が開かれていた。
大平はこう述べている。
〈日中両国は、古くから一衣帯水の隣国であり、未来永劫にそうである。好むと好まざるとに拘らず、相互に分別をもって、平和なつき合いをしなければならない間柄である。ところが、日中両国民の間には共通点よりは相違点が多く、相互の理解は想像以上に難しい。しかし、お互いに隣国として永久につき合わねばならない以上、よほどの努力と忍耐が相互に求められる。〉
7月22日、大平はホテルオークラで、中日友好協会副秘書長の孫平化と会った。孫平化は周恩来首相の指示で来日し、田中訪中に向けての下工作をしていた。中国側も日本との国交回復に前向きになっていたのだ。
大平は8月11日、帝国ホテルで開かれた日米協会主催の会合で、「細心周到な準備を怠らないで」、日中国交回復を推進していくとスピーチした。日中国交回復は日米関係を阻害するものであってはならないというのが、大平の基本的な考えである。
問題は台湾との関係だった。8月16日に台湾の大使、彭孟緝が大平を訪ね、日中国交正常化の動きへの厳重抗議を申し入れた。大平は、政治の責任からして、断腸の思いで、正常化問題に取り組まざるを得ないと答えた。
田中と大平は8月31日と9月1日に、ハワイでニクソン大統領と会見、日米安保条約の堅持を約束した。
アメリカは横須賀を空母ミッドウェーの母港としたがっていた。ミッドウェーは核を搭載していると思われたが、「核密約」がある以上、日本側からその問題を提起することはできなかった。大平は日中国交正常化後の11月にミッドウェーが横須賀を母港とすることを認めることになる。
日中交渉で懸念されるのは、中国が安保条約の規定する極東の範囲から台湾を除外するよう求めることだった。だが、どうやらそれはなさそうだったとの確信を得て、田中と大平は訪中を決断した。
大平は周恩来首相、姫鵬飛外相と交渉を重ね、毛沢東主席とも会見した。こうして9月29日に日中共同声明が出された。田中は共同声明のとりまとめを、すべて大平にまかせ、ただ「軍国主義」という表現だけは避けるよう指示した。
このときの日中交渉について、大平はこう書いている。
〈共同声明は妥協の産物である。前文で中国側の言分を入れ、本文で日本側の立場を入れたため論理的に矛盾があるが、これにより過去を清算したという所にとり得がある。……安保条約については、中国側は、本件は日米間の問題である故、とやかく言わないという態度で議論の対象にしなかった。……台湾については、中国は自分の見る所では相当長い時間帯の中で考えている模様である。〉
日中共同声明によって、日本と中国の国交が樹立された。このとき尖閣は大きな話題にならなかった。
10月、大平は日中国交正常化について説明するため、オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、ソ連を歴訪した。
1973年4月から5月にかけては、ユーゴスラビア、フランス、ベルギーを訪問した。ヨーロッパでは、中国と国交を樹立した経済大国日本への関心が高まっていた。
7月末から8月初めにかけて、大平は田中とともに訪米した。その直後、8月8日に金大中事件が発生する。韓国元大統領候補の金大中が、白昼、都心のホテルグランドパレスで拉致されたのである。事件は韓国中央情報部(KCIA)によるもので、日韓の外交問題に発展した。
11月、韓国側はこの事件にたいし遺憾の意を表明し、政治決着がはかられることになった。事件の捜査は抑えられ、日韓関係の安定が優先された。とうぜんながら、野党からは鋭い批判が浴びせられた。
その前に、大平は9月下旬から10月上旬にかけ、アメリカをはじめとして、イタリア、イギリス、西ドイツ、ソ連を歴訪していた。
大平は国連総会で演説し、アジアが安定した秩序と繁栄を求める新たな時代を迎えようとしていると述べた。
大平はロンドンで田中と落ち合い、ヒース首相と会見したあと、西ドイツを経て、最終目的地のモスクワに向かった。10月6日、フランクフルト郊外に滞在しているとき、エジプト、シリアがイスラエルを奇襲攻撃したとの知らせがはいった。第4次中東戦争がはじまったのである。
モスクワでは北方領土問題をめぐって、ブレジネフ書記長、コスイギン首相、グロムイコ外相と4回会談した。田中は「平和条約の締結の前提には、四つの島の問題がある」と詰め寄ったが、ブレジネフはシベリア開発の問題に論点をずらした。
それでも日ソ首脳会談では大きな成果がみられた。ブレジネフから、北方領土問題は未解決との言質を得たからである。北方領土問題は解決済みというこれまでのソ連の態度を崩すことができたのは、ひとつの外交的成果だった。
しかし、帰国後に待ち受けていたのは石油危機だった。ほとんどの閣僚がアラブ寄りの姿勢を示すなか、大平は対米協調を主張した。先進国が高騰を許さないよう結束すれば、産油国は困るはずだと考えていた。
11月、大平はアラブ諸国の大使やキッシンジャーと東京で会談する。田中は財界の意向を受けてアラブ寄りとなっており、イスラエルを非難する声明を発表する。これを受けて、アラブ諸国は石油の対日輸出を現状維持とした。声明を発表する前に、大平はアメリカの了解を得るよう努力した。
1974年2月、ワシントンで石油消費国会議が開かれ、大平も出席した。その結果、11月には国際エネルギー機関(IEA)が発足する。大平は単なる対米協調を超えて、石油危機後の安定的な国際秩序の構築をめざしていたのだ。
訪米前の1月に、大平は北京を訪れ、中国との貿易協定、航空協定、海運協定、漁業協定に臨んでいた。
最大の難関は航空協定だった。中国は台湾の中華航空と同じ空港に乗り入れるわけにはいかないと主張した。しかし、日本とすれば、台湾航空機の乗り入れを排除するわけにはいかない。
大平は一歩もゆずらなかった。たとえ中国との国交正常化がなされても、日台間では民間の実務関係を維持するのが原則だと述べた。
大平は交渉決裂を覚悟し、姫外相に別れのあいさつをした。これに驚愕した中国側は折れて、妥協する。その結果、台湾機は羽田、中国機は成田に振り分けるという妥協案が成立した。
日中航空協定に自民党内右派は強く反発した。青嵐会の議員は、台湾の尊厳を傷つけたとして、大平をつるし上げた。大平は政敵ともいうべき佐藤栄作のもとを訪れ、台湾派を鎮めるよう協力を求め、佐藤もこれを了承した。
こうして4月20日になって、北京で日中航空協定の調印がおこなわれた。これが外相としては大平の最後の大仕事になった。
それ以降については、ごく簡単にみておく。
7月の参院選で田中内閣が敗北すると、三木副総理と福田蔵相が閣僚を辞任し、大平はその穴を埋めるため、外相から蔵相に転じた。
11月26日に田中は辞意を表明。12月1日、椎名悦三郎副総裁の裁定により、三木武夫が次期総裁に決まった。三木内閣で、大平は蔵相に留任するが、最後まで三木とはかみ合わなかったと語っている。
1975年2月、アメリカの上院でロッキード事件が浮上し、7月27日に田中角栄が逮捕された。
12月、三木おろしにより、福田赳夫内閣が発足する。大平は福田を支持した。ただし、2年後に政権を大平に渡すという、いわゆる「大福密約」が交わされていた。
大平は党の幹事長に就任する。
その大平について、当時、幹事長室室長の奥島貞雄はこう語っている。
〈大平のあだ名は「鈍牛」。「アー、ウー」という独特の語り口を揶揄されたりもした。だが、私に言わせれば、仕えた歴代幹事長のなかで大平ほど「哲学」を感じさせた政治家はいない。敬虔なクリスチャンでもあり、熟慮の末に言葉を選び、およそ失言の類とは無縁。発言の内側にはじっくり煮込んだ肉料理のような深い味わいが醸し出されていた。発言録から「アー、ウー」を削除すると、見事な名論文になっていた。学究肌の人柄にも驚かされたものだった。即断即決の“コンピューター付きブルドーザー”が田中なら、大平は“行動する哲学者”とでも形容すべきだろうか。〉
1978年8月には日中平和条約が調印され、10月には鄧小平が来日した。
10月、大平との約束をたがえて、福田は総裁選への出馬を決意する。11月には「大福決戦」がおこなわれ、68歳の大平が総裁の座を勝ちとった。
12月7日、第1次大平内閣が発足する。総合安全保障と環太平洋連帯構想、経済中心の時代から文化重視の時代へというのが合言葉だった。外交面ではアメリカ基軸という考えは変わらない。
1979年6月には東京サミットが開かれ、大平は議長を務めた。第2次石油危機がはじまっていた。大平はこのサミットで、世界の秩序が「壊れやすい陶器のような状況」になっていることを痛感した。
10月の総選挙で、自民党はかろうじて過半数を維持した。いわゆる「40日抗争」により、大平の退陣要求が強まる。党内は分裂したが、大平はようやく首相の座を維持した。
そのころ、イランではアメリカ大使館人質事件が発生し、ソ連がアフガニスタンに侵攻していた。
12月には、中国との円借款交渉がまとまった。このとき訪中した大平は、北京の政治協商会議講堂で、「国と国との関係において最も大切なものは、国民の心と心の間に結ばれた強固な信頼であります」とあいさつしている。
1980年1月、大平はオーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニアを訪問する。環太平洋連帯構想に向けての一歩だった。
4月には、アメリカ、メキシコ、カナダを回り、カーター米大統領とも会談した。その後、ヨーロッパにも足を伸ばした。ユーゴスラビアのチトー大統領の葬儀にも出席し、5月11日に帰国した。
そのころ、国内の政治状況は不穏になっていた。
5月16日、社会党が提出した内閣不信任案が可決された。福田派、三木派、中曽根派が欠席戦術に出たためである。
大平は解散を決意する。
6月22日に衆参同時選挙がおこなわれることになった。
公示日の5月30日、大平は新宿で遊説演説した。途中で気分が悪くなったが、がまんして、そのあと4カ所回ったあと自宅で医師による診療がおこなわれた。心筋梗塞をおこしていた。
虎ノ門病院に入院した大平は、一時回復するものの6月12日に死亡する。享年70歳。
自民党は6月22日の弔い選挙で圧勝した。
クリスチャンである大平は、生前、「永遠の今」について、こう記していた。
〈神が「永遠の今」という時間を各人に恵み給うたことは、自分は自分としての永遠に連(つなが)る寄与をするよう期待されてのことではないでしょうか。〉
神が与えてくれた今という時間をだいじにして、各自がそれぞれ懸命に努力すること、それが「永遠の今」、すなわち歴史につながることだ、と信じていたのである。



