仲正昌樹『統一教会と私』を読む(2) [本]

統一教会にはいり、伝道をはじめると、著者は次第にその活動にのめり込んでいく。話を聞いてくれる学生は少ない。入会してくれたのは、たった一人だった。
珍味などの物を売る(いわゆる万物復帰)のは苦手だった。そのため、原理研のなかでも、落ちこぼれになったような気がした。それでも、いまさら退会するわけにはいかず、統一教会に身をまかせるほかなかったという。
やる気をなくしていると、もっと自分を見つめなおせと説教され、ますますうんざりしてしまう。大学でも白い目で見られ孤立しているので、授業にでる気もなくなる。左翼とぶつかるときだけ元気がでた。
原理研は韓国、日本、アメリカに組織があって、その英語略称がCARPだった。そこにドイツでもCARPを設立しようという話がもちあがる。まだドイツが東西に分かれている時代だった。著者もドイツに行ってみたいと思うようになるが、なかなか行かせてもらえなかった。やがて、チャンスがめぐってくる。ドイツ行きが決まった。
西ドイツでは最初に北西部のミュンスター、つづいてボンやケルンで伝道や物売りをはじめた。だが、うまく行かない。人間関係もよくなかった。バカにされているようなので、ケルン大学に登録して、哲学を勉強し、学位をとって、みんなを見返してやろうと思った。
そんなとき、原理研の東京ブロック長から指示があった。日本にいったん戻って、東大を卒業するようにというのだ。いろいろ考えた末、ドイツに帰らず、ふたたび東大に通うことにした。
信仰歴が6年にもなるのに統一教会のなかで、著者はなかなか認めてもらえなかった。合同結婚式に参加できる「祝福」候補者にもしてもらえない。「祝福」は再臨のメシアによる原罪の清算を意味しているのに、それが認められないというのはどうしてかと、歯がゆい思いをつのらせていたという。このあたりの感覚は信者でないとわからない。
大学はもちろん、ホームでもだんだん居心地の悪さを感じるようになったちょうどそのころ、ようやく「祝福」の話がでる。相手は日本人で、地方の教会に所属している人だという。知らされたのはそれだけだ。
こうして著者は1988年に韓国での「合同結婚式」に出席することになる。相手と会ったのは、結婚式の前日で、軽くあいさつした程度だった。
当日は、文鮮明教祖のお言葉のあと、6500組のカップルが全員で万歳(マンセー)を唱え、そのあと別の会場で、おたがいに棒で尻を3回ずつ叩き合う儀式がおこなわれた。アダムとエバ(イブ)の罪を清算する意味がこめられている。
しかし、著者にとって相手は好みではなかった。話も合わなかった。
大学院への進学をめざしたが、面接で落とされてしまう。原理研にはいっていることが大きな理由だった。
大学院受験に失敗した著者は、統一教会系の新聞「世界日報」に就職する。住まいは駒場のホームから「世界日報」の川崎の寮へ移った。
そのころ世間では霊感商法への批判が巻き起こっていたが、著者はそれを一種の献金だととらえ、マスコミが嘘の情報を垂れ流していると思っていた。その集めたお金は、世界での布教活動に使われていると理解していた。
1991年ごろ、「世界日報」でもらう給料は5万円か6万円で、かなり低かった。生活が苦しいのは神が私たちに与えた試練だと思い、感謝して働いている信者が多かったという。
しかし、けっきょく著者は大学院で学ぶ道を捨てきれなかった。ドイツ語と英語は得意なので、ドイツ思想史に関連する研究者なら、自分にもできるかもしれないと思った。
こうして著者は三たび挑戦し、ついに1992年4月に東大大学院総合文化研究科に入学することができた。それが統一教会を脱会するきっかけになる。
合同結婚式でマッチングされた相手とは気が合わず、別れることにした。いっしょに過ごしていく将来のかたちが、どうしても描けなかった。
仕事場の「世界日報」での人間関係もうまくいかない。記事の論調にも不審を感じた。文鮮明が北朝鮮を訪問し、金日成と会談してからというもの、世界日報でも北朝鮮にたいする論調が露骨にあまくなっていた。
そんなことが重なって、著者は「もう脱会してもいいかな」と思うようになる。
親から送ってもらったお金でアパートを借り、奨学金をもらうことにした。相対者の女性とは正式に別れ、「世界日報」を辞めた。退職にあたっては、退職金をもらうとともに、統一教会の批判をしないという書面にサインした。
数カ月たつと、統一教会の本部から「祝福」を辞退することを証明する書類が送られてきた。これはメシアの意志に従わないことを意味する。その書類にサインして、正式な脱会が決まった。
その後、著者はドイツ思想史の研究者となり、ふたたびドイツに留学し、統一教会で「失われた10年」を取り戻すべく、がむしゃらに勉強する。博士号を取得し、駒沢大学で非常勤講師をしながら、19大学の公募に応募し、ようやく金沢大学から採用されることになる。
「なんだかんだと騒ぎながら、35歳になるちょっと前に就職できた私は幸運だった」と回顧している。それからは研究一筋。結婚していない。「ひとりでいることに慣れてしまったのかもしれない」という。
著者にとって、宗教とは何なのか、あるいは何だったのか。
意外なことに、統一教会のメンバーシップはさほど強靱ではなかったという。
多かれ少なかれ、宗教と人間は切っても切れない関係にある。宗教とは「精神的な絆」を求める人たちの共同体だ。そのなかでは、神が私を導いていると思えると安心できる。
そんな共同体は宗教団体だけでなく、国家でも企業でも家庭でも同じかもしれない。いつの時代も、将来は不安に満ちているからだ。しかし、そうした共同体になじめない人たちもいる。
何らかのきっかけで、そこからはじきだされた人たちは、周囲から奇異にみえる「形而上学的なもの」にみずからの精神的基盤を求めるようになる。そういう人たちが新たに霊的な絆を基盤とする共同体をつくると、それが「宗教」にみえるようになる。
それはあたりまえのことで、「宗教」をやたら危険視、敵視するのはおかしい、と著者はいう。
日本でいうカルトとは、反社会的な宗教教団のことである。そこでは、反社会的ということに重点が置かれているが、異端の宗教教団をイメージだけで、安易にカルトというべきではない。信仰の自由は守られなければならないからだ。
「教団の存在自体を否定し、なんとしても解散に追いこもうとするようなマスコミの報道姿勢は、単なるスキャンだリズムだと思う」と著者は書いている。
マインドコントロールというが、人間を思いどおりに操ることはそう簡単にはできない。多くの葛藤をへて、人は信仰や忠誠心を固めていく。それは統一教会でも同じで、「組織による拘束力や強制力は、統一教会よりも普通の会社のほうが強いようにも思える」。
左翼が統一教会をはじめ宗教そのものを認めないのは、マルクス主義が宗教的性格を帯びているからだ、と著者は断言する。唯物論的な歴史的発展の法則というのは、きわめて形而上学的な想定である。労働を神聖視するのも、宗教的なイデオロギーである。マルクス主義がはやるのは、それが「疑似宗教的な『共同性』をつくり出すからだろう」。それが極端なかたちまで進んだのが、連合赤軍のリンチ殺人事件だった、と著者はいう。
いつの時代も、人とのつながり(絆=共同性)と人からの承認を求める志向性は強い。しかし、絆を強調しすぎるのは危険だ、と著者はいう。絆を求めすぎると、特異な教理に帰依しようとする傾向も強まっていく。だれにもそれを阻止する権利はないが、特定の宗教や思想にのめり込むのは、あまり好ましくない。第三者的な視点を失って、考え方が閉鎖的になっていくからだ。
新宗教は白い目で見られがちだが、信者の側にも言い分はある。自分たちは何も悪いことをしていないと思っているからだ。多くの人から見れば変わった思想であっても、それを誹謗中傷しない、ある程度の寛容さが必要ではないか、と著者はいう。
どのような社会や組織でも、全体を統率しながら、一人ひとりの状態に心を配るような権力は必要である。人間にはだれしも「私の存在価値を認めてほしい」という欲求がある。「人から認めてもらったり、人を認めるという経験が日常的に不足していると、互いに認めあうシステムを構築している宗教に人が集まりやすくなるのは、当然のことだろう」
人間にはかならず死が訪れる。しかし、それを常に意識していたら、それこそおかしくなってしまうだろう。自分が死に、魂が消滅すると考えたら、なにをやってもむなしいという気分になり、それこそ自暴自棄にもなりかねない。
しかし、魂が不死であり、自分のやっていることが神によって見守られているとしたら、不安は取り除かれ、生きることに自信がもてるようになる。著者の場合は、そうした心の安定装置が原理研=統一教会だったという。そして、統一教会に心の安定を見いだせなくなったときに、脱会の道を選んだ。
入会を決め、脱会を決めるのは、あくまでも個人だ。
生きていくうえで、だいじなのは寛容の思想だ、と著者はいう。話を聞く前に非難するのは、批判ではなく、ただの誹謗中傷である。おかしな主張を掲げていると思ったら、その中身を批判すればいいという。
著者は統一教会での体験を後悔していない。統一教会にはいっていなければ、学者になっていなかっただろうという。人とのコミュニケーションができるようになり、ドイツに行くことができ、マルクス主義や実存主義、キリスト教系の宗教哲学を学ぶことができ、取材して記事を書くことができるようになったのも統一教会のおかげだったという。
もっと早く脱会してもよかったが、研究者としてはハンデがあったからこそ、がむしゃらに努力してきた。統一教会を否定したあとは、自分で自分の道をみつけなければならなかった。いまも心酔し、尊敬している思想家はいないという。
「他人に迷惑をかけない範囲で、宗教を信じたい人は信じればいいし、辞めたくなった人は適当な時期に辞めればいい、と思う」
それは統一教会についてだけでなく、どんな宗教でもいえることだ。
仲正昌樹『統一教会と私』を読む(1) [本]

仲正昌樹は政治哲学や政治思想の研究者としてよく知られている。
マキャベリ、ルソー、カント、ヘーゲル、マルクス、ウェーバー、ニーチェ、ハイデガー、カール・シュミット、ベンヤミン、アーレント、フロム、デリダ、ハイエク、ロールズ、ドゥルーズ、ガタリ、フーコーなどなど、あまたにわたる思想家のテキストを読み解き解説する膨大な著書がある。
ぼくも何冊かもっているが、手がつかないまま、ほとんどが本棚に眠る。かれのすさまじいパワーは、いったいどこからくるのか。
1963年に広島県呉市で生まれ、81年に東京大学(理Ⅰ)に入学している。入学早々、原理研究会(原理研)にはいり、92年11月に脱会するまで、11年半、統一教会の信者だった。
本書は著者の統一教会での体験を率直につづったものである。
読みはじめて最初に感じるのは、統一教会がカルトというより、いわばサークルやセクトに近い存在だということだ。全共闘時代の大学を経験したぼくは、革命に疑問をもっていたためセクトにははいらなかったが、まわりにはセクト(共産党や新左翼を含め)に所属する人たちが大勢いた。
その伝からいえば、統一教会はキリスト教系の──そう決めつけると反発する人もいるだろうが──新宗教団体、いや新宗教セクトといってもいいのではないか。
そのコングロマリットは、統一教会を母体として、原理研、国際勝共連合、世界平和教授アカデミー、世界日報などのメディア、その他もろもろの企業からなりたっている。
なお、本書にはいわゆる暴露はない。あくまでも著者個人の体験だけがつづられている。統一教会の資金がどのように使われたのか。自民党とのつながりはどうだったのか。あるいは、統一教会の活動がどれだけ多くの家族を不幸にしたのか。また、現在名称を変えた統一教会のことも描かれていない。それを知るにはジャーナリズムの力が必要である。
それでも、本書からは統一教会がどんな団体か(だったか)が伝わってくる。
ぼく自身は相変わらず愚鈍で、読書もはかどらない。ぼうっとしていることが多い。それはいたしかたないとして、少しずつ読んでみることにした。
統一教会は1954年に韓国で文鮮明(ムンソンミョン)を教祖として設立された宗教団体である。日本に支部ができるのは1959年で、64年に宗教法人として認可されている。
その教義はキリスト教の聖書をもとにした『原理講論』に集約される。
話はアダムとエバ(イブ)の堕落論(楽園追放)からはじまる。
統一教会はこの物語を次のように理解する。
天使長ルーシェル(ルキフェル、ルーシェル)は、神が人間をかわいがるのを嫉妬して、エバを誘惑して関係をもち、それを悔やんだエバは夫となるべきアダムと積極的に交わってしまう。そのことを知った神はアダムとエバを楽園から追放する。ルーシェルは悪魔サタンと化す。
神から見捨てられたアダムとエバは、サタンがとりつきやすい体質になっている。原罪を負ってしまったからである。
しかし、神は人類を見捨てはしない。いつか再臨のメシアが人類の罪をあがない、ふたたび地上に神の国を実現する。統一教会では、その再臨のメシアこそ文鮮明だと考えられている。
統一教会の特徴は、その宗教活動が反共を中心とする政治活動とつながっていることだという。共産主義、すなわちマルクス主義はサタンの思想であって、それに対抗する真の理想社会像を示すことが求められる。
そうした「勝共理論」にもとづいて、勝共連合が結成される。勝共連合には、信者にかぎらず、信者以外の政治家や知識人、ジャーナリストも加わる。
呉市に生まれた著者が統一教会にはいったきっかけは、東大に入学した早々、原理研究会というサークルに勧誘されたためだ。勉強は得意だが、スポーツは苦手、人づきあいも好きではなく、「ドンな奴」とコンプレックスをいだいていた。日教組や労働組合のスト、左翼的なものには反感をもっていた。自己変革を迫る共産主義の雰囲気が嫌いだった。キリスト教にもとくに興味をもっていなかったという。
そんな著者がなぜ原理研(著者の言い方では原研)にひかれたのだろう。勧誘した人が自分の話をよく聞いてくれたというあたりがはじまりだった。原理研にはいれば、自分の不安や劣等感、さみしさが解消されるような気がした。
サークルのホームでは「統一原理」を教えられた。それは聖書の物語を解釈した一種の人間学で、自分のようなうらみがましい、だめな人間にも救いが待っているという壮大な体系から成り立っていた。
ホームにかよいだしてから1週間後、著者は「ツーデイズ」と呼ばれる2泊の研修合宿に参加した。そこで、さらにくわしく「統一原理」を学ぶと、統一教会を信じるという自覚をもつようになったという。聖書にもとづくその教えがじゅうぶん納得できるものと感じられた。
共産党系の民青からの嫌がらせを受けた著者は、いづらくなった東大駒場寮を出て、原理研のホームに住み込むようになった。それからしばらくして、「セブンデイズ」と呼ばれる七日間の研修に参加し、正式に統一教会の会員となった。
東大の原理研は世田谷区代沢に一軒家を借り上げ、ホームとして使っていた。そこでは20人くらいが暮らしていたが、手狭になったので、さらに近所のアパートの一室を借りた。信仰生活にもとづく合宿生活がはじまった。
原理研は学区ごとにつくられ、その上にブロックがあり、さらに全国大学原理研究会という組織があって、会長がいる。学区の下に支部がある。韓国語風に食口(しっく)と呼ばれる信者は伝道活動を実践し、礼拝に参加し、共産主義を否定するための勝共理論を学ぶ。みずからの罪を神に告白し、夜を徹して祈禱することもおこなわれていた。
原理研は基本的に統一教会、勝共連合の学生組織である。原理研では、女性会員をエバさん、男性会員をアダムと呼んでいた。男女関係を含め、堕落した人間は、「非原理的」とされ、批判された。
東大の原理研はどちらかというと特別扱いされていた。学区長には元新左翼の人もいた。東大生への伝道は大きな目標で、ときに女子学生からなる「エバ部隊」が投入されることもあったという。しかし、色仕掛けは御法度だった。
統一教会をセックス教団ととらえるのはまちがいだ、と著者はいう。合同結婚式もどちらかというと婚約に近く、家庭生活をはじめる許可を本部からもらうまでは、たがいに清い関係を保たなければならない。
原理研では物品販売の仕事もあった。人は、おカネに執着しながら、「堕落世界」、「サタン世界」で暮らしている。神の元に復帰するには、まずおカネを献金しなければならない。これが万物復帰の考え方である。
信者が物品を売るのは、ひとつの伝道であり、たとえ苦しくても伝道でおカネを集めることが、神の御旨(みむね)にかなうことになる。そして、物品を買ってくれる人も、それによって霊界が晴れ、先祖の罪が許されるのだから、これにより、たとえ霊感商法と呼ばれても、物品販売は正当化されることになる。
もっとも、そう高い物品がいきなり売れるわけではない。著者が入信する前はよく、お茶が売られていた。それが珍味に変わり、さらにメタライト(金属絵画)に変わっていったという。
夏休みには仙台で21日修練会があった。ここではさらにレベルの高い学習の場があり、信者どうしの結婚に関する話もされ、伝道(勧誘)や万物復帰(物売り)の実践もあった。ワゴン車に6、7人が乗って、珍味を売りにいく。50軒、60軒と回ってもなかなか売れなかった。徹夜祈禱も何度かおこなわれたという。
東大に帰ると、左翼との戦いが待っていた。民青からは口げんかをふっかけられ、新左翼のセクトからは暴力をふるわれた。共産主義研究会という研究会を立ち上げて、マルクス主義のテキストを取りあげ、論破する講座を開いた。巨大な立て看板をつくって、統一原理や勝共理論にもとづき、左翼批判をくり広げたりもした。
こうした活動を通じて、原理研の仲間どうしの結束がかたまっていく。左翼からいやがらせを受けるたびに「やはり左翼はサタンなんだ」という確信が強まっていく。
左翼からの批判は、著者にいわせれば荒唐無稽なものが多かったという。「根拠もなく、無茶な話を信じて暴力をふるっているくせに、自分たちは『科学的社会主義』と称する態度は、私たちよりはるかに狂信的な宗教であるとしか思えなかった」
著者も左翼から暴力を受けて、何度か病院に行ったという。
こうして著者はますます原理研の活動にのめり込んでいった。
誤解を恐れずにいうと、なんだかぼくの短い左翼体験とも似ている部分もあって、おもしろいし、なつかしくもある。
長くなったので、今回はこれくらいで。つづきは次回ということにしよう。
著者はますます統一教会にのめり込んでいくが、そこからどのようにして脱会していったのだろうか。
水野和夫『次なる100年』を読む(6) [本]
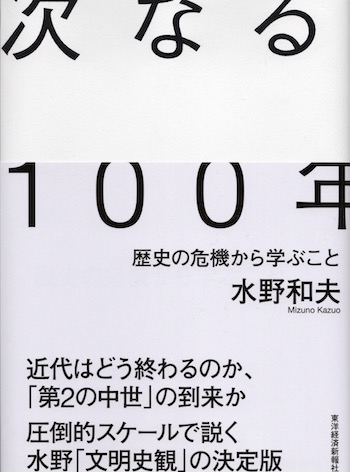
中世の中心はイコン(聖像)だった。これにたいし、近代の中心はコイン(おカネ)である。しかし、21世紀の中心はイコンでもコインでもない。コインはもはや石になりつつある。資本主義からポスト資本主義へ。そのためには何が求められるか、と著者はいう。
資本主義からポスト資本主義への指標となるのが、財政状況の急激な悪化である。これは日本だけの現象ではないが、とりわけ日本が最悪の状況にある。2020年段階で、日本の公的債務残高は対GDP比率で270.4%になっている。つまり、GDPの2.7倍、公的債務が積み上がっていることになる。アジア太平洋戦争の末期でも、公的債務残高はGDPの2倍だったから、それよりもはるかに高い割合だ。
しかし、国債をこれだけ発行しても、国債の利率が上がらないのは、いかに貯蓄(家計の金融資産と企業の資金余剰)が過剰になっているかにほかならない。
PB(基礎的財政収支)が均衡すれば、公的債務残高は減らないにしても、いま以上には増えなくなる。だが、それがいつになるかは、なかなか見通せない。
コロナ禍でも企業は設備投資を抑制し、手元流動性(手元資金)を増やしている。家計も同様で、2021年3月末の個人金融資産は過去最高の1945.8兆円となった。それが日本の財政をかろうじて支えている。
現在求められているのは、課税(とりわけ法人税課税、さらには消費税)によってPBを均衡させること、そのうえで格差・貧困問題を是正するため資産課税を強化することが求められる、と著者はいう。
日本の財政当局が恐れているのは、長期金利が上昇することである。
貿易収支がどうなっていくかも懸念材料だ。現在、日本の貿易黒字を支えているのは車と電気製品だといってよいが、電気製品の力は次第に衰え、自動車産業だけが頼みの綱になりつつある。これにたいし、石油価格の高騰が貿易収支を悪化させている。
2021年度の貿易収支は赤字となった。とはいえ経常収支が黒字を保っているのは、所得収支の黒字幅が貿易収支の赤字幅をいまのところ上回っているからだ。しかし、これからも原油価格は上昇する可能性があるので、貿易収支の赤字幅は拡大する恐れがある。経常収支が黒字のうちに、PBを均衡させていかないと、長期金利が上昇する可能性がある、と著者は懸念する。
現在、「石」と化している個人と企業の膨大な金融資産を動かさなくてはならない、と著者はいう。
世帯でいうと、2021年3月段階で、60−69歳の世帯の金融資産は平均で4985万円、70歳以上は4500万円前後、50−59歳は3000〜3500万円前後だという。もちろん、この数字は平均で、同じ年代でもばらつきがある。年金だけでほとんどじゅうぶん生活している人もいるし、少ない年金で生活に苦しんでいる人もいる。
なぜ、日本人はこれだけの金融資産を残しているのか。教育資金や結婚資金を含め、子どもに遺産を残すという動機も根強い。しかし、老後の生活資金、病気や不時の災害の備えというのがいちばん大きいという。
高齢者人口比率は2055年には36.7%になり、ピークを迎えると予想される。現在の高齢者の金融資産は使い切れない。そのため、それは遺産相続されて、次の世代の高齢者に引き継がれ、金融資産がそのまま「石化」していく可能性が強い、と著者はいう。
おカネは使ってこそ価値がある。相続税を強化(たとえば4000万円超に45%)して、資産を分配すべきだ。親子の関係を日本人全体に広げるという気持ちをもつことがだいじだ。そうすれば、保育園・幼稚園から大学まで無償化して、教育格差を縮めることができる。加えて、大学に行かない選択をした若者に一律500万円を支給するようにすればいいという。
国家がもっともだいじにしなければならないのは正義であり、公共の利益である。中間層が弱体化すると国家は崩壊する。救済こそが国家の役割である。「石」となっている金融資産は、ほんとうの富ではない、と著者はいう。
貧富の格差にともない社会秩序の安定性が失われようとしている。社会の安定化に、あり余る金融資産は寄与すべきである。
近代における所有権は、国家の正当性と結びついてきた。国家は所有権、すなわち「わたしのもの」を保証する仕組みを法的に整えていった。
国家は所有と自由を保護するからこそ、国家として認められる。それはさらに個人の「固有権」、すなわち自由権と社会権という固有の権利を国家が保障するという考え方へと発展していったという。
もちろん、人間は社会的動物として自然法を守らなければならない。人類の保全を目的とするのが自然法だ。
著者は、近代に生まれたロックに代表されるこうした考え方が、今後も継承されなくてはならないと考えている。
そうした観点からすれば、気候変動への対処や、公共善の実現、格差是正、権利侵害への補償は今後とも国家のなすべき義務なのである。
ケインズは「慈愛の義務」を果たさず「財産としての貨幣愛」だけを追求している人は半ば犯罪者だといったという。過剰な富(石と化した貨幣)は困窮者に移転してこそ生きた貨幣となる。そうした役割を果たせるのは国家だけだ、と著者は考えている。
現在の日本でいえば、法人企業利益への課税、消費税引き上げ、相続税の強化、高額所得者へのサーチャージがなされなければならない。そして、それらによって得られた30兆円前後の財源は、最低賃金の引き上げ、低年収世帯やひとり親世帯への支給、大学までの授業料無償化、芸術・文化振興予算、社会保障関連費の自然増などに回されるべきだという。
それらは単におカネの配分を意味するのではない。政治や経済は、善い社会(精神性の高い社会)をつくるための手段にすぎないのだ、と著者は強調する。
近代において、会社は法人格を有するようになり、「永遠の命を獲得した株式会社が利潤の蓄積である資本の所有者となった」。
だが21世紀になると、資金主義者による株式会社支配が露骨になると同時に、株式会社による資本蓄積がますます盛んになっている。そうした必要以上の富(石としての富)は抑制されねければならない、と著者はいう。
パンデミック下において、低所得国では絶対的貧困者が拡大するいっぽうで、先進国では少数のビリオネアの資産が膨張している。こうした状況は、どうみても善い社会の状態とは思えない。ビリオネアたちは少なくとも、パンデミック基金などをつくって、全世界の貧困者救済に寄与すべきではないか、と著者は提言する。
日本でも相対的貧困率の割合が(だいたい年間所得が200万円程度の家庭を想定すればいい)、1985年の12.0%から2018年の15.4%に増えている。なかでも、ひとり親世帯の子どもの貧困率が高い。2018年段階で、ひとり親世帯(とりわけ母子世帯)の子どもは二人に一人が貧困におちいっている。 2090万人の非正規労働者(雇用者全員の37.2%)の生活も苦しい。かれらにたいして、「日本株式会社」はけっして手を差し伸べようとはしていない。
企業の堕落は数多くの粉飾決算や不正行為にあらわれている。それは資本家や企業が貨幣愛に固執する結果である。それによって公共性が踏みにじられ、多くの固有権が侵害されている。
「日本においては、政治家、官僚そして企業経営者は品格がなく、『倫理的な力』が欠けている」。それにたいして、健全な権利感覚を取り戻すべきだ。
人間がつくりあげた秩序を常に正しい方向に是正するには、倫理的な力が求められる。モラル・サイエンスとしての経済を考えるには、倫理学、政治学も視野にいれなければならない。
「20世紀の主流派経済学は効率的な資源配分という名のもとに賃金、利子、利潤について決定してきたが、21世紀の経済学は、『価値判断』を捨象することなく『社会的公正』の観点から分配問題として考え直す必要がある」
かつて、ケインズはこう書いたという。
〈私としては、資本主義は賢明に管理されるかぎり、おそらく、経済的目的を達するうえで、今まで見られたどのような代替的システムにもまして効率的なものにすることができるが、本質的には、幾多の点できわめて好ましくないものであると考えている。〉
著者も資本主義は賢明に管理されていないとみている。貨幣幻想がいまもこの世をおおっている。貨幣愛にとりつかれたビリオネアはあたかも「不死の幻想」を追い求めているかのようだ。
金銭欲ははかない。ゼロ金利社会においては、貯蓄、すなわち我慢する必要もなくなった。
「ゼロ金利は最高の生活水準に到達したことを意味する」。これからは精神生活をだいじにし、「よりゆっくり、より近く、より寛容に」を目標にすべきだ。これからの社会は「成長なくして、分配あり」なのである。
21世紀にめざすべき方向は「堕落してきた人間の精神の向上」である。そして「自己の精神を向上させるのは芸術である」。
近代において生活水準はたしかに向上した。しかし、それに伴って人の精神は失われた。豊かな精神を取り戻すには、自由時間を増やすことが必要だ。
ゼロ金利になって、明日のことなど心配しなくてもいい社会が生まれようとしているいま、毎日を楽しみながら生きる時代が到来しつつある。それが美や芸術、文化に結びつくことはまちがいない、と著者はいう。自然を力ずくで支配するイデオロギーとも訣別しなければならない。
21世紀は資本よりも「芸術の世紀」となるだろう、と著者はいう。
資本主義を打倒せよという主張より、はるかに説得力がある。それはやろうと思えば明日からでも着手できる政治課題だからである。
水野和夫『次なる100年』を読む(5) [本]
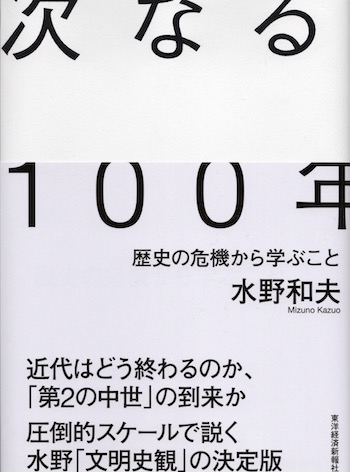
第3章「利子と資本」にはいる。200ページあるが、ごく簡単にまとめてみよう。
日本ではゼロ金利とROE(自己資本利益率)が乖離している。つまり、金利はゼロなのに企業の利潤率は高まっている。
利子の源泉が利潤だとすれば、ふつう利潤率と利子率は連動する。ところが、それが乖離しているのはなぜか。
現在、国債利回りは米国だけがプラスで、日本、ドイツ、フランスはマイナスとなっている。そのほうが、米国に過剰マネーが集まりやすいからだ。
ゼロ金利時代はゼロ成長時代でもある。先進国では、この状態が長くつづくとみられている。
日本では1998年以降、ゼロ金利のもと企業がつねに資金余剰(貯蓄余剰)となり、家計もまた資金余剰(貯蓄余剰)となって、それを政府(大量の国債)と海外(米国の債券市場)が吸い上げるかたちになっている。
いったい何がおきているのだろう。
米国の所得収支が大幅黒字を保っているのは、対外債権の収益率が対外債務の支払い利子率を上回っている(利回りギャップがある)からである。日本の株式市場にたいする外国人株主比率は1990年以降高まり、2020年の時点で20%を超えている。かれらはROE革命の名のもと、企業により高い配当率を求めるようになっている。
グローバリゼーションは植民地主義の新バージョンだ、と著者はいう。ウォール街は世界じゅうから集めた資本をあらゆる地域に投資し、ウォール街に利潤を戻す。中心のウォール街から遠ざかれば遠ざかるほど、成果にあずかることができない仕組みだ。これは一種の暴力装置だ。
いっぽう、日本ではどうか。
〈1990年代前半に急激な円高が進行したにもかかわらず、日本の貿易黒字が減少しなかったのは、実質賃金の下落などによって個人が消費支出を切り詰め、輸出を含めた投資を増やしたからである。日本は供給力を増やし、81年以降経常収支黒字を維持してきた。その結果、対外純資産が世界1位となり、その一部が米国債投資に向かう。国際関係における米国の「例外」は、日本の例外(国内のマイナス金利)によって支えられている。それは、非正規雇用や賃金下落そして預金金利の低下によって中産階級の没落という「反近代」的現象をもたらしている。〉
米国の過剰消費を日本やドイツの過小消費が支えているといってもよいだろう。
日本では中産階級が没落し、「閉ざされた選抜社会」が生まれようとしている、と著者はいう。巨大都市と小都市、地方のあいだ、正規労働者と非正規労働者のあいだに「深い溝」が生じている。
日本のメガロポリス化は1960年代半ばからはじまった。人口は都市に集中した。しかし、経済文明はいっこうに進歩していない。
ほんらい機械化が進むと、生産性が向上し、自由時間が生みだされるはずである。しかし、日本の一般労働者(正規労働者)の年間労働時間は1990年代以降、ほぼ横ばいで、ドイツ、フランス、イギリスより、はるかに高いままだ。
年収200万円以下ではたらく非正規労働者が増えている。それに比例して、中間層の割合が減っている。日本の賃金は名目、実質とも下落傾向がつづいている。
21世紀の日本では、企業が不釣り合いな利益を得ている、と著者はいう。2001年から19年にかけ、労働生産性は年平均0.61%上昇した。しかし、この期間、実質賃金は年平均0.6%減少した。これにたいし、法人企業の当期純利益は2.1倍に増加した。利潤率がますます高まるなかで、利子率はゼロとなった。
1870年代半ばから1970年代半ばにかけての1世紀は特別な時代だった。それは電気・化学・自動車の時代で、一人あたりの実質GDPが劇的に増え、生活水準と労働生産性が一気に上昇したものだ。
しかし、その後のコンピューターの時代は、かつてほどの経済成長をもたらさず、むしろ長期停滞へとつながっている。日本では実質経済成長率がほとんどゼロとなるなか、労働者の実質賃金は減っている。それなのに、大企業、中堅企業の利潤率は高まり、内部留保も増加するという現象が生じている。
利子率は企業利潤率と同じ水準で推移するのが常態だが、21世紀になって、利子率ゼロの例外状態がつづいている。このことは、企業が資本を貸与する銀行、ひいては預金者に相応の利子を払っていないことを意味している、と著者はいう。
それだけではない。
「利潤率が著しく上昇している背景には、賃下げと預金利子ゼロによって資産形成手段を奪われ、壊滅的な打撃を被って中間層からの没落の憂き目にあっている人たちの存在がある」
グローバリゼーションによって、国内での投資機会が少なくなり、海外投資が不可欠となった企業は、海外投資によって企業利益を確保している。いっぽう、国内での純投資はほぼゼロとなるので、経済はゼロ成長、ゼロインフレとなる。
「日本の長期停滞は過剰貯蓄による需要不足ではなく、過剰投資による供給力超過に原因がある」と著者はいう。
そのことは衣食住をみればよくわかる。アパレル産業では毎年10〜15億着が売れ残り、その多くが廃棄されている。日本の食品ロスは2016年推計で646トン(1人50キロ)。住宅の空き家は2018年時点で849万戸。セブンイレブンの店舗数は2018年段階で2万876店だったが、すでに減少に転じている。
設備能力の過剰性は衣料やコンビニだけではなく、日本のあらゆる分野におよんでいる。さらに、実物資産は増えていないのに、金融資産だけが増えている。
通常、利子と利潤は同じ方向に連動する。利子は利潤からしか生まれない。利潤が増えれば利子も増え、利潤が減れば利子も減る。ところが、現在おきているのは、これとは矛盾する減少だ。
利子率はゼロなのに企業の利潤は増えている。成長率はゼロなのに企業の利潤はしっかりと確保されている。
そうした奇妙な現象がつづいているのは、人件費の占める割合が減り、その分、営業利益が増大しているからである。
企業が利益を確保するには、まず人件費を削ればよい。1998年に1173万人だった非正規社員は、2020年には2090万人に増えた。そのため、1998年以降、労働生産性は上昇しているのに、実質賃金は減少している。その分、企業の利潤が増えている。
それを後押しするのが、株主重視の経営だ。しかも借入金利(利息)の低さが企業に一方的な利益をもたらしている。
こうしてゼロ成長、ゼロ金利のもと、実質賃金は低下しているのに、企業利潤と企業の内部留保だけが増えるという現象が生じている。
1999年度から2020年度までの22年間に累積した内部留保金は、154.7兆円にのぼる。それは働く人への「未払い賃金」と預金者に利子として払われなかった預かり金にほかならない、と著者はいう。
グローバルな(米国の)基準に応じたROE(自己資本利益率)と株主重視の経営が、人件費削減を中心としたリストラを継続的に促進させている。その流れは大企業から中小企業へとおよんでいるのだ。
内閣府の調査によると、6割強の人が「物質的にある程度豊かになったので、これからは心の豊かさやゆとりのある生活をすることに重きをおきたい」と答えている。さらに、6割弱の人が貯蓄や投資など将来に備えるより、これからは「毎日の生活を充実させて楽しむ」と答えている。
だが、それはあくまでも希望であって、じっさいにはほとんどの人が苦労とがまんを強いられている、と著者はいう。この30年間、国民の生活はいっこうによくなっていない。
バブル崩壊後の1990年代以降、日本経済はすでに「静態」、すなわち定常状態にはいっている。利子率はゼロで、毎期、生産、分配、消費がコンスタントに循環する単純再生産の状態にある。
内閣府の世論調査でも、今後の生活がいまと同じようなものと答える人が6割強をしめている。現在の生活が去年と比べて「同じようなもの」と答えた人も2019年には80%にのぼった。
将来の不安は1位が「老後の生活設計」(56.7%)、2位が「自分の健康」(54.2%)、3位が「家族の健康」(42.4%)、4位が「今後の収入や資産について」(42.1%)となっている。
大きな不安をかかえていても将来を達観する人が多く、日本では「足るを知る」生活態度が定着しつつある、と著者はいう。つまり、保守的な傾向が強まっているわけだ。仕事はそつなくこなし、「心の豊かさやゆとりある生活」をしたいと思う人が増えている。
しかし、そこには虚偽の現実が隠されている。
いくら会社が利益を出しても賃金は下がっている。企業では、まず利益が想定されて、そえから人件費が決められるようになる。非正規労働者の解雇や派遣切りがちゅうちょなくおこなわれる。利益追求のためには手段を選ばないという考え方が台頭している。うそも平気につく。
21世紀にはいって、理性は敗北を重ねている、と著者はいう。その結果は、身分社会への回帰だ。中産階級を生みだした20世紀は1977年に終わった。それ以降、不平等度をはかるジニ係数が増加に転じたからだ。現在の資本主義社会は18世紀以上に貨幣欲を原理として動く社会になっているという。
だとするなら、次なる100年はどこに向かうべきか。本書の結論を読んでみよう。
水野和夫『次なる100年』を読む(4) [本]
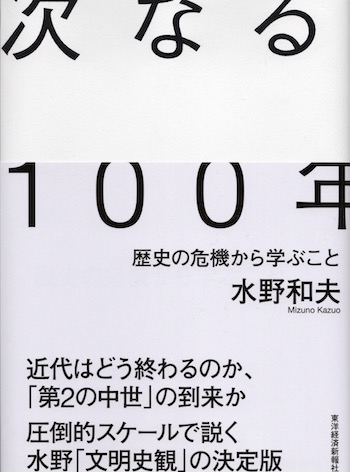
この本はけっして読みやすいとはいえない。歴史と理論、現状分析に加え、おびただしい引用で、頭がぐちゃぐちゃになる。ただでさえ、頭が回らない当方にとっては、何がなんだかわからなくなってしまう。それでも、全体としてはどうやら資本主義の生成と終焉が語られていることが、ぼんやりとながらわかってくる。
昔習った杵柄(きねづか)でいうと、資本主義が終わったら、社会主義だということになりそうだが、そうではないらしい。少なくとも昔ながらの社会主義ははなからしりぞけられている。新しい資本主義というのでもない。そもそも資本主義は終わったのだから。だとすれば、次はどうなるのかというわけだ。
先のことはだれにもわからない。それでも次はどんな時代になるのか、いやなりうるのかを知りたいと思って、この本を少しずつ読んでいる。
きょうは第2章の「グローバリゼーションと帝国──グローバリゼーションは資本帝国建設のためのイデオロギーである」を読んでいる。この章だけで160ページあるが、ポイントだけ紹介してみる。
近代を動かしてきたのは、はてしなく富をつくりだそうとする資本主義システムである。とりわけ19世紀前後からはじまる産業資本主義は、大きな資本をもとに、地下資源の化石燃料をエネルギー化し、機械と結びつけることで商品供給力を増大させてきた。
資本にはもともとグローバリゼーションをめざす傾向がある、と著者は指摘する。中世の13世紀に資本主義が誕生して以来、いやもっと古くから、資本家(商人)は国境にとらわれず経済活動をしてきた。
グローバリゼーションという概念が用いられるようになるのは1980年代からだが、グローバリゼーションの起源は、近代以前の13世紀にさかのぼるという。そのころからフィレンツェの金融業や羊毛組合は、ヨーロッパ全土にわたり、グローバルな活動をはじめていた。15世紀半ばになると、出版業のなかにもすでにグローバル企業が登場している。
16世紀後半、オランダでは近代経済が幕を開ける。オランダはイギリスに先駆けて喜望峰を経由する遠洋航海ルートを切り開き、東アジアに進出した。しかし、やがてイギリスが海を制覇する。
資本の本質はグローバルであり、資本が領土国家の規制から逃れようとするのはとうぜんだ、と著者はいう。
近代は進歩の思想にいろどられている。その信条は変化のスピードと広がりだ。すなわち「より速く、より遠く」が近代のスローガンとなる。
著者によると、そうした近代が生まれたのは、宗教戦争に終止符が打たれた1648年のウェストファリア条約以降である。だが、資本主義はすでに13世紀に生まれていた。13世紀に教会は利子と利潤を認めるようになった。そして、商人たちは遠隔交易を開始し、親方に雇われて働く人も増えていく。
14世紀には「時は金なり」の金言が定着し、富の蓄積も公認されるようになる。節約が美徳となり、資本の「蒐集」もはじまる。機械が考案されるのもこのころだ。
西ヨーロッパはすでに11世紀から貨幣の時代にはいっていた。13世紀には手形や小切手もあらわれ、資本が誕生する。16世紀末には近代国家が登場し、国境を越える貨幣を管理するようになった。
貨幣経済への急速な移行は、東方貿易とスペインのアメリカ侵略に結びついていた。貨幣の時代とともに都市化が進行する。都市市民はおカネがあれば、市場を通じて必要なものは何でも手に入るようになった。都市が帝国から独立していく。
1534年、コペルニクスが科学の時代を開き、近代がはじまる。時間が神のものから人間のものになった。そして、貨幣が世俗の神となる。
都市が資本を集め、その富で文明を築くようになる。ヨーロッパ文明はグローバル化し、資本帝国をめざすようになる。それはかつてのローマ帝国の夢の再現であると同時に、資本に裏づけられた新しい都市文明でもあった。
消費と交易が盛んになればなるほど、貨幣がますます必要になる。新しい金貨や銀貨が発行された。自由都市では封建貴族に代わって商人が行政を握るようになり、「商人の、商人による、商人のための統治」がおこなわれた。
資本主義の原型はすでに13世紀に誕生していた。16世紀になって、資本主義が近代を呼びこんだ。資本主義のほうが近代より歴史が長い、と著者はいう。
資本主義にはもともと暴力性が内在し、わずかのすきも見逃さず、暴走も辞さない。貨幣経済は中世の伝統的精神性と融合することはなかった。そのため、中世に引導を渡し、近代を導き入れる。資本は貧者を生みだしながら膨張していく。
近代は機械だ、と著者はいう。市場も国家も機械である。人はメカニズムのもとで動く。技術と経済が合体し、近代システムが確立する。技術進歩が崇拝され、機械教のもと経済成長こそが神となる。
そうしたなかで、資本は世界市場の創造に向けて動く。そのイデオロギーがグローバリゼーションだ。
「ヒト、モノ、カネの国境を自由に越える移動」がグローバリゼーションだとすれば、それは最近になってはじまったわけではなく、13世紀から存在したといえる。しかし、20世紀末になって、新自由主義のイデオロギーが広がるにつれて、それはより活発化してきた。
グローバリゼーションに明確な定義はない。だが、そこには明確なイデオロギーがある、と著者はいう。
市場の自由化とグローバルな統合。技術進歩のもたらす結果。民主主義の拡大。すべての人の利益。そして、その過程は不可避で非可逆的だという。
こうした大宣伝によって、21世紀にはいると、ほとんどだれもが、グローバリゼーションを善いものと信じるようになった。
だが、その矢先、2008年にリーマンショックがおき、2011年にはギリシア危機が発生した。グローバリゼーションは人びとの生活水準を上昇させるどころか、サブプライム層を路頭に迷わせることになった。
グローバリゼーションの本質が露わになった。
「グローバリゼーションはその推進者、米財務省、世界銀行、IMF、そしてウォール街にとってバブルの生成と崩壊を繰り返す資本を成長させる戦略なのである」
にもかかわらず日本の政策当局者は、相変わらず米国の主導するグローバリゼーションを善だと信じていると、著者はいう。
グローバリゼーションの代表企業がGAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)だ。そして、現在グローバリゼーションを主導しているのがウォール街である。GAFAは国家より巨大な権力をもちはじめており、脱税すれすれの節税をおこなっている、その株式時価総額は日本の名目GDP530兆円を上回る。「GAFA問題とは民主主義に対する挑戦なのである」と著者はいう。つまり、資本帝国による支配だ。
バブルはグローバリゼーションによってつくられる。バブルははじけさせるためにつくられる、と著者はいう。
1970年以降、実物経済にたいし金融経済が膨張しはじめた。米国の「帝国」化を支えているのは、日本の過剰マネーである。
グローバリゼーションによって、世界のマネーは米国に集中し、そのマネーは資本の自由化によって新興国に流れている。対外債権が過剰になると、債務が返済できない国がでてくる。国内でも同じことが生じる(その一例がリーマンショックだ)。
「グローバリゼーションとは、IMFを通じて、米国のワシントン・コンセンサスが世界に伝播し、米国が帝国化していくプロセスそのものである」
米国は21世紀の帝国をめざしている。そして、現在、新たな帝国をめざす中国との戦いがはじまっている、と著者はいう。
経済面からみれば、21世紀の帝国の条件は、世界じゅうからマネーを集め、世界最大の債権国として振る舞えるようになることだ。それによって債権国は債務国を支配することができる。
1991年のソ連崩壊によって、米国は世界帝国の夢を実現しえたかのように思えた。だが、その後のイスラム世界やテロとの戦いによって、その夢はたちまちついえ、2013年にオバマ大統領は「米国は世界の警察官ではない」と宣言するにいたった。
それでも、米国は帝国であることをあきらめたわけではなかった。台頭する中国との戦いがはじまった。
米国は世界最大の債権国であることを通じて、帝国の地位を保とうとしている(日本のマネーがそれを支えている)。恐れるのは現在世界第4位の純債権国である中国が、のしあがってくることだ。
米国が日本を抜いて世界最大の債権国に返り咲いたのは2010年である。
とはいえ、債権・債務関係は複雑である。米国は世界最大の債権国であるにもかかわらず、対中国の所得収支は大幅な赤字となっている。これにたいし、中国は世界4位の債権国であるにもかかわらず、全体の所得収支は世界最大の赤字をだしている。
このことは、中国は米国には債権者だが、ヨーロッパや日本にたいしては債務者であることを意味している。このあたり、国際的な債権・債務関係は入り組んでいて、じつにややこしい。
米国は日本、ヨーロッパ、中国に支えられて金融帝国としての位置を保ち、いっぽう中国は米国、日本、ヨーロッパに支えられて貿易帝国になったといえるだろう。
このああたりの議論は複雑をきわめていて、なかなか理解できないのだが、著者がこれから30年は帝国支配をめぐって、米国と中国の対立が激化すると予想していることはまちがいない。
しかし、著者は「『中国の夢』の一つである米国を総合国力で超えるという『興国の夢』は夢のまた夢である」と断言する。
中国の対外債務の支払い利子率はいちじるしく高く、その観点からみると「グローバリゼーションの勝利者は米国であり、中国が敗者となる」。なぜなら「中国は対外取引において対外資産からは低い収益率を受け取る一方で、対外資産については高い支払い利子率を払っている」からである。
それでも米国の危機感は強い。「米国の危機感は米国がこのまま手をこまねいて中国の台頭を許すと21世紀の半ばには帝国の座を降りなければならないかもしれないという点にある」。そのため自由貿易の原則を破ってでも、対中貿易赤字の増大を抑えようとしている。
ファーウェイをめぐる米中の対立は妥協の余地がなく、いつまでもつづくだろう、と著者はみる。それはサイバー空間だけではなく、リアル空間でも同じである。
帝国はつねに「過剰のはけ口」を求める。21世紀においては、グローバリゼーションというイデオロギーと、情報・通信というテクノロジーが帝国の暴力装置をかたちづくっているという。
中国が帝国をめざしているのは、やはり「過剰のはけ口」を求めているからだ。米国のグローバリゼーションに対応するのが、中国の「一帯一路」計画だ。
米国の財政赤字は減りそうにないし、貿易・経常収支赤字も縮小に転じる気配はない。それに応じて、日本をはじめとする過剰マネーが米国に流入し、ニューヨークダウを押し上げている。過剰マネーは外国企業の買収、中南米、EU、イギリスなどへの投資に向かう。こうして過大な貿易赤字をかかえながらも、米国は全世界の債権者として引きつづき君臨する。だが、そのパワーも次第に落ちはじめている、と著者は指摘する。
話はさらにつづく。
水野和夫『次なる100年』を読む(3) [本]
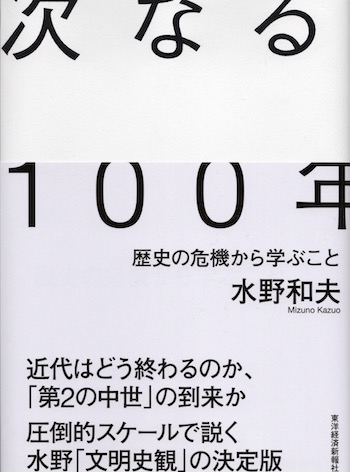
ゼロ金利、ゼロ成長、ゼロインフレは近代化の帰結であり、近代システムと資本主義システムは賞味期限が切れている、と著者はいう。長期的にみれば、たしかにそうかもしれない。
経済学は本来、救済の学問だとも著者はいう。人びとは救済を目的として貯蓄し、投資し、それによってよりよい世界を創造しようとしてきた。だが、それはしばしば過剰な蒐集と歪みを生んだ。
蒐集には上限がない。蒐集の結果生じた資本の過剰性はかならずバブルを引き起こし、戦争に向けての環境をつくりだす。
ゼロ金利はほんらい資本がじゅうぶんすぎるほど蓄積されたことを示す指標である。しかし、そうなったにもかかわらず、資本主義の悪弊、すなわち恐慌や貧困、富の遍在はなくなっていない。
「ゼロ金利が意味することは成長で富を『蒐集』する近代史が終わって、成長に依存しないシステムを構築しなければ、世界の秩序が安定しないということである」と著者はいう。
いまは「歴史の危機」にある。
著者にいわせれば、日銀による異次元金融緩和は、歴史の流れに抗う動き以外のなにものでもない。ゼロ金利という「例外状況」のなか、現在、日銀は国債コレクターの役割を果たすようになっている。預金の国債化が進んでいる。タンス預金を選択する家計も増えている。
ラ・フォンテーヌは財産は有効に使わなければ「石」と等しいと警告したが、日本が陥っているのは、そうした状況だ、と著者はいう。
利子率ゼロというのは、システムを変えろという重要なサインである。にもかかわらず、新自由主義者は近代をなにがなんでも維持し、成長を取り戻そうとしている。それは歴史の方向に逆らおうとする努力であって、いずれ失敗する運命にある。
現在、進行している動きを、著者はバブルの生成と崩壊の過程と見ている。それは1995年のITバブルからはじまり、2021年にいたる長期的なバブルの流れであって、これからおこる崩壊過程は長期にわたるものと考えている。
いまや資本が国家を超越しようとしていることはGAFAなどをみれば明らかである。資本の共同体は、もはや愛国心や従業員にたいする同志愛など関係ない。
日本ではいまや非正規雇用の割合が1994年の20.3%から2020年の37.2%に拡大した。賃金下落の原因は、非正規雇用制度の導入にある。
1997年以降、労働生産性はゆるやかに上昇しているにもかかわらず、実質賃金は下がりつづけている。そして、賃下げと株高が連動している。
〈近代は人間を中心に据えた社会として出発したが、1970年代半ばあたりから、グローバリゼーションが世界の潮流となって中間層が没落し始めた。その裏返しの現象として上位1%あるいは0.1%に富が集中するようになった。上位1%の富裕層が中心となる階級社会をめざすのか、多数の人間(いわゆる中間層)なのかが問い直されている。〉
主権国家と自由貿易、国際的な共通制度が、これまで近代的な世界システムを支えてきた。しかし、米国でのトランプ政権の誕生は、こうした近代システムが崩壊していく象徴となった。
世界の協調性は失われ、各国、各地域がそれぞれの利益を求めて、独自の道を歩もうとする傾向が強くなった。
米国では中産階級の崩壊プロセスにはいった。貧困が次世代に受け継がれ、再生産されようとしている。米国だけではない。世界各地で、多くの人が希望を失い、苦しんでいる。
1970年代は米ソによる世界支配が揺らぎはじめた時代だった。そのあと米国は世界の中心ではなくなり、ソ連は解体する。
著者は「長い16世紀」(1450年〜1650年)と、いまもつづいている「長い21世紀」(1971年〜?)とを比較しながら、「長い21世紀」──それは資本と貨幣の時代だった──も危機の世紀であって、新しい秩序形成に向かう過渡期にあることを立証しようとしている。
その「長い21世紀」のはじまりは1971年のニクソンショックだった。「帝国」の時代は終わり、そのあと、現在の混乱がつづいている。
「20世紀が『米国の世紀』だとすれば、21世紀は米国にとって歴史の危機である」
それを象徴するのが、あらゆるものの狂ったような金融化と「絶望死」の増加だ。米国を手本にしてきた日本でも、いまや「こころの内戦」と「精神のデフレ」は進んでいると、著者はいう。
21世紀でも現実に存在しているシステムは近代システムであり、資本主義システムである。それは機能不全に陥っている。だが、次のシステムの姿、かたちはまだみえていない。
21世紀の現在、世界的にみれば絶対的貧困者の数は減りつつある。しかし、低所得国やサハラ以南の諸国・地域では、むしろ貧困化が一段と進行している。
世界の富は上位1%の富者に集中するいっぽう、先進国では中間層が没落している。こうしたことをみても、資本主義の本性が邪悪に満ちていることがわかる、と著者はいう。
いまは、世界的にみても、国内的にみても、社会が二つに割れ、超えがたい「深い溝」ができている状態だ。これが、市場こそ神だとした新自由主義が招いた結末なのだ。
現在の「歴史の危機」は深刻だ、と著者はいう。
かつてケインズは、100年後のゼロ金利の時代には経済問題はほとんど解決され、貨幣愛を持つのは変わった人だけで、富を追い求める人もすくなくなるとと予想した。だが、そうした状況はやってこず、むしろまるで逆の状況が生じている。
戦争と社会の分断がつづいている。それに輪をかけているのが、かずかずの茶番劇だ。
「長い16世紀」と1971年以降に共通しているのは、歴史的な超低金利だ。このことは貨幣が魅力的な実物投資先を失ったことを意味している。投資が利益を生まないとなれば、資本家は労働の規制緩和とバーチャル市場での利益によって稼ごうとする。リスクをとって、大儲けをたくらむ冒険家もでてくる。
20世紀末以降、原油価格が急騰し、それにともない低所得者者の生活がおびやかされるようになった。日本では実質賃金は1996年をピークとして、その後、下がりつづけている。
社会の二極化が生じている。そのいっぽうで、社会秩序が乱れ、犯罪も増加している。その典型が世界各地で発生するテロ行為である。
「歴史の危機」の時代においては、真理はしばしば脇におかれ、つくられた「事実」があたかも真実であるかのように流布される。
著者はいう。
〈近代における最も重要な概念は「資本」であり、この資本が常態において生活水準をもっとよくしてくれるのであり、例外状態においては救済してくれるとの前提、あるいは信仰があったからこそ、これまで資本主義は「穢いはきれい」だと割り切って支持してきたのである。その信仰が21世紀にはいって音を立てて崩れ始めた。〉
だとすれば、われわれはどこに向かっているのだろう。
水野和夫『次なる100年』を読む(2) [本]
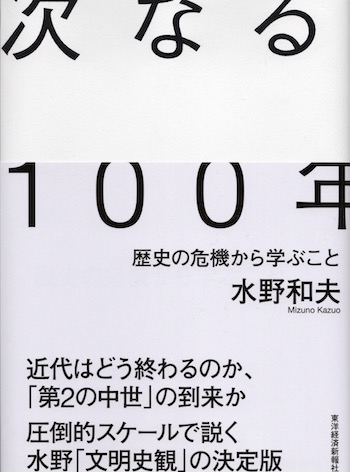
ゼロ金利は資本主義にとって「例外状況」だという。
そんな例外状況が、いま先進国を支配している。
現在、日本では実質マイナス金利のなかで、企業のROE(自己資本利益率)は、2017年度には8.7%まで上昇している。異常な低金利のもとで、バブルが生じているとみてよい。
しかし、金融緩和自体によるインフレは現在のところ生じていない(2022年の円安原油高がインフレをもたらしそうではあるが)。日銀はゼロ金利政策を当面、転換しないとしている。
2011年夏の段階で、一人あたり実質賃金は1997年にくらべ、15.1%も下落している。景気回復がつづいているのもかかわらず、生活水準は下がりつづけている。金融資産をもたない世帯の割合も高くなっている。そのいっぽうで企業利益の増加にともなって、資本家や経営者は年々富を増やしている。これは日本だけの現象ではなく、世界的な現象といえる。貧富の格差が広がっている。
資本主義がはじまったのは13世紀ごろだ、と著者はいう。
このころ商人のあいだに富の蓄積をめざす旺盛な利潤追求の精神が生まれた。それまでの農業中心の社会は、こうした利潤観念とは無縁だった。農業社会から商業社会への転換がはじまる。
利潤を確保するためには、「より遠く、より速く、より合理的に」行動しなくてはならなかった。
イタリアの商人たちはレヴァント(現在のシリアあたり)に進出し、イスラムとの交易をはじめた。その目的は東方の胡椒を得るためだったという。
資本とは利息のつくカネにほかならなかった。そこから利子という概念も生まれてくる。「利子とは、現在の貨幣の価値と将来の貨幣との間に存在する差異の別名」にほかならない。
このころ、教会も利子を公認するようになった。節約、預金、蓄財、労働は教会にとっても、福音書にかなった生き方であり、そこから利子の考え方が容認されるようになった。
16世紀から17世紀にかけては、大きな転換があった。資本家第一号は海賊のフランシス・ドレイクだ、と著者はいう。ドレイクがスペインから略奪した財宝をイギリスに持ち帰り、そこから資本の膨張がはじまる。
労働力の搾取をはじめとして、暴力的な資本蓄積こそが、資本主義の原動力だったという。そのころイギリスの東インド会社はインド支配を強めようとしていた。
資本を「蒐集」しようという衝動はこの時代にさらに高まる。科学革命が資本主義のもとでの合理的経済人の行動を後押しした。
さらに18世紀から19世紀にかけての産業革命がある。とりわけ19世紀半ばの石油の発見は、機械による効率化と連動して、労働生産性を飛躍的に高めた。
こうして13世紀以降、資本主義は国家とともに段階的に発展していく。経済的合理性を備えた近代的市民も登場した。
著者が資本主義の起源にこだわるのは理由がある。
〈資本主義の起源を求めないことには、資本主義の先行き、さらにはその終わりが決められない。資本主義の原型の誕生は「利子」の公認にあるとすれば、ゼロ金利はその終焉を意味していることになる。21世紀にゼロ金利が長期化している事実と利子論から導かれる結論を考えれば、資本主義はすでに終わっていることになる。〉
すなわち、利子こそが資本主義の指標である。その意味については、これから考察されることになるだろう。
それにしても、現在も「海賊資本主義」が世界をおおっていることを著者は指摘する。油断も隙もならないGAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)は現代の海賊だという。自然災害や金融危機、戦争などのショックに便乗して荒稼ぎする企業は後を絶たない。IT技術のつくる「電子・金融空間」(サイバー空間)が人びとの欲望を吸い取っていく。
〈経済活動が生み出す雇用と所得は実物投資空間、具体的には土地と密接に結びついていたが、「電子・金融空間」の創設がそれを断ち切った。13世紀半ばに資本と利子の概念が誕生して以来、資本の増強は雇用を増やし生活水準を向上させたが、ショック・ドクトリンは資本と雇用(市民)のリンクを断ち切ってしまった。〉
危機や幻惑をつくりだし、混乱に乗じて荒稼ぎする資本主義のやり方は16世紀も21世紀も変わらない。21世紀においては、それはますますグローバル化している。アメリカでは新自由主義の導入とともに、上位1%の人に富が集中し、下位50%の人の生活は低下するようになった。
金利が公認された「中世の秋」とゼロ金利の「近代の秋」を著者は比較する。
中世の秋は中世が終わりに向かい、都市化と資本主義が幕を開ける時代だ。
それにたいし、近代の秋においては、まだ新しい兆候はみられない。資本主義がますます猖獗(しょうけつ)をきわめ、世の中はいまだに身分制が大手を振っているようにみえる。
資本主義ははたして終わろうとしているのか。
「新しい時代の始まりが古い時代の終わりに先行しないかぎり、新しい時代は到来しない」。そのような新しい芽がどこにあるのかを、著者は探ろうとしている。
事実上のゼロ金利政策が四半世紀もつづいていることが、ポスト近代の始まりだ、と著者はいう。政府・日銀、財界は成長戦略と異次元金融緩和によって近代を維持しようとしているが、それはうまく行くはずがない。
海賊資本主義が跋扈(ばっこ)している。企業は節税に励み、できるだけ利益を確保しようと必死だ。そんななか労働分配率が低下し、格差が広がって、社会のモラルも失われようとしている。
まさに現在は「歴史の危機」にある、と著者はいう。
「ゼロ金利で『成長の時代は終わっている』にもかかわらず、それを取り戻そうとして日本政府はあらゆる政策を総動員しているが、それはせいぜい『近代の秋』を延長することにしかならない」
だとすれば、次なる100年はどういう時代になるのか。そのことを著者は問おうとしている。
水野和夫『次なる100年』 を読む(1) [本]
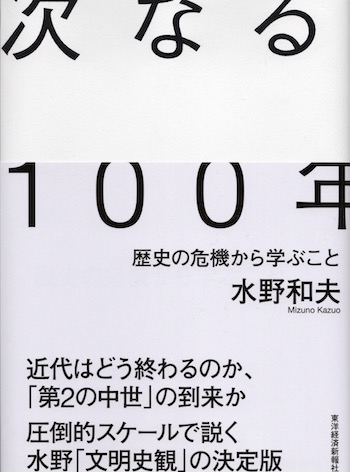
いずれにせよ暇なのだが、死ぬまでに吉本隆明の『ハイ・イメージ論』を読んでおきたいと意気込んで読みはじめたものの、2巻の宮沢賢治論のあたりで、挫折。そのうちまた挑戦してみます。つづいて、重田園江の『ホモ・エコノミクス』を読んだが、どうもピンとこなかった。中身はたいしたことがないような気がするが、ほんとうは深いのかもしれない。しかし、そもそもぼくのようなロートルの頭が中身についていけない。時代に取り残されてしまった。
気を取り直して、水野和夫の本に挑戦してみることにした。例によって、これも暇なじいさんの徘徊である。
大著である。注や索引を含めると900ページをはるかに超える。だから、のんびりと読むことにする。「はじめに」と序章、終章があり、全3章の構成だ。各章の目次は、こんな感じ。
序 章 「長い16世紀」と「長い21世紀」
第1章 ゼロ金利と「蒐集」
第2章 グローバリゼーションと帝国
第3章 利子と資本
終 章 「次なる100年」はどこに向かうのか?
目次だけではなかなかイメージがわいてこないけれど、資本主義500年(資本主義が13世紀からはじまったとすれば800年)の歴史をふり返りながら、21世紀がどんな時代になるかを想像してみるという壮大な構えをとっていることが何となくわかる。
まだ読みはじめたばかりだ。最後まで読めるかどうか。もはや時代についていけないぼくにとっては、よくわからない部分も多い。
まずは「はじめに」だ。
近代社会の原則は「私的な利益」の追求だ、と著者は書いている。神ではなく、資本が社会の中心となった。「利益追求は資本蓄積を促し今日よりも明日の生活がよくなることを人々は実感した」。だが、その時代は終わりつつある。
アメリカではこの50年来、平均的労働者の実質所得は増えていない。これは半世紀にわたって生活水準が上がっていないことを意味する。それは日本だって同じだ。近代と資本主義が終わろうとしている、と著者はいう。
その象徴がゼロ金利だという。ゼロ金利とは、いまがもっとも豊かで、これ以上豊かになることはないというメッセージである。成長の時代はもはや終わった。「より遠く、より速く、より合理的に」の時代は終わった。これからどう生きていくかが問われている。
「蒐集」(しゅうしゅう、コレクション)という概念が多用されている。世界史とは「蒐集」の歴史だという。その代表が資本主義だ。資本主義の主要目標は、おカネを蒐集することに尽きていた。
著者によれば、いまはおカネの過度の蒐集がゼロ金利を招き、ひいては資本主義の死を招来しようとしているということになる。
歴史の危機がはじまっている。
〈「歴史の危機」とは「人間の堕落」であるといえる。世界の富が集中する一方で、テロが横行する21世紀は「長い16世紀」と同様に「歴史の危機」なのである。「堕落」と「自由」は紙一重である。……1970年代以降、新自由主義が台頭し、1990年代に入ると資本の「堕落」が顕著となっている。〉
その危機を脱するために、米国はグローバリゼーションによって債権国の位置を保とうとしてきた。いっぽう、中国は新たな世界帝国に踊りでようとして、いまは米中間の冷戦が顕著になってきたという。
資本主義がフル稼働するようになったのは産業革命以降だった。産業革命の特質は、人間が自然エネルギーに頼らなくなり、地下の化石燃料に全面的に依存するようになったことだ、と著者はいう。
ITを含め機械は地下資源エネルギーを大量消費することによって、その威力を発揮する。機械によって解放された生産力は膨大だ。だが、いまや飽和状態になった需要と、エネルギー価格の上昇によって、資本主義はその勢いを失いつつある。
「これ以上膨張できない限界に達してしまった21世紀は『より近く、よりゆっくり、より寛容に』を基本原理としたシステムになっていかざるをえないであろう」と、著者は予測する。それは、これまでの「より遠く、より速く、より合理的に」という時代からの転換を意味する。
平成はけっして「敗北の時代」ではなかった。むしろ、人類に転換を促す時代のはじまりだった、と著者はとらえている。
本書の構成についての説明を聞いてみよう。
序章では、例外と常態が逆転していることが述べられる。すなわち歴史の例外だったゼロ金利がいまや常態となっている。このことは何を意味するか。
第1章では、資本がいまや物ではなく、電子・金融空間に投入されていることが述べられる。その結果、株価のバブルが生じるいっぽう、実質賃金は下落し、貧富の「越え難い深い溝」ができている。
第2章では、グローバリゼーションが「帝国」を生み落とし、帝国どうしの覇権をもたらしていることが論じられる。国民国家はもはや単独ではグローバリゼーションに対抗できなくなっている。すると、国家はこれからどこに向かうのか。
第3章が扱うのは、利子率と利潤率の相反する動き、そして所得の不平等についてである。「日米同盟とは日本が投資し(将来に備える)、米国が消費する(現在を楽しむ)という役割分担がある」ことについても触れられる。
そして終章は、21世紀の社会がいかなる方向に向かうかを論じる。はたしてケインズのいう「明日のことなど心配しなくてもいい社会」を構築できるか」が課題になる。
以上が本書の概要だ。
少しずつ読むことにします。
二つの国、二つの文化を生きる [本]

爽快な本である。人の生き方を示す本でもある。
著者の金正出氏は1946年に青森で生まれ、県立青森高校を卒業したあと、64年に北海道大学医学部に入学した。卒業後、さまざまな病院に勤務し、36歳のとき茨城県にちいさな外科診療所をつくる。それが小美玉市にある美野里病院の発端となった。
さらに特別養護老人ホームや介護老人保健施設、グループホームなどをつくり、高齢者介護にも取り組んできた。それだけでは終わらない。教育分野にも乗り出し、保育園からはじまって、何と中学校・高等学校(青丘学院)まで設立したのである。
こうしたがんばりの背景には、著者たち兄弟の成長を支えた両親の努力があったことがわかる。
著者のオモニ(母)は韓国の慶尚北道安東の貧しい農家に生まれ、兄を頼って戦前日本に渡ってきた。アボジ(父)は同じ慶尚北道大邱近くの出身で、八幡製鉄所で働いていた。ふたりは流れ着いた青森で1941年に結婚し、4人の男子に恵まれた。著者はその次男である。
戦後の生活は厳しいものだった。最初、家族は多くの同胞とともに朝鮮人長屋に住んでいた。しかし、いつまでもこういう場所にいては子どもたちによくないと考え、古い倉庫を買ってそこに移った。兄弟は4人とも日本の義務教育を受け、著者もわんぱくな少年生活を送ったという。
オモニはしっかり者で、朝から晩まではたらき、水飴の行商や養豚、密造酒づくりなどをして、一家を支えていた。次男の著者は一徹な性格で、母親は小学校の先生から「この子は、よくなればとてもよくなるけど、悪くなれば、とても悪くなる可能性がある」と言われたらしい。そんな子どもたちを4人ともまっすぐに育てたのは、まさに息子にたいするオモニの願いと献身があったからだろう。
自分が朝鮮人であることを意識しはじめたのは中学校のころからだったという。しかし、そのことで卑屈になることはなかった。むしろ金本という日本名に違和感をいだき、いやだなあと思っていた。学校の成績はよく、スポーツもよくできた。差別されたと感じたことは一度もないという。県立青森高校に進学し、がむしゃらに勉強し、北海道大学医学部に合格した。帰化はせず、そのときから本名を名乗るようになった。
アボジもよく働いたが、もともと身体がじょうぶではなかった。競輪とパチンコが大好きで、オモニとよく口げんかをしていたというのが、ほほえましい。密造酒が売れなくなると、しっかり者のオモニは新宿の焼肉店で短期間修行してから、青森駅前に「明月館」という焼肉店を開いた。その店を懸命に切り盛りし、大学に入った4人の子供たちの学費を滞りなく支えた。
次々と目標を立て、困難を乗り越え、それを実現していく著者の姿勢が爽やかである。民族に誇りをもち、家族をだいじにするところも、すがすがしい。「自分のルーツや祖先、親のことを誇りに思わないで、社会的に立派な仕事をした人を私は見たことがない」と断言する。
現代の韓国政府には批判的だ。歴史的事実を直視せず、都合のいい歴史ばかり教えているという。在日同胞の貢献についても、国民に十分知らせていない。韓国の政治家は国内に問題が起こると反日法を持ちだし、論点をずらす方向に国民を誘導する。こうしたやり方は、もうやめたほうがいいという。虚心坦懐に日本から学び、さまざまな分野で日本を追い越してこそ、韓国は世界から尊敬される国になると考えている。
著者は、両親が逆境にありながらも民族に誇りを持って自分を育ててくれたことに感謝している。そして、自身も日本人に負けないよう勉学に励み、医師となり、多くの事業を展開してきた。そこから育まれた信念が、未来へと向かう一筋の道を切り開いたことを、本書はまさに指し示している。
『始まっている未来』(宇沢弘文・内橋克人)を読む(再録) [本]

1
本書のもとになった対談は、2009年の春から夏にかけて、つまり自民党麻生政権末期におこなわれた。出版されたのは鳩山民主党政権が誕生してからだ。
ジャーナリスト内橋克人と経済学者宇沢弘文との息はぴったりあっており、内橋が宇沢から議論を引っ張りだし、時にその議論を具体例で補足するという役割を果たしている。ほとんど認識を共通する論者どうしによる対談と考えてよい。これから本書の内容を紹介するときに、基本的にいちいちふたりの名前を挙げないのは、そうした背景があることをいちおうことわっておく。
第1回の対談には「市場原理主義というゴスペル」という大見出しがつけられている。2008年の恐慌をもたらした大きな要因が、市場原理主義という考え方だと著者たちは考えている。そこでまず1929年の大恐慌にさかのぼるところから、対談は始まっている。
1920年代半ばころから、アメリカではカネ余りによる投機が起こり、「フロリダの別荘用の土地に始まって、1次産品、石油、金、美術・骨董品、ありとあらゆるものが投機の対象」になった。そのバブルが膨らんだあげく、最終的にニューヨークの株式市場が暴落し、それが金融市場から実体経済におよんでいったのが、戦前の世界大恐慌だったといえるだろう。
これに対し、ルーズヴェルト政権は、金融機関への監督を強化するいっぽう、TVA(テネシー川流域開発公社)などをつくって社会的インフラの整備に政府の資金をつぎこんで、何とか経済を回復させようとした。
こうした政策を理論的に支えていたのが、ケインズの考え方だった。宇沢によれば、ケインズは「資本主義は基本的に不均衡であり、失業の大量発生、物価の不安定、とくにインフレーション、そして所得と富の不平等といった経済的な不均衡は資本主義に内在しているものだから、それを政策的、あるいは制度的に防がなければならないという問題意識」をもっていたという。ケインズは、資本主義のもとで、安定的な経済成長、完全雇用、「すべての国民が人間らしい生活を営むことができるような制度」を実現したいと願っていた。
ところが、これとは全くちがう考え方もあった。それがナイトやハイエクの唱えた「新自由主義」だという。新自由主義は世界大恐慌の中で生まれたというより、ナチズムや共産主義に対抗するために生まれた理念だったといってよい。
宇沢はその考え方を次のようにまとめている。
〈企業の自由が最大限に保証されるときにはじめて、一人一人の人間の能力が最大限に発揮され、さまざまな生産要素が効率的に利用できるという一種の信念に基づいて、そのためにすべての資源、生産要素を私有化し、すべての市場を通じて取引するような制度をつくるという考え方です。水や大気、教育とか医療、また公共的な交通機関といった分野については、新しく市場をつくって、自由市場と自由貿易を追求していく。社会的共通資本の考え方を根本から否定するものです。パックス・アメリカーナの根源にある考え方だといってもいいと思います。〉
新自由主義のもとでは、政府はほとんど市場に介入してはならないことになっている。むしろ企業が自由に活動することを容認し、さらにそれを促すのが政府の役割というわけだ。あとで、あらためて説明するつもりだが、社会的共通資本の形成を唱える宇沢が、新自由主義に反対する側に立っていることはいうまでもない。
この新自由主義をさらにエキセントリックに政策化していったのがフリードマンの「市場原理主義」だ。
フリードマンは「自由を守るためには、共産主義者が何百万人死んでもかまわない」と思っているような人物で、麻薬をやるのは本人の勝手、黒人が貧乏なのも本人の勝手と、何ごとにも規制緩和と自己責任を唱えていた。市場原理主義の立場からすれば、もうけるためには何をやってもいいことになる。
レーガン政権と、そのあとのブッシュ政権が、銀行と証券の垣根を取っ払い、超富裕層への減税を実施し、巨額の財政赤字と貿易赤字を埋めるため、国債や金融商品(それに組みこまれていたのがサブプライムローン)を日本などに押しつけていった背景には、無節操な市場原理主義の考え方が控えていた。
それだけではない。日本では嘆かわしいことに、バブル崩壊後、アメリカ流の「規制緩和万能論」が、たちまち政財界に受け入れられていった。その走りが、細川政権時代に中谷巌が中心になってまとめたいわゆる「平岩レポート」で、そこには「自己責任原則と市場原理に立つ自由な経済社会の建設」というきらびやかな文言が並んでいた、と著者は指摘する。
そこから生まれた政策が、派遣労働(正規・非正規社員の区別)、最低賃金の抑制、後期高齢者医療制度、郵政民営化、医療・農業・教育の「改革」などなどだった。つまり国の関与や規制をやめて、企業が勝手に商売できるような環境をつくれば、何もかもうまくいくという発想だった。その結果、何が起きたか。リーマン・ショックを引き金とする、平成大恐慌だったというのである。
経済学はよくわからない。ただ思うに、経済学は科学というより、時代の雰囲気がつくった信念体系=社会思想のような気がしてならないのだ。その点では、マルクスもケインズもハイエクも同じだった。最後は処方箋(場合によっては手術)に行き着くという点で、経済学は医学と似ている。そして医術が生老病死を越えることができないように、いかなる経済術も絶対幸福を生みだすことはありえない。宗教だというつもりはまったくない。共産主義にも救済はない。ただ、どこかに限界があることは、わかっておいたほうがいいと思うのである。
へんな感想になってしまったけれど、カネに振りまわされている世界はどこかゆがんでいる。もちろんカネがなくては暮らせないし、カネさえあれば何でもできるというのもわからないわけではない。ただ、最近、世の中はますますそのような傾向が強くなって、人は自分が何だかそういう異常な世界にいることすら、実は認識できなくなっているような気がしてならない。恐慌はそのことを気づかせる機会となったが、人をそのアリジゴクに落としたのが、カネこそすべてと考えた市場原理主義だったことはたしかである。
2
内橋克人は「北欧モデル」を経済のあるべき姿として描いている。北欧ではだれもが利用できる公共的制度(社会的共通資本)があり、「生きる、働く、暮らす」という、人としての基本生活が社会的に保障されているという。
それにくらべれば、日本の社会ははるかに過酷だ。カネと権力が一番で、それを目指して人は競争する。広くいえば企業、下世話にいえば親分や大将に仕え、目立った業績を挙げるというのもよくあるパターンだ。そこから落ちこぼれてしまうと、世間のお情けにすがるか、世のはみ出し者になるしかない。大不況が日本でより深刻なのはそのためだ。
規制緩和をするのは、最初からはっきり企業のビジネスチャンスを増やすためだといわれてきた。ビジネスの機会が増えると、雇用も増えるし、買い物も便利になるし、社会のムダもなくなるし、それで経済が発展すると、いいことづくめという宣伝がなされてきた。しかし、規制緩和が打ちだされてからというもの、つまり平成になってから、日本経済はほとんど停滞していたことはまちがいない。
内橋は規制緩和と構造改革のもとで、自治体財政から切り離された公立病院が経営難におちいり、大規模小売店舗法の撤廃で地元の商店街が崩壊し、解雇自由・超低コストの労働力(派遣や非正規社員)がどんどん増え、国民医療費抑制の名のもとに後期高齢者医療制度が導入されていったことなどを例に挙げている。これをみても、規制緩和がいかに日本社会に打撃を与えていったかがわかろうというものだ。
実は規制緩和を言いだしたのはアメリカである。規制緩和は日本市場をアメリカ企業のために開放するということを意味していたのではないか。
内橋は「日米安保とは、軍事条約だけではなく経済協力とのパッケージ」だと話している。宇沢弘文も日本がますますアメリカの植民地になろうとしていると指摘する。そのことを示すのが、たとえば1980年代末から90年代にかけての「日米構造協議」だ。
〈日米構造協議の核心は、日本のGNPの10%を公共投資に当てろという要求でした。しかもその公共投資は決して日本経済の生産性を上げるために使ってはいけない。全く無駄なことに使えという信じられない要求でした。……[その結果]最終的には630兆円の公共投資を経済生産性を高めないように行うことを政府として公的に約束したのです。まさに日本の植民地化を象徴するものです。〉
630兆円というのはものすごい額で、これはいまの国債残高600兆円に該当する。地方自治体は中央政府の指示で地方債を発行し、そのカネでやたらレジャー施設をつくった。そのつけが、いま回っているのだ。
それにしても無駄なことにカネを使えというのはひどい話だ。昔、だれかから聞いたことがあるが、日本ではアメリカ派でない官僚は出世できないという。目に見えないところで、アメリカの日本に対するコントロールはずっとつづいている。前回、経済学は時代の産物だと書いたけれども、経済学はしばしばアメリカの世界戦略の道具になっている、と付け加えてもよさそうだ。
空疎なキャッチフレーズにだまされず、「生きる、働く、暮らす」の場に思想の根拠を置くことがいかにだいじかを思い知らされる。
3
宇沢弘文は戦後の日本の経済学者では下村治を高く評価している。池田内閣時代に「所得倍増計画」を唱えたが、公害などを見て、その後ゼロ成長論に転じた人だ。「佐賀の葉隠精神を体現した昭和の偉丈夫」で「日本がアメリカに植民地化されることを心から憂えていた」という。
アメリカの経済学者で宇沢がとくに評価しているのはスティグリッツだ。オバマ政権がサマーズやガイトナーといった、どちらかといえば市場原理主義者を国家経済会議委員長や財務長官に登用した理由がわからないと苦言を呈している。
これからの経済学として、宇沢が思い描いているのは「ケインズ=ベヴァリッジ」型の考え方で、その中心概念となるのが社会的共通資本である。
〈社会的共通資本は、基本的にはペイしないし、決して儲けを求めてはいけない。社会的共通資本に携わっている人々は職業的な知見と規律を保って、しかし企業として存続しなければいけない。原則赤字になるものを支える制度をつくるのが政府の役割です。社会的共通資本が本来の機能を果たせる形で持続的に維持できるような制度が、リベラリズムを理念とする社会の経済的な仕組みということでしょう。〉
やはりわかりにくい。大先生には申し訳ないのだが、ネーミングが悪いのではないかとさえ思ってしまう。
それはともかく、宇沢はこれまでの経済学の研究から、社会的共通資本という考え方に達したという。大きな影響を与えたのは、ケインズがいちばんだったのはまちがいないが、古典派では、アダム・スミスとジョン・スチュアート・ミルだったことがわかる。
スミスについては、こう話している。
〈自然、国土を大事にして、そこに生きる人々すべてが人間らしい営みをすることができるというのが、アダム・スミスの原点です。〉
ミルについては、『経済学原理』に描かれた「定常状態」が注目されている。
〈マクロ経済的にはすべての経済的な変数(実質国民所得、消費や投資など)が一定に保たれているが、ひとたび社会のなかに入ってみると、はなやかで人間的な営みが展開されている。人々の交流、文化的活動、新しい研究……。新しい何かがつくられている活気に満ちた社会であり、かつ経済全体で見ると定常的である。〉
ぼくは例によって、経済学独特の抽象や言い回しが苦手なのだが、それはともかく、宇沢によると、スミスを継承したミルのいう「定常状態」を実現するための制度が「社会的共通資本」という考え方なのだとされる。
ところが市場原理主義が横行すると、世の中、何もかもカネというような風潮になってしまった。
内橋はこういうふうに言っている。
〈人間らしく生きるには豊かさが必要だという順序なのに、いまは逆立ちして、豊かさが満たされれば人間らしく生きられる、という話になっています。つまりは、依然として人間の生存条件ではなく生産条件優位の思考法ですね。〉
この対談では、宇沢が1991年にローマ教皇ヨハネ・パウロ2世の出した回勅の主題となった「社会主義の弊害と資本主義の幻想」の提唱者だったことが明らかにされている。
その内容について、宇沢はこんなふうに説明している。
〈「社会主義の弊害」とは、社会主義のもと、市民の基本的権利は無視され、個人の自由は完全に剥奪され、人間的尊厳は跡形もなく失われてしまった。特に、狂気に陥った独裁者スターリンの支配下、ソ連全土が巨大な収容所と化し、何百万という無実の人々が処刑されたことなどを指しています。ところが、多くの人たちは資本主義になればいいと思っているが、それは大間違いで、資本主義には社会主義に劣らない深刻な問題がある。特に市場原理主義的な考え方が支配しつつあることに焦点をあてて、考えを進めたわけです。〉
この部分には宇沢の考え方がよくあらわれている。
これまで見てきたところで、社会的共通資本という概念が、近代の歴史、さらには経済学を検証したなかで、練り上げられた考え方だということがわかるだろう。
そこで、以下は、ひょっとしたら勘違いしているかもしれないぼくの勝手な解釈である。
社会的共通資本の思想とは、人が自由に暮らしていくのに必要不可欠な生活基盤をコミュニティで支えていく工夫ということなのではないだろうか。柳田国男のいう結(ゆい)である。
それは中央政府ではなく、自治体がリードしながら、社会に〈脱商品〉の領域を埋めこんでいくという具体的実践なのだ。それは村や町のよき伝統を復元する試みでもある。
ただし、社会的共通資本をになうのは、政府や役所ではなく、企業を含む自主的団体である。
その対象となるのは、自然環境であったり、道路や電気、ガス、水道であったり、教育や医療であったりする。これらは儲けの対象ではない。そのコストは原則として受益者が負担し、場合によっては税金によってまかなわれる。その運営にあたるのは官庁ではなく、専門家の集団であって、しかもその業務実態はつねに開示されていなければならない。これらはすべて社会全体の財産であり、個人的な専有は許されない。
宇沢のいう社会的共通資本は、そんなふうに理解できるのではないだろうか。さらに想像をめぐらせば、それは脱中央集権で、村と町を復活させる構想へとつながってしかるべきだ。生活の基本ラインを確保するという意味では、いざというときにも安心して生きていける場(そしてそこをステップにして社会に戻っていける場)を地域のスポットとしてつくっていくことも必要だろう。
そして、おそらく、こうした〈脱商品〉の領域を社会の中に組みこんでいくことは、必ずしも企業活動を阻害しないし、かえってそれをよい方向に促進させる場合もある。ジョン・スチュアート・ミルが描いたのは、そういう世界だったと思われる。
4
内橋克人は、未来に向けてすでに始まっている新しい経済について、多くのことを語っている。ひとつはアメリカ支配の経済からの脱却ということである。人や自然よりカネを優先する社会を終わりにしようというメッセージもある。大賛成だ。
「共生経済」をつくりだし、「FEC」自給圏を形成しよう、と内橋は提案している。共生経済は連帯・参加・協同の経済を意味する。競争経済とは正反対だ。「FEC」は食料のFと、エネルギーのEと、ケアのCを合成した内橋語。
考えてみれば、日本は食料もエネルギーも自前でまかなえず、安全保障もアメリカに牛耳られているありさまだ。医療のケアだって、近ごろはだんだんあやしくなっている。それをみんなの力で、何とかできないか。この本のタイトルにひめられているのはそんな思いだ。
内橋が参照にするのは、ドイツや北欧の経済だ。たとえばデンマークは食料自給率300%、エネルギー自給率120%。それでいて、産業も発達していて、教育水準も高く、1人あたりGDPも日本より上で、所得格差は世界で最も低く、公務員がいばっていない。面積は日本の8分の1、人口は日本の20分の1とはいえ、実際、こんな国があるのだ。
デンマークでは、市民共同発電方式がとられていて、電力会社は市民の生みだした余剰電力を必ず買い取らねばならない。電化製品には「エナジーラベル」がついていて、消費者がエネルギー効率の高い製品を選べるようになっている。あくまでも市民が経済の中心なのだ。
ヨーロッパでは環境都市づくりが進んでいる。中心部に自動車を入れない町が増えている。緑が多く、喫茶店や本屋があって、人々が散歩を楽しみ、文化を味わえる町。ぼくもプロヴァンスで確かにそんな町を見た(ただし、ここには原発もあったが)。
話変わって、宇沢弘文は地球温暖化に触れている。かれは、大気を世界の共通財産としてとらえ、その汚染を防ぐために、「比例的炭素税」を導入し、「大気安定化国際基金」をつくるという構想を持ちだしている。
炭素税というのは大気中への二酸化炭素の放出に対してかけられる税金のこと。それを各国が1人あたり国民所得に応じて、公正に分担するのが比例的炭素税だ。それによって大気汚染を少しでも抑えるねらいがある。税金は森林の育成や環境技術の開発などに用いられる。そして、その一部を「国際基金」に組み入れて、発展途上国の環境保全に役立てようというのである。
日本はどこかで道をあやまってしまった。この本には、もう一度、くにのあり方の基本に立ち返って、経済を組み立てなおすためのヒントがあちこちに示されている。
(2009年11〜12月「海神日和」)



