鄭周永『この地に生まれて』(金容権訳)を読む(3) [本]
いかにも鄭周永らしいのは、オイルショックの危機を突破するには中東に進出するしかないと考えたことである。
鄭周永は社内の反対を押しきって、1975年を中東進出元年と定め、まずバーレーンに造船所を建設、サウジアラビアの海軍基地の工事も引き受け、翌年、サウジアラビアのジュバイル産業港工事に着手した。
ジュバイルの落札にはかずかずのドラマがある。3年がかりのその工事も苦難の連続だった。だが、ジュバイルの機材を製造する蔚山(ウルサン)の現代造船所はにわかに活気づいた。
こうした海外での建設経験をへて、現代造船所は「現代重工業」へと発展していく。重工業の背後には「現代建設」とのつながりがあった。
「重工業と建設の、この特異な有機的関係によって、私たちの海外建設の外貨獲得率は他の建設企業のほとんど二倍に達した」と書いている。
田中角栄はコンピュータ付きブルドーザーと呼ばれたが、鄭周永も同じようなことを言っている。
〈私は、私の「ブルドーザー」で計算して予測する。それはいわば口と手足を持ったコンピュータだ。性能がそれほど悪くない頭をつけて、他人よりも真剣に考え抜いて研究し、努力しながら押し続けてきた。それが仕事人としての私だ。〉
障害は突破して克服するものだ。固定観念の枠に閉じこめられていてはいけない。人間には無限の潜在能力とアイデアがある。鄭周永はそう信じつづけた。
その後も現代グループは成長しつづけ、多くの会社や財団をつくりつづけた。1977年には「峨山(アサン)社会福祉財団」をつくり、医療脆弱地域にいくつも病院を建て、研究開発支援や奨学金事業にも乗り出している。
鄭周永は1977年に全経連(全国経済人連合会)の会長に就任、その会長を10年間引き受けた。そのかん、財界の自律性と独立性を守るため、政府の不当な要求や干渉とも戦った。全斗煥大統領は鄭周永を会長ポストからはずそうとしたが、それに屈しなかった。
1979年10月には、朴正熙大統領が金載圭中央情報部長に暗殺される事件がおきていた。時あたかもイラン革命が発生し、「現代」もイランから撤退せざるを得なかった。
全斗煥の軍政のもとで、経済も強制的に改編されていく。政府の命令によって、さまざまな企業が無理やりに統合されていった。経済論理が通じない暗黒時代がはじまった。「現代」も発電設備の製造ができなくなり、企業活動に大きな支障がでたという。
鄭周永はソウルでの1988年オリンピック開催に向けて、81年に推進委員長を引き受けている。その誘致のために、全力を尽くした。名古屋の勝利が決定的だと思われていた。だが、IOCの委員に猛烈なアピールをくり広げて、ついにソウル開催を勝ちとったのだ。
1982年から84年までは大韓体育会長の会長も引き受け、そのかんにも「現代電子」という新会社を設立している。
ここでも試行錯誤と試練は避けられなかった。半導体やエレクトロス部門で成果を挙げるのに5年の歳月を要している。
ほかにも現代グループは干拓事業をおこなうなど、その手がけた事業は数限りない。しかし、着目すべきは金剛山観光だろう。
ソウル・オリンピックの終わった翌年の1989年1月に、鄭周永は北朝鮮を訪れ、朝鮮労働党の外交委員長と面談し、金剛山の共同開発について話しあっている。鄭周永にとって、金剛山はふるさとの山である。子供のころや青年時代に何度も登ったことがある。
その金剛山を観光地として南北で共同開発することは、ふたたび民族がひとつになるための第一歩になると思われた。だが、その期待も、政治の荒波にもまれて、しぼんでしまうことになる。
1992年に、鄭周永はついに政界に乗り出す。政治がまちがっていると、経済がよくなることはありえないと思っていた。そこで統一国民党を結成し、3月の総選挙で31議席を得た。その5月には、大統領選挙に立候補する。だが、選ばれたのは金泳三だった。
2001年に鄭周永は亡くなる。その後、現代グループでは争いがあり、不幸も重なって、グループはバラバラになってしまい、かつての結束は失われた。

[1998年、牛500頭をつれ、板門店を通過し、公式に北朝鮮に向かう]
それでも鄭周永が韓国経済のチャンピオンだったという記憶は、これからも残っていくだろう。
鄭周永は社内の反対を押しきって、1975年を中東進出元年と定め、まずバーレーンに造船所を建設、サウジアラビアの海軍基地の工事も引き受け、翌年、サウジアラビアのジュバイル産業港工事に着手した。
ジュバイルの落札にはかずかずのドラマがある。3年がかりのその工事も苦難の連続だった。だが、ジュバイルの機材を製造する蔚山(ウルサン)の現代造船所はにわかに活気づいた。
こうした海外での建設経験をへて、現代造船所は「現代重工業」へと発展していく。重工業の背後には「現代建設」とのつながりがあった。
「重工業と建設の、この特異な有機的関係によって、私たちの海外建設の外貨獲得率は他の建設企業のほとんど二倍に達した」と書いている。
田中角栄はコンピュータ付きブルドーザーと呼ばれたが、鄭周永も同じようなことを言っている。
〈私は、私の「ブルドーザー」で計算して予測する。それはいわば口と手足を持ったコンピュータだ。性能がそれほど悪くない頭をつけて、他人よりも真剣に考え抜いて研究し、努力しながら押し続けてきた。それが仕事人としての私だ。〉
障害は突破して克服するものだ。固定観念の枠に閉じこめられていてはいけない。人間には無限の潜在能力とアイデアがある。鄭周永はそう信じつづけた。
その後も現代グループは成長しつづけ、多くの会社や財団をつくりつづけた。1977年には「峨山(アサン)社会福祉財団」をつくり、医療脆弱地域にいくつも病院を建て、研究開発支援や奨学金事業にも乗り出している。
鄭周永は1977年に全経連(全国経済人連合会)の会長に就任、その会長を10年間引き受けた。そのかん、財界の自律性と独立性を守るため、政府の不当な要求や干渉とも戦った。全斗煥大統領は鄭周永を会長ポストからはずそうとしたが、それに屈しなかった。
1979年10月には、朴正熙大統領が金載圭中央情報部長に暗殺される事件がおきていた。時あたかもイラン革命が発生し、「現代」もイランから撤退せざるを得なかった。
全斗煥の軍政のもとで、経済も強制的に改編されていく。政府の命令によって、さまざまな企業が無理やりに統合されていった。経済論理が通じない暗黒時代がはじまった。「現代」も発電設備の製造ができなくなり、企業活動に大きな支障がでたという。
鄭周永はソウルでの1988年オリンピック開催に向けて、81年に推進委員長を引き受けている。その誘致のために、全力を尽くした。名古屋の勝利が決定的だと思われていた。だが、IOCの委員に猛烈なアピールをくり広げて、ついにソウル開催を勝ちとったのだ。
1982年から84年までは大韓体育会長の会長も引き受け、そのかんにも「現代電子」という新会社を設立している。
ここでも試行錯誤と試練は避けられなかった。半導体やエレクトロス部門で成果を挙げるのに5年の歳月を要している。
ほかにも現代グループは干拓事業をおこなうなど、その手がけた事業は数限りない。しかし、着目すべきは金剛山観光だろう。
ソウル・オリンピックの終わった翌年の1989年1月に、鄭周永は北朝鮮を訪れ、朝鮮労働党の外交委員長と面談し、金剛山の共同開発について話しあっている。鄭周永にとって、金剛山はふるさとの山である。子供のころや青年時代に何度も登ったことがある。
その金剛山を観光地として南北で共同開発することは、ふたたび民族がひとつになるための第一歩になると思われた。だが、その期待も、政治の荒波にもまれて、しぼんでしまうことになる。
1992年に、鄭周永はついに政界に乗り出す。政治がまちがっていると、経済がよくなることはありえないと思っていた。そこで統一国民党を結成し、3月の総選挙で31議席を得た。その5月には、大統領選挙に立候補する。だが、選ばれたのは金泳三だった。
2001年に鄭周永は亡くなる。その後、現代グループでは争いがあり、不幸も重なって、グループはバラバラになってしまい、かつての結束は失われた。

[1998年、牛500頭をつれ、板門店を通過し、公式に北朝鮮に向かう]
それでも鄭周永が韓国経済のチャンピオンだったという記憶は、これからも残っていくだろう。
鄭周永『この地に生まれて』(金容権訳)を読む(2) [本]
経済の発展は政治環境抜きにはありえない。
1961年の軍事クーデターで、朴正熙は韓国の政権を握り、63年から79年まで大統領を務めた。その時代に「現代(ヒョンデ、対外的にはヒュンダイ)」は財閥として急成長している。そして、韓国経済もそのかんに「漢江の奇跡」と呼ばれる近代化を成し遂げた。
「現代」は政府の経済計画にしたがって、インフラと基幹産業の建設に邁進した。すべての建設工事を韓国人自身でおこない、そのために海外から先進技術を取り入れ、絶えず技術向上に努力するという原則が立てられていた。
「現代」は肥料工場や火力発電所、ダムなど、政府の発注工事に取り組んだ。それだけではない。政府の受注には限界があると見越して、海外の入札にも加わり、タイの高速道路やベトナム・カムラン湾の浚渫などの工事も請け負っている。
政府におとなしくしたがったわけではないという。鄭周永は最小の経費でできるだけ効率的な施設をつくるための代案を出しつづけた。もちろん、手抜き工事や無駄遣いなどはいっさいしなかった。企業人としてのプライドが許さなかったのだ。金のためだけではなく、いい仕事をしてこそ、国家や社会に役立つことができるという気持ちが強かったという。
春川(チュンチョン)の昭陽江ダムでも釜山の港湾工事でも、鄭周永は経費と時間を節約できる無駄のない方式を提案し、日本人技術者の鼻を明かしている。1968年にはじまった韓国の大動脈、京釜高速道路の建設でも、最新大型機材を導入し、小白山脈のたいへんなトンネル工事を乗り越え、2年半足らずで工事を終えている。

[京釜高速道路]
鄭周永は建設業ほど重要な業種はないと述べている。「私自身は内心ではあくまでも建設業を営む『建設人』であり、その誇りと自負心を失ったことはない」。そこには多くの難関や危険がひそんでいるが、そのつらさを乗り越えたときの達成感は格別なものだ。
現代財閥を語るうえでは「現代自動車」と「現代造船」(のちの「現代重工業」)が欠かせないだろう。
鄭周永が自動車産業に飛びこんだのは1967年末のことである。以前から、韓国でもこれから自動車産業が急成長するだろうと思っていた。そこでたまたまアメリカにいた弟にフォードと交渉するよう命じたというのは、大胆不敵である。粘り強い交渉の結果、フォードは「現代」と提携することを決め、1967年末に「現代自動車」が発足する。
だが、のっけから難航する。それもそのはずである。自動車を修理した経験はあるが、自動車をつくったことはない。ゼロからの出発である。
まず工場敷地の買収がなかなかうまくいかなかった。ようやく蔚山(ウルサン)に工場をつくり、68年末に最初の自動車を売りだしたが、さっぱり売れず、69年9月には工場が水害に見舞われた。
そのころ、韓国では新進、現代、起亜、アセアなどの自動車会社がしのぎをけずっていた。
69年末、政府は3年以内に自動車を完全国産化する政策を打ち出し、エンジン製造を一元化するよう求めた。だが、それはあまりにも性急な政策だった。
鄭周永は朴大統領と会ったさいに、政府の計画が強引すぎると批判した。大統領はそれを認め、方針を転換する。こうして、1975年までに国産化比率を80%にし、韓国の実情に合う小型車開発に力を注ぎ、国際競争力を備えるため競争製品の輸入を禁止するという措置がとられた。
1970年11月、現代自動車はフォードと対等の合弁比率で契約書を結び、エンジン製造工場を設立する認可を受けた。だが、そのころ現代自動車の財務状況はそれこそ火の車になっていた。
その後2年間、現代とフォードは経営方針でことごとく対立する。けっきょく、フォードのねらいは、韓国市場をのみこみ、現代自動車をフォードの部品工場にすることだったのだ。こうして1973年1月にフォードとの合弁は解消されることになる。
現代自動車は独自に小型車を開発する決意を固めた。こうして、日本の三菱自動車やイギリスのブリティッシュ・レイランド社などと技術協力契約を結び、イタリアのイタルデザイン社にデザイン設計を依頼し、小型車の開発に着手する。
1974年7月には1億ドルを投入して、年間生産能力5万6000台規模の自動車工場を建設し、76年1月についに韓国国産車「ポニー」が誕生した。
いまや自動車は韓国の輸出産業になっている。自動車は「走る国家」だ、と鄭周永はいう。20年のうちに、現代自動車は全車種で1070万台の自動車を生産し、そのうち450万台を輸出するまでに成長した。
1960年代前半から、鄭周永は造船にも興味をもっていたという。
そのエネルギーには驚くばかりだ。「企業家は常に、より新しい仕事、より大きい仕事を熱望する。より新しい仕事、より大きい仕事に対する情熱こそが、企業家がもっているエネルギーの源泉である」と書いている。
アメリカや日本にあって韓国にないものを、韓国人の手でみずからつくりあげていくのだという情熱が、企業家である鄭周永を支えていたといってもよいだろう。それが国家の方針とも一致するときに計画は動きだす。産業の主体はあくまでも企業である。
だが、言うは易く行うは難し。造船業が軌道に乗るまでにはさまざまな試練をくぐらねばならなかった。何十万トン級の船をつくるには、大きなドックが必要だ。そのためには巨額の資金を投入しなければならない。「お金を貸してください」と各国をめぐる日々がはじまった。
造船所の建設計画がスタートしたのは1970年である。自動車開発とほぼ並行している。鄭周永は造船業を建設業と同じだと考えていた。産業のつながりを頭にいれておくのはもちろんだ。加えて重要なのは情報である。産業情報をしっかりつかんでおかなければ、計画はたちまち机上の空論になってしまう。
鄭周永は、何としても韓国で造船所をつくるのだという熱情をもっていた。その熱情が、ついにヨーロッパの諸銀行からの借款を引き寄せただけではない。イギリスの技術会社と造船所からも協力が得られることになった。
だが、ここで大きな問題が浮上する。いくら船ができても買ってくれる相手がいなければ、どうしようもないのだ。「その日から私は、まだ存在もしない造船所で造る船を買ってくれる船主を探し回った」
そして、ついに並外れた船主が現れた。それがギリシアの海運王オナシスの義弟リバノスだった。リバノスの別荘で、タンカー2隻の注文を受けたときには、天にも舞い上がる気持ちになった。
じつはそのとき、造船所の場所をまだ確保していなかったというのは、驚くほかない。すでにめぼしはつけてあった。蔚山の尾浦湾である。さっそく100万坪以上の土地を購入した。不毛の土地なので、値段は安い。その場所に、建設用機材を使って、急遽、ドックの建設をはじめることにした。
1972年3月、「現代造船所」の起工式がおこなわれた。この起工式には朴大統領も参加した。それから2年3カ月のあいだに、「現代造船所」はドックを掘り、工場を建設し、同時にタンカー2隻を建造するという離れ業をやってのけた。
「蔚山造船所を建設したときが、おそらく私の一生のなかで、一番活気に溢れた時代だったのではなかっただろうか」と著者は書いている。しかし、毎日が失敗と試練の連続だった。
それに追い打ちをかけるように、オイルショックが海運業界に打撃を与える。とりわけタンカーが過剰になってしまったのだ。リバノスにも裏切られる。ひとつ乗り越えれば、また新たな苦難がはじまる。しかし、それに負けず、鄭周永は必死に突破口をさがしつづけた。
1961年の軍事クーデターで、朴正熙は韓国の政権を握り、63年から79年まで大統領を務めた。その時代に「現代(ヒョンデ、対外的にはヒュンダイ)」は財閥として急成長している。そして、韓国経済もそのかんに「漢江の奇跡」と呼ばれる近代化を成し遂げた。
「現代」は政府の経済計画にしたがって、インフラと基幹産業の建設に邁進した。すべての建設工事を韓国人自身でおこない、そのために海外から先進技術を取り入れ、絶えず技術向上に努力するという原則が立てられていた。
「現代」は肥料工場や火力発電所、ダムなど、政府の発注工事に取り組んだ。それだけではない。政府の受注には限界があると見越して、海外の入札にも加わり、タイの高速道路やベトナム・カムラン湾の浚渫などの工事も請け負っている。
政府におとなしくしたがったわけではないという。鄭周永は最小の経費でできるだけ効率的な施設をつくるための代案を出しつづけた。もちろん、手抜き工事や無駄遣いなどはいっさいしなかった。企業人としてのプライドが許さなかったのだ。金のためだけではなく、いい仕事をしてこそ、国家や社会に役立つことができるという気持ちが強かったという。
春川(チュンチョン)の昭陽江ダムでも釜山の港湾工事でも、鄭周永は経費と時間を節約できる無駄のない方式を提案し、日本人技術者の鼻を明かしている。1968年にはじまった韓国の大動脈、京釜高速道路の建設でも、最新大型機材を導入し、小白山脈のたいへんなトンネル工事を乗り越え、2年半足らずで工事を終えている。

[京釜高速道路]
鄭周永は建設業ほど重要な業種はないと述べている。「私自身は内心ではあくまでも建設業を営む『建設人』であり、その誇りと自負心を失ったことはない」。そこには多くの難関や危険がひそんでいるが、そのつらさを乗り越えたときの達成感は格別なものだ。
現代財閥を語るうえでは「現代自動車」と「現代造船」(のちの「現代重工業」)が欠かせないだろう。
鄭周永が自動車産業に飛びこんだのは1967年末のことである。以前から、韓国でもこれから自動車産業が急成長するだろうと思っていた。そこでたまたまアメリカにいた弟にフォードと交渉するよう命じたというのは、大胆不敵である。粘り強い交渉の結果、フォードは「現代」と提携することを決め、1967年末に「現代自動車」が発足する。
だが、のっけから難航する。それもそのはずである。自動車を修理した経験はあるが、自動車をつくったことはない。ゼロからの出発である。
まず工場敷地の買収がなかなかうまくいかなかった。ようやく蔚山(ウルサン)に工場をつくり、68年末に最初の自動車を売りだしたが、さっぱり売れず、69年9月には工場が水害に見舞われた。
そのころ、韓国では新進、現代、起亜、アセアなどの自動車会社がしのぎをけずっていた。
69年末、政府は3年以内に自動車を完全国産化する政策を打ち出し、エンジン製造を一元化するよう求めた。だが、それはあまりにも性急な政策だった。
鄭周永は朴大統領と会ったさいに、政府の計画が強引すぎると批判した。大統領はそれを認め、方針を転換する。こうして、1975年までに国産化比率を80%にし、韓国の実情に合う小型車開発に力を注ぎ、国際競争力を備えるため競争製品の輸入を禁止するという措置がとられた。
1970年11月、現代自動車はフォードと対等の合弁比率で契約書を結び、エンジン製造工場を設立する認可を受けた。だが、そのころ現代自動車の財務状況はそれこそ火の車になっていた。
その後2年間、現代とフォードは経営方針でことごとく対立する。けっきょく、フォードのねらいは、韓国市場をのみこみ、現代自動車をフォードの部品工場にすることだったのだ。こうして1973年1月にフォードとの合弁は解消されることになる。
現代自動車は独自に小型車を開発する決意を固めた。こうして、日本の三菱自動車やイギリスのブリティッシュ・レイランド社などと技術協力契約を結び、イタリアのイタルデザイン社にデザイン設計を依頼し、小型車の開発に着手する。
1974年7月には1億ドルを投入して、年間生産能力5万6000台規模の自動車工場を建設し、76年1月についに韓国国産車「ポニー」が誕生した。
いまや自動車は韓国の輸出産業になっている。自動車は「走る国家」だ、と鄭周永はいう。20年のうちに、現代自動車は全車種で1070万台の自動車を生産し、そのうち450万台を輸出するまでに成長した。
1960年代前半から、鄭周永は造船にも興味をもっていたという。
そのエネルギーには驚くばかりだ。「企業家は常に、より新しい仕事、より大きい仕事を熱望する。より新しい仕事、より大きい仕事に対する情熱こそが、企業家がもっているエネルギーの源泉である」と書いている。
アメリカや日本にあって韓国にないものを、韓国人の手でみずからつくりあげていくのだという情熱が、企業家である鄭周永を支えていたといってもよいだろう。それが国家の方針とも一致するときに計画は動きだす。産業の主体はあくまでも企業である。
だが、言うは易く行うは難し。造船業が軌道に乗るまでにはさまざまな試練をくぐらねばならなかった。何十万トン級の船をつくるには、大きなドックが必要だ。そのためには巨額の資金を投入しなければならない。「お金を貸してください」と各国をめぐる日々がはじまった。
造船所の建設計画がスタートしたのは1970年である。自動車開発とほぼ並行している。鄭周永は造船業を建設業と同じだと考えていた。産業のつながりを頭にいれておくのはもちろんだ。加えて重要なのは情報である。産業情報をしっかりつかんでおかなければ、計画はたちまち机上の空論になってしまう。
鄭周永は、何としても韓国で造船所をつくるのだという熱情をもっていた。その熱情が、ついにヨーロッパの諸銀行からの借款を引き寄せただけではない。イギリスの技術会社と造船所からも協力が得られることになった。
だが、ここで大きな問題が浮上する。いくら船ができても買ってくれる相手がいなければ、どうしようもないのだ。「その日から私は、まだ存在もしない造船所で造る船を買ってくれる船主を探し回った」
そして、ついに並外れた船主が現れた。それがギリシアの海運王オナシスの義弟リバノスだった。リバノスの別荘で、タンカー2隻の注文を受けたときには、天にも舞い上がる気持ちになった。
じつはそのとき、造船所の場所をまだ確保していなかったというのは、驚くほかない。すでにめぼしはつけてあった。蔚山の尾浦湾である。さっそく100万坪以上の土地を購入した。不毛の土地なので、値段は安い。その場所に、建設用機材を使って、急遽、ドックの建設をはじめることにした。
1972年3月、「現代造船所」の起工式がおこなわれた。この起工式には朴大統領も参加した。それから2年3カ月のあいだに、「現代造船所」はドックを掘り、工場を建設し、同時にタンカー2隻を建造するという離れ業をやってのけた。
「蔚山造船所を建設したときが、おそらく私の一生のなかで、一番活気に溢れた時代だったのではなかっただろうか」と著者は書いている。しかし、毎日が失敗と試練の連続だった。
それに追い打ちをかけるように、オイルショックが海運業界に打撃を与える。とりわけタンカーが過剰になってしまったのだ。リバノスにも裏切られる。ひとつ乗り越えれば、また新たな苦難がはじまる。しかし、それに負けず、鄭周永は必死に突破口をさがしつづけた。
鄭周永『この地に生まれて』(金容権訳)を読む(1) [本]
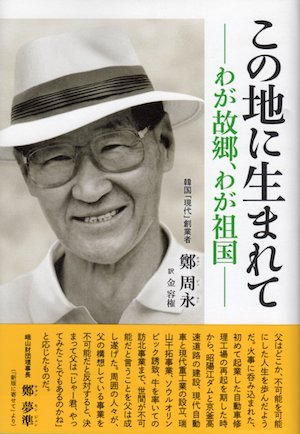
鄭周永(チョン・ジュヨン、1915〜2001)は、一代で韓国の現代(ヒョンデ)財閥をつくりあげた。本書はその自伝である。
時代の流れは激しく、現在、現代財閥はばらばらになってしまったが、それでも鄭周永が韓国の経済発展に大きく貢献したことはまちがいない。
鄭周永は日本でいえば、田中角栄に似た人物である。学歴は普通学校(小学校)だけで、貧しい村を飛び出して、建設業で財を築いた。大統領に挑戦したという点では、政治にも興味をもっていた。だが、主に力を注いだのは、実業界である。その波乱万丈の物語は、じつにおもしろい。それだけではない。実業界で生き抜くための厳しさや知恵を教えてくれるだろう。
両親は働き者だった。朝から晩まで黙々とはたらいていた。それでも村の家はいつも貧しく、食べるのが精一杯だった。
父は長男である著者に家を継いでもらいたかったらしいが、当の本人は小学校を卒業して、家の仕事を手伝ううちに、都会に出てはたらいてみたいという思いを募らせていた。その結果、3度家出して、その都度連れ戻されたというのだから、その決意は固かったのだ。そして、満17歳の4度目の家出で、著者はついに村からの脱出を果たした。
ソウルでの暮らしは苦労の連続だった。当時はまだ日本が朝鮮を支配していた時代である。日雇いから住み込みまで、お金をもらえるなら何でもやった。建築現場の作業や工場の雑用係や見習いまで、あらゆる仕事を黙々とこなした。だが、さすがに、このままでは先がないと思うようになった。
そんなとき見つけたのが、米屋での配達の仕事だった。米1俵の月給をもらえるというので、喜びがこみあげてきたという。すごいのは、命じられるままに米や雑穀を配達しただけで仕事をおしまいにしなかったことである。朝早く起きて、店の前をきれいに掃除し、倉庫の商品を仕分けし、帳簿をきちんと整理することまでやって、懸命にはたらいた。
店主はこの若者がすっかり気にいった。こうして暖簾分けしてもらうかたちで、22歳の冬、東大門市場に近い場所に、自分の店をもつことができたのだ。故郷を出てから5年目のことだった。この店を「京一商会」と名づけたのは、ソウルで一番の米屋になるという思いからだったという。
著者は持ち前の熱心さで大口顧客を開拓した。商売は日増しに繁盛し、金も貯まった。しかし、2年後、日中戦争が激しくなり、戦時体制下で米が配給制になってしまうと、米屋もあがったりになってしまう。
新しい商売を見つけなければならなかった。そこで、目をつけたのが、売りに出ていた自動車修理工場だった。米屋から自動車修理屋へという変身がまたすごい。自動車は好きだったかもしれないが、本人は自動車のことをよく知っているわけではなかった。たまたま知り合いに自動車の技術者がいただけのことである。
しかし、持ち前のカンで、手持ちの資金に高利貸からの借金を合わせて、修理工場を買い入れた。幸い、友人の技術者がよく働いてくれて、商売は順調に動きはじめた。ところが、である。仕事をはじめて、ひと月足らずで工場から出火し、預かっていた車も焼け、大きな借金をかかえてしまったのだ。
だが、これで終わらなかった。まだ若かったこともあるだろう。土下座して頼むと、なぜか高利貸は著者を見込んで、ふたたび金を貸してくれた。その金で、自動車修理工場をつくった。1940年5月のことである。
無許可の工場だったが、警察は何とか目こぼししてくれた。あっというまに修理が終わるのが評判になって、工場には次々と故障車が押し寄せた。
こうして朝から晩まではたらいたこともあって、おもしろいように金が貯まり、借金も返すことができた。ところが、そこに朝鮮総督府から横槍がはいった。太平洋戦争がはじまっていた。工場は無理やり合併させられ、会社は人の手に移ってしまう。
ここでやけをおこさないのが、著者のえらいところである。また別の仕事を見つけたのだ。今度は運送業である。
鎮南浦には精錬所があり、原料の鉱石は黄海道の笏洞鉱山から運ばれていた。そこで、鉱山から平壌の船着き場まで自動車で運搬する仕事を請け負ったのだ。
日本人の管理者からはさんざん意地悪をされた。それでも2年以上はこの仕事をつづけたという。それをやめたとたん、日本は戦争に敗れ、鉱山の日本人たちはソ連軍に連行されていった。
ひょっとしたら自分もシベリア送りになっていたかもしれないと思うと、何が幸いになるかわからない、と著者は書いている。
戦後は1年ほど無職だった。1946年になると、米軍政庁が日本人の資産を払い下げるという話を小耳にはさむ。さっそくソウル市草洞の200坪ほどの土地を買い取り、そこに「現代自動車工業社」の看板をかかげた。
自動車修理の会社だった。従業員は10人。これが現代財閥の発祥となった。
創業当時は米軍や役所の仕事がほとんどだった。そのうち建設の仕事のほうがもうかるという話を聞いた。そこで、自動車修理工場の建物に「現代土建社」という看板もつけ加えて、建設の仕事もやりはじめた。当初は米軍宿舎の新築や改修が主な仕事だった。もうけもたいしたことはなかったという。
1950年1月には、ふたつの会社を合併して、「現代建設」という名前にして、会社を南大門近くに移した。うまく大口の受注をとれば、建設はもうかるという実感をつかんでいた。
その矢先に朝鮮戦争がはじまる。著者は命からがらソウルを逃げだし、ようやく釜山にたどりついた。釜山で目にした政治家や軍人の姿には、あきれるほかなかった。しかし、米軍関係では、建設の仕事は山のようにあったのだ。
著者は米軍の仮設宿舎を造る仕事を請け負う。米軍が移動するとともに仕事は次々とはいった。国連軍がソウルを奪還したときは、ソウル大学の校舎を改造して、米軍司令部に造り替える工事も請け負った。だが、中国軍が参戦して、ふたたびソウルが陥落すると、家族、従業員ともどもまたも釜山に逃げだした。
2カ月後、ソウルが奪還される。ソウルに戻ると、仕事も増えてきた。現代建設はそのころ韓国で米軍が発注する工事をほとんど独占していたという。
1953年7月に朝鮮戦争休戦協定が結ばれ、米軍が撤退すると、現代建設の仕事は、政府関係のものが多くなった。最初に請け負ったのは、大邱と居昌(コチャン)を結ぶ高霊橋の復旧工事で、経験のない大工事のうえ、当時の猛烈なインフレのせいで、会社は大赤字を出し、あやうく倒産しそうになった。だが、このときの苦い経験が、その後の会社の発展に役立つことになる。
政府は現代建設を見捨てなかった。朝鮮戦争後は米国の援助資金で、復旧工事には事欠かなかったのだ。ダムや港湾、工場建設などを請け負って、会社は徐々に立ちなおっていく。米軍からは多くの建設機材を払い下げてもらった。
漢江人道橋の復旧工事も受注し、大きな利益を得ることができた。
韓国では、ふたたび駐韓米軍の増強がはじまっていた。現代建設は米軍から飛行場の滑走路舗装工事やドックの復旧工事を請け負う。そのさい著者はアメリカ式の仕様や品質管理などを学び、それをその後の企業経営に生かしている。
建設工事のたびにセメント不足を痛感した著者は、セメント会社の設立を計画する。だが、政府の許可がおりず、計画は頓挫。それでも、あきらめなかった。そうこうしているうちに朴政権が発足し、工場建設の許可がおりた。
現場主義が著者のモットーだという。時間の許すかぎり、たとえ日曜であっても、現場に足を運び、関係者を督励し、仕事の進展をチェックした。怠け者は嫌いだった。「適当主義で、各自に許された時間を大切にせず無駄に浪費するのは、愚かしい」という。
会社に怠け者はいらない、「本物の仕事人間」こそが韓国社会と国家の発展のために役立つというのが著者の信念だった。
「漢江の奇跡」がはじまろうとしていた。
アン・アプルボーム『権威主義の誘惑』(三浦元博訳)を読む(2) [本]
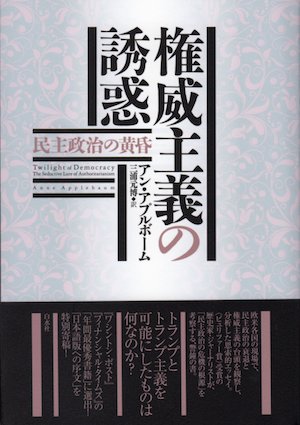
政治の変容は、経済的苦境とか不平等の増大によって理由づけられることが多い。しかし、著者によれば、いま人びとが権威主義的な考え方に引きつけられるのは、複雑さがいやになるからだという。人びとは意見の多様性に反発し、単純思考による解決を求めがちになっている。
たとえば外国人アレルギーをあおる反移民の言説もそのひとつだ。不平等や賃金低下への怒りをあおるスローガンも政治の波を引き起こすだろう。
それだけではない。いまではネットが、自分に都合のよい世界理解を促してくれる。「怒りが一つの習慣になる。不和が日常になる」。分極化が進んでいく。そこでは多様性や寛容より、単純さや結束、調和、均質性が求められるのだ。
ネット情報が広がる世界では、民主政治のルールにもとづいてコンセンサスをつくることよりも、「他者を強制的に沈黙させようとする欲求」のほうが強くなる。そうした傾向が権威主義を生むひとつの土壌になっていると著者はみている。
スペインではウェブサイトに人をひきつける映像を流すことで、極右のVoxという政党が躍進を遂げた。そこでは「スペインをふたたび偉大に」というフレーズがくり返されていた。
フランコ独裁政権が終わったあと、スペインではコンセンサスにもとづく民主政治が定着したかに思えた。だが、2009年の経済危機以降、スペインの政治は揺らぎはじめる。カタルーニャでは分離独立運動とその後の大混乱があった。そのあとYouTubeやツイッターなどを駆使して、「国民統合救済の愛国運動」を唱えるVoxが登場したのだ。
ヨーロッパの政治的な動きで、現在、注目すべきことは各国のナショナリスト政党が連携しはじめたことだ、と著者は指摘する。イスラム系住民への反発や、保守的で宗教的な世界観の推進、EUへの反対といった課題が、かれらを引き寄せている。
ここでもネットの果たしている役割が大きくなっている。数々の陰謀論やつくり話がユーザーを引きつけ、移民問題や汚職、イスラム教徒のうわさ、フェミニズム批判も大きな話題となる。
かれらが吹きこむのは愛国心であり、リベラル派を排除することである。
アメリカ建国の祖たちは、民主政治が専制政治に退行するのを防ぐには特別の措置が必要だと考えていた。自由民主主義が永遠に保証されていると思っていたわけではなかった。すべての人が生まれながらにして平等ではないこともわかっていたが、そうなるような体制をつくるよう努めていたのだ、と著者はいう。
いっぽう、左派は当初からアメリカ文明にたいして絶望的な見方を示し、この体制は芯まで腐っていると考えていた。反対にキリスト教右派は現代アメリカの世俗主義に失望し、社会はさらに悪くなるだろうと悲観していた。そうした雰囲気が強まると、極左と極右があらわれ、そのなかから過激な行動に走る者もでてくる。
著者によれば、ドナルド・トランプの出現は、思想的にはマルクス主義左派とキリスト教右派の結合によってしか説明できないという。それを代表する人物がトランプの政治顧問となったスティーヴン・バノンだ。バノンは公然とみずからをレーニン主義者と称していた。
トランプはビジネスの世界で生きてきた経営者だった。しかも、そのビジネスも必ずしも芳しいものではなかった。
著者に言わせれば、トランプは「アメリカの民主主義がすばらしいと思っていないため、諸国間の模範になろうと切望するようなアメリカには、まるで関心がないのだ」。
そこで、アメリカ・ファーストが唱えられる。さらに、トランプはアメリカの理想はまやかしだ、アメリカの政府機関は詐欺的だ、海外でのアメリカの行動は悪質だ、などと平気でいう。それが庶民に受けて、燎原の火をあおった。
トランプのアメリカには「民主政治と独裁政治の間になんら重要な違いを見ないアメリカがある」と著者はいう。トランプがあらわすのは、アメリカの文化的絶望感だ。
トランプはノスタルジーをかきたて、国民の一体性を求める。「このアメリカの一体性は、白い肌と一定のキリスト教理念、それに壁で囲まれ、守られる国土への愛着によって生まれるのだ」
冷戦終結後、ソ連が崩壊したあと、アメリカには一種の楽観主義がただよっていた。しかし、共通の敵がなくなると、反共主義者を結びつけていたきずなも崩壊してしまった。
保守グループは分裂した。そして、その一部がトランプ絶対支持に走ったのだ。かれらは終末論的悲観主義におちいっていた。ほんとうのアメリカ、真のアメリカが消滅しつつあるなら、それを救うために非常手段が必要になるかもしれないとまで考えるようになっていた。
著者はいまの時代が歴史的転換期だと感じている。そのため人びとは分断されている。
なぜいまふたたび愛国主義と権威主義が、理性的思考と法の支配を押しのけて、世界各地に広がっているのか。きわめて危険な状態だと言わねばならない。
パンデミックは何をもたらしたのか。国家権力が強化されたことはたしかだ。国境が閉じられるなか、理性的な論争は封印されがちだ。
著者はいう。
〈わたしたちはすでに民主政治の黄昏を生きている可能性がある。古代の哲学者やアメリカの建国の祖たちが恐れたように、わたしたちの文明はすでに無秩序と専制政治に向かっている可能性がある。反自由主義的・権威主義的理念の擁護者たちが権力を握る可能性がある。〉
そのいっぽうで、著者は「コロナウイルスが新しい世界的な連帯感を生むかもしれない」とも述べている。「全世界がロックダウン、隔離、感染の恐怖、死の恐怖という同じ経験をしたあとで、国際協力が拡大するかもしれない」
両方の未来がありうる。腹立たしいことに、それは確定していない、と著者はいう。先行きはむしろ暗いかもしれない。だが、機能不全におちいりがちな自由民主体制を維持するには、闇のなかを力を合わせながら慎重に進んでいくほかないというのが、著者の重い結論になっている。
アン・アプルボーム『権威主義の誘惑』(三浦元博訳)を読む(1) [本]
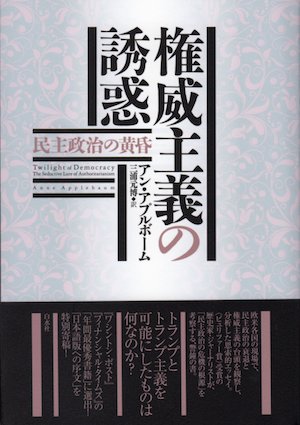
本書の内容はオビの紹介文に集約されている。
〈欧米各国の現場で、民主政治の衰退と権威主義の台頭を観察し、分析した思索的エッセイ。〈ピュリツァー賞〉受賞の歴史家・ジャーナリストが、「民主政治の危機の根源」を考察する、警鐘の書。〉
いま欧米各国で民主政治の危機が深まっていることが、このオビから伝わってくる。もちろん、それは日本も同じである。
アン・アプルボームはアメリカ生まれの女性ジャーナリストで歴史家。これまで日本で訳された歴史書としては、『グラーグ』と『鉄のカーテン』(山崎博康訳)が知られている。
みずからの政治的立場を中道右派だと公言する彼女の生活拠点は、半分ポーランドにある。夫のラデック・シコルスキは、一時ポーランドの中道右派政権で外相を務めていた。
ここで政治的スペクトルを頭にえがいてみよう。
分布図を考えてみる。両端には左右の全体主義、そして中道はそれにはさまれるかたちで、真ん中に位置する。
その中道は左派と右派にわかれる。中道左派がいわば社会民主主義の立場だとすれば、中道右派は自由民主主義を唱える。中道派の政治は、対話と説得を原則としており、自由で公平な選挙がその政治的正統性を保証する。中道左派と中道右派のあいだでは、少なくとも討議が成り立つだろう。
これにたいし、全体主義は一党独裁を原則とする。左の全体主義はインターナショナリズムの共産主義、右の全体主義はウルトラナショナリズのファシズムといってよいだろう。どちらも国内的には、イデオロギーを押しつけ、言論の自由を抑圧し、反対派を監視する体制をとる。そして、対外的には、他国にたいし攻撃的、拡張主義的な姿勢をつらぬく。ともに問答無用の強権体制だといってよい。
権威主義は中道主義から全体主義に向かう中間に位置すると考えられる。権威主義は、権力政治、統制政治を目指している。権威主義のもとでも反対党の存在はいちおう認められているが、その存在感はできるかぎり弱められている。政府は露骨な人事干渉をおこなって、政府機関だけではなく、テレビ局や新聞社、学術団体などを意のままに動かそうとする。
もちろん、こうした図式はあくまでもイメージである。現実の政治は図式どおりにはいかない。
とはいえ、あきらかにいまの政治は、いい方向に進んでいない。1989年に冷戦が終わり、世界じゅうが自由と民主主義を謳歌する時代がはじまると思われていたのもつかのま、21世紀にはいると世界の政治は権威主義と統制主義、管理主義の傾向を強めている。
いったい、なぜそんなことになったのか。
本書の第1章は、1999年の大晦日にポーランドの著者の家で開かれたささやかなパーティの場面からはじまる。
パーティにはロンドンやモスクワのジャーナリスト、ワルシャワ駐在の外交官、ニューヨークの友人など、それに夫の友人たちが集まった。多くがポーランド人で、大多数は自由主義者だったという。そのときは、だれもが民主主義と繁栄の将来が約束されていると思っていた。
それから20年、著者によれば、多くの友人たちが考え方を変え、ポーランドの極右政党「法と正義」を支持するようになっている。「法と正義」は2015年の選挙で、僅差ながら単独過半数をとると、その本質をあらわにした。
自分たちに批判的なジャーナリストや公務員、裁判官、軍人などを解雇し、反ユダヤ主義をむきだしにし、LGBTを攻撃し、さまざまな陰謀論を流して人びとをまどわすようになったという。
こうした傾向はポーランドにかぎらない。
なぜいま政治の世界で民主主義が凋落し、デマゴーグに満ちた権威主義が大手をふるうようになったのか。新右派の台頭が意味するものは何か。それを探るために、著者はヨーロッパやイギリス、そしてアメリカの新世代の知識人と会って、話を聞くことにした。
民主政治では、民主的な競争によって選ばれた人に国の統治をゆだねるのが通常のスタイルである。しかし、一党独裁国家においては、党に忠実な者が統治を担うことになる。
民主政治のもとでは、知識人は自由に自分の意見を述べることができる。これにたいし、独裁政治下での知識人の役割は指導者を擁護することだ。それによって、かれは褒賞と昇進を期待することができる。
いまポーランドでは「法と正義」、ハンガリーではオルバーンの率いるフィデスという反自由主義政党が、党員に利得をばらまく利権政治をくり広げている。ポーランドやハンガリーだけではない。旧共産主義諸国では、いまや愛国主義に裏づけられた一党独裁政治への誘惑が強まっている、と著者は懸念する。
「法と正義」は2001年にレフ・カチンスキによって設立され、現在は双子の兄のヤロスワフ・カチンスキ(2006〜07、首相)が党首を務める。レフ・カチンスキは大統領時代、カティンの森事件追悼記念式典に出席するため、ロシアに向かう途中の飛行機事故で2010年に死亡した。
著者によれば、カチンスキ兄弟は「陰謀家、策士、共謀の考案者」だという。
2015年、ヤロスワフ・カチンスキはポーランド国営テレビの社長にヤツェク・クルスキを据えた。そのあと著名なジャーナリストは解雇され、ニュース報道は歪められた。中立性の装いはかなぐり捨てられ、党の意に沿わない人びとへの攻撃がはじまった。
共産主義とファシズムの時代の「大デマ宣伝」とちがって、現代のプロパガンダは、マーケティング技術やソーシャルメディアも活用した「Mサイズのデマ」を通じて、丹念に練りあげられている、と著者はいう。それをフルに活用したのがドナルド・トランプだが、こうしたプロパガンダはポーランドやハンガリーでもしきりにくり広げられているらしい。
たとえば、ハンガリーでは、ハンガリー系のユダヤ人億万長者のジョージ・ソロスが国を破壊しようとしているといううわさが流されていた。ポーランドでは、ロシアでの追悼イベントに向かう大統領の飛行機が墜落したのは、何らかの陰謀のせいだという情報がまことしやかに流布された。
こうした陰謀論は、愛国心を刺激し、権力への支持を強化する方向に練りあげられていた。複雑な現象をごまかしで説明し、その単純さによって人びとの情緒に訴える力をもっていた。
ハンガリーのオルバーン政権は、科学アカデミーを政府の管理下に置くとともに、テレビ局や雑誌社を支配し、狭量なナショナリズムをあおっている、と著者はいう。
ヨーロッパの民主政治の危機は、旧共産主義国に特有な「東」の問題ではない。「その波はごく最近、この十年にわき上がってきたのだ」。なぜ、こうした現象が生じてきたのだろうか。
ギリシャのある政治学者は、著者にリベラルな民主政治こそがむしろ例外で、権威主義的な寡頭政治こそが一般的傾向だと話した。だが、歴史は循環するものだと構えているだけではすまないのではないか。
民主主義や能力主義、経済的な競争こそがもっとも公平な選択肢だという考え方にたいして、権威主義は国家や集団への帰属、結束と調和を強調する。そして、時にそうしたプロパガンダは人びとの感情を刺激し、客観的な理性を凌駕してしまう。
ここで、ボリス・ジョンソンの話がでてくる。
ブリュッセルで著者と会ったころ、ジョンソンは『デイリー・テレグラフ』の記者で、EUをからかったり攻撃したりする記事をさかんに流していた。でっちあげも平気だったという。
そのころ、イギリスでは、かつての栄光へのノスタルジーが広がろうとしていた。マーガレット・サッチャーが支持された背景には、そんな国民感情もあったのではないか、と著者はいう。
イギリスは特別で優位に立っているという感情。それがEUの単一市場への懐疑を生んでいた。EUはイギリスにルールを押しつけているわけではなかった。むしろ、それがイギリスに有利な条件も多かった。にもかかわらず、イギリスはEUに何かおもしろくないものを感じていたのだ。
そんななか、ジョンソンは政界に乗り出し、ロンドン市長となり、ついに首相の座を勝ちとることになる。
ロンドン市長のころは「EU離脱なんてだれも真剣に望んでいないよ」と話していたのに、国民投票キャンペーンではブレグジットを選んだ。ほんきでそうなるとは思っていなかった。もし、事態が正常に推移し、ブレグジットが選ばれなければ、おどけ者のボリス・ジョンソンが首相になることは、けっしてなかっただろう、と著者はいう。
著者によれば、ノスタルジアには二種類ある。ひとつは内省的ノスタルジアで、過去を懐かしむタイプ。もうひとつは復古的ノスタルジアで、過去の栄光を取り戻したいと願うタイプ。やっかいなのは復古的ノスタルジアのほうで、これを信奉するやからは、平気で陰謀論やうそをばらまき、進歩派を攻撃しつづける。12年間、ブレアの労働党政権がつづくなか、イギリスでは復古的ノスタルジアのマグマがたまっていた、と著者はいう。
そして、こうした復古的ノスタルジアの攻撃ターゲットになったのがEUだった。ヨーロッパとの戦いは、イングランド・ナショナリズムを呼びさました。
EUを離脱すればさまざまなメリットが得られる、EUにとどまればトルコ人を受けいれなければならなくなる、EUを離脱すればイギリスは立て直せる、イギリスは民主政治を守るためにEUを離脱しなければならない。キャンペーン中は、そんなうそやでたらめが平気で流されていた。
だが、実際にブレグジットが決まったあとは混乱がおとずれた。離脱キャンペーンの主張はことごとくまちがっており、離脱のプロセスは容易ではなく、離脱のコストは当初の予想よりはるかに大きかった。
ボリス・ジョンソンは首相の座につくと、議会を停会にしたり、リベラル派保守党員を追放したりして、強引にブレグジットを推し進めた。そして、いまやイギリスの民主政治を踏みにじるような権威主義的な改革に乗り出そうとしている、と著者はいう。
危険な権威主義の流れはますます広がっている。
もう少し、読み進めてみよう。
第2波の襲来──速水融『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』散読(4) [本]

1919年暮れから20年春にかけ、スペイン・インフルエンザの第2波(「後流行」)が襲来した。
日本でもっとも早く流行がはじまったのは、9月中旬の熊本県で、10月下旬から12月にかけ九州全県に広がり、沖縄県でも12月上旬に感染がみられるようになった。そのころ、すでに感染は全国におよんでいる。
前年の第1波にくらべると、感染者数は比較的少なかった。だが、予防の手がなく、悪性がいっそう猛烈で、死亡率が高いのが特徴だった。
このときも軍隊が大きな発生源となった。佐世保の海兵団、対馬の海軍部隊、小倉や久留米の部隊、呉軍港、広島の第5師団、豊橋の第60連隊、新潟の連隊、東京の近衛師団、弘前の第8師団、その他列挙しきれないほど、各地の軍営から数多くの感染者と死者がでている。
第2波襲来を受けた日本全国の詳しい状況については、本書を読んでいただくしかない。ここでは、東京近辺と京阪神地方にしぼって、当時の状況を紹介しておく。
京阪神地方でインフルエンザ患者がみられるようになったのは1919年12月半ばごろからである。流行がはじまると、神戸市内ではすぐに死者がではじめ、12月16日から27日までの12日間で死者数は294名に達している。姫路の師団でもインフルエンザは猛威をふるい、1920年1月5日までに36名の死者がでている。
12月はまだ序の口だった。死者が増大したのはむしろ年明けからである。大阪市内の死者は1日で一挙に370名あまりに膨れあがり、そのうちの半数がインフルエンザによる死者だった。
神戸市の鐘紡では女工5000名のうち1321名が発病し、35名が死亡した。神戸市内の死者は1月半ばに1日あたり200名を突破したが、学校の休校措置がとられたのは1月24日になってからである。マスクは全住民に行き渡らず、全警察官に配るのが精一杯だった。流行がようやく下火となるのは1月末をすぎてからである。
京都でも1月中旬から、京都日出新聞が流行性感冒による死亡者続出の記事を流しはじめていた。死亡者の年齢は20歳以下が多かった。市内の小学校は1月17日から10日間、休校となった。1月下旬に流行は市内から郡部へと拡散、多くの町や村で患者と死者がでるようになった。たとえば伏見町では359名が罹患し、61名が死亡している。
しかし、京都でも市内、府下とも、インフルエンザは2月から下火となる。といっても、完全に終息したわけではなく、4月まで患者、死者は発生した。流行が下火になると、増産されたマスクは売れ残り、業者や薬局で「持ち腐り」になったという。
東京でも第2波(「後流行」)の襲来は、1919年末から1920年2月にかけてだった。
1919年12月11日の読売新聞は、流行性感冒が近衛連隊を襲ったという記事を掲載している。18日の段階で、近衛師団の罹病者は1137名、死者は29名となった。
このころ、東京市内では、山の手も下町もインフルエンザが猛威をふるい、山の手だけでも患者が約3000名を数えるほどになっていた。
死者が増えるのは年明けからである。三河島火葬場では遺体が処理しきれなくなるほどだった。1月中旬の東京朝日新聞は、市内の1日の死亡者が100名に激増し、1日以来の感冒患者総数が実に9万人にのぼっていると伝えている。地獄の3週間がはじまっていた。
東京での死者のピークは1月19日だった。1月末になると、新規感染者の数は急速に減少し、死者数も徐々に減っていく。だが、19日の死者337名という数字は、人びとを震撼させた。看護婦は流感の猛威に押しまくられて、疲れに疲れ、とてもたりなくなっているとの記事もみられる。
著者はいう。
〈この時期に東京に住んでいた者は、文字通り生きた心地はしなかったであろう。当局は当時としては派手な、カラー版のポスターを何種類も作成して各府県に配布したし、新聞紙上ではあれこれ予防・治療の記事が多く掲載されたが、どれ一つ実際の沈静化に役立つものはなかった。ただ「時間」だけが有効で、2月に入ると統計に見るように流行は下火に、死亡者は減少に向かった。〉
著者の集計によると、第2波(「後流行」)による全国の死者数は18万6673名にのぼった。第1波の26万6479名に比べると数は少ないが、第2波のときのほうが、感染者にたいする死者の割合(死亡率)はずっと高かった。
「人類とウイルス、とくにインフルエンザ・ウイルスとの戦いは両者が存在する限り永久にくり返される」と、著者は記している。
今回のコロナ・ウイルスの場合も、戦いは半年やそこらで終わると考えないほうがいいだろう。
軍隊とインフルエンザ──速水融『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』散読(3) [本]

軍隊とインフルエンザの蔓延には深い関係がある。100年前にパンデミックが発生したのは、アメリカでインフルエンザにかかった米軍兵士がヨーロッパ戦線にウイルスを広げたことが大きな要因となった。密集、密接、密閉は軍隊につきものの環境であって、しかも移動がともなったから、軍隊はインフルエンザにとって格好の拡散器となった。
日本でよく知られるのは二等巡洋艦「矢矧(やはぎ)」のケースである。
著者によると「矢矧」は1917年2月に呉を出港し、2年近く行動したあと、1919年1月末に呉に帰投している。第1次世界大戦にともなう艦船行動だったが、そのかん一度も戦闘には加わっていない。ドイツ太平洋艦隊がすでにこの海域から追われていたからである。
「矢矧」はオーストラリア、ニュージーランド海域をいわば親善大使のように周航し、基地としていたシンガポールに戻り、内地から派遣される「千歳」と交代することになっていた。
シンガポールに戻ったのは、1918年11月9日のことである。「千歳」の到着が遅れたため11月30日までシンガポールに停泊した。その間、11月11日に第1次世界大戦は終結した。
「矢矧」の艦長は11月21日と22日に、乗組員の半舷上陸を許した。ところが24日になって、熱性患者が4名発生する。28日には、10名が同じ症状を示していることがわかった。通常の風邪と思われていたが、じつはこれがインフルエンザだった。
「千歳」の到着を受けて、「矢矧」は予定どおり、11月30日午後4時にシンガポールを出港し、マニラに向かった。艦には469名が乗り込んでいた。12月1日には69名に熱症状がでる。さらに2日には新たに50名が発熱し、もはや隔離は不可能となった。3日には看護手も軍医長も寝込んでしまう。そんななか、「矢矧」は速度を落として、のろのろとマニラに向けて南シナ海を進んでいった。
幸いだったのは、「矢矧」にシンガポールから日本に帰る便乗者がいたことだ、と著者は書いている。かれらはなぜかインフルエンザの免疫をもっており、そのなかにひとりの軍医がいたことが救いになった。こうして、ようやく「矢矧」は12月5日にマニラに到着する。この時点で、469名(うち便乗者11名)のうち約65%にあたる306名が感染していた。
到着後、重傷者はセントポール病院に入院した。だが、ほっとしたのもつかの間、7日には病院で1名が死亡する。死亡者はその後もつづいた。12月12日の時点で、死亡は累計で35名を数えた。けっきょく、12月20日までに、マニラ到着以前の1名を加え、計48名の死者をだすことになる。
「矢矧」は2019年1月20日にようやくマニラを出港し、30日に母港の呉に戻ってきた。2月1日には呉鎮守府練兵場で合同葬儀がおこなわれた。
インフルエンザに見舞われたのは「矢矧」だけではなかった。砲艦「最上」は2018年10月上旬、寄港地ペナンで、180名の乗員のほとんどがインフルエンザにかかり、17名が死亡している。
ドイツのUボートによる攻撃からイギリスとフランスの輸送船を守るために地中海に派遣された日本の第二特務艦隊(旗艦と駆逐艦8隻)からも、インフルエンザによる死者がでている。
シベリア出兵もインフルエンザとは無縁ではなかった。ロシアのボリシェヴィキ政権を打倒するため、1918年8月、日本はシベリアに兵を送った。出兵当初はまさにインフルエンザの流行期と重なったため、多数の兵士が感染し、命を落としている。
次に内地に目を転じると、陸軍病院における「流行性感冒」の患者総数と死者数は1918年が8万471人(85人)、1919年が2万1733人(646人)、1920年が3万7698人(1123人)と記録されている(()内が死者数)。しかし、実際の死者数は、呼吸器系疾患やその他による死者数を含めるともっと多かっただろう、と著者はいう。
海軍の病院でも、状況は陸軍の場合とさほど変わらない。患者は1918年に増加し、1920年には減少している。インフルエンザの患者総数と死者数は1918年が1万6465人(111人)と急増し、1919年が5153人(218人)、1920年が3238人(53人)となっている。海軍でも、呼吸器疾患その他による死者数を含めると、インフルエンザによる死者数は実際にはもっと多かったと推測される。
当時の新聞は昭和期の戦争報道とはちがい、軍隊での病気の蔓延をことこまかに報道している。流行性感冒の原因が、兵舎の通風、換気、採光にあるという的確な疑問を投げかけた新聞もあった。
当時は徴兵制で、陸軍では12月1日が新兵の入営期日だった。それを機として、兵舎では新兵に多くの感染者と死者がでた。志願制の海軍とを併せると、日本では、陸海軍で毎年7〜8万人が新兵になっていた。
著者はいう。
「当時の軍隊は、日本だけではなく、どこでも感染症流行の温床となる危険を秘めた存在であった」
そして「日本では、海外派遣の海軍艦艇やシベリア出兵時の罹患死亡者もさることながら、入営した新兵が入営後まもなく罹患し、死亡する者が少なくなかった」。
当時は軍隊がインフルエンザの温床であったことを頭にいれておこう。そして、次回は最終回として、1919年暮れから翌年春にかけての第2波(後流行)の状況をみておくことにする。
パンデミックが1年で終わると信じるのは、ほとんど妄想に近い。
本格的な流行は秋から──速水融『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』散読(2) [本]

1918年4月、日本でも巨大インフルエンザの先触れとなる小流行がはじまった。インフルエンザの流行は毎年のことなので、このときはだれもがさほど気にしなかった。
むしろ話題になったのは台湾に巡業中の大相撲の力士がインフルエンザらしきものに感染し、3人が死亡したことである。38度から40度の発熱があり、5日ほどで快方に向かうのが、インフルエンザの一般的な症状だった。新聞は台湾北部の基隆(キールン)と対岸の香港にそうした熱病の流行がみられると報じている。
日本国内では、5月初旬、横須賀軍港で軍艦「周防」に150名余の患者が発生した。中旬には保土ケ谷の富士瓦斯紡績工場で多数の工員が感染。そのころ東京市内でもぼつぼつ患者がではじめている。
このときのインフルエンザは、相撲の力士が数多く感染し、夏場所の休場者が多かったため、「角力(すもう)風邪」と呼ばれるほどだった。
6月から7月になると、近衛師団を含め、東京、仙台、金沢、松本、弘前、青森など、軍の各連隊で4000人以上の感染者がでた。感染率は非常に高かったが、死者はほとんど出ていない。
6月に衛戍(えいじゅ)病院[陸軍病院]に収容されたインフルエンザ患者数は3万人以上、海軍病院もほぼ同様だった。しかし、流行はこれでほぼ収まり、7月下旬には収束に向かっている。
日本で本格的な流行がはじまったのは、それから2カ月後、1918年9月下旬になってからである。
春が先触れにすぎなかったとすれば、このときの本格的な流行を第1波としてもよいだろう。もちろんこれを第2波と理解してもよいのだが、ここではこれを第1波と解釈して話を進めることにする。何せ、先触れとこのときとでは、感染者も死者も桁違いに数がちがいすぎるからである。
名古屋の『新愛知』(現在の中日新聞の前身)は、9月20日に日紡大垣工場で感冒が発生したと伝えている。さらに9月26日には大津の歩兵第9連隊に400名の患者が発生したと報じた。
10月12日の『読売新聞』には、山口県厚狭郡高千帆小学校(現山陽小野田市)の児童60名が39度以上の高熱を発し、鼻血を出しているという記事が掲載されている。
各地の新聞をみると、10月半ば以降、全国でインフルエンザ患者が増え、死者が続出したことが判明する。滋賀県や愛媛県、京都市でも、小中学校児童が数多く感染し、学校が閉鎖された。西日本からはじまった流行は、短期間のうちに、東日本、北日本に広がったとみられる。
本書には、全国の様子が事細かに追跡されているが、ここでは大阪・東京近辺だけに話を限ることにしよう。
大阪市内では10月29日に多くの小学校が休校となり、市電運転手2000人のうち450人が欠勤したことが報じられている。
同じころ、京都では西陣の職人の欠勤が相次ぎ、病院の看護婦の過半が感染し、治療に困難をきたしていた。11月にはいると、死者数は急速に増える。その大半が20歳から40歳までの壮年男女だった。
死者の増加により、大阪市では火葬場が混乱し、遺体が処理しきれなくなった。11月5日には大阪市内の全小学校が休校となった。
大阪市内の死者は11月12日がピークで419人に達した。なかでも学校教員の死者が多かった。
火葬場の混乱は神戸でも同様で、遺体が処理しきれず、棺桶が放置されるままになっていた。
京都、大阪、神戸でも、インフルエンザは10月20日ごろから流行しはじめ、11月半ばまでの約1カ月間、猛威をふるったとみてよいだろう。そして、12月になって少し落ち着いたあと、ふたたび1919年2月ごろからぶり返し、2月末、ようやく小康状態になった。
東京では、10月24日の各紙が流行性感冒の襲来を告げている。青山師範学校や小石川の女子師範学校も休校となっていた。
10月25日、内務省は全国に「西班牙(スペイン)風邪」に注意するよう警告をうながし、各地で「適当な処置を講じられたし」と伝えている。とくにはっきりとした指針は示されなかった。
東京市内では、インフルエンザの流行により、学校の休校が増え、遠足が中止になった。職場の欠勤者も多くなり、交通機関や通信に影響がではじめた。死者が目立つようになるのは、11月にはいってからである。砂村、町屋、桐ヶ谷、落合の火葬場は満杯となった。
11月5日には劇作家の島村抱月が、仕事場にしていた牛込の芸術倶楽部でインフルエンザのため死亡した。そして、翌年1月には恋人の松井須磨子が後追い自殺をするという悲劇を生むことになる。
11月になると、東京朝日新聞や都新聞などが、感冒による死者が増えていると報じるようになる。インフルエンザはすでに10月からはじまっていた。著者は「むしろ、新聞各紙が何も書かなかったことに作為を感じる」として、政府による何らかの情報統制があったことを示唆している。
11月下旬になると、流行は下火になった。都新聞は11月上旬に1日平均230−40人あった東京市内の死者数が、下旬には150−60人に減ったと伝えている。
10月以来、猖獗(しょうけつ)を極めたインフルエンザは東京でも12月にはいっていったん落ち着いたかにみえた。しかし、年があらたまると、ふたたび再燃する。より重大なのは、インフルエンザから肺炎に進み、亡くなる人が増えたことである。1月下旬には「盛り返した流行性感冒」といったような記事が数多くみられる。
2月3日の東京朝日新聞は、最近2週間で東京府下で1300名が死亡したと伝えている。各病院は満杯となり、新たな「入院は皆お断り」という状態だった。都新聞は、感染者の年齢が15歳から40歳であること、看護婦が払底していることを報じている。
こうした事態に東京府、東京市は「何をすべきかわからなかった、というのが実相であろう」と著者はコメントしている。警視庁当局はなすすべなく「茫然として居る」と、当時の時事新報も断じていた。
東京市長は2月5日に告諭を発し、室内や身体の清潔維持、人混みを避けること、うがいの励行、患者の隔離を奨励している。病院に行けない細民に無料の治療券を配布したり、医薬の給付をおこなったりもしている。しかし、劇場や映画館などの閉鎖はおこなわなかった。
著者は1918年秋から翌年春にかけての、この第1波(「前流行」)に関して、こんなふうにまとめている。
〈嵐のように襲来した「前流行」は、公式統計だけでも2116.8万人の罹患者、25.7万人以上の死亡者を出し、約半年にわたって暴れまわった後、いずかたともなく消えてしまった。春の到来という季節上の変化もあったろうし、多くの人が罹患し、ウイルスへの免疫抗体を持つようになった結果かもしれない。何せ病原体さえ分からなかった当時のことなので、予防や治療の結果でなかったことだけは確かである。用いられた薬も、中には肺炎の予防・治療に効くものもあったかもしれないが、流行性感冒そのものには無力だった。むしろ死亡者がこれだけで済んだのが幸運だったと考えてもいいだろう。〉
日本での第1波(「前流行」)の感染率は、国民全体の38%と、きわめて高かった。これにたいし、死亡率は12.1パーミル、すなわち1.21%となぜか低かった。人混みに出るな、手洗い、うがいをせよ、衣類・寝具を日光消毒せよといった注意を励行したことが案外きいたかもしれない、と著者も認めている。
「しかし、どこかに潜んだウイルスは、次の出番を静かに待っていたのである」。第2波が到来するのは必至だった。
第2波はくるのか──速水融『日本を襲ったスペイン・インフルエンザ』散読(1) [本]

100年前のパンデミックに関連して、少し前に本ブログで、ジョン・バリーの『グレート・インフルエンザ』の内容を紹介した。
だが、『グレート・インフルエンザ』には、日本のことは書かれていない。
はたして、あのとき日本ではどのようなことがおこっていたのか。
それを知りたくなり、ようやく本の貸し出しをしてくれるようになった図書館で、この本を借りてみた。次の予約がはいっているので、2週間以内に返却しなければならない。詳しくは読めないが、気になったところだけでもと思い、メモをとりはじめた。
夏になって、2月以来の新型コロナウイルス騒動は、ようやく一段落した感があるが、心配なのははたしてことし秋から冬にかけての第2波があるのかどうかということだ。
スペイン風邪と呼ばれることが多かった約100年前のインフルエンザ(当時の言い方では流行性感冒)と、今回の新型コロナを同等にみるわけにはいかない。インフルエンザとコロナはちがうかもしれない。それでも、かつての記録は何かの参考になるはずだ。
1918(大正7)年から20(大正8)年にかけて、日本の状況はどうだったのか。
当時は大日本帝国の時代である。帝国は内地と外地に分かれていた。内地の人口は1920年で約5600万人。加えて、日本が台湾と朝鮮を植民地とし、樺太を領有し、関東州を租借していたことを頭にいれておく必要がある。満州国が誕生するのは、もう少し後の1932年だ。
有名な歴史人口学者である著者は、100年前のインフルエンザをいちおう「スペイン・インフルエンザ」と呼んでいる。とはいえ、前にも書いたように、このときのインフルエンザの発生地は、スペインではなく、アメリカのカンザス州だったと思われる。時期はおそらく1918年1月。主に第1次世界大戦中の兵士の移動によって、全世界に広がった。2年にわたって猛威をふるい、そのときの死者は最低限で見積もっても4000万ないし5000万人といわれる。
もちろん、インフルエンザは日本にもやってきた。著者はそのときの日本での流行を3期にわけてふり返っている。すなわち、
(1)1918年4月─7月(先触れ)
(2)1918年秋─1919年春(前流行)=第1波
(3)1919年暮─1920年春(後流行)=第2波
日本でインフルエンザの本格的流行がはじまるのは1918年秋からである。その年の4月から7月にかけても先触れがある。『グレート・インフルエンザ』のジョン・バリーによると、このときのインフルエンザ・ウイルスは5月に上海に到着していたという。だから、これを第1波としてもよいのだが、1918年春から夏にかけての流行は例年とさほど変わらず、死者数も急増したわけではない。
そこで、ここでは1918年秋からの本格的流行を第1波とし、春の流行は先触れと理解しておくことにしよう。先触れから2、3カ月後、本格的な第1波がやってくる。
インフルエンザの大流行は第1波だけでは収まらなかった。第1波の流行から7カ月後、おそれていた第2波がはじまる。先触れから数えれば、このとき日本は約2年にわたって、インフルエンザの波に2度、数え方によっては3度襲われたことになる。
内務省の資料では、日本内地における第1波の患者は2116万8398人、死者は25万7363人、第2波の患者は241万2097人、死者12万7666人となっている。合計すると、患者2358万495人、死者38万5029人となる。
第1波にくらべて、第2波の患者数はずっと少ないが、患者にたいする死者の割合は第2波のほうがずっと高かった。
いずれにせよ、この内務省の資料にもとづいて、日本でのスペイン・インフルエンザによる死者数は約38万5000人という数字がまかり通っていた。
だが、著者はこの死者数は過小評価だと明言する。統計上の不備があるうえに、隠れた死者数があるからだ。そこで、著者は例年と比較した超過死亡者数をもとに、スペイン・インフルエンザによる死者数を割りだし、それを月別、男女別、主要都市別、道府県、内地・外地にわけて、新たに計算しなおしている。
その手法を紹介するのはやめておく。詳しい統計を示すのもわずらわしい。著者が計算しなおした1918年から20年にかけてのインフルエンザによる死者数だけを以下に示しておく。
日本内地 45万3452人
樺太 3749人
朝鮮 23万4164人
台湾 4万8866人
総計 74万231人
なお、このかん帝国内の人口は減っておらず、むしろ増えている。出生率が死亡率よりはるかに高かったからである。インフルエンザの流行は日本の人口を減少させるものではなかった。とはいえ、内地だけでも45万人以上が亡くなったというのは、やはりこのインフルエンザがただごとではなかったことをうかがわせる。
歴史はくり返すわけではない。歴史を知るのは同じことをくり返さないためである。そして、できれば善きことを学ぶためである。
だが、自然災害だけはくり返しやってくる。おそらく、今回のパンデミックも第2波、場合によっては第3波がやってくるだろう。
それにどう対応するか。
100年前、日本で何がおこっていたのかを、本書から学ぶなら、何らかの教訓が得られるかもしれない。
以下はその簡単なまとめである。
終息までの試練──『グレート・インフルエンザ』を読む(4) [本]

1918年10月、町は死と恐怖、静寂に包まれていた。
第1次世界大戦はまだ終わっていない。
「政府が『士気』を保持しようとしたことがかえって恐怖を助長した」、「マスコミは病気を軽視することで恐怖を与えた」と、著者は記している。
アメリカでは中部のアイオワ州やアーカンソー州の陸軍キャンプでも、何百もの兵士が死亡していた。
それでも新聞は、恐れるな、臆病者が最初の犠牲者になるなどと伝えていた。
ロサンゼルスでは、学校や教会、劇場など人びとが集まる場所が閉鎖された。
シカゴの市当局は、世間の士気をそこなうようなことをしてはならないと対策には消極的だった。新聞も「恐れてはいけない」という大きな囲み記事を流した。しかし病院は患者であふれ、多くの人が死亡していたのだ。
アリゾナ州フェニックスでも、新聞は楽観的な記事を流していた。ところがいったん地元で感染者がでると、その後はまったく何も報じなくなる。パニックを抑えるためだったという。
しかし、風のうわさで真実は伝わる。
国の公衆衛生局は、新聞を通じて、全国に次のようなアドバイスを伝えた。清潔にして、栄養のある食べ物を食べること、具合が悪くなったら、すぐにベッドにはいり、よくなるまで数日寝ているこ。そして、その記事はかならず「怖がってはいけない」というメッセージで結ばれていた。
だが、アメリカのどこにいようと、インフルエンザ・ウイルスは忍び寄ってきた。
〈ウイルスは西へ東へ、東海岸から水路と鉄道を通じて移動した。大きな山となって盛り上がって町に氾濫し、大きな波となって町をなめつくし、荒れ狂う川となって村に襲いかかり、水かさを増した小川になって集落を流れ、小さな流れとなって点在する家に流れ込んでいった。そして大きな洪水のようにすべてを覆うと、まちまちの深さとはいえ、とてつもない広がりとなってその地に居座った。〉
1918年のアメリカでのインフルエンザの広がりを、著者はそんなふうに詩的に表現している。
だれもが息をひそめていた。握手もできなかった。人は恐ろしいほどあっけなく死んでいった。社会生活は崩壊した。
アリゾナ州フェニックスでは、自警団が結成され、マスクをつけていない者や口をおおわずに咳をする者を逮捕し、開けている店を見回り、町にはいる道路を遮断して回った。
戦争は終わりかけていた。しかし、インフルエンザの恐怖は覆いかぶさったままだった。
インフルエンザがひろがったのは、もちろんアメリカだけではない。殺人ウイルスは世界を駆け巡った。
世界各地で多くの治療法が提案され、また実施されていた。なかには民間治療法や詐欺まがいの治療も見られた。新聞にはさまざまな広告があふれた。
10月半ばになると、さまざまなワクチンが登場する。だが、どれが効くかはだれにもわからなかった。すべてが試された。そして、有効な特別治療法はないという結論に達した。
ウイルスは人のいるところを求めて、地の果てにまで達した。アラスカでもイヌイットのあいだで感染がひろがる。大陸の反対側のラブラドルでも、総人口の3分の1が死亡した。
アメリカ先住民、太平洋諸島の人びと、アフリカ奥地の人びとのあいだにも感染がひろがっていた。
フランクフルトでは感染者の27%が死亡した。パリの死亡率は10%だったが、合併症を発症した場合は50%が死亡した。
リオデジャネイロの感染率は33%、ブエノスアイレスでは人口の55%がウイルスに感染した。
日本でも3分の1以上の人口が感染、内務省の発表では30万人以上が死亡している。しかし、実際の数字はもっと多かった。速水融の調査では、日本の内地だけで45万人、当時植民地の朝鮮、台湾をあわせると帝国内で74万人が死亡している。
ロシアとイランでは、人口の7%がこのウイルスで死亡した。
中国でも人数は不明だが、大勢の人が死亡したことはまちがいない。重慶では町の人口の半分以上がインフルエンザにかかった。
いちばん犠牲者が多かったのはインドである。おそらくインド全体で2000万人に近い死者がでたと見られているが、その数はもっと大きかったかもしれない、と著者はいう。
とはいえ、インフルエンザ・ウイルスにも自然のプロセスがはたらく。
1918年のウイルスは、おそらくアメリカのカンザス州で、動物の宿主から人間にはじめて飛び移った。そして、ウイルスは人から人へ移るにつれて、新しい宿主に適応し、感染力を増していった。
ここで、もうひとつの自然のプロセスがはたらきはじめる。それが免疫である。ウイルスが一度ある人口集団を通過すると、その人口集団はある程度免疫を獲得し、同じウイルスに再感染しない。
免疫ができるまでの期間はおよそ6週間から8週間である。その後は爆発的な発生はやみ、感染は突然おさまる。
1918年のウイルスはパンデミックを引き起こした。春にはまだ弱かったウイルスが、秋の致命的で爆発的なウイルスへと変異していったためである。
しかし、この殺人的なウイルスはさらに変異して、次第に弱まっていった。いちばん早く襲われた地域がもっとも死亡率が高く、流行が遅かった都市は、一般に死亡率が低かったという。
ウイルスがもっとも凶暴だったのは1918年10月の第2波だった。つづいて12月ごろには第3波がやってくる。ウイルスはまたも変異し、多くの人が感染し、またも多くの死者をだした。だが、その死亡率は第2波のときより大きくなかった。
1919年春になっても、インフルエンザの余韻はつづいた。
戦争が終わり、パリでは講和会議が開かれていた。このころになっても、パリでは10月のピーク時の半分にあたる2500人以上がインフルエンザで死亡していた。
4月はじめ、アメリカ大統領のウィルソンはインフルエンザにかかり、高熱を発した。5日ほどで快復するが、その後、精神的に不安定になり、ふだんの思考の弾力性を失ってしまう。フランスの示した対ドイツ強硬案にずるずると引きずられていくのだ。
もし、ウィルソンがインフルエンザにかかっていなかったら、ヴェルサイユ条約はずいぶんちがったものになり、アドルフ・ヒトラーの出現を許すこともなかったかもしれない、と著者は想像の羽を伸ばしている。
1919年秋になると、インフルエンザは完全に過ぎ去ったかのようにみえた。しかし、そうではなかった。
1920年春にも猛烈な勢いでぶり返す。ニューヨークとシカゴでも多くの死者がでた。ウイルスが変異して、ふたたびごくふつうのインフルエンザ・ウイルスになるまでには、あと数年を要した。
ウイルスが通り過ぎたあとには、多くの未亡人や孤児、寄る辺のない老人が残された。生き残った人のあいだにも、精神的な落ち込みや不安、虚脱感がひろがっていた。
1918年のインフルエンザによる死亡者数ははっきりとはわからない。
1927年になって、米国医師会は世界で2100万人という見積もりをだした。だが、それはあまりにも過小な数字だった。
1940年代になると、当時の死者を5000万ないし1億人とする見積もりが登場する。インドだけでも死者が2000万人に達したことがわかっている。
少なくとも5000万人というのは恐ろしい数字だった。
世界じゅうの人びとがこのインフルエンザから多くのことを学んだことはまちがいない。その後、医学も疫学も進歩した。インフルエンザ・ウイルスも発見され、ワクチンも開発された。
それでも自然は時に人間の叡智を越えていく。
そのとき、文明が生き延びていくためには、人びとがパニックになるのを抑えることがだいじだ、と著書はいう。とりわけ求められるのが指導者の役割である。
著者はいう。
〈権威の座にいる者は、人々の信頼を得なければならない。そうするためには、すべてのことをごまかさず、何事にもしらを切らず、小手先で片づけないことが大事である。〉
まったくそのとおりである。



