平山周吉『江藤淳は甦える』断想(4) [われらの時代]
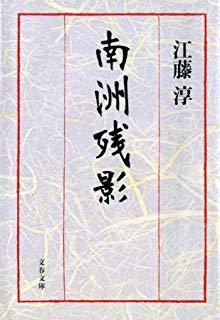
だんだんつらい話になってくるが、最後まで読むことにしよう。
1979年から翌年にかけてのアメリカ滞在時代、江藤は占領史の研究に没頭した。日本人が戦後空間を脱して、みずからの国を取り戻すのだという思いが強かった。
江藤は時折、滞在中のアメリカでも占領政策を批判する講演をしたが、それはとうぜん波紋を広げるものとなった。身の危険を感じることもあったという。アメリカの度量にも限度があった。
平山によれば、1980年代の江藤は「生き埋め」状態にあったという。それはかれが日本国憲法制定の過程、GHQによる検閲の実態を研究し、発表していた時期にあたる。
文壇にも毛嫌いされていた。江藤は1984年の『自由と禁忌』で、丸谷才一や小島信夫、大庭みな子、吉行淳之介、安岡章太郎など大御所の話題作を徹底的に批判している。評価したのは中上健次の『千年の愉楽』だけだった。
1989年には『昭和の文人』を刊行する。平野謙や堀辰雄などが断罪されるなかで、中野重治が再評価されているのが目につく。しかし、その再評価はどこかバランスを欠いている。
この年、昭和天皇が亡くなる。昭和という時代がせり上がってきたのは、このときである。
「天皇崩御に際会して、江藤の中のなにかが堰を切ったように溢れ出た」と、平山は記している。
昭和よ永遠なれとの思いが強かったという。
その思いのもと、江藤は『昭和の宰相たち』を書き継ぐ。かれによると、若槻礼次郎、田中義一から、佐藤栄作、田中角栄にいたるまで、昭和の宰相たちは、すべて天皇の宰相たちにほかならなかった。
この大河昭和史は1985年から90年まで、雑誌に連載され、単行本としては4巻で中絶した。1932年の五・一五事件で、犬養毅が暗殺されるところまでしか書かれていない。
平山によれば、1990年に公開された『昭和天皇独白録』が、それまでの記述の変更を余儀なくさせたからだという。テーマの大きさに思いのたけがおよばなかった。
1991年に還暦前の江藤は芸術院会員に選ばれている。これは大きな栄誉と喜びだったろう。
とはいえ、江藤にとって、平成は象徴天皇制と戦後民主主義におおわれた不愉快な時代となった。日本という国がなくなってしまうのではないかとさえ恐れた。象徴天皇制はかぎりなく共和制に近づいてしまう。戦後民主主義は国家の否定に行きつく。そう思っていた。
この年から、江藤はふたたび『漱石とその時代』に立ち戻り、「新潮」での連載をはじめている。記述はより慎重になっている。漱石の2年をえがくのに1巻がついやされた(第3巻)。そして、ついにこのライフワークは未完のまま、全5巻で断ち切られることになるのだ。『明暗』論が書かれることはなかった。
1994年からは西郷隆盛を論じた『南洲残影』の連載がはじまっていた。「文學界」でのこの連載は21回つづき、1998年に文藝春秋から単行本として出版される。
そのなかで、江藤はこう書く。
〈何故なら人間には、最初から「無謀」とわかっていても、やはりやらなければならぬことがあるからである。日露開戦のときがそうであり、日米開戦のときも同じだった。勝った戦が義戦で、敗北に終った戦は不義の戦だと分類してみても、戦端を開かなければならなかったときの切羽詰った心情を、今更その儘に喚起できるものでもない。況んや「方略」がよければ勝てたはずだ、いや、そもそも戦は避けられたという態(てい)の議論にいたっては、人事は万事人間の力で左右できるという、当今流行の思い上りの所産というべきではないか。〉
江藤は「大東亜戦争」に重ねて、西南戦争での西郷の挙兵を読み解こうとしていた。悲愴である。
このころ、江藤は慶應義塾大学で教えるようになっている。
『漱石とその時代』完成に向けての地道な取り組みがつづくなか、江藤は馬琴や虚子、徳田秋声にも興味をもつようになっている。漱石が終わったら、谷崎に取り組むのを楽しみにしていたという。
途中、病気で半年ほど中断するものの、還暦をすぎてからも、「漱石」の執筆はつづけられた。このころ江藤のえがく漱石は、身ぐるみ朝日新聞に買い取られた、一介の「小説記者」の「急速に老い、病んでいく」姿だった。
みずからも老いを感じるようになっていた。憂国の「逸民」の影も増していた、と平山はいう。
1993年の皇太子成婚では、いとこの長女、小和田雅子が妃に選ばれる。だが、江藤はひたすら沈黙を守っていた。むしろ、この結婚に危惧をいだいていたという。
1995年の阪神淡路大震災では、被災者の前にひざまずいて声をかける天皇と皇后に苦言を呈した。オウム真理教による地下鉄サリン事件をみて、この国が崩壊をつづけていると感じた。
1997年には慶應大学での定年を1年残して、大正大学に移籍する。20年、東工大に勤めたあと、慶應で約8年教えたことになる。
この年、江藤は日本文藝家協会理事長、三田文学会理事長、国語審議会副会長といった要職も引き受けていた。公正取引委員会での再販価格維持制度をめぐる会合にも出席している。いずれも、心身を消耗させる仕事だった。
1998年、夫人に末期がんが発見される。告知はしなかった。8カ月の闘病後、11月7日に夫人は亡くなる。
江藤は病室に泊まり込みながら、『妻と私』の原稿を書きつづけた。妻が亡くなってから、疲労のため、2カ月入院した。
妻の納骨をすませたのは、翌1999年5月である。それから2カ月半後、江藤は7月21日に自死する。
遺書にはこう書かれていた。
〈心身の不自由は進み、病苦は耐え難し。去る六月十日、脳梗塞の発作に遭いし以来の江藤淳は形骸に過ぎず。自ら処決して形骸を断ずる所以なり。乞う、諸君よ、これを諒とせられよ。〉
脳梗塞自体は軽かったという。7月8日には退院している。歩くのは少し不自由になったが、散歩することもできた。
だが、その夜、江藤は死を決意し、湯船にはいり、包丁で左手を切り自裁した。
いったい何があったのだろう。
『幼年時代』の連載がはじまったばかり。『漱石とその時代』は、たぶんもう少しがんばれば完結したのではないだろうか。
形骸というのはことばが強すぎる。あせらず養生すればよかったのにと思う。しかし、そろそろ終わりにしたいという信念を止めるわけにはいかない。
昭和に殉ずるという思いが強くなっていたのかもしれない。
非政治的人間であるぼくなどに、その気持ちははかりがたい。
ウズベキスタンの旅(3) [旅]
5月11日(土)つづき
バスはキジルクム砂漠のなかを走っています。
よく話すガイドさんです。
自分が住んでいるのは、タシケントから2時間ほどの山のふもとで、旦那さんと子どもが2人いる。仕事中は、義理のお母さんが子どもの面倒をみてくれる。ウズベキスタンでは子どもはふつう3人で、ほんとうはもうひとりほしいがあきらめた。町ではチューリップとポピーの花がきれいに咲く……。
いま向かっているのはカラカルバクスタン自治共和国で、ここには古代ホレズム王国の遺跡群が残されています。ホレズム王国には50の城があり、ゾロアスター教はここで発生したといいます。
ホレズム(ホラズムとも)は、かつてアラル海に流れ込んでいたアム川(アムダリア川)下流一帯の地域を指します。川の周辺は農業が盛んで、国家が形成されていたのでしょう。
問題はおそらくアム川の流れがよく変わったことです。川の流れが変わると、元の肥沃な土地はたちまち砂漠になってしまい、人びとは適地を求めて、新たな地へと移動しなければなりませんでした。そのとき砦もまた新たにつくられたのです。
ところで、ゾロアスター教とは紀元前6世紀にゾロアスター(ドイツ語ではツァラトゥストラ)によってつくられた宗教です。善悪二元論からなりますが、太陽神アフラマズダを信仰する一神教で、火を尊びます。そのため拝火教とも呼ばれます。
ゾロアスター教がウズベキスタンで誕生したというのはほんとうでしょうか。ゾロアスター教というとイラン高原のイメージが強いのですが、ガイドさんはあくまでもウズベキスタン説にこだわります。ちょっと場所がずれていますが、それもよしとしましょうか。
ゾロアスター教では、人は亡くなると鳥葬されます。それによって肉が鳥についばまれ、罪が消えて、白い骨だけとなります。白は善であり、その白骨を壺に収め墓にいれます。
ガイドさんによると、ウズベキスタンでは、ゾロアスター教の習慣が残っているそうです。たとえば、玄関のドアの上にヤギの角の印をつけるのは魔除け。家にはいるときは右足、出るときは左足から。そうすると、善がはいってくる。話はとまりません。
ホレズム王国をつくったのはソグド人。ゼロを発見したのもインド人ではなく、ウズベキスタン人のアル・ホレズミ(780?〜845?、アル・フワーリズミーとも)だと、ウズベキスタン自慢がつづきます。
ちょっとまゆつばですが、名前の通り、アル・ホレズミが、ここホレズム地方の出身で、大数学者だったことはまちがいありません。代数や天文学、アラビア数字の定着にも貢献しました。でも、ゼロを発見したのは、やはりインド人ですよね。
猛烈な暑さです。トプラク・カラが見えてきました。

バスはその下に停まります。
いまは砂漠ですが、かつてこのあたりは海だったといいます。その証拠に、地面に塩がふきだし、ところどころ白くなっているでしょう、とガイドさん。われわれはこの砦に登るわけです。

トプラク・カラは三重の城壁に囲まれた土の城で、1世紀から5世紀にかけての遺跡。いちばん内側の城壁は500メートル×300メートルで、城内には広間やゾロアスター教の神殿もあったといいます。
たぶん、この城壁のなかに何千人もの人が暮らしていたのです。これが古代の町のかたちです。日本の農村のようなものはありません。町の外は遊牧の世界です。
ここは城の広間でしょうか。つわものどもが夢の跡といった感じです。壁画や美術品、貨幣なども出土したようですが、それらはいまはなく、各地の博物館に収められているようです。

トプラク・カラを1938年に発見したのは、ソ連の民族学者セルゲイ・トルストフだといいます。
おや、鳥が巣をつくっているようです。大きなトカゲもみました。

ゾロアスター教が拝火教と呼ばれるのは、アトルバーンと呼ばれる聖火台に火をともして祈るからです。その根本経典は「アヴェスター」ですが、大半が失われています。
廃墟となった砦には、ゾロアスター教の神殿跡が残っています。これがそうですね。聖火台が並んでいます。

ここも何かちいさな部屋があったのでしょうか。

発掘はいまもつづいているようです。

そのあたりで記念写真を1枚。シャッターと一緒に目をつむる癖があって、このときもそれが遺憾なく発揮されています。年をとりました。

ホレズム王国はアラブ人の侵入により8世紀に滅びます。そのとき、ゾロアスター教も禁じられますが、ガイドさんによると、その影響はミナレットのタイル模様などにひそかに埋め込まれて保存されました。たとえば、鼓を縦にした模様は、ゾロアスター教の火をともす道具を表したものだといいます(これはのちほど)。
遺跡のいちばん上から向こうを眺めると、ふたつめの城壁らしきものと、さらにその先に黒い山が見えました。カラタオと呼ばれるそうです。

ここは現在、カラカルパクスタン自治州になっています。カラパクスタンとは遊牧民のかぶる黒いとんがり帽という意味だそうです。北側はアラル海ですが、いまはもう見えなくなっています。昔はよく見えたのではないでしょうか。
ガイドさんによると、アラル海が干上がったのは、綿花栽培や天然ガス採掘のためだけではなく原爆実験のためでもあったといいます。そのあたり真相はどうなのでしょう。
気温は35度以上あるでしょう。猛暑のなか遺跡見学を終えたわれわれは、ユルタと呼ばれるパオのなかで昼食をとることに。なかは絨毯がしきつめられ、暑さをしのげます。

スープ、サラダ、パン、フルーツなど、次々料理が出ましたが、メインはジャガイモとニンジンと羊肉を煮込んだ豪快な一品(ウズベキスタン風肉ジャガ?)。もちろん、ビールもいただきました。

バスはキジルクム砂漠のなかを走っています。
よく話すガイドさんです。
自分が住んでいるのは、タシケントから2時間ほどの山のふもとで、旦那さんと子どもが2人いる。仕事中は、義理のお母さんが子どもの面倒をみてくれる。ウズベキスタンでは子どもはふつう3人で、ほんとうはもうひとりほしいがあきらめた。町ではチューリップとポピーの花がきれいに咲く……。
いま向かっているのはカラカルバクスタン自治共和国で、ここには古代ホレズム王国の遺跡群が残されています。ホレズム王国には50の城があり、ゾロアスター教はここで発生したといいます。
ホレズム(ホラズムとも)は、かつてアラル海に流れ込んでいたアム川(アムダリア川)下流一帯の地域を指します。川の周辺は農業が盛んで、国家が形成されていたのでしょう。
問題はおそらくアム川の流れがよく変わったことです。川の流れが変わると、元の肥沃な土地はたちまち砂漠になってしまい、人びとは適地を求めて、新たな地へと移動しなければなりませんでした。そのとき砦もまた新たにつくられたのです。
ところで、ゾロアスター教とは紀元前6世紀にゾロアスター(ドイツ語ではツァラトゥストラ)によってつくられた宗教です。善悪二元論からなりますが、太陽神アフラマズダを信仰する一神教で、火を尊びます。そのため拝火教とも呼ばれます。
ゾロアスター教がウズベキスタンで誕生したというのはほんとうでしょうか。ゾロアスター教というとイラン高原のイメージが強いのですが、ガイドさんはあくまでもウズベキスタン説にこだわります。ちょっと場所がずれていますが、それもよしとしましょうか。
ゾロアスター教では、人は亡くなると鳥葬されます。それによって肉が鳥についばまれ、罪が消えて、白い骨だけとなります。白は善であり、その白骨を壺に収め墓にいれます。
ガイドさんによると、ウズベキスタンでは、ゾロアスター教の習慣が残っているそうです。たとえば、玄関のドアの上にヤギの角の印をつけるのは魔除け。家にはいるときは右足、出るときは左足から。そうすると、善がはいってくる。話はとまりません。
ホレズム王国をつくったのはソグド人。ゼロを発見したのもインド人ではなく、ウズベキスタン人のアル・ホレズミ(780?〜845?、アル・フワーリズミーとも)だと、ウズベキスタン自慢がつづきます。
ちょっとまゆつばですが、名前の通り、アル・ホレズミが、ここホレズム地方の出身で、大数学者だったことはまちがいありません。代数や天文学、アラビア数字の定着にも貢献しました。でも、ゼロを発見したのは、やはりインド人ですよね。
猛烈な暑さです。トプラク・カラが見えてきました。
バスはその下に停まります。
いまは砂漠ですが、かつてこのあたりは海だったといいます。その証拠に、地面に塩がふきだし、ところどころ白くなっているでしょう、とガイドさん。われわれはこの砦に登るわけです。
トプラク・カラは三重の城壁に囲まれた土の城で、1世紀から5世紀にかけての遺跡。いちばん内側の城壁は500メートル×300メートルで、城内には広間やゾロアスター教の神殿もあったといいます。
たぶん、この城壁のなかに何千人もの人が暮らしていたのです。これが古代の町のかたちです。日本の農村のようなものはありません。町の外は遊牧の世界です。
ここは城の広間でしょうか。つわものどもが夢の跡といった感じです。壁画や美術品、貨幣なども出土したようですが、それらはいまはなく、各地の博物館に収められているようです。
トプラク・カラを1938年に発見したのは、ソ連の民族学者セルゲイ・トルストフだといいます。
おや、鳥が巣をつくっているようです。大きなトカゲもみました。
ゾロアスター教が拝火教と呼ばれるのは、アトルバーンと呼ばれる聖火台に火をともして祈るからです。その根本経典は「アヴェスター」ですが、大半が失われています。
廃墟となった砦には、ゾロアスター教の神殿跡が残っています。これがそうですね。聖火台が並んでいます。
ここも何かちいさな部屋があったのでしょうか。
発掘はいまもつづいているようです。
そのあたりで記念写真を1枚。シャッターと一緒に目をつむる癖があって、このときもそれが遺憾なく発揮されています。年をとりました。
ホレズム王国はアラブ人の侵入により8世紀に滅びます。そのとき、ゾロアスター教も禁じられますが、ガイドさんによると、その影響はミナレットのタイル模様などにひそかに埋め込まれて保存されました。たとえば、鼓を縦にした模様は、ゾロアスター教の火をともす道具を表したものだといいます(これはのちほど)。
遺跡のいちばん上から向こうを眺めると、ふたつめの城壁らしきものと、さらにその先に黒い山が見えました。カラタオと呼ばれるそうです。
ここは現在、カラカルパクスタン自治州になっています。カラパクスタンとは遊牧民のかぶる黒いとんがり帽という意味だそうです。北側はアラル海ですが、いまはもう見えなくなっています。昔はよく見えたのではないでしょうか。
ガイドさんによると、アラル海が干上がったのは、綿花栽培や天然ガス採掘のためだけではなく原爆実験のためでもあったといいます。そのあたり真相はどうなのでしょう。
気温は35度以上あるでしょう。猛暑のなか遺跡見学を終えたわれわれは、ユルタと呼ばれるパオのなかで昼食をとることに。なかは絨毯がしきつめられ、暑さをしのげます。
スープ、サラダ、パン、フルーツなど、次々料理が出ましたが、メインはジャガイモとニンジンと羊肉を煮込んだ豪快な一品(ウズベキスタン風肉ジャガ?)。もちろん、ビールもいただきました。
平山周吉『江藤淳は甦える』断想(4) [われらの時代]

1971年4月、38歳の江藤淳は東京工業大学の助教授に就任した。平山は「国家の官吏」になったと書いている。ついにエスタブリッシュメントの地位を獲得したのだ。
2年後、江藤は教授に昇任し、文学を担当することになる。東工大時代は20年におよぶ。この地位には満足していたという。
教育活動に時間がとられたとはいえ、執筆活動は衰えない。『漱石とその時代』(第1部、第2部)を書き終えたあとは、立て続けに『海舟余波』、『海は甦える』に取り組んだ。
自分の知らない過去の時代の感触を知りたいという「抑えがたい欲望」があったという。言い換えれば、日本という国家につながりたいという思いである。
祖父が海軍中将だったことから「政治的人間」への関心は強い。勝海舟や山本権兵衛にたいする関心はそこから生まれる。
江藤にとって、戦後とは、どういう時代だったのか。こう書いている。
〈国家意志は、敗戦国においてはいわば奴隷の言葉によって語られなければならない。政治的指導者たちは、戦勝国に対しては「戦争の継続」である外交努力をつづけながら、半面一般の国民に対して勝者の意志を励行し、かつその過程でひそかに自己の意志をも励行するという際どい綱渡りを強制されるからである。このような状況のなかで、「国家」が一般国民にとって、望ましい「同一化のシンボル」でなくなることは自明である。〉
ここからは江藤の意識が透けてみえる。ひとつは、政治とは現実だということである。政治は無責任に現実をもてあそんではならない。
しかし、にもかかわらず、敗戦国という現実をどうとらえればよいのか。敗戦国意識に閉じこめられているかぎり、日本の戦後は終わらない。
江藤にとって、戦後民主主義とは奴隷の平和にほかならなかった。日本が戦後を脱するためには、アメリカやソ連によって強要される奴隷の姿勢から自立して、ほんらいの日本を取り戻さなければならない。そのために努力しつづけるのが、天皇の臣民たるおのれの役割である。
これはある意味では、ひじょうに不幸な意識である。というのも、江藤にとって、ほんらいの日本は、明治以降の大日本帝国時代にしかありえなかったからである。はたして、日本の未来は、大日本帝国時代の誇りを取り戻すことにかかっているのだろうか。江藤は4歳半のときに亡くなった母の面影を追い求めるように、帝国の栄光をさがしつづけることになる。
『海舟余波』は1974年に刊行された。ときあたかも、NHKの大河ドラマで、子母沢寛原作、倉本聰脚本による『勝海舟』が放送されていた。江藤はこれに便乗したわけではない。むしろ、人情仕立ての大河ドラマには反発していた。かれがえがくのは、自立した国のあり方を求めつづける海舟だった。
そのころぼくは大学をようやくレポート提出で卒業させてもらい、結婚し、ちいさな総会屋系出版社に勤めていた。あちこちふらつきながら、なんとか暮らしていく算段をするのがせいいっぱい。でも自由で楽しい時代ではあった。もちろん、気分は反体制である。
やたら、日本、日本と叫ぶ、ぎょうぎょうしい大河なんか見なかった。非国民でけっこう。鳥や獣、いや草木のように生きるのだと思っていた。政治にはほとんど関心がなかった。むしろ、嫌いだったといえるだろう。
そんなことは、どうでもよろしい。
江藤が『海舟余波』につづいて取り組んだ『海は甦える』は、日露戦争時の海軍大臣、山本権兵衛を主人公とする「ドキュメンタリー・ノヴェル」。平山の引用をみれば、明治天皇がじつにざっくばらんに山本と会話するシーンがあって、このあたりがいかにも江藤らしい。
1975年、江藤は博士論文の『漱石とアーサー王傳説』を出版する。ここで、江藤は漱石と兄嫁、登世との恋愛説を提示する。これに、大岡昇平がかみつき、大げんかとなった。
大岡は、江藤がこんな思いつきの論考で、文学博士号を手に入れたのが、気にくわなかった。加えて、この年、江藤が芸術院賞を受賞したのもおもしろくなかった。右傾化する江藤に大岡は怒りをおぼえていた。
大岡の大批判は、江藤に『漱石とその時代』を続行する意欲を失わせる。かれが漱石伝を再開するのは、それからじつに16年後の1991年で、大岡昇平が亡くなってから3年後のことである。その結果、『漱石とその時代』は、未完のまま第5巻で断ち切られる。
ふり返ると、このころから、ぼくは江藤淳への興味をなくしている。生活のため、新しくはいった会社での営業の仕事が忙しくなったこともあって、本を読むのは通勤時間の行き帰りだけになった。とうぜん、司馬遼太郎や藤沢周平、山田風太郎が多くなる。
そのころ江藤淳は大学や文壇にとどまらず、福田赳夫のブレーンとして活躍していた。
福田内閣が成立するのは1976年の年末である。江藤は文部大臣としての入閣を取り沙汰されていたが、それは実現しなかった。しかし、福田のアドヴァイザーとして、1977年2月に訪米したり、7月に東南アジア5カ国に出張したりしている。
翌78年10月には日中平和条約批准書交換に先立って、鄧小平副総理とも面会している。気分はキッシンジャーで、平山は「江藤の関心はおそらく文部行政よりも、国際関係、外務行政にあったのではないか」と記している。
1978年になると、江藤はそれまでつづけてきた文芸時評をやめ、平山によれば「占領期から続く戦後日本の実像をあぶり出す作業」に集中する。
吉本隆明は対談で「江藤淳ともあろう人が、日本の知識人流にいえば、こんなつまらんことにどうしてエネルギーを割くんだろう、という疑問があるんですよ」と江藤に問いただしている。これにたいする江藤の答えは「私はこれが私にとっての文学だからやっているのです」というものだった。政治でも学問でもなく、文学だというところが味噌である。
戦後日本の実像をあぶり出す仕事の皮切りとなったのが、日本が無条件降伏したという通説にたいする批判である。日本はポツダム宣言の第6項から第13項までの条件を受諾しただけで、それはけっして無条件降伏ではない、と江藤は主張した。言い換えれば、占領当局がポツダム宣言を逸脱して、強引な占領政策を実施したというのが江藤のとらえ方であり、そこから江藤の関心は占領政策の批判へと向けられていく。
1979年10月から9カ月間、江藤は国際交流基金派遣研究員として、ワシントンのウッドロー・ウィルソン研究所に赴任し、検閲に関する資料を中心に、占領史関係の資料の山に向きあった。その成果として、のちに出版されるのが『一九四六年憲法』や『閉された言語空間』である。
とりわけ江藤にとって宝庫となったのが、メリーランド大学のプランゲ文庫。ここには占領期に検閲された書籍や小冊子、雑誌、新聞が収録されていた。江藤は占領時代における検閲の実態を知り、GHQがいかに日本人を心理的に操作していたかを実感する。
さらに、憲法の制定過程である。GHQが新憲法を起草したことは明らかだった。当時の幣原喜重郎首相が閣議で閣僚にたいし、総司令部による憲法案を受諾すると告げている。にもかかわらず、メディアがその事実に言及することを検閲当局は禁止していた。もちろんアメリカ批判は許されない。
江藤によれば、9条の戦争放棄もアメリカの強制によるもので、日本人が心から求めたものではないという。
江藤の批判は、「不可解な日米関係の『ねじれ』の根源をつくった吉田茂に向けられ、さらに裏切りの「ユダ」と「左翼」にあふれた戦後文壇にも向けられていく。
こうした主張は、江藤淳を「絶対的少数派」の孤立へと追いこんでいった、と平山は指摘する。
日本では、いまでもアメリカに刃向かう政治家や官僚はけっしてえらくなれない。そこで、日本の権力政治は奴隷のことばでアメリカにすり寄りながら、戦後パラダイムなるものを批判し、それをつくりだしたとして左翼を攻撃する。
そこには換骨奪胎された江藤淳がいる。西部邁がいる。
江藤淳はいまも孤独なままである。
ウズベキスタンの旅(2) [旅]
5月11日(土)
中央アジアのウズベキスタンにいます。
中央アジアというのは、どのあたりを指すのでしょうか。明確な定義はないようです。文字どおりアジアの中央部というのが、ぼくの印象です。
地理的にいうと、中国、インド、ペルシア、ロシアに囲まれた地域。チベットやモンゴルも含まれるかもしれません。しかし、テュルク系の人びとが暮らす場所に限定すると、ここをトルキスタンと呼んでもいいでしょう。山と砂漠と草原からなる遊牧地帯で、現在はイスラム圏に属しています。
トルキスタンは東トルキスタンと西トルキスタンに分かれます。東トルキスタンは中国の新疆ウイグル自治区、西トルキスタンは旧ソ連に属していたアゼルバイジャン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタン、カザフスタン、キルギスなどの国々からなります。
西トルキスタンがソ連から分離独立したように、東トルキスタンも中国からの分離独立を望むのはとうぜんです。しかし、新疆ウイグル地区の面積は中国全体の6分の1を占めていますから、中国が漢民族の入植をはかるとともに、ウイグル地区の独立運動を徹底的に抑え込もうとするのも、それなりの理由があります。
中央アジアはともかく、ウズベキスタンが西トルキスタンの中央に位置することはまちがいありません。しかも、ウズベキスタンは、東をキルギスとタジキスタン、北と西をカザフスタン、南をタジキスタン、アフガニスタン、トルクメニスタンに囲まれている二重内陸国です。
面積は日本の1.2倍で、人口は約3200万。東部と南部を山岳に囲まれた乾燥地帯で、アム川(アムダリア)とシム川(シムダリア)の二大河川が流れ、そのまわりに農地とキジルクム砂漠が広がっています。
さて、ここヒヴァについての説明は後回し。というのも、ヒヴァの城内はあした見学することになっていて、きょうは砂漠のなかにある古代ホレズム王国の遺跡を見にいくからです。
それでも、いちおうホテルの屋上からみえた景色はこんな感じ。

ホテルの入り口も写真に収めました。

朝9時ホテルをバスで出発します。ガイドさんは40代の女性で、話しはじめると止まりません。
彼女によると、ウズベキスタンは米のふるさとだとか。日本の学者では加藤九祚(きゅうぞう)を尊敬しているそうです。天然ガスと綿花が大きな産業です。
畑では大勢の人が何か作業をしているようです。

これは田んぼではないでしょうか。たしかに米がつくられているようです。

綿花畑もあります。アム川(アムダリア)から縦横に引かれた水路が、田や畑の作物を支えています。

パミール高原に発するアム川は、いまはアラル海に流れ込むことなく、途中で干上がっているようです。ガイドさんは、アラル海が消えかかっているのは綿花栽培のために灌漑が過剰につくられたためではないと弁解しますが、はたして真相はどうでしょう。これは大きな運河ですね。

家畜の市場だそうですが、まだ市は開かれていないようです。

アム川が見えてきました。大河です。

郊外に同じタイプの家が並んでいますが、これは1991年の独立以来、いなかにきれいな家を建てようというカリモフ大統領の指示でつくられたものだといいます。

ウズベキスタンで観光がさかんになったのは2007年以降だそうです。スタンというのは場所、または国という意味のペルシャ語。独立前は、19世紀以来ロシア、さらにソ連の支配下にありました。平均寿命は男が65歳、女が75歳だといいます。平均収入は162万スム(約2万3000円、1000スム=約14円)ですが、物価はおそらく日本の5分の1くらいではないでしょうか。このあたり、1人あたりGDPという概念が必ずしも豊かさの尺度(幸福度はもちろん)にならないことがわかります。
バスはだんだん砂漠にはいっていきます。

中央アジアのウズベキスタンにいます。
中央アジアというのは、どのあたりを指すのでしょうか。明確な定義はないようです。文字どおりアジアの中央部というのが、ぼくの印象です。
地理的にいうと、中国、インド、ペルシア、ロシアに囲まれた地域。チベットやモンゴルも含まれるかもしれません。しかし、テュルク系の人びとが暮らす場所に限定すると、ここをトルキスタンと呼んでもいいでしょう。山と砂漠と草原からなる遊牧地帯で、現在はイスラム圏に属しています。
トルキスタンは東トルキスタンと西トルキスタンに分かれます。東トルキスタンは中国の新疆ウイグル自治区、西トルキスタンは旧ソ連に属していたアゼルバイジャン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、タジキスタン、カザフスタン、キルギスなどの国々からなります。
西トルキスタンがソ連から分離独立したように、東トルキスタンも中国からの分離独立を望むのはとうぜんです。しかし、新疆ウイグル地区の面積は中国全体の6分の1を占めていますから、中国が漢民族の入植をはかるとともに、ウイグル地区の独立運動を徹底的に抑え込もうとするのも、それなりの理由があります。
中央アジアはともかく、ウズベキスタンが西トルキスタンの中央に位置することはまちがいありません。しかも、ウズベキスタンは、東をキルギスとタジキスタン、北と西をカザフスタン、南をタジキスタン、アフガニスタン、トルクメニスタンに囲まれている二重内陸国です。
面積は日本の1.2倍で、人口は約3200万。東部と南部を山岳に囲まれた乾燥地帯で、アム川(アムダリア)とシム川(シムダリア)の二大河川が流れ、そのまわりに農地とキジルクム砂漠が広がっています。
さて、ここヒヴァについての説明は後回し。というのも、ヒヴァの城内はあした見学することになっていて、きょうは砂漠のなかにある古代ホレズム王国の遺跡を見にいくからです。
それでも、いちおうホテルの屋上からみえた景色はこんな感じ。
ホテルの入り口も写真に収めました。
朝9時ホテルをバスで出発します。ガイドさんは40代の女性で、話しはじめると止まりません。
彼女によると、ウズベキスタンは米のふるさとだとか。日本の学者では加藤九祚(きゅうぞう)を尊敬しているそうです。天然ガスと綿花が大きな産業です。
畑では大勢の人が何か作業をしているようです。
これは田んぼではないでしょうか。たしかに米がつくられているようです。
綿花畑もあります。アム川(アムダリア)から縦横に引かれた水路が、田や畑の作物を支えています。
パミール高原に発するアム川は、いまはアラル海に流れ込むことなく、途中で干上がっているようです。ガイドさんは、アラル海が消えかかっているのは綿花栽培のために灌漑が過剰につくられたためではないと弁解しますが、はたして真相はどうでしょう。これは大きな運河ですね。
家畜の市場だそうですが、まだ市は開かれていないようです。
アム川が見えてきました。大河です。
郊外に同じタイプの家が並んでいますが、これは1991年の独立以来、いなかにきれいな家を建てようというカリモフ大統領の指示でつくられたものだといいます。
ウズベキスタンで観光がさかんになったのは2007年以降だそうです。スタンというのは場所、または国という意味のペルシャ語。独立前は、19世紀以来ロシア、さらにソ連の支配下にありました。平均寿命は男が65歳、女が75歳だといいます。平均収入は162万スム(約2万3000円、1000スム=約14円)ですが、物価はおそらく日本の5分の1くらいではないでしょうか。このあたり、1人あたりGDPという概念が必ずしも豊かさの尺度(幸福度はもちろん)にならないことがわかります。
バスはだんだん砂漠にはいっていきます。
ウズベキスタンの旅(1) [旅]
最近は年に1度か2度、海外旅行にでかけます。お気楽な海外ツアーが多くなっています。年寄り夫婦のささやかな楽しみです。
ことしはカンボジアとウズベキスタンに出かけました。
せめて、その旅行の思い出を書いておかねばと思うのですが、帰国するとついおっくうになってしまい、旅行記を書くのがのびのびになってしまいます。
あまり事前予習もしないし、向こうでもガイドさんに連れられて回るので、旅の記録といっても、たいしたものではないのですが、何かの参考になればと思うのと、もし生きていれば10年前こんなところへ行ったなと思いだすために、いちおうの記録を残しておくのも悪くないでしょう。
幸い、つれあいが熱心に写真を撮ってくれています。
ですから、これは写真を中心としたお気楽な旅行記です。あまり期待しないで、眺めていただければ幸いです。
ウズベキスタンの旅をふり返ります。
2019年5月10日(金)
朝7時過ぎ船橋の自宅を出発し、京成電車で成田空港へ向かいます。8時半過ぎ、クラブツーリズムのカウンターで手続きをすませ、ウズベキスタン航空のカウンターに並びますが、なぜか手続きに1時間近くかかってしまいました。
飛行機は定刻通り11時5分に出発。タシケント到着は現地時間の午後4時45分。時差は4時間ですから、9時間半ほどの飛行でした。
タシケントに到着する2時間ほど前から、飛行機は雪をいただく山々の上を飛びつづけています。天山山脈です。
シルクロードは、この天山山脈をはさんで北路と南路に分かれているわけですね。

しばらくすると、山脈がふたつに分かれ、草原らしきものが見えてきました。

川もみえてきます。雪がなくなりました。

おや、こんなところに発電所が。原発でしょうか。

だいぶ高度が下がってきました。農地が広がっています。

空港に到着です。

暑い。ツアー参加者によると、2、3日前に、現地の気温が35度近くなるから、服装に気をつけるよう旅行社から電話があったというのですが、私たちの自宅には連絡がありませんでした。そのため、むしろ寒さ用の準備をしてきたくらいで、途中で何枚もTシャツを買うはめになります。
これが乗ってきた飛行機ですかね。

タシケントで国際線から国内線に乗り換えました。

バスで国内線ターミナルに移動し、2時間ほどの待ち時間で、西のウルゲンチ空港に。飛行時間は1時間半ほで、着いたときは夜8時半ごろになっていました。

まだ夕焼けが残っています。

ここからバスで約1時間。10時すぎ、ヒヴァ城内のホテル(マリカ・キーバック)に到着しました。観光は明日からです。
ことしはカンボジアとウズベキスタンに出かけました。
せめて、その旅行の思い出を書いておかねばと思うのですが、帰国するとついおっくうになってしまい、旅行記を書くのがのびのびになってしまいます。
あまり事前予習もしないし、向こうでもガイドさんに連れられて回るので、旅の記録といっても、たいしたものではないのですが、何かの参考になればと思うのと、もし生きていれば10年前こんなところへ行ったなと思いだすために、いちおうの記録を残しておくのも悪くないでしょう。
幸い、つれあいが熱心に写真を撮ってくれています。
ですから、これは写真を中心としたお気楽な旅行記です。あまり期待しないで、眺めていただければ幸いです。
ウズベキスタンの旅をふり返ります。
2019年5月10日(金)
朝7時過ぎ船橋の自宅を出発し、京成電車で成田空港へ向かいます。8時半過ぎ、クラブツーリズムのカウンターで手続きをすませ、ウズベキスタン航空のカウンターに並びますが、なぜか手続きに1時間近くかかってしまいました。
飛行機は定刻通り11時5分に出発。タシケント到着は現地時間の午後4時45分。時差は4時間ですから、9時間半ほどの飛行でした。
タシケントに到着する2時間ほど前から、飛行機は雪をいただく山々の上を飛びつづけています。天山山脈です。
シルクロードは、この天山山脈をはさんで北路と南路に分かれているわけですね。
しばらくすると、山脈がふたつに分かれ、草原らしきものが見えてきました。
川もみえてきます。雪がなくなりました。
おや、こんなところに発電所が。原発でしょうか。
だいぶ高度が下がってきました。農地が広がっています。
空港に到着です。
暑い。ツアー参加者によると、2、3日前に、現地の気温が35度近くなるから、服装に気をつけるよう旅行社から電話があったというのですが、私たちの自宅には連絡がありませんでした。そのため、むしろ寒さ用の準備をしてきたくらいで、途中で何枚もTシャツを買うはめになります。
これが乗ってきた飛行機ですかね。
タシケントで国際線から国内線に乗り換えました。
バスで国内線ターミナルに移動し、2時間ほどの待ち時間で、西のウルゲンチ空港に。飛行時間は1時間半ほで、着いたときは夜8時半ごろになっていました。
まだ夕焼けが残っています。
ここからバスで約1時間。10時すぎ、ヒヴァ城内のホテル(マリカ・キーバック)に到着しました。観光は明日からです。
平山周吉『江藤淳は甦る』断想(3) [われらの時代]

1964年8月にアメリカから帰国した江藤淳には、さっそく多くの仕事が殺到した。「朝日ジャーナル」に『アメリカと私』、つづいて「日本と私」(未完)を連載する。講演会や座談会もある。新聞や雑誌にも多くのエッセイを寄稿している。「文芸時評」も再開した。
オリンピックの年だった。
それはわずか2週間の祭典にすぎなかったが、日本はまるで「見えない敵に対して挑んでいるように見えた」と、江藤は「文藝春秋」に書く。
〈その敵とは、大きくいえば提督ペリーの来航以来、日本人の肩の上にのしかかっている宿命という名の敵である。歴史家のいわゆる日本の「近代化」が開始されてこのかた、われわれはつねに不幸であった。〉
近代化は日本にとって不幸な宿命だったというのは、どうみても大仰である。しかし、江藤は日本はこの宿命を背負って戦い、敗れ、復活し、また闘おうとしていると感じていた。
平山周吉によれば、東京オリンピックは「戦後日本のナショナリズムの解放だった」。
そのなかでも江藤のとらえ方は、常軌を逸するくらいの悲愴さに満ちている。とりわけ江藤は開会式において、世界が「日本の君主の前におのおのの旗を垂れて、敬礼していた」ことに感動をおぼえる。開国以来の怨みが「この儀式のなかではじめて象徴的につぐなわれた」とまで書いている。
私見をはさめば、これは抗いがたい感情であり、万歳するほかない論理である。国際的な通常の儀礼が、いつのまにか日本を頂点とする八紘一宇の舞台へと転化されてしまっている。
ますますグローバル化する世界のなかで、いわば水戸学の精神を保ちつづけることは、江藤を孤立のなかに追いこんでいったのではないだろうか。
このころ超多忙な江藤自身は、落ち着かない不安な生活を送っていた。住まいは転々として定まらず、盟友ともいえる作家、山川方夫をとつぜんの交通事故で亡くしている。夫人が子宮筋腫で、子宮を全摘し、そのあと鬱病で入院する。そうした不安が、自身をますます仕事に駆り立てていた。
「文學界」に長期連載していた「近代以前」は、1966年7月号で打ち切りになる。単行本化されるのは20年後である。プリンストン大学での日本文学講義をさらに深めるための試みだった。藤原惺窩と林羅山からはじまり、近松、西鶴を論じ、上田秋成で中断された。ほんらいは、伊藤仁斎や荻生徂徠、本居宣長も論じ、さらに洒落本や滑稽本、人情本、読本も扱うつもりだった。だが、あまりにも構想が大きすぎて、力及ばなかった。
そこで、方向を転換し、1966年8月号の「文藝」で、現代の小説を論じることにする。テーマは戦後日本の家族の変容である。連載は2回で終わるはずだったが、8回にふくらみ、江藤の代表作のひとつ『成熟と喪失』が生まれる。
ここでは安岡章太郎や庄野潤三、小島信夫などの現代小説が取りあげられている。なかでも重要なのは小島信夫の『抱擁家族』をめぐる考察である。
江藤の表現を借りれば、『抱擁家族』は「妻のアメリカ兵との姦通にきわまった混乱、無秩序から家庭を再建しようという話」。それは、まさに戦後日本を象徴する悲喜劇だった。
その主人公、俊介に江藤はみずからを投影する。ただし、江藤に喜劇意識はない。
江藤は小島信夫を絶賛する。のちに「ひとつの国の敗亡と、その国に生きる人間たちの倫理的・感覚的崩壊の過程を、小島氏ほど独特な視角から、なまなましく小説化しつづけている作家を、私はほかに誰一人として知らない」とまで書いている。
少なくとも、江藤はそう読んだのだろう。しかし、上野千鶴子は『成熟と喪失』を、「母の崩壊」、言い換えれば「女が壊れた」話として読んでいる。戦後は「母なるもの」が壊れ、女が立ちあがる時代でもあるのだ。これは、おそらく江藤自身の読みとはくいちがう評価である。
ちなみに、ぼく自身も長い大学時代にこの評論を読んだが、さっぱりわからなかった。女のこわさ(存在感)に思い至っていなかったのである。
1967年、江藤は、文壇の渦に巻きこまれながら、猛烈な勢いで仕事をこなしている。『成熟と喪失』と同時に、『一族再会』の連載もはじまっていた。のちに書き下ろしで刊行される『漱石とその時代』にも取り組んでいる。雑誌「季刊藝術」の編集も担当することになっていた。まさに超多忙の売れっ子だった。
『一族再会』は、みずからの家の物語である。それは幼いときに病死した母と、事実上一家の主だった海軍中将未亡人の祖母の話からはじまる。そして、明治の海軍一家の物語へと膨らんでいく。
江藤が「私の生きる意味」とまで断言した『漱石とその時代』もまた家庭の物語である。漱石と妻鏡子の関係に多くのページが割かれていた。平山周吉は『漱石とその時代』は『成熟と喪失』と地続きの関係にあるという。その背景には妻の不調がある。
このころから、江藤淳は大江健三郎と絶交状態に陥っている。それは1967年に刊行された大江の『万延元年のフットボール』をめぐる論争がきっかけだった。
江藤は「万延元年」を空虚で、「本当のこと」はどこにもないと論じた。切実なテーマは展開されていないと断言している。しょせんは政治ごっこなのだ。
大江が江藤の私事について、事実ではないことを触れ回ったことも、絶交をもたらす引き金となった。
江藤は文学の「産業化」と「政治化」にも警鐘を鳴らしている。
68年には大学紛争がさかんになるいっぽう、参議院選挙で、自民党公認の石原慎太郎が、300万票を超える得票数でトップ当選をはたし、タレントの青島幸男が120万票で2位につけた。
大江との仲が険悪だったのにたいし、江藤と吉本隆明は、最後まで不思議と良好な関係を保った。
江藤淳は学生運動による「革命ごっこ」や三島由紀夫による「自主防衛ごっこ」を嫌い、現実主義に立つと主張していた。
日米安保条約は即時廃棄できるわけがない。それでも、70年代後半には安保条約を「発展的解消」し、「真の自主独立」を達成できるかもしれないと思っていた。
佐藤栄作は高坂正堯や山崎正和らとならんで江藤をブレーンとして迎えた。70年の大阪万博にはどこか冷ややかだった。夫人の健康は回復しつつあり、軽井沢の千ヶ滝に別荘を購入した。この年に刊行された『漱石とその時代』は野間文芸賞と菊池寛賞を受賞した。
そうした文壇の表舞台に立つ江藤を吉本隆明はなぜか評価した。最初の対談でも「江藤さんと僕とは、なにか知らないが、グルリと一まわりばかり違って一致しているような感じがする」と語っている。
江藤自身も吉本について、のちにこう書いている。
〈私にとっては、その人の人柄を信用するのとその人の思想を信用するのとは同じことである。科学の普遍性をよそおった「指導理論」などは犬に喰われるがいい。私が吉本隆明さんの思想を信用するのは、まさにその人を信じるからである。私は吉本さんとすきやきの鍋をつつくようにして、吉本さんの詩と思想を味う。これは珍味である。なぜなら吉本さんはその人柄において、その思想において、男のなかの男だからである。〉
吉本が評価したのは、佐藤政権のブレーンを務め、日本文化会議に参加し、園遊会に出席する江藤ではない。歴史観や世界観はちがっていたが、その人柄にひかれていた。
このあたりの機微は、ぼくにはよくわからない。考え方においても、ふたりはどこか一致するところがあったのではないか。そのあたりは、ふたりの実際の作品をもう少し読んで評価する必要がある。
いずれにせよ、平山周吉はこう書いている。
〈吉本はこの後[江藤淳が自死したあと]、13年生きて87歳で亡くなった。その間、対談、インタビューなどで何度も江藤について話している。著書でも必ずといっていいくらいに江藤の名前と思い出が出てくる。二人は下町の悪ガキと山の手のお坊っちゃまクン、といった珍妙な組み合わせだったが、吉本は死ぬまでずっとお線香を絶やさなかった。〉
ぼくにとっても、不思議なのは、大学闘争のころ、どうしてあんなに吉本や江藤、三島、竹内、武田にひかれていたのだろうかということである。
こう書いてしまっては身も蓋もないが、いまとなっては懐かしい。



