平山周吉『江藤淳は甦える』断想(2) [われらの時代]

60年安保闘争が終わったあと、社会党の浅沼稲次郎が右翼の少年、山口二矢によって刺殺される。大江健三郎は、その少年をモデルにして「セヴンティーン」と「政治少年死す」を書く。三島由紀夫は「憂国」を発表。中央公論に掲載された深沢七郎の「風流夢譚」を読んで怒った17歳の少年が、中央公論社長宅を襲い、お手伝いさんを刺殺した。
1961年、江藤淳は朝日新聞の文芸時評を担当し、これらの作品についても論じていた。また、評判の悪かった三島由紀夫の『鏡子の家』を解説したことから、三島との接近もはじまっている。しかし、集中していたのは「小林秀雄論」である。
そのころアメリカ行きの話が出る。ロックフェラー財団から申し出があり、プリンストン大学に行くことが決まった。その前に、西ドイツ政府からも、バイロイト音楽祭への招待があって、1961年夏の2カ月間、江藤はヨーロッパ6カ国を遊覧している。そして、11月、『小林秀雄』が刊行されたことで、大きな仕事に一区切りがついた。
夫婦でアメリカに向かったのは1962年8月24日で、帰国は64年8月4日である。その間、63年7月18日から20日ほど本人だけ一時帰国したのを除いて、江藤夫妻はほぼ2年間、アメリカに滞在したことになる。
その2年間のことは『アメリカと私』につづられている。
アメリカ体験は、29歳から31歳にかけての江藤淳に何をもたらしたのだろう。平山周吉の評伝に沿って、そのことを考えてみよう。
江藤夫妻が住んだのはニュージャージー州の大学町プリンストンである。最初に迎えてくれたのは、1年前からプリンストン大学に留学していた経済学者の鈴木光男(東北大学講師、のち東京工業大学教授)だった。
当初2カ月ほどは大学の雰囲気になじめなかったようだ。「社会的な死を体験していた」と書いているから、得に学びたいテーマも見つからなかったのだろう。うつうつとしているところに、『小林秀雄』が新潮社文学賞を受賞したという朗報が舞い込んできた。
それで、ようやく自分を取り戻しはじめる。
プリンストンでは多くのアメリカ人学者と出会った。江藤の身元引受人は歴史学者のマリアス・ジャンセン(『坂本龍馬と明治維新』が有名)。エール大学のロバート・リフトンとも懇意になっている。
先に挙げた鈴木光男のほか、日本からは武者小路公秀、綿貫譲治、柳瀬睦男などが留学していたという。
平山周吉は、江藤が夏目漱石の研究者でもあるヴィリエルモ助教授と交わした会話を紹介している。
〈日本人への不満を述べるヴィリエルモに向かって、日米関係の根本的改善はわけもないと江藤は言い放つ。「それには、合衆国大統領が特使を送って、公式に原爆投下に遺憾の意をあらわし、併せて沖縄県を返還すればよい」。「とんでもない」とヴィリエルモは声を上げて反論する。「原爆を落としたのは、戦争中ですからね。アメリカ兵の声明を助けるためには、仕方がなかったのですよ。それに沖縄は、アメリカが大きな犠牲をはらってやっととったのですからね。とてもとてもかえせませんねえ。(略)日本は無条件降伏をしたのですよ」。〉
この会話は、そののちもずっと心に引っかかった。
沖縄返還がなされたあと、江藤淳は米軍基地がずっと残ったことが問題と考えていた。最晩年の1998年にも、日米防衛協力のためのガイドラインによって「もう一度日本が軍事的な空間として、全面的にアメリカの空間に取り込まれる」ことを危惧すると記している。
アメリカへの反発は身元引受人のマリアス・ジャンセンにたいしても同じである。日本の近代化、すなわち西洋化をよしとするかれの考え方には違和感をいだいていた。
平山周吉はこう書いている。
〈優等生の「めざましい近代化」が光の領域だとすれば、そこには当然のことながら、影の部分が存在する。それはペリー来航以来、強いられてきた日本の制度であり、歪められた日常の感覚であり、何よりも、うずいている日本人の傷痕である。〉
1963年7月に所用があって、3週間ほど日本に一時帰国したとき、羽田に迎えにきた三島由紀夫は編集者に「江藤さんも立派になったなあ」ともらしたという。
オリンピックを1年後に控えて、東京は「普請中」で、江藤はその頽廃ぶりを嘆いている。それでも、道行く人びとはニューヨークより、よほどおだやかだった。
NHKで岩波書店の吉野源三郎に会ったときには「このままでは日本はアメリカにしてやられてしまうという気がする」と話している。
プリンストンに残った夫人には何通も手紙を書いているが、「もう一年、日本のために二人で頑張ろう」と記しているのが印象的だ。
アメリカに戻ってきた江藤は、プリンストン大学の東洋学科で1年間、日本文学を教えることになった。秋学期は古典、春学期は近代文学が対象で、講義は英語でおこなわれた。
新潮社からの出版を約束していたその講義録は、けっきょく刊行されない。平山は、それがどんな講義だったかを推測している。
それは8世紀以来の日本文学史を連続体としてとらえる講義だったと思われる。世阿弥の「風姿花伝」はお気に入りの作品だった。江戸期の朱子学的世界も大きく取りあげられただろう。荻生徂徠の「弁名」や本居宣長の「紫文要領」も紹介されたにちがいない。近松や西鶴への言及もあったはずだ。朱子学的世界が壊れる近代では、やはり夏目漱石が焦点になる。小林秀雄の作品も紹介されたかもしれない。
平山はこう書いている。
〈江藤文学史の核心部分はプリンストンで構築されていった。古典に親しむことで、「日本」を引き受け、前近代と近代の断絶を埋めることで、「日本」はひとつの連続体を成していることが証明される。〉
江藤の白熱講義に感銘を受けた学生は多かった。そのなかの一人、ダニエル沖本は、のちにスタンフォード大学教授となり、オバマ政権のアジア担当アドバイザーになっている。
江藤にすれば、せっかくアメリカに来たからには、ただ学んで帰るだけではなく、アメリカ人に日本のことを少しでも教えたいという気持ちだったのだろう。アメリカ体験は、江藤の日本回帰を強めこそすれ、アメリカ崇拝にはけっして結びつかなかったのである。
平山周吉『江藤淳は甦える』断想(1) [われらの時代]
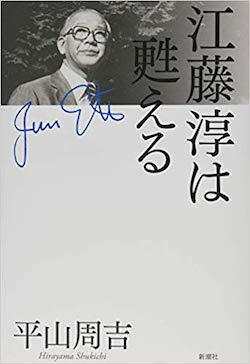
江藤淳(1932〜99)というと、夏目漱石を中心とする文芸評論、西郷隆盛や勝海舟、山本権兵衛などをめぐる歴史評論、戦後民主主義を批判しつづけた保守論客、そういうイメージが思い浮かぶ。
ぼく自身は、ほとんどといっていいくらい、江藤淳の作品を読んでいないなまけものである。愛国の風も苦手なので、たぶんこれからも熱心な読者にはならないだろう。
それでも、この本を買ったのは、江藤淳がどういう人だったかを表面だけでも知りたいと思ったからである。とくに、1960年代後半以降の江藤淳について知りたいというのが、ぼくの興味である。
江藤淳はペンネームで、本名は江頭淳夫(えがしら・あつお)という。祖父の海軍中将、江頭安太郎は将来の海軍大臣と目されていた。父の隆は三井銀行に勤めていた。父の弟、豊はのちにチッソの会長となる。いとこにあたる豊の娘、優美子は外交官の小和田恆と結婚し、現皇后の雅子の母となる。エリート家庭に生まれたといってよい。
日比谷高校時代、結核にかかり1年間休学、慶應義塾大学に進み、英文学を専攻した。1956年に『夏目漱石』でデビュー、結婚し、大学院を中退、文芸評論家の道を選んだ。そして、たちまち売れっ子になった。
1958年には「若い日本の会」を結成している。この会には、江藤を中心に、谷川俊太郎、石原慎太郎、開高健、曽野綾子、大江健三郎、浅利慶太、武満徹などが集まった。
この年、岸信介内閣は60年安保をにらみ、警察官の職務権限を強化するため、いわゆる「警職法」改正案を国会に提出する。
「若い日本の会」は、これに反発し、次のようなアピールを出した。
〈この法案は戦前の治安維持法をはじめとする一連の暗黒法に通ずるものである。私たち世代はそれらのものから直接の被害を受けず、体験を持たないが、戦争によって言いつくせぬ苦痛を味わった。この法案のもたらす危険を恐れることについては個人的体験を越えた重大かつ深刻なものを感じる。私たちはこの法案に絶対反対、その完全な撤回を要求する。〉
言論の自由を抑圧しかねない法案に反対したのだ。
「若い日本の会」は、社会党や総評などで結成される「国民会議」とは別個に行動した。江藤自身はデモ嫌いで、個人の声にこだわるという立場である。
反対運動が盛り上がるなか、警職法改正案は廃案となる。
そのころの江藤は「民主主義社会の建設」というビジョンのために動いていたという。一大ブームを巻き起こした皇太子の婚約についても、冷静に論評している。
だが、江藤は次第に同世代に愛想を尽かしはじめる。
とりわけ石原慎太郎への批判は激烈だった。「おどろくべき自己省察の欠如」(言い換えれば「不遜な自信」)などと切り捨てている。
埴谷雄高や大岡昇平との関係は良好だった。江藤に小林秀雄論を書くよう勧めたのは大岡であり、貴重な資料も提供してもらった。
『小林秀雄論』は60年安保のさなかに書き継がれ、1961年に出版される。それまで江藤は小林秀雄を全面否定していた。それが、この本で、評価ががらりと変わる。
その60年安保の年について、江藤は「危機感にかられて国会の機能回復、反岸政権のために奔走す」と、のちの「自筆年譜」に記している。
このことばに、いつわりはなかっただろう。
当初から全学連の直接行動は支持しなかった。
羽田闘争で多くの逮捕者がでたときも、埴谷雄高への手紙で、全学連は「悲劇的な茶番」であって、「全学連の過大評価はむしろいましめるべきではないでしょうか」と書いている。
安保にたいしては、いろいろな立場があってもいい。江藤は改正安保条約に批判的だったが、やみくもに反対したわけではなかった。吉本隆明との座談会では「僕は絶対に改正しちゃいけないとは言わないんで、いい方向に改定することはあり得ると思う」と発言している。
ただ、5月19日の国会で新条約案が強行採決されると、「岸信介とその一党」の横暴許すまじ、という態度に変わっていく。
国会にデモをかけるという行動には反対した。
6月10日、来日したアメリカのホワイトハウス報道官(当時の言い方では「新聞係秘書」)ハガティの車をデモ隊が取り囲み、ハガティが身の危険にさらされる事件が発生した。
江藤はこれを「非礼」かつ「愚鈍」な行動ととらえ、「進歩派指導者の退廃と無能を露呈した茶番」と非難した。デモ隊の行動は政治的感覚などまったくない無責任な反発でしかないという。
これ以降、江藤淳は安保闘争から手を引く。
樺美智子が死亡した6月15日も、ニュースを見ながら「暗たんたる気持ち」でいたというから、もはや傍観者になっている。
安保条約は6月19日に自然承認となり、23日に岸信介は辞任した。
安保闘争での疲れから、江藤淳は3度目の喀血をする。幸い、これは新しい病巣の出現によるものでなく、数カ月の療養で回復するとされた。
8月下旬、療養先の那須温泉から、江藤は埴谷雄高に私信を書いた。「朝日新聞」に掲載された「若い文学者に望むこと」と題する埴谷のエッセイについて、感想をつづったものである。
埴谷が今回の安保闘争に、若い文学者たちが「個人的自由と生命をまもるために一市民として積極的に参加した点」を評価したのにたいして、江藤はやんわりとこう批判している。
〈埴谷さんは、あたかも「市民」が現実に存在しはじめたかのようにお書きになっている。これは私たちへの御好意ですが、実は、埴谷さんの「革命」がひとつの「虚体」であるように、「市民」もまたこの国ではまだまだ「虚体」です。「虚体」を実体にしようとする努力より、「虚体」が実体だと錯覚するものを権力の具にしようとする政治の力が圧倒的に強く、だからなおさら「虚体」でありつづけるというような悪循環がくりかえされています。〉
この手紙のなかで、江藤ははっきりと「若い日本の会」から離脱することを埴谷に告げている。また全学連が、この社会の破壊をめざすカタリ派のような存在であり、埴谷こそこのカタリ派の教祖のような存在ではないかとさえ述べている。
これで埴谷との決裂は決定的になった。
はっきりいえば、安保闘争のなかで、江藤淳は「転向」したのである。これ以降、かれにとって「戦後知識人」は敵になる。その代表が丸山眞男と清水幾太郎だった。
著者は、安保後の江藤が「江頭家の家庭環境から習得した、帝国海軍と銀行員の経済的リアリズムに戻ろうとするかの如くである」と指摘している。
日本にとって、有用なのは「絶対平和」を求める知識人ではない。変転窮まりない国際世界のなかで、危険な綱渡りを強いられている実務的な「政治的人間」なのだ。安保後の江藤はそんなふうに思いはじめている。
それを日本回帰と呼んでもいいだろう。目の当たりにしたハガティ事件のショックが、国家意識を覚醒させたのだ。
江藤淳は国家なき市民よりも、日本国臣民の立場を選ぶ。埴谷雄高や大岡昇平との対立、小林秀雄への礼賛、三島由紀夫への接近はその延長上にある。
興味深いことに、安保闘争においては、江藤淳と大江健三郎の立場は意外と近かった、と著者は指摘している。
安保条約が露呈したのは、「日本がアメリカの支配下にあって、日本を動かすものが日本人の意志ではないという事実である」と、大江は述べていた。江藤の立場も基本的に変わらない。
そして、その江藤にアメリカの影が迫ってくる。
橋本治『二十世紀』を読んでみる(8) [本]

1987年、バブルがはじまる。東京株式市場の株価は2万円の大台に達する。
しかし、円高が進行していたため(年末に1ドル=122円になる)、日銀は公定歩合を2.5%に引き下げる。
日本経済は輸出中心から内需中心への転換を求められていた。とはいえ、もう十分に物はあった。これ以上、必要とも思えない外国製品を買うこともなかった。あふれたお金は土地と株に流れていく。
1988年、8年にわたったイラン・イラク戦争が終結する。イラクを応援していたのはアメリカである。パーレビ政権を倒したシーア派原理主義のイランを許すわけにはいかなかった。
1979年にサダム・フセインがイラク大統領になっていた。かつて親ソ派だったイラクは、このころ反ソ親米に転じている。
イラクの近代兵器を前に、イランはこの戦争に敗れる。双方の戦死者100万人。とりわけ、イランの若者が数多く犠牲となった。
1989年、昭和が終わる。それは「失敗の時代」のはじまりとなった。亡くなったのは昭和天皇だけではない。手塚治虫、松下幸之助、美空ひばりもこの年に亡くなっている。
竹下内閣はリクルート事件で退陣、宇野宗佑が首相になるが、女性スキャンダルで、たちまち首相の座を失う。
幼女連続殺人事件で宮崎勤が逮捕される。
東欧では、ハンガリー、東ドイツ、ブルガリア、ポーランド、チェコと、共産党政権が立て続けに崩壊する。ルーマニアのチャウシェスク大統領夫妻は処刑される。
そんなとき、日本の株価は3万8900円をつけていた。
1990年、昭和を見送った日本は、どこかまだ虚脱状態にある。
3月に公定歩合が5.25%に引き上げられると、株価は一気に暴落し、3万円台を割る。
バブルが破裂したのに、日本人はそれを直視しないまま、バブルの傷を深くしていく。
1991年、イラクがクウェートに攻め込んだため、湾岸戦争が発生する。多国籍軍が勝利し、イラク軍は撤退、停戦協定が結ばれる。
すでに東西ドイツは統一されていた。それに引きつづき、アゼルバイジャンやリトアニアにも独立の動きがでる。ソ連はそれを武力で押さえ、ゴルバチョフが初の大統領に就任する。
共産党保守派はゴルバチョフ追放のクーデターをくわだてるが、失敗する。そのあと権力を握ったのはロシア共和国のエリツィンだった。これによって、ソ連は崩壊し、12月25日に消滅する。
1992年3月、日本の株価はついに2万円台を割り、8月にはさらに1万5000円を割り込む。
警視庁は佐川急便事件の捜査に着手していた。11月には竹下登元総理が国会で喚問される。
日本人は度重なるスキャンダルにうんざりしていた。
1993年、中東ではパレスチナ解放機構のアラファト議長とイスラエルのラビン首相のあいだで平和条約が結ばれる。だが、これでパレスチナ問題がすべて解決されたわけではなかった。
橋本治はユダヤ人問題は「本来ヨーロッパで処理されるべきもの」だったはずで、それがパレスチナに持ち込まれたことで、問題がさらにややこしくなったと書いている。
日本では不況を打開するために、公定歩合が1%台まで引き下げられた。だが、一向に景気は上向かない。
政治不信は強く、自民党は分裂し、日本新党の細川護熙が非自民連立政権を組んで首相となる。だが、それも長くはつづかなかった。
1994年6月、自民党と社会党が連立を組み、社会党の村山富市が首相に。それを見て、人びとはあっけにとられた。
1995年は、何といっても阪神淡路大震災とオウム真理教事件に尽きる。ふたつとも、まさかのできごとだった。
大震災は日本があらためて地震国であることを認識させた。だが、それからしばらくして、さらに大規模な震災がつづくとは、このとき誰が予測しただろう。それは終わりではなかったのだ。
つづいておこったオウム真理教事件は意味不明のばかげた教理に、なぜ多くの人がひきつけられたのかという謎を残す事件だった。日本は病んでいた。
1996年、社会党の村山富市が首相を辞任、自民党の橋本龍太郎が首相になった。新たに厚生大臣になった菅直人はエイズ問題に取り組み、厚生省がいかに不都合なデータを隠していたかを暴いた。
住宅金融専門会社(住専)による不明瞭な融資をはじめ、さまざまな金融スキャンダルが露見する。
都合の悪いことは隠蔽するという日本官僚社会の体質がさらけだされた。それはいまも一向に改まっていない。
1997年、香港が中国に返還される。タイのバーツにはじまり、韓国のウォンも暴落する。アジア通貨危機である。
「ヘッジファンド」ということばが聞こえてきた。余った巨額のカネが世界中をうろつき回る時代になった。
日本経済は破綻していた。山一証券が自主廃業を決定する。
神戸では、酒鬼薔薇聖斗を名乗る14歳の少年による猟奇的な殺人事件が発生する。
1998年、北朝鮮のミサイル、テポドンが日本上空を通過する。
インドとパキスタンが核実験をおこなう。
大蔵省の官僚がノーパンしゃぶしゃぶで過剰接待を受けていたことがわかる。
和歌山では、毒物カレー事件が発生する。
長野では冬季オリンピックが開かれていた。
不良債権処理に苦しむ銀行への公的資金投入が実施されるのもこの年だ。「バブル経済の破綻による、人間関係の破綻」が広まっていた。日本人のモラルが壊れようとしていた。
1999年、世界の民族紛争が頻発している。
旧ユーゴスラビアのコソボ自治区では、セルビア人によるアルバニア系住民の虐殺がつづいていた。東ティモールではインドネシアからの独立を求めて、住民が決起する。
不景気の日本では、経済効果ということばが魔法の杖となり、「ミレニアム・カウントダウン」騒ぎがはじまっている。
2000年、20世紀最後の年には、少年たちの犯罪が続出する。
愛知県では17歳の少年が「人を殺してみたかった」という理由で、近所の主婦を刺殺する。バスハイジャックや金属バット殺人事件、恐喝事件もおこっている。
柏崎市では、37歳の男による少女監禁事件が発覚する。大阪では23歳の男が「私は神」と称する声明文を用意して、通り魔殺人をおこなった。
橋本治の描く20世紀末の未来図は暗い。
〈日本の社会を動かしている人間達は、自分達のなすべきことで手一杯になっていた。そこに“未来”への展望はない。いつの間にかゴールを欠いて、しかし少年達を乗せたベルトコンベアは動き続けていた。動いていればこそ、そのベルトコンベアは“破綻”を示さない。しかし、そのベルトコンベアの先には、なにもないのだ。それが20世紀最末年の日本である。〉
20世紀は終わる。だが、橋本治はけっして明るい21世紀を夢見ていなかった。
橋本治『二十世紀』を読んでみる(7) [本]
.jpg)
1974年、立花隆の「田中角栄研究」が出て、田中角栄が総理大臣を辞任する。ウォーターゲート事件でアメリカのニクソン大統領も辞任する。2年後、ロッキード事件が追い打ちをかけ、田中角栄は逮捕される。それ以降は裁判を闘い、闇将軍の道を歩む。
1975年、日本は不景気だが平和だった。紅茶キノコがブームになっている。アメリカはヴェトナムから撤退し、北ヴェトナム軍によってサイゴンが陥落。ヴェトナム戦争が終わる。カンボジアでは、ポル・ポトのクメール・ルージュがプノンペンを制圧する。
スペインのフランコ、台湾の蒋介石が死に、翌年、中国の毛沢東が死ぬ。古い独裁者の時代が終わる。
1976年、昭和は老いていく。自民党を離党した議員6人が新自由クラブを結成する。脱サラが流行する。
1977年、アメリカ西海岸で、アップルのコンピューターが誕生する。映画『スターウォーズ』が公開される。ヴァーチャル・リアリティの時代がはじまる。日本ではピンク・レディが次々とヒット曲を生みだしていた。大学闘争をへて、就職した団塊の世代は、もはや社会変革を叫ぶことなく、社会に順応していく。
1978年、南米のガイアナで、アメリカのカルト集団「人民寺院」の信者900人が集団自殺する。「人民寺院の事件は、社会に異を唱え、そのまま閉鎖され停止してしまった者達の末路を伝えるもの」だ、と橋本治はいう。
しかし、カネのために生きる近代流の生き方に異を唱える人たちも確実に広がっていた。イランではイスラム原理主義革命によって、親米の独裁者、パーレビ国王が追放された。
橋本によれば、これはキューバ革命と同じパターンなのだが、これ以来、反米のイランにアメリカは敵愾心を燃やすことになる。
1979年の日本人は欧米のジャーナリストから「ウサギ小屋に住む仕事中毒患者」と揶揄されている。
〈1970年代を経過して、「モーレツ社員」という言葉は日本人の間に深く定着していた。「貧しさからの脱出」とは、そのまま「豊かさへの一直線」になるはずで、日本人は、あるはずのゴールを目指してひた走りに走っていた。ところがしかし、そのゴールがいつの間にかなくなっていた。〉
次の時代は「心の時代」になるはずだった。そのころ、京都にノーパン喫茶がオープンする。「フーゾク」が産業になり、「オタク」が出現する。インベーダーゲームとウォークマンがはやる。
日本人は孤独だった。若者たちは、社会の一角で、社会との無縁を演じはじめる、と橋本治は書いている。
1980年、山口百恵が引退する。貧しい家で母親に育てられた彼女は、新聞配達をしてギターを手に入れ、テレビのオーデション番組で優勝し、歌手になった。
〈山口百恵は、「結婚」というゴールを勝ち取った。「仕事よりも結婚」を選択し、「結婚しても仕事を続ける」という選択をしなかった。不幸な家庭に育った彼女は、幸福な結婚を望んだ。……「新しい女の時代」に、山口百恵は少しも新しくなかった。山口百恵の新しさは、新しさが主流となろうとする時代に、平気で“古さ”を掲げたことだった。〉
1981年、イギリスのチャールズ皇太子がダイアナと結婚する。これにより、ダイアナは「世界一有名な女性」の一人となった。
だが、彼女の華やかな国際親善活動の影には、大きな問題が隠されていた。それがとうとう1996年の離婚、そして翌年の悲劇的な事故死へとつながっていく。
ダイアナが登場したころ、日本では松田聖子がアイドルになっていた。「20世紀末の20年間、許された大衆の欲望は、無限定な上昇志向となり、社会を変容させていく」
松田聖子は、そうした大衆的欲望の象徴だった、と橋本はいう。
1982年、エイズと名づけられた奇病が、人びとを震撼させる。
エイズは男どうしの性交渉によってだけではなく、異性間の性交渉でも感染することが明らかになる。決定的な治療法はなく、できるのは感染者の発病を遅らせることだけだ。
エイズは語られなかった性行為の存在を浮上させる。その人類史的意味はどこにあるのだろう。
1983年、日本は豊かだった。プラザ合意によって、円高が是認される。この年、日本では豊かなアメリカを象徴するディズニーランドがオープンし、そのいっぽうでは、かつての貧しさをえがく「おしん」が放映される。やがて「おしん」はまだ貧しいアジアの国々で喝采を浴びることになる。いまでもアジアの国の人たちが日本を好きなのは、なかば「おしん」のおかげだ。
しかし、日本ではすでにスクラップ&ビルドが進行し、モデル・チェンジが主流になりつつある。レコードの代わりにCDが登場するように、車も住宅もテレビも冷蔵庫も、何もかもがモデル・チェンジの時代である。
1984年、「日本は豊かで、国家に頼るまでもなく、民間の力は旺盛だった」と、橋本治は書く。強大な管理社会は求められていない。それよりも豊かさのなかの自由が求められていた。それが可能だったのは、民間の力が旺盛だったからだ。
〈[利潤の追求に]限定された欲望で生きる会社は、国家ほどには表立った抑圧を強制しない。国家に比べて、会社はより気弱な抑圧者である〉
人がある国に生まれる以上、国家を選択する自由はほとんどない。しかし、会社を選択するのは、少なくとも多少は自由だ。
だが、会社社会の「日本はただ騒がしく豊かで、モラルは宙ぶらりんのままだった」と、橋本治は記している。
1985年、円高を背景に、日本人はやたら海外旅行をするようになる。ブランド品を身につけるようにもなった。
テレビはお笑いの時代にはいり、シロウトの時代にもなる。少女マンガは大きく変わった。サブカルチャーが勃興し、「大衆の時代」が定着する。
子どものあいだでは「いじめ」が深刻化する。家庭内暴力も話題になり始める。
1986年、ソ連のチェルノブイリ原発が爆発事故を起こす。その前年、ソ連ではゴルバチョフが共産党書記長になっていた。だが、原発事故の真相はなかなか伝わってこなかった。ゴルバチョフがグラスノスチ(情報公開)を掲げていたにもかかわらず。
ゴルバチョフが共産党書記長に就任したとき、ソ連の経済は破綻しかけていた。その原因は大きすぎる軍事予算だった。ゴルバチョフは軍縮に舵をとるが、党内の保守派はそれに抵抗した。いっぽうのアメリカはタカ派のレーガン大統領が「強いアメリカ」にこだわっていた。
深刻な原発事故は党内保守派の介入を一時的に弱める。そこで、ゴルバチョフはペレストロイカを推し進める。それがソ連の終わりをもたらす、と橋本は書いている。
ほんとうに、いろんなことがあった。20世紀はそろそろ終わろうとしている。
橋本治『二十世紀』を読んでみる(6) [本]

1960年は安保闘争の年だ。首相の岸信介は反対の声が渦巻くなか、改定安保条約の批准を強行した。改定の目的は「アメリカに日本防衛の義務を負わせること」だった。それ自体は一見よさそうにみえる。だが、橋本にいわせれば、それは、日本がアメリカの片棒をかついで、アメリカへの協力姿勢を強めるための改定だった。
「[日本は独立したが]自立がないから、すべての議論は依存の中で空回りする」と、橋本は書いている。
1961年には池田勇人内閣の「所得倍増計画」がスタートする。そのあと、日本は東京オリンピックを迎え、高度成長に突入する。「所得倍増計画」という選挙用のスローガンは大受けして、前年の暗いムードを吹き飛ばし、人びとに「月給が倍になる」という幻想をいだかせた。もっと働いて、カネ儲けをしようという風潮が広がっていく。
1962年にはキューバ危機がおこる。ソ連製の攻撃用ミサイルがキューバに持ちこまれていることがわかり、アメリカのケネディ大統領はその撤去を求めて臨戦態勢にはいる。
これをみると、悪いのはキューバとソ連のようにみえるが、橋本はかならずしもそうではないという。
1959年のキューバ革命は、親米のバティスタ独裁政権を倒した。だが、アメリカは革命指導者のカストロを「赤」呼ばわりして、さまざまな経済制裁を科し、CIAによるキューバ侵攻作戦さえ実施した。その結果、キューバを社会主義陣営へと追いこんでいった。いわば自業自得なのである。
キューバ危機は回避されるが、「『キューバ危機』とは、冷戦構造の結果ではなく、アメリカのエゴの結果である」と、橋本治は明言している。
1963年11月22日、テキサス州ダラスでケネディが射殺される。事件の真相はいまだに謎だ。後任のジョンソンはヴェトナム戦争をエスカレートさせ、「北爆」を開始する。ヴェトナム戦争もケネディが準備したものであり、1975年までつづくことになる。
1964年10月10日、東京オリンピックが開かれる。それに先立ち、東海道新幹線が営業をはじめる。
東京オリンピックは「戦後の廃墟から復興を遂げた東京の市街を、徹底的に破壊するところから始まった」。川の上に高速道路がつくられ、下水道工事が加わり、競技場や周辺設備がつくられ、皇居の外堀が埋められ数寄屋橋がなくなる。その前に、東京タワーが完成していた。
「『作って壊す、壊して作る──そうすれば繁栄は訪れる』という信仰の始まりが東京オリンピックにあるのは間違いない」。日本人はへんなところでせっかちで、ミエっ張りだ、と橋本はいう。
1965年1月、日本ではじめてスモッグ警報が出される。「公害」という言い方はまだ定着せず、「環境汚染」ということばもない。大気汚染防止法ができるのは1968年のこと。1970年には「光化学スモッグ」が出現する。大量消費が大量のゴミを生みだしていた。
水俣では10年以上前から水俣病が発生していた。チッソの排水に含まれる有機水銀が原因だった。だが、企業はなかなか責任を認めようとしなかった。
1966年、日本にビートルズがやってきた。長髪がはやりはじめる。女性のあいだでは、まもなくミニスカートが流行する。
早稲田大学では授業料値上げ問題などから全学ストが発生し、学生運動時代の走りとなる。
中国では文化大革命がはじまり、1976年までつづく。「文化大革命は、1959年に国家主席を辞任した毛沢東の逆襲である」と橋本は明言する。中国は、近代化に失敗して失脚した「毛沢東を思想上の“皇帝”とするラジカルな原始時代へ逆戻りする」。
毛沢東はどこかズレていた。だが、若者たちは、造反には意味があるとのメッセージを受け取る。
1967年、アメリカでは『俺たちに明日はない』、『卒業』といった「ニュー・シネマ」が誕生する。もはや建前やきれいごとの時代ではない。
ヴェトナム戦争では「枯れ葉剤」が使われ、ニューヨークでは大規模な反戦デモが繰り広げられる。さらに7月にはデトロイトで、史上最大の黒人暴動が発生した。
東京では美濃部亮吉の革新都政が誕生する。
中東では第3次中東戦争が発生し、イスラエルがエジプトに圧勝する。ヨーロッパではEC(欧州共同体)が結成される。
10月には佐藤訪米を阻止しようとして、三派系全学連による羽田闘争がおこる。新左翼の登場である。
1968年、医学部の学生処分問題から東大闘争が広がる。使途不明金問題から日大闘争がおこる。フランスでは5月革命が発生する。
アメリカはヴェトナムで北爆をつづけており、中国では文化大革命が進行している。社会主義からの自由を求めて立ちあがったチェコにソ連の戦車が侵攻する。
1969年、ニクソンは北爆を強化する。
東大の安田講堂に籠もる学生たちは、機動隊によって排除された。全共闘運動が広がり、全国全共闘連合が結成される。だが、ノンセクト・ラジカルは集団とはなりえず、けっきょくは散らばっていく。そのなかで過激化したグループが赤軍派などを結成するが、豊かな時代のなかに「新しい思想」は宿らず、ひたすら崩壊の道をたどる。
アメリカでは40万人の若者を集めたロックコンサート「ウッドストック」が開かれる。宇宙船アポロ11号が月面着陸を果たす。
橋本治はこう書いている。
〈1969年に、「思想」はその役割を終えた。「思想」は「豊かさ」を作り、その豊かさの中で「思想」は不必要になった。1970年から始まるのは、「思想」を必要としない「大衆の時代」なのである。〉
1970年、大阪万博が開かれる。万博ではアポロ11号が持ち帰った「月の石」が展示されていた。日本は「繁栄の時代」に突入する。
3月には赤軍派によるよど号ハイジャック事件、11月25日には東京市ヶ谷での三島由紀夫事件が発生するが、これを契機に「繁栄の日本から、極左の学生も極右の作家も去って行った」。
ビートルズが解散する。アメリカでは女性解放のデモ行進や、ウーマンリブの集会が盛んになる。
日本では石牟礼道子の『苦界浄土』がベストセラーになった。「公害は、企業と国家権力が『悪』であるというところから始まって、やがては、文明社会・市民社会のあり方そのものが大気汚染・水質汚染を生むというところへ進む」
1971年は大衆元年だ、と橋本治は書く。銀座では歩行者天国が始まり、マクドナルドが銀座三越に第1号店をオープンした。日清食品はカップヌードルを発売。新宿には超高層ホテルが誕生し、多摩ニュータウンができあがる。繁華街の中心は銀座から新宿・渋谷・池袋に移りつつある。スーパーマーケットの時代がやってくる。
1972年、グアム島で元日本兵、横井庄一が発見される。さらに2年後、フィリピンのルバング島で小野田寛郎が発見される。沖縄が日本に復帰し、日中国交回復が実現する。
追い詰められた学生運動の生き残り、連合赤軍のメンバーがあさま山荘事件をひきおこし、別のメンバーがイスラエルのテルアビブで銃を乱射する。佐藤栄作が辞任し、田中角栄が総理大臣になっていた。
荒井(のちの松任谷)由実が歌手デビュー、『緋牡丹博徒』シリーズの藤純子がスクリーンを去る。歌謡曲に代わって、フォークソングがヒットし、やがて「ニューミュージック」となる。貧しい、つらいに代わって、オシャレが思想になっていく。
1973年には第4次中東戦争を契機に、オイルショックが発生する。原油価格が上昇し、夜の町からネオンが消える。石油の値上げで、ペルシア湾岸の産油国は一時的に大儲けした。先進国のあいだでは省エネ・省資源の考え方が生まれる。オイルショックの前、通貨は変動相場制に移行していた。円は強く、日本は世界最強の経済大国となった。
あのころのことを、いろいろ思いだす。
橋本治『二十世紀』を読んでみる(5) [本]
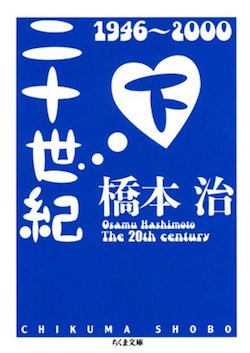
文庫版では下巻。
1946年には、すでに第2次世界大戦は終わっている。
だが、すっかり戦争のカタがついたわけではない。
19世紀以来の帝国主義時代の清算も終わっていない。ナチス・ドイツを倒すため、かりそめに結束した米ソの対立も鮮明になってくる。
20世紀後半は、それらの課題を解決するために費やされたようなものだ。
インドネシア、アルジェリア、ヴェトナムなどでは、独立に向けての動きがはじまっていた。
チャーチルは「鉄のカーテン」演説をぶち、ソ連による東欧支配を糾弾する。
日本は虚脱状態にある。極東軍事裁判がはじまり、新憲法が公布される。ラジオからは、「素人のど自慢」の歌声が流れていた。
1947年、アメリカで「赤狩り」がはじまる。トルーマンが社会主義とソ連を敵視するようになると、世界はたちまち「冷戦」状態に突入する。
1948年にはベルリンが封鎖され、朝鮮半島が韓国と北朝鮮に分断される。ヴェトナムも南北にわかれる。
とはいえ、ベビーブームの年でもある。アメリカでは「キンゼー報告」が発表され、人間の性行動に光が当てられるようになった。
1949年、ドイツは西と東に分かれる。毛沢東が中華人民共和国の成立を宣言する。蒋介石は台湾に逃れ、台北を首都とする。ふたつの中国が生まれた。
東欧はソ連の衛星国になっている。
1950年、朝鮮戦争が始まる。北の軍隊はたちまち南のソウルを占拠し、釜山に迫った。国連軍はこれを押し戻し、鴨緑江にまで迫るが、ここで中国軍が参戦し、形勢がふたたび逆転する。
1951年、朝鮮での戦争は膠着状態となる。トルーマンは中国に攻め入るというマッカーサーを解任し、北に停戦を呼びかけた。帰国したマッカーサーの「日本人は12歳の少年」という発言が物議をかもした。
この年、日本はサンフランシスコ講和条約を結び、主権を回復する。アメリカとの安保条約も締結された。
ラジオでは紅白歌合戦がはじまり、黒澤明の『羅生門』がヴェネツィア映画祭でグランプリをとる。
日本人はマッカーサーの発言に憤激したが、はたして日本人は一人前だったのか、と橋本治は問うている。
〈日本人は、占領軍の言うことを聞いたが、自分達の手で軍国主義者を追うことはしなかった。「占領軍がそれをやってくれた」と思う日本人は、それを自分達自身の手でやらなければいけないものとは思わなかった。……その後の日本人達の戦争責任に対する認識の薄さは、おそらくそのことに由来するのだろう。〉
日本ではGHQの指導のもと、1945年に労働組合法がつくられ、労働組合運動が活発になっていた。1947年にゼネストは中止させられるが、その後も組合運動は衰えたわけではない。
アメリカは日本を共産主義の防波堤にしようとしていた。1951年、共産党は武装闘争方針を採用する。
1952年、メーデーのデモ隊は皇居前広場を「人民広場」にしようとして、警官隊と衝突する。いわゆる「血のメーデー事件」である。
国会では破壊活動防止法が成立し、追放された軍国主義者が次々復帰を果たす。
1953年、スターリンが寿命を全うして死ぬ。まもなくフルシチョフがソ連の新指導者になる。フルシチョフは1956年にスターリンを弾劾する。この「雪解け」をみて、ポーランドとハンガリー、チェコはソ連の支配権から脱しようとするが、ソ連の戦車が進駐し、それを阻止する。
1954年、第5福竜丸がアメリカの水爆実験で被曝する。
戦争が終わったあとも、米ソの核実験は平然とつづけられていたどころか、むしろエスカレートしていた。
その結果、核兵器があまりにも多くなり、「うかつには戦争が出来ない」状態が生まれる。
防御のための核兵器という考え方から「核の抑止力」という倒錯めいた幻想が生まれる。「冷戦以後の世界には“豊かさ”が溢れ、しかし、なんだか落ち着かなかった」と橋本はいう。
この年、日本ではゴジラが映画に登場し、プロレスの力道山が人気を博した。中村錦之助主演の『笛吹童子』もヒットする。
アメリカでは、オードリー・ヘップバーンの『ローマの休日』が公開された。
1955年、石原慎太郎が『太陽の季節』でデビュー。アメリカではプレスリーがはやっていた。ジェームズ・ディーンがスクリーンに登場する。若者の季節がはじまろうとしている。
1956年、『経済白書』は「もはや戦後ではない」とうたう。日本経済が復興を遂げたという宣言だった。
政治の世界では、前年、すでに鳩山一郎と吉田茂による「保守合同」が実現し、自由民主党が誕生している。
橋本治は、鳩山一郎はとても政党政治家とはいえず、「公職追放にあっても不思議はない」人物だった、と書いている。いっぽうの吉田茂は「アメリカ第一主義」で、「傲慢なワンマン総理」。
このふたりが一緒になることで、政治も復興して、戦前のよき時代に戻ったことになる。その延長上に岸信介が現れる。橋本が「日本には、他に人材がいなかったのか?」と嘆くのももっともだ。
1957年、ソ連が人工衛星スプートニクを打ち上げる。日本ではそのころ「鉄腕アトム」がはやっている。
ソ連に先を越されたアメリカは悔しがり、翌年、航空宇宙局(NASA)を発足させる。以来、米ソによる宇宙開発競争が始まる。
人類が月に降り立つのは1969年である。だが、はたしてその目的は何だったのか。「ヤケっぱちの大人は、『月に行く』だけを考えて、その先を考えていなかった」
スーパーのダイエーが大阪に誕生したのも1957年である。翌年、ダイエーは神戸の三宮に2号店をオープンする。
そのころはまだデパートと商店街の時代である。私鉄の駅を拠点として団地の建設ラッシュがはじまる。
やがて、スーパーが中途半端に高級化すると、激安店が登場する。そして、1990年代にバブルがはじけると、スーパー業界にも過剰投資のツケが回ってくる。
だが、1958年の日本はまだ貧しく、無限の消費成長が信じられていた。大量生産がゴミの山を生みだすのは、まだ先のことだ。
1959年4月10日、皇太子の成婚記念パレードがテレビ中継される。このころから、日本中にテレビが普及する。プロレス中継は人気番組だった。だが、橋本は「テレビの普及は、日本人の孤独と貧しさの始まりとも重なりうる」という。
〈テレビがなくても生きていられる──その豊かさを持つ日本人はいくらでもいた。だから私は飽きなかった。だからこそ「テレビがある」以外にはなにもない人の持つ“貧しさ”を感じとってしまったのかもしれない。テレビを見ているだけの人は、テレビを見ているだけで、遊んではくれないのだ。〉
橋本治にとって、これは子ども時代の実感だった。
つづきはまた。
橋本治『二十世紀』を読んでみる(4) [本]

相変わらず、ぼちぼち橋本治の『二十世紀』を読んでいます。
そのつづき。
橋本治流にいえば、歴史は、何かへん、バカじゃないの、と問いかけるところからはじまる。逆に、そう問いかけることが禁じられたり、無視されたりする時代はどこかおかしいということになる。権力が好き勝手なことをするときは、何かヘンで、バカなことが起きているにちがいないのだ。
1930年代にはいろうとしている。
早足で、そのころのことを見ておくことにしよう。
1928年、日本でははじめて普通選挙が実施された。だが、この年には、同時に治安維持法も適用されている。普通選挙と左翼思想の取り締まりは一体となっていた。このあたりは、いかにも日本的だ。
このころ軍部は満州を手に入れようとしている。そのため、邪魔になってきた張作霖を爆殺した。政府はこの事件を隠蔽しようとするが、真相は次第に漏れ伝わってくる。
1929年、世界恐慌が発生する。橋本治によれば、恐慌とは、バブルがはじけることにほかならない。当時、アメリカは「世界一の工場主」であり、同時に「世界一の金持ち」だった。そのアメリカがこけると、世界中がみなこける。
1930年、日本では浜口雄幸首相が右翼に襲われる。こうしたできごとをみると、いかにも日本は暗い時代に向かっていたようにみえる。
しかし、暗い時代には、かえって明るいイベントが求められるのが不思議なところ。
1930年は、関東大震災からの復興を祝う「帝都復興祭」の年でもあり、昭和天皇の即位式もあって、各地ではさまざまな行列が催されていた。
円本ブームもあり、映画はまだサイレントながら、大流行。ラジオでは早慶戦が人気を博し、数々の歌謡曲がヒットしていた。映画館や芝居小屋の立ち並ぶ浅草はにぎわっていた。人びとは忍び寄るファシズムにおののいていたわけではなかった。
そんな明るい雰囲気のなか、軍部は暴走する。
1931年、満州事変が勃発する。当時は「満蒙は日本の生命線」という言い方がされていた。じつは、この「日本」とは韓国(朝鮮)のことだった、と橋本はいう。韓国こそが日本の要と考えられていた。日本人はなぜそれほど韓国がほしかったのか。それがひとつの謎である。
帝国の妄想が膨らんで、日本はついに満州を攻略するにいたるのだが、じつは日本には満州を経営するだけの力はなかった。満州とは「ただ『勝った』という栄光の記憶」にすぎない、と橋本はいう。その栄光の記憶が日本を戦争に引きずりこんでいく元凶になる。
1932年、軍部は国内でも暴走しはじめる。五・一五事件で犬養毅首相が暗殺されたあと、政府は軍に逆らえなくなる。
1933年、ドイツではヒトラー政権が誕生する。
第一次世界大戦後のいじめに、ドイツは切れた。それがナチスの台頭をもたらす。ヒトラーは賠償金の支払いを拒否し、孤立と戦争への道を選ぶことになる。ドイツ国民は、そんなヒトラーに喝采した。
1934年、ドイツではヒトラーが全権を握り、ワイマール共和国が崩壊する。そのころ、アメリカでは禁酒法が廃止され、「健全な娯楽」として、ハリウッド映画が全盛を迎える。トーキーの時代がはじまっていた。
1935年、ドイツではニュルンベルク法が制定され、ユダヤ人排除がはじまる。しかし、最初からユダヤ人絶滅政策がとられたわけではない。
「ユダヤ人、消えてなくなれ」というのが、庶民の感情である。ナチスはその感情につけこむ。
それと同時に、ナチスはスラブ人をも排除の対象にした。ヒトラーはポーランドからスラブ人の土地を奪い、そこにドイツ人を入植させようと考えていた。それがまたドイツ人に支持される。
「スラブ人奴隷化殲滅計画の方が、ユダヤ人絶滅=皆殺しよりも先」だったと、橋本は注意をうながす。
〈人間のこわさというものは、その初めに極端で矛盾に満ちた方針を立てると、やがてそれに合わせてもっともっと極端な矛盾を冒し始め、その極端や矛盾を「極端」や「矛盾」と自覚しなくなるところにある。ポーランド人やユダヤ人を虐殺していたドイツ人達には、おそらく、自分達のしていることが殺人だという自覚はなかっただろう。……ポーランド人は強制収容所へ送られ、ユダヤ人も送られ、同性愛者も送られる。「自分達と違う者」は「いやな者、劣った者」で、そのレッテルを貼られた者は、みんな追放=処分の対象になる。矛盾と極端を容認した者は、やがてその矛盾と極端に合わせて、もっとひどいことを始める。〉
何かへん、バカじゃないのという問いは圧殺されている。
1936年、スペイン内戦がはじまる。スペインはその5年前に王政が倒れ、共和国になっている。だが、国内は分裂していた。1933年、フランコ率いる保守政党ファランヘ党が政権を握る。しかし、1936年に左派の諸勢力が人民戦線をつくり、政権を奪取し、保守派を放逐する。
これにたいし、イタリアとドイツの後ろ盾を得たフランコが武装蜂起し、内戦が勃発するのだ。人民戦線はさまざまなグループの集まりだったが、スターリンがその主導権を握ろうとしたため、内部の対立が激しくなり、独立左派は抹殺された。けっきょく、スペインではフランコが人民戦線側を破り、その後、長期にわたる独裁政権を築くことになる。
同じ1936年、日本では二・二六事件が発生する。これは陸軍の皇道派によるクーデターだったが、失敗に終わる。
その後は統制派が軍を掌握し、事実上の軍事政権が確立する。軍は反乱軍を抑えただけではなく、政権をも握ったのだ。新たな軍事政権の最大の目標が満州の保全だったことはまちがいない。満州をより安定的なものにするために、軍は華北の一部を切り取る工作も辞さなかった。
1937年7月7日、北京郊外の盧溝橋での衝突をきっかけに、日中戦争がはじまる。だが、当時は日中戦争と呼ばれていなかった。「北支事変」、「支那事変」という言い方がされていた。
なぜ戦争でなく、事変なのだろうか。日本側は、それがあくまでも突発的な戦闘だとみていた。それに、中国の国民政府を認めていなかった。だから、国どうしの戦争ではないというわけである。
日本は南京に傀儡政権をつくって、それを交渉相手にして、事態を収拾しようとこころみた。だが、そんなことが思い通りいくわけがなかった。
〈日本は、対戦相手の存在を無視して、この後も中国での戦闘を続ける。なるほど日本人の頭では、「戦争」ではない「事変」なのだ。相手国の存在を否定してかかる戦争などあってたまるものかと思うのだが、日本は、そのように中国を蔑視していたのである。〉
侮蔑意識と傲慢さが、冷静な判断をできなくさせている。あとは破局まで突きすすむしかない。
1939年9月1日、ドイツ軍がポーランドに侵攻する。これにたいしイギリスとフランスが宣戦布告し、第2次世界大戦がはじまる。
その前に、ドイツはすでにオーストリアとチェコを併合していた。
20世紀の大衆文化はこのころ黄金時代を迎えている。
〈不思議だが、人間というものは、豊かさの中で破滅への準備をするらしい。……第2次世界大戦前は「豊かな時代」だった。だからこそ戦争は起こったのだ。〉
思わずうなってしまうフレーズである。
1940年、中国との泥沼の戦争がつづくなか、日本ではいつのまにか戦時体制が敷かれていた。日本のファシズムには明確なポリシーがなく、いつはじまったかもわからない。
「『一歩踏み出した以上もう後戻りは出来ない』だけで前に進むから、いつの間にかとんでもないことになってしまっている」と、橋本はいう。
1941年12月7日、日本軍は真珠湾を奇襲攻撃する。ナチスの破竹の勢いに便乗したともいえる。しかし、すでにナチスの党内はガタガタになっており、そのことに日本はまったく気づいていない。
1942年6月のミッドウェー海戦で、日本はアメリカ軍から壊滅的な打撃を受ける。それ以降、日本は負け続けになり、「限界以上の無茶」を重ねて、ついに焼け野原になる。
日米開戦前の日本には「アメリカか、ドイツか」の選択肢があり、どっちがトクかはバカでも分かるのに、「日本はバカ以下だった」と、橋本は明言する。
1943年には、とつぜん東京市が廃止され、東京都が生まれる。行政の簡素化は軍事体制と無縁ではない。「東京が『東京市』のままだったら、東京ももう少し違ったものになっていただろう」と橋本は書いている。一見よさげな都構想なるものには、注意が必要だ。
1944年は戦争以外、何もない、と橋本治は書く。
6月6日には連合国軍がノルマンディに上陸し、ドイツ軍は防戦一方となる。ハリウッドはのちにこの時期の戦闘をテーマに数々の映画をつくりだす。映画はいかにも悪役のナチスそここぞとばかり描き出す。これ以降「ファシズムに勝利する自由主義」がハリウッドの定番となる(『スターウォーズ』にもその伝統は引き継がれる)。
この年、日本も敗退を重ね、ついに11月にはB29による東京空襲がはじまる。
1945年4月28日、ムッソリーニがコモ湖畔で処刑される。4月30日、ヒトラーがベルリンで自殺する。日本は8月15日に降伏。これにより30年つづいた「戦争の時代」は終わった。
しかし、その後も、戦争状態は世界のどこかでくり返されることになる。
〈「危機」はあっても、実際上の戦争は起こらない。“周辺”は騒がしいまま、世界の“中心”は平和だった。ある意味で、歴史はゴールにたどり着いたのである。〉
だが、ほんとうに歴史は終わったのだろうか。それが、橋本の次の問いかけである。
橋本治『二十世紀』を読んでみる(3) [本]

引きつづき橋本治の『二十世紀』を読んでいる。
1910年代だ。
1911年には帝国劇場がオープンする。中産階級のあいだでは「今日は三越、明日は帝劇」といわれるようなライフスタイルがはじまっている。しかし、奥さんたちが着ているのは、まだ着物である。
平塚らいてうは雑誌『青鞜』をつくる。青鞜は青いストッキングのこと。そのころ、日本ではだれも青いストッキングなんかはいていなかっただろう、と橋本はいう。
しかし、歴史はファッションやライフスタイルから動いていく。
ヨーロッパでも、ファッションがシンプルになるのもこのころから。裾を引かないドレスが登場し、コルセットに替わってブラジャーが登場する。
女性が、ただ見えるだけでなく、ますます見せる存在になっていく。
1912年にはアルフレッド・ヴェーゲナーが「大陸移動説」を発表する。ゆるぎないと思われたこの大地が動いているという感覚。自己も絶対ではない。国家も絶対ではない。相対的なものだ。相対主義の時代がはじまっている。そのなかで、人はどのようにみずからの針路を見つければよいのだろうか。
この年、日本では明治が終わり、夏目漱石が『こころ』を発表する。美濃部達吉はいわゆる「天皇機関説」を示した。
中国では中華民国が成立する。世界は揺れている。
1913年、第1次世界大戦が勃発する。それは日本にとっては、遠い欧州の戦争のように思われた。したがって、当時の名称は「欧州大戦」。まさか、それが、「第1次世界大戦」になるとは、だれも思っていない。
日本では藩閥政治に代わり政党政治を求める声が高まっていた。いわゆる「大正デモクラシー」。政治を担うのは、元老と藩閥ではなく、国民の代表であるべきだ。
東京では笹塚から調布まで、京王電鉄が走るようになる。すでに山手線は走っていた。だが環状線にはなっていない。その要となる東京駅ができるのは、ようやく1914年のこと。
東京の歴史がはじまるのは、やっとこのころからだ、と橋本治は書いている。
サラエボから火の手が上がった戦争は、ドイツ対フランス・イギリスの戦いになってしまう。オーストリアとセルビアはそっちのけ。「これを『バカバカしい』と言わずしてなんであろう」
だが、ナショナリズムをあおって突きすすむ「バカげた」戦争がはじまるのも20世紀になってからだ、と橋本はいう。もはや、戦争は王族どうしの勝手な戦争ではありえなくなっている。
このとき日本はドイツに宣戦布告して、中国の青島を攻撃する。戦争は好景気をもたらした。イケイケのバブルになる。そのあと、調子に乗って、中国に「二十一カ条」の要求をつきつけたりもした。
日本は戦争をして領土を増やす(勢力を拡大する)という発想にこだわっている。それはすでに古臭い発想だった。
「近代日本の対外的ゴタゴタの原因は、日本が“市場”ではなく“領土”を求めたその古臭さによるものだろう」と、橋本。
ヘン、バカげた、古くさが、日本の近代史を読み解くキーワードだ。
戦争中の1916年にフランツ・ヨーゼフ1世が亡くなると、オーストリア帝国はひたすら解体への道をたどる。名門ハプスブルク家は終焉を迎える。
1917年、ドイツを出自とするイギリスの王家はそれまでのドイツ風家名を「ウインザー家」とあらためる。
ヨーロッパでの戦争はまだつづいていた。スイスに亡命中のレーニンはロシアに戻る。3月8日、デモとストライキの騒乱状態のなか、ニコライ2世は退位。これで、ロシアにも皇帝はいなくなり、ロシアは共和国になる。
さらに11月6日、ボルシェヴィキの武装蜂起により、ロシアでは史上初の社会主義政権が誕生する。
1918年、やっと第1次世界大戦が終わる。ドイツ帝国からもオスマン帝国からも皇帝が追放される。
ヨーロッパの戦死者はじつに790万人にのぼる。だが、戦争の終わりは、新たな混乱のはじまりとなった。
1919年は冥王星が発見された年でもある(2006年まで、冥王星は太陽系の第9惑星とみなされていた)。同じ年、フロイトは「無意識」を発見する。ドイツではナチス、イタリアではファシスト党が結成される。
1920年、日本は好景気が終わり、不景気になる。しかし不思議なことに、そのころ映画が娯楽の王者となり、雑誌が次々創刊されている。チャンバラ・ブームがはじまる。大阪では日本初のターミナルデパートが出現し、宝塚少女歌劇も創設される。
「右肩上がりの成長神話」が登場したのもこのころだ。
大衆時代は国家(や経済)の拡大を希求する時代でもある。こうして、戦いへのアクセルが踏まれる。
〈第1次世界大戦中の好景気は、日本に「帝国主義的な世界進出」を可能にし、その後の不景気は、「この不景気をなんとかしろ」という形で、日本を帝国主義的侵略の道──戦争へと進ませる。〉
第2次世界大戦が起こるのは、第1次世界大戦がきちんと終わらなかったからだ、と橋本治はいう。
戦勝国は敗戦国に過剰な賠償金の支払いを求めた。取れるものなら取ろうという欲が、戦争を引き延ばし、次の戦争を引き起こすことになる。
1922年、イタリアではムッソリーニが政権の座につく。
イタリアが国になったのはようやく1861年になってからだ。それまでもイタリアはあったが、ひとつのまとまった国ではなかった。そこにイタリアのややこしさがある。
第2次世界大戦を引き起こす枢軸国──ドイツ、イタリア、日本──はある意味では、いずれも新しい国だ。
ムッソリーニが実施した武装デモンストレーション「ローマ進軍」はほんらい鎮圧されるべきであったのに、かえって国王によって評価され、ムッソリーニは首相に指名される。そのあとは、やりたい放題。その無茶ぶりがかえって喝采を浴び、それがヒトラーに引き継がれていく。
1923年、レーニンは脳卒中で再起不能となり、翌年亡くなる。その後はスターリンが実権を握り、ロシアに恐怖政治を敷いていく。
ヒトラーはいわゆるミュンヘン一揆をおこし、逮捕されるが、8カ月ほどで釈放され、その間に『わが闘争』を執筆する。
日本では関東大震災が発生し、大きな被害がでるなか、朝鮮人や無政府主義者が殺害される。不安と妄想が広がっていた。
1924年、監獄から出てきたヒトラーはバイエルンで活動を再開する。そのころワイマール共和国に反対するグループが南ドイツに集まっていた。そのなかで、ヒトラーは頭角を現していく。
1925年、パリではアール・デコ(装飾美術)が登場する。アール・ヌーヴォーが貴族的、ブルジョア的だったとすれば、そのあとにつづくアール・デコは、きわめてシンプル。「大量生産を可能にした近代工業によって送り届けられる『中流市民のための美』だった」
そうした簡略化された美的感覚は、その後、世界中に広がっていく。モダニズムはビジュアルなのだ。
しかし、世の中はますます欲の時代。
〈第1次世界大戦後のヨーロッパを第2次世界大戦へと導くのは、敗戦国ドイツに対する容赦のない賠償金取り立てである。……「二度とドイツが立ち直れないくらい、徹底的に痛めつけてやれ、取れるものは全部搾り取ってやれ」という発想になる。〉
そうした強欲が、ドイツの反発をかき立てることにフランスやイギリスはあまりに無自覚だった。
1927年には、芥川龍之介が「ただぼんやりした不安」ということばを残して自殺する。その翌年、関東軍は張作霖爆殺事件を引き起こす。
さらに、それから3年後、満州事変が勃発する。日本はどうしても満州を取りたかった。
政党政治は阻まれ、葬られた。天皇の名のもとで、軍部が勝手にそのエゴを肥大化させる時代がはじまろうとしていた。
きょうはこのあたりで。のんびり気ままな読書です。それにしても、橋本治という人は、近くだけでなく、ずいぶん遠くまで見ていたのだなと感心します。
橋本治『二十世紀』を読んでみる(2) [本]

何かヘンだというところから始まるのが橋本治流である。
この本では1900年から2000年までが扱われている。
ふつう20世紀といえば、1901年から2000年までというのが常識だろう。スタートが、なぜ1900年ではないのだろうか。
それは紀元1世紀を考えてみればよい。西暦の紀元はキリストの生誕によってはじまる。ところが紀元ゼロ年という年はないのだ。だから、1世紀は紀元1年から100年までということになる。
ところが、実際にヨーロッパでは1900年に「新世紀」が盛大に祝われたという。1900年はもはや世紀末ではないという気分はよくわかる。
このころはヨーロッパの全盛時代だった。ヨーロッパで世紀という発想が意識されるようになるのは、18世紀になってからで、それまで新世紀の到来を祝うという習慣はなかったという。
しかし、ヨーロッパにとって、20世紀は「栄光の100年」にはならなかった。
1901年、イギリスではヴィクトリア女王が死に、日本では昭和天皇が生まれる。
橋本治はこんなふうに書いている。
〈大英帝国の象徴ヴィクトリア女王の死によって始まる20世紀とは、イギリスとヨーロッパが段階を追って没落して行く時間でもあった。第1次世界大戦があり、第2次世界大戦があり、この二つの大戦を通してヨーロッパの国力は削がれ、20世紀後半の世界はアメリカ・ソ連の二大国のものとなる。しかし1980年代になるとこの二大国も傾いて、世界は「日本の時代」になる。昭和天皇を“象徴”としていただいていた日本は、やがて空前絶後の繁栄を誇るようになり、そしてその日本は、昭和の終焉と共にガタガタになる。なぜなんだろう?〉
いまや「米中冷戦」の時代である。
なぜ、こんなふうに歴史は動くのだろう。
それはともかく、橋本治がおもしろいのは、大きなできごとよりも、むしろ身近なできごとに光をあてるところだ。
日本にガスこんろが登場したのは20世紀のはじめだという。
それまでガスは灯火として使われていた。ガス灯である。それが電灯に取って代わられると、ガスはこんろとして家庭のなかにはいりこむようになる。
とはいえ、日本の一般家庭にガスこんろが普及するまでには、それから50年以上かかる。戦前は炭や薪が一般的だった。そういえば、小学校のころ、ぼくもかまどで木っ端を燃やして、ご飯をたいていた。
1903年にはライト兄弟が空を飛んだ。グライダーはすでに発明されている。ライト兄弟が画期的だったのは、モーター・エンジン付きの飛行機をつくったことである。
自動車もすでに19世紀からあった。だが、最初はゴムタイヤがなかった。
そのあと改良が急速に進む。1903年にはフォードが自動車会社を設立し、1909年には飛行機がドーヴァー海峡を渡り、1914年の第1次世界大戦では、すでに空中戦を演じるまでになる。
橋本治によれば、20世紀はけっして発明の世紀ではない。
〈19世紀は、とんでもなくいろんなものが空想され、必要とされ、利用され、その結果、様々な発明発見がなされた時代なのだが、この19世紀の目覚ましさに比べれば、20世紀はろくな発明発見をしていない。〉
20世紀になって発明されたのは「飛行機とラジオとテレビと原子爆弾ぐらい」で、ほかのものは19世紀にあらかたつくられていたというのだ。ただ、20世紀には、それらが大量に商品化され、普及し、人びとの生活を変えていくことになる。
できるだけ大きな歴史にふれないのが、この本の特徴だが、1904年の日露戦争には「仕方なく」ふれている。
日本が近代化の道を歩んだ(つまりヨーロッパの真似をした)のは、「ボヤボヤしていたらインドや中国の二の舞い」になると考えたからだという。そして、「戦争に負けるはずのない大国」であるロシアを破ったあと、日本は朝鮮を支配し、「加害者」になった。
1906年に夏目漱石は『坊っちゃん』を発表する。
〈夏目漱石が登場して流暢な現代文を書いてくれるまで、我々は今口にしている言葉で文章を書けなかったし、もしかしたら、話すことだって出来なかったのかもしれないのだ。〉
ほんとうに漱石のなしとげた仕事は大きい。
20世紀にはふたつの世界大戦が発生する。しかし、それを除けば、「意外なことに、20世紀はなにごともない普通の年で満ち満ちている」と橋本は書く。
1908年にはヨーロッパやアメリカで女性運動が広がる。イギリスでは女性参政権を求めるデモ隊が国会に突入する。日本では初の女優養成所がつくられる。
1909年には上海で「国際アヘン会議」が開かれる。
アヘン戦争が勃発したのはその66年前。この時点でも、イギリスは「麻薬を売る自国民の権利」を守ろうとしていた。人に害を与える商品や、つくりすぎた商品を外国に売りつけるといった風習は、カネ儲けに由来する「悪い病気」だ、と橋本は断言する。
世界ではじめて「父の日」ができたのは1910年。「母の日」に遅れること2年。
この年、日本では大逆事件が発生する。
「大逆事件というのは、明治政府がしでかした“社会主義者への弾圧”と、暗黒裁判の典型である」
日本では「父」は圧制者の別名であり、毎日が「父の日」のようなものだった、と橋本は皮肉を飛ばす。
さて、ここまでKindleにハイライトをつけながら書いてきたが、そろそろ限界のようである。やはりパラパラとめくれる紙の本に軍配を上げたい。本にとって、パラパラとめくれるというのは、とてもだいじな要素で、ページをいったりきたりしていると、なぜか活字が頭に飛びこんできてくれるような気がするのだ。
そんなわけで、ここからは、紙の本で、のんびり『二十世紀』を読むことにする。いまのはじまりがえがかれている。



