水野和夫『次なる100年』を読む(4) [本]
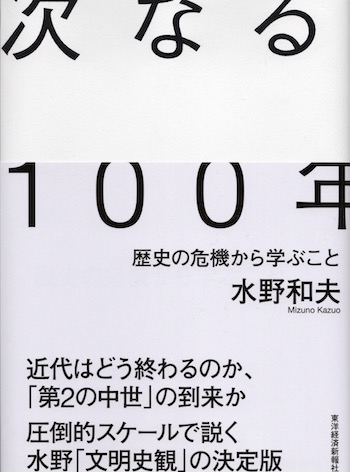
この本はけっして読みやすいとはいえない。歴史と理論、現状分析に加え、おびただしい引用で、頭がぐちゃぐちゃになる。ただでさえ、頭が回らない当方にとっては、何がなんだかわからなくなってしまう。それでも、全体としてはどうやら資本主義の生成と終焉が語られていることが、ぼんやりとながらわかってくる。
昔習った杵柄(きねづか)でいうと、資本主義が終わったら、社会主義だということになりそうだが、そうではないらしい。少なくとも昔ながらの社会主義ははなからしりぞけられている。新しい資本主義というのでもない。そもそも資本主義は終わったのだから。だとすれば、次はどうなるのかというわけだ。
先のことはだれにもわからない。それでも次はどんな時代になるのか、いやなりうるのかを知りたいと思って、この本を少しずつ読んでいる。
きょうは第2章の「グローバリゼーションと帝国──グローバリゼーションは資本帝国建設のためのイデオロギーである」を読んでいる。この章だけで160ページあるが、ポイントだけ紹介してみる。
近代を動かしてきたのは、はてしなく富をつくりだそうとする資本主義システムである。とりわけ19世紀前後からはじまる産業資本主義は、大きな資本をもとに、地下資源の化石燃料をエネルギー化し、機械と結びつけることで商品供給力を増大させてきた。
資本にはもともとグローバリゼーションをめざす傾向がある、と著者は指摘する。中世の13世紀に資本主義が誕生して以来、いやもっと古くから、資本家(商人)は国境にとらわれず経済活動をしてきた。
グローバリゼーションという概念が用いられるようになるのは1980年代からだが、グローバリゼーションの起源は、近代以前の13世紀にさかのぼるという。そのころからフィレンツェの金融業や羊毛組合は、ヨーロッパ全土にわたり、グローバルな活動をはじめていた。15世紀半ばになると、出版業のなかにもすでにグローバル企業が登場している。
16世紀後半、オランダでは近代経済が幕を開ける。オランダはイギリスに先駆けて喜望峰を経由する遠洋航海ルートを切り開き、東アジアに進出した。しかし、やがてイギリスが海を制覇する。
資本の本質はグローバルであり、資本が領土国家の規制から逃れようとするのはとうぜんだ、と著者はいう。
近代は進歩の思想にいろどられている。その信条は変化のスピードと広がりだ。すなわち「より速く、より遠く」が近代のスローガンとなる。
著者によると、そうした近代が生まれたのは、宗教戦争に終止符が打たれた1648年のウェストファリア条約以降である。だが、資本主義はすでに13世紀に生まれていた。13世紀に教会は利子と利潤を認めるようになった。そして、商人たちは遠隔交易を開始し、親方に雇われて働く人も増えていく。
14世紀には「時は金なり」の金言が定着し、富の蓄積も公認されるようになる。節約が美徳となり、資本の「蒐集」もはじまる。機械が考案されるのもこのころだ。
西ヨーロッパはすでに11世紀から貨幣の時代にはいっていた。13世紀には手形や小切手もあらわれ、資本が誕生する。16世紀末には近代国家が登場し、国境を越える貨幣を管理するようになった。
貨幣経済への急速な移行は、東方貿易とスペインのアメリカ侵略に結びついていた。貨幣の時代とともに都市化が進行する。都市市民はおカネがあれば、市場を通じて必要なものは何でも手に入るようになった。都市が帝国から独立していく。
1534年、コペルニクスが科学の時代を開き、近代がはじまる。時間が神のものから人間のものになった。そして、貨幣が世俗の神となる。
都市が資本を集め、その富で文明を築くようになる。ヨーロッパ文明はグローバル化し、資本帝国をめざすようになる。それはかつてのローマ帝国の夢の再現であると同時に、資本に裏づけられた新しい都市文明でもあった。
消費と交易が盛んになればなるほど、貨幣がますます必要になる。新しい金貨や銀貨が発行された。自由都市では封建貴族に代わって商人が行政を握るようになり、「商人の、商人による、商人のための統治」がおこなわれた。
資本主義の原型はすでに13世紀に誕生していた。16世紀になって、資本主義が近代を呼びこんだ。資本主義のほうが近代より歴史が長い、と著者はいう。
資本主義にはもともと暴力性が内在し、わずかのすきも見逃さず、暴走も辞さない。貨幣経済は中世の伝統的精神性と融合することはなかった。そのため、中世に引導を渡し、近代を導き入れる。資本は貧者を生みだしながら膨張していく。
近代は機械だ、と著者はいう。市場も国家も機械である。人はメカニズムのもとで動く。技術と経済が合体し、近代システムが確立する。技術進歩が崇拝され、機械教のもと経済成長こそが神となる。
そうしたなかで、資本は世界市場の創造に向けて動く。そのイデオロギーがグローバリゼーションだ。
「ヒト、モノ、カネの国境を自由に越える移動」がグローバリゼーションだとすれば、それは最近になってはじまったわけではなく、13世紀から存在したといえる。しかし、20世紀末になって、新自由主義のイデオロギーが広がるにつれて、それはより活発化してきた。
グローバリゼーションに明確な定義はない。だが、そこには明確なイデオロギーがある、と著者はいう。
市場の自由化とグローバルな統合。技術進歩のもたらす結果。民主主義の拡大。すべての人の利益。そして、その過程は不可避で非可逆的だという。
こうした大宣伝によって、21世紀にはいると、ほとんどだれもが、グローバリゼーションを善いものと信じるようになった。
だが、その矢先、2008年にリーマンショックがおき、2011年にはギリシア危機が発生した。グローバリゼーションは人びとの生活水準を上昇させるどころか、サブプライム層を路頭に迷わせることになった。
グローバリゼーションの本質が露わになった。
「グローバリゼーションはその推進者、米財務省、世界銀行、IMF、そしてウォール街にとってバブルの生成と崩壊を繰り返す資本を成長させる戦略なのである」
にもかかわらず日本の政策当局者は、相変わらず米国の主導するグローバリゼーションを善だと信じていると、著者はいう。
グローバリゼーションの代表企業がGAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)だ。そして、現在グローバリゼーションを主導しているのがウォール街である。GAFAは国家より巨大な権力をもちはじめており、脱税すれすれの節税をおこなっている、その株式時価総額は日本の名目GDP530兆円を上回る。「GAFA問題とは民主主義に対する挑戦なのである」と著者はいう。つまり、資本帝国による支配だ。
バブルはグローバリゼーションによってつくられる。バブルははじけさせるためにつくられる、と著者はいう。
1970年以降、実物経済にたいし金融経済が膨張しはじめた。米国の「帝国」化を支えているのは、日本の過剰マネーである。
グローバリゼーションによって、世界のマネーは米国に集中し、そのマネーは資本の自由化によって新興国に流れている。対外債権が過剰になると、債務が返済できない国がでてくる。国内でも同じことが生じる(その一例がリーマンショックだ)。
「グローバリゼーションとは、IMFを通じて、米国のワシントン・コンセンサスが世界に伝播し、米国が帝国化していくプロセスそのものである」
米国は21世紀の帝国をめざしている。そして、現在、新たな帝国をめざす中国との戦いがはじまっている、と著者はいう。
経済面からみれば、21世紀の帝国の条件は、世界じゅうからマネーを集め、世界最大の債権国として振る舞えるようになることだ。それによって債権国は債務国を支配することができる。
1991年のソ連崩壊によって、米国は世界帝国の夢を実現しえたかのように思えた。だが、その後のイスラム世界やテロとの戦いによって、その夢はたちまちついえ、2013年にオバマ大統領は「米国は世界の警察官ではない」と宣言するにいたった。
それでも、米国は帝国であることをあきらめたわけではなかった。台頭する中国との戦いがはじまった。
米国は世界最大の債権国であることを通じて、帝国の地位を保とうとしている(日本のマネーがそれを支えている)。恐れるのは現在世界第4位の純債権国である中国が、のしあがってくることだ。
米国が日本を抜いて世界最大の債権国に返り咲いたのは2010年である。
とはいえ、債権・債務関係は複雑である。米国は世界最大の債権国であるにもかかわらず、対中国の所得収支は大幅な赤字となっている。これにたいし、中国は世界4位の債権国であるにもかかわらず、全体の所得収支は世界最大の赤字をだしている。
このことは、中国は米国には債権者だが、ヨーロッパや日本にたいしては債務者であることを意味している。このあたり、国際的な債権・債務関係は入り組んでいて、じつにややこしい。
米国は日本、ヨーロッパ、中国に支えられて金融帝国としての位置を保ち、いっぽう中国は米国、日本、ヨーロッパに支えられて貿易帝国になったといえるだろう。
このああたりの議論は複雑をきわめていて、なかなか理解できないのだが、著者がこれから30年は帝国支配をめぐって、米国と中国の対立が激化すると予想していることはまちがいない。
しかし、著者は「『中国の夢』の一つである米国を総合国力で超えるという『興国の夢』は夢のまた夢である」と断言する。
中国の対外債務の支払い利子率はいちじるしく高く、その観点からみると「グローバリゼーションの勝利者は米国であり、中国が敗者となる」。なぜなら「中国は対外取引において対外資産からは低い収益率を受け取る一方で、対外資産については高い支払い利子率を払っている」からである。
それでも米国の危機感は強い。「米国の危機感は米国がこのまま手をこまねいて中国の台頭を許すと21世紀の半ばには帝国の座を降りなければならないかもしれないという点にある」。そのため自由貿易の原則を破ってでも、対中貿易赤字の増大を抑えようとしている。
ファーウェイをめぐる米中の対立は妥協の余地がなく、いつまでもつづくだろう、と著者はみる。それはサイバー空間だけではなく、リアル空間でも同じである。
帝国はつねに「過剰のはけ口」を求める。21世紀においては、グローバリゼーションというイデオロギーと、情報・通信というテクノロジーが帝国の暴力装置をかたちづくっているという。
中国が帝国をめざしているのは、やはり「過剰のはけ口」を求めているからだ。米国のグローバリゼーションに対応するのが、中国の「一帯一路」計画だ。
米国の財政赤字は減りそうにないし、貿易・経常収支赤字も縮小に転じる気配はない。それに応じて、日本をはじめとする過剰マネーが米国に流入し、ニューヨークダウを押し上げている。過剰マネーは外国企業の買収、中南米、EU、イギリスなどへの投資に向かう。こうして過大な貿易赤字をかかえながらも、米国は全世界の債権者として引きつづき君臨する。だが、そのパワーも次第に落ちはじめている、と著者は指摘する。
話はさらにつづく。



