ハイパー資本主義──『資本とイデオロギー』を読む(6) [商品世界論ノート]
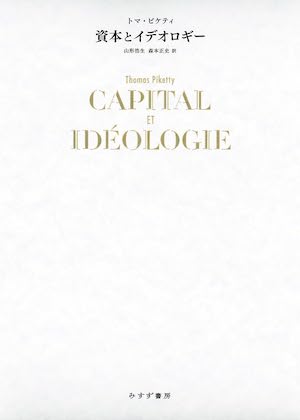
ハイパー資本主義が登場するのは1980年代以降だ。
いまや世界中の国々はこれまでにないほど密接に相互依存している。とりわけ1990年代以降は、デジタル技術の時代となり、グローバル化が段違いに進んだ。しかし、経済格差や貧困の度合いは、1980年代以降、むしろ拡大している、とピケティはいう。
ヨーロッパや中国、米国より経済格差が大きいのは中東だ。中東では、人口の少ないいくつかの国に石油資源が集中している。中東の国境は第1次世界大戦後にイギリスとフランスによって引かれたもので、その後、欧米列強が石油産出国を保護した。
中東では石油産出国と非産出国とのあいだで極端な経済格差がある。産出国内の格差も大きく、国家の富はごく一部に集中し、そこではたらく外国人労働者とのあいだでは極端な差がある。
欧米諸国では、第1次世界大戦後、富の集中は拡散へと向かい、1970年代までそのままの状態がつづいたが、1980年代からふたたび集中傾向に転じた。中国とロシアでは1990年代に民営化の波が到来して以来、経済格差が急速に広がった。インドも同じだ。
しかし、所得と富の分布に関するデータはまだまだ不正確だ。その理由は分布トップの回答者が、富、とりわけ金融資産を過少申告しているためだ。これを解決するには公的金融台帳をつくるほかないのだが、いまのところその方向性は政治的に阻まれている、とピケティはいう。
なぜビッグデータとITの時代に、資産とその分布に関する統計が透明性を欠いているのか。ピケティによると、その理由は、再分配を嫌う財産主義イデオロギーが復活したせいだ。資産の透明性を拒絶するのが、現在の新財産主義の特徴となっている。
近年の税制競争によって、かつてより直接税の税率は抑えられているにもかかわらず、租税回避やタックス・ヘイブンなどを利用した、企業や個人の資産隠しが横行している。そのいっぽうで、中下層階級の負担(消費税、賃金と年金からの控除)は軽減されず、高所得と巨額財産に累進課税を課すといった税制は検討されていない。
「金融不透明性と相まったきわめて高い富の集中の復活は、今日の世界的な新財産主義的格差体制の本質的特徴の一つだ」と、ピケティは指摘する。
2015年現在、米国ではトップ1%が総私有財産(不動産、事業資産、金融資産)の37%(1980年は23%)を所有し、トップ10%が総私有財産の74%(1980年は65%)を所有している。ロシアではトップ1%が42%、トップ10%が71%、中国ではトップ1%が30%、トップ10%が67%。フランスではトップ1%が23%、10%が55%、イギリスではトップ1%が20%、トップ10%が52%といった割合になっている。
富の遍在は1980年代以降、とりわけ90年代以降拡大した。こうした傾向は今後減速するかもしれないが、まだ持続するかもしれないという。
1970年から2000年にかけ、世界の最貧諸国はさらに貧しくなった。人口が増加しているのに、税収は少なく、国はじゅうぶんな教育投資や医療投資さえおこなうことができないありさまだ。
2008年以降の劇的な変化は、中央銀行が短期間で莫大な貨幣を創造するようになったことだ、とピケティはいう。いわゆるリーマン・ショック以降、世界の主要中央銀行は「量的緩和」に踏みこみ、貨幣創出オペレーションを編みだした。
量的緩和には銀行への長期融資と民間および政府発行の債券の買い入れが含まれる。中央銀行のこの大規模介入によって、富裕国は1930年代の世界大恐慌に匹敵する危機に陥らずにすんだ。中央銀行は銀行破綻の連鎖を防いで、「最後の貸し手」としての役割を果たした。
〈だが、中央銀行は世界のあらゆる問題を解決し、資本主義全体を規制すること(あるいは資本主義を超克すること)などできない。過度の金融自由化、拡大する格差、気候変動と闘うには、他の公的制度が必要だ。つまり、集合的な熟議と民主的な手続きに基づく議会で作られる法、税、条約などだ。〉
ピケティは中央銀行の限界をそんなふうに指摘している。とはいえ、金融危機や戦争、大規模な自然災害において、貨幣創造によって、膨大な資源を短期間で動員できる機関は中央銀行しかない。
中央銀行は民主的正当性にもとづくことなく、GDPの数倍にわたるマネーを創造することができる。だが、そのことは深刻なガバナンス問題を引き起こす可能性があるのだ。
経済金融化がここ数十年で驚くべき水準に達したことは強調に価する、とピケティはいう。ユーロ圏でも、金融資産と負債の総価値はGDPの10倍以上に達している。だが、金融部門全体の規模が実体経済よりも早く成長するような状況は永遠につづくわけがないという。
貨幣創造はいまのところさほどインフレを引き起こしていないが、一部の資産価格は上昇している。国債の名目利率はゼロに近く、実質金利はマイナスだ。これは中央銀行が大量の国債を買い入れているためだ。だからといって、大口投資家がもうかっていないかというと、そうではなく、かれらは年間6〜8%の利益を確保しているという。
ピケティは疑問を投げかける。
〈多くの国民は、ヨーロッパ経済活性化に目に見える効果がほとんどないのに、金融機関救済のためになぜあんな巨額のお金を創造したのか、そんなリソースを苦しむ労働者の救済、公共インフラ開発、再生可能エネルギー移行への大規模投資の資金に動員できないのかと、当然ながら問い始めている。〉
これはとうぜんの疑問である。
さらにピケティが問うのが、現在の新財産主義を支えるイデオロギー、とりわけハイエクの権威主義的リベラリズムだ。
ハイエクは『法と立法と自由』で、あらゆる再分配政策への恐れを表明している。再分配は既存の財産権に疑いを投げかけ、累進課税の悪循環をもたらすというのだ。ハイエクは憲法で累進課税という発想自体を禁止すべきだとも主張する。議会に財産権を損なうような立法権を与えてはならないともいう。けっきょくのところハイエクの求める議会は財産権を擁護する議会に尽きる。
ここ数十年で台頭してきた新財産主義イデオロギーは、極端な能力主義とも結びついている、とピケティはいう。それは経済システムにおける勝者を称賛するいっぽうで、敗者を無能と非難する。さらに貧困者が貧しいのは当人のせいだと主張する。
1980年代以降、教育の不公正と能力主義の偽善はますます強まっている。
能力主義イデオロギーは、起業家と億万長者賛美とも結びついている。億万長者の慈善活動への期待や称賛も絶えない。だが、それらは新財産主義がもたらす権力の讃仰にほかならないのだ、とピケティは断言する。
そろそろハイパー資本主義を終わりにしたほうがいいのではないか、というのが、ピケティの主張である。
(ピケティの『資本とイデオロギー』をこれで半分ほど読んだことになります。このあと、さかのぼって、前近代社会とは何か、近代社会について、さらに現代の政党分析などにも触れなければなりませんが、ちょっと休憩をいれます。)
ソ連解体とポスト共産主義社会──『資本とイデオロギー』を読む(5) [商品世界論ノート]
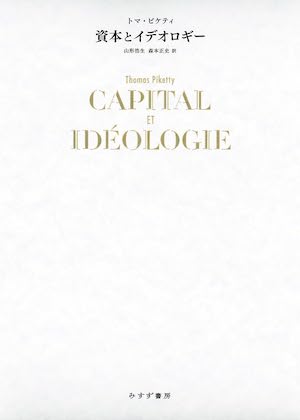
ソヴィエト(評議会)型共産主義は、財産主義イデオロギーにたいする、もっとも急進的な挑戦だった、とピケティは述べている。「財産主義は私有財産の全面的な保護が繁栄と社会調和をもたらすと請け合ったのに対し、ソヴィエト共産主義は私有財産の完全廃止と包括的な国家所有による置換に基づいていた」というわけだ。
ソヴィエト型共産主義が失敗したあと、いまやポスト共産主義社会はハイパー資本主義と変わらなくなっている。ロシアでは新興オリガルヒが海外に資産をためこんでいるし、中国はダイナミックな混合経済を発展させながらも、中央集権制による多くの不透明性をかかえている。
ソ連の試みはなぜ失敗したのか。ピケティによれば、ボリシェヴィキが政権の座についたとき、かれらには何の「科学的な」計画もなかった。明確な答えがないまま権力を維持するため、スケープゴートがつくられ、粛清と収監が日常化し、権力が超個人化した。政治・社会・経済制度の策定には、慎重さ、分権化、妥協、実験精神が必要なのに、少なくともスターリンにはそうした配慮はいっさいみられなかったという。
1920年代末には農業集産化と生産手段の国有化が強制的に導入された。それに反対したとみなされた人びとは排除・拘禁され、重労働を課されるか、死刑に処せられたのだ。
ピケティはこのような体制が長くつづいたのは不思議なくらいだと述べている。しかし、それなりの理由はあったという。
1920年から50年にかけての公共投資はたしかにロシアに近代化をもたらした。インフラ、輸送、教育、科学、公共衛生面では、たしかに改善があった。所得と富の集中は減り、少なくとも1950年代までは生活水準が上昇した。
とはいえ、言論活動をはじめとして、多くの制限があり、人びとが自由に移動することすら認められなかった。生活水準の上昇もなくなり、1980年代には、西ヨーロッパのせいぜい60%程度にとどまっていた。多くの資源が軍事部門に投入されるいっぽうで、消費財の品質は劣悪だった。
1950年代以降80年代にかけて、男性の平均寿命も低下している。ゴルバチョフによるアルコールの過剰摂取を抑える取り組みは、かえって政権への反発を招いた。
1950年代以降、脱植民地、人種平等、男女平等などの世界の動きを支持したソ連は、一種の道徳的威信を与えた。だが、その威信も1970年代には色あせていった。
ソ連の体制はあらゆるかたちの生産手段の私有にたいし、極度に過激なスタンスをとった。小規模事業でも私有を認めたら、限度がなくなり、一歩ずつ資本主義の復活に進むのではないかという恐怖があった。
「20世紀のソヴィエト・イデオロギーは、私有財産が小さな隙間から入り込んで最終的に制度全体を侵さないよう、厳格な国家所有権以外の認可を拒絶した」と、ピケティは述べる。
しかし、人が求める財やサービス(つまり商品)をすべて中央政府が規制しようとすると、そこには中央集権的で、しかも抑圧的な体制が生まれることはまちがいない。
ソ連のやり方は根本的にまちがいだった、とピケティはいう。かれがめざそうとするのは、あくまでも分権的で参加型の社会主義だ。国家所有(公有)はあってもいいが、それは透明性がなくてはならず、しかも社会所有や一時所有の企業と並び立つかたちでなくてはならない。
ポスト共産主義のロシアは、公有財産を壮絶に盗んだオリガルヒの社会になった、とピケティは評している。公有財産はたちまちのうちに民営化され、とりわけエネルギー部門が少数の抜け目ない株主の手に落ちた。
加えて、ロシアには累進税も相続税もなかったから、そこに超自由主義的な状況が生まれ、その結果、ロシアは世界でもっとも不平等な国のひとつになってしまった。財産隠しも盛んで、金融資産はタックスヘイブンに隠され、違法行為が常態化しているという。
政治面をみても「1999年にプーチンが政権についてからは、政敵の拘束とメディア弾圧によって、ロシアは[真の対立候補がいないまま]事実上独裁的な国民投票支配の下におかれている」という。
いっぽう中国はどうだろう。
私有財産の完全廃止と集産化、工業化強行という毛沢東時代の試みは完全な失敗に終わった。その失敗から教訓を学んだ中国は1978年以降、共産党の主導権を維持しながら、混合経済を発展させるという道を選んだ。
1978年段階で70%近くに達していた中国の公的資本の割合は、2005年以降、ほぼ30%に落ち着いている。
「総財産の70%近くが民営化されたためにこの国はもはや共産主義ではないが、かといって公共財が総財産の約30%超という、少ないとはいえ相当なシェアを占めているがゆえに、完全な資本主義でもない」とピケティは評する。
中国の体制はいわば独裁混合経済なのだ。
住宅用不動産はほぼすべて私有になっており、不動産はいちばんの民間投資先になっている。農地は親から子に相続できるという意味で、部分的私有になっている。
中国国民は「戸口」を与えられ、地方住民か都市住民かを指定される。地方戸口から都市戸口になれば、都市での公共サービスを受けられるようになるものの農地の所有権を奪われる。そのため、都市への出稼ぎが多い。
混合経済への移行によって、中国では経済格差が広がった。
2020年現在、中国では上位10%が約40%の所得シェアを占め、下位50%のシェアは約15%となっている(1980年には上位10%と下位50%がともに27%の割合だった)。
中国の経済格差はヨーロッパより大きく、米国に近づきつつある。国内通行証と移住制限の存在が大きな格差の一因となっている。さらに最近は社会統制制度も導入され、監視社会化が一段と進んでいる。
中国の所得と富のデータがきわめて不透明なことも、ピケティは指摘するのを忘れていない。
中国では、建前上、累進税制が採用されているが、所得税に関する詳細なデータは公表されていない。相続税はないため、相続に関するデータはまったくない。
そのため経済格差には不透明な部分があり、実際には経済格差はもっと広がっているかもしれない。汚職の規模はさらに大きく、資本逃避も増大している可能性もある。
習近平は権力の継続的行使によって、党の潜在的退廃を抑止するというが、「人口13億の国の格差を、単純に公開糾弾と収監だけで抑えるのか疑うのは当然だ」と、ピケティはいう。
経済が開放され、事業が民営化されたいまの中国は、なんでもありの世界になってしまった。国を挙げてのビジネス・ラッシュが進み、ニューリッチの億万長者が生まれた。文化大革命の時代とは隔世の感がある。
中国は西側の議会制民主主義をカネの力に左右されているとして非難しつづけている。それが当たっていないとはいえない。とはいえ、こうした主張にもとづいて、真の選挙競争なしに共産党が権力に居座りつづける姿勢はまちがっている、とピケティは断言する。
東ヨーロッパの状況も見ておこう。
共産主義体制下にあった東欧諸国のほとんどは2000年代初頭にEUに加盟した。プラス面でいえば、東欧諸国の所得格差は米国やロシアより、ずっとちいさい。共産主義からの移行は比較的穏やかにおこなわれ、ロシアのように少数のオリガルヒが所得シェアの大半を独占することはなかった。
2018年には平均所得もヨーロッパ平均の70%程度を占めるようになった。とはいえ、西ヨーロッパにくらべれば、平均所得がまだまだ低いことも事実である。
東欧の国々にはEUからかなりの給付金が流れこんでいる。とはいえ、ハンガリーやポーランド、チェコなどの人びとは、ドイツやフランスの資本が相変わらず自分たちを食いものにしていると考えている。いっぽう、東欧資本の相当な利益が国外に流出していることもたしかだ。そうしたことが東側のフラストレーションとナショナリズム(社会自国主義)の高まりを呼びさましている。
東欧のポスト共産主義諸国では、経済格差拡大の結果、幻滅が広がり、ある種の経済保守主義が生まれている、とピケティはいう。
そのため、社会民主主義政党は相手にされなくなり、リベラル保守[EU下での資本主義]とナショナリスト保守[脱EUの資本主義]の対立が目立つようになった。しかし、これは東欧だけの現象ではない。ピケティがこれを懸念すべき状況とみていることはまちがいない。かれが打ちだすのは、あくまでも新社会主義の立場だ。
社会民主主義の成果と限界──『資本とイデオロギー』を読む(4) [商品世界論ノート]
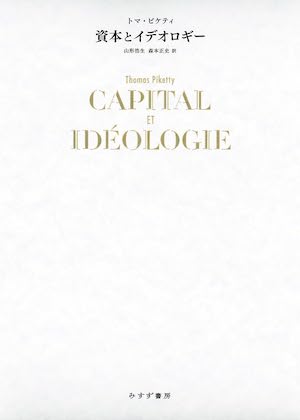
ピケティによると、1950〜80年は社会民主主義の黄金期だった。社会民主主義にもとづいて実施された税制と社会政策により、社会は以前より平等となり、繁栄したという。
ここでピケティは社会民主主義という用語をより広い意味で使っている。「私有財産と資本主義を社会に組み込もうとする政治実践と制度すべてを指す」というのだ。これは「社会民主党」を名乗る政党の時々に応じた政治綱領よりも幅広い用い方だ。
したがって、たとえ政党政治の変遷はあったとしても、ドイツやイギリス、フランス、イタリアの戦後政治は、少なからず、社会民主主義に接近していたと理解される。さらに、民主党時代の米国、かつての自民党時代の日本、一時期のアルゼンチンなども社会民主主義をとりいれていたと理解することができる。
しかし、社会民主主義の次第は1980年にはいってから大逆転することになる。それ以降はトップ10%の総所得シェアが急増し、経済格差が拡大していくのだ。
もっとも1950〜80年の社会を理想化してはならない。格差は縮まったとはいえ、それはまだ大きな格差の残る社会だった、ともピケティは述べている。
ほんらい社会民主主義がめざしたものは、公的所有だけではない。公的所有に加えて、社会所有、一時所有の3つの組み合わせだった、とピケティはいう。
ソ連型共産主義は中央集権的な国家権力による企業の国有化だけを目標とした。これにたいし、社会民主主義は、中央政府、地方公共団体による企業の公的所有だけをめざしたわけではない。株主だけではなく労働者が経営に参加する社会所有、さらには最富裕層の資産の一部を社会に還元させる一時所有の考え方ももっていたというのだ。
国有化は透明性が求められなければならないが、ソ連型共産主義の国有化はそうではなかった。社会民主主義のもとでも、国有企業はある。しかし、むしろピケティが重視するのは、あとふたつの考え方(つまり共同経営制度=社会所有と累進課税=一時所有の考え方)である。
労働者の参加による企業の権限共有という考え方は、ドイツやスウェーデンなどで、1950年代から定着した。ドイツでは従業員2000人以上の全企業では取締役会の議席の半数(500人〜2000人の企業では3分の1)を労働者が占めることが義務づけられている。こうした共同経営制度が生まれたのは、これまでの組合闘争や政治闘争の成果だった。
とはいえ、こうした共同経営制度はいまのところドイツと北欧に限定されている。
従来、イギリスの労働党やフランスの社会党は国有化と公共部門の拡大に傾いていた。これにたいし、共同経営制度を推進したのは、ドイツの社会民主党(SPD)である。SPDは1920年代、30年代には国有化を唱えていたが、1950年代からは共同経営制度の方向へと転換した。
そして、1980年代の国営化から民営化への流れを受けて、90年代以降は、フランス社会党もイギリス労働党も国有化に言及することはなくなり、むしろ共同経営制度について論議するようになっているという。
共同経営制度の目的は労働者の経営参加を拡大することによって、社会的経済的効率性を高めながら、労働条件と賃金を改善することだ。
次にピケティは教育問題を論じる。なぜなら教育こそが生活水準の改善と格差縮小に大きな役割を果たしてきたからである。社会民主主義が教育にはたしてきた役割は大きい。だが、それが挫折し、1980年代からむしろ教育格差が拡大するようになったのはなぜか。
アレクシ・ド・トクヴィルは1835年に米国の先進性は教育の普及と土地所有の分散にあることを指摘している。教育面における米国の優位性は20世紀もつづいた。
ヨーロッパの教育制度は、もともと伝統的なエリート教育への志向が強く、国民全体への教育の普及はむしろ遅れていた。それが自覚されるようになるのは20世紀にはいってからである。これにたいし、日本は早くから教育制度の改革に取り組み、1950年代にすでに高校進学率がすでに60%に達していた。
しかし、米国では1980年代以降、急速に教育が不平等化し、極端な教育階層化が生じるようになる。それは米国内の経済格差の拡大を反映している、とピケティはいう。
2010年代にはいると、米国ではトップの1%が総所得の20%を占めるいっぽうで、底辺の50%はいまや全体で総所得の12%しか得ていないという極端な経済格差が生じている。とくに底辺の50%、すなわち国民の半分の所得シェアが1980年以降、下落しつづけていることが問題だ。
生産システムがいくつかの最大企業に集中され、弱小企業が振り落とされるなかで、教育にも大きな格差が生まれるようになった。
高度な生産システムには高い技能が求められる。かつて高等教育は人口のごく一部の特権だったが、富裕国ではいまや若い世代の大半が大学を卒業するようになっている。
それでも、米国では、高等教育へのアクセスは親の所得によってほぼ決まるのが現実だという。最貧家庭の大学進学率は低く、富裕家庭の大学進学率は高い。ここから教育格差が生まれ、さらに所得格差が生じるという悪循環がはじまっている。
あまり透明とはいえない「優遇制度」もあるという。それによると、最富裕の親が多額の寄付をして、ほんらいなら入学できそうもない子どもを最高レベルの大学に入学させているというのだ。
米国では教育アクセスの格差はかなり大きくなっているが、それはヨーロッパでも例外ではないという。表向きでは機会均等や能力主義が標榜されるが、それとは裏腹に、教育アクセスが不平等になる傾向が強まっている。
社会民主主義のもとで進められてきた教育制度の改革が停滞し、むしろ逆転したようにみえるのはなぜだろう。ヨーロッパでも1980年代以降、教育への公共支出の割合は停滞し、ほぼ横ばいになっているという。
先進国が高等教育大衆化時代に移行し、大学進学率が50%以上になった時代に、公的な教育支出の凍結がもたらした影響は大きかった。それにより、下流か中流に属する家庭は、大きな経済的負担を強いられることになり、そればかりか卒業後の機会にもたいして恵まれないという結果を味わうことになった。
ピケティは1980年以降の公的な教育投資の停滞が、格差の拡大だけではなく経済成長の鈍化をもたらしたことを指摘している。「過去2世紀の歴史を見れば、教育の平等は経済において格差、財産、安定性の神聖化よりも重要な役割を果たした」のはまちがいない、と述べている。教育の平等が失われたことが、社会の停滞と緊張を招いているというのだ。
次は課税の問題である。
ピケティは、社会民主主義が挫折したもうひとつの原因は、公正な課税についてのしっかりした考え方を欠いていたためだと指摘する。かれによれば、社会主義は生産手段の国有化にこだわり、そのために累進税や共同管理、自主管理といった問題については思考停止におちいりがちだったという。
累進課税の保護と拡大については、国際協調が必要なのに、それも怠りがちだった。また公正な税制として、累進資産税という発想を採用することもなかったという。
ピケティは、20世紀の社会民主主義運動は、国民国家の狭い枠組みのなかでのみ、社会財政国家の構築に専念していたとも述べている。
たしかにヨーロッパのレベルでは1992年にEU(欧州連合)が発足し、96年には共通通貨ユーロも発行された。しかし、EUには多くの制約があり、EU各国政府は、拡大する格差と低成長にうまく対応できていない。その理由は、税制や社会政策については加盟各国の合意ができていないことだという。それどころか1980年以降の「税制ダンピング」が長期的な法人税低下をもたらし、社会福祉政策にマイナスの影響をもたらしている。
1980年代末、フランス社会党は単一通貨(ユーロ)と欧州中央銀行(ECB)設立を受け入れるのと同時に、資本フローの自由化を認めた。それにより金融自由化とグローバル化が進む。社会民主主義は経済のグローバル化に対応できなかった、ともピケティは指摘する。
一部の集団はグローバル化でもっとも利益を受けただけではなく、税率ダンピング競争によって累進課税をまぬがれ、さらなる利益を得た。それにより、富と資本はトップ集団に集中し、経済格差が広がった。
間接税が重くなるいっぽうで、資本所得(配当、金利、地代など)を多くもつ最富裕層にたいしてはむしろ税の逆進性(税がかえって低くなる)が高まっている。タックスヘイブンによる租税回避も日常化している。その意味では、国家を超えた新たな税制と税務が必要になっている、とピケティは指摘する。
広がるいっぽうの経済格差を縮小するためには、累進所得税、累進相続税、累進資産税からなる累進税体系を再確立しなくてはならない、という。所得税と相続税に関してはすでに経験がある。とりわけ、今後焦点となるのは累進資産税だ。
第2次世界大戦後、日本、ドイツ、イタリア、フランスは一度限りの資産税(財産税)を実施し、これにより巨額の債務を一挙に解消した経験がある。農地改革もある意味では私有財産にたいする特別税だったといえる。農地改革により、一定以上の大きな土地は差し押さえられ、小作農に分配された。
年次資産税に関しては、これまでの歴史を踏まえた論議が必要になる、とピケティはいう。フランスは不動産税を課している。米国の財産税は固定資産(土地、建物)だけではなく個人資産(自動車や船、金融資産)なども税の対象としている。しかし、これらの税制はいまのところ定率で、富裕層にむしろ有利にはたらいているという。
税制に関して、「既存の制度は、何よりも政治―イデオロギーのパワーバランスと、対立するさまざまな政党の動員能力で形成された、社会政治過程の結果であり、それは今後も同じような形で進化し続ける」というのが、ピケティの考え方だ。
その意味で、累進資産税はまだ将来の政治課題だといえるかもしれない。とはいえ、米国の大統領選では、たとえば5000万ドルから10億ドルまでの財産にたいして毎年2%、10億ドルを超える財産にたいして毎年3%の資産税をかけるべきだという主張も登場するようになった。ピケティ自身は超億万長者には少なくとも5〜10%の税をかけるべきだと主張している。
とはいえ、税制改革にたいする反対意見も根強い。とりわけグローバル金融資本の時代において、銀行が破綻に瀕したり、景気回復が遅れたりした場合などは、たちまち富裕税の議論は横に押しやられ、富裕層に有利な減税措置がとられたりする。
しかし、ピケティはそれでも「累進富裕税についての冷静な議論は避けられない」と主張する。
いつの時代も求められるのは、人びとの大多数が納得できる富の分配についての公正規範である。それをおろそかにしたままでいると、世界は社会の亀裂と民族的・ナショナリズム的敵意へと後退していくことになる。ピケティの警告は現在の危機に向けられている。
ピケティの20世紀論(1)──『資本とイデオロギー』を読む(3) [商品世界論ノート]
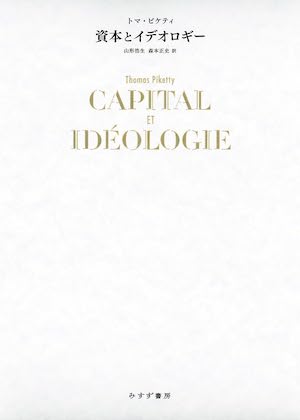
ピケティは20世紀の流れを大きく次のようにみる。
(ブルジョワ的)所有権社会が危機を迎え、社会民主主義社会が誕生し、ブルジョワ社会に対抗しようとした共産主義社会が崩壊してポスト共産主義社会が生まれ、1980年ごろからハイパー資本主義社会にはいったというのだ。たしかに、そのとおりかもしれない。
少しずつ追ってみる。あくまでも自分勝手な読み方である。
まず「所有権社会の危機」を読む。
時代は20世紀前半、とりわけ1914年から45年である。
20世紀前半をピケティは、ブルジョワ的私有財産中心の社会が力を失い、植民地帝国が崩壊していく時代ととらえている。その後は、米国とソ連に代表される、資本主義・共産主義のイデオロギー対立が生じる。
まず20世紀はじめの所得分布に関していうと、1900〜1910年においては、ヨーロッパではトップの10分の1が平均して50%のシェアを占めていた。それが1945〜50年には約30%に落ちこむ。この傾向は米国でも変わらなかったという。
20世紀はじめにトップの座を占めていたブルジョワの所得はほとんどすべてが資産からの所得だった。すなわち地代/賃料、利潤、配当、利子が主な収入である。ヨーロッパでは、第1次世界大戦前、もっとも裕福な10%が90%の私有財産を所有していた。それだけ富の集中が極端だったといえる。
その富の集中が20世紀を通じてなぜ低下していくのか。つまり、資産(不動産や事業資産、金融資産)だけで暮らしている人(ブルジョワや大地主貴族)の割合がなぜ減ってきたのか。
マルクスの生きた19世紀から時代は大きく変わろうとしていた。
ピケティは20世紀前半に、私有財産の総価値が激減したと指摘している。「私有財産の総価値は第1次世界大戦中と1920年代初めに文字通り崩壊し、その後1920年代に若干持ち直したが、大恐慌、第2次世界大戦、終戦直後に再び激減し」た。
つまり、ヨーロッパではブルジョワの世紀が終わったのだ。
その理由として考えられるのは、ひとつに植民地世界が崩壊し、海外資産が失われたことだ。さらに、大恐慌によって自由放任ドクトリンが信用を失い、国家が経済に介入するようになったことも大きい。その結果、一部では国有化の波がおき、大きな公共部門も生まれる。農地改革や家賃統制、累進課税なども金持ちの資産を減らしていった。
テレビドラマ『ダウントン・アビー』は、そうした大貴族の没落を、うまくえがいている。
1914年から45年にかけ、個人貯蓄の大半は民間投資にではなく、戦費のための公債に向けられた。加えて1920年代にはインフレが進行した。政府が紙幣の印刷に乗り出したことが、物価の高騰を招いたのだ。インフレ率が高まると、戦時公債の価値は暴落していく。
とはいえ、不動産や事業資産、株などを所有する最富裕層はインフレによる打撃を免れる傾向があった。そのいっぽう、第1次世界大戦後、多くの国は、公的債務を削減するために、私有財産への特別税を導入することになった。このとき、累進税のはたした役割は大きかった、とピケティは指摘する。
それまで先進国では、大規模な累進税制が長期間試みられたことはなかったという。ところが、第1次世界大戦後、歴史上はじめて最高レベルの所得と財産に高い税率が課されるようになったのだ。それは1920年代に少し減少するが、1930年代からふたたび上昇し、1980年までその傾向がつづく。
こうした重税が最富裕層を直撃したことはまちがいない。富裕層の総資産は減少し、そのいっぽうで資産格差は縮小した。格差縮小の進行が緩やかだったのは、累進所得税の効果が徐々にあらわれたからだ。さらに、最大級の財産が数世代の遺産贈与によって段階的に削り取られていったことも、格差縮小を後押しした。
金持ちたちはベルエポック時代(19世紀末から1914年くらいまで)の生活を維持できなくなった。もちろん、すべての富裕家族が没落したわけではない。とはいえ、フランスでもイギリスでも、富裕家族が以前の生活水準に戻るのはだんだんとむずかしくなっていった。
イギリスでは1909年から1911年にかけての「人民予算」以来、累進税率が引き上げられ、第1次世界大戦の終わりに最高税率がさらに引き上げられた。これにより、大土地所有者、すなわち貴族は大きな打撃を受けた。
ピケティは所得、財産、相続にたいする累進税の発達を先導したのがイギリスと米国だったことに着目している。富の不平等への不満が高まっていた。それが逆転するのは1980年代になってからだ。
20世紀における累進課税の導入とともに、税収は拡大し、国家の予算規模が大きくなり、いわば財政国家が成立する。
欧米では1950年代に総税収は国民所得の約30%に達した。財政国家の隆盛は経済成長の妨げにならなかった。むしろ、その逆だった、とピケティはいう。国家が経済発展で中心的な役割をはたすようになり、年金や社会保障、教育などのために大きな投資をおこなうようになったからである。
ピケティにいわせれば、20世紀はじめまでの国家は領主的支出しかおこなっていなかった。領主的支出とは、軍や警察、司法、一般行政、道路や水路などわずかな基盤インフラのための支出をさす。
ところが、20世紀が進むにつれ、国家は社会的支出に多くの税収を費やすようになり、いわば社会国家へと姿を変えることになる。ブルジョワや貴族が独占していた富は国家によって吸収されていく。
20世紀は大規模な累進課税が発達し、社会国家が隆盛した時代である。極端に集中した富は分散され、広く民間に生産資本が蓄積され、それほど豊かでない社会層にも富が行き渡ることになる。そのことが経済成長を刺激した。それが1980年代以降、なぜ逆転するようになったのかの理由については、あらためて見ていかねばならないだろう。
ピケティはブルジョワと大地主を頂点とする所有権社会が終焉を迎えたのは、戦争やら革命やらの要因はあったにせよ、結局は政治―イデオロギー的な転換があったからだと主張する。
20世紀にはいって、社会的公正や累進税、所得と富の再分配をめぐる考察や議論が進んだことが大きい。
カール・ポランニーは『大転換』のなかで、権力の均衡、金本位制、自由主義国家(実態は帝国)、自律市場からなる19世紀文明の崩壊をえがいた。19世紀文明は世界大戦に向かって進撃し、自壊することによって、ついに文明の大転換をもたらすことになる。
ハンナ・アーレントも『全体主義の起源』のなかで、ヨーロッパの所有権社会が崩壊したのは、1815年から1914年にいたる無軌道で無規制のヨーロッパ資本主義の矛盾が露呈したためだととらえている。
ボリシェヴィキとナチはポスト国民国家をめざし、全体主義国家を確立しようとした。だが、それはうまくいかない。
ピケティによると、アーレント自身は、社会的公正にもとづいて資本主義を超克する連邦主義にはきわめて懐疑的だったという。それはハイエクによる強い否定ともつながっている。
戦間期にイギリスで連邦主義が論議されたのは、何よりも戦争を防ぐためだった。旧植民地帝国の崩壊が間近いことは予想されていた。だが、国民国家に代わる連邦主義をめぐる議論はいまも結論がでていない、とピケティはいう。
〈所有権社会の崩壊は一つの重大な問いを引き起こした。資本主義を超克し、財産関係を規制するための適正な政治レベルは何か? 超国家的なレベルで経済、商業、財産の関係を組織する道を選ぶなら、資本主義と所有権社会を超克する唯一の方法は国民国家を超える方法の考案だというのは自明に思える。だが実際このために何をすればよいのか? 具体的にどんな形や中身をこの計画に与えられるだろうか?〉
ピケティにとって、その答えが社会連邦主義にもとづく社会主義の実現にあることはまちがいない。
つづく。
ピケティの新社会主義論(2) [商品世界論ノート]
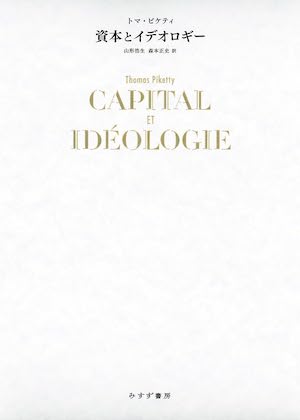
引きつづき、ピケティの新社会主義論をみていく。
累進資産税の実施にあたっては国際協力が欠かせない、とピケティはいう。税金逃れが生じる恐れがあるからだ。
しかし、国レベルだけでも、資産の透明性を高めることによって、資産への課税(不動産税と富裕税)が大きな効果をもたらすことはまちがいない。とりわけ、不動産税は、不動産の所有者が個人であっても法人であっても、情報登録を義務づけることによって、確実に課税することができる。
ピケティは、私的所有権を一時的所有権とし、社会的所有に置き換えることをめざしている。そのためには、憲法改正をおこない、企業の議決権共有や累進所得税、累進資産税、資本支給の決まりを憲法の条文に追加するべきだとも述べている。
また、政府は所得や資産の区分ごとに実際の税金支払額を公表しなければならないともいう。公表された情報にもとづいて市民は税制に関する議論を深め、議会も税のパラメーターを調整することができる。
現在、西欧では税収の内訳は、国民所得の10〜15%が所得税、15〜20%が社会保険料、10〜15%が間接税(消費税や付加価値税)となっている。しかし、ピケティによれば、間接税を正当化する理由はなく、間接税は所得税や資産税に置き換えられるべきだという。
こうした置き換えをおこなっても、全税収のうち、圧倒的な部分を占めるのは累進資産税ではなく累進所得税だ。社会保障費は独立財源として守られるが、資産税は若者への資本支給として活用され、所得税はベーシックインカム(最低所得保障)の財源として用いるというのが、ピケティの考え方だといってよい。
ベーシックインカムを拡張しなければならない、とピケティはいう。かれの提案では、ベーシックインカムは平均税引き後所得の60%に設定される。すべての成人がこの最低所得を保障される。ほかの所得が増えると支給額が減らされるのはいうまでもない。
ベーシックインカムは人口の3割ほどに適用され、その総費用は国民所得の5%ほどになるという。ベーシックインカムの目的は、少ない支払いしか受けられない人びとの所得を増やすことにある。
いうまでもなく、国には保健、教育、雇用、賃金、年金、失業手当などにたいする責任もある。さらに重要なのは公正な労働報酬にもとづく社会をつくることだ。累進所得税はそのきっかけになる。
教育システムを改善しなければならないとも書いている。現在のシステムは、エリート主義的な教育に重きを置きすぎており、多くの生徒が教育的に恵まれないまま放置されているという。
経済発展と人間の進歩は教育のおかげであって、神聖化された資本によるのではないというのがピケティのとらえ方だ。1980年代以降、アメリカでもヨーロッパでも教育格差が広がっている。教育投資への公正な分配がおこなわれていない。アメリカでもイギリスでも高名な私立大学にはいるには莫大な費用がかかり、金持ちが優位に立っている。
公平な教育というけれども、実際には偽善がまかり通っているのだ。公共教育投資も実際には一部の集団に片寄っている、とピケティはいう。教師の平均給与を上げるべきだし、初等教育と中等教育への投資をもっと増やすべきだ。高等教育の受益者には、社会的多様性がもっと反映されるべきだとも述べている。
地球温暖化は格差増大と並んで、現在、人類が直面する最大の課題である。その対策として打ち出されているのが、炭素排出削減であり、その方策として、炭素排出に課税すること(いわゆる炭素税)が検討されている。だが、それだけではじゅうぶんではない。自動車やエアコン、建物の断熱についても基準をもうけ、厳格なルールが適用されなければならない。
炭素税は累進所得税に統合することが自然だ。それを再生可能エネルギーへの移行費用に回す。炭素含有量は電気などに関してはすでに計測されている。また、炭素排出が多いとされる財やサービス、たとえばジェット燃料やビジネスクラスの航空券などに高い税率を課すことなども考えられる。
新しい社会主義がめざすのは公平な経済社会だけではない。それは政治レジームの変革とも結びついている。
現在の議会制民主主義のモデルは、格差増大に対応できていない。普通選挙は一人一票の原理にもとづいているが、実際には金銭的、経済的利害が投票を動かしている。政治資金が政党の政策に影響をおよぼしていることは、まぎれもない事実だ。
これにたいし、ピケティは企業の政治献金を禁止して、「民主的平等性バウチャー」の導入を検討せよという。これは国がすべての市民に5ユーロ程度のバウチャー(クーポン券)を渡して、各自がそれを気に入りの政党や運動に寄贈するというものだ。各政党はそれを政治資金とし、完全な透明性のもとで候補者を擁立する。
「民主的平等性バウチャーの中心的な狙いは、平等で参加型の民主主義を促進することだ」と、ピケティは書いている。それにより金権議会制民主主義を打破し、直接民主主義を拡大しようというのだ。
とはいえ、ピケティは直接民主主義を実現しようというわけではない。「直接民主主義が議会制民主主義の熟議に置きかわるとは考えにくい」とも述べているからだ。あくまでも「民主的平等性バウチャーの精神は、議会制民主主義をよりダイナミックな参加型にすることであり」、全市民が政党の政策と選挙公約に関心を向けることなのだという。
さらにピケティは国家の問題にふれる。「現在のシステムで最も明確な矛盾は、財と資本の自由な流通が、各国の税制や社会政策の選択肢を大きく制限する形でまとめられていることだ」
経済社会が国家単位でまとめられていることに、そろそろ限界が露呈しはじめているのではないか。公正の問題は、すでに超国家的な課題になっている。富裕国から貧困国への開発援助の流れも存在している。さらに環境問題や生物多様性、気候変動を考えてもグローバルな公正が求められる時代になっている。にもかかわらず、国家という枠組みは相変わらずだ。
文明国は財やサービス、資本の自由な移動を認めるようになっているが、人の移動はできるかぎり阻止している。「EUの特徴は、内部で自由な移動を実現しつつ、アフリカや中東からやってくる人については、貧困や戦争を逃れてきた人々を含め、制限が強いままだという点にある」。非ヨーロッパ移民にたいする敵意は増すばかりだ。
超国家的な公正にたいする考え方は、いまだに混乱したままだ。それでもピケティは国際間における「社会連邦主義」の推進を掲げる。当面はEU内部で共通の公正性を高める努力をつづけることが重要だ。グローバルな税制やグローバルな環境保護、研究促進、グローバルな人の移動についても、超国家的な議会で議論を深めるべきだろう。
こうした超国家民主主義モデルは、EUだけではなく、たとえばEUとアフリカ連合、EUと米国とのあいだでも確立できるはずだとも述べている。それにより多国籍企業への課税や地球温暖化への対処、移民の原則、開発援助のあり方などについても、いわば超国家議会において論議することが可能なはずだという。
とはいえ、世界社会―連邦制への移行が理想的すぎて、実際にはそう簡単ではないことも、ピケティは認めている。時代はそれに逆行しているからだ。
国際的な緊張を高めることなく、はたして世界社会―連邦制への移行は実現できるのか。当面は何カ国かのグループのあいだで、これを実行し、平和的にそれを国際レベルに広げていく努力を重ねるほかない。
大著『資本とイデオロギー』において、ピケティははっきりと新社会主義の方向を打ちだしている。
それは理想論すぎるようにみえるかもしれない。それでも注目しなければならないのは、ピケティが20世紀の社会民主主義の限界、ソ連型共産主義の抑圧性、ハイパー資本主義の暴走を踏まえながら、新社会主義=参加型社会主義を提唱していることだ。
そのことにふれることで、かれの新社会主義論の根拠がさらに明らかになってくるだろう。
ピケティの新社会主義論(1) [商品世界論ノート]
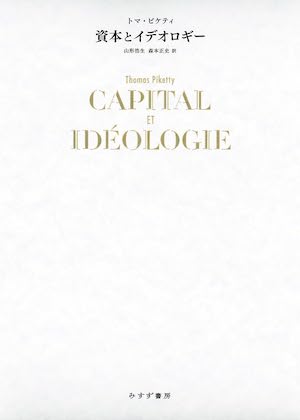
トマ・ピケティの『資本とイデオロギー』は大著で、全部読み切るには半年以上かかるだろう。それに、ぼくの頭ではたぶんとても理解しきれない。
ピケティの今回の本が大著になったのには理由がある。古代から現代までの格差の歴史をふり返ろうとしたからである。とりわけ20世紀の大転換を扱った部分はぱっと見しただけでも力がこもっている。資本主義の危機と、ふたつの世界大戦、社会民主主義の展開、その限界、共産主義の解体とポスト共産主義社会、そしてハイパー資本主義の登場と、20世紀は目まぐるしく変遷した。
それをここで過不足なく紹介するのは骨が折れる。もし元気が残っていたら、挑戦してみることにしよう。
今回は安直に『資本とイデオロギー』の最終章だけを読んでみることにした。「21世紀の参加型社会主義の要素」と題されている。
ここでピケティは、新社会主義を提唱している。
「1980年代の保守革命、ソヴィエト共産主義崩壊、新財産主義イデオロギーの発達によって、21世紀初頭の20年間で、所得と資産の集中は全世界で抑えのきかない水準に達した」と述べている。その結果、現在はさまざまなフラストレーションにあふれ、アイデンティティの亀裂と無闇なナショナリズムが世界じゅうをおおっている。
こうした状況ははたして克服できるのか。それとも、世界はこのまま混沌の時代に向かっていくのだろうか。
これにたいして、「私は今日の資本主義システムを乗り越えて、21世紀の新しい参加型社会主義の概略を描けると確信している」と、ピケティは言いきる。
いまどき、社会主義と思うかもしれない。
しかし、基本となるのは公正な社会だ。つまりだれもが、社会的、文化的、経済的、市民的、政治的な生活に参加できるようでなければならない。
ピケティが継承すべきだとしているのは、20世紀の西欧における社会民主主義であって、「ソ連などの共産主義国で試された(そしていまだに中国の公共部門で広く実践されている)、ハイパー中央集権型の国家社会主義」ではない。
ソ連とその影響を受けた国々によって、「社会主義」という用語が毀損されていることをピケティも認めている。しかし、かれがそれでも引き続き、社会主義という用語を用いるべきだというのは、とりわけ20世紀西欧における社会民主主義の経験と伝統を尊重したいと考えているからだ。
ピケティはみずからの提唱する社会主義を「参加型社会主義」と名づけている。それはどのようなものなのだろうか。
資本所有者が経済権力を専有するというのが資本主義の原理である。 その資本は私有財産(資産)と結びついている。
19世紀以来、こうした純粋な資本主義モデルを、各国は法制度や社会制度、税制によって規制してきた。
ピケティがめざす方向は、資本主義と私有財産を克服し、参加型社会主義(新社会主義)を実現することである。
それは何も暴力的な革命による必要はない。法律や税制を変えるだけで、かなりのことが実現できるというのである。
そのひとつとして、かれが挙げるのは、企業内部で徹底した権限共有をおこなうこと(資本の社会所有という原則を確立すること)。
もうひとつは巨額の財産にたいして累進課税をかけること(資産の一時所有という原則を確立すること)。
たったこれだけと思うかもしれない。だが、この変革のもたらす波及性は大きい。
その内容をみていくことにしよう。
まず企業内部での権限共有について。
具体的にいうと、これは取締役会だけではなく労働者代表も、企業内の議決権をもつようにする仕組みである。実際、ドイツやスウェーデンでは、こうした労働者参加の仕組みが実施されている。このことによって、すでに株主万能主義や短期利益主義を抑制した社会的・経済的な企業モデルが生まれつつあるという。
大株主の議決権にも上限が設けられなければならない。この生産的で公平な企業モデルには、これからさまざまな試行錯誤がなされるだろう。とはいえ、その方向は、社会に開かれた企業モデルをつくることによって、利潤追求に縛られた資本主義から生産システムを解放することにある。
次に累進資産税について。
ピケティは、際限のない所有権の集中を防ぐ制度的な仕組みを見つけなければならないという。そのためには、まずかつておこなわれていた相続と所得への累進課税を復活する必要がある。だが、それだけでは不十分だ。加えて、累進的な資産税が課されるべきだ。
現在、金持ちへの課税は、資産にくらべればごくわずかでしかない。多くの資産が免税になっており、金融資産にたいしても定率税しかかけられていないのが現状だ。
相続税を待つことなく、現時点で総資産(個人所有の不動産、事業資産、金融資産などの正味価値)に累進課税をかけるべきだ、とピケティはいう。金持ちは何十年かにわたり総資産の1〜2%を税として支払うほうが、遺産を遺族に残すときに20〜30%支払うよりも楽だとも述べている。
累進資産税の目的は、資産の循環を高め、財産の分散を促すためだ。現在、アメリカでは豊かな人びと(トップの10分の1)が総資産の70%以上を所有している。こうした状況が下層50%の人びとの経済機会を奪っていることはまちがいない。
ここで、ピケティは、これまで世界でおこなわれてきた農地改革を例に挙げる。農地改革はいまではほとんど誰もが正しかったと認める改革だ。農地改革によって、貧しい農民は自分の土地をもつようになり、田畑を耕して収穫を自分のものにすることができた。それ以前は、少数の地主の手に経済力が集中し、社会全体に貧困と対立を巻き起こしていたのだ。
しかし、ピケティにいわせれば、資産は農地だけとはかぎらない。かつての農業社会では、農地こそが資産だった。これにたいし現代では工業資産、金融資産、不動産が資産の中心となっている。いわば、現在の金持ちはかつての大地主と同じなのだ。そうだとするなら、累進資産税はいわば新時代の農地改革だというわけだ。
ピケティによれば、資産への年次累進課税、累進相続税、累進所得税の3つが、公正な社会の基本的税制となる。累進所得税には社会保障税と累進炭素税が含まれる。そして、だいじなのは、この税収によって、ベーシックインカムと公共支出のすべて(保険、教育、年金、その他)がまかなわれることだ。
ここでピケティはユニークな提言をしている。それは25歳になったすべての若者に、国がたとえば1500万円の資金を提供するというものだ。これをかれは「公的相続システム」と名づけている。この資金はどう使ってもいい。起業してもいいし、家を買ってもいいし、好きなようにつかえる。いずれにせよ、この「公的相続システム」は職業生活のスタート台になる。
その財源は、相続税と年次資産税だ。「公的相続システム」による資産の分散と若返りは、経済に新たな力をもたらすだろうという。
累進所得税について、ピケティはレーガン政権以前と同じ税率に戻すことを主張している。それは平均所得の10倍超には60〜70%、100倍超には80〜90%というものだ。
累進資産税は新しい税といえるが、重要なのは累進性だ。ピケティは、たとえばとして、全国平均より低い資産については税率0.1%、平均の2倍の資産には1%、100倍だと10%、1000倍なら60%、1万倍だと90%の累進性を提案している。これによると、億万長者の資産はただちに10分の1になる。
以上をまとめて、ピケティはこう述べている。
〈ここで提案した参加型社会主義のモデルは二つの大きな柱を持つ。まず社会的所有権と企業内の議決権共有、そして第二に一時的所有権と資本循環だ。これらは現在の私的所有権の仕組みを超克するために不可欠なツールだ。これらを組み合わせることで、今日の私有資本主義とは似ても似つかない所有権の仕組みが実現できる。これは本当の意味で資本主義の超克となる。〉
はたして、それは実現可能なのか。可能だとしても、そこには大きな落とし穴がひそんでいないか。ピケティの新社会主義論はまだまだつづく。引きつづき、考えてみることにしたい。
『貧乏人の経済学』を読む(4) [商品世界論ノート]
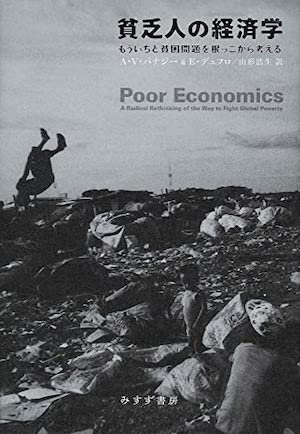
貧しい人たちは思いもかけぬ手段を用いて、稼ぎを得ようとします。かれらは天性の起業家だ、と著者はいいます。
ゴミ拾いから始めて、ゴミの分別をし、そこからリサイクル事業を立ち上げた人もいます。服飾学校を終えたあと、村の人に服飾を教え、中古ミシンを買い、縫製事業を始めた人もいます。その事業は大成功を収めました。しかし、それはごくごく例外です。
現実はといえば、多くの人の営む事業(商売)はとてもちいさくて、競争相手も多くて、ほとんどもうからないのです。インドでは1日2ドルほどの儲けがでればいいところだといいます。そういう人は、さらに融資を受けて、商売を大きくしようとはしません。
たとえ投資をして商売を大きくしても、商品を多く仕入れ、人も雇わなければいけないし、忙しい目にあうだけで、たいして儲からないことがわかっているからです。
本気で稼ぐつもりなら、どこかで壁を突破しなければなりません。それが起業のむずかしさです。たいていの人はそこであきらめてしまい、たとえ融資を受けることができても、その多くを別のことに使ってしまいます。
残念ながら貧乏な人の商売は働き口がないときに、何とか食っていくための手段でしかないようです。商売をするのはたいてい女性で、家事とかけもちです。
「貧乏人による多くの事業は、その起業家精神を証明するものではなく、むしろ彼らの暮らす経済がもっとましなものを提供してくれないというひどい失敗の症状なのかもしれない」と、著者は書いています。
そこで、成長著しいインドあたりでは、貧乏な人の夢は子どもに公務員か民間企業のサラリーマンになってほしいということになります。女の子なら、教師、公務員、看護婦が職業選択の上位を占めます。
特に公務員が人気があるのは、安定性への欲求が強いからです。「実は雇用の安定性こそが、中流階級と貧乏な人々との大きなちがいのよう」だ、と著者も指摘しています。
安定した雇用は人生の見通しを変えます。未来があるという感覚が与えられるのです。これは貧困の落とし穴にはまった人にはないものです。
都市への移住は貧乏から脱出するひとつの可能性を与えます。しかし、都市でも安定した所得が得られる仕事はごくまれです。出稼ぎはあくまでも一時的な収入を得るためでしかありません。それでも同じ村の人が都市に移住しているのなら、村のつながりをあてにして、都市でも何かの仕事を見つけられるかも知れません。とはいえ、都市で「よい仕事」を見つけるのは至難の業です。
著者はマイクロファイナンスの融資が10億人もの「はだしの起業家」を生み出すというのは幻想にほかならないと断言します。
〈マイクロ融資など、ちっちゃな事業を助ける手法は、それでも貧困者の生活において重要な役割を果たせます。というのも、そうしたちっちゃな事業は、おそらくこの先当分のあいだは貧乏な人たちが生き延びるための唯一の方法であり続けるからです。でも、それが貧困からの大量脱出になると思うのは、自己欺瞞でしかありません。〉
これはなかなか厳しい結論です。
それならば、マイクロ融資の手助けには限界があるとしたら、政治もまた救いの手にはならないという結論が導かれるかもしれません。
貧困国政府の無能ぶりと汚職はずいぶん前から指摘されてきた、と著者はいいます。たとえば、ウガンダでは、初等教育を改善するために外国からの援助をもらっても、途中でピンハネされて、その予算が実際に学校に届いたときには、ごくわずかの金額になっていました。
ところが、その調査報告がウガンダの新聞に発表されると、全国で怒りの声が巻き起こったのです。そして、ついには学校が自由に使える資金が増えていったという事実があります。
「小刻みの進歩とこうした小さな変化を積み重ねれば、時には静かな革命だって起こるのだ」と、著者はコメントしています。
途上国ではダメな政治・経済制度のもと、汚職や怠慢が横行しています。しかし、著者は、それでも「小刻みの進化」と「小さな変化」を積み重ねるなら、「静かな革命」が起こりうるのだというのです。
選挙方法のチェックと改善、公共サービスの情報開示と苦情の受け付け、村落集会の新しいやり方、そうしたこまごまとした点検と改革から大きな変化が生まれてくる可能性があります。とりわけそのなかで女性の果たす役割がだいじです。できることはいろいろ残っている、と著者はいいます。
途上国でも公務員がしていいこと、悪いことについてはたくさんの規定があります。しかし、公務員の給料が低く、監視もふじゅうぶんな場合や、裁量と目に見えぬ賄賂が横行しているところでは、つねに汚職と怠慢のリスクが発生します。
また紙の上でつくった官僚のルールが、現場と適合していないこともよく見かけられます。それは医療現場でも教育現場でも、しばしばあることです。多くの計画がかたちだけしか知らされず、実際に機能していないこともあります。それらはすべて改善の余地があります。
「大規模な無駄と政策の失敗が起こるのは何か深い構造問題があるからではなく、政策設計の段階できちんと考えなかったからであることが多い」という著者の指摘には聞くべきものがあります。
政策にたいする低い期待は、政策そのものの効果を奪っていきます。こうした悪循環を断つことがだいじです。政治といえば、「公共の利益」よりも「利益誘導型」の政治のほうが優位に立ちがちです。しかし、信頼できるメッセージがあれば、有権者は全体の利益につながる政策を支持するはずだ、と著者は述べています。
周縁部分で制度や政策を改善する余地はあり、こうした変化を持続し、積み重ねていくことが、「静かな革命」につながるのだというのが、著者の考え方のようです。
最後に貧しい人たちの生活を改善するための5つの教訓が示されています。
第1に、貧しい人は正しい情報をもっていないことが多く、それを伝えることがだいじだということです。
第2に、貧しい人はあまりにも多くさまざまな問題をかかえこみすぎており、たえず心配を強いられているが、預金にしても健康にしても、正しいとわかっていることを確実に実行すれば、現在の生活を改善できるということです。
第3に、貧しい人たちはこれまで市場や金融からも排除されていたが、マイクロファイナンスが新しい生活の可能性を開き、公共サービスの充実もますます求められているということです。
第4に、貧乏な国は貧乏だからといって、失敗を運命づけられているわけではなく、むしろ周縁から無知、イデオロギー、惰性を克服していけば、いくらでも改善の余地はあるということです。
第5に、悲観主義におちいらず、無理のない期待をもちつづけることがだいじであって、それは楽ではないが、不可能な道ではないということです。
最後に著者は貧困を解決する一般原理などはないと述べています。現場の実情を辛抱づよく理解することに努め、貧困から抜けだす道をさぐる以外にないのです。貧困は何千年も人類とともにありましたが、さまざまなアイデアを探求することで、だれもが1日1ドル以下で暮らさなくておいい世界に到達できるはずだと記しています。
われわれはおうおうにして自分の国のことしか考えず、それもしばしば自分に都合のいいことばかりを想定しがちですが、もっと世界全体のことに目を開くのもだいじではないでしょうか。そのことを本書は教えてくれます。
『貧乏人の経済学』を読む(3) [商品世界論ノート]
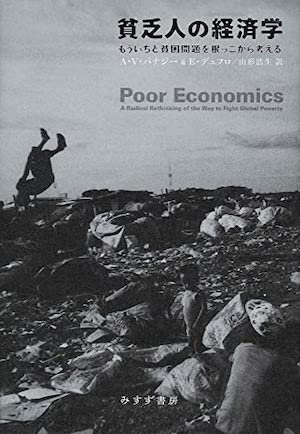
貧困の落とし穴から脱出するには、当の家族がみずからの力で脱出の方向を探る以外に方法はありません。すべての人を幸福にする社会主義はひとつの理想かもしれませんが、現実には存在しないといってもよいでしょう。だとすれば、いま現に存在する制度が、はたしてどの程度、貧困からの脱出を手助けする手段となるのかが問われなければならない、と著者はいいます。
人生にはリスクがつきものです。雇われていた会社を解雇される、夫と離婚する、子どもが引きこもりになる、事業に失敗する、干魃や洪水で田畑がだめになる、その他さまざまな困難が人を襲います。加えて、内乱や政治不安、金融危機や盗難、詐欺が生活を直撃することになれば、そこから立ちなおるのは、そう簡単ではありません。
いったん貧困のゾーンに陥ってしまうと、そこからはなかなか抜けだせなくなります。しまいには立ちなおろうとする意欲も失い、すっかり落ちこみ、何ごとにも集中できなくなるのは悲しい現実です。
貧しい人のあいだでも、できるかぎりリスクを避けるための工夫はなされている、と著者はいいます。たとえば所有する畑を分散する、家族のメンバーが多様な職業につく、出稼ぎにいくといったことです。貧しい一家が小作人になる道を選ぶこともあります。たくさんの仕事を掛け持ちする場合もあります。
村には困っている人を助ける助け合いのネットワークもありますが、それには限界もあります。
とりわけ健康上の問題が生じて、収入が落ちこみ、医療費もかさんだりすると、近所の助けだけでは間に合いません。そこで、仕方なく金貸しからカネを借りることになりますが、そうなると金利が積み重なって、借金がたちまち膨らんでいきます。
富裕国ではさまざまな保険が行き渡っていますが、途上国では健康保険を含め、貧しい人向けの保険はほとんどない、と著者はいいます。マイクロファイナンスのなかには、保険を導入しようとした機関もありました。しかし、保険にはいろうとした人はほとんどいなかったといいます。
なぜ貧しい人は保険にはいろうとしないのか。災害がおこったときは国が助けてくれるとたかをくくっているという見方もあります。保険をかけても、はたして元がとれるのかと疑いをもっている人が多いという見方もあります。
いずれにせよ、かなりの後押しと説得がなければ、貧しい人は保険にはいりたがらないといいます。保険会社への信用もいまひとつです。さらに、保険が支払われるのは、最悪の病気や事故の場合だけだということが、保険加入をためらわせています。
そのため、著者は当面は政府による介入が必要だといいます。政府が公共の資金を投入して、保険に補助金を出し、貧しい人のあいだにも保険システムが行き渡るよう努めるべきだと提言しています。保険会社を育成することは、途上国政府のひとつの任務といえるでしょう。
マイクロファイナンスについて考えてみましょう。
何も持たない貧しい人が商売をはじめます。路上に果物や野菜を並べて、それを売ります。屋台を引いて、食べ物を売ったりもします。その仕入れ費用やレンタル料はばかにならず、ほとんど稼ぎにならないこともあります。こうした貧乏な人たちの商売を手助けするためにつくられたのがマイクロファイナンスだといいます。
マイクロファイナンスの目的は、貧しい人への小規模融資によって、人びとを貧困の落とし穴から脱出させることです。銀行は貧乏人におカネを貸してくれません。金貸しは貸してくれますが、法外な利息をとります。それでも貧乏な人たちは金貸しからカネを借りて、その結果、悲惨な目にあうことが多かったのです。
マイクロファイナンスは、1970年代半ばにバングラデシュでムハマド・ユヌスがグラミン銀行をつくったときがはじまりです。以来、世界各地でさまざまなマイクロファイナンス機関がつくられ、現在、その利用者は2億人ともいわれます。
マイクロファイナンスの特徴は、個人に融資するのではなく、借り手のグループに融資し、連帯責任を負わせることだといいます。一定額を毎週ごと返済しなければならず、借り手は毎週、グループごとに集まって、決められた返済金額を融資担当者に渡すことになっています。南アジアのマイクロファイナンスでは、年利はほぼ25%ですが、債務不履行はまずないといいます。
マイクロファイナンスははたして貧困からの脱出に役立っているのでしょうか。奇跡的とはいえないが、まあまあの成果はもたらしているというのが著者たちの結論です。
それは多くの起業を手助けし、自転車や冷蔵庫、テレビなどの耐久財の購入に結びつくいっぽう、無駄な消費の抑制にも寄与しています。そのいっぽう、女性の地位はさほど上がっていないし、教育や保険への支出も増えていないこともわかっています。
マイクロファイナンスは全能ではありません。著者たちは、はっきりとその限界も指摘しています。マイクロファイナンス機関を特徴づける「貸し倒れゼロ」のこだわりが、多くの潜在的利用者にとっては厳しすぎるといいます。
マイクロファイナンスからおカネを借りて、新規事業をはじめ、それを成功させるには、相当の勇気と知恵が必要です。しかも、返済は連帯責任ですから、緊張関係もあります。
さらにいうと、マイクロファイナンスはあくまでも多くの貧乏な人に低金利で融資するのが目的なので、より大きな企業をめざす人にとってはじゅうぶんではないといいます。リスクをとりたがる人物にはまったく向いていないのです。ほとんどの融資はきわめて少額なままです。
著者はこう指摘します。
〈マイクロファイナンス運動は、困難はあっても貧乏な人に貸すのは可能だということを実証しました。マイクロファイナンス機関がどれほど貧乏人の暮らしを変えるかについては議論の余地があるでしょう。でもマイクロファイナンス融資がいまのような規模に達したという事実だけでも、驚くべき成果です。貧乏な人に向けたプログラムのなかで、これほど多くの人を助けたものはありません。でも、貧乏人への融資を成功に導いたプログラムの構造そのものが、もっと大きな事業の創設と資金提供への踏み台になれない原因になっています。発展途上国の金融にとって、次の大きな挑戦は中規模企業への資金提供手法を見つけることです。〉
限界はあるにせよ、マイクロファイナンスが多くの貧しい人を救っていることは事実のようです。
貯金の話にもふれています。
貧乏な人はほとんど融資をあてにできない。かといって、リスクを避けるための保険にはまずはいらない。貯金するかというと、貯金もしない。そんなふうに著者は書いています。
貧乏人はなぜ貯金しないのか。かれらも将来のことを心配していないわけではない。しかし、貧乏人でフォーマルな貯蓄機関に貯蓄口座を持っている人はあまりいない。かれらがよく利用するのは英語ではメリーゴーラウンド、フランス語ではトンタンと呼ばれる回転型貯蓄信用組合だといいます。
これは昔、日本にあった講のようなものです。何人か、あるいは何十人かのメンバーが定期的に集まって、共通の鍋に同じ金額を預け、ある程度の期間がくると、メンバーのひとりが、鍋の全額を受け取れるという仕組みです。いくつもの貯蓄信用組合(講)にはいっている人もいます。
このいわば講からおカネをもらった人はトウモロコシを買ったり、家を建てる資金の一部にしたりします。これは伝統的な創意工夫ですが、それはほかに代替案がないからです。
銀行は少額口座を扱おうとしません。管理費用がかかるからです。おカネを引きだすには引き出し手数料がかかるため、貧しい人は銀行口座をつくろうとしないといいます。
改善策がないわけではありません。たとえばグループを組んで、グループで口座をつくり、みんなで引き出しや預け入れをおこなうというのもひとつです。銀行が近くになくても、地元の商店に行けば預金ができるようにするというのもひとつの方法です。携帯電話を使って預金の出し入れを簡単にすることもできるでしょう。
しかし、そもそも預金しようとする人が少ないのです。預金を増やすには、たとえば少しお茶を控えるだけでいいのです。塵も積もればというわけですね。ところが、そうしないで、おカネがあればついつい使ってしまい、肝心なときにはおカネがないというのが実情のようです。
人間の心理と時間不整合はよく生じることだといいます。きょうはほしいものを買って、明日からはもっと有意義なおカネの使い方をするぞと決心するのは、よくある心理です。ところが明日になると、誘惑に負けてしまいます。その点、アルコールやタバコ、お菓子、お茶などは典型的な誘惑財だといいます。
収穫直後におカネを手にした農民が、その一部を貯蓄しないで、すぐに使ってしまうのには、あればパッと使うという心理がはたらいているのだろうか、と著者は推察します。
なかには娘の結婚資金として貯蓄するために、マイクロファイナンスから借金をするという人もいます。おカネを借りれば返済しなければならないから、無駄なおカネを使わないようにできるというのです。貯蓄をするために、わざわざ高い利子を払ってマイクロファイナンスからおカネを借りる必要はないのに、そうするのは転倒した心理ですが、少しずつ貯金しておカネを貯めようとしても、途中で使ってしまいそうで、自信がないというのもわかります。
しかし、こうした心理も貯蓄慣れしていないことから発しているのかもしれません。おカネがあれば、それを無駄づかいしかねません。どうせ明日誘惑に負けるなら、今日のうちに使ってしまおうというわけです。その結果、負のスパイラルが生じます。
能動的に預金するにはよほどの自制心を必要とします。サラリーマンならば、天引きで自動的に貯金することも可能ですが、日々ストレスにさらされている貧しい人が自制心を発揮するのはかなり困難なことだ、と著者はいいます。
こうして豊かな人はますます豊かになり、貧しい人はますます貧しくなるという構図が生まれます。
貯蓄のない貧しい人は、何らかの物入りがあれば、借金をしないわけにはいかず、借金をすれば、そこからなかなか抜けだすことができません。すると、ますますストレスがたまっていきます。
貧困の落とし穴から抜けだすには、長期的な目標と楽観主義が必要です。目先の気まぐれに流されず、無駄を切り詰め、ストレスを回避し、将来に希望をもつこと。そこから、貯金をしようという動機も生まれてくるはずだ、と著者はいいます。
できるだけ簡単に紹介しました。次回は結論になります。
『貧乏人の経済学』を読む(2) [商品世界論ノート]
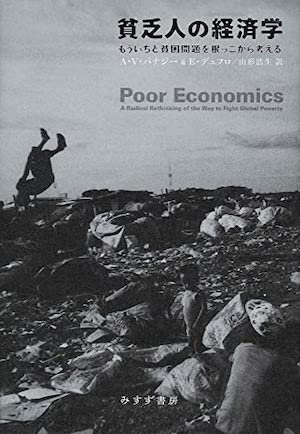
食につづき健康が取りあげられます。
世界では毎年、5歳未満で亡くなる子どもたちが900万人いますが、そのうち2割がロタウイルスによる下痢が原因です。この症状は水を殺菌する塩素剤漂白剤と、塩と砂糖を含む経口補水液(ORS)で改善しますが、こうした手軽な方法が、上下水道のまだ普及していない地域では、ほとんど使われていない、と著者は指摘しています。
貧困と健康が密接に結びついていることはたしかです。不健康なら働けず、働けなければ借金がかさみます。健康を維持するには、蚊帳によるマラリアの予防、上下水道の整備などが大きな効果を発揮するのはまちがいありません。
しかし、こうした公衆衛生の普及には費用がかかります。でもたいした費用ではないのです。蚊帳もそうですが、水道がない場合は塩素系漂白剤を利用すればよいのです。しかし、多くの人はそれを利用しようとしません。
健康に関心がないわけではないのです。問題はかれらがむしろ伝統と習慣にもとづいて、困難を乗り越えようとすることにある、と著者は指摘します。インドでは病気になったとき、貧しい人びとが頼るのは、いまだに祈祷師と無資格の民間医なのです。民間医は注射に加え、やたら抗生物質を濫発しますが、その治療は「何の役にも立たないどころか害になる」と著者は憤慨しています。
さらに問題なのは予防措置を実施する政府の保健センターがうまく機能していないことです。保健センターは閉まっていることが多く、開いていてもおざなりな対応しかせず、村民にあまりあてにされていないのです。そのため、村民が信頼するのは昔ながらの方法で、相変わらず心療治療師や祈祷師に頼りがちになります。
しかし、移動式の予防接種キャンプを組織して村を訪れ、予防接種をすれば何か景品をもらえるというようにすれば、村人は集まり、予防接種の摂取率は高まるといいます。こうしたちいさなインセンティブも人びとを後押しすることになるのです。その意味では、ちょっとした工夫次第で貧しい村の健康を促進することが可能になる、と著者は指摘します。もちろん、そのさいには予防接種の効果にたいする説明も必要になってくるでしょう。
貧しい国の保健政策で第一の目標とすべきことは「貧乏な人々の予防的ケアをできるだけ容易にしつつ、同時に人々が得る治療の質を規制すること」だと、著者は論じています。
次は教育問題です。
教育は受けたほうがいいにきまっています。多くの国で小学校は無料になっています。しかし、途上国では、子どもの欠席率がかなりの割合にのぼり、中学校どころか小学校にも行かない(あるいは行かせてもらえない)子どもたちが多いといいます。
世界のほとんどどこでも小学校と中学校は設置されるようになってきました。学校に行く子どもも増えてきました。それでも簡単な文章を読んだり、簡単な算数ができたりする子どもの割合は低いのが実情です。
親からみれば教育は子どもへの投資であり、贈り物でもあります。しかし、それを嫌がる親もいます。教育におカネをかけるより、自分たちのために子どもをすぐはたらかせたほうがよいと考える親もいるからです。
しかし、教育による学習が高賃金の雇用と結びついていることはたしかです。中等教育を終えた人のほうが正規の仕事につきやすいし、自分の事業にしてもうまく営むことができるのです。教育を受けないまま仕事をしても、その成果には限界があるでしょう。
問題は途上国の学校制度そのものにある、と著者はいいます。2005年の段階で、インドでは公立小学校に通う5年生のうち47%が2年生レベルの文章を読めず、私立学校でも32%が同じ状況だというのです。しかも、6年生になるまで学校に通いつづける生徒は少ないのです。
途上国では、親は富を獲得する手段として教育をとらえがちです。「彼らにとって教育は宝くじのようなもの」だ、と著者はいいます。そのため、親は子どもたちを「頭のいい」子と「頭の悪い」子に選別し、「頭のいい」と思われる子だけに教育資金を集中的に投入するのです。その結果、かえって貧困の落とし穴から抜け出せなくなってしまうことがあるといいます。
教育制度自体がいまだにエリート主義を取っていることも問題です。多くの子どもたちはそれについて行けず、クラスも最高クラスと最低クラスに選別されていくことになります。最低クラスに配属された教師は投げやりになり、ろくに授業もしなくなります。
教師は落ちこぼれの子を無視し、親もその子の教育に興味を失ってしまいます。加えて多くの偏見とステレオタイプの思い込みが、子どもたちの教育機会を奪ってしまいます。
多くの発展途上国では、カリキュラムや教え方が、ふつうの子どもよりエリート向けにつくられています。そのため、教育にはごく一部を除いて、期待はずれの成果しか得られないのです。著者はあまりできない子どもたちをどう教えるか、そのため補習教育プログラムをどう組みこんでいくかがだいじだ、と主張します。エリートをつくるのもだいじですが、教育の本来の目的は、子ども全員がじゅうぶんに読み書き、計算ができるようにすることなのです。重要なのは、子どもたちを思いやりをもって扱い、ほんとうの潜在能力を発揮できるよう助けることだ、と著者は強調します。
「すべての子供が学校で基礎をきちんと学ぶのは十分可能だし、それだけに焦点を絞って取り組めば、実はかなり簡単に実現できる」。教師にしても、能力のある補習講師になるには、訓練はさほどいらない。そして、子どもたちが学教で自信をもつようになれば、かれらにも貧困の落とし穴から脱出できるチャンスが生まれるはずだ、といいます。
家族計画についても論じられています。
中国の一人っ子政策は有名ですが、インドでも一時、全国で強制的な不妊手術が実施されていました。しかし、この政策は国民の反発をくらい、インディラ・ガンジー政権の敗北とともに廃止されます。
日本ではいまや人口減少が懸念されていますが、世界全体の人口はまだまだ増えつづけています。人口増加は気候温暖化を引き起こし、食糧問題や水不足を引き起こします。人口抑制の必要が論じられているにもかかわらず、途上国では人口はいっこうに減る気配がありません。
途上国では、なぜ貧しい人びとが大家族をもとうとするのでしょうか。避妊法はもちろん知られています。とはいえ、とくに女性は、夫や義母、あるいは社会から、自分の望む以上に子どもをつくれというプレッシャーを受けているといいます。
著者にいわせれば、途上国では、多くの親が子どもをいわば金融資産と考えていることが問題です。子どもが多くいれば、自分たちが年を取ったときに、そのうちの誰かが面倒を見てくれるはずだという考えが、いまだに根強いといいます。
娘があまり喜ばれないのは、女性は結婚するものだし、そのときには持参金を持たせなければならないし、結婚すれば夫の家庭にはいってしまうと考えられているからです。そのため男の子がほしい夫婦は、男の子が生まれるまで子どもをつくりつづけます。伝統的家族のなかでは、女の子は労働力として評価されないかぎり、だいじにされず差別されるといいます。
豊かな国では、こうした考え方をする必要がありません。社会保障や健康保険、投資信託、退職金などが、老後の不安を解消してくれるからです。人生にはリスクがつきものですが、貧しい国では豊かな国ほどリスクを軽減する制度が整っていません。大家族をつくることは、そうしたリスクを軽減するためのひとつの防御策ととらえられているようです。しかし、子だくさんは同時に貧乏とつながるところにむずかしさがあります。
著者はこう書いています。
〈もっとも有効な人口政策とは、子だくさん(特にたくさんの男児)を不要にすることかもしれません。効果的な社会的セーフティー・ネット(たとえば健康保険や高齢年金)や、あるいは老後に備えた収益性の高い貯蓄を実現する金融商品の開発で、出生率の十分な減少と、おそらく女児に対する差別の緩和も実現できます。〉
しかし、はたしてそれは可能なのでしょうか。
こうした制度面の整備が次の課題となってきます。
『貧乏人の経済学』を読む(1) [商品世界論ノート]
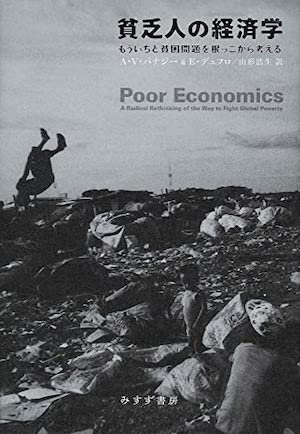
ツンドク本の整理です。原著のタイトルPoor Economics を『貧乏人の経済学』と訳す理由はわからないでもありませんが、やや違和感があります。刺激が強すぎるというか、ちがうニュアンスを喚起させるというか、まるで自分のことを言われているみたいというか。最初『貧困の経済学』でじゅうぶんなのではないかと思ったりもしたのですが、それでは「人」に即したこの本の意図が伝わらないかと考え直したりもします。タイトルはむずかしいですね。
それはともかく、本書は開発経済学の専門家、アビジット・バナジーとエスター(エステル)・デュフロの共著です。バナジーはインド・コルカタ(旧カルカッタ)生まれの経済学者、デュフロはフランス人の経済学者(ともに現在マサチューセッツ工科大学教授)。ふたりは本書出版後の2015年に結婚し、2019年にノーベル経済学賞を共同受賞しています。
ぼく自身は、開発途上国の貧困問題について、ほとんど何も知りません。もちろんニュースなどで伝えられることもありますが、あまり深く考えたことはありませんでした。しかし、評判になっている本なので、読んでみるかと買い求め、それだけで満足し、ツンドク本のままになっていました。それを今回は思い立って読んでみようというわけです。おかげさまで、暇だけは財産で、当面、時間はあります。
とはいえ、最近は活字が以前にもまして頭にはいってこないし、読みはじめるとすぐ眠くなってしまう始末です。こっくりこっくり、同じページをいったりきたりして、なかなか前に進みません。中身もすぐ忘れてしまいます。そこで、いつものように、少しずつ読みながらメモにまとめてみることにしました。途中で挫折したら、あやまるほかありません。もっともぼくが挫折したところで、それを気にとめる人もいないでしょう。
「はじめに」で、「貧乏な人の経済学は、貧困の経済学と混同されることがあまりに多い」と書かれています。貧困の経済学はあまたある。しかし、それはほんとうに現実の「貧乏な人」に即して論じられているのかというわけです。
著者たちは「貧乏な人々が住む裏道や村に出かけ、質問をして、データを探す」ところからやりなおし、あらたな道筋をみつけようとしたといいます。
ここで注目されるのは、世界の最貧者です。2005年段階で、貧困国といわれる50カ国のなかで、1日1ドル以下で暮らす人が8億6500万人(全世界人口の13%)いました。その実際を知らなければ、さまざまな方策を立て、さまざまな援助をおこなっても、まったく空振りに終わってしまう、と著者たちはいいます。
貧乏の落とし穴にはまると、人はそこからなかなか抜けだせない。課題はあまりに大きい。それでも努力をつづける必要がある。「成功は必ずしも、見た目ほど遠いわけではない」と宣言するところから、本書はスタートします。情熱が感じられます。
世界の貧困問題はあまりにも大きく、手のつけようがないようにみえます。しかし、一つずつ解決していけばよいのだというのが、著者たちのスタンスのようです。
ところが、貧困問題を「大問題」として、一挙に片づけようという考え方も根強く存在します。たとえば国連顧問でコロンビア大学教授のジェフリー・サックスは、現在よりはるかに大規模な外国援助の必要性を強調します。
そのいっぽう、ニューヨーク大学教授のウィリアム・イースタリーは援助などは無意味などころか弊害が大きく、現地の人びとの自立を促すことにはならないと反論します。
著者たちの考えは、そのどちらでもありません。具体的なプロジェクトをつくって、それに適切な援助をおこなうことは必要だ。ただし、援助は何でもかでもやればよいというものではないと論じています。つまり、援助は有効なこともあれば、有効でない(かえって害を与える)場合もあるということです。あくまでも現場に即して、問題を理解し、適切な方法を見いださなければならないというわけです。
3つのiが政策の失敗や援助の低効果を招く原因になっているという指摘がおもしろいですね。それはイデオロギー(ideology)、無知(ignorance)、惰性(inertia)です。たしかにそうかもしれません。ただし、これは貧困対策にかぎった問題ではないでしょう。
ここからが第1部です。「個人の暮らし」と題されています。
まずは食の問題。
最初に目を開かされるのは、貧困といえば飢餓だと思うのはまちがいだ、と著者が指摘しているところです。たしかに大飢饉は起こりうる。しかし、世界で10億人が飢えているという見方は、けっして正しくないといいます。
おカネのない貧乏な人が、じゅうぶんに食べられないというのは事実でしょう。だからといって1日1ドル以下で暮らす人が、その少ない実入りをすべて食糧につぎ込んでいるわけではありません。アルコールやタバコ、お祭りに使っていることも多いのです。少し収入が増えても、それは主食に回らず、美食や嗜好品に向かう傾向があるといいます。
少なくとも現在の地球では、1日1人あたり2700キロカロリーが供給できるほど、食料はじゅうぶんに生産されています。絶対的な食糧難はありません。水道と公衆衛生の普及、重労働の軽減などによって、人の平均カロリー摂取量はむしろ減っています。飢えがあるとすれば、それは食糧分配の仕組み(さらに干魃や戦争)のせいです。餓えはもちろん大きな問題です。しかし、「多くの人が貧乏なままなのは、食が足りていないせいではない」と、著者たちはいいます。
とはいえ、こういう言い方は誤解を生むかもしれません。最貧層のカロリー摂取量が少なく、栄養不良が身体の発達に影響をおよぼしていることはたしかです。食べるものが増えて、それが栄養をよく考慮したものであれば、子どもを含め、体力もついて、一家の生活はより改善される可能性があります。
にもかかわらず、食事の慣習を変えるのはむずかしく、貧しい人びとはなかなかバランスのよい食事を取ろうとしないことが問題なのです。かれらは食事を改善するよりも、昔ながらの伝統にしたがって、結婚式や持参金、祭や葬儀などに収入の多くを費やしてしまいます。あるいは最近では、テレビや携帯におカネをつぎこんでしまいます。
貧困と栄養不良はけっして無関係ではありません。だからといって、貧乏な人には安価な穀物を与えればよいという食糧政策はまちがっている、と著者たちはいいます。問題はカロリー量ではなく、ほかの栄養素であり、バランスのよい食事なのです。慣習はなかなかあらたまらないかもしれません。しかし、少なくとも、お腹のなかの子どもと、ちいさな子どもにたいしては、その栄養状態が配慮されるよう、政府が保健所や学校、保育園を通じて必要な対策をとることはできるはずだ、と著者は述べています。
まだ、はじまったばかり。引きつづき読んでみましょう。
食につづいて、「個人の暮らし」では、健康、教育、家族計画の問題が論じられます。



