貨幣の力──ヒックス『経済史の理論』を読む(4) [商品世界論ノート]

都市国家の時代はゆっくりと終わりに向かい、代わってスペイン、オランダ、フランス、イギリスなど、領域国家の時代がはじまる。
しかし、都市国家を動かしていた商人経済はすっかり解体されたわけではない。ある意味ではそれはたしかに解体だった。ヴェネツィアはゴーストタウンになってしまう。だが、領域国家は商人経済を吸収することを忘れなかった。いまや商人経済を保護し、商業センターを発展させるのは「国家」の役割になる。その局面をヒックスは「中期の局面」と名づけている。
ヒックスのいう「中期の局面」を、われわれは「近世」と呼んでもいいだろう。
「中期の局面」の特徴は、商人共同体の内部に限られていた商人経済が、いわば周辺にはみだしていくところに求められる、とヒックスは書いている。「従前の非商業的な周辺部分はさまざまな側面において、市場に対して開放的となる」
すなわち領域国家が商人経済を取り込むことによって、国家のなかに市場が浸透していくことになる。やがて、国家が外部に拡張していくにつれて、市場も外部に広がっていくことになるだろう。
ヒックスは近代(産業革命)以前の「中期の局面」(近世といってもよい)における市場の浸透を4つの分野にわたって考察する。すなわち貨幣(金融)、財政(国家)、農業、労働の4つの分野だ。これらの4つの分野はもちろん相互にからんでいるが、これをあえて4つに分けることによって、市場が浸透するプロセスがより明らかになってくる、とヒックスは考えている。
これをいっぺんに説明するのは骨が折れる。そこで、きょうはテーマを貨幣(金融)にかぎって、第5章の「貨幣・法・信用」を読んでみることにする。
貨幣はだいたいが鋳造された金属片で、国家によってつくられたもののように思われている。それはけっしてまちがいではないが、貨幣は鋳造貨幣がつくられる前から存在した。貨幣はそもそもが商人経済の創出物で、国家はそれを継承したにすぎない、とヒックスはいう。
たとえば村落に商人がいるとしよう。かれはいつでも商品を仲介できるように交換性のある財貨を保存しなければならなかった。そして、保蔵と隠匿が容易で、しかも損耗しにくい財貨といえば、けっきょくは金や銀などの貴金属に落ち着くというわけだ。
貴金属が「価値保蔵」機能をもつと、それは次第に均質化されて、「価値尺度」や「支払手段」としても利用されるようになる。国家が介入してくるのはこの時点だ。
国家は貨幣鋳造所をつくり、金属貨幣に王の刻印を押すようになる。それによって、貨幣には保証が与えられ、より受けとりやすいものになった。最初、リュディアやイオニア(ともに小アジア)でつくられた鋳貨はたちまちのうちにギリシア世界に広がっていった。
初期の金属貨幣は比較的大型のもので、これは貨幣が価値保蔵物だったことを示している。ところが紀元前5世紀ごろに支払手段として小型貨幣がつくられるようになり、さらに代用貨幣として青銅貨幣が登場すると、貨幣はより使用しやすくなった。ギリシアは次第に貨幣経済社会へと移行する。
金属貨幣はギリシア世界の外部にも広がっていく。ペルシアからインド、バルカン諸国、さらにローマへと。ケルト人も貨幣を鋳造するようになった。商業が衰退すると、一時的に貨幣が使われなくなることもあったが、「商業活動が行われるかぎり、どこにおいても貨幣は恒常的に使用されてきた」と、ヒックスはいう。
そして、貨幣は中世都市国家後の「中期の局面」(近世)においても継承された。王は貨幣を放棄しなかった。貨幣の鋳造によって、直接、間接に利益を得ることができたためでもある。加えて、貨幣を媒介とする交易は王にも多くの財貨をもたらしていた。
都市国家のもうひとつの遺産が「法」だった、とヒックスは説明する。それは中国や日本におけるような商業を規制する法ではなく、むしろ商業を促進し、商人の権利を守る都市国家の法にほかならなかった。
ローマ法は古代ギリシアでつくられた「商人法」を受け入れ、発展させた。ローマ帝国は貨幣による評価と支払いに依存していた。ローマ帝国が滅亡したあと、貨幣経済は収縮するが、完全に消えることはなく、やがて新しい都市国家の興隆がふたたび貨幣経済を盛り返し、同時に「商人法」も維持されることになる。
都市国家が衰退し、「中期の局面」すなわち近世の領域国家の時代にいたっても、貨幣制度と法律制度は継承され、発展することになる。
こうして貨幣と「商人法」を論じたあと、ヒックスが強調するのが、都市国家時代につくられた「信用」制度の継承である。
ルネサンス時代、貨幣は信用および金融と結びつき、その性格を変えようとしていた。
古代ギリシア人とローマ人は利子を取ることに良心のとがを感じなかったが、キリスト教は利子をとることを罪悪と考えていた。しかし、いかなる時代も商業取引がおのずから金融取引に発展していくことは避けられなかった。
当初、商品の取引は「代理人」に委託されていた。貨幣が普及するようになると、現物を委託するよりも、貨幣を貸し付けるほうが取引としてはずっと楽になる。
貨幣の貸付によって債務者は負担を負う。債権者に元金を返済するだけではなく、利子も支払わなければならないからである。債権者は債務不履行の危険度が大きければ大きいほど、高い利子を求める。これはとうぜんのことだった。
ギリシア・ローマ時代には、借金を払えない債務者は、制裁を受け、しばしば「債務奴隷」の地位におとされていた。だが、こうした残酷な制度に代わって、次第に貸付にたいして担保を求める慣習が定着するようになる。この場合、債務者は債権者にたいし、負債以上の価値を持つ物件を預託し、借金返済後にその物件を返却してもらうことになる。
しかし、担保物件つきの貸付が成立する場合はごく限られている。そこで、物件を預託しなくても、抵当権を設定するだけで借り入れができる方式が生まれる。この場合は、貸付の担保は債権者の手にわたらず、債務者の手元に残され、債務不履行の場合にかぎって、債権者が担保を手に入れることになる。
担保貸付にたいして無担保貸付も存在した。無担保貸付は貸し手にとって危険度が高いため、ふつうは高利がともなう。しかし、商人仲間のあいだでは、借り手の信用に応じて、質物や担保をとらずに、低い利子で貸付がなされる場合もあった。商人経済の発展にとっては、こうした信用にもとづく低利子の融資が大きな役割を果たした、とヒックスは指摘する。
だが、信用を確保するには、相手の経営状態を知っているだけではじゅうぶんではない。そこで信用を拡大するため、保証人や金融仲介人が求められるようになる。銀行が登場するのは、こうした金融仲介を専業とする者のなかからだ。そのころキリスト教においても、ある程度の利子を認める考え方が定着するようになっていた。
危険分散を可能にするには、加えて保険の導入が求められた。中世に都市国家を営んでいたイタリア人は、保険契約に精通していたことで知られる。14世紀にはすでに海上保険が存在していたし、万一の事態に備えるためのさまざまな方策も考え抜かれていた。
「中期の局面」としての近世は、こうした金融制度や保険制度を都市国家の経験から受け継ぐことになる。さらに加えて、証券市場や有限責任会社(株式会社)制度が確立されるようになると、「中期の局面」は終了し、「近代の局面」の展開がはじまる、というのがヒックスの基本的な見取図だといってよい。
だが、先走るのはやめておこう。近代を語るには、その前提として、貨幣(金融)に加えて、国家(財政)や農業、労働の分野への「市場の浸透」を論じなくてはならないからである。
都市国家をめぐって──ヒックス『経済史の理論』を読む(3) [商品世界論ノート]

ここで都市国家の経済理論を述べてみたい、とヒックスはいう。モデルとされているのは、古代のアテナイだけではなく、中世のヴェネツィアやフィレンツェ、ジェノヴァなどだといってよい。
都市国家の中核は、対外商業に従事する商人の団体である。商人たちは都市国家の外にある地域と取引をし、商人経済が都市国家を支えている。その意味で、都市国家はひとつの商業センターになっている。
たとえばAという商品をもつA地域とBという商品をもつB地域があるとする。A地域は商品Bをほしがっており、B地域は商品Aをほしがっている。すると、都市国家の商人たちはA地域とB地域の仲立ちをすることによって利益を得、同時にA地域もB地域もみずからが持たない商品を手に入れることで潤うことになる。ただし商品A、商品Bが貢納によるものであるとすれば、利益を得るのは領民全体ではなく領主にとどまる可能性が強い。
だが、通常、商業が拡大すると、その利幅は少なくなっていく。商人の利潤率は取引量に比して下落し、商業の拡大テンポも鈍っていく。そこで商人は新しい商品や新しい販路を求めて、商業の多様化をはかることを迫られる。
一口に商業の多様化といっても、それは楽なことではない。そこで、都市国家が重要性を発揮することになる。都市国家は商人の取引に安全保障を与え、商業の多様化という困難な課題解決を後押しすることになる、とヒックスは書いている。
商業が多様化するとしても、その拡大にはおのずから限界がある。だが、それにいたるまでに多くの余地が残されている。
取引量が拡大するにつれて、組織が合理化され、その結果、取引費用が減少し、それによって商人の利益はむしろ増えるかもしれない。都市国家の拡大が全体の利益の拡大をもたらす可能性もある。商人数の増大は競争の激化をもたらすが、そのいっぽうで商業活動に一種の棲み分けをもたらし、商業をより効率的にすることも考えられる。
商人経済の拡大と充実は危険の減少にもつながる。商業活動のありかたについての知識が深まり、無知に起因する損害を減らすからだ。取引が増えるにつれて、財産や契約を保護する制度も確立するようになり、さまざまな取り決めがなされるようになる。それが可能になるのは商業センターとしての都市国家が存在するからだ、とヒックスは断言する。
また都市国家には海外に交易の根拠地を設け、植民地をつくるという強い誘因が存在することをヒックスは強調している。フェニキア人しかり、古代のギリシア人しかり、中世のイタリア人も地中海や黒海に植民都市をつくった。
植民地がつくられるとなると、それは先住民や敵対者から守られなくてはならない。そのさい往々にして武力が発動されることになる。都市国家による植民地化は近代国家による植民地化とは大きく異なるが、それでも都市国家が植民地形成の初期モデルとなったことはまちがいない、とヒックスは考えている。
都市国家は商業経済と植民地化によって、内的にも外的にも拡大していく。競争はより激化し、利潤率は下がっていくものの、組織はより効率的になるために、全体としての利益は拡大する方向にある。ただし、それを阻害するものがあるとすれば、地理上の新しい地域で、商品の新しい供給源が開発されたときである、とヒックスはいう(たとえばアメリカ新大陸の発見やインド航路の開発を考えてみよう)。
だが、その前に商業の成長が限界に達する。
〈もし商人が既存の市場においてもっと効率的に営業するための新しい組織を発見することに失敗したり、新しい市場を発見したりすることに失敗すれば、価格がかれらにとって不利な方向に動いていくことに気付くだろう。というよりはむしろ、取引量を拡大しようとすれば、価格がかれらに不利な方向に動いていくという状況に達するであろう。〉
もはや組織の効率化もできなくなり、新たな市場も開拓できなくなったときに、むりやり商品の販売量を増やそうとしても、値崩れをおこし、かえって利潤は減少してしまうという状況におちいってしまうのだ。
それでも都市国家が依然として商業の拡大をめざすなら、都市国家どうしの戦争が勃発する。都市国家どうしの戦争がおこりやすいのは、「まさにこの時点、すなわち商業の成長が限界に近づきはじめる時」である、とヒックスはいう。古代ギリシアのペロポネソス戦争や、1400年ごろのジェノヴァとヴェネツィアの戦争の背景には、こうした商業的要因がひそんでいるという。
しかし、都市国家どうしが協定を結んで、地域内で棲み分けるようになることも考えられないではない。すると、都市国家の指令のもとで、「商人は慣習的権利・義務の体系の中において、一つの地位を受け入れるようになっていく」。
商業の拡大が停止したといっても、商業は衰退したわけではない。利潤水準は依然として高いが、利潤を拡大のために再投資しないことが、高利潤を維持するための条件となる。すると、市場の喧噪に代わって秩序がもたらされる時期がやってくる、とヒックスはいう。
〈拡大を特徴づけた活気は直ちには失われないであろうが、いずれ活気は商業の革新から去って他に向かわざるをえない。だが、安全の保障と富があるので、他の分野に転ずることが可能である。商業の拡大は知的刺激を与えていたが、それがもはや知的活力の対象となりえない時点にたちいたると、芸術は芸術のために、学問は学問のために追究することが可能となる。〉
こうしてアテナイには芸術と学問が興隆し、フィレンツェやヴェネツィアにはルネサンスがもたらされた。「しかし、果実が熟れるときは常に秋なのである」。都市国家はその商業活力を失ったときに、最後の花を開いたあと、危機に陥っていくことになる。
市場の発生と発展──ヒックス『経済史の理論』を読む(2) [商品世界論ノート]

市場はどのようにして発生するのだろうか。王国が存在し、そこに慣習的な農業経済がいとなまれているとする。そこに市場が誕生するとすれば、それはどのような経過をたどるか。ヒックスが想定するのは、そのような原初的な場面である。
市場発生の前提となるのは、商業の専門化である。もちろん、人類の初期段階から交易は存在し、贈与のやりとりはあった。けれども、それは商業ではない。商人の登場こそが、市場発生のカギになるはずだ。
そして、商人が商人になるのは、商品を手に入れるからである。だが、商人が山賊や海賊だったわけではない。
市場が日常化する前には市(いち)があったと考えられる。それは祭の場からはじまり、やがて定期的に開かれる市となる。そこにやってくるのは農民たちだった。
その農民のなかで豊かな者、あるいは商品(財貨)を多くもつ者が、商人に転化するというのが、商人の発生で考えられるひとつのルートである。そして、すぐに売れなくても、耐久的な商品を安全に保管し、いつでも売れるようにするところから、商店が生まれる。
やがて、その商品は市にやってくる購買者の要望に合わせて加工されるようになるだろう。そうしているうちに市は発達し、商人の専門化もさらに進むようになる。
市が時間的に連続し、空間的にも広がり、多くの商人が登場するようになると、市場が誕生する。
これがひとつのルートだ。
だが、市場の発生には、もうひとつの道筋が考えられる、とヒックスはいう。
それは王の経済から市場が発生する場合である。
強大な王は近隣の族長から使節を受け入れ、貢ぎものを受けとる。それによって王は近隣地域との交誼を認め、返礼品として贈りものを渡す。
そうした交易を実際に担うのは王の廷臣だ。だが、共同体間の対外交易(商品のやりとり)が定着するにつれて、廷臣は独立した商人へと転化する。廷臣が交易の報酬として、ある程度の利益を受けとる(そのためには商品が売られなくてはならない)ようになると、半ば独立した商人が生まれる。
王の経済は対外交易にとどまらない。王室経済は貢租にもとづき現物で収められる、しかし、王室を支える者は数多くいる。多くの廷臣や軍隊は欠かせない。王室は専門技術をもつ数多くの手工業者や奴隷もかかえている。手工業者は王室だけではなく、次第に市場とのかかわりを深くしていくだろう。
こうして王の経済のもとでも、対外商業と国内商業が合体して、相互に強めあい、市場化が促進されていくことになる。
ヒックスはこう書いている。
〈メンフィスやテーベ[いずれもエジプト]、ニネヴェやニルムードやバビロン[いずれもメソポタミア]、長安や洛陽[いずれも中国]などの諸都市は、なによりもまず拡大された宮廷であって、王の従臣、そのまた従臣、さらにそのまた従臣が居住している点を十分考えるべきである。しかしながら、これらの都市に市場があったことについては疑いがない。〉
こうして、これまでの慣習型経済、指令型経済のなかから、商人的経済が発生し、次第に独自の領域を占めることになる。
商人経済は指令経済とちがって、上からの絶対命令的な計画にもとづくものではない。あくまでも個人主義的なものだ。だが、商人経済はけっして無秩序なものではなく、組織だっている、とヒックスはいう。
市場は一種の集会であり、市場が維持されるには一定の秩序が求められる。そのため、政府の保護が必要になってくるだろうとも書いている。
暴力にたいして財産が保護されなければならないのはいうまでもない。だが、市場において、それ以上にだいじなのは、商人の所有権が確認されることで、それを抜きにしては買い手との商品取引は成り立たない。
売買契約が成立すると、買い手にたいし商品の所有権の移転が約束される。こうした契約は保護されなければならない。万一、不測の事態が生じた場合にも、それにどう対処するかが双方で合意されているなら、交易は持続し、促進されることになる。
商人と非商人のあいだならともかく、商人と商人のあいだでは、こうした合意が成立しやすい。しかし、商人間でも商品の取引については、誤解や詐欺がおこらないとも限らない。その場合には紛争が生じるが、契約を保証するためには法的な諸制度が必要になってくる。
商人経済が定着するには財産の保護と契約の保護がなされなければならない。だが、伝統社会においてはそれは期待できなかった、とヒックスは書いている。
とはいえ、商人どうしで、ある程度の約束は可能だったし、また、そのために商人どうしが結束することもできた。さらに、第三者の商人によって契約のなかに仲裁条項を含める場合もあったという。
だが、最終的には国家による法体系の確立が求められた。その点で、市場は国家と無縁に発生したわけではなく、国家による承認や保証とけっして切り離せなかったというのが、ヒックスの見解である。
国家と市場との関係には紆余曲折があった。たとえばといって、ここでヒックスが例に挙げるのが、中国の明朝初期(15世紀)における海外交易の拡張であり、日本の徳川政権における国内商業の発達である。いずれも国家の保護なしには、その隆盛はありえなかった。
だが、そうした商業は持続的にみずからを拡大していく成長力をもっていなかった。唯一の例外は、国家の支配者がみずから深く商業、とりわけ対外商業とかかわっている場合だけだ、とヒックスはいう。
その例外がヨーロッパの「都市国家」だった。
「ヨーロッパ文明が都市国家局面を通過したという事実は、ヨーロッパの歴史とアジアの歴史の相違を解く重要な鍵である」と、ヒックスは論じる。
ヨーロッパの都市国家をはぐくんだのは地中海である。その代表例が古代ギリシアの都市国家だが、中世イタリアの都市国家とルネサンスがそれを再現することになった。そして、地中海における商業の繁栄は、北海、バルト海沿岸のハンザ都市や、ドイツと低地地方の都市国家(とりわけアムステルダム)の繁栄へとつながっていく。
ヨーロッパに生まれた典型的な都市国家こそが、商業を発達させる原動力になった、とヒックスはとらえている。
ヒックス『経済史の理論』を読む(1) [商品世界論ノート]

ジョン・リチャード・ヒックス(1904〜89)は『価値と資本』、『資本と成長』などの著作で知られる理論経済学の巨匠だ。その巨匠が1969年に経済史に関する本書を出版したことに、経済学者のあいだでは当時、驚きの声が広がったという。ヒックスはそれまでの理論経済学の業績にたいして、1972年にノーベル経済学賞を受賞するが、本人はむしろ『経済史の理論』のほうを評価してほしかったと語っている。
訳者解説によると、本書は市場社会の発達に主軸を置いて、全世界にわたる人類史全体を取り扱った野心作だという。経済史の事実をこと細かに論じた歴史書ではない。タイトルに「理論」──「セオリー」というほうが、かえってイメージしやすいか──とあるように、あくまでも経済制度(システム)の発展に重点が置かれている。
これもツンドク本になっていた。もうあまり先がないから、そのまま処分してもいいのだが、それではちょっと心残りだ。本棚の整理と頭の体操を兼ねて、パラパラとページをめくってみる。読んでも、すぐ中身を忘れてしまうから、例によってメモをとることにした。
最初に強調されるのは、これが特殊な状況や個人の行動を扱った歴史ではなく、あくまでも一般史だということである。歴史上、統計的に扱える一般性をもつ現象に光をあてること、さらに社会の経済的状態について、その標準的な発展を記述すること、世界経済史をひとつの趨勢として取りあげることが強調されている。とりわけ重視されるのが資本主義の勃興に先立つ「市場の勃興」であり、それがいつどのように生じたかである。さらにそれが「工業主義」、すなわち産業革命にいたり、その後、市場にたいする否定的反応(すなわち社会主義)が生じるまでが論じられる。
経済学者は市場の存在を当たり前と考えがちで、市場をできるだけ完全なものと想定する傾向が強かったと述べている。その後、ソ連の中央計画経済や戦時の統制経済を研究しなければならなくなったことから、非市場経済組織の研究がはじまる。しかし、完全な市場経済が存在しないように、完全な中央計画経済が存在しないこともあきらかだという。ヒックスが本書を出版した1969年は冷戦時代のさなかで、ふたつの政治経済体制が存在していたことを頭に入れておく必要があるだろう。
とはいえ、かれが最初に取りあげるのは、歴史の流れからいえば、部族国家をはじまりとして、古代から中世にいたる時代である。
この時代においても、もちろん商品は存在し、市場もなかったわけではない。しかし、商品や市場はまだ社会の中心となっていたわけではないし、商品世界は成立していない。
ここで、かれは大なたで割ったように大胆なコンセプトを持ちだす。非市場経済は「慣習経済」と「指令経済」のふたつのタイプによって成り立っていたというのだ。そして、それはもはや消え去ったわけではなく、いまも残っているという。
出発点となるのは原始的非市場経済である。その経済の特徴は「慣習経済」で、個人の役割は伝統によって定められ、その共同体は長期間、ほかから妨げられることなく存続していた。
ところが、その共同体が危機に面して軍事的性格をもたざるをえないことがある。このとき共同体は「慣習経済」から「指令経済」へと移行し、軍事的専制主義に向かって直進する。そのきっかけとなる危機は人工の圧力による場合も考えられるし、他部族の侵入による場合も考えられる。
いずれにせよ、軍事的専制主義は古代帝国への道を切り開くことになるだろう。めざすのは領土の拡張であり、奴隷を基盤とする指令経済である。
だが、ほとんど純粋な指令経済は、非常事態を別として長くは存続しない。いずれは軍政が民政に移行し、形式上はともかく、中央権力は権力としての実態を失ってしまう。「封建制」はそうした状況をさす、とヒックスはとらえている。
封建制のもとでは、将軍たちが領国の支配者に任じられ、さらに司令官が一地区の支配者となる。かれらは中央にたいして忠誠の感情をもっているとしても、中央の権力は非常に制限されたものになってしまう。
指令経済であっても、慣習経済であっても、支配階級を養うのが貢納であることはまちがいない。それらは当初、強制されるようにみえるかもしれないが、次第に慣習化されていく。
王のもとでの軍事的専制は封建制に移行しやすい。王国が大小の領国からなる場合は、いったん中央政府に税を集め、それを地方に分散するよりも、地方領主が税を集め、残りを中央に収めるほうが合理的だからである。すると、純粋な封建制のもとでは、中央政府は長期的には衰退していく危険性にさらされることになる。
そこで中央権力は権力の浸食に立ち向かおうとする。その手段となったのが官僚制だ、とヒックスはいう。
官僚を統制するには、官僚への監察制度と昇進制度、さらには新人登用制度が必要になってくる。早い段階で、こうした官僚制度を活用した文明のひとつが古代エジプトだった。さらに官僚制が成功した国家としては、中国を挙げることができる。
それでも封建制への移行の芽は常にひそんでいた。官職は世襲になりがちで、加えて地方貴族の出現が中央の権力をおびやかす恐れがあった。
ヒックスは「非市場経済」を「慣習経済」と「指令経済」、さらにその混合型としてとらえている。古代帝国の官僚制のもとでは「指令経済」の要素が強い。しかし、「指令経済」は世襲的な貴族制や伝統的なカースト制の引力によって、「慣習経済」に引き戻される傾向をもっている。
しかし、「慣習経済」であっても「指令経済」であっても、「非市場経済」には共通するものがある。つまり、貢納にもとづいていることだ。
農民は「承認された権威」にたいして貢租を支払う。「承認された権威」は政治的権威とはかぎらない。宗教的権威の場合もある。
帝国の形態をとる指令経済のもとでは貢租は中央権力に高度に集中され、封建制のもとでは大小さまざまの領主が貢租を収めることになる。
支配者はこうした貢租を軍隊と官僚を養うためだけに用いるわけではない。非常事態が去れば、みずからの権威を誇示するための豪奢な消費のためにも用いる。それは領民の心をつかむ消費ともなりうる。分業が生まれるのは王の宮廷からである。
非市場経済は「貢納経済」としてとらえることができる。貢納経済は市場経済とは対照的なもので、経済のひとつの本来的な形態である。貢納経済は市場に先行する。言い換えれば、国家は市場に先行するということだ。
市場経済は貢納経済を背景として生じる。たが、市場の成立後も貢納経済は残存し、自由放任主義の全盛期においても、けっして消滅することはなかった。租税が消滅することはなかったからである。
おもしろいことにヒックスは、中央計画経済からなるソ連型の社会主義を、一種の貢納経済とみていた。国民の余剰は企業と政府に分散されるのではなく、中央政府に集中されるからである。
だが、そのことはともかくとして、いまは次の章、「市場の勃興」、「都市国家と植民地」に焦点を移すことにしよう。非市場経済がどのように市場経済に移行したかが論じられる。
『儀礼としての消費』を読む(5) [商品世界論ノート]

日常生活を営むうえで必須となる、労力を含む財が貨幣によってしか手に入らない世界を商品世界と名づけるならば、そうした商品世界が生まれたのは、19世紀以降といっていいだろう。もちろん、それ以前にも貨幣は存在し、貨幣が存在するところには商品もあったから、歴史的にみると商品世界の発生ははるか古代にさかのぼる。
だが、それが近代の商品世界と異なるのは、近代以前においては貨幣と商品があくまでも非日常的で特別の授与物であり、日常生活からは相対的に切り離されていた点にある。しかし、近代になるにしたがって、貨幣と商品は次第に日常生活に浸透し、いまや貨幣と商品がなければ、日常生活が営めない時代となった。生産と消費が分離され、貨幣によってしか媒介されないのが商品世界の特徴だともいえる。
著者のメアリー・ダグラスはここで野生(未開)社会と商品世界の比較をもちだしている。
カリフォルニア州北部太平洋岸には先住民のユロック族がいる。1920年代にまとめられたその民族誌によると、かれらは村落集団をつくり、漁と狩りで暮らし、貝殻貨幣による財のやりとりをおこなっていた。統治機構はなく首長もいない。親類や仲間で暮らし、豊かな人も貧しい人もいる。貨幣がともなうのは結婚のときである。殺人や姦通にたいする代償も貨幣で支払われる。儀式では高い価値をもつ財が見せびらかされるように用いられる。ユロック族の人口は5つの村を合わせて600人ほどだ(現在はもう少し増えている)。
ユロック族の日々の生活は漁や狩猟、採集による食べ物、そのための道具、さらには医療、住まいの整備などによって営まれる。これらはみずからの努力に加えて、親戚や仲間との協力によって確保される。貨幣が支払われるとすれば医療ぐらいのものである。
ところが、宝物となると話は別になる。黒曜石の首飾り、珍しい毛皮、色鮮やかな羽根、ボートなど、これらは貝殻貨幣によってしか取引されない。そのため、人びとはこぞって貝殻貨幣を蓄積していた。
財は日常的な財と非日常的な財に分かれている。そして、使われる頻度は少ないけれど、より立派な非日常的な財をもつ者こそが、その社会での影響力をもつ存在とみなされたのだ。ユロック族は自由な社会をつくっていたが、それでも富は均等に分配されていたわけではない。宝物をもつ金持ちは最初から優位な立場にあった、と著者はいう。
ナイジェリアのティブ族は長老たちによって支配されていた。長老たちの最大の役割は、村を監督することと結婚を取り決めることだった。
ここでの財も、家事用の財と威信にかかわる財にわかれていた。
農地で生産されるヤムイモやシコクビエ、モロコシ、飼われているヤギやヒツジ、犬、鶏、それに、ものを運んだり貯めたりする籠や壺、鍬などの道具は、家事用の財である。これにたいし、金属の棒や布、銃、奴隷などは威信を示す財となった。こうした威信財は戦争か交易によってしか手に入らず、若者たちはこうした宝を手に入れることで名声を得、長老へとのしあがった。
日常財と威信財とのあいだに交換関係は存在しない。威信財をもつ者は政治的に優位な立場を確保し、村の情報を制御し、女たちを統制することができた。ティブ族のあいだでは、婚姻は商取引とは無縁で、嫁資などというものは軽蔑されていた。ヨーロッパから貨幣が到来するまでは、こうした社会システムが維持されていたという。
未開社会では、流通(商品取引)が制限されている。ナイジェリアのハウサ族はイスラム教徒で、女性は隔離状態に置かれ、外での仕事といえば、食事にかかわるものくらいだった。女性たちは輸入されたカラフルな壺や椀などを熱狂的に収集することがある。だが、それらは日常品というのではなく、宝として手元にとどめられ、自分の娘や養女が結婚するときに分け与えられる。こうした宝は、女性たちにとっての威信財なのである。
宝は社会的信用ともつながっている。宝の収集は飽くことを知らなかった。しかも、それらは最新の流行や高度の専門化をあらわすもので、いわばブランド品でなければならなかった。
ハウサ族の女性たちが収拾したのはチェコスロバキア製の釉薬のかかった壺に限られていた。トロブリアンド島のクラ交易で受け入れられる品目も、赤い貝殻の数珠と白い貝殻の腕輪だけだった。こうして未開社会においても、消費は単に欲求の充足をめざすだけでなく、威信の発揮と結びついていたことがわかる、と著者はいう。
ここでの目的は未開社会も現代社会も人の消費行動は変わらないことを示すことになる。現代社会を批判する視座として未開社会をもちだしているわけではない点は理解しておく必要があるだろう。
そのため、部族社会においても消費の格差があり、排除の力がはたらいていることを指摘したあと、著者はそれは現代の社会、国際関係でも同じだと述べることになる。
現在、産業活動は3つの部門に分けられるのが通例になっている。第1次産業は農業、林業、漁業、第2次産業は鉱業、製造業、建設業、第3次産業は商業、運輸、金融、サービス業というように。
経済発展にともない、労働人口は第1次産業部門から第2次、第3次産業部門へと移行し、現在、先進国では第3次部門が最大の雇用割合を占めるようになっている。
著者は産業部門のアナロジーから、家計も3つの水準にわけられるという定式を導きだす。
第1の水準は食べることに追われ、それがやっとの段階。第2の水準は労働節約的な用具が導入され、家計に新しい技術が備わった段階。第3の水準は、掃除にしろ料理にしろ家での仕事がさまざまなサービスに委ねられ、家計の消費が衣食住だけではなく、教育やレジャー、保険、金融にまで広がっている段階だ。
第2次世界大戦前と後をくらべると、イギリスでも労働者階級の実質所得は高くなった。それでも、所得格差はなくなっていないし、労働人口の大きな割合が低賃金労働に甘んじている。さらに、貧富の格差は所得や富の格差にとどまらず、いわば生活様式そのもののちがいとなってあらわれている。
ひとつの国のなかに社会階級が厳然と存在するように、国際関係においても豊かな国と貧しい国の格差が存在する。その格差は経済の活動規模の大きさにもとづく。
著者はいう。
〈最も豊かな国々は、輸出品の販路も生産パターンも最も多様化されており、最大のサーヴィス部門(金融・研究・教育・管理などを含む)を持っている。最も貧しい国々は、ほとんどの場合、たった一つの生産物、それもたいていは効率の低い農業に、全エネルギーを注ぎ込んでいる。〉
開発途上国では農業部門の生産性が低く、そのため人口の大部分が土地に縛りつけられ、非農業部門の成長する余地が残されていない。そのため、先進国と開発途上国とのギャップはますます広がりつづける。それは一国内における豊かな世帯と貧しい世帯の関係と同じだという。
消費者は個人として財を選択するわけではない。みずからの属する階層にふさわしく、みずからが置かれた社会関係のなかで財を選択する。貧困の問題は、生活者が孤立し、そうした社会関係と情報システムからさえも切り離されてしまうことにある、と著者は考えている。
ここで、著者は消費が産業連関によって広がっていくことを示そうとする。
産業が連関することはよく知られている。たとえばマレーシアでは1次産品(ゴム、スズ、パーム油)の輸出が軽工業を生みだす要因となった。それと同じように、新しい技術が産業連関を通じて、新たな消費を生みだしていく、と著者は考える。
1948年から1970年にかけ、イギリスでは電力の消費者が増え、電力消費量が増えた。これは、都市人口の増大と新技術の普及(テレビ、冷蔵庫、掃除機、洗濯機、エアコンなど)にともなう現象である。これは技術と消費の連関が実現されたケースだという。
社会と消費の連関もみられる。旅行や電話、レジャー、社交、さまざまな行事のための支出は、技術というよりも、世間とのかかわりと関係している。社会的な消費は、家族内から世代間、地域へと広がっていく。とはいえ、その消費には、社会階級のランクによるちがいがみられる。
さらに社会と消費の連関でいえば、移住が社会的孤立をもたらす場合もあるけれども、血縁集団から切り離されて、新たな地域共同体に暮らすことが、別の利点をもたらす場合も多いという。よりよい所得と生活条件が与えられる地域で暮らせるようになるなら、まちがいなく消費能力は向上し、物質的生活水準が向上する。逆に地域に閉じこもってしまうなら、強い集団的アイデンティティから抜けだすことができず、低い消費水準に甘んじてしまうケースもある。
最後に情報と消費の連関がある。
労働者階級のあいだでも、パブの仲間どうしのつき合いが情報を得る重要な手段となっている。得られた情報のもたらす報酬が大きいほど、それを得るためにいっそう多くの時間と資源を支出することが正当化される。
とはいえ、概して規模の利益を得ることができるのは、いちばん有利な立場にある者だ。専門的情報への接近は、社会階級のランクによって異なっており、ここには一種の障壁が築かれていることを認めざるをえない、と著者はいう。
ハイランクの社会階級の消費が、より大きな利益をもたらす情報と結びついているという話は腹立たしいが、これも商品世界の現実なのだろう。
著者はこう書いている。
開発途上国においては、消費階級ははっきりと3つの層に分かれる。まず大地主・支配者階級があり、次に農民がつづき、最後に土地のない労働者となる。これらの階級がみずからの立場に応じて、財(商品)のセットを使っている。
これにたいし、先進国の場合は社会構造の区分けがむずかしく、もっと漠然としている。職業と所得に応じたグループ分けはある程度有効だが、富そのものは評価しにくく、職業分類もあてにならない。
ここで著者は先進国の消費パターンを探るために、商品を3つのセットに分類する。(1)第1次生産物のセット、(2)技術的なセット、(3)情報関係のセット。(1)が食品、(2)が耐久消費財、(3)が教育や教養、社交などに代表されることはいうまでもない。
低レベルの消費階層では、支出の多くが食品に向けられ、中レベルでは食品の割合が相対的に下がって、耐久消費財が購入され、高レベルでは食品の割合がさらに下がって、より値段の高い耐久消費財が購入され、情報関係の商品により関心が向けられることがわかる。
低レベルと高レベルの消費のちがいは、あきらかに所得に制約されている。とはいえ、すべての商品(サービス)がすべての人に開かれているのが身分制社会とのちがいだ。だれもが医者にかかったり、ゴルフをしたり、スポーツを見学したり、コンサートを楽しんだりすることができるからである。
とはいえ、所得は仕事内容や職業と結びついており、所得の高い階層はより高度な消費活動を実現する。消費にはランクづけされたヒエラルキーがある。彼らは人より豊かであることによって需要をリードし、活動に価値を与える、と著者はいう。つまり、消費階級は厳然と存在するといってよい。
消費階級は職業にほぼ対応する。職業としては、管理・経営職、専門・技術職、教育者がほとんどトップの階級を占める。事務職や営業職がこれにつづき、熟練労働者、肉体労働者、無職者の順に階級が形成される。
ここで著者は自動車と電話、銀行口座を財のサンプルとして持ちだし、1973年段階の消費階級のヒエラルキーを分類する。高い階級は自動車も電話も銀行口座ももっている。これにたいし、階級が低くなるにつれて、そうしたセットをもたない家計が増えてくる。ここにみられる消費パターンのひらきをみても、消費にもとづく階級構造が存在することが実証できる、と著者はいう。
トップの消費階級には、低い消費階級にたいする強い排他性がみられる。所得の大きさは、食べ物から服装、住まい、家具、装飾にいたるすみずみにまで反映される。しかし、その排他性は先端的な消費をリードするもので、下層階級にとっても憧れの的となり、それが大衆文化に変容し、次第に広がっていくことも、著者は認めている。
さらに著者は、専門職階級のほとんどが電話をもつのに、労働者階級の多くが電話をもたない(いっぽうテレビはどの階級ももっている)のはなぜかという興味深い問いを発し、「貧しい人はいつでも時間を持ち合わせているけれども、それを使ってなすべきことは豊かな人より少ない」という結論に達している。電話はコミュニケーション・ツールだが(その点、スマホは遊びの道具として進化した)、労働者階級の多くはそうしたものを無駄とみているというわけだ。こうした指摘をはたしてどうとらえるべきだろうか。いずれにしても電話(あるいはスマホ)という商品が消費学の大きな対象となりうることを示唆している点はおもしろい。
貧しい人びとは、その生活条件によって長期的な視野をもつことができないとも書いている。時間がないわけではなく、時間は浪費されているというのだ。これにたいし、カネのある有閑階級は、多くの空き時間を必死に埋めようと、熱に浮かされたように突進しているという。このように社会階級によって、時間の過ごし方は大いに異なる。
官僚組織にせよ、第3次産業にせよ、その管理と財務には費用節約的な技術革新の余地がたぶんに残されている。
芸術も第3次産業の部門である。ここに入り込むには、名前の定まった人びとの列に挑戦し、新しいアートに置き換えなければならない。新たな流行を作りだすためには、競り合いに勝って、ゲームをスピードアップする必要がある。そうした競り合いのなかで、トップ階級と最下位階級とのあいだのランクはますます広がっていくことになる。
消費には熱力学の法則が成り立ち、熱源のエネルギーがいくつもの仕切りを突破して徐々に広がっていく、というたとえも持ちだされている。その広がりは富の分布に応じながら、少しずつ世界を変容させていく。
その熱源となるのは変動しつづける技術である、と著者はいう。さらに、そこには資源の要素を組み込まなければならない。
われわれは社会階級の存在を意識しなければならない。豊かな特権階級に注目するだけで、貧しい人びとがどのように生活しているかを知らなければ、厳密な消費理論など築けるわけがない、と著者は述べている。
ここには商品世界にたいする鋭い批判はみられない。商品世界の生みだすさまざまな軋轢、おカネでは解決できない問題の指摘、さらに脱商品世界に向けての構想が述べられているわけでもない。それでも、これまで人類が普遍的に築いてきた、財(商品)の世界の構造を冷静にとらえることの重要性を本書は指摘しているのである。
商品世界の膨張──『儀礼としての消費』を読む(4) [商品世界論ノート]

著者はこう書いている。
〈人間は社会的存在である。財の物理的性質だけを見ていても、決して需要を説明することはできない。人間が財を必要とするのは、他の人々とコミュニケートするためであり、自分のまわりで起きていることに意味を付与するためである。〉
これが人はなぜ商品(財)を求めるのか、についての著者の回答である。そういわれても、すっきりと納得するのはむずかしいだろう。
さて、これをどう理解すればよいか。
コミュニケートとは交換、連絡、意思疎通、拝領などを意味する。商品が交換によって得られることはまちがいない。それは単なる財の移動にとどまらない。たがいに何かをもらいあうのである。
その何かとは大きくみれば文化だといってもよい。本にしても机にしてもパソコンにしても、それらの商品を得るには、他者とコミュニケートしなければならず、その結果として、人は文化を獲得し、自分のまわりで起きていることを認識することができる。
さらに著者は、商品世界においては、情報をコントロールすることがだいじであって、このコントロールを失うと、商品世界から脱落し、逆にコントロールを強めれば強めるほど、商品世界での大きな権力をもつことになるとも記している。
ここから、財のグルーピングが生じる。衣食住にかかわる財の集合は、社会階級ごとに区分される。露骨にいえば、上流階級はいい家に住み、いい衣装を身につけ、いい食事をとっているわけである。
だが、商品世界はずっと固定されているわけではない。常に新しい商品が生まれ、それが必需品となり、文化を変動させていく。はじめ新商品にたいする需要は低いが、それが全人口に広がるにつれて、需要曲線は急勾配に上昇し、その後、徐々に平坦となり、飽和状態に達する。1960年ごろは、電話やテレビ、洗濯機、掃除機などがそうした商品だった。
そのいっぽうで、著者はすたれていく商品があることも指摘している。たとえば、純銀のシガレット・ケース、嗅ぎタバコ入れ、タバコのパイプ、甘いプディングの付け合わせにする干した果物や豆、等々。著者の郷愁がヴィクトリア朝時代に置かれていることが推察されて、おもしろいが、いずれにせよ、われわれのまわりでも、昭和レトロのように、さまざまな商品が消えていっているのである。
著者の挙げる例は、いささか古くさいが、イギリスではテレビが全階級に普及したのに(それでもテレビを長く見るのは労働者階級だという)、電話は労働者階級にはあまり普及していないとの指摘もある。電話は上流階級の必需品だが、労働者階級はさほど電話を必要としていなかったというわけである。いまのスマホ時代には、ちょっと考えられないエピソードだ。
テレビの流行を感染症モデルでとらえているのもおもしろい。ひとつの家庭がテレビを買うと、テレビにたいする免疫ができるが、それを知った別の家庭がこんどはテレビという病原体に感染するというのだ。それはテレビだけではないだろう。友達のサークルで、スマホがはやると、それがたちまち伝染するのと同じである。そこでは価格と所得の需要理論は、流行の感染に圧倒されてしまいそうになる。
〈産業化によって消費者の生活は複雑になってきている。物質的な財を見ても、実際、いろいろな物がいやが上にも多くなってきている。それでも、幸福のため、一貫した可知的な文化のために必要なマーキング作業の交換から落ちこぼれないようにしようと思ったら、今いる位置から後退しないよう、ますます頑張って走らねばならない。〉
要するに、いまの時代は産業化によって、どんどん新商品がつくられているために、消費者は世間でのつきあいに取り残されないよう、がんばって新商品をとりいれ、新たな文化に順応していかなければならないというわけである。
もちろん、消費を動かすのは新商品だけではない。多くの人の場合、結婚し、子どもが生まれ、老齢になるにつれ、ライフサイクルに応じて、消費の内容は変化していく。また万一のできごとに備える必要も高まっていくだろう。
近代産業社会では、生活水準は主な生活用品の所有水準によって決まってくる。所有する財は家族の規模によっても異なるし、個人それぞれの事情や趣味によっても異なる。商品の構成は、過去の所得の結果であり、未来に予測される所得の影響を受ける。さらに所有する商品が文化や流行の影響を受けることもいうまでもない。
こうして商品世界は変動していく。膨張していくといってもよい。産業社会の進展とともに次々と新たな商品が生まれるなかで、著者が注目している商品とサービスは「個人の体があく機会を増やすための財」である。
家庭電化製品はたしかに家庭での労働を軽減し、「体があく機会」を増やした。著者は、そうした新商品(「最新式の技術的補助器具、新発明の資本設備」)は、時間とエネルギーを軽減してくれるものだとして、それらは当初、贅沢品にとどまるかもしれないが、実質所得の上昇とともに、家庭のなかに受け入れられていくことになると論じている。
消費には周期性があり、それはひとつに世代交代が関係している、とも指摘している。
各家庭には、その所得に応じた衣食住の消費セットのようなものがある。たとえば食器は普段使いのものともてなし用のもの、ビール用のコップとワイン用のグラス、洋服はふだん着るものと外出用のもの、葬式や結婚式のもの、住の分野では部屋数やさまざまな家具、台所や風呂の設備、寝室のベッドなど枚挙にいとまがない。そうした衣食住の消費セットは、世代交代にともなう新しい家庭の創出と、そのライフサイクルに応じて再編されていくことになる。人口が増えるとGDPが増えるというのは、そういうことだ。
だが、著者はこんなふうにいう。
〈社会の成員は誰もが潜在的に人生において同じ機会を持っているのだが、その場合ですら、財の間の質の差は行事のランクや人々のランクのマーカーとなるのである。必需品の文化的側面は低評価かつ高頻度の行事における使用として明らかになり、他方、奢侈品は本質的に高評価かつ低頻度の行事において使用される傾向を持つ。〉
つまり、どの家庭も衣食住の消費セット(乗用車なども加えてよい)をもつが、そこにも所得に応じた階層性が忍びこむというわけである。必需品がふだん使いで、奢侈品が行事用の特別な品なのはまちがいないが、ハイランクの家庭にとっては、一般家庭の贅沢品がふだん使いの必需品になることも示唆されている。
さらに所得に応じて消費の質はより高度になっていく。大量生産品ではなく、特別注文の製品が選ばれることになる。
毎日、周期的にくり返される高頻度な仕事は、低ランクなものとみなされるがちだという知見も示されている。その代表的なものが家庭内労働だ。家を掃除し、ベッドを整え、衣類を洗濯し、食事を用意し、買い物に行くのは一日も欠かせない高頻度の仕事だ。これに乳幼児と病人の世話も加わると、女性の負担はかぎりなく重くなる。
そして、ここにも階層性がはたらく。「地位が高くなるにつれて周期の制約はゆるくなり、地位が低くなるにつれて周期の制約が強まる」。イギリスの貴族と使用人の関係を想像すればよいだろう。貴族は使用人によって高頻度の仕事から解放されるわけだ。
だが、「ライフスタイルの変化は、家計の過程における周期性のパターンの変化」をもたらす。使用人がいなくても、新たな商品群が投入されると、家庭内で必須とされる「周期性のパターン」労働が軽減されるのだ。
「今日の奢侈品の中で未来の必需品となるのは、性質として周期性を緩和する効果を持つ財の集合であろう」と著者は述べている。われわれはそうした効果をもつ財(商品)として、洗濯機や冷蔵庫、掃除機、食洗機などの電化製品、その他もろもろの用具を挙げることができるだろう。
商品が流行の波に乗り、やがてすたれていくのは、消費者のきまぐれによるのではなく、ライフスタイルの変化、代替商品の登場、価格の効果などによるものだ。しかし、著者が重視するのは消費の技術が「体があく」方向に作用することである。実質所得の上昇がそれを可能にするとも述べている。
「消費者は一定の財の所有者とみなされるのではなく、消費行動において一つの周期性のパターンを実行しているものとみなされなければならない」。著者のとらえ方では、貧困とは、この周期性のパターンが最低所得のもとで最悪の状況を示しているケースをいう。
消費の周期性とパターンは恒常所得と相関している。同一の社会階層内においては同一の消費水準が成立し、同一のつきあい関係が生まれる。
ある年齢になると、人はだいたい自分の所得がこれからどのくらいになるかがわかるようになる。人生の後半に向かって、消費水準をいっそう高めようとは思わなくなる。
ドイツの調査では、家庭の耐久財を所有する割合は、肉体労働者も公務員・専門職も同じだった。しかし、より所得の多い公務員・専門職は家の家具や内装におカネをかけていた。これは家を社交に使うことが多いためだという。
消費水準が社会階層によって異なるのは、所得のちがいもさることながら、同一階層内のコミュニケーションが存在するからである。
さて、こうした商品世界をどのように評価すればいいかが次の問題となってくる。
『儀礼としての消費』を読む(3) [商品世界論ノート]

この本が読みづらいのは内容もさることながら、翻訳のひどさが関係しているのかもしれない。加えて、ぼくの頭がわるいことをつけ加えれば、たちまち三拍子そろった投げだし本候補になる。
しかし、読みはじめたからには意地である。どこまで読めるかはわからないが、できるかぎり先まで進んでみる。
著者は消費を人類学的に定義すればどうなるかと問うている。
経済学は消費が消費者による商品(財)の自由な選択であり、消費そのものは市場の終わったところではじまると規定している。つまり、消費者は自由に商品を選び、商品を自由に消費するということだ。これは取引にもとづいて商品の所有権が移転されたあと、あらたな所有者によって商品が自由に使用されることを意味している。
だが、商品には文化が刻印されている。その文化は伝統であるとともに常に変化しつづけている。「消費こそは、文化をめぐる闘いが繰り広げられ、文化が形をとっていく闘技場である」と著者はいう。そのとおりだろう。
どのような商品を選ぶかは各個人や家庭の自由であり、それはどのような文化を選ぶかということでもある。ちょっとふりかえってみるだけでいい。食品にかぎらず、テレビやパソコン、本、スマホ、車、電車、保険、医者、ジム等々、われわれは日々さまざまな商品を選んでいる。
どのような商品を選ぶか、あるいは選ばないかは、常に変動しつづける文化(および技術)を受け入れるか、受け入れないのかを決定することでもある。われわれは商品(「もの」と「こと」)を選択的に買いつづけることによって自分たちなりの「文化生活」を営んでいるといってもいい。
文化のなかには売り買いしてはいけないものもある。それは商品化できない価値だ。たとえば投票用紙、政治的地位、親や子ども、にせ商品などなど。もし、それを売ったら、道徳的非難や法的制裁を免れないだろう。
おカネとは別に贈与の領域も存在する。贈与もまた消費に結びつくかもしれない。だが、それはあきらかに商品の生産、流通、消費からなる商品世界からはみだした領域である。
とはいえ、商品世界以前を含めて人類社会全体を考えても、やはり物質的な財が文化を構成し、社会関係をつくり、維持するものであることはまちがいない、と著者はいう。
たとえば南スーダンのヌエル族(ヌアー族)は多くの家畜を所有している。家畜は家族の財産であって、相続や結婚などのさいに受け渡されたり、屠られたりするだいじな財なのだ。このことをみても、財は単に欲求を満たす手段ではなく、社会関係をつくり、維持する手段であることがわかる、と著者はいう。
こうした人類学的認識を現代社会に適応することは可能だろうか。
そのためには財の有用性という考え方をひとまず棚に上げて、財を言語と同じように人間の創造力のもたらした媒介と考えてみたらどうだろうか、と著者は提案する。
財と言語が同じだという発想はおもしろい。言語が受け継がれた文化の膨大な蓄積をもとに、いまも更新されつづけるコミュニケーション・ツールだとするなら、人類にとって、財もまた地球の物質をもとにつくりつづけられ、交換されるコミュニケーション・ツールではないかというのである。
社会には慣習があり、ルールがある。人類学はこれを「儀礼」と呼んでいる。この儀礼を無視して、人は社会のなかで生活していけない。
著者はこう書いている。
〈財は儀礼の付属物にほかならない。消費とは、その主要な機能が所与の出来事の流れに意味を付与することにあるような、一つの儀礼の過程である。〉
こむずかしいことを書いている。財(商品)は儀礼の付属物というのは、財は文化習慣にもとづいて購入され、そろえられるという意味だ。
考えてみれば、儀礼(文化的習慣)は、それこそいくつもある。正月、成人式、入学式、花見、夏休み、祭礼、結婚式、葬儀など、人生はいくつもの儀礼に満ちている。儀礼を全般的な文化習慣として理解すれば、日常の食事や洗濯、掃除、家の修理、読書やレジャー、その他もろもろも儀礼である。
そこに付属物としての財(やサービス)が加わる。さらに財(やサービス)は、消費されることによって、儀礼や習慣に意味を付与する。すなわちハレとケからなる日々を祝福することになるのである。
ここで著者は儀礼、すなわち文化的習慣は、じつに固着的で根強いと指摘している。それはカレンダー、すなわち時節や季節、さらには周期とともに動いていく。
もっとも、文化的、社会的習慣が強固に存在するからといって、人は習慣に従わず、そこから離れて、自由な行動と私的な楽しみを選ぶこともできる、と著者はいう。だが、それもまた何かの刺激によって、新たな文化が選択されているのかもしれない。また、それと気づかない部分に「記憶の儀礼」がはたらいている可能性もあるという。
個人が新たな慣習を創出し、それを社会的レベルにまで拡張しようとしたら、新たな慣習にしたがう仲間を増やしていく必要がある。著者はそうした例として、イングランドで「ガイ・フォークスの祭」(冬の花火で大騒ぎ)が盛んになり、「ハロウィーン」がすたれたこと、クリスマスが盛んになって新年は影が薄くなったことなどを挙げている。
とはいえ、伝統はやはり根強く、人類学で広く知られるポトラッチ(首長が富をばらまく祭)にしても、そのリーダーが「村の首長」から金持ちの「平民の人間」に代わるのは容易ではないという。
このあたりの記述はややこしい。要するに、新たな慣習が生まれ、新たな消費が公共化するまでには、長い時間と働きかけが必要になるというのである(すると明治の文明開化や戦後の高度成長はどう考えればいいのだろうか)。
さらに読み進めてみよう。
著者は、消費財(商品)は単なるメッセージではなく、情報システムそのものからなる、とも述べている。ここでいうメッセージとは価格とか用途のことだ。これにたいし情報は文化の伝達にかかわっている。情報は読み解かれねばならない何か、すなわち文化である。
もはや財を物質的財と精神的財に区別するのは無意味になっている。たとえば食べ物や飲み物を味わうことは、単に肉体的な経験ではなく精神的な経験でもある。食事はその献立から作法にいたるまで、社会や家庭の文化であり、技術なのだといってもよい。
さらに、ここでマーキングという概念が持ちこまれる。マーキングとは「しるし」をつけることだ。商品には「しるし」がつけられている。たとえば、これはプラダのバッグだとか、これは村上春樹の本だとか。それによって商品は差別化されて、消費者の選択を待つことになる。
おカネを払って「もの」や「こと」(すなわち商品)を選んだ人のあいだには、タイガーズの試合を見るために甲子園球場に足を運んだときのように(これはぼくの勝手なたとえだが)、熱狂的な共感が生まれるかもしれない。そのことをみても、消費には単なる財の個人的消化にとどまらず、文化的コミュニケーションが含まれていることがわかる。
「財のいかなる選択も文化の結果であるとともに文化に寄与するものである」というわけだ。
商品の選択には、文化的なセンスをともなう。文化とは何も上流文化だけをさすわけではない。大衆文化も存在するだろう。人びとは情報の海のなかで、商品を選択し、みずからにとって、できるだけ好ましい立場を築きあげようとする。
「消費者はマーキング活動をやりとりするために財を必要とする」と、著者は書いている。これは必ずしも見せびらかしや見栄の張り合いと同じではない。ほかの人にどう見られ、どういう印象を与えるかは大きな問題である。
羨望と競い合いは人間の救いがたい本性で、それが消費を促していることは疑いない。とはいえ、個人や集団には内に閉じこもろうとする傾向もある。貴族たちはそれによって特権集団を維持しようとしてきた。
閉鎖集団は族内結婚によって、アウトサイダーを締めだす。そのさい、消費慣習は排除のための武器となる。「共有された文化は共有された自然へと形を変える」というわけだ。
いっぽう、上流階級に食いこもうとする人びとは洗練された消費慣習を身につけようとする。だが、閉鎖的な集団に食いこむにはたいへんな努力を必要とする。
人類学的な消費理論は、財を情報ととらえ、より高度な財をもつ階層が他の階層を排除するものととらえる。いっぽう、排除された階層のなかからは上流階層に侵入しようとする動きも認められる。
財をめぐる需要、すなわち消費は、単なる欲求の満足や羨望によるものではなく、権力と特権を手に入れ、それを維持するための活動でもある、と著者はいう。
おカネを前にして、消費は形式的には平等である。いまは大衆社会にちがいない。それでも「下層階級と比べ、上流の家庭は社会的階層組織の中にあって、互いにいっそう緊密に結びつく傾向にあり、はるかに広い社会的ネットワークの中にいる」と著者はいう。
経済学は個々人による合理的な選択を消費理論の前提としている。しかし、じっさいには個人は抽象的な個人ではありえず、それぞれの社会階級に属しながら、かなり傾向の異なる消費活動をおこなっているのだ。
商品(財)が情報システムだとすれば、上流階級、中産階級、労働者階級では、それぞれの社会的接触によって手に入る情報は階級ごとにかなり異なる。高い稼得能力は、情報をコントロールしうる能力でもある。社会的接触を失い、機会から切り離され、隔離された者には、どんづまりの職しか与えられない、と著者はいう。
これは厳しい現実だと言わねばならない。著者は、だからといって、金持ちは金持ちらしく、貧乏人は貧乏人らしく生活すればいいといっているわけではない。だが、現に社会階層が存在し、そこに排除の論理がはたらき、階層によって消費のスタイルが異なっているのは事実である。これは商品世界を考えるうえで、けっして無視されてはならないことだ、と著者は考えている。
『儀礼としての消費』を読む(2) [商品世界論ノート]

人はなぜ商品(財)を求めるかという問いにたいし、経済学は明確に答えていない、と著者はいう。経済学は価格と所得の変化にたいして、消費がどのように変化するかを機械的に説明するだけ。いっぽうのモラリストは、ひたすら消費社会の貪欲ぶりを非難するばかりだ。
人はなぜものやサービスを買うのか。身体的必要、さらには精神的必要のためというのが普通の答えだろう。さらに、そこから必要と贅沢を区別し、贅沢を否定する議論もでてくる。
差別化や見せびらかし(衒示)もまた、人が商品を求める動機と考えられてきた。そこには非合理な人間の欲望を感じ取ることができる。
だが、現代経済学は人が商品を求めるさいの身体的・精神的必要、あるいは見せびらかしといった心理的動機を排除してきた。個人の好みは所与とされ、商品の価格が下落すれば多くの量を買い、上昇すれば少なく買う。所得が増えたり、減ったりしても商品を買う量は変化するというわけだ。
要するに、現代経済学は、人が経済的合理性にもとづいて行動すると仮定したうえで、価格と所得の変化に応じて、商品の購入量がどう決まるかを論じてきたのである。
もっとも経済学者のなかには、こうした機械的な仮定に疑問を投げかけた者もいる、と著者はいう。
サイモン・クズネッツは食物や健康、レクリエーションへの支出を経済コストととらえるのは、人を仕事のために生きる馬車馬のように考える見方だと批判した。
フランク・ナイトは逆に、生産過程を何らかの幸福を得るための犠牲だと考える経済学の仮定はまちがっているという。
ピエロ・スラッファは生産と消費をばらばらにとらえるのではなく、ひとつの循環過程のシステムとして考えるべきだという。
いずれにせよ著者メアリー・ダグラスのような人類学者の目からすれば、経済学者の厳密な仮定にもとづく経済理論構築は、自分の手を縛ったうえで、理論のための理論づくりにいそしんでいるように思えたのだ。
著者はいう。現代経済学を学んでも、人がなぜ商品(財)を求めるのかの答えはでない。それでは、「人はなぜ貯蓄するか」についてはどうだろう。
ケインズは、人間は所得が増えると消費を増やすが、そっくりそのまま消費に回すのではなく、その一部を貯蓄すると考えた。
しかし、過去1世紀を振り返ると、実質所得が増加したわりに貯蓄はそれほど増えているわけではない、と著者はいう。さらにさまざまな民族の生活誌をみると、倹約を美徳とする文化もあれば、倹約を欲深で下劣とみる文化もある。したがってケインズの定式は普遍的にあてはまるわけではないという。
ウェーバーは経済を「伝統経済」、「農民経済」、「冒険商人的資本主義」、「個人主義的資本制」の類型でとらえた。16世紀から17世紀にかけては、大きな変化が生じた。私的蓄積を非難するカトリック様式から、私的蓄積を承認するプロテスタント様式への転換が生じたという。
ウェーバーの関心は伝統的経済から資本主義的な私的経済への移行がいかにして生じたかに向けられていた。
伝統経済にとっては土地こそが収入源であり、王や貴族たちは領地を確保するために無茶な浪費をし、家臣の忠誠心を引きだした。人間的なつながりがきわめて重要だった。敵味方のあいだでは脅迫とへつらいが入り乱れ、寝返りがくり返されていた。
聖職者は大領主から土地の寄贈を受けることによって、財産を獲得した。だが、その財産は聖堂やモニュメント、十字軍、巡礼、何千という宗教儀式のために費やされた。中世においては、フランシスコ会やアウグスティヌス会、カルメル会、ドミニコ会などが広い土地を所有し、修道会としての資産を蓄積していた。
ここで、著者は集団と個との関係を論じる。集団はみずからが長期的な観点をもち、公共(成員)の利益を代表すると主張し、そのため成員のコントロール(支配)をゆだねられるといってよい。伝統的経済は集団的環境のもとに成り立っている。
集団の背景にはもちろん個人がある。近代の特徴は集団的環境のなかから個人主義的環境が誕生することである。集団の圧力が弱まるなかで、個人の責任が重視される個人主義的秩序が生まれる。そこでは個人間の関係は集団の価値によってではなく、猛烈な競争によってランキングされる。こうして個人間の競争の平等と公正さを律するルールが求められるようになる。
集団的環境から個人主義的環境への移行は、節倹と貯蓄の考え方に大きな変化をもたらす。
伝統社会では個人の私的蓄積の可能性はきわめて低い。教会や修道院でもそれは同じである。個人の貯えは常に集団の目的のために吸い上げられる。個人はほとんど蓄積せず、集団が富を蓄積する。
すると、個人主義的環境のなかで、人はなぜ貯蓄するようになるのか。近代産業社会においては「個人は[集団から]解き放たれることで自由になるのではなく、きわめて困難な社会環境の中に引き込まれる」というのが著者の見方である。競争社会のなかで諸個人はみずからの身を守るために、ちいさな集団をつくるいっぽうで、将来の不安に備えて貯蓄に励まざるをえない。
ここで、経済学が消費をどう考えていたかを、もう一度振り返ってみよう、と著者はいう。従来、経済学では、消費者はあくまでも個として支出を決定するとされていた。ところが、消費者がご近所の買い物や広告に影響されることはいうまでもない。そこで、個人主義的でアトム化された消費者のモデルは、デューゼンベリーによって修正されることになったという。
デューゼンベリーによると、商品(財)は特定目的(活動)のために特殊化されているからこそ商品なのである。そのうえで、同じ目的をもつ複数の商品は、文化的尺度にもとづいてランクづけされ、所得に応じて選択される。
高度な消費水準をもつ社会では、消費者により多く支出させようとする持続的な圧力がはたらいている。そのため、比較的高所得の人は社会的に課される文化的要求を満たしたうえで、貯蓄のための「残余」をもつ。これにたいし低所得の人は文化的要求を満たすのがせいいっぱいで、あまり貯蓄を残すことができない。これがデューゼンベリーによる(残余としての)貯蓄の説明である。
デューゼンベリーは、たえざる文化的変化が消費増加への欲求を強めていくことを示した。さらに、上流階層と下流階層、あるいは専門職と非専門職とでは、文化水準にたいする欲求が異なることも指摘した。
とはいえ、著者はデューゼンベリーが貯蓄を消費需要の「残余」と考えていることを批判する。著者によれば、貯蓄はけっして消費の残余ではなく、文化的に求められる第一の先行要件なのだ。商品世界のつくりだす文化水準は、いま支出するよう個人に圧力をかける。だが、そのいっぽうで、商品世界は未来に備えて貯えるよう個人に圧力をかけているのだという。
ここで著者はさらにフリードマンの恒常所得理論を紹介する。フリードマンは所得を恒常所得と一時所得に分けたうえで、貯蓄は将来への備えであって、残余のカテゴリーではないと仮定している。
フリードマンの恒常所得理論は、個人が一生にわたる消費計画をもち、その範囲で日々の予算配分をおこなうものと想定する。個人の人生計画は変わっていくが、そのガイドラインとなるのは恒常所得と恒常消費である。消費者は生涯の目的に応じて、恒常所得を消費と貯蓄に振り分け、みずからの経済環境を維持しようとする。
恒常所得理論は、たまたま手に入った所得によってではなく、期待される生涯所得にもとづき、一生の所得の流れを構造的に分析しようというものだ。
デューゼンベリーとフリードマンが前提としているのは、個人主義的な色彩の強い合理的な市場社会である。だが、それはすべての社会の状況を説明できるものではない。たとえば中世ボルドーの大貴族は破滅的なカネの使い方をしていたし、いまでも「明日は明日の風が吹く」とばかりに手に入ったカネをたちまち浪費してしまう労働者もいる。
社会環境は多様である。経済学者の仮定の範囲をたちまちはみだしてしまう。貧困の問題を理解するには、経済学者の仮定からはみだす部分を考慮に入れなければならない、と著者はいう。
いずれにせよ消費社会を論ずるにあたっては、軽薄にそれを批判するのではなく、消費と貯蓄の冷静な分析にもとづかなければならない、というのが著者の考え方である。
じつに曲がりくねった議論というべきだろう。ついていくのは容易ではない。投げだす人が多いのもわかる。
しかし、思えば、消費といい貯蓄といい、ふだんわれわれがあたりまえのように取っている行動は、近代に現れた商品世界特有の現象なのであって、それが何を意味するかを考え直してみることは、人類学的にも重要なテーマなのである。
『儀礼としての消費』 を読む(1) [商品世界論ノート]

人類学でいう「儀礼」というのは何だろう。ふつうは「宗教的儀礼」を連想するが、もっと広く「日ごろの習慣」と言い換えたほうがよいのではないか。あるいは少し厳密に「文化的習慣」といってもよい。
いずれにしても「儀礼としての消費」と題されると、それだけで頭がついていけなくなる。
ずっと本棚に眠っていたメアリー・ダグラスとバロン・イシャウッドの共著『儀礼としての消費』(浅田彰・佐和隆光訳、講談社学術文庫、2012)を、たぶん理解できないだろうなと思いつつ読んでみることにする。
メアリー・ダグラス(1921〜2007)はイギリス人の人類学者。日本で訳された本としてはほかに『汚穢(おわい)と禁忌』がある。バロン・イシャウッドはイギリスの経済学者で、消費者行動理論の研究を専門としている。
原著のタイトルはThe World of Goodsで、日本語版とはイメージが異なる。訳者の佐和隆光は『財の世界』と紹介している。だが、これでは日本語のタイトルとなりにくいので『儀礼としての消費』と変えたわけだ。それによって人類学による消費へのアプローチであることが示唆されている。
ところでgoodsをどう訳すかは、意外とむずかしい。商品、財、品物、用品、それともグッズ? 商品と訳せば、タイトルはまさに『商品世界』となる。そんなことにこだわるのは、ぼくが「商品世界論ノート」などという、あてどないテーマを考えようとしているからだ。
商品と財はことなる。商品は売買される財をさすが、財そのものではない。しかし、商品と財は同じだといってもよい。財が市場を意識するときに、それは商品となる。
goodsはcommodityよりも広義の商品(財)としてとらえることができる。コモディティが市場にある商品そのものを指すとすれば、グッズは商品の流れを含むと解釈することもできる。その流れは次のようになるだろう。
(1)市場を意識した財=つくられようとしている商品
(2)市場に出された財=取引される商品そのもの
(3)所有された財=消費され利用されている商品
商品世界はこうした時間的経過を含む財の関係性のなかで成り立っているといってよいだろう。さらにつけ加えれば、商品世界を成り立たせているのは、商品世界を動かし支える血液でもある貨幣にほかならない。その点で、ダグラス、イシャウッドの『儀礼としての消費』は、原題をそのままに、人類学的アプローチにもとづく『商品世界論』と受けとめてもいいだろう。
以上はたあいない前置き。以下、のんびり中身を読むことにする。難解なので、はたして最後まで読み切ることができるか、はなはだ心もとない。
まず「序」について。
こんなふうな記述がある。
「コンシューマリズムは貪欲で愚鈍、そのうえ、必要とは何かということに無神経だとして、酷評される」
これは消費主義、あるいは消費社会にたいする強い批判だ。しかし、著者たちはこうしたモラリストによる消費社会批判は、商品世界を理解することにつながらないという。
人はなぜ商品を買うのか。そのこと自体から考えてみなくてはならない。経済学では一般に、人が商品を買うのは、物質的幸福や精神的幸福を得るため、あるいは人にみせびらかすため、といわれる。最初のふたつは個人的必要であり、あとの「みせびらかし」(誇示、衒示)は社会的欲求にもとづくものとされる。
だが、はたしてそうなのか。商品(できあがった財)と労働(財をつくること)、消費(財を利用すること)は人の一連の行動であって、消費だけを切り取って、それを分析し、あとでパズルのように組み立てるのは、経済学者の悪癖ともいえる抽象癖、すなわち合理的個人という仮定に由来するのではないか、と著者たちはいう。
なかなかむずかしいことを言っている。
むずかしい話は苦手だ。それ以前に、残念ながら、ぼくにはそれを理解するだけの教養(知識の蓄積)がない。
ただ、著者たちが消費の目的を、「物質的幸福や精神的幸福を得るため、あるいは人にみせびらかすため」と規定する経済学者の割り切り方に疑念をいだいていることは理解できる。
ここでもちだされるのが、小説家ヘンリー・ジェームズ(1843〜1916)による3つの部屋の記述である。
いずれも金持ちの女性が内装し、飾りつけた部屋だが、小説では、はじめてきた訪問者が、この部屋をひとめ見渡しただけで、住んでいる人の生活や性格、社会的地位、さらには隠された意味を読みとるシーンがえがかれている。
最初にアメリカ人の主人公ストレーサーが、パリのミス・ゴストリーのアパルトマンを訪ねる(『使者たち』)。
そこは彼女の「最後の巣」のようにみえ、薄暗がりの部屋部屋には、古い象牙や錦織などがそれこそぎっしりと置かれ、まるで「海賊の洞窟」のようで、あちこちの暗がりに金色や紫色が輝いていた。
次に同じ主人公は、ベルシャス街に住むド・ヴィオネ夫人の部屋を訪ねる。そこは古きパリを思わせる気品にあふれていた。父親から継承したにちがいない雑多な小物や飾り、特別注文の記念品、小さな古いミニアチュアやメダリオン、絵や本などが整理されてきれいに並べられていた。
いかにも古き良き時代のブルジョワの部屋が保たれている。だが、主人公は「最上の対面を保とうとする空気」のなかから、無理やり隠そうとしている何かがあることに気づいてしまう。それは秘められた「不義の愛」だ。
3番目にとりあげられるのは、アメリカ南部の青年がボストンの親類の部屋を訪ねる場面だ(『ボストンの人々』)。
青年は通された客間に南部とはまるでちがう文化都市ボストンの趣味のよさを感じる。テーブルやソファ、小さな書架に置かれている書物、壁にかけら得た写真や水彩画、ずっしりとした感じのカーテンに「文化そのもの」を感じる。
いきなり、ヘンリー・ジェームズによる3つの部屋の記述を並べられて、われわれは面食らう。著者たちはいったい何を言いたいのだろう。
ふだんはあまり意識しないかもしれないが、人はかつては商品だった財(あるいはサービスとしての商品)に囲まれて暮らしている。いま自分がいる部屋を見渡しているだけでも、そのことがわかるはずだ。
はたして、ヘンリー・ジェームズのえがく3つ部屋には、ヴェブレンなどの経済学者のいう衒示的(げんじてき)消費、すなわちみせびらかしの消費があるだろうか。ここにあるのは、むしろ終末、体面、プライバシーの空間なのではないか。そこに置かれたそれぞれの財(商品)に全体の意味が隠されている。
財(商品)は「生きた情報システムの一部」だ、と著者たちはいう。ひとつひとつの財を走査(スキャン)し、読み解き、ランクづけることから、「生きた情報システム」、すなわち現代の商品世界を浮かび上がらせることができるのではないか。
さらに「市場も商品もほとんどないような遠いエキゾチックな場所」と商品世界を比べてみることも重要だろうとも述べている。「人類学からもたらされる洞察は、私たち自身に強力な望遠鏡を向けるように思われる」
そこから、何が導かれるか。
「序」のしめくくりは、こうなっている。
「財は中立的だが、財の使用は社会的である。財は垣根としても橋としても使われうるのである。」
商品(財)は文化そのものなのだ。それは所有されることによって、人との境(垣根)をつくる。そのいっぽうで、それは人とのつながり(コミュニケーション、橋)をつくるものでもあるのだ。
やれやれ、まだ「序」が終わったばかり。最後まで読めるか不安になってくる。
ハイパー資本主義──『資本とイデオロギー』を読む(6) [商品世界論ノート]
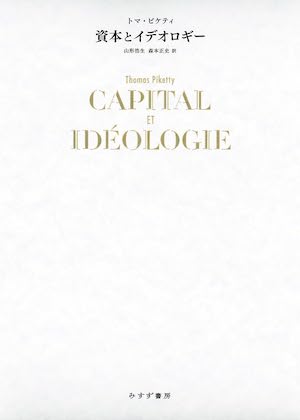
ハイパー資本主義が登場するのは1980年代以降だ。
いまや世界中の国々はこれまでにないほど密接に相互依存している。とりわけ1990年代以降は、デジタル技術の時代となり、グローバル化が段違いに進んだ。しかし、経済格差や貧困の度合いは、1980年代以降、むしろ拡大している、とピケティはいう。
ヨーロッパや中国、米国より経済格差が大きいのは中東だ。中東では、人口の少ないいくつかの国に石油資源が集中している。中東の国境は第1次世界大戦後にイギリスとフランスによって引かれたもので、その後、欧米列強が石油産出国を保護した。
中東では石油産出国と非産出国とのあいだで極端な経済格差がある。産出国内の格差も大きく、国家の富はごく一部に集中し、そこではたらく外国人労働者とのあいだでは極端な差がある。
欧米諸国では、第1次世界大戦後、富の集中は拡散へと向かい、1970年代までそのままの状態がつづいたが、1980年代からふたたび集中傾向に転じた。中国とロシアでは1990年代に民営化の波が到来して以来、経済格差が急速に広がった。インドも同じだ。
しかし、所得と富の分布に関するデータはまだまだ不正確だ。その理由は分布トップの回答者が、富、とりわけ金融資産を過少申告しているためだ。これを解決するには公的金融台帳をつくるほかないのだが、いまのところその方向性は政治的に阻まれている、とピケティはいう。
なぜビッグデータとITの時代に、資産とその分布に関する統計が透明性を欠いているのか。ピケティによると、その理由は、再分配を嫌う財産主義イデオロギーが復活したせいだ。資産の透明性を拒絶するのが、現在の新財産主義の特徴となっている。
近年の税制競争によって、かつてより直接税の税率は抑えられているにもかかわらず、租税回避やタックス・ヘイブンなどを利用した、企業や個人の資産隠しが横行している。そのいっぽうで、中下層階級の負担(消費税、賃金と年金からの控除)は軽減されず、高所得と巨額財産に累進課税を課すといった税制は検討されていない。
「金融不透明性と相まったきわめて高い富の集中の復活は、今日の世界的な新財産主義的格差体制の本質的特徴の一つだ」と、ピケティは指摘する。
2015年現在、米国ではトップ1%が総私有財産(不動産、事業資産、金融資産)の37%(1980年は23%)を所有し、トップ10%が総私有財産の74%(1980年は65%)を所有している。ロシアではトップ1%が42%、トップ10%が71%、中国ではトップ1%が30%、トップ10%が67%。フランスではトップ1%が23%、10%が55%、イギリスではトップ1%が20%、トップ10%が52%といった割合になっている。
富の遍在は1980年代以降、とりわけ90年代以降拡大した。こうした傾向は今後減速するかもしれないが、まだ持続するかもしれないという。
1970年から2000年にかけ、世界の最貧諸国はさらに貧しくなった。人口が増加しているのに、税収は少なく、国はじゅうぶんな教育投資や医療投資さえおこなうことができないありさまだ。
2008年以降の劇的な変化は、中央銀行が短期間で莫大な貨幣を創造するようになったことだ、とピケティはいう。いわゆるリーマン・ショック以降、世界の主要中央銀行は「量的緩和」に踏みこみ、貨幣創出オペレーションを編みだした。
量的緩和には銀行への長期融資と民間および政府発行の債券の買い入れが含まれる。中央銀行のこの大規模介入によって、富裕国は1930年代の世界大恐慌に匹敵する危機に陥らずにすんだ。中央銀行は銀行破綻の連鎖を防いで、「最後の貸し手」としての役割を果たした。
〈だが、中央銀行は世界のあらゆる問題を解決し、資本主義全体を規制すること(あるいは資本主義を超克すること)などできない。過度の金融自由化、拡大する格差、気候変動と闘うには、他の公的制度が必要だ。つまり、集合的な熟議と民主的な手続きに基づく議会で作られる法、税、条約などだ。〉
ピケティは中央銀行の限界をそんなふうに指摘している。とはいえ、金融危機や戦争、大規模な自然災害において、貨幣創造によって、膨大な資源を短期間で動員できる機関は中央銀行しかない。
中央銀行は民主的正当性にもとづくことなく、GDPの数倍にわたるマネーを創造することができる。だが、そのことは深刻なガバナンス問題を引き起こす可能性があるのだ。
経済金融化がここ数十年で驚くべき水準に達したことは強調に価する、とピケティはいう。ユーロ圏でも、金融資産と負債の総価値はGDPの10倍以上に達している。だが、金融部門全体の規模が実体経済よりも早く成長するような状況は永遠につづくわけがないという。
貨幣創造はいまのところさほどインフレを引き起こしていないが、一部の資産価格は上昇している。国債の名目利率はゼロに近く、実質金利はマイナスだ。これは中央銀行が大量の国債を買い入れているためだ。だからといって、大口投資家がもうかっていないかというと、そうではなく、かれらは年間6〜8%の利益を確保しているという。
ピケティは疑問を投げかける。
〈多くの国民は、ヨーロッパ経済活性化に目に見える効果がほとんどないのに、金融機関救済のためになぜあんな巨額のお金を創造したのか、そんなリソースを苦しむ労働者の救済、公共インフラ開発、再生可能エネルギー移行への大規模投資の資金に動員できないのかと、当然ながら問い始めている。〉
これはとうぜんの疑問である。
さらにピケティが問うのが、現在の新財産主義を支えるイデオロギー、とりわけハイエクの権威主義的リベラリズムだ。
ハイエクは『法と立法と自由』で、あらゆる再分配政策への恐れを表明している。再分配は既存の財産権に疑いを投げかけ、累進課税の悪循環をもたらすというのだ。ハイエクは憲法で累進課税という発想自体を禁止すべきだとも主張する。議会に財産権を損なうような立法権を与えてはならないともいう。けっきょくのところハイエクの求める議会は財産権を擁護する議会に尽きる。
ここ数十年で台頭してきた新財産主義イデオロギーは、極端な能力主義とも結びついている、とピケティはいう。それは経済システムにおける勝者を称賛するいっぽうで、敗者を無能と非難する。さらに貧困者が貧しいのは当人のせいだと主張する。
1980年代以降、教育の不公正と能力主義の偽善はますます強まっている。
能力主義イデオロギーは、起業家と億万長者賛美とも結びついている。億万長者の慈善活動への期待や称賛も絶えない。だが、それらは新財産主義がもたらす権力の讃仰にほかならないのだ、とピケティは断言する。
そろそろハイパー資本主義を終わりにしたほうがいいのではないか、というのが、ピケティの主張である。
(ピケティの『資本とイデオロギー』をこれで半分ほど読んだことになります。このあと、さかのぼって、前近代社会とは何か、近代社会について、さらに現代の政党分析などにも触れなければなりませんが、ちょっと休憩をいれます。)



