ソ連時代の消費生活(1)──オックスフォード版論集『消費の歴史』から [われらの時代]
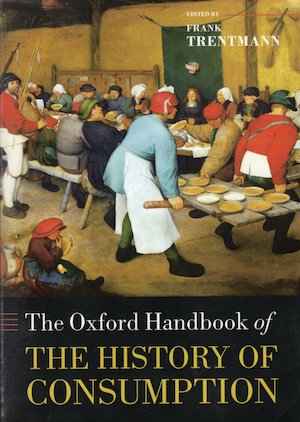
あのころ、50年ほど前の「われらの時代」に、「われら」はばくぜんと社会主義に憧れをいだいていた。資本主義に対抗する概念が社会主義しか思い浮かばなかったためだ。周囲には「世界同時革命」なるものを叫ぶ党派もあった。しかし、ぼく自身は、世界革命により国家をなくし、社会主義を実現するのだというかれらの観念的な主張に、いまひとつ納得がいかなかった。
すでに社会主義国家なるものは存在していた。その代表がソ連であり、中国であったことはいうまでもない。「われら」はふたつの国をスターリニズム国家と断定し(なかには中国の毛沢東思想をスターリニズムと区別する党派もあったが)、社会主義の別のあり方をさぐろうとしていた。先進資本主義国のあり方にたいしても現存社会主義国のあり方にたいしても否定性を提示しつづけること。いわば否定の弁証法を武器にすることによって、何か新たな方向が見えてくるのではないかと考えていた。
しかし、ぼくの場合は、そうした発想も夢想のうちにたちまち消えていった。大学生時代は終わり、何か仕事を見つけなくてはならなかった。幸いにも仕事は楽しく、やりがいがあった。20年にわたって書籍編集の仕事をつづけることができたのは、ありがたいことだと思っている。
ところが、退職して不思議と気になりはじめたのが、やはりあのころ考えていたことなのだ。埋められてしまった記憶を掘り起こし、あのころの関心を引き延ばしていくと、遅まきながらも、いくつもの発見があることに気づく。
オックスフォード版『消費の歴史』(The History of Consumption, 2013)から、シーラ・フィッツパトリックの「ソ連時代の消費生活」(Sheila Fitzpatrick, Things Under Socialism: The Soviet Experience)を読んでみる。
消費という面から、ソヴィエト社会主義の経験をとらえようとしているところがおもしろい。
厳密にいうとソ連(ソヴィエト連邦)が成立するのは1922年のことだが、ここでは1917年の10月革命後(正確には1918年のボリシェヴィキ・クーデタ—後というべきかもしれない)の5年もソ連時代に含めておくことにしよう。
フィッツパトリックによると、社会主義のもとでは、財はいかなる問題も引き起こさず、それが問題を引き起こすのはもっぱら資本主義の場合と考えられていたという。
資本主義のもとで、財は商品となり、利潤を求めて売りにだされる。商品は資本家と労働者の対立、不公平な分配をもたらすだすだけではない。欲望やねたみ、「物神崇拝」を生みだし、資本主義的な文化や行動様式をつくりだす。ところが、社会主義になると、そんな事態はおこらなくなり、だれもが平等で、満足できる生活を送れるはずだった。
ロシアの理論家、ブハーリンとプレオブラジェンスキーは『共産主義のABC』のなかで、共産主義のもとでは商品はなくなり、財だけとなると論じた。そして、その財はマルクスとエンゲルスが主張したように「各人の能力に応じ、各人の欲求に応じて」配分されるとした。
しかし、個人の欲求などというものが、はたして決められるものなのだろうか。だれかがもっとほしいというなら、それに応じることができるだろうか、とフィッツパトリックは問うている。
ブハーリンらによれば、財の不足といった問題が生じるのは短期間で、一時的にはやむなく個人の労働量に応じた分配方法が必要になってくるけれども、こうした問題はすぐに克服される。というのも、社会主義のもとでは、ありあまるほどの財がもたらされるから、分配をめぐる争いなどはなくなってしまうからである。財がふんだんに提供されるのは時間の問題だ、とブハーリンらは主張した。
将来にたいする楽観論は、革命が完遂されるまでは、物品が不足する場合もあるという現状認識と結びついていた。したがって、当面の革命の任務は、貧乏人を豊かにし、金持ちを貧乏にすることだと考えられた。こうしてソヴィエト初期の政策と実践は再分配の実施に向けられることになった。
この再分配戦略で最初に実施されたのは、民間企業や個人財産、工場、金融機関を国が接収し、それらを国有化すること、さらには個人住宅を自治体の管理下に置くことだった。そのため、国家は「階級の敵」であるブルジョワジーから財産を奪った。プロレタリア国家である以上、財産はプロレタリアートのものと考えられたからである。
人びとが直接ブルジョワの財産を奪う事態も発生した。革命直後には農民が地主を所有地から追いだしたり、都市の「革命家」が店や住宅に押し入ったりする事件も発生している。また集権化が進んだ1920年代には、農民たちが富農と目された「クラーク」の土地を収用し、その分け前にあずかるようになった。
しかし、ボリシェヴィキは一般に、直接的な荒っぽい民衆行動を抑えようとした。正しい財産没収法は、党や国家の機関に通報したうえで、没収品の目録をつくることだった。家捜しの結果、「人民の敵」とみなされるような物品が見つかった場合、所有者はその「目録」に署名させられ、物品を押収される。何はともあれ、社会主義の第一歩は、ブルジョワ的財産の没収からはじまったのである。
再分配の積極的一面は、必要とする者に押収財産を譲渡することだが、それは革命初期の時代には、きわめて大ざっぱかつ恣意的におこなわれた。
国家による配給制はもともと戦時体制に伴うものだった。ロシアでは帝政が倒れたあとも、暫定政府のもとで、配給制が引き継がれ、パンや砂糖、肉などが配給されていた。だが、10月革命以降、ソヴィエト体制となっても配給制は廃止されなかった。配給制はプロレタリア的な仕組みとみなされるようになった、とフィッツパトリックは記している。
住宅政策についても同じ原則が貫かれた。都市では広々としたブルジョワの住宅をプロレタリアートに配分する方策がとられ、かつての所有者は住宅の一部屋か二部屋に閉じこめられた。
この方式はのちの悪名高い「集合アパート」の原型となる。ひとつの部屋にいくつもの家族が暮らし、台所や風呂、ホールも共有されていた。集合アパートは社会主義イデオロギーの産物だったといえる、とフィッツパトリックは指摘する。
社会主義においては、集団生活が基本的な政治方針だった。家族は集団で食事をとり、同じ洗濯機を使って洗濯し、共有のセカンドハウス(ダーチャ)やリゾートで休暇をとるべきだとされた。アパートは国家の所有で、家具なども支給されていた。町の住民は公共の交通機関を使って移動することもできたが、村にはだれもが使用するための馬や荷馬車を集めておく場所があった。文化宮殿がつくられ、旧貴族の屋敷がそれにあてられたが、それは人民に属するものとされていた。
「社会主義的日常生活」の建設に取りかかるのだと意気ごむ者もいなかったわけではない。とりわけ、女性の解放が革命の重要課題とされていた。こうしていくつかのモデル・アパート街区がつくられた。
そのひとつがモイセイ・ギンズブルクの設計したナルコムフィン集合アパートである。そのアパートには共同の台所と食堂、共同のジムや図書館、洗濯機などが設置され、両親が働くあいだ子どもをあずかる保育所などもあった。
アバンギャルドの「構成主義」建築家や芸術家、理論家は、1920年代にこうした問題に真剣に取り組んだ。アレクサンドル・ロトチェンコは1925年に「これは人間や女性、財産にたいする新たな取り組みであり、われわれのもつ財産は平等な同志のものだ」と書いている。理論家のボリス・アルヴァトフは、プロレタリアートは工業によって大量生産されたものに、特別の親近感をいだくはずだと論じた。
だが、レーニンとトロツキーは、構成主義者のおしゃべりが、やるべき仕事を無視して、革命に悪評をもたらしているとみなした。
ほとんどのボリシェヴィキ指導者は、日常生活を立て直す計画はまだあとのことだと考えていた。ボリシェヴィキからみれば、日常的なことはどうでもよいもので、それはどちらかというと抑制されなければならなかった。日常生活の優先は、革命の成果を台無しにしかねないと考えていた。財はどちらかというと中心課題ではなく、過去の残存物の悪影響にほかならなかった。重要なことは行動を変容させることだ。
日常生活にもっとも強い関心をいだいていた党の指導者、レオン・トロツキーは、教育と行動というテーマで多くの本を書いている。読むことを学ぶこと、演説の仕方や女性への接し方、衛生への知識、効率のよい働き方、時間厳守、飲酒をやめること、などなど。だが、カリスマ的なトロツキーでさえ、政治と「階級の敵」との戦いにしか興味のない若い共産主義者に、日常生活を変える仕事が魅力的だと説得することはできなかった。
フィッツパトリックによれば、一般にボリシェヴィキ指導者の財にたいする考え方は、できれば財を持とうと思わないほうがよいというものだったという。1920年代に推奨されたライフスタイルは、本だけあればいい「清貧」な生活である。これは革命以前の所有についてのラディカルな伝統を引き継いだものだ。レーニンの妻クループスカヤは「自分たちの家族はこれまでどんな不動産もどんな財産ももったことがない」と述懐している。
1920年代のボリシェヴィキは、機能的で大量生産されたものを好んでいた(アメリカ風のものやアバンギャルド風のものは嫌いだった)。かれらは同時に「近代性」の支持者であって、農民や職人のつくった古くさい貧相な品物や、ブルジョワや貴族がもつような贅沢な品物は好きではなかった。
財に関して言えば、一般にボリシェヴィキはそれを認めるというより、それに反対する立場をとっていた。ソヴィエト初期に衛生学上の観点から唯一推奨されていた品物は、石鹸とハンカチ、歯ブラシだった。
表向き、ボリシェヴィキ指導者は物にたいして無関心な態度を装っていた。とはいえ、食料や衣服、隠れ場所は保証されていたのである。いっぽう一般の人たちは困窮し、もっと物がほしいと感じていた。のちの外相リトヴィノフと結婚したイギリス人女性は、ロシアにやってきた当初、「思想」はあふれているが、「物」はなにもないと感じた。だが、まもなく、そうではなくて、「モスクワでは物がごちゃごちゃと積まれていて、だいじに扱われていないのだ」と気づいたという。流通システムが機能せず、配給制がとられていたせいだ。
それは欠乏のせいでもあった。内戦が終わって、一息ついたころ、楽観主義者のなかには、これで革命が終わって、ふだんの生活が戻ってくると思う者もいた。だが、実際には、革命がさらに進行し、以前よりさらに欠乏の度合いが深刻化するのだった。
スターリンによる「上からの革命」がはじまっていた。それは国家が主導する経済躍進政策であって、急速な工業化と農業の集団化、民間交易の禁止、中央経済計画の導入をともなうものだった。
第1次5カ年計画(1928〜32年)で、都市の生活水準は一気に低下する。ふたたび配給制が採用されたが、それは内戦時のような平等なものではなかった。商人や僧侶などには、配給切符が与えられなかった。優先的に配給をもらえたのは、たとえば重工業ではたらく労働者で、職場から物資の配給を受けた。これはいまにはじまったことではなかった。というのも、内戦中も特別の学者や芸術家は「学術配給」をもらっていたし、党の高官は内戦中も戦間期も豊富な食料を受け取っていたからである。
しかし、ソヴィエト生活のなかで、リストにあるエリートメンバーだけに、一般開放されない店が品物を売る習慣が定着するのは1930年代になってからである。国家が倉庫に保管する品物を手にすることができるのはエリート層の特権だった。
そのころ、農業の集団化によって、食料事情は絶望的な様相を呈していた。集団化のポイントは農民に耕作を強要し、集団的に農産物を販売させることである。国家はそれを安い価格で買い取り、工業化のための「社会主義的蓄積」に利用しようとした。しかし、農民はこれに抵抗し、国家も取り立てをやめなかったため、1932年から翌年にかけて、飢饉が発生する。農村部では何百万人もが殺害され、農村から都市に何百万人もが流れこみ、それにより都市の配給制は崩壊寸前になった。
国家がわずかな支払いで農産物を収奪したことを考えれば、「調達」は押収と変わらなかった。しかし、クラーク(富農)にたいしては、公然たる押収がなされ、教会も攻撃をまぬかれなかった。鉄製の鐘などは工業化のために鋳つぶされた。
集団化が食料供給を危機におとしいれるいっぽう、職人などへの圧迫も強まった。その結果、家庭でふだん使う湯沸かしや袋、釘、板、ペンキ、スプーン、フォーク、皿、洗面器、ランプ、バスケットなどが突然、消えてなくなる。靴を含め、革製品も市場で見かけなくなった。集団化がはじまった途端、農民が家畜を大量処分したからだ。
ボタンも針も糸もなかった。消費経済がいくぶんか回復し、仕立業が認められるようになった1930年代半ばになっても、スーツをつくろうと思えば、洋服の生地はもちろん、針や糸も自分で準備しなければならなかった。小物が貴重品になっていた。金属片や雑巾、ガラス、古靴、コルク、スズ、人間の髪の毛なども貴重な品物だった。
人口の急速な流入により、都市は混み合ってきた。モスクワの平均的居住スペースは1930年に1人あたり5.5平方メートル。バラックや寮と並んで、集合アパートが基本的な住まいとなり、その状態は1950年代後半までつづく。集合住宅では、しばしば仲の悪い気にくわない隣人とも、疑心暗鬼なまま、生活を共にしなければならなかった。
集合住宅で自分の領域をもとうとするなら、食料は自分で見つけねばならず、それには相当の技術を要した。当初、一時的と考えられた物不足は次第に集団化と工業化にともなう構造的な問題だとわかってきた。それは絶対的な不足というより、体制の問題だった。
社会主義のもとでは、企業や個人に必要な物資が行き渡らず、その結果、企業や個人が物資を隠匿する傾向があった。政府当局はこれをどうすることもできなかった。体制に問題があるなら、ひとびとは自分で物資を手に入れるほかなかった。行列に並ぶか、闇屋から不法に品物を手に入れるか、配給のいい仕事場を見つけるか、それともコネを見つけてサバイバルをはかるか。だれもが必死だった。
ソヴィエトでの特権は、物品を所有できることではなく、倉庫のなかに国家が所有している物品にアクセスできることだった。1930年代には大衆の現状をよそに、こうしたソヴィエトの新エリート層が増えつつあった。
ある高官の妻は、自分たちは財も所有せず、こうした特権もなかったと述懐する。車は夫を仕事場に送っていくためであり、食料パッケージは受け取っていたが、家具は国家から与えられたもので、いずれ返却しなければならない。
「私たちの家族に物への執着などなかった」と別の高官の娘は述懐する。それでも、かれらは自分用の自動車や「すてきなアパート」もダーチャ(別荘)も与えられていたのだ。「ゴージャスな家具」はなかった。「本棚は別として、すべての製品には製造番号つきの真鍮製タグがついていた」
とはいえ、党のエリートと一般庶民は、国家によってはっきりと区別されていた、とフィッツパトリックは指摘する。
こうしたロシア式社会主義はその後、次第に変質していく。しかし、ロシア社会主義による社会主義の原型的理念が、「われら」のあいだにも染みついていたことは、中国の「文化大革命」や日本赤軍をみても、はっきりと見て取れるのである。根本から考えなおすことが求められていた。



