満州事変──美濃部達吉遠望(62) [美濃部達吉遠望]

1931年(昭和6年)5月16日に政府は官吏減俸を断行すると表明した。これにたいし、鉄道省や逓信省の職員から集団的な反対運動が巻き起こった。その騒ぎを収めるため、政府は段階的に減額率を首相で20%、判任官(役所による直接任用者)で3%と定め、それ以下の下級者はさしあたり減俸しないことにした。
減俸の実施は6月1日からとし、4万6000人の官吏が対象となった。当時の首相の年俸は1万2000円(現在でいえば3600万円程度か)、減俸対象となった中堅官吏の年収は2400円程度(同じく720万円程度)だったという。
減俸の背景には税収の落ちこみがある。政府は予算の節約によって、財政危機を乗り越えようとする姿勢を示した。それが同時に不況下における国民のがまんを促すものとなると考えていた。ケインズ政策にみられるような、赤字財政による農村救済策や都市の失業対策は取られなかった。
民政党政府は、浜口政権以来、当初、官吏だけではなく判事まで含む減俸を打ちだしていた。裁判所や役所の多くの職員から反発の声が挙がり、ストライキまでおこりそうな気配となったのはとうぜんである。それが、けっきょくは第2次若槻政権の妥協案で、減俸が決まった。
このとき、美濃部達吉は時代が変わったという感慨をいだいた。
「中央公論」7月号にこう書いている。
かつて官僚といえば「上命下従」で、ほとんど軍隊的な規律が保たれていたものだが、「旧時代のような軍隊的の規律は今日の官僚に対しては、もはや望むべからざるに至った」。
その理由として、達吉は官吏の経済的地位の低下、自尊心の減退などを挙げている。官僚といえども、いまはかつての武士のような特権階級ではなく、高等官を別とすれば、社会からとりわけ尊敬されることもなく、経済的にみても一般人民と変わらない存在になっている。
加えて、日本の政治が官僚政治から政党政治に変わったことが、官吏の本質に重要な変化をもたらした。
薩長藩閥が政権を握る官僚政治の時代においては、官僚は絶対にその権威に服従しなければならなかった。ところが、政党政治がはじまると、政府と官僚の関係は一変した。
そこから「官僚の政党化」と「官僚の独立化」というまったく相反する傾向が生じた、と達吉はいう。
官僚の政党化というのは、官僚が政友会系か民政党系かというように政治的色彩を帯びることを指す。そのいっぽうで、官僚が政府から相対的に独立した勢力をもつようになったのもたしかだった。
達吉は官僚の独立化をむしろ支持する。
〈私は政党政治の下において、官僚がその所属の長官に対し、ただ命これ奉じ、いかに無理な命令でも絶対服従の地位に立つことをもって、望ましい状態であるとは信じない。むしろ反対に、官僚が独立の地位を有せねばならぬことを自覚し、政党の勢力から超越して、法律と正義とを保持し、政党政府がその政党的見地からみだりにこれを蹂躙せんとする場合には、敢然としてこれに反対するだけの勇気あらんことを望むものである。〉
達吉は、政党政治下における官僚が「政党の勢力から超越して、法律と正義とを保持し」、みずからの仕事への気概をもつことを望んでいた。
いっぽうで、達吉は今回の政府による減俸に官吏が反対したことに同情していた。国庫の収入不足の犠牲を官吏のみに負わせるのは理不尽であって、官吏が反対運動を起こしたのも無理ないと考えていた。
官吏の俸給は勅令によって定められており、法律を改正しなくても実施できるようになっていた。
政府は当初、裁判所の判事にたいしても減俸を実施しようとしたが、反対運動にあってそれを断念した。判事の俸給は裁判所構成法によって保証されていたからである。判事はその一身上の権利が行政権によって左右されないよう法律上、保護されていたのだ。
そこで、政府は官吏にしぼって減俸を実施することにしたのだが、達吉はそれは官吏の財産権を侵害するものだと論ずる。官吏の給与は国家に雇用され、国家のために勤務する報酬として与えられているもので、官吏はその官職にあるかぎり、少なくとも定められた俸給を請求しうる権利を有しているはずだという。
今回、政府が官吏にのみ減俸を強いるのも不公平だった。経費削減をいうのなら、その範囲は恩給や議員の歳費、裁判所の判事にもおよばなければならない。だが、それらは法律の改正を必要とするため、政府は安直に法改正を必要としない官吏の俸給のみを減俸の対象とした。
「それは実質においては官吏のみにその減額高に相当するだけの特別所得税を課するのと同様である」と、達吉はいう。
それでも政府は官吏の減俸を断行した。大不況のもと国民が苦しい生活を強いられているのだから、せめて官吏の減俸という姿勢を示さなければ、政府への国民の反発がますます高まると考えたのかもしれない。
また、蔵相の井上準之助がいうように、率先して官吏が減俸に甘んじることによって、国民が節約意識を高め、緊張して経済的苦難に立ち向かう雰囲気が生まれると思ったのかもしれない。
だが、そうした政府のがまん政策は裏目に出る。政府への反発はむしろ高まっていた。それが爆発したのは、本土から遠く離れた満州においてである。
歴史家の半藤一利によると、満州の制覇を構想したのは、関東軍作戦参謀の石原莞爾(かんじ)だった。石原は世界最終戦はアメリカとの持久戦になると考え、日本がそれに勝利するためには満州を拠点にして国力を高めなければならないと思っていたという。
石原の案を受けて、1931年(昭和6年)6月、参謀本部は「満蒙問題解決方策大綱」を作成した。当時、すでに日本国内では「満蒙は日本の生命線」という言い方が定着するようになっていた。
陸軍が目指したのは満州を日本の植民地にすることである。だが、いきなりは無理なので、当面は満州を独立国にし、そこに親日政権を打ち立てることを目標とした。
昭和天皇は早くから満州での軍の不穏な動きを憂慮していた。6月にはいると、天皇は側近のアドバイスを受け、若槻内閣の陸相、南次郎に軍規を引き締めるよう命じた。首相の若槻にも満蒙問題については日中親善を基調にするようにと話している。満州でことをおこすなと示唆したのである。
ところが、6月27日に中村震太郎大尉がスパイ容疑で中国軍に殺され、7月2日に中国人と日本人が衝突する万宝山事件が発生すると、日本国内では満州での軍事出動を促す声が高まっていく。
政府は万一の事態が発生するのを恐れ、満蒙の問題は軍が先走らず、外務大臣に任せるよう、何度も南陸相に釘を差した。南はそれに従うような素振りを見せながら、そのかたわら関東軍の方針を是認し、9月28日の謀略実施を認めていたという。
8月1日には本庄繁が関東軍司令官に任命された。8月中旬、関東軍の高級参謀、板垣征四郎が上京し、永田鉄山軍事課長、岡村寧次(やすじ)補任課長、今村均作戦課長、建川美次(よしつぐ)作戦部長と極秘会談をもち、作戦を綿密に打ち合わせている。
その作戦は単純そのもので、満鉄の線路を隠密裏に爆破し、それを中国軍(奉天軍)のせいにして、関東軍が出動するというものだった。
ところが、いざ実行という段階になって、南陸相が急に慎重になった。9月14日、南は関東軍に思いとどまるよう説得するため、建川作戦部長を満州に派遣した。
作戦中止を勧告するため建川がやってくることを知った関東軍の板垣征四郎や石原莞爾は決断を迫られる。そして、いったんは中止を決意するものの、むしろ、ここまで来たらやってしまおうという空気が強くなり、9月28日の予定を18日に早めることにした。
すでに実行部隊は奉天郊外の柳条湖で、いつでも爆薬を仕掛けられるよう待機していた。思いとどまるよう説得にきた建川が奉天の料亭で接待を受けているさなかの9月18日午後10時20分、柳条湖付近で鉄道が爆破された。
その情報がはいると、鉄道爆破は中国軍によるものだとして、関東軍はただちに出動し、張学良軍が本拠としている奉天城および郊外の北大営を攻撃、占拠した。このとき張学良は北平(北京)に滞在していた。
柳条湖事件勃発にさいし、政府はあくまでも不拡大方針で臨んだ。
ところが、いったん動きはじめた軍の勢いは止まらない。
9月19日には奉天につづき長春、21日には吉林が占領される。この日、林銑十郎が率いる朝鮮軍が鴨緑江を越えて、天皇の許可がないまま満州にはいった。ほんらいなら統帥権干犯となる朝鮮軍のこの単独行動を、政府は閣議で事後承認せざるを得なかった。
こうして満州事変は拡大していく。10月8日には張学良政府の所在地である錦州が爆撃され、11月19日にはチチハル、翌1932年2月5日にはハルビンが占領された。そして3月1日には満州国建国が宣言されることになるのである。
こうした電光石火の動きをみて、朝日新聞や東京日日新聞など、それまで軍に批判的だった新聞は、手のひらを返したように軍を全面的に応援し、民衆の好戦的意欲をあおるようになった。
立花隆はこう書いている。
〈満州事変というと、あの広大な満州の片すみで起きた小さな戦火のような気がするかもしれないが、それまで遼東半島の先端部の租借地(旅順、大連)と満鉄の付属地の管理権しか持っていなかった日本が、小さな爆破事件(実は関東軍特務の自作自演の陰謀)を口実に、一挙にいまの日本本土の三倍という広大な土地を電光石火の作戦で手中にしてしまったという一大軍事作戦なのである。そしてそこに、アッという間に、日本の手で新しい国家を作りあげてしまったが、その国家は、政治も経済も軍事もすべて日本が完全コントロールする人工国家だった。事実上、日本の満州領有がなされたのである。〉
こうして世界恐慌の波が収まらないなか、日本は戦争という一見勇ましい突破口を選択したのである。
行財政整理座談会──美濃部達吉遠望(61) [美濃部達吉遠望]

1931年(昭和6年)5月15日の午後、美濃部達吉は東京朝日新聞の企画した「行財政整理座談会」に出席するため、帝国ホテルにはいった。
この日の出席者は達吉を含め、井上準之助(蔵相)、田中隆三(文相)、久原房之助(政友会幹事長)、山本条太郎(政友会政調会長)、山道襄一(民政党幹事長)、武藤山治(衆院議員、元鐘紡社長)、藤原銀次郎(貴族院議員、王子製紙社長)、上田貞次郎(東京商大教授)など16人だった。
5時間におよぶ活発な議論が交わされ、達吉も持論の陸海軍大臣文官制などを主張したが、話はまとまらず、日をあらため、6月2日に第2回目の座談会を開くことになった。このときも、達吉は出席し、随所で発言している。
東京朝日新聞は5月16日から6月14日にかけ、座談会の内容を紙面に連載した。のちに『打開の道を討して』と題し、「朝日民衆講座」シリーズの1冊として単行本としても刊行されている。
この座談会では、さまざまな行財政改革案が出された。行政面では省庁の統合、事務の簡素化、民間への委託などが提起され、財政面では恩給法の改正、補助金や機密費の縮小、官吏の減員減俸、官業の整理、特別会計の改善、公債問題、郵便貯金の運用改善などが話しあわれた。さらに討議は軍制の改革や軍事費の整理、国防計画にまでおよんだため、出席しなかった陸軍内部からは強い反発が巻き起こった。
この座談会が開かれた背景には、1929年の世界恐慌以来の不景気を受けて税収が落ちこみ、民政党の若槻内閣が苦しい予算編成を強いられていたことがある。緊縮財政のもと、行財政の整理が求められていた。
第二次若槻内閣は経済重視の内閣だった。金本位制(金解禁)のもと固定通貨レートを維持しながら、世界恐慌後の不況に対応するというむずかしい舵取りを迫られていた。
経済界ではいわゆる昭和恐慌のもと、カルテルが結ばれ、産業の合理化が進められていたが、政府も同様に官吏の減俸を実施し、さらに陸軍の整理に踏みこもうとしているところだった。不況が深刻化するなか、農村は疲弊し、都市では失業が増えていた。
この座談会で、達吉は忌憚のない意見を述べているが、ここではそのひとつを挙げておこう。長い引用になるけれども、かれの話しぶりが伝わってくる。
〈私は何ら経験もありませぬし深い考えもないですが、まず根本において決しなければならぬ問題は、私は政府のやるべき仕事の範囲、これを現在より縮小すべきかどうかということがまず第一の問題じゃないかと思うのであります。もし政府の今までやっておる仕事が政府のなすべき正当なる任務であるといたしますならば、たいした整理は行われないのでありますが、私はいま政府のやっておることは余計なことをしておる。政府のなすべからざることにまで手をだしておることがかなり多くはなかろうか、すなわち政府の任務をむしろ縮小するということに方針をとることが国民の福利の方面からいっても適当ではなかろうかと思っておるのであります。
もっとも産業方面にいたりますと、だんだん政治と経済との関係が密接になり、ことに自由放任主義ということが今日はとうていとりえない状態になっておるのでありまして、経済方面の仕事については政府の仕事が今後ますます増える傾きがありますが、たとえば自治団体[地方公共団体]にたいする監督であるとか、あるいは教育行政のことであるとかいうような問題になりますと、むしろ政府は下の者の自由にまかせる、政府はあまり干渉を加えない、したがって内務省の現在の仕事、文部省の現在の仕事というものはかなり縮小する余地はなかろうかと思うのであります。
したがって文部省は私は廃止せらるべきものではなかろうかと思っておる。内務省の一局とするのが適当であろう。またその後、事務の縮小のともない局課の廃合がありましょうが、そういうことは比較的小さい問題になるのでありますが、そこでこの自治体などを自由にまかしておくということに致しますると、いよいよ腐敗する、自治団体の種類によっては非常なる腐敗を来すことはないとも限らんのであります。しかし政府が監督しておったからといって、それを矯正するということはむずかしい。政府の力をもってしてはだんだんできなくなる。むしろ腐敗するものなら腐敗させて他日自覚するときまで構わずほうっておく。人民が自覚するまで自治団体のなすようにまかしておくくらいの覚悟をもってやるが至当ではなかろうか。〉
達吉は「小さい政府」を唱えているといってもよい。省庁を統合し、文部省などは内務省の内局にしてしまえばよいという。さらに地方のことは政府が干渉せず自治体にまかせるべきだと主張した。
いったん話しはじめると、堰を切ったようにとまらなくなる。達吉はさらにことばを継いで、とうとうと弁じる。
〈また同時に産業政策であるとか、教育行政、あるいはいろいろの施政が政党政治で内閣が変わるたびに方針が変化するということでは誠に困るのであります。政府の自由になしうる権力というものは現在よりはるかに縮小して、たとえば水力電気の許可を与えるというような権力も政府の自由にできないようにする。それには何か永久的な合議機関、何か裁判所のような──裁判所ではありませんが、そのような機関を設けて、許可とか認可というようなものについて企業者から出願するとそれに対して利害関係者から反対意見を述べることを得せしめる。裁判所みたいな公平な特殊の機関を設けてそれに許可とか認可とかやらせる。政府のなすべき仕事は、現在よりもはるかに縮小して、五人くらいの合議体で内閣を組織するというような方針にするのがよくはないかと思うのであります。しかしこれは私の空想でありまして実際のことは知らないのでありますからすぐ実行しうる策ではないかも知れません。井上さんにいわせれば不可能とおっしゃる(笑い声)かもしれませんが……〉
達吉が求めるのは、行政機能の継続性と、役所組織の簡素化、さらには役所本体から分離した許認可機関の設立、さらには小回りのきく政府といったところだろうか。
ここで達吉から水を向けられた蔵相の井上準之助は、和気藹々とした雰囲気のなかで、こう答えている。
〈私は美濃部君の説にはだいたい賛成です。政府があまり余計なことに手をだして干渉しすぎた弊害が、日本の政府のやり方にはかなり認められるだろうと思うのであります。美濃部君のように極端なことはすぐに行われようとは思いませんが、自分の頭からいえば美濃部さんの説に賛成しております。イギリス流のごく簡単な政治がよい政治と思う。文部大臣がここにおられるので文部省を内務省の一局とするようなことがよいか悪いか述べられませんけれども(笑い声)……美濃部さんのおっしゃることは参考になることが多いと私は思います。〉
井上には金本位制(金解禁)を堅持するという信念がある。日本は第一次世界大戦中に離脱した金本位制に昨年ようやく復帰したばかりだった。欧米のスタンダードである金本位制を維持してこそ、日本は世界の先進国だという誇りがある。そのためには、多少のがまんも必要だと考えていた。いまはしんぼうの時期だ。
だが、こうした緊縮政策に批判的な意見がなかったわけではない。鐘紡の元社長で、いまは衆議院議員として国民同志会を率いる武藤山治は、座談会の冒頭、こう発言していた。
〈行財政の整理の必要なことは私が申し述べるまでもありませぬが、今日は国民経済が非常に悲境に陥っている、不景気の極度に達している、この場合において、政府がはたして徹底的に行政財政の整理をするということの、経済界に及ぼしきたる影響はどうであろうか。もし今日政府が徹底的にこのうえ行政財政の整理を行えば、現在の経済界に向かって購買力の減少となり、消費のいっそう減退となって不景気をいやがうえにも促進する結果をおこすと私は思います。〉
政府のとっている緊縮政策が、金本位制と恐慌のダブルパンチのなか、よけいに不景気を長引かせるだけではないかと批判したのである。
これにたいし、蔵相の井上は、これから政府の実施しようとしている官吏の減俸策が、国民精神にいい意味での節約意識をもたらすにちがいないと論じている。
〈歳入が減ったならばそれに応じて歳出を減らす。歳出を減らすならば行政組織も変えてみよう。すなわち行政組織をただ今いうごとく簡捷(かんしょう)を計ろう、無駄なことをやめよう。こういうことを考えておる。これは私やむをえませぬと思います。……それは俸給を減らしたように何割というようにはわかりませんが、とにかく私は時代相当に国民が節約せんければならぬというので緊張するということが、実際収入の減るよりも世の中に至大の影響を与えると思う。……むしろ収入が実際減るということと人間が緊張するということは同じであって、非常にいいことじゃないかと思っている。〉
武藤が「それは間違っていると思います」と反論するのはとうぜんだった。官吏の減俸は経済の各方面に影響をもたらす。さらに現在の物価下落が、多くの企業倒産を招き、景気に悪影響をもたらすと指摘している。
この座談会に登場しない陸軍が、官吏の減俸につづくと思われる軍制の整理を苦々しく思っていたことはまちがいない。
実際、大正期以来の軍縮によって、陸軍では21個師団のうち4個師団が廃止され、将校約1200人を含め、9万6400人の軍人が解雇されていた。軍の内部では、政府によってこれ以上軍備縮小が進められるならば、満蒙問題が緊迫化するなか、国家は重大な危機に面するという思いがつのっていた。
そして、9月18日、ついに満洲事変が勃発する。
議会制度の危機と三月事件──美濃部達吉遠望(60) [美濃部達吉遠望]


1931年(昭和6年)2月9日、美濃部達吉は「議会制度の危機」という一文をまとめた。3月号の「中央公論」に掲載された。
首相の浜口雄幸は前年11月14日、右翼青年の銃撃を受けて重傷を負った。その入院中は、外相の幣原喜重郎が首相代理に就いた。
幣原は貴族院議員ではあったが民政党に属していなかった。そのため、はたして首相代理に就く資格があるのかという議論も党内であった。だが、緊急事態にともなう一時的な措置としては、与野党ともやむなしという方向でとりあえず折り合いがつけられた。
しかし、それでおとなしく野党が引き下がっていたわけではない。
2月3日、第59通常議会で、ロンドン条約に関して、幣原が「この条約はご批准になっております」と答弁した。これにたいし、政友会はその言葉尻をとらえ、これは天皇に責任を押しつけるものだ、と激しく批判する。議会は紛糾し、議場での大乱闘まで招いた末、審議が10日間停止された。
達吉の「議会制度の危機」はそのかんに執筆されたと思われる。
〈日本の近年の議会政治の実際を観察する者は、何人(なんぴと)といえどもそれが満足すべき状態にあると断言しうるものはないであろう。いずれの方面を見ても、悲観すべき材料のみ多く、その前途に光明を望むべき材料は、不幸にしてはなはだ乏しい。〉
そう書きだしたうえで、達吉はなぜ日本の議会政治がうまく機能しないのかを探ろうとしている。
ひとつは選挙にカネがかかりすぎること。さらに政府による選挙干渉が常態化していること。そのため、さまざまなスキャンダルが生じる。
議会の権威は失墜し、政府も議会を尊重しない。そのため政府は議会での審議ではなく、緊急勅令に頼りがちになる。枢密院がいまでも政治に大きな役割を果たしつづけている。
議会での質疑は本格的な論戦とはならず、言葉尻をとらえての言いがかりに終始することが多い。国体を危うくするとか、不忠不信といった言い方が横行し、新聞がまたそれをはやしたてる。議会不要論まで登場する始末だ。
議会制度に不信がつのっているのは日本だけではない。世界的な現象といえるだろう。とくに世界大戦後はロシアにソヴィエト政権が誕生し、イタリアでもファシスト政権が発足した。代議政治の衰運が声高く叫ばれている。
その原因としては、(1)議員の能力不足、(2)政党優先主義にもとづく議員の独立性喪失、(3)資金集めの過程で生じる政党と資本家の癒着、(4)政党間の争いの極端化や暴力による議事妨害、さらに(5)内閣の不安定などが挙げられる。
それでは議会制度は滅亡の運命を免れないのか、と達吉は問う。その恐れがないわけではない。すでにイタリアでは、ムッソリーニがあっという間にファシストの天下を確立してしまった。しかし、即断即決の独裁政治がいいのかといえば、「私は強くこれを否定したい」と達吉は断言する。
〈議会政治は、たとえいかなる弱点があるにせよ、なお他に見ることをえない大なる長所をもっているもので、われわれは極力これを擁護することに努めたいと思う。独裁政治は、国家非常の変に処する一時の権道としては、時に絶対に必要であることもあり、これによって議会政治におけるよりははるかに多く実際の効果を挙げうることがあるけれども、それは要するに、一時の過渡的の手段として認めうべきにとどまり、正常なる制度としては、われわれはこれを忍びえない。〉
議会政治の長所をもう一度見直すべきだ、と達吉はいう。
第一の長所は反対党にたいする寛容の態度だ。多数党も絶対不動の地位をもっているわけではなく、反対党もその存在の権利を主張することができる。これによって、暴力によらず、合法的な手段によって、政権の移動を実現することが可能になる。その点では、治安維持法は天下の悪法であり、立憲政治の根本精神を無視するものだと達吉は公言してはばからない。
独裁政治には、あくまでも反対である。
〈独裁政治は、ファシストの政治にせよ、コムミュニストの政治にせよ、いずれも一国一党の政治である。ただ政府に追随し服従する者のみが認容せられて、これに反対する者の存在を許さない。人民は自己の自由なる信念によって行動することをえないで、一に政府者に盲従することを余儀なくせらるる。政府に反対する者は、すなわち国賊であり、ただに自由の行動を許されないのみならず、その生命をすらも脅かさるる。スパイの暗中飛躍と正義を無視した暴力の圧迫とは、その必然の結果である。〉
たとえ、さまざまな欠点はあろうとも、議会政治をよしとするほかない。
議会政治の第二の長所、それは「国の政治を公開して国民の批判の下に立たしむることにある」。議会の討論がいかに低劣なものであっても、その言論は新聞によって報道され、国民の政治思想が刺激されることはまちがいない。いかに政府の権力が強大でも、議会があれば国民環視のもとで政府の施政を批判することができるのであって、これが議会制度の価値ともいえる。批判を許さない独裁政治との大きなちがいである。
議会政治の第三の長所。それは国民の期待にもとづいて、政治を担う者が選ばれることである。国民は直接にはただ議員を選出するだけだが、その選挙結果によって、多数を占めた政党が内閣を組織する大命を受けることになるのが立憲政治の原則である。
こうした議会政治の長所を維持するためには、現行の選挙制度を刷新し、各政党の責任のもと、能力のある議員が選ばれるように工夫しなければならないし、それによって言論と寛容にもとづく政治を実現しなければならない、と達吉は訴えている。
しかし、現実は達吉のそんな思いとは逆方向に進んでいた。
まさに達吉の論考が発表されたころ、軍によるクーデター計画が持ちあがっていた。
首謀者は陸軍参謀本部ロシア班長の橋本欣五郎。中国大陸における政府の無策に業を煮やしていた。
橋本は陸軍内に「桜会」と称する青年将校の集まりを組織した。軍事クーデターにより民政党の浜口政権を倒し、陸軍大臣の宇垣一成を首班とする内閣をつくるのが目的だった。
「三月事件」と呼ばれる。
実際、計画は着々と進行していた。右翼思想家の大川周明も賛同し、右翼団体、大行社の清水行之助(こうのすけ)、国家社会主義者で社会民衆党の赤松克麿(かつまろ)も計画に加わることになっていた。
計画では3月20日ごろに、社会民衆党などの組織するデモ隊が国会を包囲し、右翼団体や軍の一部が民政党や政友会などの本部、さらには首相官邸を襲う。そして、その混乱に乗じて、東京の第一師団が出動し、戒厳令を布き、浜口首相に辞任を迫る。こうして、宇垣陸相による軍事政権を樹立するというものだった。
だが、肝心の宇垣が時期尚早として動かず、軍の内部でも反対意見があって、計画は頓挫する。
それこそ統帥権干犯というべき机上のクーデター計画だった。
にもかかわらず、軍の内部から議会政治を否定し、軍事政権を樹立するという発想が生まれたという点で、三月事件はその後につづく日本的ファシズムへの道を開く契機となった。
野党政友会の激しい要求にもとづいて、療養に努めていた浜口首相は無理を押して、3月10日に衆議院に出席し、翌日も貴族院で答弁に立った。その後も、野党の答弁要求はやまず、その無理がたたって、4月4日に再入院し、13日に首相を辞任する。
後任には、元老西園寺公望の推挙により、ふたたび若槻礼次郎が首相の座についた。
三月事件の実相は、宮中も夏まで知ることはなく、昭和天皇の耳に入れられることもなかった。
紛糾する統帥権問題と浜口首相暗殺未遂事件──美濃部達吉遠望(59) [美濃部達吉遠望]

野党政友会が統帥権干犯という政治用語をもちだして政府を攻撃しつづける喧噪のなか、1930年(昭和5年)5月13日に第58特別議会は終了した。しかし、ロンドン海軍軍縮条約問題は、これで終結したわけではなかった。議会閉会後は国家主義団体による条約反対運動が活発になった。
条約が発効するには批准という手続きが必要だった。明治憲法下においては、条約批准はあくまでも天皇の大権に属し、そのためには枢密院の決議を要した。反対運動が活発になったのは、枢密院にはたらきかけるためでもある。
ロンドンから帰国した財部海相が5月19日に昭和天皇に会議の内容を報告すると、天皇は海相の労をねぎらい、早期の条約批准を督促した。天皇はあくまでもアメリカやイギリスと協調した軍縮を支持している。
政府と海軍の関係は相変わらずぎくしゃくしていた。
6月5日、海軍軍令部次長の末次信正は定例の進講をおこなったさい、条約批判を展開し、天皇を不愉快な思いにさせている。
さらに6月10日、軍令部長の加藤寛治が、従来の慣例を破って、海相ではなく天皇に直接辞表を提出した。加藤には過日、海軍出身の侍従長、鈴木貫太郎に天皇への上奏をはばまれ、軍令部の反対を伝えられないままロンドン条約締結の回訓が出されたことにたいする遺憾の思いがつのっていた。
加藤による異例の行動に宮中は色めき立つが、事態は穏便のうちに収拾され、翌日、新たな軍令部長に谷口尚真海軍大将、軍令部次長に永野修身が任命された。
右翼団体はこうした経緯を横目にみながら、天皇側近の鈴木侍従長や牧野内大臣が軍令部の意向を握りつぶしたとして、かれらを攻撃する文書を新聞などに流しつづけた。
そして、ロンドン条約は7月24日から枢密院での審議がはじまり、10月1日にようやく可決される。その間、政府は裏工作をおこたらず、政友会は右翼団体とともに、政府を攻撃しつづけていた。
10月2日、ロンドン海軍軍縮条約は批准された。浜口内閣の粘り勝ちである。財部彪海相は混乱を招いた責任を取って、翌日辞任した。
枢密院での審議がはかどらないなか、美濃部達吉は9月8日の「帝国大学新聞」に「ロンドン条約をめぐる論争」と題する評論を寄せている。
ロンドン条約をめぐる争いは次の2点だ、と達吉はいう。
第一、条約の調印について、あらかじめ海軍軍令部の同意を得ることが、法律上必要なのかどうか。
第二、条約で定められた兵力量がはたして国防上において十分なものなのか。
この2点について、達吉は軍令部の意見を斟酌(しんしゃく)し、尊重することはだいじだが、条約調印の判断はあくまでも海軍大臣を含む政府の責任にもとづくものと論じた。これは政府の編制大権と軍の統帥大権を区別する従来からの見解をくり返したものであり、兵力量の決定ももっぱら政府の責任に帰するとしたものである。
軍部当局の意見を絶対とするのは、国家にとってはかえって危険であり、軍部の意見にしたがうなら、軍備の縮小はけっして望めない、と達吉は言いきる。まして、条約の締結にあたっては、軍が直接関与すべきではない。
それなのに、枢密院の答弁で政府は、条約の締結にあたっては、軍令部の同意を得たなどと姑息(こそく)な答弁をし、みずからの責任を堂々と主張しなかった、と達吉は批判した。
さらに、こう述べている。
〈思うに、ロンドン条約をめぐる種々の論争は、その根底においては、平和主義と軍国主義の争いにほかならぬ。
明治時代のわが国策は、明白なる軍国主義であった。しかしてまた、それは国民の支援を得て、完全に成功して、日本をして世界的強国の一つたらしめたのである。
しかしながら、世界の大勢は一変した。今日においてなお軍国主義を維持することは、国家を危殆におとしいれる恐れあるものである。この形勢の推移を察せず、今もなお軍国主義をもって国を守るゆえんであるとし、兵権をもって政権の上に立たしめんと努めるのは、国家のために危うきことこの上もない。〉
ロンドン条約をめぐる争いは、達吉にいわせれば平和主義と軍国主義の戦いにほかならなかった。
軍がすでに調印された条約の批准をあくまでも阻みつづけようとする姿勢に達吉は危険な兆候を感じていた。
しかし、ロンドン海軍条約は、浜口内閣のやや姑息とはいえ揺るぎない姿勢によって、枢密院の審議をへて、ようやく批准されるにいたったのである。
だが、その過程で、統帥権の問題、すなわち軍の兵権が大きく浮上したことはまちがいなかった。
それから3年後の1933年(昭和8年)10月になって、達吉は「帝国大学新聞」に「いわゆる統帥権干犯問題」なる一文を寄せ、ロンドン海軍軍縮条約をめぐる論戦こそが、日本の大きな分かれ道だったと回顧することになる。
1931年には満洲事変、1932年には五・一五事件が発生していた。
犬養毅首相が暗殺されて以来、日本の政党政治は幕を閉じていたが、それでもまだ政党そのものは残っており、政友会の代議士のなかには相変わらず3年前のロンドン海軍軍縮条約は統帥権の干犯だったと言いつのっる者がいた。
統帥権干犯という旗を振ったのは、1932年末に急死した政友会の森恪(もりつとむ)で、軍部と結びつき、中国侵出を推し進めていた。
これにたいし、達吉は天皇の威光を背負った統帥権干犯という用語そのものを批判した。
〈統帥権とは申すまでもなく、天皇陛下が大元帥として陸海軍を統帥したまう大権である。もし他の何人(なんぴと)かが、陛下のご委任を受けて、ほしいままに陛下の陸海軍を指揮し統帥しようと企てたとすれば、それこそ統帥権の干犯であって、わが国体の尊厳を冒瀆するものであるが、その以外に統帥権の干犯というような不礼この上もない事柄のありうるはずはない。〉
ロンドン海軍条約締結のさい、反対論者は政府が海軍軍令部長の同意を得ないまま条約を締結したことが「統帥権干犯」にあたると主張した。だが、条約の締結はあくまでも政府の権限に属する。海軍大臣と軍令部長の意見が完全に一致しなかったのは遺憾なことだったかもしれないが、それを統帥権の干犯だと主張するのはいかがなものか。
達吉にいわせれば、それを統帥権干犯と大上段に批判するのは、軍令部長の権限と天皇の大権を混同するものである。それは、あたかも統帥権を軍令部長の権限と同一視するもので、それこそ統帥権の干犯にあたる。
〈統帥権の干犯などということは、国民の容易に口にすべき事柄ではない。もし真にそんなことが起こったとすれば、それこそ国体の破壊であって、陛下の陸海軍のほかに別個の陸海軍がこれと対立することになるのである。〉
達吉の懸念はすでに現実のものとなりつつある。独立性を主張する軍にたいし、政府のコントロールがきかなくなろうとしていた。さらに軍内部の分裂はまもなく1936年(昭和11年)の二・二六事件を事件を引き起こすことになる。その後、政府は実質上の軍政府へと変貌していく。
そんな事態を招かないよう、達吉は最後まで訴える。
〈政府が軍部の権限にまで立ちいってこれを侵犯することが避けなければならぬと同様に、軍部が政府の権限に立ちいってこれを侵犯することも、また極力これを避けねばならぬ。……もし国の外交も財政も教育も産業も軍部の意見によって指導せらるるようになったならば、それはただに聖旨にもとることの甚だしいのみならず国家の運命を危うくし国民の生活を不安に陥いるるものである。〉
こうして統帥権干犯という用語が独り歩きするようになる前、ひとつのテロ事件が発生する。ロンドン海軍軍縮条約が批准されて、ひと月ほどたった1930年(昭和5年)11月14日のことである。
浜口首相は東京駅の第4ホームから、午前9時発の神戸行き特急「燕」に乗ろうとしていた。岡山県でおこなわれる陸軍大演習の参観に向かおうとしていたのだ。そのとき至近距離から銃撃された。犯人は右翼団体、愛国社に属する24歳の青年、佐郷屋留雄(さごうやとめお)だった。
浜口は腹部を撃たれたが、駅長室に運びこまれ、駆けつけた東大医学部教授、塩田広重によって輸血をほどこされた。その後、東大病院に搬送され、手術の末、一命を取り留めたものの、臨時首相として一時、外相の幣原喜重郎を指名したあと、首相に復帰したものの翌年4月に辞任。その無理がたたって翌年8月26日に死亡した。
三浦展『大下流国家』『永続孤独社会』を読む(2) [時事]

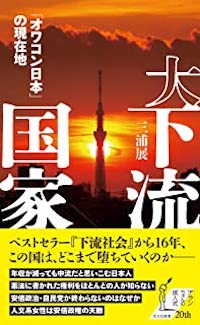
きょうは前回につづき三浦展さんの『永続孤独社会』を取りあげてみよう。
本書は『第四の消費』の続編とみてよい。そこで、第四の消費とは何かがまず説明されなければならない。
消費社会が誕生するのは、産業革命によって大量の商品が生みだされ、それを消費する消費者が登場してからだ。そうした消費社会が生まれたのは、日本では大正時代にはいってからだとされる。
著者によれば、「第一の消費社会」が登場するのは1912年から37年にかけてだ。そのあと、戦争によって、消費社会は中断される(異論もあるだろう)。
この時代、東京、大阪などの大都市で人口が増え、モダン文化が興隆し、大衆消費社会が生まれる。衣食住が洋風化し、ラジオ放送がはじまり、多くの雑誌が発刊され、娯楽文化が花開き、郊外住宅が開発され、キャラメルやカルピス、ウィスキーなども発売されている。ターミナル駅に多くの百貨店が開業し、鉄筋コンクリート造りのアパートがつくられた。
「第二の消費社会」は1945年から1974年にかけてだ。
高度経済成長時代と呼ばれるこの時代は、洗濯機、冷蔵庫、テレビの「三種の神器」、さらにカー、クーラー、カラーテレビ「3C」が普及する。マイホーム、マイカー時代が到来する。少品種大量生産がこの時代の特徴だ。
第二の消費社会はオイルショックによって終わりを告げ、そのあと「第三の消費社会」がはじまる。1975年から1997年にかけて、消費の流れは「家族から個人へ」と変化した。
ウオークマンやパソコン、軽自動車、ミニコンなどが登場し、個人をターゲットにした多品種少量生産が主流になる。第二の消費社会で主流だったスーパーに代わってコンビニが売り上げを伸ばす。ファミリーレストランやファストフード店などの外食産業が急成長する。ブランド志向、高級化、カタログ文化が進む。物質主義から自分らしさ、生きがいなど心の領域が重視されるようになる。ディスカバージャパンがはじまる時代でもある。
そんな第三の消費社会も、山一証券が破綻した1997年には終わり、1998年以降、「第四の消費社会」がはじまったと著者はみている。この時代には、二度の大震災がおこり、非正規雇用が広がり、個人化、孤立化が進んだ。自殺者も多くなり、凶悪犯罪も目立つようになった。
この時代の特徴は脱私有化志向だという。フリーマーケットやリサイクル、古着、リノベーションが進んだ。できるだけモノを買わない、貯めない、自分だけで私有せずみんなで共有するという考え方が生まれてきた。シェアやレンタルが注目されるようになった。こうした傾向は3・11の東日本大震災後にとりわけ加速されたという。
「人々が、モノ、コト、場所、時間、知恵、力などをシェアすることで価値を共有し、共感し、分断ではなくつながりを生み出す」といった時代がはじまったのだ。日本志向、地方志向、シンプル志向、エコ志向が強くなっている。シェアハウスも人気を呼んでいる。
衣食住、文化、レジャーなどの基本的欲求が満たされるようになったいま、人びとはどこに向かおうとしているのか。
消費は生産の一部ではない、と著者はいう。消費社会が発展していくにつれ、消費は単なる物の消費から人間的サービスの消費と変わり、そこからさらに、みずからの充足を求めて、みずからの生活を創りだし、人と人との関係を創りだすものになりつつあるという。
いまは魔法のような(ヴァーチャルな)時代だ。生活の実感がない。
魔法の時代はいまも進行している。パソコンやスマホ、ゲーム、インスタ、ヴァーチャルな映像や音楽が日常を支配している。
そんななかで、自分なりの生活を取り戻すこころみもはじまっている。中古品を買うどころか、拾ったものを利用したり、自分で考えて必要なものをつくるのもトレンドだという。
買ったモノに翻弄されて人生を消費するよりも、充実した時間を過ごして満足する方向が模索されはじめている。人と人とのコミュニケーションに楽しさを見つけ、悲しさを受け止めてもらえる、そんな共感の場がこれからの社会に求められるという。
生涯未婚率や離婚率の高さ、伴侶との離別などが重なり、これからの社会は総シングル化していくといわれる。親に寄生するパラサイトシングルも、単独世帯もどんどん高齢化している。
シングル世帯だけではない。病人や高齢者をかかえた家庭も多くなっている。児童虐待も増えている。これまで家庭内のケアは主に主婦が担っていたが、いまやそんな時代ではない。ケアは個人がお金を出して得なければならなくなった。
住宅の維持・管理や高齢者の世話、子どもの教育、医療も、時に食事も、ある意味ではケアであって、そうしたケア市場が膨らんでいる。
加えてリスク社会である。
結婚や親の介護、子育て、老後、仕事、健康、資産管理にもリスクがある。コロナやインフルエンザ、天候異変、テロ、大地震、津波、原発事故にも備えなくてはならない。こんななかで伸びているのは、旅行、娯楽、散策などの時間消費、健康消費、癒やし消費くらいなものだという。
ひとりで生きていく覚悟をする女性はジムやヨガに通い、癒やしよりも強さを求めるようになった。
シェアハウスやルームシェアは増えているが、2019年以降は伸び悩んでいる。住宅のリノベーションもマンネリ気味だ。つながりやきずなにも飽きがきている。シンプル志向や日本志向も頭打ちになりつつある。「第四の消費」もそろそろ曲がり角にきている。
ここで、著者は最近の状況を「永続孤独社会」という呼び方で表現している。
落ちこぼれ、孤独、格差、自殺、虐待、殺人。どう考えても、いまの社会はおかしい。そんな重要なシグナルが発されているのに、人はそれは自分とは無関係と思い込み、ただのニュースとして処理しようとする。
若い人のあいだでも、「人生を楽しみたい」と思う人より、「無気力あきらめ派」が増えているという。やりたいと願う仕事につけない人が増えている。
若い男性、若い女性、一人暮らしの人、いわゆるパラサイトシングルの人ほど孤独感が強いのだという。これからは生涯未婚の単独世帯が増えていく。いまは孤独でなくても、人は離婚や死別を含め、たくさんの経済リスクや「孤独になるリスク」をかかえている。介護という問題もある。家族を介護する人は孤独度が高まる傾向がある。
「永続孤独社会」がはじまっているのだ。
若い世代の多くは家族や友人・知人とのコミュニケーションがうまくいかないこと、健康への不安などから孤独を感じるという。恋人がいても孤独を感じる人が増えているらしい。加えて、未婚期間が長いこと、あるいは生涯未婚であることが、孤独感をいやます。場合によっては、それに親の介護がのしかかってくる。
未婚が多いのは、条件や性格、価値観を含め、人と人とのマッチングがむずかしいからである。商品を選ぶように結婚相手を選ぼうとすると、満足できそうな相手はなかなか見つからないし、選択に失敗するということも大いにありうる。そこで「あきらめ派」も増えてくる。
「親ガチャ」(親を選べない)という言い方がはやり、「運命」や「宿命」を強く感じ、そのくせ「奇跡」がおこるのを待っているのが、現代の若者に共通する心象風景だという。
「個人化」が進み、各人が各人の「多様性」を認め、「寛容性」をよそおい、互いに交わらない人間関係のもとで暮らす孤独社会が生まれている。
そこからはみ出して、接近してくる人は「うざい」として排斥される。永続的な愛情などは信じられなくなり、それに代わって、一時の「つながり」や「ご縁」が尊重される。
恋愛もストリーミング化され、気分に応じて相手が選択される。さらにメタバースの時代になると、自分好みの恋愛対象がつくられる。
近年、若者の性行動は消極化しているといわれる。SNSを利用した事件もおきたりするが、どちらかというとリアルからの撤退が進み、ヴァーチャルで満足する傾向が進んでいるのではないかという。
メタバース時代には「第四の消費」も終わっているかもしれない。
「第五の消費」がどのようなものになるかは、まだわからない、と著者はいう。しかし、すでにはじまっているメタバースに著者は懐疑的である。
「本当に孤独に陥ってメタバースに逃げ込まなくてはならない前に、シェア的なライフスタイルの中に自分を自然に位置づけられるような社会・コミュニティの仕組みが必要であろう」と書いているからである。
無駄なものは買わず、のんびりマイペースで、人生を楽しむというのが「第四の消費」の方向だが、実際は生活がきつきつで、それどころではない人が増えている。
著者が探ろうとしているのは、新しいまちづくりだ。
コロナ禍によって仕事や子育てなどでダメージを受けた若者と女性たちが主導権を握って、まちをつくりなおしていかなければならない。そのためには「若者特区」や「女性特区」のようなものをつくらないといけないと提唱している。
消費社会を推し進めるだけでは、人はすりつぶされてしまうばかりだ。生活の場をつくりなおすことが求められている。
三浦展『大下流国家』『永続孤独社会』 を読む(1) [時事]
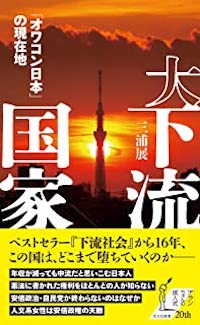

最近はすっかり隠居生活なので、世の中に疎くなっている。フェイスブックで知り合いになっている三浦展(あつし)さんの新書を2冊読んでみることにした。それにしても、次々と本を出しつづける三浦さんのパワーには驚く。わたしの知るのはそのごく一端にすぎない。
『大下流社会』のサブタイトルは「オワコン日本」の現在地となっている。
そもそもオワコンという言い方を知らなかった。終わったコンテンツをさすのだという。いま日本はオワコン状態にはいり、大半の人が日本の繁栄の時代は終わっていると感じている。とはいえ、自民党支持者のなかでは、そのことを認めない人も多いという。
国連の人口予測によると、2060年の日本の人口予測は約9833万人。2020年の1億2648万人からかなり減って、その順位は現在の世界11位から20位に落ちると予測されている。もっと厳しい見方をする推計もある。
すると、とうぜん国内需要も減って、現在のGDP世界3位からも転落している可能性が高い。
世界からみて、日本はだんだん遅れた国になりつつある。論文数ランキングも落ち、留学生の数も減り、ジェンダーギャップはむしろ広がり、国連の幸福度調査も世界56位に甘んじ、報道自由度ランキングは180カ国中67位、子どもの学力も伸び悩んでいる。
経済大国だった日本が「大下流国家」になろうとしているという。
消費格差も進む。中流商品が売れなくなり、商品は上流向けと下流向けに二極化した。それはシャンプーからパン、ヨーグルトなどの食品、スーツを含む衣料品、自動車におよぶ。
上流はたしかに存在する。しかし、それよりも中流の下流化が進んでいる。
ところが、不思議なことに、内閣府の階層意識調査では、2011年から20年の10年のあいだに、日本ではわずかながらも上流意識(13%から17%)が増え、下層意識(12%から10%)が減っている。まだまだ中流意識が強い。
いったいどういうことだろう。
正規雇用公務員の上流意識は高まっている。これにたいし、45〜54歳男性のパート・派遣は下流意識が82%となっている。そのあいだが、いわば「中流」だが、著者によると、この10年の特徴は「年収が500万円なくても、400万円前後でも中流であるという意識の変容が起こった」ことだという。
ちなみに、男性の年間平均給与額は1997年の577万7000円をピークに下がりつづけ、2013年から回復して、2019年にようやく539万7000円まで戻った。
バブル崩壊後、日本人は貧しくなった。そのなかでデフレが進行し、安く暮らせるようになったことが、給料が少なくなっても中流だという「ニセ中流」意識を生んだという。
二人以上世帯の消費支出は2000年の380万円7937円が2019年の352万547円と低下している。そのかんエンゲル係数は上昇した。しかし、日本人はそれほど生活に不満を感じていない。
コンビニやマクドナルド、ケンタッキー、丸亀うどんなどもあり、食べるものには不自由しないからだ。着るものもユニクロどころか、GU、ワークマンでじゅうぶんだ。メルカリやヤフオクで中古品を安く買える。映画や音楽もネット配信を利用すればいい。
じっさいは下流化しているのに、自分は中流と思いこむ「ニセ中流」が増えている。それが下流意識が減った(自分はいまでも中流と思い込んでいる)ことを示す統計の数字になって現れている。
2008年から2019年にかけてはリーマンショック後のデフレ時代だったにもかかわらず、生活満足度における日本人の不満の度合いは下がった(内閣府の調査では「まだまだ不満」、「きわめて不満だ」が、2008年には併せて38.4%だったのに、2019年には25%になっている)。
給料は上がらないが、物価も下がったからである。下流なれしたのかもしれない。公害や住宅難、石油ショック、リーマン・ショックなどのあった高度成長期やバブル期のほうが、ずっと日本人の不満度は高かった。
いまは、とりわけ不満を抱く20代男性の割合が低くなった。逆に女性は社会進出が進んだために、不満をもつことが多くなっているという。
著者によると、2011年から20年までの10年間で、20〜30代の年収300万〜400万台の満足度が増加しているという。つまり、「中の下」の満足度が上昇している。仕事があって、親子そろって楽しく食事ができればじゅうぶんという人が増えている。
田舎志向、人間関係志向、シンプル志向、エコ志向、ていねいな生活志向も増えているという。ブログの発信・書き込みをしたり、民泊をしたり、友達を多くつくったり、ものを増やさない生活をしたり、ルームシェアをしたり、クールビズを実践したり、エコバッグを持参したり、長く使える商品を購入したりといったことが、それなりに満足度を高めている。
自分の生活が「快適」で「愛」を感じられ、「平和」であればいいといった個人志向も強くなっている。それは家庭生活において、もっとも求められていることだ。
著者自身、「戦後日本社会の最大の価値はまさに社会の平和を実現、維持したことである」と指摘している。
いっぽう、「世の中をよくする」ことへの関心はますます薄れている。何もかも政治家まかせというわけではないが、やっかいごとは避けるきらいがある。。
個人の問題にたいする関心は大きい。社会保障の将来に不安をもち、貧富の差が拡大していることを懸念し、ネット上の誹謗中傷やブラック企業に憤り、教育にお金がかかりすぎることを疑問に思っている。
競争主義や成果主義、新自由主義的な価値観には抵抗があり、グローバル化や外国人の増加には積極的ではなく、まじめに働く人がむくわれるべきだと考える人が多い。
それでも、あまり挑戦的ではない生き方が浮かび上がる。これを保守化というのだろうか。
階層意識でみると、「下流」や「中の下」の人は、多くが毎日を生きるのが精一杯で、貧富の差が拡大している、ブラック企業が多い、年金・医療費など社会保障が心配と感じている。
いっぽう上流意識をもつ人は、生活保護が行きすぎだ、対中国・北朝鮮・韓国政策が軟弱だ、日本人はのんびりしすぎている、正規雇用されない人は能力や性格に問題がある、強力な政治的リーダーが必要だ、テレビがばかばかしい、新聞は信用できないなどと感じている。
著者は第2次安倍政権(2012〜20年)の評価について独自の調査をおこなっている(これは本書が出版された2021年段階の評価である)。
日本の下流社会化を促進したのは安倍政権だ、と著者は断言する。
しかし、全体の傾向として、安倍政権を「評価する」は約40%、「評価しない」は約32%だった。男女差はあまりないが、男性にくらべ女性のほうが、評価する割合は低い。
それほど強く支持されていたわけではないが、かといって反対が圧倒的だったわけでもない。
若い世代は自民党支持が多いといわれるが、じっさいには「どちらでもない」が多く、「評価しない」が少ない。25〜34歳の男性の単独世帯は「まあ評価する」が多く、25〜34歳のシングルマザー世帯は「評価する」はきわめて少ない。
学歴別にみると、男性の高学歴者ほど安倍政権にたいする評価は高く、逆に女性の高学歴者は「評価する」が少なくなっている。
収入別でいうと、高収入の男性ほど安倍政権にたいする評価は高く、不思議なことに高収入の女性は「評価する」が減っている。
年齢別にみると、若い男性で高収入の人は安倍政権への評価が高い。しかし、低収入の人になると、「評価しない」が多くなる。
年収200万円未満の人は35歳〜44歳の男性では「評価しない」が44%、同じく45歳〜54歳の男性では「評価しない」が45%になる。
要するに、高収入の人ほど評価は高くなり、低収入の人ほど評価は低くなる。また、この15年間で「豊かになった」と感じる人ほど評価は高く、「貧しくなった」と感じる人ほど評価は低い。
パート・派遣の人や離別女性の安倍政権評価は低く、専業主婦にも思ったより人気がない。
階層意識が「上」になるほど安倍政権への評価が高いのは、それが自民党支持層と重なっているからだろう。これにたいし、階層が低くなると評価も相対的に低くなるが、アンケートでは下流の人でも、「評価しない」傾向が39%なのに「評価する」が35%と拮抗している。
著者によると、階層意識が「上」でも3割弱、安倍政権を評価しない人がいるが、これはインテリ層、リベラル層だという。いっぽう、階層が「中の下」や「下」なのに評価する人は、中年男性が多く、二流大学卒でボンボンというところに何となく親しみを感じているようだという。
儲け志向の人は安倍政権を評価し、正義志向の人は評価しない傾向がある。しかし、いまの日本では「世の中をよくする」という志向はますます弱まっており、社会主義はとっくに過去のイデオロギーとなり、新自由主義的な価値観に適応することだけが求められているのが現実だという。
社会志向よりも個人志向が強まっている。社会への関心は薄れ、歴史は忘れられ、そこにネトウヨの言論がはいりこむ。ポピュリズムは好きだが、民主主義は好きではないという人が増えているのではないか、と著者は懸念する。
しかし、安倍政権の支持者が反知性主義的かというと、かならずしもそうではないという。たくさん本を読んでいる人も多い。けれども、それはどちらかというと経済書や実務書、技術書、小説などで、いわゆる人文書やジャーナリズム関係の本は少ない。
「若い世代の安倍支持・自民支持の多さは新聞を読まないからだ」と著者は断言する。書籍やマンガをスマホで閲覧し、SNSを積極的に利用し、ネットニュースをよく見る若者ほど自民支持の傾向が強いという。
ブランド品など高級品志向の強い人が安倍政権を評価するのはとうぜんかもしれない。タワーマンションに住み、フィットネスクラブに通い、容姿に気を遣い、経済・ビジネス書を読むタイプの人は概して安倍政権を支持していた。
安倍政権を支持するのは、愛国心や軍事力、強い外交、強力なリーダーシップを重視し、日本志向、排外的傾向が強いグループである。むしろ中流や下流の中年男性のなかに、そうした安倍支持者が多い。
上流・中流が安倍政権を評価するのは、主にアベノミクスと安倍外交にたいしてである。「中の下」を含む下流は、従来からのしきたりや保守性、反共意識、見た目のよさなどから安倍政権を支持しているという。
しかし、下流の中年男性は基本的には安倍政権を評価していない。経済的格差の拡大が、中年男性の評価を二極化していたという。
これにたいし、中流の人の「どちらでもない」派は、無党派層で政治にはさほど関心がない。別に安倍政権でもかまわないと思っていた。
さらに著者は「そもそも現在の若者は自民党を保守と思わず、共産党を保守と思い、維新を革新と思うのだという」とも書いている。
安倍政権とは何だったのかを問う時期がきている。本書がそうしたきっかけを与えてくれることはまちがいない。
統帥権とは何か──美濃部達吉遠望(58) [美濃部達吉遠望]

1930年(昭和5年)4月にロンドン海軍条約が調印されることになった時点で、美濃部達吉は「帝国大学新聞」にこう書いている。
〈日本の最初からの主張がそのまま貫徹せらるることを得なかったとはいえ、すべての国際協定は相互の譲歩と妥協とによってのみ成立しうべきものであるから、それもまことにやむをえないところといわねばならぬ。もし協定が不成立に終わり、再び無制限な製艦競争が行わるるものとすれば、それはわれわれ国民の忍びえないところで、協定の内容が十分の満足に値するものではないとしても、なおわれわれはその成立を喜ばねばならぬ。〉
ロンドンでは補助艦(巡洋艦、駆逐艦、潜水艦)の対米比率7割を確保するという政府目標はわずかに達成できなかったけれども、ともかくも無制限な軍備競争に歯止めがかかったことを達吉は喜んでいる。
しかし、なぜロンドン条約に関して軍部と内閣のあいだに意見の不一致がみられ、それが政争の具に化そうとしているのか。
海軍軍令部はあくまでも対米7割の要求を貫徹しようとし、これにたいし内閣は全権の交渉にもとづく妥協案を容認した。内閣が条約を締結したことにたいし、軍令部はその後もあくまでも反対する姿勢を示した。内閣は軍を統帥する天皇の大権を犯して、天皇の勅裁を仰ぎ、勝手に条約を結んだと思い詰めていた。
ここで、念のためにつけ加えておくと、昭和天皇自身は国際協調派であり、軍縮推進を支持する立場をとっており、むしろ軍の突出を懸念していたという事実を記しておかねばならないだろう。
海軍軍令部の主張に正当性はあるのか。
明治憲法にはたしかに「天皇は陸海軍を統帥す」と定められている。軍事の統帥権は直接天皇に属するのであって、内閣の関与を許すものではなかった。
しかし、ここで達吉は軍統帥の大権は軍編制の大権とは異なるという考え方をもちだす。軍の統帥権は軍の活動を指揮統率する権限であり、参謀本部や軍令部が責任をもつ。これにたいし、軍の編制権は軍の設置や規模、編制を決める権限であって、それは国の外交や財政にかかわる事柄である以上、国の政務に属し、内閣のみがその輔弼(ほひつ)の任にあたるというのである。
もちろん、ロンドンの海軍条約に関しても、軍令部や軍事参議院[軍事諮問機関]は意見を述べることができる。しかし、軍の編制権について責任を有するのは内閣であって、条約を調印するのも内閣の責任に属し、議会での討議をへて、条約の批准を審議するのは枢密院の役割である。
「故に条約上の批准はたとえそれが軍事に関するものであっても、純然たる国務上の行為であって、もはや帷幄(いあく)[天皇直属]の機関のこれに関与しうべきものではない」と、達吉は論じた。
4月23日から5月13日まで、第58特別議会が開かれた。
議会は冒頭から荒れて、議場は野党政友会による政府批判の場と化した。政友会の犬養毅(総裁)と鳩山一郎(総務)はともに軍部の独走を懸念する考え方をもちながらも、野党の立場から、ロンドン条約には国防上の欠陥があり、その調印は統帥権干犯にあたる、と激しく政府を批判した。これにたいし、浜口首相は答弁を拒否し、官僚的、非立憲的だとの非難を招くことになる。
ほんらい、議会は論戦の場であるべきである。それによって、国民が政治に関心をもち、政治的意識を高めることも期待できる。たとえ与党が議会で絶対多数を占めていたとしても、少数政党の鋭い質問に答えるのを余儀なくされるところに、達吉は立憲政治の妙味を感じていた。
今回の議会において政府は明白な答弁を回避しつづける姿勢をとりつづけた。重要な問題なのだから、政策論争があってしかるべきだと思わざるをえない。
いっぽうで、達吉は政府が不答弁主義を貫く理由がわからないでもなかった。
〈それはいうまでもなく、明白に政府の所信を言明することによって、政府と軍部との衝突を来(きた)さんことを恐れたためであって、すなわちこの問題に関して政府と軍部との間に、完全なる意見の一致を得ておらぬことを明示するものである。〉
そう記す達吉は日本の立憲政治の脆弱(ぜいじゃく)さを感じないわけにはいかない。日本の議会政治はようやく確立されたとはいえ、その政治基盤はじつにあやうい。
〈わが今日の状態においては、内閣の進退を左右すべき政治上の勢力として、衆議院は必ずしも重きをなすに足らず、その外に、貴族院があるのみならず、なお軍部があり、枢密院があるのであって、これがわが争うべからざる現状であり、しかしてそれは議会における海軍条約問題に関する論争の間にも、暗黙に示されたところである。〉
つまり、日本では貴族院はともかく、軍部や枢密院が反対すれば、たとえ議会で多数派を握る政党内閣であっても、たちまち崩壊してしまうのが現実だった。軍部には内閣に陸相や海相を送らないという奥の手があり、枢密院には内閣による緊急勅令案を拒否するという裏技があった。
そのため、政府は天皇をかさにきた軍部や枢密院を刺激しないよう万全の注意を払わねばならず、やむなく議会での不答弁主義を貫く事態もありえたのである。それは日本の議会主義の発達にとって、不幸な現象以外の何ものでもなかった。
それでも達吉が政府によるロンドン条約調印を擁護しつづけたのは、あくまでもデモクラシーにもとづく議会政治を守ろうとしたためである。
議会開催中、達吉は「東京朝日新聞」でも、政府を支持する論陣を張った。
天皇の大権のもと、「軍の統帥については、これを政府の職責の外に置き、専ら軍部当局者の自由活動に一任することは相当の理由あること」はいうまでもない。とはいえ、陸軍大臣や海軍大臣は現役の武官として政府の一角を占めている。
すると、陸海軍と陸海軍大臣を包含する政府とのあいだに完全なる意見の一致をみない場合はどのように考えればよいか。陸海軍は統帥の大権を有しているとしても、それにはおのずから限界があり、陸海軍編制の大権は政府に属しているとみるべきである、と達吉は主張する。
〈軍部の当局は、自ら戦争の任に当たるべき当事者であるから、いやが上にも戦闘力を強からしむることに努むるのが当然の傾向であって、外交、財政、経済、世界的思想の趨勢等政治上の関係を考慮することの乏しいのは免れがたいところである。これに絶対の価値を置くことは、国家をして軍国主義の弊に陥らしむる恐れがある。その意見はできるだけ尊重することが適当であるとしても、それはただ参考材料たるにとどめ、それをいかほどにまで採用するかは、もっぱら政府の決するところとなすことが、国家のために是非とも必要である。〉
達吉はそのように論じ、政府が議会で言えないことをいわば代弁した。
雑誌「改造」の6月号でも、達吉は統帥権と編制権は分離して考えるべきだと主張した。しかし、ここではそもそも統帥権の独立とは何かという問題にさらに踏みこんでいる。
〈統帥権の独立とは、陸海軍の統帥についての大権が内閣の責任の外に置かれ、内閣は全然それに関与することを得ず、したがってまた議会もこれを批判し論議しえないことをいう。かくのごとき原則は、立憲政治の普通の原則としては一般に認めらるるところではない。立憲政治は責任政治であり、国のすべての政治については[内閣が]国民に対し、ことに議会に対して責任をとるものであることを要求する。……その結果として陸海軍もまた内閣大臣の統轄の下に立ち、陸海軍の行動についても、内閣がその終局の責任を負担するものとせらるることが、各立憲国の普通の原則である。〉
ところが、なぜ日本においては、統帥権の独立というような変則がまかりとおっているのか。それは日本の憲法が旧ドイツ、オーストリアの憲法をとりいれたことに由来する。この両国だけは、陸海軍の統帥を他の一般国務と区別し、統帥権を皇帝の大権に属するものと規定していた。
統帥権独立の原則は主としてドイツで発達した制度だ、と達吉はいう。しかし、そのドイツでも革命後、統帥権の独立は認められなくなった。
「今日においては統帥権の独立というような原則は、日本を除くのほかは、世界のいずれの立憲国においても認めないところとなったということができる」
立憲政治の原則においては、統帥大権についても国務大臣がこれを輔弼し、その責にあたるのがとうぜんであり、統帥権の独立というような原則はまったく認めるべきではない。
とはいえ、日本では現実に統帥権が早くから一般の政務から分離されて、政府からある程度独立した地位を保ってきたのも事実である。統帥権に関して天皇を補佐するのは国務大臣ではなく、参謀本部や軍令部といった軍の機関であり、軍事参議院が天皇の諮詢(しじゅん)にあたることになっている。
しかしながら、統帥権のおよぶ範囲にはおのずから限界があり、それは軍令にかぎられ、軍の編制など軍政については大権を輔弼する任はもっぱら内閣に属する。こうした主張を達吉はくり返した。
さらに、政府が軍の主張におもねることなく、みずからの見識において兵力の量を定めることができるためには、現在のような陸海軍大臣の現役武官制を撤廃し、文官制を採用すべきだとも主張している。
達吉は明治憲法のアポリアにまで踏みこんでいた。



