4月でなく10月がピークだった──『グレート・インフルエンザ』を読む(3) [本]

「これはインフルエンザだった。ただのインフルエンザだった。圧倒的多数の患者は快方に向かった。患者は持ちこたえ、軽度な者も重篤な者もいたが回復していった」
著者はそう書いている。
にもかかわらず、1918年にただのインフルエンザ・ウイルスがなぜパンデミックを引き起こし、何千万もの人を死にいたらしめたのだろうか。
頭痛、発熱、悪寒、筋肉のしびれ、関節の痛み、呼吸不全、下痢、嘔吐、耳や目の痛み、嗅覚異常、鼻や気管支からの出血、精神障害、ありとあらゆる症状が重症感染者を襲った。死が訪れるのも急激だった。
人びとは手をこまぬいてインフルエンザの流行をみていたわけではない。医学者はこのインフルエンザ病原体を発見するとともに、その治療法やワクチンの開発に向け、懸命の努力をつづけていた。だが、インフルエンザ病原体が細菌ではなくウイルスであることがわかるのは、1930年代になってからだ。
ニューヨーク市では1918年9月15日に、はじめてインフルエンザによる死者がでた。当初、市は何の対策もとろうとしなかった。いたるところで感染がひろがるようになって、ようやく患者の隔離に踏み切った。しかし、病気はすぐにおさまるとの見方を示した。
だが、それは甘かった。感染者は何十万と増えていった。最終的にニューヨーク市の死者数は、市当局の発表で3万3000人に達する。だが、実際の死者数はもっと多かった、と著者はいう。市が途中で感染による死亡者数を数えるのをやめてしまったからである。
そのころ、アメリカ政府はどう動いていたのだろう。
著者によれば、「1918年の夏には、ウィルソン[大統領]は国民生活のあらゆる面に国策を徹底させ、国民の関心と意思をすべて戦争に集中させるための大きな官僚機構をつくりあげていた」。
経済は軍事管理下におかれていた。民主主義もまた制限されている。言論は統制され、政府に反対する者は容赦なく逮捕される状況だった。
参戦とともに、徴兵対象者は18歳から45歳までの男子にひろげられていた。基幹産業ではたらいていない者は全員招集の対象になった。
戦争末期になっても、ウィルソンは攻撃の手を緩めなかった。それどころか国を挙げて、完全な勝利に向けてさらに圧力を加えていた。インフルエンザ対策など見向きもされなかったわけである。
とはいえ、陸海軍でインフルエンザが蔓延しているのを無視するわけにはいかなかった。そのため、9月末に徴兵は一時中止された。
停戦まではまだ2カ月あった。ヨーロッパ戦線はまだ米兵の投入を求めていた。
そのころ兵員輸送船リバイアサン号が、多くの兵を乗せてバージニア州の港を出港していた。狭苦しいところに何百人もの男たちが詰め込まれ、船内は過密なうえ、換気が行き届かなかった。
港をでて48時間すると、医務室はインフルエンザで倒れた兵士や水兵でいっぱいになった。やがて地獄がはじまる。
海上での埋葬がはじまった。デッキに並べられた遺体は、名前を呼ばれ、つぎつぎ海に投げこまれていった。輸送船は浮かぶ棺桶と化した。
それでも参謀総長のマーチ大将は、ヨーロッパへ兵士を輸送するよう主張し、軍はこのあとも兵員輸送船をだしつづけた。
ウィルソン大統領は兵士のことを気にかけてはいたが、民間人にたいしてはそれ以上に何もしなかった。インフルエンザに関しては公衆衛生局長のルパート・ブルーに対策をゆだねただけで、そのルパートはさらに何もしなかったどころか、関連研究を妨害するほどだった。
9月17日には、西海岸のピュージェット湾でもインフルエンザが発生し、21日には首都ワシントンでインフルエンザによる初の死者がでた。それでも公衆衛生局長は何の対策もとらなかった。
唯一おこなったのは、むやみに人混みには行かない、咳やくしゃみをするときは手で口をおおう、食事の前は手を洗う、口、肌、衣服を清潔に、きれいな空気を深呼吸して思い切り吸い込む、といったアドバイスを新聞を通じて発表しただけである。
だが、こんなとってつけたようなアドバイスだけで、市民が安心できるわけはなかった。病気は軍のキャンプからキャンプへと飛び火し、すでに多くの兵士が死んでいたからである。
徴兵は一時中止された。9月末、マサチューセッツ州では、すでに数千人の死者がでていた。海岸部だけではない。内陸地でも爆発的に感染がひろがっていた。
「一番残酷な月は4月でなく10月だった」と、著者は記している。
インフルエンザの嵐は止められなかった。遮断と隔離によってインフルエンザの進行を妨げ、一時的な抑止帯をつくるくらいしか打つ手はなかった。
このウイルスに感染した場合、効く薬はなかった。人の免疫システムがはたらくのを期待するほかない。
とはいえ、適切な医療がほどこされるなら、細菌による2次感染で肺炎をおこすのを防ぐことは可能だった。それにはは医師による措置と医薬品が必要だった。それにX線装置や酸素吸入器があるに越したことはない。だが、医師も医薬品も酸素吸入器もベッドも足りなかった。
さらに重要なのは看護婦だった、と著者は指摘する。
〈医師よりも看護婦のほうが役に立った。看護によって患者は緊張をやわらげ、潤いや安らぎ、平穏を保ち、最良の栄養を与えられ、高熱のときは冷やしてもらえた。看護はこの病気の患者に生き残る最大のチャンスを与えることができた。命を救うことができた。〉
だが、その看護婦の数も決定的に不足していた。フランスでの戦闘激化にともない、赤十字社が予備の看護婦を残らず集めて、前線へ送りこんでいたためである。
一般にウイルスは時間がたてば弱まっていく。インフルエンザの流行がピークを迎えて下火になるまでは6週間から8週間を要する。だが、1918年のパンデミックでは、その期間が持ちこたえられなかった。
東部の港湾都市、フィラデルフィアは孤立していた。大流行がはじまったころに汚職で逮捕され、自身も感染した市長は、まったく何もしなかった。市の衛生当局はまったく信用されていなかった。
市当局に代わって主導権をとったのは、フィラデルフィアの名家だった。その指示のもと女性たちのグループが立ちあがり、地区ごとに医療活動や物資供給をはじめた。
その動きをみて、市の衛生当局がようやく重い腰を上げる。医師の派遣や街路の清掃、死体の片づけをはじめたのだ。
死体は町中にあふれ、その片づけ大幅に遅れていた。遺体の回収にトラックや荷馬車が用いられた。掘削機を使って、大量の墓穴が掘られ、遺体仮置場に積まれた死体が次々と埋められていった。
50万人以上のフィラデルフィア市民が感染していた。10月10日のたった1日だけで、759人の死亡者がでた。
混乱と恐怖で町は内部崩壊しはじめていた。どこからも援助は得られなかった。病気が病気だけに、ボランティアに応募する人は少なかった。
市内では物が買えなくなった。日用品店も石炭業者も雑貨屋も店を閉じていた。工場はほとんど機能を停止していた。
そんななか、医師や看護婦、警察官は英雄的に任務を遂行していた。
10月16日からの1週間だけで、4597人ものフィラデルフィア市民が死亡した。
インフルエンザの流行は永遠につづくかのように思えた。
しかし、それは終わる。次回はそれがどのようにして終わったかをみていく。
第2波のウイルス襲来──『グレート・インフルエンザ』を読む(2) [本]

第1次世界大戦末期、1918年1月にアメリカのカンザス州で発生したインフルエンザ・ウイルスは、その後、兵士とともにヨーロッパにわたり、3月から7月にかけ大流行を引き起こすが、それほど悪性ではなく、死者もさほど多くださなかった。
8月10日、それまで前線でのインフルエンザ感染に悩まされてきたイギリス軍司令部は、インフルエンザの終息を宣言する。フランスに駐留するアメリカ海外派遣軍も、7月下旬に大流行はほぼ終息したと発表した。
だが、ウイルスは消えたわけではなかった。著者の表現を引用すれば、「山火事は木の根本で燃え続け、寄り集まって姿を変え、適応し、爪をとぎ、虎視眈々(こしたんたん)と、炎となって燃え上がる機会を待ちに待っていた」。
継代と変異ということがいわれる。宿主を変え、代替わりするにつれ、ウイルスは感染力を高め、致死性をもつものへと変化していく。また、その逆もある。
1918年6月30日、イギリスの貨物船シティ・オブ・エクセター号がアメリカのフィラデルフィアに入港した。船内ではインフルエンザが蔓延していた。感染した船員はペンシルベニア病院に搬送され、病棟は封鎖されたたが、船員は次から次へ肺炎で死亡していった。
当局は士気をそこねかねないとして、この事件の報道を禁じた。
7月第2週には、イギリスのロンドンで287人がインフルエンザ肺炎で死亡していた。じつはヨーロッパではウイルスが徐々に致死性を高めていたのだ。
大流行は終息しつつあるとの宣言は、希望的観測でしかなかった。第2波の大爆発に向けて、ウイルスはじわじわと死の触手を伸ばしていたのである。
8月初旬には、フランスからニューヨークに向かう汽船の乗員がひどくインフルエンザにやられた。8月12日、ブルックリンに入港したノルウェーの貨物船からは、200人の感染者が出た。だが、ニューヨーク市は感染拡大の防止策をとらなかった。
フランスに派遣された200万のアメリカ軍兵士の40%はブルターニュ半島のブレストに入港した。8月10日、ブレストに駐留するフランス軍水兵から多くのインフルエンザ感染者が発生し、海軍病院に搬送される。肺炎による死亡者は少なくなかった。
「その後数週間のうちにブレスト周辺地域全体が炎に包まれた」と、著者は記している。アメリカ兵とフランス兵の交流によって、ウイルスが大量にまき散らされたのだ。
8月中旬から下旬にかけては、西アフリカのシエラレオネでもヨーロッパの船舶からの感染がひろがり、死者がでた。
8月末、アメリカのボストンでは、海軍の水兵2人がインフルエンザを申請したのを皮切りに59人が入院。9月にはいると市民のあいだにも感染者がではじめる。
次はボストン北方約50キロにあるキャンプ・ディベンズだった。ここには数万人の兵士が集まっていたが、9月にはいってからインフルエンザ感染が次々報告されるようになった。
そして、それはとつぜん爆発する。9月22日にはキャンプ全体の約20%が病気にかかり、そのうち75%が入院、肺炎による死亡者も増えていた。重い肺炎になってから死ぬまではあっというまだった。
キャンプの病院はまさに戦場になっていた。2500しか病床がないのに、収容者は6000人を超え、500人以上が死亡した。200人の看護婦のうち70人が病気で倒れた。
兵士がウイルスを運んでいた。兵士の移動とともにウイルスは合衆国の海岸沿いを南に、また中西部に、そして太平洋にまで達した。
このころ、ヒトからヒトに感染するうちに、ウイルスは世界中で致死性をもつウイルスに変異しつつあった。
アメリカだけではなかった。世界をめぐったウイルスはインドのボンベイ(ムンバイ)でも、猛威を振るいはじめていた。
フィラデルフィアの海軍工廠にボストンの水兵300人がやってきたのは9月7日のこと。
フィラデルフィアはアメリカの東海岸にある。地図で海岸線をたどれば、北からボストン、ニューヨーク、フィラデルフィア、ボルチモア、ワシントンといった日本でもおなじみの市名が目にはいるだろう。
フィラデルフィアには戦時中、世界最大の造船所がつくられ、大きな機関車工場や製鋼所もあった。もともと過密状態のところに、さらに大勢の労働者が吸い寄せられ、街は人であふれかえっていた。
だが、賄賂が横行し、市政は腐敗しきっていた。そのいっぽう、病院や学校はお粗末なまま、ほとんどかえりみられなかった。
ボストンからやってきた水兵のうち19人にインフルエンザの症状がでた。到着から4日後のことである。海軍の軍医は兵舎を封鎖し、念入りな消毒をおこなった。
にもかかわらず、インフルエンザは水兵のあいだに、たちまちひろがり、600人以上の病状が悪化する。海軍病院だけでは感染者を収容しきれず、一部は民間病院に搬送された。9月17日、その民間病院の医師5人と看護婦14人が倒れた。市民にも病状がではじめていた。
ボストンの水兵はフィラデルフィアだけでなく、太平洋岸のピュージェット湾(ワシントン州)や、五大湖の海軍訓練所にも送られていた。やがて、インフルエンザは西海岸や中部でも猛威を振るうことになる。
フィラデルフィア市当局は、公衆衛生局や衛生委員会を含め、インフルエンザに何の対応もとっていなかった。
早急に市民の集会の禁止、会社や学校の閉鎖、感染者の隔離といった措置を実施すべきだった。
だが、当局は市民に多少のしばらく成り行きを見守るということ以外、何も決めなかった。新聞もインフルエンザは何ら危険なものではないと伝え、海軍の医官も病気はすぐにおさまるだろうと断言した。
だが、そのころフィラデルフィアでは、すでに水兵だけではなく、看護婦や市民のなかからも死者がではじめていたのだ。
「当時は異常な時代だった。第1次大戦のせいだ。この事情を理解せずにインフルエンザの世界的流行を考えることはできない」と著者は記す。
アメリカはすでに200万の米兵をヨーロッパに派遣していた。加えて少なくとも200万の増派が必要と見込まれていた。情報統制は重要であり、士気を損ねる報道は禁止され、反戦を唱える者は容赦なく投獄された。
フィラデルフィアでは9月28日に自由国債パレードが予定されていた。だれもが国債を買って、戦争遂行に協力しようというわけである。
医師たちは人の大勢集まるパレードを中止すべきだと忠告したが、市当局も新聞編集者もまったく聞く耳をもたなかった。
パレードは強行され、3キロにわたる行列に何十万もの見物人が声援を送った。
パレードから2日後、市の公衆衛生局は、海軍基地と同様のインフルエンザが、一般市民のあいだでも発生していると発表した。
9月はじめ、アメリカ中部イリノイ州ロックフォード近郊のキャンプ・グラントには4万人の兵士が集結していた。兵舎は過密状態になっていた。160キロ離れた五大湖の海軍訓練所ではすでにインフルエンザ患者がでていたことを、このキャンプを指揮するハガドーン大佐も知っていた。
しかし、大佐はむしろ兵士を密集させるよう命じた。インフルエンザ患者がではじめると、感染の爆発に歯止めがかからなくなった。
病床が足りなくなり、簡易ベッドがあちこちつくられ、何百人もの兵士が死亡した。医療関係者にも死亡者がでた。
ところが、キャンプは封鎖されなかった。それどころか、3000人以上の兵士が列車に乗せられて、ここから1500キロ先にあるジョージア州オーガスタ近郊の別のキャンプに送られていた。
兵士を詰め込んだ列車内の換気は劣悪で、途中、大勢の兵士はバタバタと倒れた。そして、目的地到着後、2000人がインフルエンザで入院し、143人が死亡することになる。
10月にはいると、キャンプ・グラントでは5000人近くがインフルエンザに感染していた。死亡者は500人を突破する。責任を感じたハガドーン大佐がピストル自殺。
だが、「自らの犠牲をもってしても、インフルエンザの大流行はおさまらなかった」。
いっぽう、フィラデルフィアでは9月28日の自由国債パレードから72時間もたたないうちに、市内31病院のベッドは一つ残らずふさがっていた。死者もではじめた。
パレードから5日後、市当局は集会を禁止し、教会、学校、劇場、酒場を閉鎖した。巨大なポスターがはられ、市民には人混みを避け、くしゃみや咳をするときはハンカチを使うよう警告が出された。
しかし、すでに手遅れだった。パレードから10日たつと、患者は毎日数十万人、死者は数百人の割合で増え、いっこうに収まる気配はなかった。
棺桶が足りなくなり、遺体を置く場所さえなくなった。葬儀屋も墓掘り人も病気になり、積み上げられた遺体が埋葬を待っていた。
フィラデルフィアの街は恐怖で凍りついた。
「凍りついて、まさに文字どおり沈黙した」と著者は記している。
そのころ、ウイルスはすでにアメリカ全土にひろがり、大西洋岸、メキシコ湾岸、太平洋岸、そして五大湖周辺にどっかと腰を据えていた。
はたして、この先どうなるのか。
話はつづく。もう少し読んでみよう。
100年前のパンデミック──『グレート・インフルエンザ』を読む(1) [本]
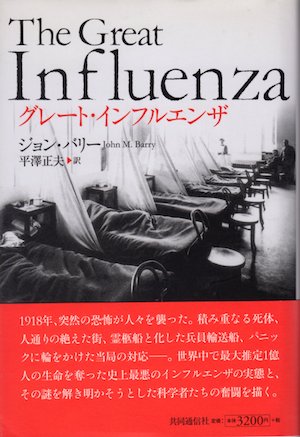
著者の科学史家ジョン・バリーは、本書でこう書いている。
〈1918年、人間は完全に近代化し科学知識をきわめ、自然を侵略する戦いにかまけていた。けれども自然は自らの機会を選ぶ。いま、そのときを選んで人間に攻撃をしかけていた。しかも、もの憂げに突っつくようなことではすませなかった。近代の人間、つまり近代の科学的手法を実践する人間は、怒り心頭に発した自然と初めて対決させられたのである。〉
これはほぼ100年前のパンデミックと、それと闘った人びとをえがいた力作の科学ドキュメントである。
無論、100年前と今とでは、社会の成り立ちも経済や医学の発展も、それこそ雲泥の差がある。単純に100年前と今とを結びつけて論じるわけにはいくまい。しかし、文明や科学がいくら発展しても、人が自然を押さえつけられないのはいうまでもない。今回の新コロナウイルスがパンデミック(世界的流行)となってひろがったのをみても、そのことがわかるだろう。
2005年に平澤正夫訳で翻訳出版された本書は、現在のパンデミックについて考えるひとつの鏡となりうる。いろいろなことを考えさせてくれる本である。
インフルエンザ・ウイルスとコロナ・ウイルスは形状がちがうが、その症状はほぼ同じだと思われる。コロナはふつうの風邪を引き起こすウイルスで、インフルエンザにくらべてこれまで軽視されていた。そのため今回パンデミックを引き起こした新型コロナ・ウイルスの正体についてはまだよくわかっていない。その性格もはっきりとはわからず、治療法も確立されず、ワクチンもできていないのが、こわいところだ。
例によって、ゆっくりとしか本が読めないので、まとめも少しずつだ。また、医学知識がないので、重要な部分を飛ばし読みしてしまう恐れがある。本書で多くのページを占めている医学者の奮闘についてもあまり触れない(これによりインフルエンザの正体がウイルスであることがわかり、ウイルス学が発達するのだが)。それに翻訳本の性格上、話がアメリカ中心であることもご承知いただきたい。
このパンデミックによって、1918年の日本がどういう状況におかれたかはまた別のテーマになるだろう。ちなみに、内務省の資料では、「スペイン風邪」と呼ばれたこのパンデミックで、日本では三十数万人が命を落としたとされる。そのなかには文芸評論家で劇作家の島村抱月が含まれていたこと、そして島村のあとを追って松井須磨子が自殺したことを、エピソードとして挙げておいてもいいだろう。
少しずつ読んでみる。
このインフルエンザは、1918年にアメリカで出現したとみるのが、現在ではほぼ定説になっている。最初に死者を出したのはフィラデルフィアである。
1920年に終息するまでに、人類史上これまでに発生したいかなる病気よりも短期間で多くの人びとを死にいたらしめた。
当時の世界人口は現在の3分の1足らずの約20億だ。そのうち最低に見積もっても2100万人がこのパンデミックで死亡したとされる。しかし著者によればこの数字はあまりにも過小評価で、少なくとも5000万人、ひょっとしたら1億人が死亡したという(インドだけでも2000万人が死亡している)。
ふつうインフルエンザはまず老人や幼児を先に殺すが、1918年のパンデミックは20代、30代の若者を襲った。「彼らは異常なほどの速さとむごたらしさで死んでいった」と、著者も書いている。
2年以上にわたるパンデミックのあいだ、死者の3分の2は24週間(6カ月)に集中し、その大部分は1918年9月半ばから12月はじめにかけて亡くなっている。
注目すべきは、このパンデミックが一度だけでは終わらず、3波にわたったことである。
第1波のピークは1918年4月、第2波のピークは10月、そして第3波は12月にやってきた。第2波のウイルスは、第1波よりもはるかに致死性が高くなっていた。人から人に感染するうちに変異したと考えられる。しかし、人もまた次第にウイルスにたいする抗体を身につけるようになった。
1918年のインフルエンザ・ウイルスが発生した場所は、アメリカ中部のカンザス州ハスケル郡とみて、ほぼまちがいないという。農民が豚や鶏とともに暮らし、牧場主が何万頭もの牛を飼っている農村地帯である。
ウイルスはカンザス州を東に横断し、広大な陸軍基地にひろがり、船でヨーロッパに渡った。その後、北米、ヨーロッパ、南米、アジア、アフリカ、太平洋の島々へと世界を席捲する。
最初にこのインフルエンザに気づいたのは、ハスケル郡の医師、ローリング・マイナーだった。こんな凶暴なインフルエンザはこれまで見たこともなかった。1月後半から2月初旬にかけ、健康で頑丈な人たちが、まるで銃で撃たれたかのように、とつぜんバタバタと病に倒れていった。
地元紙も多くの人が肺炎にかかっていることを報じる。マイナーもまた国の公衆衛生局に警告を発した。しかし、3月になると病気は消滅したかのようにみえた。これで収まれば、インフルエンザは地域的な感染で終わるはずだった。
しかし、そのころ同じカンザス州で300キロほど離れた広大な軍用地フォートライリーのキャンプ・ファンストンにいた兵士が、インフルエンザにかかった。かれはハスケル郡にほど近いある町に帰省していた。ほかにもハスケル郡で徴兵された大勢の男たちが、キャンプ・ファンストンで訓練を受けていた。このファンストンでインフルエンザ患者が大量発生するのである。
第1次世界大戦は1914年にはじまったが、アメリカは1918年まで参戦しなかった。
1915年にドイツの潜水艦がイギリスの豪華客船ルシタニア号を撃沈し、その船に乗っていた多くのアメリカ人が死亡した。
1917年には、ドイツが中立国の船舶や商船への無制限潜水艦戦を宣言した。それでもアメリカは参戦しなかった。
その後、ツィンマーマン・メモが発覚する。これはドイツの外相ツィンマーマンがメキシコに対米戦を促すものだったが、アメリカの世論はこれに憤激する。そこで、ウィルソン大統領はついに1917年4月2日、議会に参戦の決意を表明する。
いったん参戦を決意すると、正義の人ウィルソンにとって、この戦争は聖戦となった。ウィルソンはアメリカを徹底した戦時体制下においた。
宣戦布告とともに、徹底的な報道検閲がはじまり、非愛国的な記事を書いた者を逮捕することも可能になった。新聞や出版物は自己検閲をはじめるようになる。士気を損なう恐れがある歌も禁止された。
ウィルソンが戦争への道を選んだ途端、挙国一致の戦争がはじまり、アメリカ陸軍は増強された。訓練のため、兵舎には徴集された若い男たちがぎゅう詰めでひしめきあっていた。
インフルエンザは、そんなとき思いがけず発生したのである。
キャンプ・ファンストンの病院がはじめてインフルエンザの兵士を受けいれたのは1918年3月4日のことである。それから3週間もしないうちにファンストンでは1100人の兵士の体調が悪化し、かなりの数の兵士が入院せざるをえなくなった。
ファンストンで最初の患者が出てから2週間後の3月18日、こんどはジョージア州のふたつのキャンプでインフルエンザが発生し、部隊の10%の兵士が病気にかかった。
その後、ドミノ倒しのように、ほかのキャンプでもインフルエンザが発生、陸軍キャンプ36カ所のうち、じつに24カ所がインフルエンザに見舞われた。だが、初期の病状はさほど深刻ではなかった。
ヨーロッパでは4月初旬からインフルエンザが異常発生する。最初に発生した場所はアメリカ軍兵士が上陸したフランスのブルターニュ半島西端にある軍港ブレストだった。
そのあとブレストを起点にして、病気はたちまち同心円状にひろがっていった。症状は概しておだやかで、兵士は一時的に衰弱したものの、やがて回復していった。
インフルエンザは4月遅くにパリを襲い、ほぼ同時にイタリアに到着する。イギリス陸軍で最初の患者が出たのは4月中旬で、そのあと爆発的にひろがり、数万人が入院する事態となった。
事情は敵方のドイツ陸軍も同じだった。戦場のドイツ軍兵士も4月以降、インフルエンザの流行に悩まされた。そのため、大規模攻撃が延期されることもあったという。
このインフルエンザには当初、名前がなかった。スペインで、はじめて、「スペイン風邪」という名前がつく。
それには理由がある。
当時、アメリカでも、フランス、イギリス、ドイツでも報道管制が敷かれており、兵士の士気を損ないかねない報道はいっさいなされなかった。ところが、中立国のスペインでは報道管制がなされず、新聞がインフルエンザの記事で埋めつくされたのである。
そのため、このインフルエンザは「スペイン風邪」と呼ばれるようになった。
実際に、スペインで突如発生したわけではなかった。あくまでもウイルスの発生源はアメリカであり、アメリカ軍がこのウイルスをヨーロッパに運んだのだ。
その後、インフルエンザはたちまち世界へひろがっていく。5月にはインドのボンベイ(ムンバイ)やカルカッタ(コルカタ)、中国の上海にも到達した。
8月になって、それはいったん終息したかにみえた。
だが、ほっとしたのもつかの間、10月になって、それは猛烈な致死性をもつウイルスに変異して、ふたたび世界を襲うのである。
これからの日中関係──ヴォーゲル『日中関係史』を読む(4) [本]

【最悪の関係】
2009年9月に首相の座についた鳩山由紀夫は、これまでのアメリカ依存に距離を置き、中国ともよりよい関係を築きたいと考えていた。
9カ月後に鳩山のあとを継いだ菅直人も同じく中国との友好方針を堅持した。
しかし、その民主党政権のもとで、日中関係は最悪の状態におちいる。
2010年9月7日、尖閣諸島の北東で、海上保安庁の巡視船が中国籍のトロール船を発見し、退出を求めたところ、トロール船は巡視船に体当たりし、そのまま逃走しようとした。そこで海上保安庁の職員が2時間後、この船に乗り込み、船長と船員を連行した。船長は酒に酔っていた。
中国政府は船長と船員の即時釈放を要求し、翌日、日本政府は船員とトロール船を中国に戻した。しかし、巡視船に体当たりした船長は事情聴取のため拘留された。
その対抗措置として、中国は河北省で日本の建設会社の社員4人を逮捕する。中国国内では反日デモが発生。さらに中国政府は日本にたいするレアアース輸出を制限する措置をとった。
2日後、日本政府は逮捕した船長を処分保留のまま釈放する。
中国漁船衝突事件以後、中国のメディアは反日報道を繰り返した。
2012年になると、東京都知事の石原慎太郎が挑発的な行動に出る。東京都が尖閣諸島を購入するため、基金をつのるというのだ。
民主党の野田佳彦首相は石原の計画が中国を激怒させることを恐れ、ひそかに国による購入を決定する。朝日新聞がこれを尖閣諸島の「国有化」と報じると、中国はこれに猛反発し、中国国内各地で反日デモが発生、日本人の所有する商店や工場が襲撃された。尖閣諸島周辺も緊迫がつづいた。
日中衝突の危険性が収まるのは2013年10月になってからである。
【経済関係の発展】
2012年には習近平が中国共産党総書記になり、安倍晋三が日本の首相に選出された。
「安倍は従来どおり日米同盟を支持しながら、中国の感情を逆なですることも避けた」というのが、著者の評価である。
それによって、日中対立は次第に収まってくる。
政治的な緊張がつづいたにもかかわらず、日中間の貿易関係は発展していた。著者は「隣に世界最大の人口を抱える国があるという事実は、多くの面で日本にとって好運だった」と述べている。
21世紀にはいってから十年以上、日本のGDPは1%前後でしか成長していなかったが、海外事業は年率5%以上伸びており、日本の対中貿易収支はほぼ黒字続きとなっている。
海外事業収入と利益が国内事業を上回る日本企業が多くなっている。海外投資収益の国内環流額は2000年以降5倍となり、2014年には約5.6兆円となった。
2016年10月時点で、中国に進出する日本企業は、アメリカの8400社より多く、約3万社となっている。かつてはローテクの軽工業製品製造が主だったが、いまでは重工業品やハイテク製品の製造が中心を占める。サービス業への投資割合も増えている。
さらに、著者はこんなふうに書いている。
〈日中は政治的には敵対したが、日本の大手商社は中国全土に支店や支社を構え、その規模も対米事業と同じか、それ以上に成長していた。中国市場で最大手の日系商社、伊藤忠は、中国14都市に支社を構えている。伊藤忠に次ぐ三菱、三井、住友といった大手商社も、中国の全主要都市に支社や支店を構え、北京語や、場合によってはさらに方言まで話せる日本人社員が現地社員を指揮している。〉
日系企業の活動が、中国のGDP増加に寄与している面は否定できない。
それでも反日デモのようなリスクはある。そこで、日本企業はいまでは「チャイナ・プラス・ワン」の方策をとり、中国で愛国主義が暴発しても、他国の工場で増産して生産量を保つという柔軟な戦略をとるようになっている、と著者はいう。
政治体制のちがいにもかかわらず、経済面での日中関係はきわめて密接なものとなっているのだ。
【緊張緩和?】
2014年以降、日中間の緊張は徐々に緩和した。
2014年11月に北京で開かれたAPEC首脳会議では、習近平も安倍晋三も、表向き厳しい表情で撮影に応じたが、じっさいにはなごやかにことばを交わしたという。
2015年4月にインドネシアで開かれたアジア・アフリカ会議でも、25分間、日中首脳会談が開かれた。
外交官どうしの接触も頻繁になっている。
2010年に日中関係が緊張してから、日本人の中国旅行者は横ばいだが、来日する中国人の数は2013年以降、激増している。2018年時点で、中国人への訪日ビザ発給数は840万近くになった。
こうした中国人観光客が日本の観光地やデパート、家電量販店などの売り上げに寄与していることはまちがいなく、また日本旅行を通じて、日本に好印象をもつ中国人の割合も増えている。
いっぽう日本人の中国にたいする印象はさほど改善していない。尖閣問題にせよ、反日デモにせよ、中国から圧力をかけられたという思いが、中国への警戒感をいだかせているのだ。
2018年10月には安倍首相が訪中し、習国家主席と会見した。中国はすでに突出した経済大国、軍事大国になっていた。安倍はこのとき「競争から協調へ、日中関係を新たな時代へ押し上げたい」と述べている。2019年6月には習近平がG20大阪サミットに参加するため来日。さらに2020年にあらためて日本を訪れたいという意向を示している。
日本人はすでに中国人とあらゆる分野で深い関係性にもとづくネットワークを築いているが、中国と軍事的な協力関係を結ぶことはありえない。むしろ強国となった中国を目の前にして、日本はアメリカとの軍事的・政治的・経済的関係をより強固に維持していくだろう、というのが著者の見方である。
こう書いている。
〈日中両国のつながりはすでに強いが、今後数十年でさらに拡大することが予想される。それでも、1870年代以降の日中間の歴史が、両国にとってなお大きな火種であることに変わりがない。日本にとって中国がどれだけ重要でも、それによって1945年以来に日米両国の築きあげた、深く前向きな結束が解けることはないのである。〉
政冷経熱というのが、最近の日中関係をいいあらわすことばになっている。しかし、目標とすべきは政温経熱だ、と著者はいう。
〈歴史的に形成された感情の激しさを考えると、日中がすぐに信頼関係を育み、親友になれると考えるのは現実離している。それは数十年先の目標である。次の10年間に達成すべき妥当な目標は、両国が信頼できるパートナーになれるよう、明快で率直でビジネスライクな関係を良好に保つことだ。次の10年間で日中が「政熱」を享受できると期待するのは、非現実的である。しかし両国が、「一帯一路」のような構想や、環境問題解決のための共同プロジェクトや、多国籍組織において、もし協力関係を拡大しつづけることができるなら、「政温」を達成することは不可能ではない。〉
ここには日中双方の見方だという著者の、冷静でかつ温かい見方がある。
とはいえ、ぼくなどには中国の民主化を願う思いも強い。
日中対立のはじまり──ヴォーゲル『日中関係史』を読む(3) [本]

【天皇訪中】
1992年10月、天皇明仁が中国を訪問する。天皇が中国を訪問するのは、史上はじめてのことだった。
歓迎晩餐会で天皇はこうあいさつした。
「この両国の関係の永きにわたる歴史において、我が国が中国国民に対し多大の苦難を与えた不幸な一時期がありました。これは私の深く悲しみとするところであります」
天皇訪中は日中友好関係の礎となるかにみえた。
ところが、その後、日中関係はむしろ緊張の度合いを高めていく。
1991年にはソ連が崩壊するという大事件が発生していた。
1992年に中国では鄧小平が引退し、江沢民が最高指導者となった。日本でも田中角栄が1993年に亡くなる。時代が変わりつつあった。
中国経済は1980年代以降、日本の経済援助や技術援助で急速な成長を遂げた。中国のGDPは1978年の1495億ドルから1993年の4447億ドルへと一気にはねあがった。
いっぽうの日本経済は1990年代はじめにバブル崩壊を引き起こしていた。中国にとって日本はもはや経済の手本ではなくなりつつあった。
台湾では総統に就任した李登輝が民主化に着手し、1994年に憲法を改正、総統の直接選挙制を導入する。
1995年に李登輝はアメリカ入国を認められた。これに反発した中国は台湾海峡でのミサイル発射テストを実施した。これにたいし、アメリカは台湾周辺海域に空母戦闘群を2個派遣した。この事態を重くみた江沢民は、国防費引き上げに踏み切った。
台湾の微妙な状況について、著書はこう記している。
【愛国主義教育】
1980年代後半になると、中国は日本がアメリカからの独立性を高め、自衛隊を強化していくことを恐れるようになる。だが、現実には日本はむしろアメリカとの同盟関係を強化していく。在日米軍の駐留経費負担を増やし、周辺で事態が発生した場合は米軍と協力して対応する姿勢を強めていった。
1989年の天安門事件以降、中国はみずからの政治体制に危機感をいだくようになった。そして、一時鈍化した経済成長が1993年以降回復に転じると、国防費増大に力をそそぐようになる。
政治体制の危機を覚えるなか、中国国内ではむしろ日本脅威論が再浮上してくる。「中国は、アメリカの最新兵器が日本に渡るのを恐れただけでなく、軍事力を高めた日本が、アメリカに依存せずに独自の行動をとりはじめることも警戒した」と、著者はいう。
それは杞憂だった。しかし、1997年に日米両国が「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」を改訂し、米軍と自衛隊の協力態勢が構築されると、中国は尖閣諸島と台湾周辺での日本の動きを警戒するようになっていく。
体制への危機感を覚える中国は、愛国主義教育を推進する方向に舵を切った。映画やテレビがフルに活用された。愛国主義教育には、日本の過去の残虐行為と日本の謝罪の不十分さを強調することも含まれていた。
「1990年代半ば以降、中国人の中で最も強く反日感情を剥き出しにしたのは、日本占領時代を経験した高齢者ではなく、愛国主義教育を受けた若い世代である」と著者は書いている。
こうした愛国主義教育は中国だけでなく、韓国や東南アジアにも飛び火した。
【膨張への懸念】
著者は次のように指摘する。
〈1992年以降、日中間の緊張が高まった時期は、中国が自信を増した時期だった。それは同時に日本で、まもなく中国が経済規模のみならず軍事力でも、日本を上回るだろうという懸念が広まった時期でもあった。〉
1993年以降、中国は高度成長をつづけたが、日本はバブル崩壊以降、停滞したままだった。2001年に世界貿易機関(WTO)に加盟すると、中国はますます自信を深めていった。2008年の世界金融危機も中国にはほとんど影響をもたらさなかった。
2008年の北京オリンピックから2年後、中国のGDPは日本を抜き、世界第2位となった。1989年から2002年までは江沢民、2002年から12年までは胡錦濤が国家の指導者となり、政治も安定していた。これにたいし、1994年から2012年にかけ、日本では首相が13人も入れ替わり、政治の混迷がつづいた。
そのかん、日中間の緊張をもっとも高めたのが尖閣諸島問題である。
1971年にアメリカから沖縄が返還されたとき、尖閣諸島の施政権も日本に返還された。しかし、1970年には、すでに台湾と中国が島の領有権を主張していた。この海域に海底油田が存在する可能性が判明したからである(実際にはその量は思ったほどではなかった)。さらに水産資源の乱獲が進み、漁船が沖合にでるようになると、島々は漁業権争いの的になっていく。
尖閣の領有権をめぐる日中それぞれの主張はいまだに決着をみていない。日本は領土問題が存在すること自体を認めていない。1990年代には、日本が近辺の防衛を強化し、中国軍も活動範囲を広げたため、状況が悪化していく。
【緊張緩和への努力】
日中間に緊張が高まったのは、中国が日本を追い越し、アジア最大の経済国となる過程においてだった、と著者は断言する。
それでも、両国はなんとか対立が激化しないように努めた。
1995年には村山談話が発表される。
「わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで……植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました。……ここに改めて痛切な反省の意を表し、心からのお詫びの気持ちを表明いたします」
中国側はこの談話を歓迎した。
1995年8月の村山富市首相、97年9月の橋本龍太郎首相の訪中を受けて、1998年には江沢民国家主席が来日した。
ところが、この来日は結果的に日中間の緊張を高めることになった。
江沢民は共同宣言に中国へのお詫びを入れることを要求、これにたいし小渕恵三首相はそれを拒否し、代わりに口頭でそれを表明することにした。さらに江沢民は宮中晩餐会で、日本がどのような歴史観をもつべきかを説教するスピーチをおこなった。日本国民は辟易した、と著者は書いている。
それでも、このときの共同宣言では、両国政府要人の相互訪問、経済・科学面での協力、文化交流、環境分野での協力がうたわれていた。江沢民来日後も日本の対中貿易と対中投資は膨らみつづけた。
1999年11月には小渕首相が中国を訪問する。小渕は中国のWTO加盟を支援すること、さらには33項目の協力プロジェクトを推進することを中国側に伝えた(中国は2002年からWTOに加盟)。
2000年には朱鎔基首相が来日した。このとき朱鎔基は日本に強く謝罪を求めることはなかった。テレビでは、日本の市民100人と直接やりとりする様子も放映され、この来日は日本人にはわりあい好感をもって受け止められた。
【小泉政権とその後】
2001年8月13日に(8月15日ではなく)小泉純一郎首相が靖国神社を参拝すると、中国メディアはそれにかみついた。訪中したさいに小泉は盧溝橋と中国人民抗日戦争記念館を訪れ、犠牲者にお詫びと哀悼の気持ちをあらわし、二度と戦争を起こしてはならないと述べた。そのうえで、それ以降、小泉は毎年、靖国を参拝することになる。
著者はこう書いている。
〈日本国民にとって、首相の靖国神社参拝の是非の背後にあるのは、日本が戦争中の戦争犯罪を認めるか否かではなかった。日本国民はその責任をすでに受け入れていたからである。問題はむしろ、小泉が政治学者ジェラルド・カーティスに述べたように、相手が日本人だろうと外国人であろうと、母国のために命を犠牲にした日本兵に敬意を払うなと他人に命じられる筋合いはない、という点だった。靖国参拝を貫いた小泉首相は、日本国民から高い支持を得た。しかし中国にとっては、小泉の靖国参拝は日本の軍国主義者たちへの表敬であり、歴史と向き合おうとしない日本国民を象徴するものになった。〉
小泉政権時代、日中関係は悪化していく。
中国では2003年に胡錦濤が国家主席に就任。胡錦濤自身はむしろ緊張緩和の方向に動いたが、実際の流れはその逆となった。
2004年にはサッカーのアジア杯が中国各地で開かれたが、日本代表チームが勝つたびに、中国各地では反日感情むきだしのデモが発生した。とりわけ北京での決勝戦で日本が中国を破ると、デモは暴徒化した。
2005年、中国政府は日本の常任理事国入りを阻止するため、東南アジア諸国にはたらきかけると同時に、国内で反日デモを組織した。デモ隊は暴徒化し、日系レストランや日本製品を売る店の窓ガラスを割り、日本車を破壊するなどした。
2003年まで日本は中国最大の貿易相手国であり、それ以降もほぼ第2位を維持していた。また中国にある日本企業も、約1000万人の中国人労働者を雇用していた。にもかかわらず、こうした反日デモが発生したのである。
2006年には第1次安倍晋三内閣が発足した。安倍首相が最初の訪問先に選んだのは中国だった。
2008年の北京オリンピックが近づくと、中国指導部は日本との関係改善に奔走するようになる。その年5月には胡錦濤国家主席が東京を訪問、東シナ海における日中ガス田開発プロジェクトに合意している。同月に発生した四川省地震で、日本は61名の緊急援助隊を送った。
8月の北京オリンピックはスムーズに開催された。
だが、2009年に日本で民主党政権が発足すると、日中関係は最悪の状態におちいっていく。
日中蜜月時代──ヴォーゲル『日中関係史』を読む(2) [本]

【日中国交正常化】
1972年9月の日中国交正常化は画期的なできごとだった。
本書によれば、国交正常化に向けた土台づくりは、以前から入念におこなわれていたという。
72年4月には日本経済研究センター理事長の大来佐武郎が訪中し、周恩来首相と会って、国交正常化の可能性を探っている。
7月に田中が首相に就任すると、大平正芳外相が日中国交正常化の担当になった。
同月、中日友好協会の孫平化が来日し、周恩来のメッセージを伝えた。中国側は3つの原則を提示していた。中国は一つであること、中国政府の代表は中華人民共和国であること、台湾との日華平和条約は破棄されねばならないということ。
7月25日には、公明党の竹入義勝委員長が北京を訪れ、周恩来と会見した。8月10日、自民党が田中の中国訪問を了承する。
8月31日から9月1日にかけ、田中はハワイでニクソン米大統領と会見し、日本がアメリカから約7億1000万ドルの物品を購入するとともに、繊維製品の輸出を削減することを申し入れた。そのさい、ニクソンは日本がアメリカより先に中国との国交正常化を実現することに異議を唱えなかった。
9月中旬には小坂善太郎が国会議員代表団を率いて、北京にはいり、周恩来と会見した。
いっぽう、椎名悦三郎元外相は9月17日から台湾を訪れ、日本は中華人民共和国と外交関係を結ぶが、台湾との貿易や文化交流は続けると伝えた。これに怒った蒋介石は椎名と面会せず、椎名は息子の蒋経国と会って、日本の立場を説明した。
田中と大平は9月25日から30日まで北京を訪問する。晩餐会での田中の「ご迷惑」発言をめぐって、中国側は不快感を示したものの、4回の首脳会談をへて、両国が日中国交正常化の共同声明に調印した。尖閣諸島の帰属問題は棚上げとなった。田中は毛沢東とも会見した。
この共同声明には重要な文言が盛りこまれている。
「日本側は、過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し、深く反省する」
この文言について、双方はじゅうぶんに理解したはずだった。
【日中平和友好条約まで】
1972年の国交正常化後、日中協力プロジェクトが実施されることになった。しかし、78年の日中平和条約調印まで、大胆な改革開放に向けた合意は形成されなかった。
そのころ外国人が自由に中国国内を旅行することはできなかったが、それでも日本人の中国旅行者は少しずつ増えていった。
日中関係が一気に進展しなかったのは、1976年に毛沢東が死去するまで、江青ら「四人組」が大きな力を保っていたからだ、と著者はいう。
それでも日中間貿易は、かなりのスピードで拡大し、1972年の年間11億ドルが75年には40億ドル近くまで増大する。日本は化学肥料や工作機械を輸出し、化学繊維工場の建設を援助した。これにたいし、中国が日本に輸出したのは主に石油であって、輸出できるだけの工業製品はつくられていなかった。
1971年に沖縄返還協定が調印された時点で、アメリカは尖閣諸島の管轄権を日本に移譲することを決定した。中国は1971年12月にはじめて尖閣諸島の領有権を主張するが、日本の専門家はその主張を認めなかった。1978年に日中平和友好条約が調印されたさいに来日した鄧小平は、記者会見で、島の領有権問題は棚上げにして、未来の世代にゆだねようと述べた。
実際に日中関係が進展するのは、1978年の平和友好条約締結以降である。それまでに、貿易協定、ビザの発給、通関手数料、領事館の設置、航空路線の確立など、こまごまとした実際問題がひとつひとつ調整、処理されねばならなかった。
【鄧小平の来日】
1978年8月に、それまで難航していた平和条約が締結された背景には、77年夏に復権を果たした鄧小平の決断があった、と著者はいう。
条約の締結を受けて、鄧小平は78年10月に来日する。到着後、来日の目的を問われるて、鄧小平はひとつは日中平和条約の批准書交換、もうひとつは日本の友人たちへの謝意、さらに徐福が求めた秘薬を探すためと答えた。
中国にとって不老不死の秘薬、それはまさしく近代化実現のための秘策にほかならなかった。
鄧小平は各地で歓迎を受けた。新日鉄の君津製作所、日産の座間工場、大阪の松下電器の工場などを訪れ、新幹線にも乗っている。これらの体験はすべて中国の近代化を導くモデルとなった。
日本滞在中、鄧小平は、日本が戦争中の政府主導の経済体制から戦後のより開放的な市場経済体制にどのように移行したのかをさかんに聞いて回ったという。
昭和天皇とも会見し、ロッキード事件で保釈中の田中角栄とも会っている。
福田赳夫首相と懇談したときには、こう述べている。
「友好関係と協力は、中国と日本の10億の人々が共有する願いです。……両国の国民の代表として、何世代にもわたって友好関係を続けましょう」
鄧小平来日からまもなく実施された世論調査では、日本人の約78%が中国に親しみを感じると答えていた。
その後、日中の経済関係者の交流が盛んになった。
中国の工場では「日本の品質管理から学ぼう」という標語が掲げられた。いっぽう、著者によれば「日本の実業家の多くは、日本の侵略による中国の被害に対し、自分たちの世代が取り得る最善の方法は謝罪の継続ではなく、むしろ中国の産業と生活水準の向上を支援することだと考えていた」という。
実際、国際協力事業団(JIKA)も中国の技術支援の要望に応えて、さまざまな分野の専門家を中国に送りこんだ。中国からも多くの留学生が日本の大学や研究機関にはいり、先端技術を学んだ。
【改革開放への模索】
1976年9月に毛沢東が死去したあと党主席に就任した華国鋒は、積極的に海外からの新技術を導入した。地方政府や省庁はこぞって機械を輸入し、模範工場をつくりはじめた。
石油採掘などの巨大事業を運営する官僚たちは「石油派」と呼ばれ、大慶油田などの大プロジェクトを完成させた。1978年12月には、さまざまな日本企業が参加して、宝山製鉄所の起工式がおこなわれた。
地方官僚は新工場建設に貪欲で、じゅうぶんな準備が整う前に、きそって外国企業と工場誘致契約を結ぼうとした。しかし、外貨が不足していた。
中越戦争が勃発したこともあって、1979年2月には日本企業との約26億ドルの契約が凍結された。だが、日本の企業や銀行が支払いの繰り延べや貸し付けをまとめることで、一部事業が再開された。
1980年後半には、いくつかのプロジェクトが中止される。そのなかには宝山製鉄所のプロジェクトも含まれていた。
中国側の当初のもくろみは、石油の増産によって外貨を稼ぎ、その外貨で多くのプラントを建設するというものだった。しかし、その計画は挫折する。
鄧小平は訪中した大来佐武郎や土光敏夫(経団連会長)と会い、資金が足りず、契約を結んだ工場の代金が払えないことを率直に認めた。
大来は外貨不足を軽減するために、日本の経済援助を活用しては、と中国側に提案した。こうして1979年から2001年にかけ、日本は中国に総額159億ドルの経済援助をおこなうことになった。
宝山製鉄所プロジェクトが再開できたのは、日本の援助によるところが大きかったという。
1981年にはまたもプラント契約のキャンセル問題が発生する。このときも大来は訪中して、中国政府が契約をキャンセルすれば、国際的に中国の信用は失墜すると警告した。同時に、日本の財界にも中国への理解を求めた。
1981年からは日中経済知識交流会が発足し、経済問題に関する日中の話し合いがおこなわれるようになった。また世界銀行も中国に経済アドバイザーを送り、中国の発展に大きな役割を果たした。
日本からの借款により、中国では宝山製鉄所を含め、停滞していたプロジェクトがふたたび動きはじめた。宝山製鉄所で鉄鋼生産がはじまったのは1985年からである。その後、宝山をモデルとして、中国では多くの製鉄所がつくられ、2015年までに年間8億トンの粗鋼を生産できるようになった。
1978年から84年にかけ、中国は外国と約117億ドルにおよぶプラント・技術供与契約を結んだが、そのうち60億ドルが日本との契約だったという。
【1980年代の日中関係】
平和友好条約締結後、日中間の文化交流も進んだ。多くの日本語書籍が中国語に翻訳された。日本映画も中国で広く上映され、テレビでは連続ドラマ『おしん』が放送され、抜群の人気を博した。
1984年、胡耀邦は日本の青年約3000人を中国に招待した。この年にはまた「日中友好21世紀委員会」の初会合も開かれている。
このように1978年から92年にかけては日中間の蜜月時代だったが、そのかん政治的摩擦がなかったわけではない。
1982年以降、日本の文部省は青少年に愛国心をもたせるよう学習指導要領を変更するようになる。日本で軍国主義への批判が弱まるのをみて、中国メディアは反発し、日中戦争中の日本軍による南京大虐殺や三光作戦、細菌兵器実験を大きく取りあげるようになった。
1985年8月15日に中曽根康弘首相が靖国神社を公式参拝すると、中国はそれを激しく批判した。
1987年には京都の光華寮問題をめぐって、大阪高裁が光華寮は台湾のものという判断を示したことから、中国の学生による大規模な反日デモがおきた。
とはいえ、1980年代を通じて、中国はほかのどの国より日本と密接な関係にあった、と著者はいう。
1989年6月4日には天安門事件が発生した。北京市街で多くのデモ参加者が殺されたことに日本人はショックを受け、世論調査では中国に親しみを感じる日本人の割合が大きく減少し、52%となった。
当初、日本政府は欧米諸国と一緒になって中国に制裁を加えたが、いち早く制裁を解除する。1991年、欧米諸国に先んじて、日本は中国への円借款を再開した。この年8月、海部俊樹首相は中国を訪れ、翌年の国交正常化20周年にちなんで、天皇訪中を提案した。
ヴォーゲル『日中関係史』を読む(1) [本]
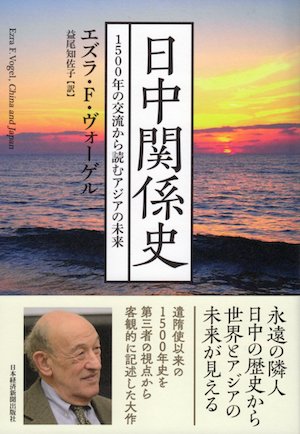
著者のエズラ・ヴォーゲルはハーヴァード大学名誉教授。著書に『ジャパン・アズ・ナンバーワン』や『現代中国の父 鄧小平』などがあり、日本でもよく知られた人だ。ことし90歳になる。
本書「まえがき」には、こう書かれている。
〈日中関係には、「緊迫」「危険」「難解」「複雑」という言葉が当てはまる。……もし日中関係の取り扱いを間違えば、両国は軍拡競争に走り、二国間、地域、グローバルな問題で協力が行き詰まり、最終的には紛争になるだろう。だが、日中関係を適切に取り扱うことができれば、両国は国際秩序と地域の協力枠組みを守るために助け合える。貿易、経済建設、研究開発、平和維持、自然災害対応などの分野で、両国は力を合わせていけるはずなのである。〉
ここには、これからの日中関係が大きな紛争にいたることなく、平和的な友好関係を保ちながら推移してほしいという著者の願いがこめられている。
だが、現実にはどうか。世界史をみても、「日中ほど長い歴史を持つ二国間関係はあまりない」のだが、それにしても両国の関係は荒々しい紆余曲折をへてきた。近代においては、とりわけ戦争と対立がきわだっている。
「私は自分自身を、日本と中国の双方の見方だと思っている」と、著者は書いている。第三者というより、両国をよく知るもっと身近な仲裁者のような立場である。
理解しあうには、両国が真摯に歴史に向き合うことがだいじなのは、どちらもわかっている。しかし、そこにはたがいの複雑な感情がからみあって、バランスのとれた観点をもつことなど不可能なのである。
「それ[日本と中国]以外の国の研究者であれば、より客観的でバランスのとれた観点から歴史を検証し、日中の相互理解に何らかの貢献ができるかもしれない」。アメリカ人の歴史家という立場が有益なのはそのためである。
本書はそういう思いからえがかれた、1500年にわたる日中関係史といってよい。
重点は近現代、すなわちこの200年に置かれている。それはもっとも評価がわかれる時期ともいえる。
長大な本書を網羅的に紹介するのは骨が折れる。ここでは現代、すなわち戦後に焦点をしぼって紹介する。日清、日露、第1次世界大戦、日中戦争にいたる激動の時代は現代を理解するうえでも、とても重要なのだが、それはむしろ背景としてつねに念頭におくことにしよう。
現代を扱った章は4つに分かたれている。
第9章 大日本帝国の崩壊と冷戦 1945〜1972年
第10章 協力 1972〜1992年
第11章 日中関係の悪化 1992〜2018年
第12章 新時代に向かって
これをみれば、戦後の日中関係は、断絶、協力、反発、(そしてあわよくば)共存という流れのなかで動いていることがわかる。
転換点になったのは1972年である。ぼくにとっては「われらの時代」だった。
この年、ぼくは日中学生友好会の一員として中国を訪れた。それ以降、中国には行っていない。
中国に好感情をいだいていたわけではなかった。むしろスターリニズムの国だと決めつけていた。それはあのころ読み親しんでいた吉本隆明の影響だったにちがいない。
それでも学生友好会にもぐり込んだのは、いちどこの目で実際の中国を見てみたいという思いが強かったからである。すでに収束しつつあったとはいえ、文化大革命への興味もなかったわけではない。
だが、何といっても竹内好が、われわれにとって中国がいかに大きな意味をもつかを教えてくれていた。この人からさまざまなこと、とりわけ生活(文化)の幅が、政治の幅よりもずっと大きいことを教わらなければ、ぼくも中国にさして興味をもたなかったかもしれない。
大学をでてから、中国との関係はだんだんと失われていった。それでもいま中国がどうなっているかという関心はつづいていたが、それはニュースで知るくらいの断片的なものにとどまる。
本書がありがたいのは、とりわけ現在の日中関係をバランスのとれた視点から大きく描いてくれていることである。政治に敏感な向きからすれば、著者の見方は甘すぎるという見方もじゅうぶん成り立つだろう。しかし、日中がふたたび戦争をはじめるといった悪夢は見たくないという思いからすれば、本書のえがく歴史は、少なくとも未来への可能性をつないでくれるものだ。
以下は備忘のためのメモである。
【引き揚げ】
1945年に大日本帝国は崩壊する。日本は植民地の朝鮮と台湾、それに実質上、帝国の一部だった満洲を失う。当時、日本の人口は7200万人だったが、そのうち690万人(兵士370万人、民間人320万人)が外地でくらしていた。日本にとっては、その引き揚げが当初の課題だった。
ソ連の侵攻後、満洲でおよそ60万の日本人捕虜が、シベリアなどに送られ、建設現場で肉体労働者として働かされた。かれらが帰還を認められたのは1947年から49年にかけてであり、およそ45万人が日本に戻ることができた。
中国に取り残され、帰還を待つあいだに死亡した日本人は20万人と推定される。なかには中国に留まった家族や孤児もいるが、大半の日本人は1950年4月までに帰国を果たすことができた。
1949年に中国で共産党が権力を握ったときも、およそ3万4000人の日本人が旧満洲に残留していた。そのなかには、中国人民解放軍空軍の創設に貢献した人物もいる。
いっぽう戦争が終わったあと、日本では台湾と朝鮮の出身者が数百万人くらしていた。そして、帰国の道を選ばなかった多くの人々は、日本社会のなかで苦難の道を歩んだ。
【中国大陸】
大日本帝国が崩壊したあとは、大きな空白地帯が生まれた。
1945年9月3日に日本軍が正式に降伏したあと、中国大陸では国民党と共産党の協調関係が維持できなくなった。終戦とともに、共産党軍、国民党軍、ソ連軍が競い合うように満洲へと向かった。満洲に備蓄された兵器と工場を接収するためである。
「日本の侵略がなければ、国民党は1930年代半ばに共産党を壊滅させていたかもしれない」と著者は書いている。しかし、日中戦争により、国民党は西南部に後退し、共産党は西北部を拠点として、反日統一戦線を組むことになった。
日本が降伏すると、1945年から49年にかけ国共内戦がはじまる。重要な戦いで勝利を収めたのは共産党である。国民党は軍事を優先して経済政策を怠ったため、支配地域で激しいインフレと物資不足を招いた。その結果、汚職がはびこり、国民の支持を失う。これにたいし、共産党は土地の分配を約束することで、農民のあいだから多くの兵士を集めていた。
共産党軍は北平(現北京)を占領したあと、長江に向かって南下する。長江を渡るころ、国民党軍はすでにもちこたえられなくなっていた。1949年10月1日、共産党は中華人民共和国の建国を宣言する。
【占領下の日本】
いっぽう日本は1945年9月から52年4月まで、アメリカの占領下に置かれている。占領軍がまず考えたのは、天皇の力を利用することである。そのうえで、財閥解体、農地改革、教育改革をはじめ、日本がふたたび軍国主義に戻らないようにするための改革を実施した。
戦後の最初の2年間に、日本では数万人が餓死した。食料供給元の植民地を失ったことも大きかった。すでに日本は食料を海外から輸入しなければやっていけなくなっていた。輸出を増やす必要があった。それまで満洲から輸入していた原材料や食料を肩代わりしたのはアメリカである。輸出を促進するため、日本では政府が主導して、工業製品の品質向上がはかる体制がつくられた。
1946年5月から東京裁判がはじまり、48年11月にA級戦犯28人に判決が言い渡された。うち軍人6人と文官1人が死刑になった。ほかの国々でも、日本の戦犯が裁かれた。中国では883人の日本人が裁判にかけられ、149人が処刑されている。
1947年になると、冷戦が激化し、世界の分断が進んでいた。占領当局は日本をソ連に対抗する同盟国候補とみなすようになる。1950年に朝鮮戦争が勃発すると、米軍は朝鮮半島に投入され、日本では警察予備隊がつくられた。そして、1954年の自衛隊設置となる。
この「逆コース」戦略を生みだしたのはジョージ・ケナン。ケナンの対日政策の最大の目標は、強く安定した経済の構築であり、そのため大企業を解体するという初期の占領政策は廃止されなければならなかった。
日本企業は合成繊維をはじめとする新技術をアメリカから取り入れて、勢いを取り戻した。輸出が増えるとともに、食料や原料を輸入する余裕もできた。
【朝鮮戦争】
戦後、朝鮮半島は共産主義陣営と資本主義陣営がぶつかりあう舞台となった。戦後、朝鮮半島は38度線を境として、南側がアメリカ、北側がソ連により分割占領された。1948年8月15日に南側で大韓民国、9月9日に北側で朝鮮民主主義人民共和国が誕生する。その翌年、アメリカ軍もソ連軍も朝鮮半島から撤退した。
1950年6月25日、重武装の北朝鮮軍が38度線を越えて南側に侵攻を開始した。北朝鮮の金日成はすでに毛沢東の支持をとりつけていたが、アメリカ軍が介入するとは予想していない。北朝鮮軍はただちにソウルを占拠し、さらに釜山近くまで侵攻した。
7月7日、国連は国連軍を朝鮮半島に派遣することで合意(ソ連は安全保障理事会をボイコット中)した。これを受け、アメリカ軍は9月15日に仁川に上陸し、2週間後にソウルを奪還した。国連軍が38度線を越えると、約20万の中国義勇軍が北朝鮮にはいった。国連軍は押し戻され、ソウルはふたたび北朝鮮と中国義勇軍の手に落ちた。
その後、戦況は膠着状態となり、1953年7月27日に休戦協定が結ばれる。そのかん、日本はアメリカ軍の兵站基地となり、それにより日本経済はおおいに潤う。
【台湾】
日本の植民地時代、台湾の平均的な生活水準と教育水準は大陸中国よりずっと高かった。そこに1947年、蒋介石の国民党勢力が大挙して渡ってきた。1947年2月28日には、台北で暴動が発生、国民党軍は1万8000から2万8000人の住民を殺害した。
国民党が台湾を支配するようになってからも、日本企業が排除されることはなかった。日本の産業復興とともに、台湾でも工業化が進み、多くの台湾企業が成功を収めた。
著者はこう書いている。
〈1960年代半ばまで、日本の実業家の多くは、台湾は小さな島だがビジネスチャンスは大陸より大きいと考えていた。台湾の人口は大陸より少ないが、日本は1964年まで台湾により多くの製品を輸出していた。〉
日本企業が台湾だけでなく大陸と経済関係の構築を望んでいたことはいうまでもない。
【戦後の日中関係】
1949年から72年まで、日本は中国と非公式な接触を保っていた。わずかながら日中貿易もつづいている。
中国側は廖承志と郭沫若、日本側は宇都宮徳馬、松村謙三、河野一郎、高碕達之助が政治的窓口となっていた。
朝鮮戦争終結後の日中関係は山あり谷ありだった。
著者はこうまとめる。
〈1953年から1957年までは、周恩来、吉田茂、鳩山一郎、石橋湛山が関係改善に努力した。1957年から1961年までは、中国が左傾化し、日本が右傾化したために両国関係が悪化した。1961年から1966年までは、中国が大躍進政策をとりやめ、池田勇人首相が挑発を避ける努力をしたために関係はいくぶん改善し、廖承志と高碕達之助のイニシャルをとった「LT貿易」協定が結ばれた。文化大革命初期の1966年から1971年まで、両国関係はふたたび後退した。〉
1949年以降も日本は対中貿易を拡大したいという意向をもっていた。だが、アメリカはそれに反対し、吉田茂は日本が共産中国と2国間条約を結ばないことを約束させられた。
サンフランシスコ講和条約が発効したあと、日本は台湾と日華平和条約を締結する。だが、吉田は最終的に中国とのあいだに全面的な平和・通商関係を樹立することを望んでいた。
朝鮮戦争が終結し、中国国内の政治が安定すると、中国共産党は外国との関係を改善する方向に舵を切った。それを主導したのが周恩来である。
周恩来は日本との関係改善と貿易拡大をめざしていた。1955年に日本で55年体制と呼ばれる安定した政治経済体制ができあがると、鳩山一郎と石橋湛山は中国との関係改善に向けて大胆なアプローチをとった。
1955年にインドネシアのバンドンで開かれたアジア・アフリカ会議で、中国と日本は秘密会談をおこなうが、突破口は開けなかった。
それでも、この年、78人の国会議員が中国を訪問し、東京と大阪で「中国商品見本市」が開かれた。小規模とはいえ、貿易関係は1955年から56年にかけ徐々に増加していった。このころ約2000人の日本人が中国を訪れ、中国代表団も日本を訪問している。
中国は1957年から60年にかけ政治的締めつけ(反右派闘争)を強化する。それは岸政権時代と重なっていた。岸信介は保守派で親台派として知られていた。1958年、長崎での中国国旗毀損事件をきっかけに、毛沢東は日本との経済関係を断ち切り、1959年と60年の日中貿易は低迷する。
中国の大躍進政策は大惨事を招いた。そのいっぽう、日本経済は順調に成長する。
中国は穀物を育てるための化学肥料と、農業機械を製造するための鉄鋼を必要としていた。木綿に代わって化学繊維を取り入れたいとも思っていた。
1960年には中ソ関係が決裂した。中国からソ連の技術者が一斉に引き揚げる。そこで中国は日本に目を向けようとするが、それが具体化するのは池田勇人政権になってからである。
1960年7月、中国の代表団が日本を訪問、これを受けて高碕達之助を団長とする団が中国を訪問した。1962年11月には廖承志と高碕達之助のあいだで「日中長期総合貿易に関する覚書」が交わされた。これがいわゆる両者のイニシャルをとったLT貿易のはじまりとなる。民間の「友好商社」による貿易も認められていた。
この協定により、倉敷レイヨン(現クラレ)は中国にビニロン・プラントを建設する。化学肥料や鉄鋼も中国に輸出された。
台湾政府とアメリカはLT貿易に強く反対した。しかし、民間企業による友好貿易は急速に増え、相互の貿易額は1961年の4800万ドルから66年の6億2100万ドルへと拡大する。
だが、その後の文化大革命により、貿易の伸びは頭打ちとなった。それでも1960年代半ばに日本の対中貿易は対台貿易を追い越していた。
【文化大革命と田中訪中】
文化大革命がはじまると、日本の実業家は中国から引き上げていった。しかし、68年には紅衛兵の攻撃も下火となり、「日中覚書貿易」協定が結ばれる。69年と70年に日中貿易の額は増加に転じた。だが、それは年間10億ドルにとどかない微々たるものだった。
1971年7月、キッシンジャーが中国を訪問する。8月、ニクソンは1ドル360円の固定為替レートを自由化すると発表。いわゆるニクソン・ショックである。ショックはそれだけでは終わらない。1972年2月にニクソンは中国を訪問した。
いっぽう1972年7月7日に首相に就任した田中角栄は、就任からわずか2カ月後の9月25日から30日まで中国を訪問し、29日に日中国交正常化声明を発表した。
笹倉明の新刊 [本]

幻冬舎から笹倉明(僧名プラ・アキラ・アマロー)の新刊新書『出家への道──苦の果てに出逢ったタイ仏教』が発売されました。
笹倉は姫路の高校(淳心学院)の同窓生です。学校は中高一貫のカトリック校で、かれは高校のときからの編入でしたが、すぐに仲良くなりました。
大学も同じ早稲田で、学部はちがうものの、ときどき会って、おしゃべりし、おまえ相変わらず字が下手やなあなどと言われていました。
その後、かれは作家の道を歩み、1980年の『海を越えた者たち』ですばる文学賞佳作、88年の『漂流裁判』でサントリーミステリー大賞、89年の『遠い国からの殺人者』で直木賞を受賞、あれよあれよといううちに売れっ子になっていきます。
それから何冊も本を書きますが、あまりヒット作にはめぐまれなかったようです。奥田瑛二と笛木優子がからむ『新・雪国』という映画を2001年に制作したりもしましたが、失敗に終わりました。
そのかれがタイで暮らすようになったと聞いたのは、もう十年以上前のことです。そして、2、3年前、タイで出家して坊さんになったという新聞記事を読みました。
オビにはこんな紹介があります。
〈直木賞作家である著者は、自らの才能に対する疑いと不安、楽な方へと流れてしまう性(さが)ゆえに、仕事に行きづまり、経済的にも困窮、逃げ出すようにしてタイへ移住する。仏教の国・タイで目にしたのは、毎朝の托鉢風景。俗世への執着を断った修行僧と、彼らに食物を捧げる人々の満ち足りた表情を眺めているうち、著者は我欲に流され、愚行を重ねてきた己の人生のために、一つの決心をするのだった〉
そのとおりかもしれませんが、この紹介は自虐的すぎるかな。かれは才能もあったし、じゅうぶん努力していたと思うのです。それでなければ、直木賞はとれませんよ。
さらにオビには、大きく「異国へと落ちていった直木賞作家はついに俗世を捨てた。なぜだったのか?」との文字が躍ります。
いったい何があったのだろう。おもしろそう。
そう思って、多くの人がこの本を手にとってくれたら、ぼく自身もうれしいです。
じっさい、ここには檀一雄の『火宅の人』ではないですが、複雑な人間模様もあけすけに語られています。
ほんと、人間って困ったものですね。悩みはつきません。
それにつけ、思うのは、たとえ直木賞をとっても、作家として持続的に稼いでいくのが、いかにむずかしいかということです。
この本には、そのアップダウンの生活ぶりもつぶさにえがかれています。
私たちは、だいたい成功物語しか見ないものですが、世間はきびしいもので、大半の人が挫折や苦難を強いられています。
仏教がその救いになるかどうかはわかりません。しかし、だいじなのは、どこかで精神のバランスを保ち、愉快な気持ちで毎日をすごすということかもしれませんね。
人生に浮沈はつきものです。苦悩もまとわりつきます。それでも、それを吹き飛ばす道は、どこかにみつかるはずです。
いまは笹倉が、遠い異国の僧院から、悩める人を照らす存在になってくれることを願っている、というのが正直な気持ちです。
修行はまだまだ。どうぞ達者で、と一声かけたくなりました。山っ気は禁物です。
「純粋な幸福」をめぐる妄想 [本]
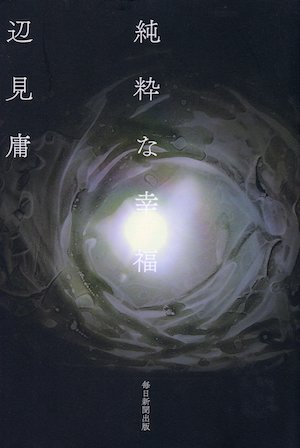
詩や文学はわからない。想像力に欠けるため、どうも苦手なのだ。
それでも、辺見庸の詩集『純粋な幸福』のなかから、長詩「純粋な幸福」を読んでみる。理会にはほど遠いから、以下はただの思い込み、ないし妄想である。
この長詩はちいさな映画館で、ひとり映画に魅入るようにして読むのがいい。そんなふうに、自分の頭のなかにもスクリーンを広げて、次々くり広げられるスペクタクルを、大笑いしたり、唖然としたり、あきれたりしながら、楽しむべきではないか。そんなふうに思ったりする。
出演者は生きている死者たちである。死者たちは死んでいない。むしろ、作者のなかで、生きていた昔より溌剌、奔放になっている。
かれらは松林のなかでつがい、バスに乗って町にでかけ、燃えさかる町に突入し、古い映画館で無声映画を見て、草原で凧になって散華する人たちを眺める。
ほんとうは、そんなふうに要約することに何の意味もない。ことばは根のように広がり、からまり、爆発し、つながっているからだ。その混沌が楽しい。音が美しい。笑える。ことば遊び、エロス、歌と踊り、バイオレンスにあふれている。
ハッピーな詩集である。
肝心なことを書き忘れていた。
純粋な幸福とは何のことか。
味も素っ気もなくいってしまえば、それは「天皇の国にいる喜び」にほかならない。思い込みかもしれないが、ぼくは勝手にそう感じている。もちろん反語である。
たとえば正月の一般参賀で、天皇は「年頭に当たり我が国と世界の人々の安寧と幸せを祈ります」との「おことば」を発するのが恒例になっている。
なぜ、われら国民や世界の人びとが天皇に「安寧と幸せ」を祈られなければならないのか。その「おことば」だけでなく、パレードや行幸、被災地訪問に、われわれが「純粋な幸福」を感じるのは、どうしてなのか。
皇居前広場の祝典で「嵐」もこんなふうに歌った。
ごらんよ僕らは君のそばにいる
君が笑えば世界は輝く
誰かの幸せが今を照らす
僕らのよろこびよ君に届け
これが皇室から発せられる「純粋な幸福」のメッセージでなくて何だろう。奉祝はそんな皇室がいつまでもつづくことを願う祭典にほかならない。
そんなときに縁起でもないかもしれないが、なぜかぼくは1970年11月25日に自裁した三島由紀夫のことを思いおこす。
ミシマは見えざる日本の神に、鍛え上げた最高の知性と肉体を人身御供として捧げることに人生の価値を見いだしたのだった。その目的は日本文化の永遠と安寧を祈ることにあった。
皇室にとっては、さぞ迷惑なことだったろう。腹を切ったとき、ミシマは「純粋な幸福」を感じていたのだろうか。
長詩の一節。
……たくさんの、あおむいたひとの筏。無数の人の艀。足─海側。あたま─山側。河口の造船所ほうこうにながれてゆく。上流からくだってくる、ぼうぼうと発光する幾千の、目をみひらき、あおむいたにんげんたち。あおむいてながれて、戦争をうたふ、純粋な幸福の(無)意識たち。……
臠という漢字があるそうだ。一片の肉。「れん」と読むのだそうだ。
この字にはもうひとつの読み方がある。すなわち「みそなわす」。つまり、神なる存在が、ごらんになる。
われらはかんかんのうを踊らされる臠にすぎない。それを賢きあたりが「みそなわす」のが、永くつづくこの国の風俗である。
そんなことは、もうやめにしないか。
エロスと卑俗と哄笑の大爆発が、18禁のスクリーンいっぱいに広がる。
吉野作造の朝鮮論(2)──中村稔『私の日韓歴史認識』(増補新版)断想(5) [本]

吉野作造は1919年3月のいわゆる三・一運動をどのようにみていたのだろうか。
その前に、まず本書によって、そもそも三・一運動とは何であったかを確認しておこう。
第1次世界大戦終結後、アメリカのウィルソン大統領は、14カ条の平和原則を発表し、そのなかで民族自決をうたった。
これに刺激を受けて、海外在住の朝鮮人独立運動家11名が独立宣言書を起草、採択した。
1919年1月、朝鮮国王、高宗が亡くなる。そのことも、朝鮮内での独立機運を高めたという。
独立運動で、当初中心的な役割を果たしたのは、天道教やキリスト教などの宗教団体である。いっぽう学生たちも、独自に運動を開始していた。
だが、宗教団体は土壇場になって手を引く。
3月1日、学生や民衆、四、五千人が、当時京城のパゴダ公園に集まった。午後2時すぎ、独立宣言書が朗読された。
「われらはここに、わが朝鮮国が独立国であること、および朝鮮人が自由の民であることを宣言する」ではじまる宣言書である。
学生や民衆はいっせいに「大韓独立万歳」と高唱したあと、太極旗を先頭に3隊に分かれて、徳寿宮、外国領事館、総督府に向けて、非暴力的な市内デモ行進をした。これにたいし、総督府の憲兵警察が出動し、デモを鎮圧した。午後7時すぎ、デモはいったん沈静化した。
3月3日、高宗の葬儀当日、京城は人の波にあふれ、あちこち哀惜の声が上がった。
5日になるとふたたび大規模なデモが再開される。治安警察はこれを厳しく弾圧した。その後、商店がデモに呼応して店を閉め、労働者や職工がストライキを実施し、農民も立ちあがった。
中村によれば、「示威運動は、憲兵警察に弾圧されてのちに武器を取っての抗争に移行していった」。
これにたいする官憲の弾圧は苛酷だった。
水原(スウォン)郡のある町では、20数名のキリスト教徒と天道教徒が教会に閉じこめられて射殺された。
逮捕され、拷問の末、獄死した女子学生もいる。
ある集計によれば、朝鮮人の死者は7509名、負傷者は1万5961名、被囚者は4万6948名。これにたいし、日本側の被害は官憲の死者8名、負傷者158名だったとされる。
この事件を吉野作造はどうとらえていたのだろう。
「中央公論」に発表された「朝鮮暴動前後策」で、吉野は「朝鮮の暴動は何と云っても大正の歴史における一大汚点である」と書き起こす。
かれはさらにいう。暴徒を徹底的に鎮圧すべしという意見もあるいっぽう、朝鮮人の困窮を救うべきだという意見もある。だが、だいじなのは「一視同仁政策の徹底」である。そのためには朝鮮人にある種の自治を認める方向に進むとともに、(米国人宣教師を含む)第三者による事件の真相解明機関を設けるべきだ。
さらに別の論考では、「我々は朝鮮の問題を論ずる時に、曽(かつ)て朝鮮人の利益幸福を真実に考へた事があるか」と問いかけ、次のように論じる。
問題は、今度の朝鮮暴動でも、国民のあいだに「自己の反省」がないことだ。日本人はなぜ朝鮮全土に排日姿勢があふれているかを考えたことがあるのか。それはまさに日本による統治の失敗を意味している。にもかかわらず、当局者には何ら反省がみられない。
朝鮮人が日本の統治をどのように考えているかを朝鮮人の立場から考えてみる必要がある。朝鮮人の日本人にたいする怨恨は根が深い、と吉野はいう。
水原(スウォン)の虐殺が、朝鮮人の憲兵殺しにたいする報復措置だという言い方についても、それは野蛮きわまるという考え方だと述べている。吉野は事件をうやむやにせず、真相を徹底的に究明すべきだと主張した。
三・一運動は日本の朝鮮統治の失敗を象徴している。少なくとも今後の統治にあたっては、次の点に留意しなければならない、と吉野はいう。
ひとつは朝鮮人にたいする差別的待遇の撤廃である。とりわけ、教育面での差別をなくさなくてはいけない。官吏採用についても、地位や給与の面で、日本人と朝鮮人とのあいだで差別があるのをやめるべきだ。
「武人政治」は撤廃されなければならない。
朝鮮の伝統や文化を無視した、無理やりの同化政策はとりやめるべきだ。
そして、言論の自由を与えよ。憲兵政治は愚かである。
こうした見解は、石橋湛山の考え方とも共通する、と著者の中村稔は指摘する。
三・一運動を受けて、日本政府はどう対応したか。
長谷川好道に代わって、朝鮮総督に斎藤実が就任した。斎藤は、これからは「文化政治」をやるのだと打ちあげている。
あたかも、吉野作造の提案が受けいれられたかにみえるが、その実態はまったくちがっていた。
斎藤新総督のもと、憲兵警察制度は廃止された。地方自治の拡充や、「内鮮人共学」が高らかに宣言された。朝鮮語の新聞・雑誌発行も認められ、会社設立を許可制から届出制にすることによって、朝鮮人の会社設立も容易になった。
そのいっぽうで、この時期、朝鮮各地では、「内鮮融和」のため、天照大神と明治天皇を祭神とする朝鮮神宮が盛んにつくられている。
文化政治の名のもとで、実際におこなわれたのは、日本によるソフトな政治支配強化だった。
警察官の数も警察署の数もむしろ増えていた。地方政治でも日本人がより実権を握るようになっている。朝鮮語教育はむしろ減らされ、日本語教育が強化された。検閲もむしろ厳しくなっている。実業面でも、日本人企業がこの時期より多く進出した。そして、朝鮮神宮がむしろ朝鮮人の反感を招いていたことはいうまでもない。
これにたいし、吉野は「朝鮮に於ける統治の改善は幾分内地人の慈悲心を満足せしめては居るだらうが、朝鮮人の満足は買って居ない」とはっきり書いている。
〈朝鮮人は法律上日本臣民である。けれども固有の日本臣民と同一に待遇する事は出来ないといふ事実に基いて、全然内地人と同様の権利を与へられて居ない。是れ法律に於ても朝鮮人を日本人となるべきもので、既に日本人であるものと見てゐない証拠である。……此根本的誤謬が悟られ且(か)つ改められざる限り、吾々日本国民の懸案としての朝鮮問題は実質的に一歩も進める事は出来ない。〉
吉野は朝鮮のような歴史と文化をもつ国の人びとに、「同化」を押しつける反面、差別と侮蔑で事に当たろうとする日本当局の愚を諭している。
帝国時代にこういう主張をした人物がいたことは、もっと評価されるべきである。
いまは植民地時代ではない。しかし、植民地時代の反省から生じたこうしたまっとうな感覚は、現在も継承されるべきだと思われる。



