ポール・ジョンソン『現代史』をめぐって(1)──大世紀末パレード(8) [大世紀末パレード]
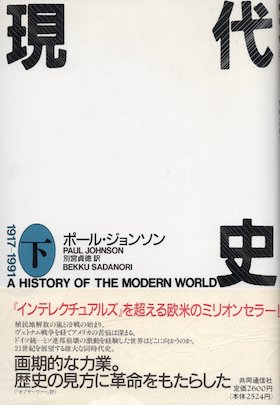
ここで、方向を変えて、1980年代を鳥瞰してみることにする。ぼく自身が編集を担当したポール・ジョンソン(1928〜2023)の『現代史』(別宮貞徳訳)を紹介してみたい。著者はイギリスの保守派で毒舌の歴史家、ジャーナリスト、評論家として知られる。
原著はもともと1983年に出されたものだった。その原著に、日本語版のためにぼくが依頼して、ソ連崩壊までの章を書き下ろしてもらった。翻訳され、日本で発行されたのは1992年のことだ。その最終章は「自由の復権」と名づけられ、こんなふうにはじまっている。
〈1980年代は現代史の分岐点の一つである。民主主義は自信を取り戻し広がった。法の支配が地球上広範囲に確立され、国際的な略奪行為は阻止され処罰を受ける。国際連合、とくに安全保障理事会は、はじめてその創立者の意図に沿って機能しはじめるようになった。資本主義経済は力強く繁栄し、市場経済こそ富を増し生活水準を向上させるためのもっとも確実な、また唯一の道であるという認識があらゆるところで定着していった。知的な綱領としての集産主義は崩れ去り、それを放棄する動きがその拠点においてさえ始まった。最後の植民地コングロマリット、スターリンの帝国は解体される。ソヴィエト体制そのものが歪みを増し、諸問題が幾重にもかさなって、超大国としての地位も危うくなれば冷戦の継続を望む意志も衰えを見せた。1990年代のはじめにはもはや核戦争の悪夢は薄れ、世界はより安全に、安定度を加え、そしてなによりも希望に満ちてきた。〉
いま思えば、スターリンの帝国が解体され、民主主義が自信を取り戻し、世界は「希望に満ちてきた」という感覚は、いっときの幻影だったのではないかとさえ思えてくる。なにかが終わったのはたしかだ。だが、その後の世界の歩みはむしろ戦争と苦難と抑圧に満ちていたのではないか。だとすれば、終わりは終わりではなく、はじまりははじまりではなかったことになる。
ポール・ジョンソンが1980年代の世界をどのようにみていたかを紹介しておきたい。
最初に強調されるのは、20世紀にさまざまなイデオロギーがしのぎを削ったにしても、「人類の圧倒的多数の人びとにとっては、宗教が実際にいまでも自分たちの生活の大きな部分を占めている」ということである。宗教が消滅するという考え方は、むしろ古くさくなったとさえ述べている。
とりわけ、この時代にローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世(1920〜2005、在位1978〜2005)のはたした役割は大きかった。カトリック信仰の強いポーランド出身で、詩人、劇作家、哲学者でもあった。衰退しかかっていた伝統的カトリシズムの復興をやりとげた人物である。1981年5月に暗殺されそうになったが、1980年代から90年代にかけ世界各国を何度も訪れ、2億人の人びとと接した。カトリック信者の数は1978年時点で約7億4000万人だったが、2020年現在では約12億人に増えているといわれる。もともと多かったヨーロッパ、北米に加え、中南米、アフリカで信者数が大きく伸びている。
もっとも北米やヨーロッパの先進国では、教会の日曜礼拝に出席する人の数は少なくなった。そのいっぽうで、カトリシズムやプロテスタントの教義からはずれた、カリスマ的な根本主義の宗派が勢いを伸ばした。中南米では過激な政治行動を求める「解放の神学」が登場したが、大きな大衆的支持を受けるにいたらなかった。米国では福音主義のプロテスタントがメディアを利用して大躍進し、中南米まで伝道活動を広げている。
注目すべきはイスラム原理主義が力をつけ、1980年代以降、大きく広がったことだ。これに対抗するかたちで、ユダヤ教超正統派も復活した。ジョンソンによれば、ユダヤ教超正統派は「ダヴィデの王国の『歴史的』国境線を拡大するとともに、イスラエルを神権政治の国に改造することを目標としている」という。
イスラム世界は西アフリカから地中海南部、東アフリカ、バルカン諸国、小アジア、中東、南西アジア、マレーシア、インドネシア、フィリピンにいたるまで大きく広がっている。2020年時点でその信者数は19億人。
1970年代以降は、いわば「イスラム復興」の時代となったが、「その一つの支えとなったのは石油によって新たな富を得たことからくる辟易させられるほどの自信である」とジョンソンはいう。
とはいえ、イスラム教の内部はスンニ派、シーア派、イスマーイール派、ドゥルーズ派、アラウィー派などと分裂しており、それがしばしば対立を呼ぶ原因となっている。
中東の対立は加えて、何よりもイスラエルという国家の存在によるところが大きい。1980年代までは、イスラエルが結局のところ衰退する、とアラブ側は考えていた。だが、それは大きな誤りだった。
1979年にはイランで革命が発生し、国王が追放され、アヤトラ・ホメイニのシーア派原理主義者が実権を握った。その後、長年にわたる国境紛争に端を発して、イランとイラクのあいだで大規模な戦争がはじまる。イラクのサダム・フセイン大統領は、シャトルアラブ川とイランの油田を手中に収めるため迅速な勝利を得ようとしたが、そのもくろみは失敗し、戦争は8年もつづいて、両国で100万人以上の死者を出した。宗教が原因の戦争ではなかったが、それでもスンニ派とシーア派の対立が戦争の激しさをあおった面はある。
そのことはレバノンも同じだ。レバノン内戦は1975年から90年にかけて断続的に発生し、シリア、パレスチナ解放機構(PLO)、イスラエルが介入し、イスラム教の諸宗派がからんで収まりがつかなくなり、「商業都市ベイルートは滅び、レバノンはもはや独立国としては存在せず、古来のキリスト教共同体は優越性を失った」。
アフガニスタンでは1978年4月にソ連の後押しによりダウド政権が倒された。政権を握った人民民主党はイスラム教の勢力をそごうとして恐怖政治を敷く。その後、政治が混乱するなか、1979年末にソ連がアフガニスタンに侵攻する。ソ連の侵攻はムジャヒディンと呼ばれる反政府民族主義ゲリラによる激しい抵抗をもたらし、1988年5月のソ連軍の完全撤退につながる。
「ソ連指導部が最終的にアフガニスタンからの撤退を切望したのは、一つにはゲリラ戦が近隣のソヴィエト・アジアのイスラム地域にまで拡大するのではないかと懸念したからだった」と、ジョンソンは論じている。事実、ソ連領内でも、1970年代から80年代にかけて、イスラム復興の動きが強まっていた。
歴史は宗教を抜きにしては論じることができない。宗教と信仰は人びとの生活に深く根ざしている。たとえ、宗教を無視する風潮が強まったとしても、政治を宗教に完全に置き換えることはできなかった、とジョンソンはいう。
いまも中東地域をはじめ、世界の紛争は収まる気配をみせていない。島国の日本人にとっては遠い彼岸のできごとのようにみえるかもしれない。しかし、それがもはや他人事(ひとごと)ではないことを、『現代史』は教えてくれる。世界のできごとが近所のできごとと変わらない時代がはじまっているのだ。
『現代史』はこれからさらに1980年代の世界を探索していく。もう一度、あのころを思いだしながら、少しずつ読み進めてみる。
労働市場の形成──ヒックス『経済史の理論』を読む(7) [商品世界論ノート]

ヒックスは最初に「仕事」と「労働」を区別している。農民や役人、職人、商人、地主などは、それぞれの「仕事」をもっているが、労働者はそうではない。これにたいし、労働者の特徴は「誰かのために働く」ということだという。労働者は主にたいして「従者」の関係にある。
こうした主従関係は古代から存在した。
古くから労働は交易の対象(すなわち商品)であり、そこにはふたつのタイプがあった。労働者がすっかりそのまま売られるのが奴隷制、用役(マルクスの概念でいえば労働力)のみが賃貸されるのが賃金支払制だ。
ヒックスは奴隷制を論じるところからはじめている。
古代から奴隷は、戦争捕虜や奴隷狩りの産物だった。奴隷はしばしば家内労働や家族の従者として用いられ、家族の一員として厚遇されることもなかったわけではない。しかし、概して奴隷の身分は低く、その主人によって自由に売買される存在だった。
奴隷はまた店舗や仕事場で使用された。この場合、奴隷の待遇は、主人との関係性によって決まり、責任を与えられることもあれば、牛馬のように酷使されることもあった。運がよければ、事業をまかされ、解放奴隷となった者もいる。
しかし、奴隷制の暗い面が噴きだすのは、もっぱら大規模に奴隷が使用された場合だ、とヒックスはいう。プランテーションやガレー船、鉱山で使用された場合は、奴隷には苛酷な運命が待っていた。
近代のプランテーションでは、西インド諸島の砂糖農場やアメリカの綿花農場がよく知られている。南アメリカの鉱山では多くの奴隷がこきつかわれていた。
ヒックスはこう書いている。
〈奴隷労働をもち、かなり大規模な企業を経営している奴隷所有者にとっては、奴隷は生産用具であって、他の一切の生産用具と同じやり方で奴隷所有者の計算の中にはいってくる。すなわち、近代の製造業者の機械に対する見方と同じである。〉
奴隷が低廉なときには、奴隷は集団的に大量使用され、死ぬまで酷使され、市場で買い替えられた。ところが奴隷が高価になると、主人にとっては奴隷をだいじに扱うことが得策となり、奴隷の子どもを育てて、次世代の奴隷にすることも有用な選択肢となっていく。
19世紀はじめに奴隷貿易は廃止された。その理由は、アフリカでの奴隷狩りがあまりにも残酷であるとともに、大西洋航路で失われる奴隷の数があまりにも多かったからである。だが、奴隷貿易が廃止されたあとも、奴隷制そのものは長いあいだ廃止されなかった。
奴隷貿易の廃止により、奴隷の待遇は農奴並みに向上した。だが、奴隷制が存在するかぎり、奴隷は売られたり、別の地に移されることを免れなかった。家族がばらばらにされることも多かった。
いっぽう「自由」労働市場も奴隷制が廃止される以前から存在した。人道的な問題は別として、効率面からみると、奴隷労働と自由労働とではさほど差があるわけではない。自由労働が奴隷労働にとって代わった理由は、自由労働のほうが低廉になったからにほかならない、とヒックスは断言する。
奴隷労働には短期的維持費だけでなく長期的維持費もかかる。これにたいし自由労働の場合は、雇用契約期間が終了すれば、賃金を支払う必要がない。しかし、自由労働の供給が少なければ、賃金は上昇するだろう。したがって、次のようなことがいえる。
〈もし奴隷労働が豊富であれば、それは自由労働を駆逐することになり、逆に自由労働が比較的豊富であれば、それは奴隷を駆逐することとなる。両者は労働の供給源としては互いに競合的であって、両方ともに用いられるときには、一方の利用可能性が他方の価値(賃金ないし資本価値)に影響を与える。〉
これが奴隷労働と自由労働との経済的選択の論理である。
歴史的にみれば、ギリシア人やローマ人は戦争捕虜を奴隷としていた。カエサルやアウグストゥスの時代になると、奴隷労働は少なくなり、労働力は大部分が自由労働になった。中世になると、奴隷はさらに希少になり、自由労働制度が確立される。ふたたび奴隷制が活発になるのは、15世紀になってアフリカ航路が開かれてからである。
西ヨーロッパでは中世以来、自由労働が基本となっていたが、都市の発達が農村人口を引き寄せたことはまちがいない。11世紀から13世紀にかけ西ヨーロッパでは急速な人口増加が生じ、農民の一部が働き口を求めて都市に流入した。
かれらは商人階級になることをめざすが、昇進をはたせる人はごくまれで、たいていは臨時雇いや半雇いとなり、半ば労働者、半ば乞食の境遇に甘んじ、家庭をもつこともままならなかった。だからといって、もはや農村に戻ることもできない。すると都市は労働不足ではなく、労働過剰の状態におちいる。
植民地時代のアメリカの場合は例外である。農業用の土地はふんだんにあった。そのため都市ではたらく労働者には高い賃金を払わなければならなかった。そうでなければ、たちまちかれらは都市を離れ、開拓農民として生きる道を選ぶからである。
こうした特殊事情により、アメリカでは奴隷制度が自由労働制度よりも低廉となり、土地を開くにあたってはアフリカから大量の奴隷がつれてこられたのである。近代になって、奴隷制がふたたびあらわれたのは「ヨーロッパには奴隷に対する需要はなかったが、アメリカにはあった」からだ、とヒックスは記している。
だが、いまは近代の産業革命以前にもう一度戻ってみよう。そのころ、西ヨーロッパの労働事情はどうだったのだろう。
理屈上でいえば、産業革命以前でも手工業を含めた商業の発展は、労働需要を増やしたはずである。農村から人口が流入しても、都市では過剰労働が吸収され、労働不足となって、賃金が上昇していく局面がおとずれてもおかしくない。だが、そうした現象は生じなかった。
「当時の経済においては農業部門がきわめて広大な部分を占めていたために、商業に雇用される機会は、それが増大しているときですら依然として規模は小さかった」と、ヒックスは指摘する。
ところで、一概に都市の労働力といっても、それは同質ではありえない。労働力の質が高く、希少であればあるほど賃金も高くなる。そして、より質の高い労働力をもつ労働者は安定した雇用と生活の保障を求めるようになるだろう。逆に都市プロレタリアートと呼ばれる低い等級の場合は、生活の保障もないし、賃金も低い。
低級労働から高級労働まで、自由労働は等級別に構成されている、とヒックスはいう。低級労働から高級労働への移動は容易ではない。それを可能にするのは訓練と教育である。だが、それには費用をともなう。
そうした費用が払えない場合の訓練・教育法としては徒弟制度が存在した。親方に束縛される徒弟は、奴隷の身分とさほど変わりない。かれらは厳しい徒弟期間をすごさなければならない。
したがって、近代的な労働市場が生まれるのは「産業革命」をまたなければならない、とヒックスは論じている。
日航123便に何がおこったのか──大世紀末パレード(7) [大世紀末パレード]
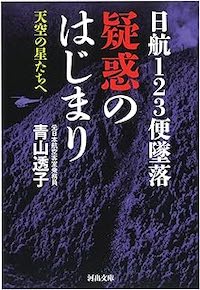
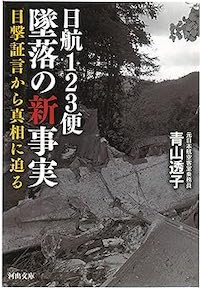
1985年を語るうえで避けて通れない「大事故」がある。
8月12日月曜日の18時、東京羽田空港を離陸して大阪伊丹空港に向かった日航ジャンボ機123便が相模湾上空で非常事態におちいり、群馬県上野村の御巣鷹山尾根に墜落したのだ。
墜落位置の特定には時間がかかり、翌朝になってようやく判明した。地元の消防団員が機体を発見し、生存者の救助にあたった。乗客乗員524人のうち、生存者はわずか4人。犠牲者のなかには歌手の坂本九さんや阪神球団社長の中埜肇さんなども含まれていた。
生存者発見の通知をうけた日赤の医師と看護婦が、警視庁のヘリコプターで現場に到着したのが12時13分。その後、自衛隊の救援ヘリが到着し、13時5分にようやく生存者の収容がはじまった。
生存者は川上慶子さん(12歳)、吉崎美紀子さん(8歳)、吉崎博子さん(35歳)、落合由実さん(26歳)の4人だった。4人とも機体後部の座席に座っていた。
事故原因については、その後、断片的にさまざまな報道がなされたが、しばらくたって、事故調査委員会が次のような結論を出した。
事故機の機体は7年前に「しりもち事故」をおこしていたが、ボーイング社の修理がふじゅうぶんだったため、「後部圧力隔壁」に疲労亀裂を生じていた。その圧力隔壁が破壊されたため、機内に急減圧が生じ、突風が吹いて、垂直尾翼が吹き飛ばされ、機体のコントロールが不能になった。
要するに、ボーイング社の修理ミスによる「後部圧力隔壁」の破壊が事故原因だというわけだ。そのとき、圧力隔壁ということばが頭にインプットされたことを、ぼくも覚えている。そして、ほとんどだれもが、公表された事故原因に何となく納得し、二度とこうしたことがないようにと、このとき犠牲になった人びとを毎年追悼するようになった。
ところが、圧力隔壁破壊説に疑問をもちはじめた人がいる。みずからも日本航空の客室乗務員(当時の呼び名はスチュワーデス)を務めた経験のある青山透子さんである。彼女はこの墜落で何人かの同僚を亡くしている。
圧力隔壁はほんとうに破壊されたのだろうか。これははたして「事故」だったのだろうか。
彼女はこう書いている。
〈生存者の座席の位置は、最後尾周辺に集中している。特に当時、多くの人々の記憶に残った川上慶子さんは最後尾の列である。圧力隔壁の前にあるトイレを挟んだその座席は、乗客の中で最も後部圧力隔壁に近い位置だが、彼女は、頑強な垂直尾翼を吹き飛ばすほどの急減圧による空気圧の影響は全く受けなかった。現実に吹き飛ばされたわけでもなく、耳鼻咽喉もダメージを受けず、他の生存者を含めてみても、誰も鼓膜すら破れていない。〉
事故調査報告では、修理不十分な圧力隔壁が壊れ、客室内を突風が突き抜けて、内側から垂直尾翼を吹き飛ばしたことになっている。
ところが、川上慶子さんの事例をみても、客室内に突風が突き抜けた形跡はまったくみられないのだ。飛行機がコントロールを失って飛びつづけるあいだも、乗客は座席についたままで、心を平静に保ち遺書を書き残した人もいる。
飛行機が異常な爆発音をとらえたのは、伊豆半島と大島のあいだを飛行していた18時24分39秒のことだという。このとき急減圧は生じていない。急減圧が生じたなら機内で爆風が発生し、物が飛び散り、人も飛び上がり、鼓膜も破れたはずだが、そうした事態は生じていない。
だが、すでにこのとき垂直尾翼は吹き飛ばされていた。垂直尾翼を失った飛行機が操縦不能になることは容易に想像できる。機長は無事に着陸することだけを願って、必死に操縦桿を握っていた。御巣鷹の尾根に墜落したのは18時56分のことである。
事故の原因は圧力隔壁が壊れたことだとされるが、それはあくまでも経過説明の(しかも根拠の乏しい)仮説であって、垂直尾翼が吹き飛んだことこそが致命的な問題だった。たとえ圧力隔壁が壊れたとしても、そのとき生じた内圧で垂直尾翼が吹き飛ぶとは考えにくい。もし、そんなものすごい内圧が生じていたなら、最後部の座席に座っていた4人も機外に飛ばされていたかもしれない、と青山さんは指摘する。
じっさいには何がおきていたのか。いちばん可能性が強いのは、垂直尾翼が「外力」によって破壊されたということである。その垂直尾翼は相模湾に落下し、現在も一部しか回収されていない。
垂直尾翼を破壊した「外力」とはいったい何だったのだろう。
相当大きな破壊力をもつものがぶつからないと、頑丈な垂直尾翼がこわれるはずはない。しかも、損傷を受けたのは、垂直尾翼の横側である。
隕石がぶつかったという説は却下される。なぜなら真横から隕石が当たるとは考えにくいからだ。
いちばん可能性が高いのは、空中を飛ぶ何かの物体が、垂直尾翼の側面にあたったということである。ひょっとするとミサイルだったのではないかという疑念がわく。
青山さんによると、日航123便が墜落した日には、防衛庁が護衛艦「まつゆき」の試運転を実施していた。自衛隊と米軍との合同訓練がおこなわれた前々日には、国産ミサイルのモデルとなった米国製ミサイルが飛ばされたという記録がある。すると、日航機が墜落した日も、何かのミサイル実験がおこなわれていたのではないか。
どこから発射されたかは別として、「練習用のオレンジ色の物体[模擬ミサイル]を誤って発射させて外力を発生したことによって垂直尾翼が破壊され、それが墜落の原因を作った」と、青山さんは確信するようになった。
しかも、当日は「航空自衛隊戦闘機のファントム2機が墜落前の日航機を追尾したことが目撃されて」いた。米軍も情報をつかんでいた。墜落現場はすぐに特定できたはずだ。にもかかわらず、それが発表されず翌朝まで延ばされ、人命救助が遅れた背景には、自衛隊による何らかの隠蔽工作があった可能性が否定できない、と彼女はいう。
後部圧力隔壁破壊説には大きな疑問が残る。日航123便墜落「事故」の真相はまだ謎に包まれているのだ。
農業の市場化──ヒックス『経済史の理論』を読む(6) [商品世界論ノート]

ヒックスはこんなふうに書いている。
土地・労働という生産要素、農業・工業という生産形態は、いつの時代にも生産に不可欠なものだ。しかし、それらは当初、市場に包摂されているわけではなかった。市場と金融はあくまでも商人経済の産物だった。土地と労働、農業と工業が市場化(さらには金融化)され、土地市場、労働市場、農業市場、工業市場が生まれると、近代が誕生し、いわば「商品世界」が形成される。
そうした全体の流れを頭にいれておくとして、今回のテーマは農業の市場化である。
近代以前の農業は領主−農民体制のもとに成り立っていた。領主は土地を支配し、農民は土地を耕しているが、領主と農民は互いに相手を必要としていた。たとえ農民にかかる負担が大きかったとしても、農民はその見返りとして何かを得ていたのだ、とヒックスはいう。
その何かとは端的にいえば保護である。農民は村落をつくり、労働を投入して作物をつくるまで、多くの時間を必要とする。しかし、自己の労働の果実を、侵略者や盗賊から守るのは容易ではなかった。これにたいし領主が農民に与えるのは、家臣団による軍事的保護である。
さらに地域内や隣接地域とのさまざまな紛争も解決されなければならなかった。領主はいわば防衛と司法の役割をはたしていた。その見返りとして、農民は領主に貢租を納めたというわけだ。
問題は、こうした領主−農民体制に市場がどのようにして入りこんでいったのかだ。その第一歩は農民と行商人との交易だろう。もっと重要なのは領主自身の交易だ。領主と農民は、この地には産しない商品を求めて、行商人との交易をはじめる。
交易は貨幣があればより便利だろう。領主も農民が貢租を物納でなく貨幣で収めてくれれば手間が省ける。貢租を貨幣で収めるためには、農民が農産物を商人に売って、貨幣を手に入れなくてはならない。そして、その一部を手元に残し、残りを領主に収めるかたちにすればよい。
農産物が売られるようになると、農業市場が生まれる。しかし、そのうち、農民の貢租に頼るのではなく、耕作地の一部を自分のものとし、直轄地をつくろうという領主がでてくるかもしれない。すると領主はこの直轄地に農民を集め、市場向けの商品をつくらせるようになる。ここでは農民はより身の安全を保障されるものの、領主に直属する「農奴」となっていく。
それでも領主−農民体制はまだ崩れていない。同じ領地のなかでも領主直轄地ではない農地を耕す農民も多い。農民は市場と関係をもつようになっても、土地と密接に結びついている。
この時点ではそもそも土地所有権は確立していない。領主も土地に権利をもっており、農民も土地に権利をもっているのだ。
国王の命令によって領主が変わる場合もあるかもしれない。しかし、その土地は売買されるわけではない。
領主が商人からより多くの金を借りたい場合はどうだろう。土地の権利は慣習的なもので、もともと担保価値は低い。それでも無理やり土地を担保にして借入をおこなおうとするなら、領主は一定の土地にたいするみずからの財産権を主張する必要に迫られる。
担保は所有権の移転、すなわち事実上の売却へとつながる。だが、領主が一部の土地を売却し、土地の所有者が変わったとしても、だれかがそこを耕作しなければならない。農産物を生みださない土地は価値がないからである。
新たに土地財産を手に入れた者は、農民と契約して貨幣地代を受けとる。それに違反する場合は農民に立ち退きを迫らなければならない。だが、そうした取り決めは紛争のもとともなる。
新たな土地所有者は、農民に年限を決めて土地を貸すこともできる。ここでは借地農業経営が成立する。
14世紀のヨーロッパでは、黒死病の流行により人口が減少した。それにともない、農民が離散する。こうして、地代の減少と賃金の上昇が生じると、多くの領主が財政困難のため、農地を手放すようになった。その農地を買い取ったのは、農民であり、これにより自由農民制への移行がはじまる。
いっぽう、貴族からの借地による直接農場経営が、賃金労働者を雇い入れるかたちで、より合理的におこなわれるようになる。
そのどちらもが、旧来の領主−農民体制を崩していくことになる、とヒックスはとらえている。
だが、東ヨーロッパでは人口の減少が、これとは逆の事態を招いた。すなわち農民の土地へのしばりつけが強制的におこなわれたのだ。ここでは農民はふたたび「農奴」化されることになる。しかも、この抑圧体制は長きにわたって維持された。
ここでヒックスは農業の市場化が同時に法と秩序の浸透をともなっていたことを指摘する。すると、これまで農民を保護していた領主の役割を「国家」が引き継ぐことになる。
権力が領主から国家に移るさいには革命が生じることがある。革命が生じなくても、権力の移行によって貴族は飾り物と化し、自分たちの所有地から生計を支えるだけの収入を得るだけの存在になっていく。
いずれにせよ、近代においては実質的に国家が領主にとって代わるという事態が生じるのだ、とヒックスはいう。
だからといって、国家と領主の役割が変わるわけではない。国家は農地改革をおこなうことによって、農民に農地の所有権をもたせる場合もあるし、逆に国営農場制度をつくり、その農地に農民を帰属させる場合もある。だが、いずれにせよ国家は農地の保護者として、租税を請求する権利をもつようになる。
農業は自然の影響に左右されるため、農業経営者による決定が重要な役割をもっている。ただし、国営農場の場合は、どのような作物をつくるか、それをどのように販売するかの決定は、現場の経営者によってではなく、もっと上でなされる。それが往々にして大きな齟齬をきたす。
借地農は自作農と同じく、独立農場経営者とみなされる。しかし、同じ借地農でも、プランテーションの場合は、その意思決定は所有者との契約に縛られることになる。
独立農場経営者は、市場向けの農産品を生産し、それをできるだけ多く売らなければならない。地代や租税、負債など対外的な支払もあるからだ。独立農場経営者の経営規模は概して小さい。そのことは資本の不足につながる。
土地の改良や農業機械への投資は多額の費用を要する。農産物の産出量はかならずしも安定しているとはいえない。自然災害による悪影響も考えられる。市場価格も変動しがちだ。こうした事態に備えるためにも、資本が必要になってくるのだが、資金を借り入れようとしても、土地は不確実な担保にしかならないため、しばしば高利貸に頼ることになり、これまで農民は大きな債務負担をかかえることが多かった。そうした農民の窮状を救おうとしたのが農業信用組合や土地銀行だ。
いっぽうで、地主が資本を十分にもっているなら、地主が自分の小作人を助けるというケースも考えられた、とヒックスはいう。これはとりわけイギリスの大地主の場合だ。かれらは大きな土地にたいし、資本を長期投資し、生産性を改善する技術を導入することによって、農業からの収益を確保しようとした。
だが、その場合ももはや領主―農民の関係は存在しない。農業経営者のために資本の供給を保証するのは国家である、とヒックスはいう。
さらにこう指摘している。
〈今世紀に非常に多くの国々の農業を変えた技術改良によって、農業に従事する人々の割合が減少しつつあることは周知のことがらである。かつてはすべての経済的職業のなかで首位であったものが、いまや他の職業と同様に、一つの「産業」にすぎなくなろうとしている。これらの技術改良がもたらしたもう一つの帰結は、一人の農業経営者がうまく管理できる(少なくとも算出量で計った)単位の規模が著しく大きくなったことである。……さらにもう一つの帰結は、大きな農地の管理が昔に比べて容易になったので、従属農場経営が相対的に有利になったことである。〉
市場化は農業を大きく変えていった。市場化の進展は領主支配を崩し、それに代わって、国家が大きな役割をはたすようになる。それとともに、農業はひとつの「産業」になっていく。こうした過程をヒックスはえがいたといえるだろう。
ちっちゃな大論争(2)──大世紀末パレード(6) [大世紀末パレード]

1985年1月から4月にかけ、吉本隆明は雑誌「海燕」で埴谷雄高と論争をくり広げた。
論争の後半で、埴谷は84年9月21日号の雑誌「an an」に掲載された、最新ファッションをまとった吉本の写真に衝撃をうけた。
埴谷はこう書いている(数字は算用数字で表記した)。
〈最初の写真には、多くの書物に囲まれた広い書斎で、16,000円のセーター、13,800円のダンガリーシャツを着ながら原稿を書いているあなたの横向きの姿が写されていますが、この書斎の天井から垂れているシャンデリアもテーブル、ランプも豪華だと思いながらも、あなたの勉強ぶりに感心しこそすれ、苦言などありません。私が衝撃をうけたのは、次のページの写真でした。〉
埴谷が衝撃を受けたというのは、外の感じのよい建物を背に腰掛け、微笑する吉本のもう1枚の写真だった。光の関係で、吉本の背後にはまるで後光が射しているかのようにみえた。
〈そして、そのとき、あなたは、62,000円のレーヨンツイードのジャケット、29,000円のレーヨンシャツ、25,000円のパンツ、18,000円のカーディガン、5,500円のシルクのタイ、を身につけ、そして、足許は見えませんけれど、35,000円の靴をはいています。このような「ぶったくり商品」のCM画像に「現代思想界をリードする吉本隆明」がなってくれることに、吾国の高度資本主義は、まことに「後光」が射す思いを懐いたことでしょう。
吾国の資本主義は、朝鮮戦争とヴェトナム戦争の血の上に「火事場泥棒」のボロ儲けを重ねたあげく、高度な技術と設備を整えて、つぎには、「ぶったくり商品」の「進出」によって「収奪」を積みあげに積みあげる高度成長なるものをとげました。〉
左翼の理念をかかげて冷たい皮肉を放つ埴谷の「苦言」に、吉本はことこまかに反論した。
いま自分が住んでいる家はお寺の借地に建てられた建売住宅で、もとからついていたシャンデリアのぶら下がった応接間を仕事場の書斎に転用しているだけだ。家の広さは埴谷邸の半分もなく、そこに家族4人がくらしている。それをあたかもぜいたくなくらしをしているように記すのは、「最低のスターリン主義者」の卑しさを示す以外の何ものでもない。
じっさい、売れっ子評論家とはいえ、ほとんど筆一本でくらしている吉本の収入は、ベストセラー作家などとちがって、さほど多くはなかっただろう。もっとも、その点は埴谷も同じである。
さらに吉本は自分の身につけているものがいかに高価なものかを強調する視線の卑しさに、スターリン主義的な(あるいは毛沢東思想的な、といってもよいが)理念がまとわりついていることを感じた。
「アンアン」で吉本が披露したのはコム・デ・ギャルソンの紳士服だった。ここで、吉本はコム・デ・ギャルソンを主宰する川久保玲のファッション・デザインが世界最高水準をもつ、いかにすぐれたものであるかを強調する。そして、そのモデルを務めた自分に「苦言」を呈する埴谷に、資本主義企業のつくりだす商品それ自体を否定する左翼の類型的視線を覚えるのだった。
吉本はどこか「アンアン」をさげすんでいるようにみえる左翼インテリの埴谷をさとすように、こうも述べている。
〈「アンアン」という雑誌は、先進資本主義国である日本の中学や高校出のOL(貴方に判りやすい用語を使えば、中級または下級の女子賃労働者です)を読者対象として、その消費生活のファッション便覧(マニュアル)の役割をもつ愉しい雑誌です。総じて消費生活用の雑誌は生産の観点と逆に読まれなくてはなりませんが、この雑誌の読み方は、貴方の侮蔑をこめた反感とは逆さまでなければなりません。先進資本主義国日本の中級ないし下級の女子賃労働者は、こんなファッション便覧に眼くばりするような消費生活をもてるほど、豊かになったのか、というように読まれるべきです。〉
「アンアン」に載っているような商品は、あくまでもあこがれであり、目標であっても、それを楽々と買えるOLは少なかっただろう。それでも、レーニンやスターリンの唱える「社会主義」のもとでは、「アンアン」のようなファッション・マニュアル誌の存在自体が認められなかったはずである。
ここで吉本は、いまや大衆がみずからを「解放する方位」は、スターリン主義的な「社会主義」の「まやかしの倫理」の先にではなく、資本主義の転位する延長上にあるはずだ、とはっきり宣言している。先進資本主義「国」の労働者が豊かな生活ができる賃金を確保しつつ、週休3日制を獲得できる方向をめざさなければならない。そのときこそ、むしろ資本主義の延長に、自由な社会主義という理想が実現されるというべきではないか。
吉本は「日本の資本制を、単色に悪魔の貌に仕立てようとして」いる埴谷にレーニン-スターリン主義に同調する「まやかしの偽装倫理」を感じた。そして、現在克服すべき思想的課題は、資本主義そのものよりも、ポルポトによる虐殺や反対派への弾圧などをもたらしているレーニン-スターリン主義的な社会主義の側にあると考えていた。
ここで吉本は「重層的な非決定へ」をみずからの理念としたいと述べている。それはどういうことか。
埴谷は、経済進出する日本を「悪魔」と呼んでいる「タイの青年」をもちだして、ファッション雑誌に写真姿をさらしている吉本のていたらくを非難した。それは「疑似倫理」にもとづくあまりにも短絡的な思考だ、と吉本は反論する。資本主義にも否定面がないわけではない。しかし、自然破壊や公害、環境問題など資本主義を批判する材料をかき集め、ひっくるめて資本主義そのものを「悪の根源」とする決定論的なやり方は空虚だと論じた。
はっきり言ってしまうと、ここで吉本はマルクス主義的な決定論(決めつけ)から脱出しようとしていたのである。そこから「重層的な非決定へ」という視座が打ち出される。
〈私の場所からみえる「現在」は、モダンやポスト・モダンに単層的に収束できるようにおもわれないのです。ここでは「重層的な非決定」がどうしても不可避であるようにおもわれてなりません。……破片はどれも浅薄で取るにたりないものですし、核心というのもそれを寄せあつめたガラクタにしか視えないかもしれません。でもそれで「現在」が終りだとおもったら間違うようにおもわれます。〉
いまおきている諸現象を、外在的な物差しではなく、内在的、かつ重層的にとらえていかなければならない。
とはいえ、これ以降、吉本が反「社会主義」の立場をむしろ決定的にしていったのは確かである。そのぶん、資本主義には甘くなった。じっさい、日本資本主義は1980年代をピークとして、吉本の期待した「超資本主義」に転位することなく、低迷をつづけることになる。
国家の財政基盤──ヒックス『経済史の理論』を読む(5) [商品世界論ノート]

第6章「国家の財政」を読んでみる。
ここでは都市国家を引き継いだ近世(ヒックスのことばでいえば「中期の局面」)の領域国家としての「君主国家」が、常に財政危機に悩まされ、それを克服する過程で近代の「国民国家」へと変成していく内的必然性が論じられている。
近世の君主国家は常に貨幣不足を経験していた、とヒックスはいう。このことは王が困窮していたことを意味している。そのため、王は身近なところから財産を没収しようとして、たびたび内乱を招いた。
王が困窮していた原因は、租税収入が慢性的に不足していたからである。王の財政は農業に依拠していたが、近世にはいると商業が国富の大きな部分を占めるようになる。ところが、王は商人階級の富を完全に捕捉することができなかったため、商人階級への有効な課税ができなかったのだ、とヒックスはいう。
たとえば、商品の取引にたいしては、二、三の港で関税を徴収することができた。だが、それは全体のごく一部を把捉したにすぎず、しかも徴収に手間もかかった。かといって、直接税として所得税をとることもむずかしかった。効率のよい所得税のための条件ができたのは、ごく最近のことで、近世においてはまだ所得という概念すら普及していない、とヒックスは記している。
商人の利潤を把握して、それに課税する仕組みもできていなかった。それがようやくできるようになるのは、ひとつに有限責任会社、すなわち株式会社が登場してからである。株式会社には利潤を確定し、そこから配当金を支払う義務がある。利潤が確定されると、課税が可能になる。
所得税がないときは財産税に頼らなければならないが、そもそも財産の大きさを評価するには煩雑な作業を必要とした。そのため、それは(たとえば日本における検地にしても)頻繁にはなされず、過去の評価に頼らざるを得なかったため、いくらでも課税を逃れる抜け道があった。
そのため、近世の政府は必要とする税収を確保することが、きわめて困難だった、とヒックスはいう。徴収は手間がかかるだけでなく、きわめて不公平だった。しかも支配者が新しい税を課そうとすると、「暴君」への反乱を招く恐れすらあった。アメリカ独立戦争のきっかけとなったボストン茶会事件(1773年)もそのひとつだったといえるだろう。
とはいえ、政府の支出はたえず増大していく傾向にある。とりわけ戦争のような非常事態が生じたさいには、王は臨時的な支出を工面しなければならなかった。そのために取られた方策が借入にほかならない。
借入はいわば国家にたいする無担保融資である。だが、近世の国家には概して信用がなかった。返済期限がきても王が返済を拒否することはじゅうぶんに考えられ、じっさい王はしばしば借金返済をボイコットした。
すると、次に考えられるのは、国家にたいする担保貸付である。実際に、戴冠式用の宝石類や土地財産(王領地)、あるいは徴税請負権が「質」に取られることもあったという。さらに国家への貸付にたいしては、債権者の将来の課税を免除するという特権を付与する場合もあった。
その結果、貧者は依然として税を支払い、富者は大部分の税を免れるという状況を招くことになる。フランスの君主制が崩壊した背景には、こうした財政の末期的症状がみられた、とヒックスは指摘する。
だが、国家の財政を満たすほかの手段は考えられなかったのだろうか。王は貨幣の鋳造権をもっていたのだから、それを活用して、貨幣供給を操作することもできたはずだ。じっさい王はそれを試みた。
貨幣の供給は、金・銀貨の時代には貨幣鋳造所に送られてくる金属の供給に依存していた。近世のヨーロッパでは、すでに王は収入の大部分を貨幣で受けとるようになっていた。その貨幣を王は鋳造所に回し、さらに卑金属を混ぜて改鋳し、貨幣の量を増やすことができた。
金属の最大の供給源は商人だった。交易をおこなう商人のもとには貨幣だけではなく金や銀そのものが集まっている。商人たちは摩耗した鋳貨や金銀の地金を王の貨幣鋳造所にもっていき、手数料や税を払って新しい貨幣を受けとった。政府はそれによって収入を得たが、そのさいあまりに貨幣の品質を落とすならば、商人による金属の供給そのものが途絶えてしまう恐れがあった。
それは主に国際的に通用する大「通貨」、すなわち正貨について言えることである。だが、国内だけで通用する地方通貨に関しては、それを「法貨」とすることで、かなりの悪鋳が可能だった。そのため、政府は非常事態にさいしては、補助財源を確保するために、地方通貨の操作をおこなったという。
だが、大量の悪鋳がおこなわれれば、貨幣供給量が増え、物価が上がり、インフレーションが生じる。それによって政府の収入も増えたことはまちがいないが、インフレーションは政府収入の実質的価値を減少させたから、インフレ政策は結局のところ、政府を弱体化させることになった。
つまり、政府が支出増に対応するには、商人からの借入も貨幣の改鋳も抜本的な対策になりえなかったということだ。
近世の国家にくらべると、近代の国家ははるかに強力な財政基盤をもつようになった、とヒックスはいう。どうしてか。
ひとつは政府が政府の借入を短期間ではなく、長期間のものとし、年利を保証することによってである。これにより、比較的信用の高い借入制度(国債発行)が導入されるようになった。
より重要なのが銀行制度の発展である。銀行はこれまでも商人間の金融を仲介する役割をはたしていたが、それがより信用度の低い国家への貸付をおこなうようになると、逆に国家は銀行を保護せざるをえなくなる。最終的には中央銀行の設立へと向かっていくことになるだろう。
銀行は預金を受け入れるとともに、小切手や手形を発行するようになる。これによって銀行は実質的に貨幣(紙幣)を生みだすことができるようになった。
ヒックスはこう書いている。
〈重要なのは、貨幣創出の経路が銀行によって提供されていることである。「国家」が自分自身の通貨で表わされている負債の支払を履行しないという危険はもはやなくなる。「国家」はいつでも銀行制度を通じて借入を行なうことが可能となったからである。〉
中央銀行による紙幣の発行は、金融の幅を広げるとともに、国家による貨幣供給の統制を可能にした。それにより国家は「貨幣に対する支配力」をもつことになり、政府の財政基盤はより強化されるようになった。
だが、もうひとつ肝心なことが残っている。それは国家が課税力を著しく強化したことである。いまや国家は所得税、利潤税、販売税、それに相続税、固定資産税などの財産税をも収入源とするようになっているが、それらはすべて金融の発展、すなわち貨幣による評価が可能になったからこそである。
財政基盤の強化は、強力な行政を生みだす。大規模でこまかい行政は、金を投じないかぎり実現できない。ヒックスは「産業革命」になぞらえて、これを近代における「行政革命」と名づけている。
歴史的にみれば、もともと商人経済は政治的権威から逃避する傾向をもっていた。しかし、近代の特徴は、国家が商人経済を基盤としながら、商人経済を統制することができるようになったことだ、とヒックスは論じている。
ちっちゃな大論争(1)──大世紀末パレード(5) [大世紀末パレード]

そのころ吉本隆明と埴谷雄高(はにや・ゆたか)のあいだで大論争がくり広げられた。
全共闘の端っこにいたぼくにとって、吉本、埴谷といえば、あこがれの思想家、文学者で、その思いは中年サラリーマンになっても変わらなかった。
1985年春、そのふたりが、じつにくだらないと思われることをきっかけに、大論争をおっぱじめるのだ。吉本はその論争をへて、みずから定めた方向性を「重層的な非決定へ」と名づけ、それをタイトルとする重厚な単行本を出版する。
ことの発端は前年に岩波書店から、大岡昇平と埴谷雄高がふたりの対談集『二つの同時代史』を刊行したことにある。そのなかに60年安保で全学連とともに闘い、警察に逮捕された吉本をからかった部分があった。
その部分を引用しておこう。
埴谷 吉本も押し出されて敗走したんだが、追われた道路のはしでやっと塀を越えて逃げ込んだところが警視庁の中だったんだ(笑)。それで吉本は捕まっちゃったんだが、それを花田清輝は戯文詩に書いた。「逃げた先が警視庁」というようにね。花田も、吉本・花田論争をまだ根にもっていてね。
大岡 あれはおもしろいね、ケチのつけ方が。吉本はスパイで、だから警視庁の玄関から降りて来た、とかね(笑)。
埴谷 そうだったかな。
大岡 釈放されて出てくるんなら、玄関から出て来たっていいと思ったけれどね。あの論争は、ちょっと花田に分がなかったからな。
文学界の巨匠といえる大岡と埴谷のふたりが、60年安保での吉本の闘いぶりがいかにドジなものであったかをからかっているようにみえる。
こうしたからかいにたいし、吉本は内心怒った。あのとき、全学連とともに安保闘争を必死で闘った吉本は、国会周辺で機動隊から襲撃され、素手のままぬかるみと暗黒のなかを潰走した。そして、三十数名の学生、市民とともに、警視庁の構内に追い詰められ逮捕されたのである。けっして、笑える話ではなかった。
加えて、埴谷は、1956年から60年にかけて吉本と花田清輝とのあいだで繰り広げられた(文学者の戦争責任などをめぐる)論争で押され気味だった花田が、戯文詩のなかで、吉本の「逃げた先が警視庁」と皮肉ったことを紹介する。それにおいかぶさるように、大岡が、花田は吉本がスパイで警視庁からでてきたとまで言ってるぜ、と知ったかぶりの発言をした。
花田が、吉本は警視庁に逃げこんだなどと諷刺したのはまちがいない。しかし、吉本がスパイなどといった発言をした事実は確認されなかった。日本共産党が全学連をおとしいれるために、全学連主流派(共産主義者同盟)はスパイで、だから警視庁に逃げこんだという作り話を流していたことは伝わっていた。だからといって、花田が吉本は警視庁のスパイなどと評したことはなかったのだ。
実際には吉本は6月15日に(警視庁への)「建造物侵入現行犯」の疑いで逮捕され、高井戸署に移され、数日にわたる取り調べのあと釈放されている。警視庁の玄関から降りてくること自体ありえなかった。
吉本は大岡昇平と埴谷雄高、並びに版元の岩波書店に、花田の発言とされる事実誤認を訂正するよう求めた。
埴谷と吉本とのあいだで「論争」が巻き起こったのは、それからである。埴谷が雑誌「海燕」に二度の公開書簡を発表したのにたいし、吉本は同じ誌上で二度にわたり反論を加えた。
そこで明らかになったのは、吉本と埴谷の立場(考え方)が完全にわかれつつあったということである。
埴谷は大岡の発言が不用意だったとエッセイに記すことで、ことを収めるつもりでいた。ところが、吉本はそれでは腹が収まらない。スターリズムと対決していたはずの埴谷が、1982年にヨーロッパへのアメリカの核兵器配備に反対する文学者の「反核宣言」に署名したことを蒸し返して、埴谷がレーニン-スターリン主義者の同調者に成り果てていると批判した。
現在の「社会主義」国家がもたらしてきた現実は、理念にとはほど遠いものだ、と吉本はいう。ソルジェニーツィンの『収容所群島』、ソ連のアフガニスタン侵略、ポル・ポト派による大虐殺、中ソ国境紛争、中国・ベトナム戦争、さらにはポーランドの「連帯」にたいする鎮圧をみても、それは「ファシズムとおなじ国家社会主義のヴァリエーション」であって、その根底にはレーニン-スターリン主義にもとづく政治的暴力があると指摘した。
さらに吉本は、大衆にとっては、現在の「社会主義」国よりも「先進資本主義体制」のもたらした成果のほうが、はるかに大きいと断言する。ソルジェニーツィンは「いま、われわれは、せめて資本主義のもとでプロレタリアートが享受している程度に、わが国のプロレタリアートに食べるものと着るものとを与え、余暇を恵んでやりたいと思うだけである」と述べたが、吉本はそのソルジェニーツィンに共感を示すようになっている。
吉本が埴谷を批判するのは、スターリン主義を厳しく糾弾する埴谷のなかにレーニンの思想を称揚する古い左翼性が強固にこびりついているようにみえることだった。そこから話はレーニン批判へと移る。
ここで取りあげられるのはレーニンの『国家と革命』だ。吉本はそれを執拗に批判しているが、ことこまかにそれを点検するのは気が重い。
要点だけを記す。
〈レーニンがエンゲルスの国家観を集約した理念のうち、国家の本質規定である「だから、あらゆる国家は非自由で非人民的な国家である。」(『国家と革命』)は「現在」レーニン-スターリン自身の理念国家であるソ連国家をはじめ、あらゆる社会主義諸「国」や資本主義諸「国」の本質的な欠陥を照し出す鏡になっております。またレーニンの論理的な短絡と狭窄の産物である「国家」は「監獄その他を自由にすることのできる武装した人間の特殊な部隊にある。」(『国家と革命』)という理念の当然の報いとして、資本主義諸「国」よりも、もっと自由度の少ない、賃労働者(階級)の生活水準も低い「強制収容所その他を自由にできる武装した人間の特殊な部隊」であるソ連その他の社会主義「国」の権力を創り出しています。〉
レーニンの国家論はきわめて幅の狭いもので、国家を暴力装置ととらえるものだといってよい。党が国家を領導することによって「国家」を乗り越えようとしたレーニンとスターリンの共産党が、まさに強制収容所などに代表される「非自由で非人民的な」監獄国家をつくりあげたことを吉本は批判した。
さらに吉本は「革命やその世界の概念を、理念を仕込んだ支配したがりの、陰謀好きな知識人のせまく暗く、快活でない党派のものにしてしまった」のも、レーニンにほかならなかった、とも述べている。
レーニン-スターリン主義の根本的な問題は、「正しい」思想をもつ唯一の党(指導者)が国家の上に立って国家を指導し、党に反対する者は徹底して排除していくという発想にあった。そうした考え方は、21世紀のいまも中国にかぎらず多くの権威主義的国家に引き継がれている。
このあと、吉本と埴谷の論争は思わぬ方向に広がっていく。いわゆるコム・デ・ギャルソン論争である。長くなったので、そのつづきはまたにしよう。
貨幣の力──ヒックス『経済史の理論』を読む(4) [商品世界論ノート]

都市国家の時代はゆっくりと終わりに向かい、代わってスペイン、オランダ、フランス、イギリスなど、領域国家の時代がはじまる。
しかし、都市国家を動かしていた商人経済はすっかり解体されたわけではない。ある意味ではそれはたしかに解体だった。ヴェネツィアはゴーストタウンになってしまう。だが、領域国家は商人経済を吸収することを忘れなかった。いまや商人経済を保護し、商業センターを発展させるのは「国家」の役割になる。その局面をヒックスは「中期の局面」と名づけている。
ヒックスのいう「中期の局面」を、われわれは「近世」と呼んでもいいだろう。
「中期の局面」の特徴は、商人共同体の内部に限られていた商人経済が、いわば周辺にはみだしていくところに求められる、とヒックスは書いている。「従前の非商業的な周辺部分はさまざまな側面において、市場に対して開放的となる」
すなわち領域国家が商人経済を取り込むことによって、国家のなかに市場が浸透していくことになる。やがて、国家が外部に拡張していくにつれて、市場も外部に広がっていくことになるだろう。
ヒックスは近代(産業革命)以前の「中期の局面」(近世といってもよい)における市場の浸透を4つの分野にわたって考察する。すなわち貨幣(金融)、財政(国家)、農業、労働の4つの分野だ。これらの4つの分野はもちろん相互にからんでいるが、これをあえて4つに分けることによって、市場が浸透するプロセスがより明らかになってくる、とヒックスは考えている。
これをいっぺんに説明するのは骨が折れる。そこで、きょうはテーマを貨幣(金融)にかぎって、第5章の「貨幣・法・信用」を読んでみることにする。
貨幣はだいたいが鋳造された金属片で、国家によってつくられたもののように思われている。それはけっしてまちがいではないが、貨幣は鋳造貨幣がつくられる前から存在した。貨幣はそもそもが商人経済の創出物で、国家はそれを継承したにすぎない、とヒックスはいう。
たとえば村落に商人がいるとしよう。かれはいつでも商品を仲介できるように交換性のある財貨を保存しなければならなかった。そして、保蔵と隠匿が容易で、しかも損耗しにくい財貨といえば、けっきょくは金や銀などの貴金属に落ち着くというわけだ。
貴金属が「価値保蔵」機能をもつと、それは次第に均質化されて、「価値尺度」や「支払手段」としても利用されるようになる。国家が介入してくるのはこの時点だ。
国家は貨幣鋳造所をつくり、金属貨幣に王の刻印を押すようになる。それによって、貨幣には保証が与えられ、より受けとりやすいものになった。最初、リュディアやイオニア(ともに小アジア)でつくられた鋳貨はたちまちのうちにギリシア世界に広がっていった。
初期の金属貨幣は比較的大型のもので、これは貨幣が価値保蔵物だったことを示している。ところが紀元前5世紀ごろに支払手段として小型貨幣がつくられるようになり、さらに代用貨幣として青銅貨幣が登場すると、貨幣はより使用しやすくなった。ギリシアは次第に貨幣経済社会へと移行する。
金属貨幣はギリシア世界の外部にも広がっていく。ペルシアからインド、バルカン諸国、さらにローマへと。ケルト人も貨幣を鋳造するようになった。商業が衰退すると、一時的に貨幣が使われなくなることもあったが、「商業活動が行われるかぎり、どこにおいても貨幣は恒常的に使用されてきた」と、ヒックスはいう。
そして、貨幣は中世都市国家後の「中期の局面」(近世)においても継承された。王は貨幣を放棄しなかった。貨幣の鋳造によって、直接、間接に利益を得ることができたためでもある。加えて、貨幣を媒介とする交易は王にも多くの財貨をもたらしていた。
都市国家のもうひとつの遺産が「法」だった、とヒックスは説明する。それは中国や日本におけるような商業を規制する法ではなく、むしろ商業を促進し、商人の権利を守る都市国家の法にほかならなかった。
ローマ法は古代ギリシアでつくられた「商人法」を受け入れ、発展させた。ローマ帝国は貨幣による評価と支払いに依存していた。ローマ帝国が滅亡したあと、貨幣経済は収縮するが、完全に消えることはなく、やがて新しい都市国家の興隆がふたたび貨幣経済を盛り返し、同時に「商人法」も維持されることになる。
都市国家が衰退し、「中期の局面」すなわち近世の領域国家の時代にいたっても、貨幣制度と法律制度は継承され、発展することになる。
こうして貨幣と「商人法」を論じたあと、ヒックスが強調するのが、都市国家時代につくられた「信用」制度の継承である。
ルネサンス時代、貨幣は信用および金融と結びつき、その性格を変えようとしていた。
古代ギリシア人とローマ人は利子を取ることに良心のとがを感じなかったが、キリスト教は利子をとることを罪悪と考えていた。しかし、いかなる時代も商業取引がおのずから金融取引に発展していくことは避けられなかった。
当初、商品の取引は「代理人」に委託されていた。貨幣が普及するようになると、現物を委託するよりも、貨幣を貸し付けるほうが取引としてはずっと楽になる。
貨幣の貸付によって債務者は負担を負う。債権者に元金を返済するだけではなく、利子も支払わなければならないからである。債権者は債務不履行の危険度が大きければ大きいほど、高い利子を求める。これはとうぜんのことだった。
ギリシア・ローマ時代には、借金を払えない債務者は、制裁を受け、しばしば「債務奴隷」の地位におとされていた。だが、こうした残酷な制度に代わって、次第に貸付にたいして担保を求める慣習が定着するようになる。この場合、債務者は債権者にたいし、負債以上の価値を持つ物件を預託し、借金返済後にその物件を返却してもらうことになる。
しかし、担保物件つきの貸付が成立する場合はごく限られている。そこで、物件を預託しなくても、抵当権を設定するだけで借り入れができる方式が生まれる。この場合は、貸付の担保は債権者の手にわたらず、債務者の手元に残され、債務不履行の場合にかぎって、債権者が担保を手に入れることになる。
担保貸付にたいして無担保貸付も存在した。無担保貸付は貸し手にとって危険度が高いため、ふつうは高利がともなう。しかし、商人仲間のあいだでは、借り手の信用に応じて、質物や担保をとらずに、低い利子で貸付がなされる場合もあった。商人経済の発展にとっては、こうした信用にもとづく低利子の融資が大きな役割を果たした、とヒックスは指摘する。
だが、信用を確保するには、相手の経営状態を知っているだけではじゅうぶんではない。そこで信用を拡大するため、保証人や金融仲介人が求められるようになる。銀行が登場するのは、こうした金融仲介を専業とする者のなかからだ。そのころキリスト教においても、ある程度の利子を認める考え方が定着するようになっていた。
危険分散を可能にするには、加えて保険の導入が求められた。中世に都市国家を営んでいたイタリア人は、保険契約に精通していたことで知られる。14世紀にはすでに海上保険が存在していたし、万一の事態に備えるためのさまざまな方策も考え抜かれていた。
「中期の局面」としての近世は、こうした金融制度や保険制度を都市国家の経験から受け継ぐことになる。さらに加えて、証券市場や有限責任会社(株式会社)制度が確立されるようになると、「中期の局面」は終了し、「近代の局面」の展開がはじまる、というのがヒックスの基本的な見取図だといってよい。
だが、先走るのはやめておこう。近代を語るには、その前提として、貨幣(金融)に加えて、国家(財政)や農業、労働の分野への「市場の浸透」を論じなくてはならないからである。
プラザ合意と中曽根政権──大世紀末パレード(4) [大世紀末パレード]

.svg.png)
あのころのことを少しずつ思い出してみる。
薄らいでしまった記憶を導いてくれるのは、引きつづき吉崎達彦の『1985年』だ。
1985年は戦後40年にあたる。1950年以降、日本は驚異的な経済成長を遂げ、この年までにGNPは80倍になり、一人あたり国民所得は50倍、輸出は140倍、輸入は90倍になった。自動車を中心に日本の対米輸出は増大し、1985年のアメリカの対日赤字は500億ドル近くまで膨らんでいた。
当時、アメリカ大統領はロナルド・レーガン、日本の首相は中曽根康弘だった。日本の経済進出を受けて、アメリカでは「ジャパン・バッシング(日本叩き)」の動きが強まっていた。
日本政府は大慌てで、外国製品輸入のキャンペーンを張る。4月20日には中曽根首相がみずから日本橋の高島屋を訪れ、開催中の「輸入商品フェア」で7万1000円の買い物をする。ところが、首相が買い上げたのはイタリア製のネクタイとブルゾン、フランス製のスポーツシャツ、孫のためのイギリス製ダートゲームで、肝心のアメリカ製品はひとつもなかったという笑い話が残っている。
とってつけたような外国製品輸入促進策は、容易に進むはずがなかった。
いっぽう「強いアメリカ」を標榜してレーガン政権が打ちだした「レーガノミックス」は、財政赤字と金利上昇、ドル高、貿易赤字を招いた。アメリカにとっては、財政赤字と貿易赤字の「双子の赤字」が大きな課題となっていた。
日米通商摩擦が浮上する。これを解決するうまい手が考えられた。それが通貨調整だった。
1985年9月22日、ニューヨークのプラザホテルに先進5カ国の財務大臣(大蔵大臣)、中央銀行総裁が集められた(日本からは竹下登蔵相が参加)。そして、わずか20分ほどの会議で、ドル安に向け各国が外国為替市場で協調介入をおこなうことが決定された。
いわゆる「プラザ合意」である。
プラザ合意の効き目は絶大だった。東京市場では合意前に1ドル=242円だった為替相場が、85年末には1ドル=200円まで上昇した。その勢いは止まらない。86年2月に相場は1ドル=180円をつけ、5月には165円、8月には154円となった。
そうなると、これから先どうなっていくのかという恐怖が襲ってくる。日本政府は景気後退を予測して、強力な景気対策を打った。鉄道や道路を中心に大型のインフラ投資が発注され、1985年に5%だった公定歩合は87年2月までに2.5%まで段階的に引き下げられていった。それが結果的にバブル経済を生むことになる。株価と地価が急速に上昇していく。
ここで中曽根政権について論じるべきなのだろうが、手元に詳しい資料がない。図書館に行くのも面倒だ(近くの図書館は改修工事のため9カ月近く休館になっている)。
そのため手近なところで、いつも世話になっている中村隆英『昭和史』の記述を借りることにする。
中曽根康弘は、鈴木善幸首相が突然辞任したあと、田中角栄の率いる田中派の支援を受けて、1982年11月に総理の座についた。その政権は3次にわたり、1987年11月まで5年間つづくことになる。
1985年はまだその中間期にあたっている。
世界を眺めると、そのころアメリカではロナルド・レーガン(1981〜89)、イギリスではマーガレット・サッチャー(1979〜90)、フランスではフランソワ・ミッテラン(1981〜95)、西ドイツではヘルムート・コール(1982〜98)、中国では鄧小平(1978〜97)、韓国では全斗煥(1981〜88)、北朝鮮では金日成(1948〜94)、台湾では蒋経国(1978〜88)、フィリピンではフェルディナンド・マルコス(1965〜86)、インドネシアではスハルト(1968〜98)が政権を握っている。それこそ錚々(そうそう)たるメンバーだといってよい。
そこにミハイル・ゴルバチョフが1985年3月にソ連共産党中央委員会書記長の座につくところから、世界史の激動がはじまる。
複雑な国際環境のなか、中曽根が最重視したのが日米関係だったことはいうまでもない。首相就任から1カ月後、中曽根は韓国につづき、アメリカを訪問し、レーガン大統領に日米は「運命共同体」であり、日本列島は「不沈空母」であると語った。
レーガンといわゆる「ロン・ヤス関係」を結ぶとともに、親米反ソの立場を鮮明にしたのである。三木武夫内閣が決めた防衛費のGNP比1%枠を突破し、防衛費増大を実現したのも中曽根だった。
内政面では、中曽根内閣は、前内閣の臨時行政調査会答申を実行に移そうとしたといえるだろう。臨時行政調査会は財政再建と行政改革をめざして、鈴木内閣時代の1981年3月に設置され、経団連名誉会長の土光敏夫が会長を務めた。そのため「土光臨調」とも称される。
戦後の赤字国債は1965年にはじめて発行され、2度の石油危機をへた1981年にいたって、その累積額は増え、80兆円を超していた(2023年現在は1068兆円)。このままの勢いでは増税が避けられなかった。
だが、土光臨調はあえて「増税なき財政再建」を旗印にかかげた。
答申は5次までおこなわれ、政府は徹底した行政の合理化と簡素化を求められた。
その提言内容は、政府は「小さな政府」をめざし、(1)1984年までに赤字国債発行額をゼロにする、(2)コメ、国鉄、健康保険の3K赤字を解消する、(3)特殊法人を整理し、民営への移管をはかる、(4)省庁の統廃合をはかる、(5)国鉄、日本電信電話公社(電電公社)、日本専売公社を民営化する、などといった厳しいものだった。
土光は答申がでたら、かならずこれを実行してほしいと政府に強く求めていた。
しかし、と中村隆英は書いている。
〈しかし、政府側はいわば総論賛成各論反対の昔ながらの姿勢を変えず、各省庁はいずれも激しい抵抗を繰り返したため、行政機構の改革はほとんど実現しないままに終り、臨調の担当部局であった行政管理庁が解消されて総務庁に切り替えられた程度の改革しかできなかった。〉
国債発行はつづく。行政改革もほんの小手先でしかおこなわれない。
ただひとつ積極的に実施されたのが、公共部門、とりわけ国鉄、電電公社、専売公社の民営化だった。
電信・電話事業を担っていた日本電信電話公社は1985年4月に民営化され、NTTグループとなる。タバコと塩の専売事業を担っていた日本専売公社も同じ時に民営化され、日本たばこ産業が誕生する。
難関は国鉄の分割民営化だった。国鉄は自動車時代におされて、大赤字を抱えていたうえに、その内部では1970年以来、激しい労使間対立がつづいていた。
分割民営化案にたいしては、国労や動労の組合側はもちろんのこと、国鉄幹部のあいだでも強い抵抗がみられた。
その経緯を中村はこう解説する。
〈国鉄幹部は、民営化はやむをえないとしても全国一社体制を残そうと抵抗したが押し切られたのである。明治以来の国鉄がこのような形で終焉をつげたことは、政治家や特権企業が鉄道を食い物にしてきたこと、古い大家族主義の労使関係の破綻をはじめ多くの理由が指摘されている。そのいずれもが誤りではあるまいが、同時に、石油危機以後の古典的な自由経済論の復活が、その底流として存在したことを忘れるべきではないであろう。第二次石油危機のあとで発足した臨調は「小さい政府」の発想を打ち出し、大赤字を出しつづける国鉄を、ともかく民間企業として再編することに成功したのである。〉
多くのコメントが必要かもしれないが、それはあとに回そう。
いずれにせよ、国鉄分割民営化法案は難航したものの1986年11月に成立し、87年4月からJRグループ(6つの旅客事業会社と日本貨物鉄道)が誕生することになる。
そして中曽根内閣は国鉄分割民営化を最大の功績として、1987年11月に「禅譲」によって退陣する。そのあとを継いだのは、田中派から抜けて、「経世会」を結成した竹下登だった。
きょうはこのあたりで終わりとしよう。ぼんやりとしか覚えていなかったが、ほんとうにあのころはいろいろなことがあったのだと思う。
都市国家をめぐって──ヒックス『経済史の理論』を読む(3) [商品世界論ノート]

ここで都市国家の経済理論を述べてみたい、とヒックスはいう。モデルとされているのは、古代のアテナイだけではなく、中世のヴェネツィアやフィレンツェ、ジェノヴァなどだといってよい。
都市国家の中核は、対外商業に従事する商人の団体である。商人たちは都市国家の外にある地域と取引をし、商人経済が都市国家を支えている。その意味で、都市国家はひとつの商業センターになっている。
たとえばAという商品をもつA地域とBという商品をもつB地域があるとする。A地域は商品Bをほしがっており、B地域は商品Aをほしがっている。すると、都市国家の商人たちはA地域とB地域の仲立ちをすることによって利益を得、同時にA地域もB地域もみずからが持たない商品を手に入れることで潤うことになる。ただし商品A、商品Bが貢納によるものであるとすれば、利益を得るのは領民全体ではなく領主にとどまる可能性が強い。
だが、通常、商業が拡大すると、その利幅は少なくなっていく。商人の利潤率は取引量に比して下落し、商業の拡大テンポも鈍っていく。そこで商人は新しい商品や新しい販路を求めて、商業の多様化をはかることを迫られる。
一口に商業の多様化といっても、それは楽なことではない。そこで、都市国家が重要性を発揮することになる。都市国家は商人の取引に安全保障を与え、商業の多様化という困難な課題解決を後押しすることになる、とヒックスは書いている。
商業が多様化するとしても、その拡大にはおのずから限界がある。だが、それにいたるまでに多くの余地が残されている。
取引量が拡大するにつれて、組織が合理化され、その結果、取引費用が減少し、それによって商人の利益はむしろ増えるかもしれない。都市国家の拡大が全体の利益の拡大をもたらす可能性もある。商人数の増大は競争の激化をもたらすが、そのいっぽうで商業活動に一種の棲み分けをもたらし、商業をより効率的にすることも考えられる。
商人経済の拡大と充実は危険の減少にもつながる。商業活動のありかたについての知識が深まり、無知に起因する損害を減らすからだ。取引が増えるにつれて、財産や契約を保護する制度も確立するようになり、さまざまな取り決めがなされるようになる。それが可能になるのは商業センターとしての都市国家が存在するからだ、とヒックスは断言する。
また都市国家には海外に交易の根拠地を設け、植民地をつくるという強い誘因が存在することをヒックスは強調している。フェニキア人しかり、古代のギリシア人しかり、中世のイタリア人も地中海や黒海に植民都市をつくった。
植民地がつくられるとなると、それは先住民や敵対者から守られなくてはならない。そのさい往々にして武力が発動されることになる。都市国家による植民地化は近代国家による植民地化とは大きく異なるが、それでも都市国家が植民地形成の初期モデルとなったことはまちがいない、とヒックスは考えている。
都市国家は商業経済と植民地化によって、内的にも外的にも拡大していく。競争はより激化し、利潤率は下がっていくものの、組織はより効率的になるために、全体としての利益は拡大する方向にある。ただし、それを阻害するものがあるとすれば、地理上の新しい地域で、商品の新しい供給源が開発されたときである、とヒックスはいう(たとえばアメリカ新大陸の発見やインド航路の開発を考えてみよう)。
だが、その前に商業の成長が限界に達する。
〈もし商人が既存の市場においてもっと効率的に営業するための新しい組織を発見することに失敗したり、新しい市場を発見したりすることに失敗すれば、価格がかれらにとって不利な方向に動いていくことに気付くだろう。というよりはむしろ、取引量を拡大しようとすれば、価格がかれらに不利な方向に動いていくという状況に達するであろう。〉
もはや組織の効率化もできなくなり、新たな市場も開拓できなくなったときに、むりやり商品の販売量を増やそうとしても、値崩れをおこし、かえって利潤は減少してしまうという状況におちいってしまうのだ。
それでも都市国家が依然として商業の拡大をめざすなら、都市国家どうしの戦争が勃発する。都市国家どうしの戦争がおこりやすいのは、「まさにこの時点、すなわち商業の成長が限界に近づきはじめる時」である、とヒックスはいう。古代ギリシアのペロポネソス戦争や、1400年ごろのジェノヴァとヴェネツィアの戦争の背景には、こうした商業的要因がひそんでいるという。
しかし、都市国家どうしが協定を結んで、地域内で棲み分けるようになることも考えられないではない。すると、都市国家の指令のもとで、「商人は慣習的権利・義務の体系の中において、一つの地位を受け入れるようになっていく」。
商業の拡大が停止したといっても、商業は衰退したわけではない。利潤水準は依然として高いが、利潤を拡大のために再投資しないことが、高利潤を維持するための条件となる。すると、市場の喧噪に代わって秩序がもたらされる時期がやってくる、とヒックスはいう。
〈拡大を特徴づけた活気は直ちには失われないであろうが、いずれ活気は商業の革新から去って他に向かわざるをえない。だが、安全の保障と富があるので、他の分野に転ずることが可能である。商業の拡大は知的刺激を与えていたが、それがもはや知的活力の対象となりえない時点にたちいたると、芸術は芸術のために、学問は学問のために追究することが可能となる。〉
こうしてアテナイには芸術と学問が興隆し、フィレンツェやヴェネツィアにはルネサンスがもたらされた。「しかし、果実が熟れるときは常に秋なのである」。都市国家はその商業活力を失ったときに、最後の花を開いたあと、危機に陥っていくことになる。



