危機の時代──ホブズボーム『20世紀の歴史』をかじってみる(7) [われらの時代]

ここから、最後の第Ⅲ部「地すべり」にはいる。1970年代からソ連崩壊前後までを追っている。全部で6章にわかれているが、最初に「第14章 危機の時代」を読んでみる。
「1973年以後の20数年の歴史は、世界が方向感覚を失い、不安定と危機にすべり込んでいく歴史である」とホブズボームは書いている。
このあたりからの記述は、どうしてもエッセイ風になってしまう。同時代を語るのはむずかしい。
世界経済は安定を失った。大恐慌時代のような混乱はなかった。とはいえ、1973年から75年にかけ、先進国の工業生産は10%、貿易は13%減少している。先進国では、その後、経済成長の伸びは落ちている。
例外はアジア、とりわけ中国を中心とする新興工業国で、これらの国々が20世紀末まで世界経済を引っぱっていくことになる。しかし、アフリカや西アジア、中南米では、人びとはむしろ貧しくなった。そして、ソ連が崩壊したあと、ロシアや東欧のGDPは急速に下落する。
1973年以降、世界でふたたび現れてきたのが、失業と貧困の問題である。1980年代にはいると、もっとも豊かな国でも、ホームレスの姿をよくみるようになった。所得格差も広がっていく。低所得層に転落する中間層も増えてきた。国の歳入も減り、社会保障の財源を確保するのもむずかしくなってくる。
「この危機の20数年の中心的な事実は、資本主義がもはや黄金時代のように機能しなくなったという点にあった」とホブズボームはいう。これまでのケインズ政策はうまくいかなくなっていた。これに対抗して出てくるのが、ハイエクやフリードマンの新自由主義である。
ちいさな政府と市場万能主義を唱える新自由主義は、新たな経済政策として、一時もてはやされた。政府のムダにメスが入れられ、国営企業の民営化が進む。しかし、政府は悪くビジネスはよいというだけでは、新しい経済政策になりえなかった。
実際はこの時期も経済全体に占める国家の割合は、ますます大きくなっており、サッチャー政権は実際には労働党政権より多くの税を市民に課していた、とホブズボームは論じている。
新自由主義はイデオロギーで、実際の経済政策には結びつかなかった。アメリカのレーガン政権も1979−82年の不況を乗り切るために、巨大な財政赤字と巨大な軍備増強をおこない、強引な為替管理を実施したが、これはむしろケインズ的な手法の悪用だった。
1990年代になって、ふたたび世界経済が後退したときには、新自由主義の勢いはすでに衰えていた。
1970年代以降、グローバル化と技術革命によって世界経済は大きく変化した。国際分業によって、工業は古い地域と国から新しい地域と国へと移動していった。技術革命には、人間の技能と労働を機械に置き換え、労働力を切り捨てていく傾向があった。
その理由は「技術が高度になれば、生産の人的構成要素は機械的構成要素とくらべて高価になっていかざるを得ない」からだ。人間はコストとして評価される。人をできるだけ減らさなければならない(あるいは人間のコストをできるだけ低くしなければならない)。そこで構造的な失業問題が生じる。
「危機の20数年の歴史的な悲劇性は……市場経済が新しい職を発生させるよりも早くに人間を切り捨てていることにあった」とホブズボームはいう。政府も労働組合も、この流れにじゅうぶんに対応できなくなっていた。
情報時代に新たな技術を習得するには、大きな努力を必要とした。労働力の一部を再訓練できたとしても、なくなった職を埋め合わすだけの職はなかった。それを社会保障でカバーするにも限界があった。
それでも、人びとはどんなことをしても暮らしていかねばならない。仕事がみつかればまだましだ。ひそかに闇の経済が広がる。黄金時代が終わったあと、先進国でも下流社会が生まれつつあった、とホブズボームは記している。
1970年代以降は、不況とリストラが社会の緊張を生み落とし、それが政治にも地殻変動をもたらしていった。
労働者階級の分断を背景に、西側ではそれまで大きな勢力を保っていた社会民主主義政党や労働党などの既存左翼が力を失い、それぞれのテーマをかかげる小政党が誕生する。そのなかには環境問題をかかげる緑の党や、分離主義、排外主義を主張する極右政党までが含まれていた。
先進国では以前の安定した政治構造が分解しつつあった。そして、「大衆主義的な煽動政治と、指導者個人を高度に全面的に押し出す手法と、外国人にたいする敵意とを結合している勢力」が、新しい政治勢力として台頭してくるのだ。
危機が訪れたのは、「第二世界」の社会主義諸国も同じだった。中央集権的な経済計画は、1970年代ごろからうまくいかなくなっていた。1980年代には、社会主義的な経済計画を改革するための方策が考えだされる。それが目指していたのは、共産主義を西側の社会民主主義に似たものにすることだった。そのモデルとなったのは、スウェーデンだったという。
だが、改革はなされない。ソ連圏の共産主義体制は硬直しており、そのため危機は体制の生死にかかわる問題となり、けっきょく体制は生き延びることができなかった、とホブズボームはいう。
ソ連圏では、社会よりも前に体制が先に崩壊した。「ソ連と東ヨーロッパの社会の枠組みは、体制の崩壊の結果として粉々に崩れた」のだと、ホブズボームはいう。
資本主義経済のダイナミズムが、社会に激変をもたらしたのにたいして、社会主義諸国では、奇妙なことに社会の伝統的価値と習慣が、共産主義のふたによって、むしろよく保存されていた。
〈社会主義下の生活が相対的に静穏であったのは恐怖によるものではなかった。体制は、西欧的な社会転換の全面的な衝撃から市民を隔離していた。……彼ら市民が変化を経験したとすれば、それは国家を通じて、そして国家にたいする彼らの対応を通じておこった。国家が変化させようとしなかったものは、以前と同じくあまり変化しなかった。政権についた共産主義の逆説は、それは保守的だということにあった。〉
このあたりの把握は、論議の余地があるだろう。
第三世界にとっても、危機の20年数年は多様な影響をおよぼした。とはいえ、同じ第三世界でも、アジア諸国とペルー、サハラ以南の荒廃した国々を比較するのはほとんど無意味である。
唯一、一般化できるとすれば、第三世界のほとんどの国が大きな債務を負っていたことだ、とホブズボームは書いている。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンは巨額の国際債務をかかえていた。GNPにたいし相対的にもっとも大きな負債をかかえていたのはモザンビーク、タンザニア、ソマリア、ザンビア、コンゴなどアフリカの国々で、いくつかの国は戦争や経済破綻で荒廃していた。
1980年にはメキシコをはじめ中南米諸国が債務不履行状態におちいり、金融体制が崩壊の危機に瀕する。だが、それらの国々は国際機関の助けを借りて、徐々に危機を脱することができた。
1990年になると、利潤を目的とする先進国は第三世界の大部分を無視するようになった。外国からかなりの投資がなされていたのは、アジアでは中国、タイ、マレーシア、インドネシア、中南米ではアルゼンチン、メキシコ、ブラジルなどにかぎられていた。
全体として、旧ソ連圏を含め、世界のかなり大きな部分が世界経済から脱落しつつあった。ソ連圏が崩壊したあと、東ヨーロッパで外国投資を招きよせているのは、ポーランドとチェコだけだった。
危機の20数年は、金持ちの国と貧しい国との格差をさらに広げることになった。
危機の時代には、国家の枠組みも変容してくる。
グローバル化によって、国民国家の枠組みがゆるみ、企業も団体も国際化していったのだ。そのいっぽうで、国家からの分離と自治を求める地方分権の動きも活発になっていく。戦争と苦難の末、分離独立する国家も生まれる。だからといって、国民国家がなくなったわけではない。新国家の建設に向かわない国家の解体は、アフガニスタンやアフリカの一部のように無政府状態を生み落とすことになる。
地球規模においては自由貿易が理想であり、国家が表向きに保護主義を唱えるのははばかられるようになった。それでも各国は、たとえば固有の産業や農業にたいして、ひそかに保護主義を発動していた。
欧州共同体(のちに欧州連合)や北米自由貿易協定のような地域連合も生まれたが、その負担と恩恵をめぐって、各国の思惑は揺れていた。いっぽうで分離主義の動きはユーゴスラビアやチェコスロバキアの分割となってあらわれ、イタリアやスペインでの分離運動として継続した。
戦後の文化革命にたいする反動も生まれた。伝統的な社会構造が破壊され、あまりにも個の時代になった反動として、コミュニティの必要性が叫ばれるようになる。特定のアイデンティティをもちたいという思いは強く、それが政治活動にもつながっていく。
アイデンティティの政治と20世紀末のナショナリズムはつながっている、とホブズボームはいう。それは分離と排除、排外性への志向をももたらした。
だが、排他主義的なアイデンティティの政治は、けっしてうまく行かない。それは問題にたいする情緒的な反応でしかないからだ。だが、国民国家はもはやそうした排他主義に対処できなくなっている。国際連合やさまざまな国際機関もまた無力である。
にもかかわらず、欧州連合のような超国家的集合体も生まれたし、国際通貨基金、世界銀行といった金融組織もいまだに機能をはたしていることも忘れてはならない、とホブズボームはいう。コスモポリタニズム(地球村)への希望を失ってはいけないというのだろう。
ソ連型社会主義──ホブズボーム『20世紀の歴史』をかじってみる(6) [われらの時代]

引きつづき、ホブズボームのまとめである。
第二次大戦に参戦したソ連の勢力範囲は、1945年にはエルベ川からアドリア海を結ぶ東の領域、バルカン半島全域にまで拡大した。いまやポーランド、チェコスロバキア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、アルバニア、それに東ドイツまでもが社会主義圏にはいっていた。さらに1945年には朝鮮北部、1949年には中国、それから長い戦争を経てベトナム、ラオス、カンボジア、1959年にはキューバ、1970年代にはアフリカへと社会主義の勢力圏は広がっていく。
第二次大戦以前、ソ連は孤立していた。
レーニン自身は、ロシア革命は世界革命の口火にすぎず、やがてドイツでも革命がおこるものと信じていた。だが、そうはならなかった。そのため、ソ連は閉鎖的な小宇宙を形成せざるを得なかった。
レーニンの前には、後進的な農業国であるロシアをいかに先進的な工業国に発展させるかという課題が残されていた。そのため、こころみられたのが、中央集権的な国家経済計画である。
マルクスとエンゲルスは、資本主義に代わる経済のあり方を、ほとんど論じていない。内戦の危機に直面したレーニンは、社会主義政権を守るために、みずから政策を打ちださなくてはならなかった。こうして1918年半ばには全産業が国有化され、さらに「戦時共産主義」政策が打ちだされる。
内戦に勝つためには、資源調達の計画と統制は必至だった。理論家のブハーリンなどは、これを機に市場を廃止して、必需品を人民に現物で配給するシステムを構想した。だが、配給制はあくまでも臨時の措置であり、それが長くつづかないのはいうまでもなかった。
レーニンはそこで1921年に新経済政策(NEP)を導入することになる。それはレーニンにいわせれば、戦時共産主義から国家資本主義への後退にちがいなかったが、市場経済の部分的導入は、多少なりとも経済の疲弊を回復する効果をもたらした。
NEPは成功して、ソヴィエト経済は1920年の荒廃状態から抜けだした。だが、その時点でもソ連は圧倒的に農村社会であり、このままNEPをつづけていても、長期的な経済成長は望めそうになかった。
国家による強制と統制が求められた。そこで経済計画がつくられ、中央集権化された指令経済が実施されることになる。病死したレーニンに代わって、それを担ったのが、残忍で無慈悲なスターリンだった。
スターリン体制は、農民をふたたび農奴に変え、400万から1300万人の囚人労働力を経済の重要部分にあてた、とホブズボームは評している。
1928年の5カ年計画は、石炭、鉄と鉄鋼、電気、石油などの産業をつくること自体に重点を置いた。それは上からの命令に応えて、「突撃」作業で達成された。
しかし、「命令による工業化が多くの浪費と非能率をともないながらも目覚ましい成果をあげ」、それによって、ともかくもソ連はドイツとの戦争で生き延びることができた、とホブズボームはいう。
もうひとつ忘れてはならないのは、ソヴィエト体制が、少なくとも住民に最低限のものを保障していたことである。最低限とはいえ、仕事、食物、衣服、住宅、年金、健康保険、教育は保障されていた。のちにノーメンクラトゥーラと呼ばれる特権階級が発生するものの、ソヴィエト社会は、基本的に平等だった。
しかし、農民は別だった。農民は労働者と区別されていた。農業の集団化は大失敗に終わった。穀物生産は低下し、家畜は半減し、1932年から翌年にかけては大飢饉が発生した。
その後もソ連の農業は低迷し、1970年代はじめでも、穀物の4分の1を輸入に頼らなければならないほどだったという。かろうじて、ソ連の農業が破滅を免れたのは1938年以降、わずかながら農民に私有地が認められたからである。
さらに、ソ連体制の欠陥について、ホブズボームは過度の官僚制と体制自体の硬直化を挙げている。消費財にたいする資本財の優位は変わらず、分配システムは劣悪だった。何よりも工業化が優先されていたのだ。
ホブズボームによれば、ソ連の政治体制は、ヨーロッパの左翼の伝統とは異なり、きわめて特異なものだった。民主主義はうわべだけで、命令による政治があたりまえで、スターリンによる独裁体制が築かれていた。それはマルクスやレーニンが期待したものではなかったという。
スターリンは暴力と恐怖によって党を支配した。1930年代には、多くの古参ボリシェヴィキたちを含め、党員にたいする大粛清をおこなっている。
絶対権力の体制下には、立憲主義も自由な新聞も民主主義も対抗勢力もなかった。ラーゲリ(強制収容所)がようやく空になるのは、1950年代末になってからだ。その後、市民が大量に投獄され殺害されることはなくなった。だが、ソ連は警察国家、権威主義的社会として、自由のない国でありつづけた。
ソ連の政治的弾圧によって犠牲になった人の数は、正確にはわからない。しかし、少なくとも1000万人から多くて2000万人にのぼる、とホブズボームはみている。
だが、ソ連はファシズムのような全体主義国家ではなかったという指摘が目をひく。政治に関心があるのは知識人だけで、市民はむしろ驚異的なまでに「脱政治化」されてしまったところに、ソヴィエト体制の特徴があるというのだ。これは、ある意味、全体主義より怖いことかもしれない。
第二次大戦後に生まれた共産主義国家は、すべてソ連型をモデルにしていた。それは東欧諸国でも同じであり、さらには中国共産党の場合もほぼ同じといえる。ただし、第三世界から社会主義陣営にはいった国々は多少色合いがちがう。いずれにせよ、こうした国々は最高指導者のもと、一党政治体制と文化的なプロパガンダ、国家による計画経済によって運営されていた。多くの国では大量裁判や処刑もつきものだった。
共産党が工業化と近代化をもたらした国々では、新政権は一時、国民の支持を集めた。しかし、ソ連によって併合されたバルト三国や、ソ連が略奪をはたらいた東ドイツでは、ソ連にたいする反発は根強かった。
すでにユーゴスラビアは、ソ連の指令に抵抗して、独自の路線を歩むようになっていたが、その影響はさほど大きくなかった。問題は1956年にフルシチョフがスターリン批判を展開してからである。ポーランドでは改革派が指導部を握った。ハンガリーでは革命が発生し、ソ連軍によって鎮圧された。中国はソ連に反発し、中ソ対立がはじまった。そして、それは次第にエスカレートしていく。
ポーランドで改革のきっかけとなったのは、1956年のポズナンにおける労働運動だった。それから1980年代末の「連帯」にいたるまで、ポーランドの労働運動は、知識人と同盟しつつ、社会主義に反対する運動をくり広げていく。
チェコスロバキアは1950年代はじめの粛清によって、政治的に無力化されていたが、それでも次第に脱スターリン化が進んでいた。そしてついに1968年に党内クーデターによりドプチェクが書記長に選出され、「プラハの春」が生まれる。だが、これもソ連の軍事介入により転覆された。
ソ連は軍事的威嚇によって、その後20年にわたってソヴィエト・ブロックを維持する。しかし、ソ連を中心とした国際共産主義運動はもはや命脈を保てなくなっていた、とホブズボームはいう。
1960年代にはいると、社会主義諸国の経済成長率は西側にくらべて顕著に減速しはじめていた。経済改革はまったく功を奏さない。
そして「1970年代に世界経済が新しい不確実性の時期に入ると、『現存する』社会主義経済が非社会主義経済を追い越したり上回ったりすると期待する者は、東にも西にももはや誰もいなくなり、東が西と同じ歩調で進むと予想する者もいなくなった」。
ここには中国についての言及がほとんどない。本書が1994年に上梓されたことを考えれば、それもやむをえないことだ。それはまた新たな課題だろう。
ここから、いよいよ本書は第Ⅲ部の「地すべり」の時代へとはいっていく。
第三世界の流動──ホブズボーム『20世紀の歴史』をかじってみる(5) [われらの時代]
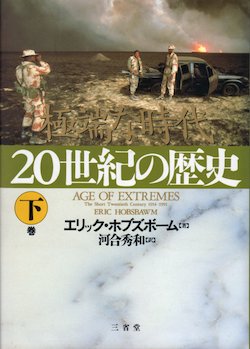
引きつづき、ホブズボームから。
ここでは、いちおう戦後世界を3つのカテゴリーに分類したうえで、話が進められている。
第二次大戦後、第三世界では脱植民地化と革命、それに人口爆発が生じた。これにより、世界人口は1950年以降の40年間に倍増する。医学と薬学の進歩が、幼児死亡率を急速に低下させていた。人口問題は貧困問題ともつながっており、インドや中国の政府はつねに出産制限や家族制限を国民に強要していた。
植民地後の新国家に求められたのはどのような体制を採用するかであり、多くの国が旧宗主国の政治体制を選んだものの、少なからぬ国がソ連をモデルとし、人民民主主義共和国を名乗ることになった。しかし、いずれにせよ、そのどれもが権威主義的な国家であり、1980年代には軍事クーデターがおきて、軍事政権が増えていく。
軍事クーデターによる政権転覆は、意外と新しい時代の産物だ、とホブズボームはいう。それまで軍人は必要以上に政治に介入することはなかったが、地球上に200以上国ができると、状況が変わってくる。
第三世界では軍事政権が成立しやすく、とりわけ混迷と混乱をきわめるアフリカの国では、しばしば軍事クーデターが発生した。それは不安定と危険に左右される政治を生み落とした。
野心的な国々は、中央計画型のソ連モデル、あるいは輸入代替政策によって、後進的な農業国から脱し、体系的な工業化を実現しようとした。とりわけ重要なのは石油であって、石油をもつ国は、その資源を自国で支配し、開発しようとした。欧米の私企業が支配していた石油産業を国有化することによって、外国企業にたいし優位に立つことができるようになった。
経済計画を立てるうえで、問題は熟練と経験のある専門家がいないこと、経済近代化に向けての知識と民衆の共感がないことだった。そのため新興国による工業化目標は、しばしば裏づけのないものとなり、おうおうにして大失敗を招くことになった。闇経済が繁栄し、腐敗がはびこる。あげくのはてに生存を支える農業は無視されていた、とホブズボームは書いている。
とはいえブラジルやメキシコなどの新興工業諸国は、1970年代以降、一時、7%の年間成長率を記録していた。輸入代替政策による工業化が、政府の公共支出とあいまって、国内の高度の需要を支えていたのだ。計画化と国家の主導は欠かせなかった。問題はそれが適切だったかどうかということである。
しかし、第三世界に暮らす人びとにとって、問題は国家の発展よりも、農業や牧畜を営む自分たちの暮らしだった。ところがアジアでもアフリカでも、農民のくらしはかえっていっそう貧しくなった。沿岸と内陸部、都市と僻地では、くらし向きがまるでちがっていたのだ。
政府が近代化を推し進めるにつれ、内陸部と僻地は沿岸と都市によって支配されることになった。政治もまた、読み書きができる者たちによって運用されていた。教育は文字どおり権力を意味した。教育を受けた者は公務員としての地位を保証されたからである。
南アメリカでは、知識への渇望が1950年以降、村から都市への大量移民を引き起こした。都市に行って自動車の運転をならえば、救急車の運転手に雇われる可能性もあった。
しかし、中南米では、最大の課題は何よりも農地改革だった。大土地所有を解体して農民と土地のない労働者に再分配することが求められていた。さらには地代の削減や小作制度の改善をはじめ、土地の国有化と集団化にいたるまで、政策の幅はいくつもあった。
第二次大戦後は、世界中が農地改革を経験した時代である。中国では共産主義型の農地改革がおこなわれた。日本、台湾、韓国でも農地改革が実施された。中東では1952年のエジプト革命にならって、イラクやシリア、アルジェリアが農地改革をおこなっている。中南米では農地改革はかけ声倒れに終わることが多く、キューバ革命によってようやく本格的な農地改革が実施された、とホブズボームはいう。
荘園やプランテーション、ソ連型の国営農場の場合とちがい、一般に農業改革は農民の潜在的な生産力を引きだすことができた。インドのパンジャブ地方では、企業家精神に富んだ農民が国際的な商品作物を生みだしている。
しかし、農地改革への要求は、生産性よりも平等にもとづいていた。1970年代において、所得の不平等は中南米がいちばん高く、ついでアフリカだったが、アジア諸国は低かった。所得分配の不平等は、国内市場の発展を遅らせがちだった。
中南米の農地改革で、インディオたちはかつて奪われた土地を取り返し、そこをふたたび共有地とした。だが、大農場制度が崩壊したあと、その土地は新たな農業組織として活用されることはなく、農業発展をもたらすことはなかった。
ここでホブズボームは、あらためて「第三世界」の意味を問うている。第三世界は1950年代はじめにつくられた概念で、先進資本主義国の「第一世界」と共産主義諸国の「第二世界」と対比するための用語だった。インドとパプアニューギニア、エジプトとガボンをまとめて「第三世界」とするのはあきらかにおかしいが、それでもこれらの国々がかつて古い帝国主義的な工業世界に従属し、いまや新しい国家として発展しようとしているという点では、「第三世界」という言い方にもそれなりに意味がある、とホブズボームは書いている。
こうした第三世界のなかから生まれたのが「非同盟」運動だった。1955年にインドネシアのバンドンで開かれた国際会議に集まったインド、エジプト、中国、インドネシアの指導者たちは、多少なりとも社会主義的であり、資本主義とは異なる独自の道を歩もうとしていた。だが、ただちにアメリカは反撃に出て、反ソ軍事体制として、東南アジア条約機構(SEATO)や中央条約機構(CENTO)をつくって、反共の砦を築き上げた。非同盟運動は宙に浮いてしまう。
だが、たとえ対ソブロックがつくられたとしても、帝国崩壊後の世界には、冷戦とは関係なく、紛争の種が残っていた。インド亜大陸では1962年と65年に中印戦争、1971年にインド・パキスタン戦争が発生する。そして中東は常に不安定で、ほとんどあらゆる地域で紛争が生じた。なかでもイスラエルが動乱の中心原因だった。アフリカも紛争の地だった。
これらの紛争は、本質的には冷戦と無関係だった、とホブズボームはいう。言い換えれば冷戦が終わっても、問題は少しも解決しなかったのである。
中南米はキューバ革命がおこるまで、国際紛争から切り離されていた。中南米は、いくつかの飛び地を別とすれば、早くから植民地を脱し、言語的にも宗教的にも西欧化していた。大量の白人移民が住む地域を除いて、人種通婚が進み、ほんものの原住民はほとんどいなくなっており、純粋の白人もいなくなっていた。基本的に人種政治や人種ナショナリズムとは無縁の地域だったという。
1948年に米州機構(OAS)がつくられ、中南米諸国は政治的にも経済的にもアメリカにしたがう姿勢を保っていた。それがキューバ革命以降、様相が変わってくるのである。
とはいえ、第三世界の概念は1970年代にはいるころから崩れていった。経済発展を遂げる国が出てきたためである。人口の少ない石油産出国の場合は、1人あたりGNPがアメリカを超えるほどになった。香港、シンガポール、台湾、韓国は急速に発展していた。インドやブラジルなどの成長も著しかった。
新国際分業によって、古い工業はいまや新興工業国に移転されつつあった。それが加速されたのは、とりわけ1973年以降の20年間においてである。
こうして第三世界は、繁栄する国と中位の国、それに最貧国へと分岐していくことになった。とりわけ冷戦が終わって経済援助がもらえなくなったアフリカの国々は貧困におちいり、ソマリアのように戦場と化す国もでてくる。
第三世界のうちには観光産業が盛んになる国もあれば、豊かな国々へ労働移民をだす国もでてくる。チュニジア、モロッコ、アルジェリアからはフランスへの移民、中南米からは多くの人がアメリカに移住していた。石油産出国への移民も盛んだった。だが、やがてこうした流れは、先進国における移民締めだしの動きへとつながっていく。
第三世界を分断し、混乱させたのは、世界経済の発展だけではなかった。イスラム世界では、原理主義運動や伝統主義的な運動が巻き起ころうとしていた。
第三世界の大都市は変化のるつぼになっていた。そして、その現代的な風潮はいなかにも広がっていった。コロンビアの国境地帯は、ボリビアとペルーのコカを運ぶ中継基地、それをコカインに加工する工場の所在地になった。
都市の文明が地方のくらしを一変させようとしていた。農村の経済は都市への出稼ぎによっても支えられていた。そうした地下経済によって、南アフリカの黒人居住地(ホームランド)や南米高地の共同社会はようやく維持されていたのである。
何はともあれ、大きな社会的転換が、第三世界のかつての生活を不安定と混乱におとしいれていた。
〈それは、二つの社会的転換に根ざしていた。社会秩序がばらばらになってしまった村落における深刻なアイデンティティの危機と、高度の教育を受けた若者たちの大衆的社会層としての登場である。村々は内と外への移住で性質を変え、現金経済のもたらした貧富の差で分断され、教育による社会的上昇の不均等さによる不安定に悩まされ、人々を隔ててはいたがそれぞれの社会的立場についての疑いを残さなかったカーストと身分という物理的、言語的な区別のしるしがぼやけていき、こうして人々は当然に彼らの共同社会についれの不安の中で生きていた。〉
ホブズボームは「第三世界には、社会的転換の政治的結果をまったく予見できない広大な領域があった」し、そこには、不安定で、引火性の高い世界が広がっていたと論じている。
大きな社会変化──ホブズボーム『20世紀の歴史』をかじってみる(4) [われらの時代]

翻訳書では、ここから下巻にはいる。第10章は「社会革命1945年−90年」、第11章は「文化革命」と題されている。
今回は、この2章を読んでみることにする。
第二次大戦後、社会や文化は大きく変化した。その変化をホブズボームがどのようにとらえているかが、この2章の課題である。
「20世紀後半のもっとも劇的で広範囲な社会的変化、われわれを過去の世界から切り離している変化は、農民層の死滅であった」と、ホブズボームは書いている。
死滅というのは大げさすぎるにしても、戦後、農業人口の割合が激減したのはたしかである。日本でも1947年に全労働人口の52.4%あった農業人口の割合が85年には9%まで減少している。それはアメリカや西ヨーロッパでも同じだった。農業人口の減少は先進国にかぎらない。ラテンアメリカでも、中東や北アフリカでも、社会主義圏の東欧でも、農業人口の割合は半減している。
1980年になっても、農業人口が多数を占めている国は、中東ではトルコ、サハラ以南のアフリカくらいだったという。それまで農民が大多数だったインド、東南アジア、中国でも、その割合は人口の半数を割り込もうとしていた。
農業人口が減ったのは、農業でも資本集約的生産性が増大したためといってよい。言い換えれば、機械化農業が発展し、加えて農業化学やバイオテクロロジー、選択的繁殖技術が導入され、農業はそれまでのように数多くの人手を必要としなくなった。
1960年代の「緑の革命」は、世界の貧しい地域に灌漑と科学的農法を導入した。これにより穀物の増産が実現され、第三世界も人口増に対応できるようになった。いっぽう、食糧を自給するためというより、むしろ先進国市場向けの輸出用作物に重点を置く農業も増えてきた。
農村に人が減ると、都市に人があふれる。「20世紀後半の世界は、かつてなく都市化された」と、ホブズボームはいう。1980年代半ばには、世界人口の42%が都市に住むようになっていた。
都市はふくれあがる。だが、次第に巨大都市の中心部、ビジネス街や官庁街は、夜間にはむしろ人口が減って、人びとは郊外や都市周辺に住み、スプロール化が進むようになった。
先進世界の都市では、道路網が張りめぐらされ、鉄道や地下鉄が発達し、中心部に高層ビルが建てられ、周辺部にはショッピングセンターやレジャー施設がつくられていく。
これにたいし、第三世界の都市は、分散化することなく、いわば村の集合体として、膨れあがっていった。使われていない空き地があれば、いつのまにか不法占拠者の集団が住みついていた。
いずれにせよ、20世紀後半には、都市問題が大きな課題となっていった。
ホブズボームは、次に戦後の変化として、大衆教育の充実を挙げる。
戦後は中等教育、高等教育への要求が高まり、実際、教育を受ける人の割合が増えていった。ホブズボームは、1968年に学生の叛乱が世界的に広がったのも、そのことと無関係ではないと述べている。
親たちが可能なかぎり、子どもたちを学校に進ませたのは、かれらによりよい所得と高い地位を得させるためだった。世界的な好況によって、ごくふつうの家庭でも、子どもを大学に進学させることが可能になった。
1970年代を通して、世界の大学の数は2倍になっている。何百万もの大学生(日本は1950年に32万、1968年に185万、2000年に270万)が大学都市や大学構内に集まり、ひとつの文化的、政治的勢力を形成するようになった。
1968年は、かれらが政治的に爆発した年である。だが、それは革命には結びつかなかった、とホブズボームはいう。学生の叛乱はほとんど労働運動と結びつかず──「プロレタリア大衆の念頭に革命はまるでなかった」──、大きな政治的影響力ももたなかった。そして、一部の急進派は小集団テロリズムで革命をおこそうとして、手早く排除されていった。
学生たちはなぜ左翼的急進主義を選んだのだろう。ひとつに、若者が伝統的に激しい気力、暴動と無秩序、革命的情熱の発生源だったことがある。もうひとつは、この時期に大学生が爆発的に増大したことがあげられる。大学はこうしたなだれ込んでくる学生に組織的にも知的にも対応する準備ができておらず、そのため緊張が生じた。ベトナム戦争への反対、古くさい政治体制、その他の問題も多少の影響を与えたかもしれない。
そんなふうにホブズボームは解釈している。
学生運動の暴発は世界的大好況の絶頂において生じた。かれらは以前の世代よりずっとめぐまれているはずだという批判は、かれらにとって意味をなさなかった。若者たちの不満は、この社会のあり方自体に向けられていたからだ、ともホブズボームは記している。
もうひとつの大きな変化。それは1980年代にはいって、産業労働者の人口が顕著に減りはじめたことだ。生産技術の革新が、人間労働力を節約する方向にはたらいていったことがひとつの原因である。
黄金時代には、産業労働者の割合は就労人口の3分の1を占めていた。それが1980年代、90年代になると縮小していった。
19世紀、20世紀初頭の古い産業は没落した。いまや「アメリカの鉄鋼業の従業員は、マクドナルドのハンバーガー・レストランの従業員よりも少ない」とホブズボームは書いている。
繊維、衣服、靴などの軽工業は新興国に移動した。鉄鋼業や造船業などの重工業も、古い産業国ではほとんど消滅し、かつての工業地帯は「ラスト(赤さび)ベルト」と化した。
1970年代、80年代に経済危機が深まると、かつてのように産業は拡大せず、労働節約的な技術が導入されても労働力が増えていた時代は終わった。「労働者階級は目に見えて新しい技術の犠牲になった」。大量生産ラインの単純労働者は、自動機械に置き換えられていった。
1980年代末になると、製造業に雇用される労働者の割合は、全民間雇用の4分の1程度となり、アメリカでは20%以下になった。とうぜん労働運動は弱体化していく。だが、問題はむしろ数よりも質、すなわち労働者の意識の変化だった、とホブズボームはいう。
20世紀の終わりに向かい、旧来の労働者階級は分解していく。もともと労働者階級の収入はホワイトカラーや中産階級よりも少なかったが、かれらにはそれなりのプライドや生活スタイルもあって、集団として団結していた。しかし、戦後の黄金期をへて、労働者の生活も変わっていった。「繁栄と私生活化が、貧困と公共の場での集団性が結合させていたものを切り離したのである」
労働者はいまや贅沢品の買い手であり、車やテレビ、カメラの所有者でもあった。完全雇用と消費社会が、労働者に自分たちの父親よりも豊かな生活、必需品以外も買うことのできる生活をもたらしていたのだ。
さらに、1980年代にはいると、労働者階級は、ハイテク技術に対応する豊かな労働者と、最底辺の労働者に分解し、労働者間の格差が広がっていく。
技術労働者は政治的保守派を支持するようになる。伝統的な社会主義組織は、富の再分配と福祉を支持していたが、上層の労働者はもはやその政策を支持しない。ホブズボームによれば「イギリスのサッチャー政権が成功したのは、本質的には熟練労働者が労働党を離れたからであった」。
19世紀には大量の移民労働者が労働者階級を分断することはなかった。移民の多くはそれなりの自分たちの居場所をみつけ、社会に適応していった。しかし、戦後の移民はもっぱら労働力不足に対応するため、政府主導でおこなわれ、労働者のあいだで、さまざまなあつれきを生むことになった。
女性、とりわけ既婚女性が労働の場に進出したことも、労働者階級に大きな影響をもたらした、とホブズボームはいう。働く既婚女性の割合は、アメリカでは1940年に14%以下だったのに1980年には半分を超えている。
先進国で女性労働力を吸収していったのは、とりわけ第三次産業である。新興工業国でも、製造業の飛び地で、女性労働力が求められていた。
高等教育を受ける女性も増えていった。いまや大学教育は男子よりも女子のあいだに広がっているほどだ。1960年代以降の女性解放運動を支えたのは、既婚女性の職場進出と、女子への高等教育の普及だった、とホブズボームは分析する。
選挙のおこなわれているほとんどの国で、女性は1960年代までに参政権を獲得している。女性はいまやかつてなく大きな政治勢力となった。女性の公的役割が変化し、多くの女性が国の指導的立場を担うようになった。
それでも女性の置かれた地位は、国によってさまざまである。旧社会主義世界では、すべての女性は仕事についていたが、政治の指導的な場からはしめだされていた。しかも、ホブズボームによると、「たいていのソ連の既婚女性は……西欧の女性の権利擁護論者とは逆に、家庭にいて家事だけをするという贅沢にあこがれていた」という。
男性支配の制度と慣習を変えようとした革命は、ソ連でも途上国でも、たいていが夢のままで終わった。むしろ1930年代のソ連は、女性を子どもを産む存在と位置づけ、計画的出産を推進する反動的な時代だった。
社会主義世界は女性の権利のための運動を生みださなかった。それどころか、そもそも1980年代以前は国家と党の支持していない政治的な動きが禁じられていたのだ。
フェミニズムに先鞭をつけたのはアメリカである。1980年代にはいると、女性たちはオフィスや知的職業でも、大きな割合を占めるようになった。
既婚女性が働くようになったのは、児童労働が消滅したからである。そのため、長い期間にわたって、両親は長いあいだ子どもを養わなくてはならなかった。女性が働きにでるようになったのは、そのためでもある。
とはいえ、中流家庭にとっては、女性が働いたからといって、家族の所得を大きく増やすことにはならなかっただろう。問題は所得よりも、自由と自立の要求だった。女性が外で働くのは解放的な要素がからんでいた。そのことが結婚や生活のスタイルにも大きな変化をもたらすことになる。
第11章にはいろう。
戦後の大きな変化は家族や世代関係にもあらわれている、とホブズボームは書いている。
伝統的な家族関係は、結婚という制度、家庭での夫の優位、両親による子どもの養育、数人からなる世帯の形成、年長世代への敬意、つながりの深い親族・血縁関係によって成り立っていた。だが、20世紀後半には、この関係が変化してきたという。
ひとつは離婚が増えたことである。ホブズボームによると、イングランドでは1960年と1980年のあいだにイングランドの離婚率は3倍になった。その傾向は先進国ではどこも同じだという。
もうひとつは一人住まいが増えたことである。結婚しない人が増加している。
さらに伝統的な核家族が減っていることがあげられる。1980年代半ばに、スウェーデンでは、全出産数の約半分は未婚女性によるものだったという。1991年、アメリカの黒人世帯では、半数以上が単身の母親が世帯主となっていた。
家族のかたちが変化しはじめたのは1960年代、70年代だった。アメリカでもイギリスでも同性愛行為は1960年代に合法化されている。イタリアでは1970年に離婚が合法化、1978年に中絶が合法化され、ともに国民投票で確認されている。
家族関係が変化した背景には、若者文化の台頭がある、とホブズボームはみる。映画、音楽、ファッション、スポーツなどなど、これらをすべて若者が引っぱっていた。しかも若者は購買力のかたまりでもあり、コンピューター文化の先導者でもあった。世代の役割は逆転した。子どもはもはや両親の知らないことを知っていた。
若者文化の国際性にも注目しなければならない。ロック・ミュージックは社会主義圏を含め、世界を席巻した。映画やテレビ、ラジオ、レコードなどを通じて、地球規模の若者文化が成立した。これは20世紀後半まではみられないことだった、とホブズボームはいう。
1925年前後に生まれた世代と1950年前後に生まれた世代とのあいだには、大きな歴史的ギャップがあった。若者たちは過去から切断された社会に生きていた。年長者はこうした若者を理解できなかったし、若者たちは1930年代の経験を理解できなかった。世代間の断絶が生まれた。
若者文化は文化革命の土台となった。それは民衆的で、規則にこだわらない文化を生みだした。初期のハリウッド映画には中流階級的な上品な規制がかけられていたが、そうした規制は次第にとりはずされていく。パリの五月革命は「禁止することは禁止されている」という標語を生みだした。すべての人びとが、外からの制約を受けずに「自分自身のことをする」ようになった、とホブズボームはいう。
私的な解放と政治的な解放が手を携えて進んだ。外部のきずなを断つ、もっとも安直な方法は性と麻薬だった。同性愛文化やマリファナの吸引も広がっていく。絶対的個人主義のもと、個々人がそれぞれの願望を追求する風潮が生まれ、それを大衆消費社会(裏ビジネスを含め)が支える構図ができあがった。
古い社会的組織と慣行は挑戦を受けた。人びとはさらなる平等を求めるようになった。新しい個人主義が誕生する。教会のミサに行く人びとの数は少なくなり、伝統的な家族のきずなも緩んだ。権利と義務、相互の責任、罪と罰、犠牲、良心といった古い道徳は、欲望の充足を願う行動を前にしてかすんでいった。
かつての地図は役に立たなくなり、不確実性と予測不可能性が世界をおおうようになる。こうして、極端な自由市場的自由主義が横行するようになった。
絶対的自由主義のもとに、共同体と家族は急速に解体されていった。1980年代になると、そのあとに「下層階級」という無気味なことばが登場する。ホブズボームによれば、「下層階級」とは先進的な市場経済諸国において、じゅうぶんに暮らしていけない人びとのことを指している。
「三分の二社会」という言い方も生まれた。市場経済は国民の三分の二しか満たすことができず、あとの三分の一はそこから取り残されてしまうというわけである。
ホブズボームは、資本主義の発展が、いまや古い価値体系や習慣、一般通念までをも破壊し、いわば市場万能のもとにホッブズ的ジャングルをつくりだしていると批判し、こんなふうに書いている。
〈20世紀最後の3分の1に生じた文化革命は、資本主義の歴史的な相続財産を崩し始めた。そして、そのような資産なしに資本主義を運営することがいかに困難であるかを証明し始めた。1970年代、80年代に流行した新自由主義の歴史的な皮肉は、それが共産主義政権の廃墟を見下し、勝ち誇ったまさにその瞬間に、それ自身が以前ほどにもっともらしい理論とは思えなくなったことであった。市場は、それがいかに裸で不じゅうぶんであるかをもはや隠しきれなくなった時に、勝利を唱えたのである。〉
資本主義はみずからの養分としての社会や文化を破壊しながら成長しつづけたが、気がつくと、そのあとには裸の個がたたずむ荒野が残されていた。資本主義はもはや発展の土壌を見失ってしまったのだ。20世紀の終わりに共産主義政権を打ち破り、勝ち誇った資本主義は、すでにみずからの墓穴を掘りはじめている、とホブズボームは見ている。
こうした見方が正しいかどうかはわからない。どこか違和感もある。早々と結論を下す前に、さらに先を読んでみよう。
豊かな社会の到来──ホブズボーム『20世紀の歴史』をかじってみる(3) [われらの時代]

[94歳のホブズボーム]
先日、図書館でちくま学芸文庫にはいっているホブズボームの『20世紀の歴史』を借りてみた。いずれにせよ翻訳物はなかなか頭にはいらないのだが、これも相当な代物だった。それで、けっきょく引きつづき手元の三省堂版を読み進めることにした。
きょう読んでみるのは、第Ⅱ部「黄金時代」の第9章「黄金の歳月」。社会主義が資本主義に敗れ去ることになる核心がここに描かれている。ホブズボームはあくまでも冷静な記述に徹している。
先進国の人びとが、戦後の四半世紀は黄金の歳月だったと気づいたのは、1970年代の波乱の時代、1980年代の悪夢の時代を迎えてからだ、とホブズボームは記している。
だが、その黄金期は国によってばらつきがある。戦争の被害を受けなかったアメリカが1950年には西ヨーロッパ諸国や日本にくらべ圧倒的な経済力を誇っていたことはいうまでもない。
ヨーロッパ諸国や日本にとっては、戦争からの復興が最優先課題だった。復興に多少時間がかかった西ドイツと日本を別にして、1950年にはほとんどの国が戦前の経済水準をとりもどしていた。そして、1960年代にはいると先進諸国はこれまでにない繁栄ぶりを謳歌するようになる。
経済成長率が高かったのは資本主義諸国だけではない。すくなくとも1950年代終わりまでは、ソ連の経済発展もめざましかった。中国はともかくとして、第三世界でも食糧生産が増え、人口が増加していた。だが、1960年代以降は、豊かな世界と貧しい世界との経済格差が広がっていく。
世界経済は爆発的な勢いで成長していた。世界の工業製品の生産は、1950年代はじめから70年代はじめにかけ4倍となり、工業製品の世界貿易は10倍になった。農業の生産性も高まり、農業生産高は倍以上になっている。だが、経済発展にともない汚染と環境悪化も進んでいく。都市化の進展は、都市の乱開発を生んだ。
工業化と都市化は、化石燃料の使用増加を抜きには語れない。化石燃料は使い尽くされる心配よりも早く、つぎつぎと新しい資源が発見されていった。1950年から73年にかけて、石油価格は1バレル=2ドル以下という安さを保っていた。そのことが工業化や生活向上に寄与しただけでなく、自動車社会の到来を促進することにもなる。
世界の経済発展がアメリカをモデルにしたものであることを、ホブズボームは否定しない。「世界的大好況の大部分は、こうしてアメリカに追いつくことであり、アメリカでは古い傾向の継続であった」
自動車産業からジャンク・フード、観光にいたるまで、資本がターゲットにしているのは大衆市場だった。この時代、かつては高価だった冷蔵庫、洗濯機、電話なども安価になり、誰でもが容易に手にはいるようになった。
技術革命によって、新製品も生まれた。プラスチック製品、ナイロン、ポリエチレン、テレビ、磁気テープ、その他エレクトロニクス商品、トランジスター、コンピューターなどなど、数えたらきりがない。
こうした新技術とそれにもとづく新商品が、世界の日常生活を一変させていったのだ。何もかもが便利で、これまでできなかったこともできるようになった。新しいとは、単によいだけではなく、革命的変化を意味していた、とホブズボームはいう。
経済成長の中心を担ったのが「研究と開発」である。「技術革新はきわめて経済的な過程でもあり、新製品を開発する費用が生産費の中でますます大きな、そして不可欠の部分を占めるようになった」
新しい技術は、圧倒的に資本集約的で労働節約的だった。ということは不断の投資が必要で、労働力はあまり必要としないということでもあった。しかし、経済が速く成長したために、労働力は不足気味で、そのため農民や移民に加え、既婚女性までが労働力市場に加わっていくことになる。
資本主義を悩ませていた好況と不況の循環は、賢明なマクロ経済管理によって、いまや穏やかな経済発展軌道に変わった。先進国では大量失業はどこにもなかった。労働者の所得は上昇し、福祉国家のもと医療や老後の保障も得られるようになった。
資本主義が「大躍進」を果たしたのは、アメリカという先進モデルがあったためだけではない。資本主義の改革に加え、経済のグローバル化が実現されたからだ、とホブズボームはいう。
資本主義は、いまや「混合経済」体制になっていた。すなわち市場経済をベースにして、国家が経済を計画し、管理する体制である。新しい資本主義の目標は、完全雇用の実現と、経済的不平等の軽減、福祉と社会保障、市場の民主化(大衆消費市場の実現)だった。
経済のグローバル化は、国際分業と貿易を促進した。先進工業国は輸入工業製品を代替的に生産しながら自国の工業生産力を高め、世界に乗り出していった。
技術の移転にも注目しなければならない。古い技術は、次第に途上国へと移転されていく。石油と内燃機関の工業技術はアメリカからヨーロッパや日本に移転し、その工業化を支えた。化学と薬学の分野が第三世界に与えた衝撃は大きかった。それにより人口爆発が生じたからである。さらに情報技術と遺伝子工学は、その後の世界に大きな変化をもたらしていく。
戦後資本主義はこれまでとはみちがえるものになっていた。ホブズボームにいわせれば、それは経済的自由主義と社会民主主義、それに経済計画を組み合わせた体制だった。
経済再建計画は早くから練られていた。生産の増加と貿易の拡大、完全雇用、工業化、近代化はだれもが望むところだった。市場経済と雇用を維持しながら政府の統制と管理を強化するというケインズ的な方向は、社会民主主義の考え方とも一致していた。
戦後の国際的経済制度に関しては、「多くのアイデアと提案はイギリスから出たが、行動への政治的圧力をかけたのはワシントンである」とホブズボームは書いている。
いずれにせよ、ケインズなどの提案したアイデアのなかから、国際通貨基金(IMF)と世界銀行の構想がまとまった。この二つの制度の目的は、長期的な国際投資を増進し、為替の安定性を維持し、国際収支問題に対処することだった。さらにこれに加えて、貿易障壁を徐々に削減していくために、関税と貿易に関する一般協定(GATT)が結ばれた。
これらの制度は、ドルによる経済支配と結びついていた。その体制が崩れるのは1970年代はじめになってからである。しかし、そのときまでアメリカを中心に資本主義世界経済は発展した。
とはいえ、ホブズボームによれば、「黄金時代の世界経済は、超国家的(トランスナショナル)というよりもまだ国家間的(インターナショナル)であった」。
経済活動が国家の枠を超えることはなかった。経済が国家の枠を超えるようになるのは、1970年以降である。
多国籍企業が登場し、タックス・ヘイブンが生まれた。多国籍企業は「国境を越えて市場を内部化」することで、国家から独立した動きをみせるようになる。新しい国際分業が古い国際分業を掘り崩しはじめた。
1970年代には、繊維製品や紙製品、エレクトロニクス、デジタル時計などの生産は発展途上国に移っていた。部品製造と組み立てを、世界の別々の地域でおこない、それを本社センターで管理する仕組みも誕生した。
工場が高コストの場所から安い労働力のある場所に移っていくのは自然なことだった。こうして、ケインズ的な結合(経済成長と大量消費、高賃金、労働者保護、労働生産性の増大)は次第に崩れていく。それが黄金時代の終わりをもたらした。
福祉国家を実現した先進国の黄金時代は、穏健左派が政治のヘゲモニーを握っていた時代でもある。1968年には、突如学生運動が噴出した。黄金時代が疲弊のきざしをみせはじめたのはそのころだ。アメリカの覇権は衰え、世界通貨体制は崩壊しようとしていた。
だが、学生叛乱は政治的・経済的現象ではなく、一過性の文化現象にすぎなかった、とホブズボームはいう。
「1968年は、終わりでも始まりでもなく、一つの兆候でしかなかった」。経済体制が過熱していたことはまちがいない。しかし、1929年のような破局の予兆はなかった。
それが1973年の石油ショックと、それに引きつづく大不況につながるとはだれも予想していなかった。そして、これ以降、世界経済は地すべりをおこし、大きく変化していくのである。
冷戦の時代──ホブズボーム『20世紀の歴史』をかじってみる(2) [われらの時代]

20世紀後半は、いわゆる「冷戦の時代」で、それは1945年から89年までつづいた。歴史には何層もの色彩が塗り重ねられているとすれば、冷戦はやはり20世紀後半の基層となる色彩だったといえるだろう。
冷戦とは核時代における米ソ両陣営の軍事対立のことだ。しかし、米ソ間で直接の軍事衝突が生じなかったことが、この時代の特徴である。
ホブズボームはこの状況をとらえていたのだろうか。
〈冷戦の特異さは、客観的に言って世界戦争の直接的な危険はなかったという点にあった。しかも、双方の側、とくにアメリカの側の世界終末論的なレトリックにもかかわらず、二つの超大国の政府はともに第二次大戦終結時の世界的な権力配分を承認していた。〉
この権力配分が決められたのは、第二次大戦末期の1943年から45年にかけて米英ソの首脳(ルーズヴェルト、チャーチル、スターリン)によって開かれた一連の会議においてである。のちにチャーチルが「鉄のカーテン」と呼ぶヨーロッパの権力配分は、その後、冷戦が終わるまで、ずっと維持されることになった。
問題はヨーロッパ以外の地域だった。日本はアメリカが完全に占領していた。中国はソ連の意向に反して、意外にも中国共産党が政権を掌握した。旧植民地帝国の解体はもはや避けられなかった。だが、その将来の方向は定かではなく、そのことが米ソの摩擦を生む要因となった。
そして、まもなくポスト植民地の新国家は「第三世界」の道を模索し、米ソ両陣営に属さない「非同盟」を標榜するようになっていく。中国もまたソ連から離れて、独自の方向を歩んでいくことになる。
1950年には朝鮮戦争が発生し、1962年にはキューバ・ミサイル危機が生じた。しかし、米ソ両国の直接対決は回避された。
ソ連は1953年に東ドイツ、1956年にハンガリーに直接介入する。これにたいし、アメリカは干渉することを避けている。第二次大戦後の勢力配分は守られたのである。
1949年にソ連が核兵器開発に成功すると、「超大国はともに相互敵対政策の道具としての戦争を明白に放棄した」とホブズボームは述べている。しかし、核使用のジェスチャーは、その後も世界を不必要な戦争に投げ込む危険性を招くことになった。
このあたりは評価が分かれるところだが、ホブズボームは冷戦を仕掛けたのは、むしろ西側だったとみている(しかし、正確にはむしろ、冷戦の原因をつくったのはソ連で、冷戦を仕組んだのはアメリカだというべきだろう)。
戦後すぐの段階においては、資本主義の将来はけっして確実なものではないと思われていた。ヨーロッパの多くの国々が、共産党勢力の増大に悩まされていた。アメリカの職業的外交官たちは、このことに「世界終末論」的な危機感をいだき、現実にはありえなかったソ連の膨張を何としてでも阻止しなければならないと考えるようになった。
「戦後のソヴィエトの基本的な姿勢は、攻撃的ではなく防衛的だった」。ソ連はアメリカの「封じ込め政策」に対応し、毅然とした態度をとらなければならなかった、というのがホブズボームの見方である(とうぜん、異論はあるだろう)。
こうして双方が非妥協的な態度をとるようになった。とりわけ、それはイデオロギー的な対立として表面化していった。
アメリカでは反共主義は人気があり、そのおかげで世界的強国としての強気の外交政策を展開することができた、とホブズボームはいう。その結果、双方が相互破壊のための狂気の軍備競争をエスカレートさせていった。そして、全般的な危機が深まるなか、核兵器の開発は米ソだけではなく、イギリス、フランス、中国、イスラエル、南アフリカ、インドにまでおよんでいくことになる。
冷戦の目的は、共産主義の撃滅ではなく、封じ込めだった。
冷戦期間中には、3つの大きな戦争があった。朝鮮戦争、ベトナム戦争、アフガニスタン戦争である。朝鮮戦争は引き分けに終わった。ベトナム戦争ではアメリカが敗北し、アフガニスタン戦争ではソ連が敗北した。
冷戦は世界をアメリカとソ連の陣営に二分した。西側では共産党が政権の座につくことはなく、政治の局外者にとどまっていた。アメリカと対決するためにつくられたコミンフォルムは1956年に解散している。東ヨーロッパでは、ユーゴスラビアをのぞいて、ソ連の抑圧的な直接支配がおよんでいた。
戦争の結果は、西側諸国では右翼的、国家主義的政党の排除をもたらした。それにより西側諸国の政権は、社会民主党的な左翼から穏健な非ナショナリスト的な右翼までのスペクトラムで形成されることになった。ヨーロッパではとりわけキリスト教民主主義にもとづく政党が中心的な役割を果たした。
1947年にアメリカはヨーロッパ復興のために、大規模なマーシャル・プランを発動する。アメリカは日本経済復活のためにも大きな力を注いだ。さらに反ソ軍事同盟として、ヨーロッパにたいしては北大西洋条約機構(NATO)、日本にたいしては日米安保条約を導入することになる。
しかし、冷戦が生み落としたものとして、とりわけ注目しなければならないのは、欧州共同体(EC)である。ECの意義はフランスとドイツの敵対関係に終止符を打っただけにとどまらない。それはアメリカと一歩距離を置きつつ、ソ連に打ち勝つための国家連合にほかならず、1993年以降は欧州連合(EU)へと発展していくことになる。
ソ連にたいする同盟が、アメリカの基本政策であり、軍事計画もアメリカ主導のもとで実施された。しかし、冷戦の時代がつづき、ヨーロッパと日本の経済が復興するとともに、アメリカの絶対的優位は崩れていった。1971年8月のドル・ショック以降、西側各国の為替制度は固定制から変動制に移行しはじめる。冷戦が終わった時点では、軍事体制に関してもアメリカは一国だけでその覇権を維持できない状態になっていた。
しかし、それはまだ先のことである。
1950年から53年までの朝鮮戦争、1953年のスターリンの死以後の地殻変動は、世界的な危機にはいたらなかった。フルシチョフがソ連で政権の座についたときには、デタント(緊張緩和)がささやかれるほどだった。
ところが、その直後にキューバ・ミサイル危機が訪れる。幸いにも、この異常な緊張も回避された。
だが、冷戦は終わらなかった。その後、脱植民地化と第三世界の革命が進行するなかで、米ソ両国のあいだでは、神経質な駆け引きがくり広げられる。1961年にはベルリンの壁が築かれていた。そして、ケネディは1963年に暗殺され、フルシチョフは1964年に追放されることになる。
世界の核兵器を管理、削減するため、1968年には米ソ英仏、中国の5カ国のあいだで核拡散防止条約(NPT)が締結された。1969年からは米ソ間で戦略兵器制限交渉(SALT)が開始された。
だが、そのころベトナム戦争に深入りしていたアメリカは、国際的に孤立していたばかりか、国内的にも反戦デモを招くなどして、混乱をきわめていた。
1973年に第4次中東戦争(ヨム・キプル戦争)が発生したときも、アメリカは的確に対応できなかった。このとき、中東のアラブ諸国はイスラエルへの加担を阻止するため、OPECを通じて、石油を武器に西側諸国を威嚇したのだ。その結果、石油の世界価格は何倍にもはねあがったが、アメリカは手をこまぬいたままだった。
1974年から79年にかけて、アジア、アフリカ、中南米では革命の波が巻き起こった。独裁的な新政権は、表向き社会主義の立場を標榜したため、アメリカはそれをソ連の世界支配への野望と受け取った。
こうして、いわば第2次冷戦がはじまる。第三世界を舞台にした第2次冷戦で、アメリカはベトナム戦争の愚を避け、間接的に局地戦争を戦う戦術をとった。
1974年のポルトガル革命、翌年にはフランコの死にともなうスペインの政変があったものの、ヨーロッパの状況は安定していた。そうしたなか、アメリカはエジプトからソ連を追放し、中国を反ソ同盟に引き込むことに成功する。
いっぽう、ソ連はアフリカの旧ポルトガル植民地を社会主義陣営に引き入れ、エチオピア革命を成功させ、インド洋の両側に海軍基地を確保していた。イランでも革命がおき、アフガニスタンにはソ連軍が侵攻していた。
だが、そのころソ連は破産しはじめていたのだ、とホブズボームはいう。ブレジネフ政権(1964−82年)の根拠のない自己満足が、無意味な軍拡競争を加速させていた。
アメリカの力はソ連よりも決定的に大きかった。それでもアメリカはソ連による核攻撃という空想的なシナリオを捨てきれないでいた。
1970年代のアメリカのトラウマが、レーガン政権(1980−88年)に軍事力誇示の姿勢をとらせたといってよい。アメリカは立て続けに、1983年のグレナダ侵攻、1986年のリビア爆撃、1989年のパナマ侵攻に踏み切った。そして、思いがけぬソヴィエト・ブロック崩壊がアメリカのトラウマをいやすことになる。
レーガンのいう「悪の帝国」ソ連にたいする十字軍は、実際的というよりイデオロギー的なものだった、とホブズボームは評する。「黄金時代」が終わったあと、アメリカとイギリスでは、社会主義的なものをすべて敵とみなすイデオロギー右派が政権を握っていたのだ。
ソ連が崩壊したとき、アメリカはソ連との冷戦に勝利したのだとの言説が、あたかも真実であるかのように広められた。だが、レーガン、ゴルバチョフとのあいだで1986年のレイキャビク会談、1987年のワシントン会談がおこなわれたときも、米ソ両国の首脳、とりわけゴルバチョフは核兵器のない世界での平和共存をめざしていたのである。
冷戦の終わりとソヴィエト体制の終わりは別の現象だ、とホブズボームはいう。問題は資本主義に代わるべき社会主義が、改革された資本主義にはるかに遅れをとってしまったことにあった。1960年代以降、社会主義は政治的、軍事的、経済的、イデオロギー的に、もはや競争力を失ってしまっていた。ソ連はもはやアメリカとの軍拡競争に耐えられなかった。
ソ連型の中央計画的指令経済は、世界のグローバル化が進むなかでは生き延びられなかった。1986年、87年の段階で、ソ連が超大国でないことは、すでに明らかになっていた。
第二次大戦後、それまでの列強は没落し、アメリカの覇権が確立された。アメリカと対抗するソ連ブロックが強権的につくりだされたものの、その勢力は弱かった。中国はソ連の支配権から離脱し、アメリカ帝国主義に敵意をもつ第三世界にたいしても、ソ連は現実の支配力をもっているわけではなかった。
冷戦がもたらしたのは膨大な量の武器であり、国際武器市場だった。それは冷戦後もなくなったわけではない。また冷戦の終結が、単一の超大国による「新世界秩序」を生みだしたわけでもなかった。「冷戦の終わりは国際紛争の終わりではないことが証明された」
古いものは終わったが、新しいものはまだ見えていない。ホブズボームはそう記している。
冷戦終結から30年、いま世界はどう変わったのだろうか。
ホブズボーム『20世紀の歴史』をかじってみる(1) [われらの時代]
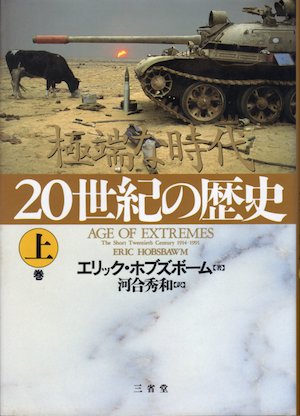
このブログは1968年ごろの「われらの時代」に焦点を合わせている。このころぼくは、いなかの家を離れて、東京で下宿生活をしていたが、すでに大学からドロップアウトしていた。といっても、気のちいさい、二十歳のただのノンポリ学生にすぎなかった。1968年に特別の思い入れがあるわけではない。
ごく単純な数字合わせをしてみる。すると、1968年の23年前は1945年、23年後は1991年ということになる。言い換えれば、1968年は第二次世界大戦の終結と、ソ連邦崩壊の中間点にある。
さらにもっと長く射程をとってみると、1968年の51年前は1917年、51年後は2019年だ。ロシア革命がおこり、下り坂の平成が終わっている。
どのように射程をとるかは自由だが、こんなふうに時間軸をのばしてみると、なぜか1968年が何かの折り返し点だったように思えてくるのが不思議だ。もっとも、それは勝手な思い過ごしかもしれない。
さらに思うのは、かくも長い歴史の大半を、ぼくが世界の片隅で、無事にすごすことができたことだ。これも気がちいさかったことの効用。しかし、そんなことはどうでもよろしい。
本書はErick Hobsbawm, Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914-1991, Pantheon, 1994 を翻訳したものだ。1996年にはVintage からペーパーバックもでている。
著者のエリック・ホブズボーム(1917−2012)はイギリスの大歴史家。その経歴をみると、ポーランド系ユダヤ人の父、オーストリア人の母とのあいだにエジプトのアレクサンドリアで生まれている。ウィーン、ベルリンを経て、1933年イギリスに移住。1936年イギリス共産党に入党、その後60年間、共産党にとどまりつづけた。ケンブリッジ大学で博士号をとり、ロンドン大学教授として歴史を教えた。主な著書として、「長い19世紀」を扱った3部作『市民革命と産業革命』、『資本の時代』、『帝国の時代』、そして「短い20世紀」を扱った本書、その他がある。
「長い19世紀」にたいして、「短い20世紀」という言い方がされるのは、20世紀こそ著者が実際に生きた時代であり、「短い」という形容には、20世紀がめくるめく激動のうちに、あっというまに過ぎ去ってしまったという実感が含まれているのかもしれない。と同時に、20世紀の意味はまだ解明されはじめたばかりで、いまは「短い」歴史しか書けないという感慨から名づけられた可能性もある。
ぼくがもっている(いただいた)のは1996年に三省堂から河合秀和訳で出版されたもので、日本語版上下巻のタイトルは『20世紀の歴史──極端な時代』となっている。
本書には別の翻訳もある。2018年にちくま学芸文庫として大井由紀訳でだされたもので、その上下巻のタイトルは『20世紀の歴史──両極端の時代』となっている。タイトルの微妙なちがいにお気づきだろうか。「極端な時代」か「両極端の時代」か。Extremesが複数形であることを考えれば、「両極端の」のほうがより正確かもしれない。
とはいえ、ぼくがもっているのは三省堂版だ。河合秀和訳と大井由紀訳とを厳密に比較していないので、どちらがいいかについては、何ともいえないが、ここでは河合秀和訳で読書メモをまとめてみることにする。
いずれにせよ、ぼくが読もうとしているのは、後半の第二次世界大戦終結後の部分だけである。つまり、1968年を折り返しにして、1945年から1991年まで。戦前を飛ばしてしまうのは、特に理由があるわけではない。上下巻の大著なので、とても読み切る自信がないというに尽きる。しかも、後半を読むといっても、それはどちらかというと斜め読みだから(とくに翻訳書がそうだが、最近は何を読んでも頭にはいってこない)、以下のまとめは雑な印象にとどまる。期待は禁物である。
とはいえ、まず「総論」にあたる「大局的な見方」だけでも眺めて、いちおう本書の概要をつかんでおいたほうがよさそうだ。
ホブズボームは1914年から1991年までの「短い20世紀」をサンドイッチのように3段階にわけている。(1)1914年から第二次大戦終結までの災厄と二度の大戦に見舞われた「破局の時代」(2)異様なまでの経済成長と社会変容が生じた1945年から70年代はじめまでの「黄金の時代」(3)それ以降の混乱と危機に満ちた「地すべりの時代」である。
20世紀が「両極端の時代」というのは、前半の「破局の時代」と中盤から後半にかけての「黄金の時代」が両極端をなしているようにみえるからだ。
いま読もうとしているのは、(2)と(3)で、ぼくはほぼ同時代を生きてきた。
20世紀を語るうえで、資本主義と社会主義という思想的対立軸は、やはり欠くことができない、とホブズボームはいう。とりわけ、第二次世界大戦後、資本主義が黄金時代を迎えたのにたいして、その後の「地すべりの時代」において、現存する社会主義が没落していったのはなぜかを詳しくみていかねばならないと述べている。
とはいえ、ソ連型社会主義の没落以降、資本主義も完全な勝利を収めたわけではなく、大量失業や深刻な不況、経済格差、財政問題などの重荷をかかえるようになっいる。それにともない、自由民主主義の政治体制も揺らぎはじめている。社会的・道徳的危機も進んでいる、とホブズボームはいう。そのかぎりでは、「地すべりの時代」はいまもつづいているのかもしれない。
1994年に出版された本書は、無論21世紀の現在(2020年)にいたるまでの動きをとらえてはいない。著者は20世紀があまりよい終わり方をしなかったとみていた。これはソ連体制の崩壊に「歴史の終わり」をとらえた楽観的な見方とは対称的なとらえ方だったともいえる。
本書が範囲とする1914年から1990年までを俯瞰してみよう。
1914年の世界と1990年の世界はどうちがっていたのだろう。そのかん、人類は戦争による大量死を経験した。にもかかわらず、世界人口は3倍に増え、60億に達した。人間は過去のいかなる時代よりも長命になり、商品世界が発展して、身の回りの財やサービスも増大した。人びとはかつてよりよい暮らしをするようになった。たいていの人が読み書きができるようになったのも、歴史上はじめてのことである。技術の進歩も著しい。交通通信革命は、時間と距離を事実上、消滅させてしまった。
にもかかわらず、20世紀の終わりが不安な気分に満ちているのはどうしてだろう、と著者は問う。それは20世紀が暴力と殺戮の世紀だったことと関係しているが、それだけではない。何か地すべりのようなものがおきているからではないか、と著者は推察している。
さらに20世紀の初めと終わりには大きなちがいがあるという。第一に世界がヨーロッパ中心ではなくなり、アメリカの世紀となったこと、第二に、グローバル化が加速され、地球が一つの作業単位となったこと、第三に、伝統的な社会関係が崩れ、人間の意識が自己中心的になったことだ。
著者はあまりよい終わり方をしなかった20世紀とはちがい、次の世紀が「よりよい、より公正で、より生命力のある世界であることを希望しよう」と述べている。だが、21世紀の20年はその期待を裏切り、むしろ混沌と不安を増しているように思える。
以上は本書を読むにあたっての前置きである。
それにつけても思うのは、同時代評価のむずかしさである。終生マルクス主義者としての立場をつらぬいたホブズボームは、けっしてソ連に寛容ではなかったが、それでもスターリニズムを徹底して糾弾することはなかった。かれがソ連(や中国)を歴史的にどう評価していたのかも、ひとつのポイントである。
なお、ぼくの手元の本棚には、このころの歴史を扱った本が何冊かある。
ぼく自身が編集を担当したポール・ジョンソンの『現代史』は保守派ジャーナリストによるものでおもしろい。トニー・ジャットの『ヨーロッパ戦後史』はすばらしい本だ。イアン・カーショーの2冊本もある。アン・アプルボームの『鉄のカーテン』はソ連による東欧支配の実態を明かした力作だ。ほかにもいろいろある。こうした本などもちらちら眺めながら、海外旅行に行けないコロナの夏に、ホブズボームの『20世紀の歴史』を少しばかりかじってみようと思っている。
吉本隆明『共同幻想論』をめぐって(6) [われらの時代]
[8月5日、八幡平にて]
神話の時間性は、つねに歴史が途絶えてしまう時間よりもはるかに遠隔を志向している、と吉本は書いている。
『古事記』を神話と読むことによって、吉本は日本における国家の起源に迫ろうとしていた。もちろん神話は実際の歴史ではなく、事実でも事件でもない。それは事実や事件の象徴であって、共同幻想のかたち(ゲシュタルト)を示したものである。
国家の形成をさぐるさいに、吉本がもっとも着目するのが、アマテラスとスサノオの関係である。
姉のアマテラスが高天原を統治する天つ神の象徴であるのにたいし、スサノオは農耕社会を支配する国つ神(しかも出雲系)の象徴と理解される。
のちの大和政権からみれば、スサノオは二重の意味での反抗者にはちがいないのだが、それでもけっきょくは天つ神に服属する。それによって「〈姉妹〉と〈兄弟〉による〈共同幻想〉の天上的および現世的な分割支配」を実現させることになる。
スサノオが高天原を追放され出雲に降りるのは、共同体の「原罪」、すなわち天つ罪を犯したからである。その原罪は、のちにつづく農耕民全体が(税として)背負わねばならぬものとして設定されることになる。
スサノオは八岐大蛇(ヤマタノオロチ)を退治し、地元のクシナダヒメと結婚して、出雲を支配する。こうして出雲を農耕社会へと発展させるのだが、それはアマテラスの赦(ゆる)しを得てのことである。スサノオが天つ罪を犯したという事実は何ら帳消しにはならない。
スサノオが犯した天つ罪とは何か。吉本はそれが「畔放ち、溝埋み、樋放ち[田の用水路を壊すこと]、頻蒔(しきま)き[穀物の重ね蒔き]、串刺し、生け剥ぎ、逆剥ぎ、屎戸(くそへ[神聖な場所に汚物をまきちらすこと])」であったことを指摘する。
『古事記』にしたがえば、この部分は次のようになる(吉本訳による)。
〈(高天原での神儀裁判に負けて逆上したスサノオは、自分が勝ったのだと言い張り)勝ちにまかせてアマテラスの耕作田の畔をこわし、その溝を埋め、また神食をたべる家に屎(くそ)をし散らした。そんなことをしても、アマテラスは咎めずに申すには「屎のようなのは酔って吐き散らすとてわたしの兄弟がしたのでしょう。また田の畔をこわし溝を埋めたのは、耕地が惜しいとおもってわが兄弟がしたのでしょう」と善く解釈して言ったが、なおその悪い振まいはやまなかった。アマテラスが清祓用のハタ織場にいて神衣を織らせているときに、そのハタ屋の頂に穴をあけて、斑馬を逆剥ぎにして剥ぎおとしたので、ハタ織女がこれをみておどろき梭(ひ)に陰部をつきさして死んでしまった。それゆえそこでアマテラスは忌みおそれて天の石屋戸をあけてそのなかに隠れてしまった。そこで高天の原はことごとく暗くなり、地上の国も闇にとざされた。これによって永久の夜がつづいた。〉
おなじみの話だが、天つ罪が農耕や機織りなどにかかわる共同体の規範にたいする侵犯を指していたことがわかる。このことは、高天原が先進的な農耕共同体だったことを意味している。
スサノオの乱暴は、機織り女の死という重大な事件を招いた。農耕共同体の規範を破ったスサノオは、物損を弁償するだけでなく、ヒゲを抜かれ、手足の爪をはがされて、高天原から追放される。
だが、それだけではすまなかった。スサノオの罪は「原罪」のようなものとなって、スサノオの降りた出雲国にも覆いかぶさってくるのである。
ここで、天つ罪がのちに大和朝廷になる共同体の法だとするなら、この列島には、出雲に代表されるような大和勢力以外の土着勢力が存在していたはずだ、と吉本は考えている。
そして、前農耕的段階にある土着勢力もまた固有のプリミティブな法概念を有していた。それが「国つ罪」と称されるものである。
その国つ罪とは、生膚断ち[傷害]、死膚断ち[死体損壊]、白人[白斑あるいはハンセン病]、こくみ[こぶ、あるいはくる病]、おのが母犯せる罪、おのが子犯せる罪、母と子と犯せる罪、子と母と犯せる罪[以上4つは近親相姦罪]、畜(けもの)犯せる罪[獣姦罪]、昆(は)ふ虫の災[毒蛇やサソリなどの災難]、高つ神の災[落雷]、高つ鳥の災[猛禽類による災難]、畜仆(けものたお)し蠱物(まじもの)する罪[家畜を殺して、他人に呪いをかける罪]、などなどである。
こうしてみると、天つ罪よりも国つ罪のほうが、より原生的な罪であることがわかる。にもかかわらず、農耕にまつわる罪である天つ罪のほうが、自然的カテゴリーというべき国つ罪より上位にくるのは、なぜなのか。
吉本自身は、前農耕的な氏族制のなかから部族的な共同性(前国家)が形成されていくにつれ、「しだいに〈天つ罪〉のカテゴリーに属する農耕社会法を〈共同幻想〉として抽出するにいたったことは容易に推定することができる」と慎重な言い方をしている。ただし、農耕規範的な天つ罪が共同規範として押しだされ、それまでの国つ罪が共同体の掟や習俗として継承される過程には、単なる移行ではなく、不連続的な飛躍があったはずだとも述べている。不連続的な飛躍とは、征服を意味するはずである。
国家の成立にはかならず征服という契機がからんでいる。『古事記』でも、スサノオやヤマトタケルの英雄譚が、征服物語として展開されることは、だれもが知っているだろう。
もうひとつ吉本が注目するのは、清祓(きよめはらい)の行為である。
たとえば、黄泉の国から戻ってきたイザナギは筑紫の日向の原で、川にはいり、身を清めている。死(感染)のケガレをおとし、それによって生き返るのである(イザナギはこの清祓によって、アマテラス、ツクヨミ、スサノオの3子を得る)。
清祓は、対他的な関係から生じるケガレを、いわば罪と受け止め、それを洗い流そうとする宗教行為である。
疫病や異変は、何かの神のたたりと意識され、新たな神社の建立に結びつくことになる。
さらに時代がくだると、もともと清祓によって解消されるはずの罪が、法によって裁かれ、それによって一定の刑罰が科せられるようになる。
宗教から法が分離されるようになる。その分離には、公権力を有する国家の成立がからんでいるはずだ、と吉本は考えている。
国家の起源をさかのぼるのは難しい。
何千年も前の遠い先史時代にさかのぼるのはたしかだが、そのころの歴史資料や生活資料はごくかぎられている。
とはいえ、共同体が国家とよばれるようになる段階においては、「村落社会の〈共同幻想〉がどんな意味でも血縁的な共同性から独立にあらわれたもの」になっているはずだ、と吉本はいう。最初の国家が氏族社会段階ではなく、部族国家のかたちをとっていたのはまちがいないだろう。
3世紀末の『魏志倭人伝』には、この列島には100余りの国があり、そのうち30余りの国が大陸と交渉をもっていると記されている。
魏志にあらわれた倭の30国は、すくなくとも邪馬台国に従属していた、と吉本は指摘している。
邪馬台国を支配しているのは卑弥呼とよばれる女王であり、卑弥呼はシャーマン的な神権をもち、その弟が政治的な権力を掌握している。その支配部族は阿毎(アマ)姓を名乗っていた(アマ=天=海を連想させる)。
応神くらいまでの初期天皇の和名をみると、ヒコとミミ、ワケという呼び名が多い。そのうちヒコとミミは、魏志の倭30国の官名として記載されたものだ、と吉本はいう。ヒコやミミ、ワケが国の権力最高位を指す名称であり、初期天皇はそれらの名称を踏襲していたと思われる。
さらに吉本は『古事記』の応神記の記述から、「初期王権の本質は呪術宗教的な絶対権の世襲に権威があったとしかかんがえられず」、それは実際の統治とは別だったと論じている。
天皇位を継承することは「政治的権力の即自的な掌握ではなく、宗教的な権威の継承によって政治的権力を神話によって統御することを意味した」というわけだ。
こうした制度が変質するのは、7世紀はじめである。『隋書』には、倭王のシャーマン的な呪術性を漢帝が道理にかなっていないと批判し、それによって倭の制度が改められたことが記されているという(だが、ほんとうにそうだったかは疑わしい)。
隋書の記載は推古朝に関連しており、このころにはすでに安定した政治体制が確立しており、刑罰を含め、法の整備もなされていることがうかがわれる。
だが、倭国の様子を詳しく記述しているのは、むしろ3世紀の魏志のほうである。まだ邪馬台国の時代である。
このころ倭の地域では、法を犯した者は、軽いと妻子を没収され、重いと一族と親族を滅せられた。租調がとりたてられ、国々には市が立ち、それを監督する者がいたことも記されている。
吉本は、倭の30国が海辺に面した九州地方の国家だったろうと推測している。その漁夫たちは、水にもぐって魚や貝をとり、顔や体にいれずみをしていた。
倭の人びとは、大人(首長)にはひざまずいて敬意をあらわし、下戸(庶民)は道で大人で会うと、草むらにかくれるようにし、何かしゃべるときは、うずくまったり、膝をついたりしていた。
家屋内では、寝所は別々で、食事をするときには全員がひとつの部屋に集まった。婚姻については、大人はみな4、5人を妻としており、下戸でも2、3人妻がいる。奴碑もいたとされる。
こうした倭の国家群(国家連合)の構造を、吉本は次のようにえがく。
〈いくつかの既知の国家群があるとそのなかに中心的な国家があり、そこでは宗教的な権力と権威と強制力を具現した女王がいて、この女王の《兄弟》が政治的な実権を掌握している。その王権のもとに官制があり主要な大官とそれを補佐する官人がある。この上層官僚は《ヒコ》と《ミミ》とか《ワケ》とかよばれて国政を担当している。……中心的な国家は連合している国家群におそらくは補佐的な副大官を派遣して各国家群の大官あるいは国王にたいし補佐と監視をかねている。〉
ほとんど日本の近世にいたるまでの国家構造と変わらない。邪馬台国は日本の国家の原型をつくったといってよい。その王位の継承は、吉本によれば「宗教的あるいはシャーマン的な呪力の継承」という意味が強く、「政治的権力の掌握とは一応別個のものと考えられていた」。
おそらく邪馬台国の段階はすでに先進的なもので、国家の始原からすれば、長い年数をへている。にもかかわらず、邪馬台国が日本の国家の原型をつくったと吉本はみている。
『古事記』の伝承は、時間的にみれば『魏志』よりもはるか昔にさかのぼる射程をもっている。それでもアマ氏の始祖と目されるアマテラスが呪術宗教的な威力をもちつつ、土俗的な水耕稲作部族の始祖と目されるスサノオに地上の政治権力を委ねるという構図は、邪馬台国にも受け継がれており、天皇制の本質にもどこかつながっている、と吉本はいう。
論点はまだまだあるが、きりがないので、このあたりでやめておこう。
おもしろい。しかし、あらためて読みなおして思うのは、なぜ1968年に出版されたこの本が、当時、大学生のあいだで猛烈に読まれたのか、いまとなっては首をひねるほかないということである。
たぶん、あのころ、ぼくらは国家とぶつかっていたのだろう。そして、国家の解体学をめざしていた吉本に共感し、よくわからぬなりに『共同幻想論』を読んだのにちがいない。
国家の解体には国家の消滅という意味合いが含まれていたのかもしれないが、かならずしもそうではない。『解体新書』というネーミングを踏襲すれば、それは国家の解剖学を意味していたはずである。
国家はあやしい。何をしでかすかわからない。とりわけ社会主義国家なるものは、いちばんあやしい。その国家のばらまく共同幻想にたいし、われわれは自覚的でなければならない。
とはいえ、われわれは共同幻想をまぬかれない。共同幻想のなかを生きているのだ。だから、せめてそのことを自覚し、遠くをみつめて、日々を歩むほかない。
あのころ、ぼくらは現存する国家を超える思想を吉本に求めていたのかもしれない。吉本に答えはなかった。その答えはそれぞれ各自がみつけださなければならなかった。
吉本隆明『共同幻想論』をめぐって(5) [われらの時代]
[8月6日、遠野伝承園にて]
国家の成立までを追う探求がつづいている。その探求は自己とその経験から出発し、文学的で詩的なスタイルをとっているので、一見、理解しづらく、脈絡がつながらないようにもみえる。しかし、よくよくみれば、日本における国家の成立を追求しつづける吉本の姿勢は一貫している。
きょう読んでみる「母制論」も「対幻想論」も、ざっと眺めると、なんのことかさっぱりわからないという印象をもたれるかもしれない。ふたつのテーマは、家族論というジャンルでくくることができる。問題は、家族と国家の次元が頭のなかで、すぐに結びつかないことである。
それはさておき、いまは国家成立以前の状況に思いをはせてみよう。族長に率いられた氏族社会を思いえがけばよいのかもしれない。おそらく、そこで日々営まれているのは、氏族=家族集団の集合活動である。その活動のなかから、部族が生まれ、国家が登場するという流れを考えるなら、国家誕生の過程には、家族の問題、吉本のことばでいえば「対幻想」が大きくかかわっていることが想定できる。
「母制論」と「対幻想論」は、『古事記』を主な素材としながら、国家の登場するまでのあわいとでもいうべき期間を扱っているとみてよいだろう。
ここで吉本はまずエンゲルスの『家族、私有財産及び国家の起源』でえがかれた原始時代の家族像を否定するところから出発している。
エンゲルスは、モーガンの『古代社会』にヒントを得て、原始時代には、内に向けて閉じられた家族などというものはなく、人びとは集団婚のもとに暮らしていたと考えていた。エンゲルスによれば、集団婚とは「男の全集団と女の全集団がたがいに所有しあい、ほとんど嫉妬の余地を残していない形態」のことである。
しかし、吉本は男と女は(あるいは同性どうしでも)、好き嫌いや嫉妬にかられる存在であり、そこからしてもフリーセックスの願望を投影した集団婚の実在性は疑わしいと述べる。
エンゲルスはさらに集団婚から母系制(母権制)を導きだそうとした。集団婚では、ある子どもの父はだれかわからないが、母はだれかがわかる。だから、子の血統は母方によってしか証明できず、そのため共同体内における母の力が強くなるというわけである。
だが、吉本はこんなばかな話はないという。母親ならば、たいてい子どもの父親がだれかはわかるはずであり、母権制を集団婚から導こうという発想は根本的にまちがっているという。「〈母系〉制の基盤はけっして原始集団婚にもとめられないし、だいいち原始集団婚の存在ということがきわめてあやふやである」
吉本は未開社会において、母系制(母権制)が存在したであろうことをむげに否定してはいない。
とはいえ、純粋な一対の男女がそのまま共同体の主導権を握ることは考えられない。
〈いうまでもなく、家族の《対なる幻想》が部落の《共同幻想》に同致するためには、《対なる幻想》の意識が《空間》的に拡大しなければならない。このばあい、《空間》的な拡大にたえるのは、けっして《夫婦》ではないだろう。夫婦としての一対の男・女はかならず《空間》的には縮小する志向性をもっている。それはできるならばまったく外界の共同性から窺いしれないところに分離しようとする傾向をもっている。〉
共同体内で対幻想が拡大して、共同幻想に同致するのはどういう場合だろう。その典型として、吉本は『古事記』にえがかれている姉アマテラスと弟スサノオの関係を取りあげる。
アマテラスもスサノオもイザナギの子であり、父からアマテラスは高天原を、スサノオは海原を統治するよう命じられる。しかし、海原の統治を嫌がり、亡き母の国に行きたいと泣き叫ぶスサノオは、イザナギの怒りを買って追放されてしまう。
そしてスサノオはアマテラスのところに向かうのだが、弟が国を奪いにきたと思ったアマテラスは川(天の安河)のほとりで武装して待ち構え、かれを高天原に入れようとしない。
そこで、邪心のないことを証明するために、スサノオは「うけひ(神儀裁判)」をしようと提案し、それぞれ子を産んで、それが女だったら「きたない心」、男だったら「清らな心」をもっていると判定しようという。しかし、スサノオから生まれたのは3人の女、アマテラスから生まれたのは5人の男だったので、逆上したスサノオは高天原で乱暴狼藉をはたらくことになる。
ご存じのように話はこれからまだつづくのだが、とりあえずここで打ち切っておこう。問題はこの神話が何を意味しているかである。
アマテラスとスサノオのあいだに姉弟の相姦関係があるわけではない。ふたりは、ともに子をつくりだす力をもつ神であって(男が子を産むのはへんかもしれないが)、相姦関係がないから、それぞれ子を産むのである。
にもかかわらず、アマテラスとスサノオは同じイザナギの子として対幻想関係にある。幻想的な子産みは、それ自体政治的決定につながる祭儀行為にほかならない。ここでは、あきらかにアマテラスがスサノオの上位にあり、そのかぎりでは母権制の存在がほのめかされているとみることもできる。
吉本は、沖縄の久高島で、島の女性たちとその兄弟だけでとりおこなわれるイザイホウの神事を例に挙げて、ここでも「水田稲作が定着する以前の時代の〈共同幻想〉と〈対幻想〉との同致する〈母系〉制社会の遺制を想定することはできる」としている。
氏族社会において重要なことは、兄弟・姉妹どうしの性交が、共同規範として禁止されていることだ。それでも同一家族の兄弟・姉妹間には性行為をともなわない対幻想が持続する。
それだけではない。原始的な氏族社会では、共同体において姉妹が宗権を掌握したときには、兄弟が政権をになうというシャーマン的な統治形態が成立しうるのである。
吉本はさらに対幻想についての考察を推し進める。
氏族はいかにして生まれるのか。
フロイトは「原始群族の父祖」という概念を最初に設け、息子たちがその父祖を殺すところから話をはじめている。だが、父祖を倒したあとも共同体内の争いは絶えなかった。そこで、息子たちは父祖になることをあきらめ、禁制の象徴として、トーテムを立てることにし、そのもとで、それぞれ家族をつくるようにしたというのである。これはエンゲルスとは根本的にことなる発想だ。
このフロイトの発想を受けて、吉本はいう。
〈《対なる幻想》を《共同なる幻想》に同致しうる人物を血縁から疎外したとき《家族》は発生した。そしてこの疎外された人物は宗教的な権力を集団全体にふるうものであることも、集団のある場面でふるうものであることもできた。それゆえ《家族》の本質はただそれが《対なる幻想》であるということだけである。そこで父権が優位であるか母権が優位であるかはどちらでもいいことである。また、《対なる幻想》はそれ自体の構造をもっており、ひとたびその構造の内部に踏みこんでいけば、集団の共同的な体制と独立であるということもできる。〉
これをみると、吉本がいかに個人とともに家族に大きな思想的根拠を与えているかがわかる。自己幻想と対幻想は心的には、共同幻想に対抗しうる領域であり、いかなる共同幻想も最終的に個人や家族を侵すことはできないのだ。
もちろん、家族の形態にも歴史があって、それを一律に近代的家族として扱うわけにはいかないだろう。それでも、氏族社会において、族長という存在が分離され、族長に共同幻想の核を集中させることで、はじめて家族が発生し、男と女の対幻想のなかから、しだいに個としての自己幻想が登場してくるというとらえ方は、みごとというほかない。
こうして家族は歴史を通じて、普遍的な人間関係となった。
エンゲルスの家族論はけっきょくのところ家族の否定と解体という共産主義的理念にもとづいている。家族は解体され、男と女の一時的関係に還元され、男と女はひたすら共同体の要請にしたがって行動するものとされる。しかし、人類はかつてそのような時代を経験したとも思えないし、将来そのような時代を経験するとも信じられない、と吉本はいう。
ここで吉本は、共同幻想と対幻想が同致しているとみられる、イザナギとイザナミによる国生み神話をとりあげる。
イザナギとイザナミは性的な関係をもち、子を産むが、それが八つの島になるというのが国生み神話である。生まれた子どもが八つの島になるのだから、たしかにここでは共同幻想と対幻想が同致しているようにみえる。
これが国に八つの島が存在していることが認識されたあとにつくられた農耕時代以降の神話であることはまちがいない。子を産むことが、穀物の実りの豊穣と結びついていることからみても、それはあきらかだろう。
だが、この同致は、産めよ殖やせよのもとに意図的につくりだされた共同幻想の浸透によるものなのである。農耕を中心とする部族国家が生まれたこの段階で、共同幻想と対幻想はじっさいには分離されていたとみるべきだ、と吉本は考えている。
それをもたらしたのは時間意識である。当初、穀物が実る時間と女性に子ができる時間は同じであるかのようにみられ、そこから穀母神的な観念が生まれた。だが、共同幻想と対幻想の一致はすぐに崩れる。
なぜなら穀物の栽培と収穫が年ごとになされるのにたいし、子どもの成育には少なくとも十数年の年月がかかるからである。その時間性のちがいが、共同幻想と対幻想のちがいを意識させることになった、と吉本はいう。
〈もちろん、この段階でも穀物の栽培と収穫を、男・女の《性的》な行為とむすびつける観念は消失したはずがない。しかし、すでに両者のあいだには時間性の相違が自覚されているために共同幻想と《対》幻想とを同一視する観念は矛盾にさらされ、それを人間は農耕祭儀として疎外するほかに矛盾を解消する方途はなくなったのである。農耕祭儀がかならず《性》的な行為の象徴をそのなかに含みながらも、ついに祭儀としての人間の現実的な《対》幻想から疎遠になっていったのはそのためである。〉
農耕祭儀を媒介としながら、国家と家族は分離する端緒に立った。しかし、氏族社会が部族国家に転移するには、別の契機が必要だった。
そのことを、次回最終回でみていくことにしよう。
吉本隆明『共同幻想論』をめぐって(4) [われらの時代]
[8月6日、遠野伝承園にて]
狐を媒介にして、共同幻想に同調し、人の運勢や収穫のよしあしを占う「いずな使い」に比べ、巫女(ふじょ、みこ)がいちだん高いレベルにあるとみられるのはなぜか。
吉本はこんなふうに語っている。
〈わたしのかんがえでは《巫女》は共同幻想を自己の対なる幻想の対象となしうるものを意味している。いいかえれば村落の共同幻想が《巫女》にとっては《性》的な対象なのだ。巫女における《性》行為の対象は、共同幻想の凝集された対象物である。〉
例によって、むずかしい言い方だが、巫女が女性でなければならないことはまちがいない。
そして、女性が巫女になりうるのは、吉本によれば、女性の本質にもとづいている。そもそも女性とは「〈性〉的対象を自己幻想にえらぶか、共同幻想にえらぶ」存在なのだ。
この定義があたっているかどうかはわからない。女性には、共同幻想を性的に引き寄せる力が、もともと備わっていると理解しておこう。女性は狐などを媒体としなくても、みずからのからだによって共同幻想と一体化しうるのだ。
その共同幻想は、一般に神と呼ばれる目に見えぬ力である。村里では、その神は何も神社に祭られている祭神とはかぎらない。池に住む蛇や森の熊、樹齢何百年もの樹木、遠い先祖や亡き父母、夭折した子どもも、また神にちがいなかった。
巫女はこうした共同幻想と一体化して、人びとに災厄の予兆や病気の原因を告げ、ことの吉凶を占い、戦いの勝利を祈る存在だった。
共同体のまつりごとに、巫女は欠かせなかった。何せ、巫女は神と直接結びついているからである。
だが、女性ならばだれでもが巫女になれたわけではない。神が乗り移るには、特別の訓練なり集中なりを要しただろう。
上代の巫女には、共同体の祭司という大きな役割が与えられていた。だが、時代が下るにつれて、巫女は神社に所属する者(未婚の女性)と、民間の「口寄せ」(イタコ)へと分化していくことになる。
口寄せになるのは、盲目の女性が多かった。
岩手県の遠野では、祭の日になると、家にイタコがやってきて、神棚や床の間に飾ってあるオシラサマ(農業と養蚕の神さま)を遊ばせたという。『遠野物語』では、オシラサマについて、イタコがこんなふうに語っている(口語訳)。
〈昔あるところに貧しい百姓がおり、妻はなくて美しい娘がいた。馬を一頭かっていたが娘は馬を愛して夫婦になった。ある夜これを知った父親は娘に知らせず馬をつれだして桑の木につりさげて殺した。娘はこれを知り悲しんで死んだ馬の首にすがって泣いた。父親はこれをにくんで馬の首を斧できり落したが、たちまち娘はその首に乗ったまま天に昇り去った。〉
これがオシラサマ伝説の由来である。オシラサマは30センチほどの桑の棒の先に馬と娘の顔を刻んだ対の姿をしており、それにきれいな布が着せられている。
[8月6日、遠野ふるさと村にて]
巫女は、悲劇のうちに他界に去った夫婦神を、祭の日に地上に戻し、家族といっしょに楽しんでもらう仲立ちをするわけである。
ここで『共同幻想論』は、「巫女論」から「他界論」へと移る。
一見つながりがなさそうだが、無論、巫女と他界には大きな関係がある。
他界とは彼岸、あの世のことである。
リアルに他界を見ることはできない。他界とは彼岸に想定される共同幻想のことである。他界をイメージするには、死の関門を通らなければいけない、と吉本は書いている。
だれもが生理的に死を体験する。しかし、死の問題がむずかしいのは、それを自身が心で体験することはできず(というより体験したときにはすでに死んでおり)、他者の生理的な死についても、それをそばで見つめることくらいしかできないことである。
そのため、死は心的体験としては、想像の領域でしかとらえることができない。死のイメージは、共同幻想の領域からやってくるほかない。吉本によれば、死とは「人間の自己幻想(または対幻想)が極限のかたちで共同幻想に〈侵蝕〉された状態」のことと理解される。
死は人を此岸の共同幻想から彼岸の共同幻想、言い換えれば他界に追いやることになる。
こうした他界は時間性だけではなく空間性をもっている。日本の伝説では、亡くなった人が神となって集まっている場所こそが他界として想定されていた。そして、この世から他界への道行きが、さまざまな幽霊話として伝わるいっぽうで、時に現実の場所としてつくられることにもなる。
デンデラ野とかダンノハナと呼ばれる場所である。
『遠野物語』の記述を挙げておこう(口語訳)。
〈遠野の近隣には幾つか、おなじダンノハナという地名がある。その近傍にはこれと相対してかならず蓮台野[デンデラ野と同じ]という地がある。昔は六十をこえた老人はすべてこの蓮台野に追いやる風習があった。捨てられた老人は徒(いたずら)に死んでしまうこともならず、日中は里へおりて農作して口を糊した。そのためにいまもその近隣では朝に野らにでるのをハカダチといい、夕方野らからかえるのをハカアガリと云っている。〉
ダンノハナは村境の墓地であり、その向こうに広がるデンデラ野は、いわば現世の他界である。正確には他界への入り口といってもよいだろう。家の役にたたなくなった老人は、このデンデラ野においやられた。ちょっと悲しい話だが、現実は今も昔もさほど変わらないといえるだろう。
民衆にとって他界はそう遠い場所ではなかった。死者は他界に行って、神となり、村落と田を守った。墓地に刻まれた墓標には、すでに他界に行ってしまった死者たちとのつながりを示す名前と時間が示されていた。
つぎの「祭儀論」は、神となった祖先たちが、他界からこの世に戻ってくる話である。
祭儀は民俗的な幻想行為である。祭儀がとりもつのは死と生の循環であり、他界とこの世との行き来である。
『古事記』では、死と生はさほど隔たったものとして描かれていない、と吉本はいう。イザナミはイザナギを追って死者の国に行くし、スサノオに殺されたオオケヅ姫からは蚕や稲、栗、小豆、麦、大豆が生まれる。
民間の農耕儀礼には、田の神を迎える行事があった。田に降りる田の神は家の神でもあり、祖神でもあった。
吉本が紹介する能登の事例では、田の神は12月5日に家に迎えられ、さまざまな饗応と儀礼(田神迎え、アエノコト、若木迎え、田打ち、田神送りなど)をへて、2月10日の田神送りの翌日から田に降りることになっている。
そして、この農耕祭儀こそが、天皇の世襲を正統化する大嘗祭の原型だというのが、ここでのポイントである。
吉本はこう書いている。
〈天皇の世襲大嘗祭では、民俗的な農耕祭儀の《田神迎え》である12月5日と《田神送り》である2月10日とのあいだの祭儀時間は、共時的に圧縮されて、一夜のうちに行われる悠紀[ゆき]殿と主基[すき]殿におけるおなじ祭儀の繰返しに転化される。かれは薄べりひとつへだてた悠紀殿と主基殿を出入りするだけで農耕民の《家》と所有(あるいは耕作)田のあいだの祭儀空間を抽象的に往来し、同時に《田神迎え》と《田神送り》のあいだの二カ月ほどの祭儀空間を数時間に圧縮するのである。〉
大嘗祭において、「田の神」祭儀は抽象化され、司祭である天皇は二重化されて、ここで神へと転ずることになる。
まず、天皇は悠紀殿と主基殿にもうけられた神座にやってきた神と差し向かいで食事をする。さらに、
〈悠紀、主基殿の内部には寝具がしかれており、かけ布団と、さか枕がもうけられている。おそらくこれは《性》行為の模擬的な表象であるとともになにものかの《死》となにものかの《生誕》を象徴するものといえる。〉
吉本は、ここで新天皇は、祖神との模擬的な性行為を通じて、対幻想を最高の共同幻想と同致させ、みずからを神として再生させるのだと考えている。そして、神となった天皇は絶対的な規範力(精神的支配力)を有するようになるとされるのだ。
大嘗祭の目的は、新天皇が祖神の霊を受け継ぎ、生神として再生するという共同幻想を演出することにあったといえるだろう。
こうして、われわれはようやく天皇の誕生する場に立ち会うことになる。
吉本はこう言う。
〈共同幻想が原始宗教的な仮象であらわれようと、現在のように制度的あるいはイデオロギー的な仮象をもってあらわれようと、共同幻想の《彼岸》に描かれる共同幻想がすべて消滅しなければならぬという課題は、共同幻想自体が消滅しなければならぬという課題とともに、現在でも依然として、人間の存在にとってラジカルな本質的課題である。〉
当時は、かっこいいなと思ったものである。



