革命と戦争──ホブズボーム『帝国の時代』を読む(6) [商品世界論ノート]

先進資本主義国だけを見れば、19世紀末は政治的な安定期だった。経済的にも繁栄と拡大が保たれていた。だが、世界全体をみると、このころ、周辺部では革命の嵐が吹き荒れており、その嵐はやがて中央部におよぶことになる。
そんな地域としてあげられるのが、オスマン帝国、ロシア帝国、ハプスブルク帝国、中国、イラン(ペルシャ)、メキシコなどである。ブルジョワの世紀にあって、これらの地域の古風な政治構造はぐらついていた。
清朝は弱体化し、帝国主義勢力の猛攻撃により、その体制は風前の灯となっていた。満州に進出したロシアを撃退した日本は、すでに獲得した台湾に加えて、さらに多くのものを得ようとしていた。イギリスは香港と上海に拠点を置き、チベットを事実上分離した。フランスはインドシナを植民地とし、ポルトガルはマカオを保全している。ドイツも中国に食らいついている。アメリカは中国に門戸開放を迫っていた。
中国では宮廷の支配層と秘密結社、南部のブルジョワ勢力がしのぎをけずっていた。宮廷内の改革は失敗し、清朝は1911年に南部と中央部の反乱によって崩壊する。しかし、それに取って代わったのは、不安定な軍閥勢力で、その後約40年にわたり、中国に安定した国家体制が築かれることはなかった。
オスマン帝国もまた崩壊への道をたどっていた。その領土は西洋の列強によって蚕食されている。バルカン半島では民族独立の勢いが強まり、北アフリカや中東の一部もイギリスやフランスの手にわたった。
「事実、1914年には、すでにトルコはヨーロッパからほぼ完全に姿を消し、アフリカからも全面的に締め出され、中東においてのみ脆弱な帝国をなんとか保持していたものの、[第1次]世界大戦後まで生き延びられなかった」
しかし、トルコには民族的な核というべきイスラム住民の巨大なブロックが残っていた。それを核としてトルコの愛国主義をかきたてたのが、いわゆる「青年トルコ党」である。
青年トルコ党による1908年のトルコ革命は、事実上、失敗に終わる。当初、掲げられた自由主義的、議会制的な枠組みは、軍事的、独裁的な体制、トルコ的なナショナリズムへと変じていった。そして、オスマン帝国がドイツへの傾斜を強めていったことが、第1次世界大戦での致命的な敗北を招くことになる。
その後トルコでは、ケマル・アタチュルクのもと、近代化が推し進められる。とはいえ「トルコ革命の──特に経済における──弱点は、革命を膨大なトルコ農村大衆に強制する力がなかったこと、あるいは農村社会の構造を変えられなかったことにあった」とホブズボームは指摘する。
揺れ動いていたのはイラン(ペルシャ)も同じだった。イランでは1906年に憲法が発布され、国民議会が成立する。イギリスとロシアはイランの分割を画策したが、イランの君主制は残った。そして、第1次世界大戦後には、その軍司令官が最後の王朝となるパーレヴィ朝(1921〜79)を開くことになる。
1910年にはメキシコでも革命がはじまった。世界ではほとんど注目されなかった革命だが、それは従属的世界でおこった労働者大衆による最初の革命だった、とホブズボームはいう。だが、革命後のメキシコの輪郭は1930年代末まで明らかになることはない。
イギリスの植民地では、白人の植民地を除いて、イギリスの支配に抵抗する動きがはじまっていた。エジプトもそうだが、とくに深刻なのはインドだった。
19世紀末には、ツァーリの支配するロシア帝国は、あきらかに時代遅れで、革命は不可避とみられていた。問題はそれがどのような革命になるかだった。
クリミア戦争(1854〜56)はロシアの脆弱さを白日のもとにさらした。1861年に農奴制は廃止されたが、農業は近代化されなかった。貧困、土地収奪、高い税金、低い穀物価格によって、ほぼ1億人にのぼる農民の不安は高まっていた。
ナロードニキは、小農民の村落自治体が社会主義への基盤になると考えた。これにたいし、ロシアのマルクス主義者は、それは不可能で、むしろ労働者に基盤をおくべきだと主張した。
1890年から1904年にかけ、ロシアでは鉄道の敷設が進み、石炭や鉄、鋼の産出高が一挙に増えていく。それにともない、産業プロレタリアートも成長していた。帝国西部のポーランド、ウクライナ、アゼルバイジャンの発展も著しかった。民族的、階級的な緊張が高まっていく。
ツァー打倒の動きが生じる。テロリズムは帝政の弱体化にはあまりつながらない。1900年代になって、旧ナロードニキは「社会革命党」という左翼農村政党を結成する。いっぽう、レーニンはロシア社会主義労働党のなかにボルシェヴィキと呼ばれるグループをつくった。
ツァーリ政権のもと、大衆の反ユダヤ主義が加速し、ユダヤ人はますます差別され虐待されるようになっていた。そのため、かれらは革命運動に引き寄せられていった。
1900年以降は社会不安が急速に高まっていく。しばらく落ち着いていた小農民の暴動が頻発し、ロストフやオデッサ、バクーの労働者はゼネストを組織した。
社会不安が増大するなか、ロシア政府は拡大政策に乗りだし、勢いを増す日本と衝突、屈辱的な敗北を味わう。1905年1月には革命が勃発する。ツァーリは革命のうねりを受け、日本との和平交渉を急いだ。
1905年の革命により、サンクトペテルブルクでは評議会(ソヴィエト)が一時的な権力機関として機能した。だが農民の反乱や労働者のストライキは次第に押さえこまれていく。1907年に革命は沈静化した。
ツァーリの体制が改革されることはない。
ホブズボームはこう書いている。
〈明らかなことは、1905年革命の敗北が、ツァーリズムに代わる潜在的に「ブルジョワ」的な代替物を生み出さなかったし、6年以上の小康期間をツァーリズムに与えもしなかったということだ。1912─14年まで、ロシアは明らかに社会的騒擾で再び騒然となっていた。革命的状況が再び近づきつつあるとレーニンは確信した。〉
ヨーロッパで全面戦争が勃発するとは、だれも予期していなかった。1914年7月のサラエヴォ事件が、まさか世界戦争に火をつけるとは想像もしていなかったのだ。
〈1914年7月の国際的危機の最後の絶望的な日々にあってさえ、政治家たちは、取り返しのつかない行動をとりながらも、自分たちが世界戦争を始動させているとは本当には考えていなかった。きっと何らかの方式が、過去にもたびたびそうだったように見いだされるはずだと考えられていた。反戦派の人々も、長年予言してきた破局が今、自分に降りかかっているとはやはり信じられなかった。〉
1871年から1914年にかけ、ヨーロッパでは、戦争はゲームの世界で、ほとんど現実の世界ではなかったはずだった。徴兵制は通過儀礼にすぎなかったし、一般市民にとって軍隊とは軍楽隊であり、パレードだと思われていた。
散発的な戦争がなかったわけではないし、国内の鎮圧行動もあることはあった。植民地では多くの兵士が軍事行動ではなく疫病で亡くなっていた。この時期、イギリスでは南ア戦争を除けば、陸海軍兵士の生活はごく平和なものだった、とホブズボームはいう。
武器の開発は進んでいた。各国が他国に遅れをとらないよう相互に競争していたためである。軍事支出もはねあがっていた。軍需産業も盛んで、エンゲルスが「戦争が巨大企業の一部門になった」と書いているほどである。
ホブズボームにいわせれば「政府は、軍需工業に対して、平和時に必要とする量をはるかに超える生産力を保持させるよう配慮しなければならなかった」。
それでも、世界戦争は兵器製造者の陰謀によって引き起こされたわけではなかった。軍備の蓄積が事態を一触即発のものにしていたのはたしかかもしれない。しかし、ヨーロッパで戦争が勃発したのは、列強を戦争に駆り立てた国際情勢にあったことはまちがいない。
第1次世界大戦はなぜおこったのだろうか。引き金となったのは、バルカンの辺鄙な地方都市で、一学生テロリストによってオーストリアの皇太子が暗殺されたことである。だが、その時点では、どの国もヨーロッパの全面戦争など望んではいなかった。
1870年の普仏戦争以来、ドイツとフランスは敵対していた。またドイツがオーストリア=ハンガリーと恒久的な同盟を結んでいたのも事実である。加えてイタリアとも同盟が結ばれ、「三国同盟」となった。
オーストリアはボスニア・ヘルツェゴビナを併合することで、バルカン地域の紛争に巻きこまれ、ロシアと対峙するようになっていた。そのロシアがフランスと同調するのは必然の流れだった。
そうしたことが国際関係の緊張を高めていたことはまちがいない。だからといって、全面的なヨーロッパ戦争が不可避だったわけではない。「フランスはオーストリアと、またロシアもドイツと本気で反目していたわけではなかった」。
しかし、この同盟システムが時限爆弾をかかえるようになったのは、1903年から1907年にかけて、イギリスが反ドイツ陣営に加担することを決めてからである。それにより、いわゆる「三国協商」が成立した。
それまでイギリスはドイツと敵対していなかった。むしろ、アフリカや中央アジアで、フランスやロシアと敵対してきた。それがなぜドイツとの敵対に転じたのだろう。
ホブズボームはその原因を(1)国際的パワーゲームの世界化にともないロシアやフランスの脅威が薄れたこと[普仏戦争ではフランス、日露戦争ではロシアが敗れていた]、(2)イギリスにたいするドイツ経済の驚異的追い上げにみている。
ドイツの急激な産業発展がイギリスに大きな影を投げかけていた。大英帝国はもはや経済世界の中心ではなくなろうとしていた。
〈たとえ世界の金融取引および商業取引が依然として、いや事実ますます、ロンドンを通じて行なわれていたとしても、イギリスは明らかにもはや「世界の工場」ではなかったし、実際その主要な輸入市場でもなくなっていた。逆にその相対的衰退は歴然としていた。〉
オスマン帝国内にドイツが浸透していることもイギリスにとっては懸念材料だった。とはいえ、イギリスとて海外の権益取得をためらっているわけではなかった。アフリカでは、フランスと取引し、イギリスがエジプトに独占的権益をもつ代わりに、フランスにモロッコをまかせるというような取り決めもしていた。
ドイツはたしかに強大になりつつあったが、世界の覇者として具体的にイギリスに取って代わろうとしていたわけではない。だが、ドイツが1897年以降、大艦隊の建設にとりかかったことが、世界の海軍大国であるイギリスに脅威を与えていた。ドイツ艦隊の基地はすべて対岸の北海におかれている。その目的はイギリス海軍との交戦以外にありえなかった。
〈このような状況下で、また両国産業の経済的敵対関係も加わるとなれば、イギリスがドイツを仮想敵国の中で最も敵対する可能性の高い、また最も危険な国とみなしても不思議はなかった。イギリスがフランスに接近し、またロシアの危険性が日本によって最小化されるやいなや、ロシアにも近づいたのは理の当然だった〉
ドイツが工業的にずば抜けた存在であるだけでなく優勢な軍事強国になったことがイギリスに脅威を感じさせていた。思いもかけぬ英仏露三国協商が結ばれたのには、そんな背景がある。
こうして、ヨーロッパは三国同盟と三国協商のブロックに分割される。そのブロックを背景に、各国は1905年以降、瀬戸際政策に走った。モロッコをめぐる危機、オーストリアによるボスニア・ヘルツェゴビナの併合、イタリアによるリビア占領、バルカン戦争、そして1914年6月28日にサラエヴォ事件が発生する。
サラエヴォ事件は、ほんらいオーストリア政治の一偶発事件にすぎなかった。それなのになぜ事件から5週間もたたないうちにヨーロッパは戦争に突入していったのか。
事態の推移ははっきりしている。ドイツがオーストリアを全面支援して戦争に加わったことが、いやおうもなくその後の決定(ロシア、フランス、イギリスの参戦)につながったのだ。
ロシアは1905年以降の国内危機を大ロシア民族主義によって乗り越えようとしていた。ドイツの民主主義勢力は軍国主義を抑えることができなかった。オーストリア=ハンガリーの政治は国内の民族問題でもめにもめ、崩壊寸前だった。
「最悪だったのは、解決困難な国内問題に直面した国々が、国外での軍事的勝利によってその解決を図るという賭けの誘惑に乗ったことではないだろうか」
ホブズボームは国際的危機と国内的危機が1914年直前の数年間に融合していたことが、予期せぬ戦争を招いたとみている。
いったんはじまった戦争は容易には終わらなかった。反戦運動は取るに足りないものだった。
「雷雨と同様に戦争は重苦しい期待の閉塞感を打ち破り空気を浄化した」。その結果、戦争で2000万人の死傷者が出た。
平和の時代、自信に満ちたブルジョワ文明、増大しつづけた富、西欧の諸帝国の時代は、不可避的に戦争、革命、危機の萌芽を含んでいたのだ、とホブズボームは書いている。
21世紀にいたっても、革命と戦争の時代はまだ幕を下ろしていない。
理性と不安──ホブズボーム『帝国の時代』を読む(5) [商品世界論ノート]

この時代(1875〜1914)、芸術や科学、学問の分野では何がおこっていたのだろう。
ブルジョワ社会は揺らぎ、大衆社会が生まれはじめている。それにともない、芸術も変容するが、状況は混沌としている。
音楽では18世紀、19世紀のクラシックと並んで、マーラーやシュトラウス、ドビュッシーが登場し、グランド・オペラが流行し、ロシア・バレエがもてはやされる。いっぽう、オペレッタや身近な歌曲も人気を博するようになった。
文学ではトマス・ハーディ、トーマス・マン、あるいはマルセル・プルーストの名声が高まる。イプセンやチェーホフは演劇の新境地を開いた。
芸術が隆盛していたことはまちがいない、とホブズボームはいう。それは豊かになった都市中産階級と識字能力をもつ大衆によって下支えされていた。「この時期に、創造的芸術家として生計を立てようとした人々が増えたことは否定できない」
日刊紙や定期刊行物も増え、広告産業が出現し、ポスターという視覚芸術が生まれ、工芸家がデザインした消費財がよく売れるようになった。それは国際的な影響力をもち、各地に飛び火して、新たな芸術を生みだしていく。
大衆のための建築も花開いた。ロンドン、ミラノ、モスクワ、ボンベイ(ムンバイ)その他数限りない駅舎、パリのエッフェル塔やニューヨークの摩天楼、劇場、美術館、博物館のような公共施設、そして、かずかずの記念碑、これらはすべて大衆に開かれたものだ。
にもかかわらず、この時代は「世紀末」と「デカダン」ということばに彩られている、とホブズボームはいう。オペラにしても従来のありきたりのものとは異なるもの(たとえばビゼーの「カルメン」やシュトラウスの「サロメ」)が求められ、自然主義の作家(ゾラなど)が登場し、ゴッホやムンクがリアリズムの枠を越えた絵をかくようになり、アール・ヌーヴォーが隆盛し、郊外住宅や田園都市へのあこがれが広がっていく。
しかし、文化的なエリート主義と大衆主義、刷新への願望と中産階級のペシミズムとのあいだには常に緊張がある。
アヴァン・ギャルド(前衛芸術)は、この時代にも存在した。アヴァン・ギャルド芸術家は伝統主義者と世紀末モダニストを一様に非難し、大衆が望みもせずついても行けない方向に突き進んでいった。しかし、かれらは孤立していたわけではなく、中産階級文化の一郭をなしていた、とホブズボームはいう。
〈新しい革命家たちが帰属していたのは、同じ仲間同士、適当な街区のカフェにたむろする反体制の若者の議論好きなグループ、批評家たちと新しい「イズム」(キュービズム、未来主義、渦巻き主義)のための宣言書の起草者、小雑誌、新しい芸術作品やその創作家への鋭い眼識や嗜好を持つ若干の興行主や収集家たち……だった。〉
しかし、そうしたアヴァン・ギャルド派をよそに、社会の民主化を背景として、一種の大衆芸術が世界制覇に乗りだそうとしていた。
酒場やダンスホール、キャバレーでは、新たな音楽やダンスが登場した。発行部数100万部以上に達する大衆紙も生まれた。映画はそれまでにない画期的な芸術で、そこからはまもなくチャップリンのようなスターがでてくる。それがトーキーとなるのは1920年代にはいってからだ。
〈大衆が映画の中で目にし、愛好したものは、まさに、かつてプロの演芸が聴衆をびっくりさせ、昂奮させ、楽しませ、感動させていた限りのすべてのものだった。〉
帝国の時代は、科学に転換がもたらされた時代でもあった。
その科学革命は科学と直感がそのまま結びつくのではなく、むしろ分離する過程をたどった、とホブズボームはいう。
ひとつは数学的思考の進歩である。「数学の基礎は、いかなる直感への訴えも厳格に排除することによって再定式化された」
それでも、数学と現実世界との関係を否定することは不可能だった。
物理学のガリレオ的ないしニュートン的宇宙は危機に見舞われ、アインシュタインの相対性理論に置きかわろうとしている。
だが、「科学はそれ以後、ほとんどの人々に理解できないものになった。それへの依存がますます認識されるようになる一方で、多くの人々が認知しない何ものかになったのだ」。
古い物理学の秩序が崩壊していくなかから、電磁気学が発展し、新種の放射線が発見された。物理学のパラダイムが転換される。マックス・プランクは新たな量子理論を打ち立てた。
細菌学と免疫学はまさに帝国主義の産物である。植民地での白人の活動を妨げていたマラリアや黄熱病などの熱帯病は克服されなければならなかった。梅毒の研究も進展した。
ただ、医学などの分野を除いて、科学の基礎研究は応用に生かされてはいなかった。それが可能になるには、工業経済の技術的発展を待たなければならない。
いっぽう進化の概念はイデオロギー的な色彩を帯びて、社会ダーウィニズムをもたらし、超人の思想と優生学を生んでいた。社会民主主義者もダーウィニズムに熱狂していた。
1900年以降は遺伝学が発達した。遺伝学はダーウィニズムに突然変異の概念をもたらす。
知の世界の変動は外部世界の変動と直接関係しているわけではない。しかし、歴史家はプランクの量子仮説、メンデルの再発見、フッサールの『論理学研究』、フロイトの『夢判断』、セザンヌの『玉葱のある静物』が同じ1900年の日付をもつことに衝撃をおぼえる、とホブズボームは書いている。
だが、アインシュタインにせよプランクにせよ、理論家たちはじつは自分で解消できない矛盾、ないしパラドックスに直面していた。そこから逃げ込もうとして、マッハやデュエムのような新実証主義も生まれる。
科学革命は正しいと思われていた。それはたしかに進歩をもたらすものだった。だが、それはほんとうに進歩といえるのか。進歩が引き起こしたさまざまな矛盾があらわになろうとしていた。それが世紀末とデカダンの風景だった。
知性の危機に対処するもうひとつの手段が、理性と科学を放棄することだった、とホブズボームは書いている。オカルティズムや降霊術、超心理学がはやった。だが、その影響はほとんど無視できるものだ。
それよりも1875年から1914年にかけての特徴は、大衆教育と独学がめざましい発展を遂げたことだといえるだろう。教師の数も増大していた。新しい教育のもとでは、迷妄に代わって科学と理性が力と進歩を与えるようになった。そんななか、伝統的な宗教は後退していく。
もちろん世界的な規模においては、宗教の力はまだまだ大きい。しかし、少なくとも西欧では都市住民のあいだで宗教心は薄れつつあった。カトリック諸国では教権反対主義が大きな力をもつようになる。1905年にフランスは教会と国家の分離に踏みこんだ。
「要するに、ほとんどのヨーロッパで進歩と非宗教化が手を取り合って進んでいた」。教会はもはや独占的地位をもたなくなった。
そのころマルクス主義の影響が大きくなっていた。多くの知識人がマルクス主義にひかれ、社会科学、歴史学もマルクス主義の影響を強く受けていた。
いっぽう、マルクス主義とは一線を画する社会科学、人間科学も登場する。たとえばフロイトの精神分析学もその一つだ。経済学では歴史学派が誕生する反面、合理的な理論経済学もその一歩を踏み出す。ソシュールの言語学はコミュニケーションの抽象的で静態的な構造モデルをつくりあげた。
実証主義的で厳密な社会科学が生まれようとしていた。限界効用と均衡の新しい経済学はジェヴォンズ、ワルラス、メンガーにさかのぼることができる。フロイトは心理学を刷新し、性的衝動の強大な力を明るみにだした。
人間の理性的思考能力が行動におよぼす影響がいかに少ないのかを示したのはル・ボンの群衆心理学である。
社会学は民主化と大衆文化が社会に何をもたらすかという不安のなかから生まれた。そのなかで、とりわけ注目されたのが、デュルケームであり、ウェーバーである。かれらは社会が現実にいかに動いているか、そしてブルジョワ社会がどこから生まれ、これからどこに向かっていくのかに関心を集中した。
社会学の発展を動機づけたのは、ブルジョワ社会の状況にたいする危機感、それを崩壊にいたらせないための方策にほかならなかった、とホブズボームは書いている。だが、その答えは出なかった。戦争と革命が近づいてきたからである。
北一輝と美濃部達吉──美濃部達吉遠望(26) [美濃部達吉遠望]

北輝次郎(一輝)はみずからを社会主義者にして帝国主義者(国家主義者)と名乗っていた。そして、社会主義と国家主義を合体する思想を築くために奮闘し、満23歳の1906年(明治39年)5月に大著『国体論及び純正社会主義』を自費出版する。本は発行後5日で発禁となり、差し押さえられた。
社会主義と国家主義が合体した思想を、われわれは現在ファシズムと呼んでいる。しかし、これを政治的罵倒の言辞として扱うのではなく、北のいわば純粋ファシズムの思想、すなわち昭和維新の思想を、社会主義も国家主義も輝きを失った現在から、見つめなおしてみることは、それなりに価値があると思われる。
結論的にいえば、北の考え方の特徴は、国家を正義としての社会主義を実現する共同体ととらえたところにある。その国家を統率するのは、君主としての天皇である。ただし、その天皇は「教育勅語」の万世一系思想によって脚色された天皇、いわば「天皇の国民」の上に鎮座する天皇ではなく、民主的な「国民の天皇」でなくてはならない。
いま、北一輝の思想と行動を詳しく論じるつもりはない。松本健一に名著『評伝北一輝』(全5巻)がある。ここでは、それを参考にしながら、北と美濃部が交錯する1906年の思想風景にかぎって紹介してみることにする。
『国体論及び純正社会主義』は次の5編からなる。
(1)社会主義の経済的正義
(2)社会主義の倫理的思想
(3)生物進化論と社会哲学
(4)いわゆる国体論の復古的革命主義
(5)社会主義の啓蒙運動
この目次からもわかるように、いわゆる国体論を批判し、社会主義を宣伝することが主な内容となっている。美濃部達吉が批判されるのは、国体論批判に関する第4編においてである。
だが、その前に、北一輝が社会主義をどのように考えているかをみておくことにしよう。
現代社会は貧困と犯罪にあふれている。これを取り除くことができるのは社会主義だけだ。北はそう断言し、まず貧困について論じはじめる。
ほんらい労働者の苦痛を軽減し、社会をより豊かにするはずの機械が、かえって労働者を苦しめ、失業者を増やしているのは、経済的貴族、すなわち少数の資本家階級のせいである。かれらは地主と手を携えて、この国の土地と人民を支配している。
この「経済的貴族国」のもとで、人びとは農奴と奴隷になって苦しんでいる。いつかかれらがストライキに走り、暴動を起こすのは目に見えている。そうした事態は避けなければならない。したがって、その前に、社会主義を実現し、正義と権利の名において「土地および生産機関の公有」を実施しなければならないのだ、と北はいう。
「経済的貴族国」を「経済的公民国家」へと移行させることはその第一段階である。この公民国家のもとでは、国民はそれぞれ義務かつ権利として、国家によって雇用を保証され、いわば「徴兵的労働組織」においてはたらき、外国の経済力と戦う。
だが、それはまだ社会主義にはほど遠い段階だ。労使関係は服従を強いられ、報酬の差も大きい。社会主義国家が誕生すれば、労働者は「全世界と協同扶助を共に」するために働く。自由と独立も保証されるようになり、職務のいかんにかかわらず報酬も同一となる。国家はその段階に向かって進化していく。
松本健一は、北一輝にとって「社会主義は社会に経済的幸福をもたらすがゆえに、正義なのである」と記している。それは貧しい社会主義ではなく、豊かな社会主義であり、最終的には「世界連邦」をめざすものと考えられていた。
次に論じられるのが犯罪についてである。下層階級による犯罪はほとんどが経済的欠乏によるものだが、上層階級もより高尚な生活を手に入れようとして犯罪に走る。社会の必然的現象といえるこうした犯罪を減らすには、社会主義によるしかない。経済的貴族国を覆し、経済的な自由と平等を実現する社会主義は「倫理的理想」でもある、と北はいう。
社会主義は個性の圧殺をはかるものではない。むしろ、個人の個性を尊ぶものだ。なぜなら、社会を進化させる唯一の手段は、個人の個性にほかならないからである。
ただし、北は個人と国家が対立するとは考えない。社会主義のもと、個人と国家が共進化することによってこそ、社会全体の幸福が得られると考えている。
人類は半神半獣の存在であり、いわば類神人なのだ、と北はいう。しかも、人類は社会的動物なのであって、人間を分子とする社会は、それ自体が有機体なのである。
人間が「小我」としての生物だとすれば、人民を包摂する国家は「大我」としての有機体である。そして、人間が進化するように国家も進化する。
人類は生物界の生存競争を勝ち抜くことによって、現在の優勝者となり、相互扶助のもと獣類から神類へと進化しようとしている(まるでユヴァリ・ハラリのいう「ホモ・デウス」のようだ)。
国家もまた民族国家間の抗争をくり返しながら、それに生き残って世界連邦を形成するにいたるはずだ。その段階では階級闘争も戦争もなくなっている。北は世界連邦を「無我」と呼んでおり、「小我」である人が「大我」を悟り、さらに「無我」の境地にいたることこそが、人生の意義だとしている。
北はマルサスの人口論を否定し、人口は幾何級数的には増えないという。生物種は生存進化に必要なだけしか子を育てない。人口の増加には共同体の進化の理法、いわば「宇宙目的論」があって、それは戦争を経つつも、最終的には人口過多のない世界連邦へといたる、と北はいう。
そして、いよいよ国体論批判がはじまる。日本の国体は天皇の偶像崇拝のうえに成り立っているというのが批判のポイントである。
天皇は天照大神からはじまる万世一系の末裔などではない。ほかの国々と同じく君主なのであって、「国家の一分子」であり、「国家の機関」であることは自明である。北はこうした考え方を一木喜徳郎や美濃部達吉から受け継いでいる。
近代国家においては、主権はあくまでも国家にあり、そのなかで天皇は「機関」としての役割をはたしているのだ。もし、穂積八束などがいうように天皇こそが国家の主体だというのなら、日露戦争は国家の戦争ではなく、天皇一人の戦争となり、6万の死者を出したのは万世一系の天皇だと論ずるほかなくなってしまう、と北はいう。
ただし、達吉が天皇を国家の「最高機関」としたのにたいして、天皇は国家の「特権機関」だと切り返す。北によれば、わが国においての最高機関は天皇と議会であって、天皇は最高機関そのものではなく、あくまでも特権機関だということになる。このあたりの認識は、民主主義をさらに強く意識したものとなっている(二・二六事件の青年将校にあこがれた晩年の三島由紀夫は、北が国家機関説論者であることを知って、愕然とした)。
復古主義者の穂積八束は、「わが万国無比の国体においては、国民は一家の赤子(せきし)であり、天皇は家長として民の父母である」と唱えていた。だが、北は日本の歴史をふり返ることによって、こうした主張に反駁する。
天皇が日本の国土と人民を私有する唯一の「家長君主」だったのは、平安時代までである。それがいまもつづいていると考えるのは時代錯誤もはなはだしい。
北によれば、日本の国は3期の進化を経てきた。松本健一は、それを次のようにまとめている。
〈第一期は……天皇が唯一の家長君主としてあった「君主国」時代である。第二期は、皇室が神道的信仰のうえに「神道の羅馬(ローマ)法王」としてあった時代で、このときはその法王から征夷大将軍として統治権をわかたれた「鎌倉の神聖皇帝」がほかの封建的諸侯とともに、政権に「覚醒」している状態である。すなわち、諸侯の併存する「貴族国」時代である。この第二期は、明治維新まで継続したわけである。さて、第三期はそれまで貴族階級(封建諸侯)によって独占されていた政権を「百姓一揆と下級武士」がわかちもったことになり、政権への「覚醒」が、さらに大多数に拡張した状態である。「万機公論に由る」という「民主国」が、これである。つまり、日本国家は「君主国」、「貴族国」、「民主国」という進化過程をたどった。〉
北の歴史認識は明解である。ところが「民主国」になったはずの日本が、復古的な「教育勅語」などをいただいているのは、どうしたことか。口語に直すと、「われわれは国家の前に有している権利にもとづき、教育勅語の外に独立しなくてはならない」と北はいう。
松本健一によれば、北一輝は大日本帝国憲法における天皇機関説によって、教育勅語に代表される国体論を破却しようとしたのだという。
だからこそ、『国体論及び純正社会主義』のなかで、こう述べる(口語訳)。
〈今日の国体論者は武士道とともに立った武門を怒り、武門が立って皇室が衰えたと悲憤慷慨する。しかも、万世一系のかなづちに頭蓋骨を叩かれて、武士道とともに天皇陛下万歳を叫ぼうとしている。まるで土人部落だ。〉
国体論者は天皇をまるで土人部落の酋長のように扱っている、と北は差別語満載でいう。
皇室が歴史上、連綿とつづいてきたのは事実である。それは尊貴な系統を利用して、支配者がみずからの地位を正統化しようとした島国独特の風習である。加えて皇統が連綿とつづいたのは天皇が神道の祭主となったためである。そのため、新たな政治権力が登場しても、天皇の宗教的権威は奪われることがなかった。そんなふうに北は論じる。
だからといって、北は天皇をおとしめるわけではない。その逆である。北にとって、明治維新は王政復古ではなく、あくまでも維新革命だった。1300年前の古代がよみがえったわけではない。国民の団結力を背景として、明治維新という民主革命が発生し、生まれながらの英雄である明治大帝が登場したのである。
北はいう(口語訳)。
〈維新革命の根本義が民主主義であることを理解しないために、日本民族はほとんど自己の歴史を意識せず、勝手な憶説独断を並べて、王政復古、あるいは大政奉還などといい、みずから現在の意義を意識していない。……維新革命の国体論は、天皇と握手して貴族階級を転覆したかたちにおいて君主主義に似ているけれども、天皇も国民も共に国家の分子として行動した絶対的平等主義の点において、堂々たる民主主義なのである。〉
北にとって、維新革命は王政復古などではなく、あくまでも明治デモクラシーのはじまりなのだった。教育勅語などによって国民を万世一系神話に縛りつけようとする輩は、維新の精神を踏みにじる者にほかならない。
北において、社会主義とは明治国家を初発の理念に引き戻す運動にほかならなかった。普通選挙を通じて、経済的維新革命による土地資本の国有化を実現し、天皇を君主とする国民のための国家をめざさなければならない。これがかれのユートピア的な革命論だった。
しかし、北の社会主義革命路線を達吉が支持することはないだろう。その後、北は国家を否定する幸徳秋水や大杉栄のほうにではなく、宮崎滔天や内田良平のほうに接近し、「支那革命」に展望を見いだしていくのである。
早稲田での憲法講義(2)──美濃部達吉遠望(25) [美濃部達吉遠望]

早稲田大学法律科での美濃部達吉による帝国憲法講義がつづいている。
国家の作用は、具体的には立法、司法、行政のかたちをとり、それを裏づけるのが予算であることはいうまでもない。憲法講義ではそれらのことも詳しく論じられている。
立法、司法、行政が、それぞれ議会、裁判所、政府という国家機関を構成するとすれば、立憲君主制のもと国家の外に存在するわけではない天皇もまたとうぜん国家機関として位置づけられることになる。
達吉がとりわけ力を入れて講じたのは、国民とは何かということであり、さらには天皇と内閣、議会という三つの国家機関の関係についてだった。
国民について、達吉はいう。国民とは国家に属するすべての人民のことである。したがって、いわゆる臣民だけではなく君主も国民であり、領土内に滞在する外国人も国民と言わなければならない。
国民は国家の統治権に参与する権利を有する点において公民であり、いっぽう国家の統治権に服する義務をもつ点で臣民であるという二重性をもっている、と達吉は論じている。
外国人は領土内に滞在を認められるあいだは、統治権に服従するかぎりにおいて国民と同じ扱いを受け、原則として国民と同じ権利を有するが、兵役義務は除外されるものの、参政権を享有することはできない。
ここで注目すべきは、達吉が国民が国家にたいして義務を有しているだけではなく権利、すなわち公権を有していることを強調している点である。近代においては、国民は国家の奴隷として国家に服従するのではなく、一個の侵されざる人格として国家に対している。また国家も公法で定められる以上に国民にたいして統治権をふるうことはできない。
国民は自由意志の主体としての権利を有している。権利とは自己の利益を主張する意志の力のことだが、その権利は法がそれを認めることによって生じる。こうした権利は歴史的に徐々に形成されてきたものである。
国民の権利には公権と私権がある。公権は法によってはじめて付与されるものであり、私権は婚姻や売買などにしても、慣習のなかから形成されてきたものが多い。もっとも、私権とてけっして法とは無関係とはいえない。一般に公法に属するものが公権であり、私法に属するものが私権といえるだろう。
公権は公益にかかわっている。公権は(1)参政権(2)国家の行為を要求する権利(3)自由権の3つに大別される、と達吉はいう。
国家の機関が国民に義務を課することができるためには、国民の参政権によって、その国家機関たることが承認されなければならない。君主が皇位につき、議員が議員の地位につき、官吏がその立場にふさわしい行動をとることができるのも、大きくみれば国民の承認があるからである。
国家の行為は国民の利益のためにおこなうものである。ただし、それは直接に個人のためではなく、公共の利益のためにおこなわれる。そして、国民は国家に公共の利益をはかるよう求める権利をもっている。
さらに、国民は自由権をもっている。自由権とは個人が法律によって定められた制限以外は、国家によって自己の自由を侵害されない権利をいう。たとえば集会結社の自由とは、法律で定められた制限以外は国家によって集会結社を妨げられないことを意味する。
達吉は皇室の地位が特別であり、それが皇室典範によって定められていることを強調する。そのうえで、国家の機関としての天皇とその輔弼機関について述べる。
君主である天皇は国家の最高機関であり、対外的な統治権発動の源泉である。こうした最高機関がなければ国家は成立しえない。しかし、天皇は国家の最高機関であっても統治権の主体ではない、と達吉はいう。
天皇が国家の機関だなどというと、何となく君主の尊厳を害するように思うかもしれないが、天皇が国家の機関であるのは、国家が永続的かつ統一的な団体であることから生じるもので、皇室の尊厳とは何ら関係がない。
しかも、君主はひとりの人格、言い換えれば一身上の権利として統治権を有するわけではない。国家の委任を受けて、統治権を行使するわけでもないというのだ。
憲法の明文にもとづき、いまでも君主は統治権の主体だと主張する者が多い。だが、それは学理的には支持しがたい、と達吉はいう。
立憲君主国においては、君主の統治権はさまざまなかたちで制限されている。君主の国務上の行為は大臣の副署を必要とするという規定もそのひとつだ。裁判権も独立の地位を有している。立法権もそうだ。法律は議会の議決をへなくては成立しえない。その意味で、統治権のすべてが君主に帰属しているわけではないのである。
だが、このことは、君主が統治権の全体を総攬する妨げにはならない、と達吉はいう。なぜなら国務大臣も裁判所も議会も、君主からその権限を与えられているからである。
天皇は実際には統治権の全部を総攬(そうらん)しているわけではないけれども、統治三権の活動を承認するという意味において、最高機関としての性格をもつというのが達吉の考え方だといってよい。法律が議会での議決をへたのち、天皇が裁可することによって、はじめて施行されるのも、そのためだ。
君主は自己の権利をおこなうものではない。国家の機関として天皇がおこなうところは君主の権利ではなく、国家の権利である、と達吉はいう。それであるがゆえに、天皇は不可侵権、すなわち神聖にして侵すべからずという原則によって守られ、一身上の尊厳を維持するための栄誉権と財産権を有しているのだという。
わが国の君主の大権はイギリスよりずっと大きい、と達吉は論じている。それは帝国憲法がプロイセン憲法を模範としたためでもあるが、その大権はプロイセン憲法よりも大きい、と達吉は説明している。
国家の機関として次に重要なのが国務大臣である。国務大臣は君主の国務上の行為を輔弼し、その責に任ずる機関であるという。ここで、明治体制が現在のような議員内閣制を採用していないことはいうまでもないだろう。
達吉によれば、独裁君主国においては、国務大臣の役割はあくまでも君主の輔弼にとどまる。しかし、立憲君主国においては、君主は国務大臣の輔弼なくしては、例外を除いてすべての国務行為をおこなうことができない。ここで、その例外のなかに軍事上の命令が含まれていることが、その後の軍部の暴走を招くことを、後世のわれわれとしてはコメントしておきたいところである。
それはともかくとして、立憲国であるわが国においては、総理大臣を筆頭として、国務大臣は無任所の者を除いて、各省(外務、内務、大蔵、司法、陸軍、海軍、農商務、文部、逓信)の大臣を担任する。国務大臣は君主の行為を輔弼するために、みずからの職責をはたすものとされている。
さらに、達吉が国家の機関として重要なのが議会だと指摘するのはとうぜんだろう。
近代においては、君主と議会は統一的団体である国家の機関として存在する。そして、その議会は中世とは異なり、全国民を代表するものとして、選挙によって選出されるものとなったという。
口語に直すと、議会について、達吉はこんなふうに述べている。
〈立憲国においては、議会の組織によって、国民の全体がひとつの国家機関としての地位を得るようになった。とはいえ、この国家機関はみずからその権限を行使することができない。議会を通してのみ、これを行使することができる。議会は国民の代表機関として、国民の名において、その権限を行使するのである。議会の決議は、法律上の意義において国民の意志なのである。〉
議会は国民の代表機関として、その議決を通して国民の意志を表明するというのが、達吉の見方である。
さらに、議会は憲法によって直接定められた国家の機関であり、君主によって授けられたものではなく、君主の命令に服するものではない、とも明言している。それは君主と同じく国家の直接機関なのである。
「君主と議会という二つの直接機関が並び存することは、立憲国が専制国と区別されるゆえんである」
とはいえ、議会は君主と平等の地位を有するものではない。議会の権限はもっぱら立法権にとどまる。国内における国家意志の作成に参与し、行政を監督するにとどまり、直接国民に対してはいささかも統治権を発動することができない。
議会について達吉は、ほかに二院制の理由、選挙権の要件、その他さまざまな問題をことこまかに論じている。現行選挙法の欠点についてもふれている。
議会の主要な任務は、法案の制定に参与し、政府の重要な行為(とりわけ予算)に同意し、行政の監督をなすことである。そのことを強調しながら、達吉は議会の発展に期待したのだといってよい。
帝国憲法のもと、国家機関としての天皇と内閣、議会がそれぞれ適切な役割を果たしつつ、近代国家として日本が成長していく姿を達吉は期待していた。だが、支配層のなかでは、絶対天皇の名のもとでみずからの政策を押し通そうとする者がいまだに多かった。かれらは天皇が国家機関だとすれば、その国家機関がいつか失われる可能性があることを恐れていたのである。
早稲田での憲法講義(1)──美濃部達吉遠望(24) [美濃部達吉遠望]
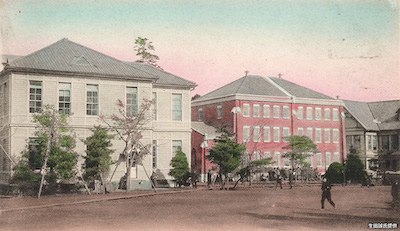
ヨーロッパ留学から帰国した1902年(明治35年)から美濃部達吉は東京帝国大学教授として法科大学(法学部と改組されるのは1919年)で比較法制史を教えていた。だが、ほんらい公法に関心が強かったため、早稲田大学や日本大学に出向いて、憲法に関する講義もおこなうようになった。
奥付がないため、発行年月日ははっきりとわからないものの、達吉が早稲田大学の法律科でおこなった帝国憲法講義録が早稲田大学出版部から出されている。推測するにおそらく1905年(明治38年)前後の出版と思われる。北一輝が美濃部の講義に出たか、あるいはこの講義録を読んだことはまちがいない。
ここで、いささか退屈かもしれないが、この講義がどういう内容のものであったかをふり返っておくのも悪くないだろう。憲法にたいする達吉の考え方はこのころからほとんど変わらず、1920年(大正9年)から東京大学で憲法講座を受け持つようになっても、講義の内容は基本的に同じだったと思われる。
早稲田での講義は、そもそも国家とは何かというところからはじまっている。日本だけではない。世界にはさまざまな国があって、それらは対立したり交流したりして、現在の国際関係を築いている。したがって、国家という現象はけっして一国だけの特有の現象なのではなく、文明国に共通の普遍的な現象であって、そこで国家にたいする共通の概念が成り立つ。とはいえ、それぞれの国には、それぞれの歴史的背景があることも忘れてはならない。そう指摘しつつ、達吉は近代国家とは何かを論じている。
国家が成立するには、国民と領土と統治権力が存在しなければならない。つまり、国家とは「唯一最高の権力の下に一定の土地の上に定着したる多数人類の結合したるもの」である。ただし、そう規定するだけでは、国家の性質を説明したとは、とてもいえない。
古くからある考えとして国家有機体説がある。国家は生き物と同じで、自然に成長し、発達し、衰亡するというものだ。だが、それは自然のアナロジーにすぎず、政治学的な説明を満たすものではない。
法律的にいえば、国家を統治の目的物(客体)とみるか、統治状態とみるか、統治権の主体とみるかという3つのとらえ方がある。
国家を統治の目的物とみるのは、政治的意志が国家の上に立つと想定する中世の封建的な考え方だ。君主が臣民や領土を自己の所有物とみなすこうした考え方は、近代の国家観念とは相いれない、と達吉は断言する。近代国家においては臣民は奴隷ではなく、みずからの権利の主体であって、君主はあたかもみずからの所有物であるかのように、臣民を支配することはできない。
次に国家を統治状態ととらえる見方は、統治されている状態を国家とみなすというもので、国家を主体的、活動的に把握しているとは言いがたい。そこで最近では、国家をひとつの人格のようにとらえ、ひとつの権利主体とみなす考え方が定説になった、と達吉は説明する。
国家人格説は、国家を法人(集合人格)とみなす考え方だといってよい。世代交代によって君主や臣民が入れ替わっても、法人としての国家は存続する。君主は国家の外に立つのではなく、国家の内部に不可分な存在として位置づけられる。さらに、国家はそれ自体が活動能力をもつ主体とみなされる。ただし、国家という法人の特徴は、唯一の統治権力をもつことであって、その点は同じ法人であっても地方団体とことなるところに注意しなければならない。
したがって、統治権の主体は君主の一身ではなく、国家そのものにある。たとえ法律に統治権は君主に属すると記されていても、近代の国家思想においては、君主は自己一身の利益のために統治権を発揮することはできない。
国家はどのように発生し、消滅するのか。
西洋では、国家が発生するのは、国民が契約を結んで国家団体を形成し、その自由の一部を割いて、国権に服従するという考え方がある。だが、それは誤った前提にもとづくもので、契約説は歴史的にも論理的にも国家の起源を説明するものではない。人が共同生活を営むのは、自然の要求であって、契約によるのではない。領土、国民を統一する権力は自然に生まれたとみるべきだろう、と達吉はいう。
といっても、契約や法律によって国家が生まれた例がないわけではない。アメリカ合衆国やドイツ帝国などもそうだ。多くの州が連合して国家がつくられた。
いっぽう、統一的な権力が失われ、国民や領土がなくなった場合には、国家は消滅する。現在の政府が転覆され、これに代わる政府が成立しないときは、国家は事実上その存在を失ったものといえる。
そう述べたうえで、達吉は近代国家を成立させる前提となっている法について説明する。法には公法と私法があるという。公法とは、国家と国家および国家と国民の関係、国家の組織を定めた法であり、私法とは国民と国民との個人相互間の関係を定めた法である。
公法は国家の権力の発動に関する法律であって、国家にたいする国民の権利、義務を定めたうえで、権力の恣意的な発動を抑制するためのものでもある、と達吉は論じている。
法には制定法と慣習法があるが、近代においては立法の発達に伴い、慣習法は次第にその価値を減じ、国家の制定する法を法とするという考え方が一般的になっているという。
まだはじまったばかりだが、こんなふうに達吉の講義は、一部の隙もないほど論理的に組み立てられていることがわかる。いまそれをことごとく紹介していては、それだけで1冊の本になってしまう。そこで、以下は注目すべき箇所にだけいくつかスポットライトをあてるにとどめよう。
憲法について、達吉はこんなふうに述べている。
憲法とは国家の基本法であり、国権の組織と行動に関する大原則を定めた法をいうが、立憲国の憲法は代議制を認め、議会を国権に参与させることを根本としている。
ヨーロッパでは、ほとんどの国が成文憲法をもっている。それは近代に発達したもので、18世紀以降に生まれたものだ。アメリカ合衆国に発し、フランス革命によって伝播し、それがついにわが国にも及んだといえる。
帝国憲法が主にプロイセン憲法を模範としていることはよく知られている。プロイセン憲法の特徴は、議会の権限が国内の関係にとどまり、外部に関しては国家的行為がすべて君主の名でおこなわれることである、と達吉は論じている。
憲法は最強の効力を有する国家の法であって、これを変更するには憲法改正の法律にもとづかなければならない。ただし、解釈の変更、あるいは新たな法の制定によって、事実上、変更と同様の結果を生じることはありうるとも述べている。
統治権をもつのは、近代においては国家のみである。一般に権力は命令を発することができるが、それを強制することはできない。それは会社でも学校でも同じだが、命令に従わない個人にたいし懲戒処分をおこなうことはできても、その個人は同時にその集団を脱退する権利をもっている。ところが統治権は命令にたいする服従を強制することができ、これに違反する場合は個人を抑留することができる。中世の時代とは異なり、今日の国家においては、国家以外に国家の権力から独立した統治権はどこにも存在しない。
統治権は不可分である。三権分立は権力を分割するものではなく、あくまでも唯一の権力を行使するにあたって、その機関を分立したものである。ただし、機関はどのように分立したとしても、そのために権力の統一が妨げられることはない、と達吉は述べている。
つづいて、主権という概念が説明される。主権という概念が生まれたのは中世のフランスにおいてであり、それは教会や封建諸侯などの権力に掣肘されない最高権という意味をもち、その権力はもっぱら君主に属していた。そして、18世紀にいたるとルソーにみられるように、国家のすべての権力は国民に属するべきだという考え方が登場する。
しかし、主権の本来の意味は、外部の力によって抑制されることのない国家の権力ということだ、と達吉は説明する。したがって、君主主権説か国民主権説かというのは、政治上の主義の問題であって、主権概念とはほんらい無関係である。
主権は国家権力、ないし国家の最高機関、あるいは統治権と同じ意味で用いられている。しかし、厳密にいえば、主権とは、国家の権力が最高かつ独立の性質をもつことにほかならない。すなわち国家の権力が内部においては最高の位置にあり、外部にたいしては独立しているときに、国家の主権は保たれているということができる。
国家の権力は無制限というわけではない。国家は対外的には国際法、対内的には国法によって拘束され、国権はその法律のもとにおいてのみ活動することができる。そして、逆に統治権があっても主権のない国家が存在することをみれば、主権がかならずしも国家存立の必須要件ではないことも追述されている。
達吉はさらに国家について論じる。国家は無形の団体であって、それ自体が意志や能力をもつわけではない。それを動かしているのは人間であって、その集合的意志が国家の意思となり、国家の機関をかたちづくっている。
国家の機関は人格をもつものではなく、国家のために国家の意志と権利、義務を実行に移すことを目的としている。国家の機関に属する者は、もちろん個人としての意思をもっている。だが、かれらは議員であれ、官吏であれ、たとえ君主であっても、あくまでも自己の意思や権利を唱えるのではなく、国家を代表して国家のために、それぞれその統治権を発揮するのである。
近代において、君主が国家の機関だということは、国家が統一的団体であることから生じる論理上、当然の結果である。もし近代国家においても、君主は国家の機関ではなく、みずから権利の主体だというのならば、それは国家の統一的団体としての性質を破壊するものだ、と達吉はいう。
専制君主国においては、直接の国家機関は君主のみであって、残りの国家機関はすべて間接機関である。しかし、立憲君主国においては、直接機関はふたつ以上あり、君主と議会は等しく国家の直接機関である。国家の直接機関は必ずしもひとつである必要はない。立憲君主国においては、たとえ条文に君主がその一身をもって統治権を総攬すと記されていても、学理上はそうしたことはありえない。要は、国家が国家としての統一された意志を有することが重要なのだ、と達吉は述べている。
国体についても触れている。大きく分ければ国体は君主国と共和国に区別される。それはさらに細かく分類されるだろう。ただし、近代の立憲君主国の特徴は、最高機関である君主のもとにそれと相ならんで代議制度をもつこと、君主の国務上の行為はかならず国務大臣の副署を必要とすること、司法権が独立していることだという。
達吉が日本は近代の立憲君主国であって、中世の君主国ではないと主張していることはいうまでもない。
退屈かもしれないが、もう少し、その講義に耳を傾けていただけるとありがたい。
平民新聞と佐渡新聞──美濃部達吉遠望(23) [美濃部達吉遠望]
幸徳秋水、堺利彦、内村鑑三の3人が、日露開戦論に転じた「万朝報(よろずちょうほう)」を辞めたのは、1903年(明治36年)10月9日のことである。幸徳と堺は、新たに東京市麹町有楽町3丁目、現在の有楽町マリオンのあるあたりに借家の事務所を構え、翌月から週刊で「平民新聞」を発行した。
11月15日の平民新聞創刊号には、編集方針ともいうべき「宣言」が掲げられた。いわく自由、平等、博愛、いわく平民主義、いわく社会主義、いわく平和主義、いわく国際主義。
さらに「発刊の序」では、好戦の気分に包まれているいまこそ、正義や人道や平和を主張しなければならない、との決意が述べられた。
その翌月には、石川三四郎と西川光二郎が社員に加わった。
戦争を起こそうとしているのは一部の資本家であって、これに政事家や学者、新聞屋などが同調して、開戦をあおっているのだというのが、幸徳秋水の見方である。
翌1904年(明治37年)2月に日露戦争がはじまっても、平民新聞は非戦の旗を下ろさなかった。ほとんどの新聞が愛国心をあおり、戦意高揚をはかるなかで、平民新聞だけは非戦の論陣を張っている。
戦争がすでにはじまったとはいえ、われわれは口あり筆あり紙あるかぎり、戦争反対を絶叫する。兵士諸君、諸君は人を殺すために戦場に行くのか。それならば諸君は単に一個の自働機械だ。そればかりではない。戦争がもたらすのは増税であり、軍国主義であり、物価騰貴であり、風俗の堕落だ。
「露国社会党に与える書」という論説は、諸君とわれらは同志、兄弟、姉妹であり、断じて戦うべきではない、戦うべき共通の敵は軍国主義なのだと、まだ見ぬロシアの同志に訴える。
3月27日には、「嗚呼(ああ)増税!」と題する社説を掲げ、今回の戦争が国民に大きな負担を強いていることを批判した。
その一節を原文のまま引用してみよう。
〈今の国際的紛争が、単に少数階級を利するも、一般国民の平和を攪乱し、幸福を損傷し、進歩を阻碍(そがい)するの、極めて悲惨の事実たるは吾人の屡(しばし)ば苦言せる所也、而(しか)も事遂に此に至れる者一(いつ)に野心ある政治家之を唱え、功名に急なる軍人之を喜び、奸猾(かんかつ)なる投機師之に賛し、而して多くの新聞記者、之に附和雷同し、曲筆雑文、競ふて無邪気なる一般国民を煽動教唆せるの為めにあらずや〉
現在では読むことさえむずかしいが、人の心をわきたたせる名文である。
さらに、この社説には、国民の不幸と苦痛を除去するには、どうすればよいかという対策まで書かれている。つづいて引用する。
〈何ぞ夫(そ)れ然らん、国民にして真に其不幸と苦痛とを除去せんと欲せば、直ちに起(たち)て其不幸と苦痛との来由を除去すべきのみ、来由とは何ぞや、現時国家の不良なる制度組織是れ也、政治家、投機師、軍人、貴族の政治を変じて、国民の政治となし、「戦争の為め」の政治を変じて、平和の為めの政治となし、圧制、束縛、掠奪の政治を変じて、平和、幸福、進歩の政治となすに在るのみ、而して之を為す如何、政権を国民全体に分配すること其始也、土地資本の私有を禁じて生産の結果を生産者の手中に収むる其終也、換言すれば現時の軍国制度、資本制度、階級制度を改更して社会主義的制度を実行するに在り〉
戦争をやめ、現在の制度を社会主義制度に改めよ、とはっきり書いてある。この社説を執筆したのは幸徳秋水だった。
これにたいし、東京地方裁判所は新聞紙条例違反を理由に平民新聞を発行禁止とし、発行兼編集人の堺利彦を軽禁固3月に処した。
発行禁止が解除されたあとも、平民新聞は政府への批判をやめなかった。10月には発行1周年記念として、堺利彦が英語から翻訳した「共産党宣言」が掲載された。だが、これも発行停止処分となった。
こうして発行停止と起訴がつづくなかで、堺や幸徳は追いつめられ、ついに1905年1月29日付の第64号をもって平民新聞は廃刊となる。ロシアとの戦争はまだつづいていた。
堺利彦の評伝を残した黒岩比佐子は、平民社とそこに集まった同志について、こう書いている。
〈ロシアと交戦中でありながら、非戦を唱える社会主義者は、世間からも国賊視された。親兄弟からも白い目で見られ、恩師や先輩からは叱責され、友人たちも離れていくという四面楚歌の状態で、彼らが信頼できたのは同志だけだった。〉
だが、かれらはあきらめなかった。「平民新聞」が消滅したあと、おなじ平民社で、安部磯雄も加わって「直言」が発行される。2月28日に幸徳秋水と西川光二郎は巣鴨監獄に収監された。堺利彦は「直言」に通俗社会主義の連載を開始した。愉快な記事や女性問題特集も加えられた。
幸徳秋水は獄中で体調を崩し、7月28日に出獄したあとも小田原で静養する。アメリカに行ってみたいと考えるようになっていた。
5月に日本の連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を撃破すると、日本中がわきたち、これで日本の勝利はまちがいないという雰囲気が広がった。期待が大きく膨らむなか8月にポーツマス会議が開かれ、その結果に人びとは失望する。その怒りが日比谷焼き討ち事件となって爆発し、これにたいし政府が戒厳令を発動したことは前にも述べた。
新聞雑誌は次々に発行停止を命じられた。平民社の「直言」は、木下尚江(なおえ)が書いた「政府の猛省を促す」という記事が問題とされ、9月に発行停止が命じられ、そのまま解除されなかった。これにより「直言」は廃刊となり、平民社の解散も決まった。
社会主義者は分裂する。木下尚江、安部磯雄はキリスト教社会主義を唱える「新紀元」を創刊し、西川光二郎らは堺利彦の協力のもとで唯物論的社会主義を唱える「光」を創刊した。そして、幸徳秋水は11月14日、戒厳令下の東京を離れて、アメリカに渡った。社会主義者にとって、冬の時代がはじまろうとしていた。

そのころ早稲田大学の政治学科に聴講生として在籍する佐渡出身の青年がいた。弟が早稲田の予科にはいったのを契機に、1904年(明治37年)夏から、弟と同居するようになったのだ。本人にとっては二度目の上京となる。一度目は5年前で、目の手術をするためだったが、けっきょくうまく行かず、右目を失明するにいたる。そのため学業不振となり、佐渡中学を退学していた。
青年の名前は北輝次郎。のちに北一輝と名乗るようになる。日露戦争が終わったときは満22歳だった。
佐渡ではすでによく知られた人物だった。実家は裕福な酒造業者だったが、家業は傾き、初代両津町長を務めた父は1903年(明治36年)に亡くなった。それ以前から、北は地元の「佐渡新聞」に次々と論説を発表するようになっていた。
時節柄、日露開戦にからむものが増えていた。北はみずから社会主義者であることを公然と名乗りながら、満洲問題を解決するには日本はロシアと戦わざるを得ないと主張する。1903年(明治36年)7月4日の佐渡新聞には「露国に対する開戦、しからずんば日本帝国の滅亡」と記した。帝国主義時代においては、帝国は生存競争に勝ち抜かないかぎり生きていけない。非開戦論者は、戦わずして生存競争の敗者である、と論じた。
尊敬する幸徳秋水や木下尚江が、主戦論に転じた「万朝報」を辞めたと聞いたとき、北はあらためて非開戦論を批判して、10月27日の佐渡新聞で高らかにこう宣言した。原文で示す。
〈吾人は明白に告白せむ。吾人は社会主義を主張す。社会主義は吾人に於ては、渾(す)べての者なり。殆ど宗教なり。吾人は呼吸する限り社会主義の主張を抛(なげう)たざるべし。社会主義の主張は価値なき吾人の生涯に於て最後の呼吸に達するまでの唯一の者たるべきを信ず。而も同時に吾人は亦(また)明白に告白せざるべからず。吾人は社会主義を主張するが為めに帝国主義を捨つる能はず。否、吾人は社会主義の為めに断々として帝国主義を主張す。吾人に於ては帝国主義の主張は社会主義の実現の前提なり。吾人にして社会主義を抱かずむば帝国主義は主張せざるべく、吾人が帝国主義を提げて日露開戦を呼号せる者、基く所実に社会主義の理想に存す。社会主義者にして而して帝国主義者。〉
北はみずからが社会主義者であると同時に帝国主義者であることを宣言したのである。そして、帝国主義の名によって日露開戦を主張するのは、社会主義の理想を実現するためだと主張した。
このひらめきは矛盾に満ちていた。社会主義、さらに民主主義と帝国主義は、どこでどうつながっているのか。そして天皇をいただくこの日本で、みずからの理想を実現するには、何が求められているのか。北はこの謎を解くため、しばし沈思する。そして長い論考を書きはじめた。
それは佐渡では完成しない。何としても東京に出なければならない。その思いが翌年夏の上京と早稲田大学での聴講につながった。日露戦争はすでにはじまっていた。
北は早稲田大学政治学科でおこなわれた講義を聞き、上野の帝国図書館にも通いながら、みずからのひらめきが招いた謎を解くために奮闘する。奮闘2年、1906年(明治39年)2月末、2000枚に達する原稿ができあがった。そのタイトルは『国体論及び純正社会主義』と名づけられた。
その緒言には、社会民主主義をそしり国体論の妄想を伝播した代表的学者として、金井延や田島錦治、有賀長雄、穂積八束、井上密、一木喜徳郎、井上哲次郎、山路愛山、安部磯雄などのほか、美濃部達吉の名前がでてくる。
どうやら、このころ達吉は東京帝国大学だけではなく、早稲田大学でも教えていたらしい。北一輝は美濃部達吉の講義を聞いたと思われる。
二つの国、二つの文化を生きる [本]

爽快な本である。人の生き方を示す本でもある。
著者の金正出氏は1946年に青森で生まれ、県立青森高校を卒業したあと、64年に北海道大学医学部に入学した。卒業後、さまざまな病院に勤務し、36歳のとき茨城県にちいさな外科診療所をつくる。それが小美玉市にある美野里病院の発端となった。
さらに特別養護老人ホームや介護老人保健施設、グループホームなどをつくり、高齢者介護にも取り組んできた。それだけでは終わらない。教育分野にも乗り出し、保育園からはじまって、何と中学校・高等学校(青丘学院)まで設立したのである。
こうしたがんばりの背景には、著者たち兄弟の成長を支えた両親の努力があったことがわかる。
著者のオモニ(母)は韓国の慶尚北道安東の貧しい農家に生まれ、兄を頼って戦前日本に渡ってきた。アボジ(父)は同じ慶尚北道大邱近くの出身で、八幡製鉄所で働いていた。ふたりは流れ着いた青森で1941年に結婚し、4人の男子に恵まれた。著者はその次男である。
戦後の生活は厳しいものだった。最初、家族は多くの同胞とともに朝鮮人長屋に住んでいた。しかし、いつまでもこういう場所にいては子どもたちによくないと考え、古い倉庫を買ってそこに移った。兄弟は4人とも日本の義務教育を受け、著者もわんぱくな少年生活を送ったという。
オモニはしっかり者で、朝から晩まではたらき、水飴の行商や養豚、密造酒づくりなどをして、一家を支えていた。次男の著者は一徹な性格で、母親は小学校の先生から「この子は、よくなればとてもよくなるけど、悪くなれば、とても悪くなる可能性がある」と言われたらしい。そんな子どもたちを4人ともまっすぐに育てたのは、まさに息子にたいするオモニの願いと献身があったからだろう。
自分が朝鮮人であることを意識しはじめたのは中学校のころからだったという。しかし、そのことで卑屈になることはなかった。むしろ金本という日本名に違和感をいだき、いやだなあと思っていた。学校の成績はよく、スポーツもよくできた。差別されたと感じたことは一度もないという。県立青森高校に進学し、がむしゃらに勉強し、北海道大学医学部に合格した。帰化はせず、そのときから本名を名乗るようになった。
アボジもよく働いたが、もともと身体がじょうぶではなかった。競輪とパチンコが大好きで、オモニとよく口げんかをしていたというのが、ほほえましい。密造酒が売れなくなると、しっかり者のオモニは新宿の焼肉店で短期間修行してから、青森駅前に「明月館」という焼肉店を開いた。その店を懸命に切り盛りし、大学に入った4人の子供たちの学費を滞りなく支えた。
次々と目標を立て、困難を乗り越え、それを実現していく著者の姿勢が爽やかである。民族に誇りをもち、家族をだいじにするところも、すがすがしい。「自分のルーツや祖先、親のことを誇りに思わないで、社会的に立派な仕事をした人を私は見たことがない」と断言する。
現代の韓国政府には批判的だ。歴史的事実を直視せず、都合のいい歴史ばかり教えているという。在日同胞の貢献についても、国民に十分知らせていない。韓国の政治家は国内に問題が起こると反日法を持ちだし、論点をずらす方向に国民を誘導する。こうしたやり方は、もうやめたほうがいいという。虚心坦懐に日本から学び、さまざまな分野で日本を追い越してこそ、韓国は世界から尊敬される国になると考えている。
著者は、両親が逆境にありながらも民族に誇りを持って自分を育ててくれたことに感謝している。そして、自身も日本人に負けないよう勉学に励み、医師となり、多くの事業を展開してきた。そこから育まれた信念が、未来へと向かう一筋の道を切り開いたことを、本書はまさに指し示している。
戒厳令のなかで──美濃部達吉遠望(22) [美濃部達吉遠望]
ほんとうは国会図書館に行って、当時の資料にあたらなければならないのだが、なんだかぐずぐずと自宅に籠もったまま、東京に出るのがおっくうになってしまった。そこで立花隆の『天皇と東大』を借りて、今回の話を進めることにする。国会図書館に行く機会があれば、この部分の記述も多少膨らみがでてくるかもしれない。そのことをはじめにことわっておく。
ポーツマス会談がはじまろうというのに、東大教授、戸水寛人は相変わらずロシアとの戦争を継続すべしとの主張をぶちあげていた。それに堪忍袋の切れた文部大臣、久保田譲は、1905年(明治38年)8月25日、東大総長の山川健次郎を通さず、直接、戸水を休職処分とした。東大の教授陣は、この処分に猛反発する。その先頭に立ったのが美濃部達吉だった。
主戦論を唱えていた「東京朝日新聞」などは、むしろ戸水の言論を擁護していた。
8月10日からアメリカのポーツマスで開かれていた講和会議は、難航の末、ようやく9月4日に決着し、日本とロシアのあいだで条約が結ばれた。いわゆるポーツマス条約である。
ほとんどの日本人は、あれだけ多くの犠牲者(戦死者8万1000人、戦傷病者31万8000人)を出し、多額の費用をかけながらもロシアに大勝したのだから、広い土地と多くの賠償金を獲得できるものと思っていた。ところが、その結果が賠償金はゼロで、土地は樺太の南半分にすぎなかったのを知って、国民は怒りを爆発させた。
政府は日本の戦力が限界に達しており、これ以上戦うとかえって大国ロシアに手痛い敗北を喫すると冷静に判断していた。だからこそ、戸水のような威勢のよい戦争継続論を抑え、ようやくロシアとの講和に持ちこんだのだが、その成果が戸水らが唱えていたような講和条件をかなえるものにならないことは、最初からわかりきっていた。
だが、賠償金はゼロで、土地は南樺太だけだったとしても、ポーツマス条約で日本政府が確保した権利は、じつは大きかったのである。
ロシアは大韓帝国(朝鮮)における日本の権益を認め、満洲から全面的に撤退するとともに、清国から租借した旅順、大連などの権益、ならびに東清鉄道の支線であるハルビン・旅順間の鉄道(南満洲鉄道)とそれに付属する炭坑などを日本に引き渡すことになった。それはのちの韓国併合や満洲進出につながる内容を含んでいたのだ。
にもかかわらず、東京朝日新聞、大阪毎日新聞、万朝報、報知新聞など当時の主力紙は政府がろくに賠償金も土地も取れなかったことをこぞって非難し、国民の悲憤をあおった。
その結果、日比谷焼き討ち事件が発生する。9月5日、日本時間でポーツマス条約が締結される当日、講和に反対する国民大会が日比谷公園で開催されることになり、約3万人の群衆が集まった。その群衆が公園を封鎖しようとした警官隊と衝突し、暴動が広がった。公園近くの内務大臣官邸が焼き討ちされ、東京市内の警察署や交番が次々と襲われ、唯一講和に賛成した徳富蘇峰の国民新聞は社屋を破壊された。
政府は9月6日に緊急勅令を出し、東京市とその周辺を戒厳令下に置いた。同時に言論統制が敷かれ、政府が不都合とみなした新聞雑誌は発行を差し止められた。戒厳令と言論統制が解除されるのは、約3カ月後の11月29日である。
こうして講和に反対する動きは押さえこまれていく。しかし、このかんも戸水教授の憤激は収まらず、政府打倒まで叫ぶようになっていたという。立花隆によると、戸水は「政府を倒して批准交換を拒みさえすれば今日の危急を救うことができる」とまで主張したが、さすがにこれについていく者はいなかった。
8月25日に休職処分を受けてからも、戸水はそれをさほど気にすることなく報知新聞の客員論説委員になって論説を書いたり、各地を講演してまわっていたという。さらに9月半ばになると、ほかにローマ法を教える者がいないというので、講師として東大での講義もつづけるようになった。
しかし、戸村よりもショックを受けていたのは大学の教授会だった。文部大臣が直接、教授の処分をおこなうのはおかしいし、それを黙って受け入れた山川健次郎総長もまちがっているという議論が巻き起こった。
立花隆はこう書いている。
〈教授たちは、ただちに行動した。この事件を学問の自由の挑戦と重く受けとめた憲法学教授、美濃部達吉の呼びかけで、教授会有志(小野塚喜平次、高野岩三郎、上杉慎吉、中田薫、山崎覚次郎ら)が公法研究室に集まり、政府当局へ抗議文を提出することと、『国家学会雑誌』で、この問題を取りあげ、学問の自由を擁護する論文を各人が寄稿することを申し合わせた。有志は山川総長にも処分不当を訴え抗議した。〉
このとき、達吉は国家学会の機関誌『国家学会雑誌』の編集主任をしており、次に発行される10月号をすべて戸水問題の特集にあてることを決意した。法科大学(法学部)の教授15人全員が寄稿した。
『国家学会雑誌』10月号の冒頭「小引」(まえがき)に達吉はこう記している。
口語に直して示してみよう。
〈戸水教授が休職の命を受けたのは、官庁事務の都合によるとされるが、実はその言論をとがめるためである。しかし、罪あることを官庁の事務にことよせてその職を奪うのは法の濫用である。〉
文官分限令は第11条に、政府は官庁事務の都合によって、必要な場合は文官に休職を命じることができると定めていた。戸水の休職は、この文官分限令にもとづくものだったが、それは大学の教官人事は教授会の決定によってなされるという大学自治の原則に反したものであり、あきらかに法の濫用だ、というのが達吉の主張である。
さらに、こう書いている。
〈彼の言論ははたして罪があるといえるか。はたして教授の任に背いているといえるか。教授の言論はもちろん自由であるべきだ。権力をもってこれを拘束するのはまちがっている。彼の言論にはあるいは誤っているものがあるかもしれない。それが誤っているとするなら、また言論によってその誤りを証明するだけのことである。それがたまたま政策に反しているからといって、その口をふさごうとするのは、まさに権力の濫用である。〉
達吉は今回の政府による休職処分を糾弾した。
この巻頭言につづき、各教授が一斉に論陣を張った。
金井延(のぶる)は、皇室の尊厳をけがし、政体を破壊し、朝憲を紊乱(びんらん)するものは別として、それ以外の言論はいかなるものであっても、学者の言論に圧迫を加えるのは立憲政治の基本に反すると論じた。
寺尾亨(とおる)は学者に政治を論じるなというのは、学者は不要だというのと同じであり、大学教授は文部大臣の配下ではないと主張した。岡田朝太郎も新聞紙条例または出版法に違反しないかぎり、どんな過激な政論であっても、大学教授の言論の自由は認められるべきだと主張した。ほかに小野塚喜平次、高野岩三郎、姉崎正治、中川孝太郎、河津暹、上杉慎吉、志田鉀太郞、山田三良、筧克彦、高橋作衞 が、それぞれの立場から、今回の政府の措置を批判した。
興味深いのは、のちに大正デモクラシーの先駆者と呼ばれた小野塚喜平次の考え方である。当初、小野塚は日露開戦前に戸水と行動を共にしていたが、その過激な言論についていけず、戸水とは逆の立場をとるようになった。それでも、文部大臣による今回の措置は不当だと主張した。大学を政府の手足のように考えるのは根本的にまちがっているという。
〈旧式の政治家は、いまなお専制の迷夢のなかをさまよい、国家と政府のちがいもわきまえない。学術と国家の関係も知らない。一時の政治的便宜のために、みだりに政権によって文教を左右したがっているようだ。〉
こうした風潮がつづけば先はいったいどうなるか。
〈仮に反動思想が奔騰(ほんとう)するのに任せ、大学教授の言論の自由が政府当局者によって規制され、学者がこれを甘受して争わず、学生がこれをおかしいと思わず、世人もまたたこれを当たり前とみるようになれば、その結果、どんな事態になるだろう。学術研究の制限、学者の性格の堕落、学生の教授に対する尊敬減退、世人の大学に対する軽侮冷笑、これらは早晩発生するにちがいない悲惨な運命である。〉
学者の独立が保たれることは、学術進歩の必要条件であり、かつ国家発展に欠かせないことなのである。それが認められないなら、国家は必ず衰微する。そうならないよう学者は奮闘しなければならない。今回の戸水教授休職問題は、単に個人の問題ではなく、大学教授全体にかかわる問題なのであり、われわれはみずからの良心に沿って闘わなければならない。そんなふうに訴えた。
達吉も小野塚と同じ意見だった。戸水とは見解がちがうが、言論の自由は守らなければならないという。雑誌に掲載した「権力の濫用とこれに対する反抗」という論考で、およそ次のように論じている。
〈私はあえて戸水氏の言動を弁護しようとするものではない。まして、その主張の内容に同意するものでもない。講和条件などに関しては、交戦国どうしの軍事力、経済力、列国の関係など、きわめて微妙かつ複雑なさまざまな状態を観察したのちに決定さるべきものである。私は戸水氏の主張がはたして正確で遺漏なき材料にもとづいているかどうか疑問である。〉
達吉は戸水の見解に批判的であることを前もって表明しながらも、そうした民意がある以上、立憲政治は民意を尊重し、自由に意見を発表させる機会を与えるのが、政治の根本だと論じた。それを抑圧するのは権力の濫用である。
さらに先般の日比谷焼き討ち事件に触れて、こう書いた。
〈日露戦争の終結にあたり、不幸にしてこのような権力の濫用例を目の当たりにしたのは、はなはだ遺憾である。政府はみずからの外交が招いた民意の反抗を抑圧するために、集会を禁止し、言論を制限し、新聞の発行停止を再開し、遂に天子の膝元において戒厳令を発令するにいたった。〉
これまでの歴史をふり返ってみても、権力の濫用がかならず民衆側の反抗を招いたことを忘れてはならない。イギリスのマグナカルタしかり、アメリカの独立戦争しかり、フランス革命しかり。
「最近、東京市において先月5日以後の騒擾が起こったのもまた権力の濫用に対する反抗によるものである」
そのうえで、一時の騒擾(そうじょう)なら押さえられるかもしれないが、民衆の側が、違法とはいえない穏和で力強い手段をとるようになれば、国政を円満に進行するのがむずかしい事態になるかもしれない、と政府に警告した。
これを読んだ当局者は美濃部を嫌悪し、何らかの手段でこの反抗的な人物を懲戒すべきだという議論も起こったという。だが、達吉は昂然としていた。学問は政治から独立していると信じていたからである。
中産階級の生活と意識──ホブズボーム『帝国の時代』を読む(4) [商品世界論ノート]

帝国の時代は中産階級の時代でもある。ここでいう中産階級とは、支配階級(王族や貴族)と労働者階級のあいだに立つ階級で、実業家(ブルジョワ)、専門職(医者や弁護士)、高級官吏などの幅広い層を指す。ブルジョワ的な生活スタイルが生まれたのは19世紀末になってからで、ここから第1次世界大戦までの時代は懐古的にベル・エポックと呼ばれる。ホブズボームはそんなブルジョワ的な生活スタイルをえがいている。
まず居心地のよい庭園つき郊外住宅。それは貴族やジェントリーのような大邸宅ではなく、プライヴェートな生活を重視する空間で、大ブルジョワの威信と財力を示す邸宅とも異なっていた。もちろんそれは都市周辺の中産階級層の邸宅、そして都市中心部の労働者が住む仮設住宅ともちがっていた。
19世紀中葉の経済成長は中産階級に巨額の富をもたらした。それが私生活優先の生活スタイルを促進した、とホブズボームは指摘する。
政治の民主化にともない、最強のブルジョワは別として、中産階級の政治的影響力は弱まっていく。いっぽうピューリタン的な価値観は弱まり、快適さと楽しみを求める消費が高まっていた。ブルジョワ家族のなかでは女性の解放が進み、それが家の装飾やスタイルにも影響していく。余暇や観光も日常化していた。こうした中産階級の数は増えていた。
中産階級の定義は難しい、とホブズボームは嘆いている。ブルジョワといえば、それだけで色眼鏡をかけたイメージでとらえられがちだし、そもそもそういう階級があるのかも疑問だった。イギリスでは貴族とブルジョワ、ブルジョワとその下の階層との境界もあいまいだった。
貴族階級は出自や世襲の称号、土地所有権(領地)などで定義できるし、労働者階級は賃金にもとづく雇用関係や肉体労働によって定義できる。しかし、中産階級はどう定義すればよいのか。
それでも19世紀半ばの中産階級の基準はかなり明確だった、とホブズボームはいう。
〈有給の上級公務員を除けば、この階級に属する者は次のいずれかであることが前提されていた。それは、資本もしくは投資による所得を有すること、および(あるいは)、労働者を雇って採算のとれる企業家として活動すること、ないし「フリー」の専門職の一員として活動することだ。〉
資本家、企業家、経営者、医者、大学教授、法律家、上級公務員などを含む、こうした中産階級は流動的とはいえ、確実に増えていた。それを階級と呼ぶのは、そうした仕事がしばしば世代によって継承されたためである。
この時代は学校教育が盛んになる。「学校教育は、特に、社会の中流および上流として認められる領域に入るための切符と、新しく上の階級に入った者に自分より下の階層とを区別するような風習を身につける方法を提供した」と、ホブズボームは皮肉な言い方をしている。
教育がさほど普及しない時代、旧支配階級はごく限られた家族によって政治や経済を支配していた。大学が価値をもったのは、そうした旧支配階級のためではなく、これから階級の階段を上ろうとする人びとのためだった。学校教育が中産階級としての身分を手に入れる手段となったのだ。
こうして大学で学ぶ学生の数は増え、中産階級の数も増えていく。経済学者グスタフ・シュモラーは、ドイツでは中産階級が人口の4分の1を占めるようになったとみていた。ゾンバルトは3500万人の労働者にたいして、中産階級は1250万人ととらえていた。
学校のなかでは、さらにランクやグループが形成されていく。そして、そこで形成された同窓会組織のような潜在的ネットワークが、経済的、社会的な人のつながりをつくっていった。高等教育は中産階級下層の子弟が高いレベルに上がるための階段を提供した。だが、それは農民の子弟や労働者の子弟には、ほぼ閉ざされていた、とホブズボームは書いている。
もともと中産階級は人びとの上に立つ潜在的主人だったといえる。ところが、俸給で働く管理職や重役、技術専門家などが中産階級の仲間入りするようになる。職人や小商店主などの旧来のプチブルに加えて、膨大な新興プチブルも増えてくる。それは都市化にともなう現象だった。こうして、中産階級は上層と下層にわかれることになる。そのギャップはとてつもなく大きかった。
そうした階層を区分けする基準は、居住場所や住居であったり、教育やスポーツであったりした。もともと貴族のスポーツだった狩猟や射撃、競馬、フェンシングが中産階級に取り入れられ、さらに自動車、ゴルフ、テニスなどが流行するようになった。
19世紀終わりから20世紀初めにかけては、中産階級末端に属するホワイトカラーが増えてくる。さらに、その上には専門職や管理職、重役や上級公務員などがいた。直接事業にかかわるブルジョワは比較的少数になるいっぽう、とてつもない配当を得る大金持ちや大富豪が存在した。
大富豪でなくても、ブルジョワの世界に属する人びとの生活は潤沢だった。召使いと女性家庭教師を雇い、豪勢な家に住み、年2回長期休暇をとり、さまざまな趣味やスポーツにふけることができた。それがロックフェラーやモーガン、カーネギーになれば、まさにけたちがいの生活が待っていた。あとは慈善事業のために資金を提供するくらいしかなかっただろう。
急速な工業化がブルジョワ階級に自信をもたらしていた。労働者を治める力もじゅうぶんにあると感じられた。だが、すでに混迷ははじまっていた、とホブズボームはいう。
20世紀にはいると自由主義は分裂、衰退し、ナショナリズム、帝国主義、戦争が浮上してくるのだ。
「女性の解放」がはじまるのは19世紀終わりからだ、とホブズボームは書いている。だが、解放は先進国の中産階級と上層階級にかぎられていた。
先進国は低出生率、低死亡率の社会に移行しようとしていた。乳児死亡率は大きく低下する。女性の晩婚化が進み、計画的な避妊が普及した。それによって、子供の数が制限されていく。
工業化以前は、大半の男女が家庭の枠内で、それぞれ仕事を分担していた。農民は料理や子育て以外に農作業でも妻を必要とした。手工業の親方や小店主は商いのために妻を必要とした。
プロト(前段階)工業化のなかで、家内工業や問屋制家内工業が成長すると、女性や児童がそれに加わるようになる。だが、その後の工業化によって、労働の場が家庭から切り離されると、外で働いて稼ぐのは男の役割となり、女は家計のやりくりと家事、育児を引き受けることになった。
全体として19世紀の工業化は、公の経済から既婚女性を締め出す課程としてとらえることができる、とホブズボームはいう。そして、女性たちは政治の世界からも締め出されていった。
だが、男の収入だけでじゅうぶんな所得が得られない場合は、女も子供も安い賃労働ではたらかなければならなかった。いっぽう、未婚女性の仕事は増えていた。織布や縫製、食料品製造の仕事もそうである。女中奉公は衰退したが、その代わり商店や事務所の雇用が増えた。初等教育が発展すると、多くの女性が教師としてはたらくようになる。
大半の労働者階級の女性は厳しい無権利状態のもとで労働していた。しかし、中産階級の女性のあいだから参政権を含め女性解放の動きが出てくる。
フェビアン協会が結成されたのは1883年である。会員の4分の1が女性だった。
「新しい女性」が出現するこの時代、たしかに女性の経済的重要性が増していた。大量消費を必要とする資本主義経済のもと、広告産業は女性に焦点を合わせなければならなかった。家庭の必需品は種類が増えたものの限られていた。化粧品とかファッションなどの贅沢品は、中産階級の女性たちが相手だった。
19世紀終わりから20世紀はじめにかけ、女性の地位と願望にめざましい変化があったのはたしかだ、とホブズボームは書いている。女子のための中等、高等教育が発展した。社会活動の自由も広がった。社交ダンスが盛んになり、ファッションが変わり、スポーツが楽しめるようになった。女性向けの小説、女性向けの雑誌や記事も増えてきた。
フェミニストの運動は戦闘的ではあったが、ごく小規模なものだった、とホブズボームは指摘する。運動に加わるのは、中産階級の女性たちの一部に限られていた。多くの女性たちは婦人参政権、高等教育を受ける権利、専門職に就く権利、男性と同じ法的地位や権利などにさほど関心を示さなかったという。
解放を願う多くの女性はフェミニズムより教会、あるいは社会主義政党に向かったという。教会は女性の権利を擁護した。そして、一部の有能で前衛的な女性は政党に加わった。だが、圧倒的大多数の女性は、女性らしさと共存できる活動に向かった。医者になる女性も増えていく。
政府は婦人参政権運動を妨害していた。婦人参政権は、女性の大規模な運動を結集できるような運動ではなかった。それでもイギリスとアメリカでは徐々に大きな支持を得ていく。
女性解放のもうひとつの柱は性の解放である。上流世界では、プルーストの小説にみられるように、性の選択の自由が認められようとしていた。自由恋愛も奨励されるようになった。だが、それはしばしば問題を引き起こした。
1880年代にはガス調理器が普及しはじめ、1903年には「真空掃除機」が登場し、1909年には電気アイロンが登場する。クリーニング業も機械化された。幼児学校、保育所、給食も普及していく。だが、それで問題が解決したわけではなかった。
仕事と家庭の両立はむずかしかった。結婚しない女性も増えてきた。仕事を選んだ女性は大きな代償を払わねばならなかった。
それでは帝国の時代に、はたして女性の地位はどれほど改善されたのか、とホブズボームは問う。多くの職業や専門職に就く突破口が開かれたのはたしかである。選挙権に象徴される平等の市民権もまもなく手にはいる。だが、賃金の平等という問題では、大きな進展はなく、男性よりはるかに低い賃金に甘んじなければならなかった。
この時代、解放という点で進展が見られたのは、社会的地位を得た中産階級上層の女性と、結婚前のはたらく若い女性たちにとどまる。新旧のプチブルや中産階級下層の女性、そして労働階級の女性にとっては、解放はほど遠い問題だった。だが、女性の解放とはそもそも何なのか。その答えはまだ出ていない、とホブズボームは述べている。



