西鶴の話(4)──商品世界ファイル(22) [商品世界ファイル]

商売には浮き沈みがあるという話を書きました。とはいえ、資本の発展にもっとも重要なのは、商品の動きをつかむことであり、それには場所と時代が関係してきます。西鶴の『日本永代蔵』も、商売の盛んな場所とその特異性を追いかけています。
ここではマルクスのえがく乱暴な原始的蓄積とはことなる、地道でこつこつとした資本蓄積の姿がとらえられています。
泉州(いまの大阪府南部)の唐金屋(からかねや)は大船をつくり、北国の海を乗り回して、難波(なにわ)に米を運び大儲けした、と西鶴は記しています。
大坂が日本一の港となったのは、北前船に加え、瀬戸内航路でも西国から大量の米が運ばれていたからです。米の相場は北浜(のち堂島)の米市で決まります。
米は当時、最大の商品でした。各藩の財政は年貢によって支えられており、物納された米は大半が売却され、貨幣に代えられます。各藩の米を扱う鴻池や淀屋が実質上、金融業者となり、大名にカネを貸すようになるのは必然でした。
運ばれた米は町で消費されました。なかでも、江戸、大坂、京都が3大消費地でした。もっとも、人の生活は米だけあれば足りるというものではありません。人がくらしていくには、衣食住それぞれの支えがなくてはなりません。
町では、それに応じて、さまざまな商品が生みだされ、貨幣を仲立ちとして、商品を売り買いすることによって、生活が成り立つ仕組みができあがります。こうした商品をつくりだす職人や、それを売る商人が増えて、市場に出回る商品が多くなるにつれて、町は繁盛することになります。
そして、かつてはほぼ自給自足していた村が、こんどは町のために商品をつくるようになり、また町の商品を買うようにもなって、貨幣経済が全国に行き渡り、商品世界が拡大していくことになります。
大坂が画期的なのは、商売のネタがどこにでも転がっていることだ、と西鶴は書いています。たとえば、大坂では蔵がいっぱいになって、米俵を置ききれないと、外に置いておくことがあります。俵を運搬しなおすたびに、米がこぼれ落ちます。そのこぼれ米を集めている老女がいました。貧しそうな憐れな老女の姿をみて、それをとがめる者はいません。ところが、老女は集めた米をためて、こっそり売り払っていたのです。そのうちに、へそくりがたまりにたまって、20年あまりのうちに12貫500目(いまの金額にして2000万円以上)になったといいます。
この資金を元手に、老女のせがれは今橋のたもとで銭店を開きました。銀貨などを小銭に両替する商売です。それが繁盛して、この息子はいっぱしの両替商になりました。(巻1の3)
着物も重要な商品です。
昔とちがって、服装はしだいにぜいたくになり、人は万事不相応に華麗を好むようになった、と西鶴は書いています。太平の世の到来が、服装にも大きな変化をもたらしていました。
西鶴によれば、京都室町の仕立屋は、腕のいい多くの職人をそろえていました。人びとはここに絹や木綿の反物を持ちこんで、着物をつくってもらうようになります。元禄のころから、上等の着物の仕立ては家でやらず、だんだん専門の職人にまかせるようになっていたようです。
江戸では本町(日本橋本町)に呉服屋が並んでいました。いずれも京都の出店です。こうした呉服屋の番頭や手代は、得意先の大名屋敷に出入りして、抜け目なく商売をしていました。
ところが、次第に世の中がせちがらくなり、大名屋敷も入札で、業者に品物を請け負わせるようになります。そのため呉服屋はもうけの幅が少なくなります。しかも、当時は掛け売りが一般的だったので、こげつきの恐れもありました。このままでは、算盤が引きあわなくなり、店の経営が苦しくなる、とみんなが心配する矢先のこと。
そこにさっそうと登場したのが、三井九郎右衛門(正しくは八郎右衛門高平[1653〜1738]、西鶴はわざと仮名にしています)という男です。伊勢松坂から進出し、豊富な資金力を背景に、天和3年(1683)、日本橋駿河町に越後屋という大きな新店を開きました。
すべて現金掛け値なしと決め、それぞれ品ごとに専門の手代40人を担当させて、商売をはじめたのですが、これが大評判になりました。現金売りですが、ほかと比べて安いし、品揃えが豊富、端切れでも売ってくれるし、急ぎの羽織なども即座に仕立ててくれます。毎日平均150両(いまでいえば1700万円近く)の商いをしている、と西鶴は書いています。
三井の越後屋が、現在の三越へつながることは、つけ加えるまでもないでしょう。(巻1の4)
ここで場所は京都に移ります。狭い借屋暮らしをしている大金持ちがいました。藤屋市兵衛、通称、藤市です。
世渡りの基本は万事ぬかりないことだ、と西鶴は書いていますが、藤市の特徴は、つねに情報を集めていたことです。両替屋、米問屋、薬屋、呉服屋の手代から、いつも銭や米の相場、長崎の様子を聞いています。繰綿や塩、酒の相場にも注意を怠らず、それをメモしていました。
藤市は京都の室町通御池之町(おいけのちょう)に店をだし、長崎商いで2000貫目(いまでいうと36億円)の財をなした大商人です。
そのしまつぶりは徹底していました。
身なりはこざっぱりしていましたが、質素でした。絹物もほとんどもたず、紋服もありきたりのもの。野道でセンブリなどをみつけると、これは腹薬になると持ち帰るほどです。正月用の賃餅もぬくもりの冷めた餅を目方で買います。冷めたほうが目方が減るというのがその理由でした。
茄子(なす)の初物も買うのは少しだけ。家の空き地には、もっぱら実用的な草木を植えています。娘も寺子屋に通わせることなく、家で手習いを教え、とうとう京でいちばんの賢い子に育てあげました。親がしまつなのを知って、子も人の世話にならず身の回りのことは自分でする習慣を身につけ、華美な遊びにはまったく染まりませんでした。
正月に客がたずねてきて、藤市に世渡りの秘訣を聞きました。藤市は丁寧に教えます。客はそろそろ夜食がでるころだと期待します。「そこを出さぬのが長者になる心がけだ」と、釘を刺すところに藤市の本領があります。
むだな出費を抑え、地道に資本の蓄積に努めることが商売の秘訣でした。(巻2の1)
次の場所は山形の酒田です。
日本海に面し、最上川河口に位置する酒田は、江戸時代、北前船の寄港地としてにぎわっていました。
鐙屋(あぶみや)は、その酒田を代表する廻船問屋で、現在もその屋敷が残っています。鐙屋という名前からは、もともと馬方が宿泊する宿だったことがうかがえます。
西鶴も、鐙屋はもともとちいさな宿屋をしていたのが、万事行き届いているので、諸国から多くの商人が集まるようになったと書いています。そして、鐙屋は、そのうち米や紅花などの買問屋も営むようになりました。
問屋が失敗するのは、商品が売れると見越して、無理な商いをするからです。その点、鐙屋は堅実で、客の売り物、買い物をだいじにし、客に迷惑をかけることもなく、たしかな商売をつづけました。
カネ(貨幣)の流通と、もの(商品)流通は連動しています。日本海と瀬戸内海を往復して、北国・出羽(のちには北海道まで)と大坂を結ぶ北前船の西廻り航路は、寛文12年(1672)に、河村瑞賢によって開発されました。
これによって、出羽、北陸の米が安全かつ容易に大坂に運ばれるようになります。その航路は、すでに開発されていた江戸に向かう東廻りと連結し、これにより江戸時代初期に、本州を一周する航路が完成しました。
当初の目的は、大坂と江戸に年貢米を輸送することでした。しかし、輸送されたのは米だけではありません。商品の数や量がどんどん増えていきました。
酒田からは内陸の特産品、紅花が大坂へ運ばれ、上方からは木綿や砂糖、着物、道具などが入荷し、東北各地に流れていきます。
交易の発展は、商業の中心地と地域を結び、地域の発展を促していきます。江戸時代のはじめには、そんな好循環がはじまっていました。
酒田はそんな流通を担う北前船の一大寄港地でした。その船数は天和年間(1681〜83)で、毎年、春から9月までで3000艘におよんでいたといいます。
鐙屋は北前船の交易にたずさわる商人に宿を提供するところから出発し、買問屋として商人の欲しがる物品を集め、それを売ることによっておおいに繁盛しました。その亭主と女房は万事如才なく、客の機嫌をとり、並々ならぬ才覚と度胸によって商売を取り仕切っていた、と西鶴は記しています。(巻2の5)
江戸で一旗揚げる話もあります。
ある文無しの男が江戸にやってきました。まずは日本橋の南詰めに1日立って、人の群れを観察してみることにしました。祭でもないのに大勢の人が行き交い、大通りも往来の人であふれています。だれか財布でも落とさないかと目を皿にしてみていましたが、さすがにそんな人はいません。なるほど、カネを稼ぐのは容易ではないと、いまさらながら気づかされました。
元手がなくてもかせげる仕事はないかと思案しているうち、ある日、男は大名屋敷の普請を終えた大工の見習い小僧たちが、かんなくずや檜の木っ端をぽろぽろ落としていくのに気づきました。それを拾っていくと、ひとかたまりの荷物ができました。ためしに売ってみたところ、手取りで250文(7000円たらず)になりました。
足もとにこんな金もうけの種がころがっていたとは、と男はびっくりします。それから、木屑や木っ端を集めつづけました。雨の日には、木屑を削って、箸をつくり、須田町や瀬戸物町の八百屋に卸売りをするようになりました。それが箸屋のはじまりです。
こうして、この男、箸屋甚兵衛は、しだいに金持ちになり、ついには材木屋をいとなみ、材木町に大きな屋敷を構えるようになったといいます。持ち前の度胸で、手堅く材木を売り買いして、40年のうちに10万両(108億円)の財産を築いたと伝えられます。
そして70歳をすぎてからは、それまでの木綿着物を飛騨紬に替え、江戸前の魚の味も覚え、築地本願寺にも日参し、木挽町の芝居を見物し、茶の湯をもよおしたりして、余生をすごしました。
人は若いときに貯えて、年を寄ってから人生を楽しみ、人にほどこすことが肝心だ、と西鶴は教えます。カネはあの世にはもっていけません。しかし、この世でなくてはならないものはカネというわけです。
ここには徒手空拳から富を築き、晩年はゆっくり思いのまますごすという、いわば町人の理想がえがかれています。箸屋の場合は、江戸で大きな需要のあった木材の商売に致富のきっかけをつかんだのです。(巻3の1)
次の場所は大坂に接した堺の町です。
堺の樋口屋は世渡りに油断なく、むだ使いをしたことがありません。算盤を忘れず、家計はつましく、見かけはきれいにし、物事に義理がたく、しかも優雅です。
ある夜更け、樋口屋の戸をたたいて、酢を買いにきた人がいます。下男が「おいくらほど」と聞くと、客は「お手数ながら一文(30円)ほど」といいます。すると、下男はめんどうになり、「本日は閉めておりますので、あすにでもおこしください」といって、客を追い返してしまいました。
たまたまこのやりとりを聞いていた主人は、翌朝この下男を呼んで、門口を3尺(1メートル)ほど掘れと命じました。
下男は諸肌ぬぎになって、汗水を垂らしながら、鍬で地面を掘ります。
「どうだ、銭はでてきたか」と主人。
「いや、小石と貝殻だけです」と下男。
これを聞いて主人はさとします。
「これだけ骨を折っても、銭一文も手にはいらないことがわかっただろう。これからは一文商いもだいじにしなさい」
主人は家業をまじめに勤めることがいかにたいせつかを説きます。借金があれば、毎日のもうけのなかからその分を取り置いて、まとめて月の返済にあてること、小遣い帳をつけてむだな買い物をしないこと、それからよほど困ったときは外聞にかまわず思い切った処理をし、また一から出直す覚悟をすることなどを下男に教えました。
西鶴は、堺では成金はまれで、親から二代、三代とつづけて、堅実な商売をしていると絶賛しています。
しかし、こうした堺の繁栄がいつまでもつづかなかったことを、西鶴はまだ知りません。港としての機能が次第に失われたことが、商業都市、堺の経済基盤を押し流していくことになります。(巻4の5)
長崎の繁栄もつけ加えておきましょう。
まず金平糖と胡椒の話です。
金平糖は高級輸入菓子で、南京から渡ってくる輸入品を高い値段で買っていました。これを何とか日本でもつくれないかと考え、その製法を見つけたのが長崎の人です。ケシ粒に少しずつ糖蜜をかけて粒をつくり、それをかきまぜながら、さらに糖蜜をかけて大きくしていきます。できあがるには2、3週間もかかるといいます。
原料は安いのに、製法がむずかしいため珍重された金平糖は、高い値がついて、おおいに儲かりました。まもなく男は金平糖づくりを女性たちにまかせ、自分は小間物店を開き、一代で千貫目(18億円)の財産を築いたといいます。
胡椒もまた中国から伝来した珍品でした。原産はインドです。だが、湯を通してあるため、それをまいても、木になりませんでした。しかし、あるとき高野山で3石もの胡椒をまいたところ、そこから2本だけ芽が出て木に成長し、それから日本でも栽培されるようになった、と西鶴は書いています。
ちなみに、中国から日本に胡椒がはいったのは8世紀半ばのことです。平安時代には山椒とともに調味料として利用されていました。
唐辛子より胡椒のほうが先に伝わっていたというのは意外に思うかもしれませんが、事実です。唐辛子は中南米が原産で、それが日本に伝来するのは、ようやく16世紀半ばになってからです。朝鮮には17世紀初めに日本から伝わったという説があります。
西鶴は長崎の隆盛をたたえています。季節ごとに中国から貿易船がはいってきて、糸や巻物、薬品、鮫皮、香木、諸道具、その他思わぬ珍品を運んできますが、どれも落札し、売れ残ることがありません。それを買う京、大坂、江戸、堺の商人たちは、商品への目利きがたしかで、しくじることがありません。
長崎の商売では、ひとつだけ注意しなければならないことがあります。それは海上の心配のほかに、いつ吹きだすとも知れない恋風がおこることだ、と西鶴は冗談めかして書いています。すなわち問題は、長崎に丸山という廓があることです。これはたしかに商売の妨げになったかもしれません。疑似恋愛の場所である遊郭とカネはたがいにひきつけあう要素をもっていたからです。
とはいえ、資本主義が恋の風と贅沢に結びついていることは、ゾンバルトも認めているところです。これに新商品への熱狂も加えるべきでしょうか。資本主義はケチと節約だけで成り立っているわけではなく、かならず消費と結びついています。
とうぜんながら、こうした資本主義の風潮と商人の台頭を苦々しく思っている人も数多くいました。そうした一人として、次に江戸時代の代表的儒者、荻生徂徠の考え方をみておくことにしましょう。
西鶴の話(3)──商品世界ファイル(21) [商品世界ファイル]

西鶴は『日本永代蔵』で商売の栄枯盛衰をえがいています。金持ちが転落するのは、一種の教訓となっていますが、そんな話ばかりではありません。なかには、挫折や失敗をへて、身代を立てなおしていく話もあります。そんな話をいくつか集めてみます。
京都の大黒屋は京都でも指折りの金持ちで、米問屋を営んでいました。その主人がそろそろ隠居しようと思うころ、長男の新六がにわかにぐれだします。色遊びにうつつをぬかし、半年もしないうちに170貫目(約3億円)もの穴をあけてしまいました。手代がなんとか帳尻をあわせて、盆前の決算を乗り切ったものの、その後も新六の道楽はやみません。
そこで、とうとう勘当ということになります。新六は伏見稲荷門前の借家に身を隠し、わが身を嘆く日がつづきました。年もおしつまった12月28日、風呂にはいっていると、血相を変えた親父さまが突然あらわれたので、ふんどしもつけず、綿入れを1枚引っ掛けて逃げだしました。たぶん、大黒屋に借金取りが押し寄せたので、親父さまの堪忍袋の緒が切れたのでしょう。
江戸に行こうと思っていました。1文もないので、道中苦労したことはいうまでもありません。生まれもった才覚で、何とか銭をかせぎだし、餓えをしのぎました。
江戸に着いたときは2貫300文(6万2000円ほど)残っていました。日も暮れかかっているのに、宿のあてもありません。そこで、新六は東海寺(北品川の禅寺)の門前で一夜を明かすことにしました。大勢の乞食がたむろしています。波の音が響いて、眠れないまま、みんなが身の上話をするのを聞くともなく聞いていました。
だれもが親の代からの乞食ではありませんでした。ひとりは大和の竜田の里から江戸に出たのだといいます。江戸にくだって、一旗揚げようと、わずかな元手で酒の店を開きましたが、これが大失敗。もうひとりは泉州堺の出身で、芸事で身を立てようとしましたが、商売になりませんでした。さらに別のひとりは江戸の生え抜きで、日本橋に大きな屋敷をもっていましたが、何せおカネを使うことしか知らなかったため、そのうち自分の家まで売ってしまい、乞食になったといいます。
話を聞いて、新六も身につまされるばかりでう。親に勘当された身を語りました。それにしても、これから江戸で生きていくにはどうすればよいか。カネがカネを生む世の中、元手がなくては商売もはじめられない。新六は話を聞いたお礼として、3人の乞食に300文(約8000円)ずつやって、たまたま知るべがあった伝馬町の木綿問屋を訪れ、それまでの事情を正直に話しました。
すると問屋の主人は同情してくれて、江戸でひと稼ぎするよう励ましてくれました。そこで、新六はまず木綿を買いこみ、手ぬぐいの切り売りをすることにしました。縁日に目をつけ、下谷の天神(寛永寺黒門近くにあった牛天神)に行き、手水鉢(ちょうずばち)のそばで売ったら、参詣の人が縁起をかついで、よく買ってくれました。
そんなふうに毎日工夫して、商売をつづけていたら、10年たたないうちに5000両(約5億円)たまって、金持ちなり、町の人からも尊敬を集めるようになったといいます。店ののれんには菅笠をかぶった大黒が染められていました。これが江戸の笠大黒屋のはじまりだ、と西鶴は話を結んでいます。(巻2の3)
大金持ちの息子から、勘当されて乞食どうぜんの身に、そしてまた大金持ちに。人生どんなふうに転がるかわからないものです。世をうらんでも仕方ない。けっきょく、自分で自分の道を切り開くしかないのだ、と西鶴は主張しているようにもみえます。
つづいてのエピソードは、駿河府中(いまの静岡市)本町にあった呉服屋、菱屋の話です。かつては繁盛し、大店をいとなんでいました。安倍川紙衣(かみこ[防寒などに用いた紙の衣])に縮緬皺や小紋をつけて売りだしたのが評判を呼んで、30年あまりのあいだに千貫目(18億円)の身代を築きました。
ところが、息子の忠助はまるで無能、収支も決算もせず、帳面もつけないというだらしなさで、店はたちまち倒産してしまいます。いったいにカネ儲けはむつかしく、減るのも早いものだ、と西鶴は書いています。
努力なくして、カネはたまらぬものです。しかし、ただの努力だけでも、カネはたまらないでしょう。商品を買う人が減れば、カネは逃げていくからです。紙子がいつまでもよく売れたとは思えません。
その後、忠助は浅間神社(現在の静岡市葵区)の前の町はずれで、借家住まいをする身となりました。親類縁者も寄りつかず、かつての手代も音信不通となり、悲しい日々を送っていました。
かといって、はたらくわけではありません。小夜(さよ)の中山にある峰の観音にお参りに行き、「もう一度長者にしてくだされ」と願って鐘をつくのがせいいっぱい。そんな男を観音さまが助けてくれるわけもありません。
しかし、さすがに何もしないのでは、日々のくらしが成り立ちません。そこで忠助は竹細工の名人に習って、鬢水(びんみず[髪油])入れや花籠をつくって、13歳になる娘に町で売らせ、生計を立てていました。
ところが、あるとき、伊勢参りから帰る江戸の豪商が、たまたまこの娘を見初めたのです。そして、ぜひ息子の嫁にしたいと親元にやってきました。こうして忠助夫婦は娘ともども江戸に引き取られ、わが子の世話になる仕合わせな身の上となったといいます。まさに、ことわざにいうとおり、「みめは果報のひとつ」だ、と西鶴は結んでいます。
ほんとうにこんなことがあったのでしょうか。しかし、貧乏な家の娘がスカウトされて有名なタレントになるという話は、いまでもありそうですから、あながちなかったともいえません。
人生はまさに変転きわまりないのです。カネがカネを生む世の中で、人は翻弄されます。そのなかで、人生はしょせん一代かぎり、男も女も与えられた運をしっかり見定め、みずからの才覚で自分の道を切り開いていかなくてはならない、と西鶴は諭しているようにみえます。
京の染物屋、桔梗屋(ききょうや)の話も紹介しておきましょう。
正直一途に商売に励んできましたが、そのかいもなく貧乏暮らしがつづいています。
あるとき、やけをおこして、わら人形で貧乏神をつくり、これを神棚に祭って、元旦から七草まで精一杯もてなすことにしました。貧乏神でも家の神さま。毎日、仕事があって、食べていけるのも、そのおかげというわけです。
めったにないもてなしを受けた貧乏神は大喜び。七草の夜に、亭主の夢枕に立って、しきりに感謝を述べ、この家を繁盛させてやると約束しました。
しかし、貧乏神がこの家を繁盛させてやると告げたわけは何だろう、何か工夫できることがあるのではないか、と桔梗屋は考えました。
染めといえば紅(べに)です。紅染めは山形の紅花で染めた本染めがいちばんですが、値段が高い。もっと安くできないものだろうか。
そこで桔梗屋はいろいろ工夫を重ね、蘇芳(すおう)で下染めし、それを酢で蒸し返すと、本染めと遜色のない中紅(なかもみ)ができあがりました。
桔梗屋は染めあがった品物をみずから担いで江戸に下り、本町の呉服屋に売りさばきました。しかし、手ぶらでは帰りませんでした。京に戻るさいには、奥州の絹と綿を仕入れて、それを京で売ったのです。
いまでは桔梗屋は一家75人を指図する大旦那となり、長者町(いまの上京区仲之町)に大屋敷を構えるまでになりました。
製造と流通の工夫で財をなした桔梗屋甚兵衛は延宝9年(1681年)に亡くなっています。西鶴の話は、どれも実際にあったことです。(巻4の1)
筑前博多の商人の話も取りあげておきましょう。この人は不運なことに1年に3度まで嵐にあって貨物を失い、すっかり元手をなくしてしまい、家でぼんやり暮らしています。
あるときのことです。ふとみると、クモが杉の梢に糸を張ろうとしています。外は強い嵐。クモの糸はたちまちちぎれてしまいます。だが、何度失敗しても、クモは糸をくりだし、ついに巣をつくりあげました。
男はそれに心打たれます。「気短にものごとを投げだしてはいけない」と思い、家屋敷を売り払い、それを元手として、ひとり長崎にくだりました。
ようやく伝手を見つけて、長崎博多町の入札市にはいりこみ、舶来の唐織や薬、鮫皮[刀の鞘に用いる]、諸道具に出合いました。買えばもうかるとわかっています。しかし、それを買うだけの資金がありません。みすみす京や堺の商人に品物をさらわれてしまいました。
やけになった男は、丸山の遊郭にでかけました。昔はぶりのよかったころに出会った花鳥という太夫を揚げて、一夜かぎりの遊びおさめにしようと思ったのです。
花鳥の部屋にあがります。だが、そこに立てられている枕屏風をみているうちに、そのみごとさに見とれてしまいました。よくみれば、ほんものの定家の小倉色紙が6枚も張ってありませんか。
それから男は明け暮れ花鳥のもとに通いづめ、すっかりなじみになり、ついにその屏風をゆずってもらうことに成功します。男はそれを持って上方におもむき、さる大名にこの古屏風を献上して、かなりのカネを下げ渡されました。それを元手として、ついには長崎でも知られる金屋(かなや)という大貿易商になったといいます。
これだけなら、遊女をうまくだましてカネもうけした悪い男の話で終わってしまいます。しかし、西鶴は男が花鳥を身請けして、思う男のところに縁づけてやったという逸話をつけ加えています。遊女も「このご恩は忘れませぬ」と、男に感謝したといいます。これなどは、回りまわって、カネが人を救う話になっています。もちろん、その逆もおおいにありうることですが。
亭主が亡くなって、残された後家が店を再建する話も記録されています。
松屋は奈良の春日の里で、晒布(さらしぬの)の買問屋を営んでいた。ちなみに、晒布は麻や木綿でつくる反物で(木綿のものが更紗)、奈良の特産品でした。松屋はその晒布を買って、諸国の商人に売る商売をしていました。
ところが、あいにく、その主人が平生の贅沢と不摂生がたたって、50歳で早死にしてしまいます。あとに残されたのは38歳の後家と幼い子どもでした。悪いことに、だいぶ借金も積もっていました。
器量よしにもかかわらず、後家は再婚せず、髪を短くして、白粉(おしろい)もつけず、懸命に亡き夫の後始末に奔走しました。
借金は銀5貫目(およそ900万円)ほどでした。最初は借金を返済するため、多くの債権者に自宅を引き渡すつもりでした。しかし、だれも受け取ろうとしません。その処理がめんどうだったのと、母子をいきなり追いだすような不人情をしたくなかったからでしょう。
そこで、後家はこの家を頼母子(たのもし)の入札(いれふだ)で売ることにした。1人から銀4匁(約7200円)ずつ受け取って、札にあたった人にこの家を渡すことにしました。いまでいう宝くじのようなものです。
すると3000枚の札がはいって、後家は銀12貫目(約2100万円)を受け取ることになりました。札にあたったのは、人につかわれていた下女で、彼女はめでたくこの家を受け取ることになります。後家はこれで5貫目の借金を払って、残った7貫目(約1260万円)を元手に商売をはじめ、ふたたび金持ちになったといいます。女性社長の誕生です。(巻1の5)
これは才覚によって、降りかかってくる苦難を乗り越える話です。「永代蔵」には、困ったときの知恵袋のような話が、随所に盛りこまれています。
どんなに困窮していても、地道に努力し、工夫を積み重ねていれば、いつか幸運が舞いこんでくるかもしれないという話です。
西鶴の話(2)──商品世界ファイル(20) [商品世界ファイル]

『日本永代蔵』には、タイトルとは裏腹に、いかに蔵(資産)が永代につづくのがむずかしいかが、数多くえがかれています。まさに、ビジネスは栄枯盛衰といえるでしょう。
よくでてくるのが、親の築いた身代を息子がつぶしてしまうという、ありがちのパターンです。いちがいに責められないような気もします。息子には家を守って、商売を広げるよりも、パアっとカネを使って、遊びまくるほうが楽しかったのでしょう。カネの力はおそろしいものです。そして、それはどこか空しさを秘めています。
たとえば、こんな話が出てきます。
場所は京都です。商売一筋、2000貫(いまなら36億円)をためこんで亡くなった父親の跡を21歳の息子が継ぎました。この息子も最初は倹約家で、商売熱心でした。
ところが、父親の墓参りから戻る途中、禁裏[御所]の薬草園のそばで、封じ文を拾ったところから、歯車がくるいはじめます。この封じ文はどうやら花川という島原の遊女に、客のひとりがあてたもので、そのなかには一歩金(約3万円)と、詫び状らしきものがはいっていました。
このままネコババするのもまずいと思いました。そこで、男はそれまでいったことのない島原に行き、花川という女郎を訪ねます。花川には会えませんでした。このところ気分が悪く引きこもっているといいます。
そのまま引き返せば、なにごともおこらなかったはずです。しかし、ここでついむらむらした気分が顔をのぞかせます。せっかく評判の島原に来たのだから、一生の記念に遊んでいこうと思ったのです。そこで、男は出口の茶屋にあがり、安上がりの囲い女郎を呼んでもらい、飲みつけぬ酒に酔いました。
これが転落のはじまり。若旦那はだんだん悪い遊びを覚え、値の張る太夫買いまでするようになります。太鼓持ちに囲まれ、「扇屋の恋風さま」とおだてられ、連日、散財するうちに、あっというまに財産をなくしてしまいました。(巻1の2)
金持ちがいたのは京大坂だけではありません。
大和の朝日村(現在の天理市佐保庄町)に、川端の九助という小百姓が住んでいました。九助は50歳すぎまで、田を耕し、毎年決まって1石2斗の年貢米を収める地道なくらしをつづけてきました。
節分には、窓に鰯(いわし)の頭や柊(ひいらぎ)を差し、豆まきをして、鬼を払い福を招くのが恒例でした。ある年、豆まきで庭に散らばった豆をひろい、それを野にうずめてみました。すると、不思議なことに芽が出て、葉が茂り、両手にあまるほどの豆がとれたのです。
毎年、その豆をまいていると、10年後には88石もの収穫が得られるようになり、それを売ると、大きな収入が得られました。
九助はこの収入で、田畑を買い集め、ほどなく大百姓になりました。作物に肥料をほどこし、田の草をとり、水を掻いて手入れをするので、稲もたわわに実り、木綿もたっぷりと取れるようになりました。
九助はさらに工夫を怠りませんでした。田を耕す細攫(こまざらえ)をこしらえ、唐箕(からみ)や千石通しを発明し、さらには穂を扱く後家倒しといわれる道具も発明しました。唐弓を導入し、繰綿(くりわた)を買いこみ、大勢でそれを打って、江戸に打綿の荷を積みだすようにもなりました。
こうして九助は大金持ちとなりました。88歳で亡くなったときには家屋敷のほか1700貫目(約30億円)もの財産を残していたといいます。
その財産はそっくり息子の九之助が受け継ぎました。金持ちの息子というのは、どうして同じようなパターンをたどるのでしょう。九之助にとって興味があるのは、カネを稼ぐことではなく、もっぱらカネを使うことでした。多武峰(とうのみね)の麓の村に京大坂の飛子(とびこ[男娼])の隠れ家があると聞いて、さっそく通いつめて、男色にはげみます。それから奈良の廓、京の島原にも足を伸ばし、女色にもふけりました。
こうして九之助は酒色の道におぼれるようになるのですが、8、9年のうちにすっかりからだを壊し、34歳で頓死してしまいます。あとには男子が3人残されました。その遺言状を開いてみて、みんながあきれかえりました。親譲りの1700貫目は使い果たし、残ったのは借金だけだったのです。(巻5の3)
道楽息子に跡をとらせるくらいなら、できのよい養子をとったほうがいいと思うのも不思議ではありません。ところが、その養子がくせものでした。
美作(みまさか[現在の岡山県])の津山に、万屋(よろづや)という金持ちがいました。
その万屋のひとり息子は、鼻紙にぜいたくな杉原紙をつかっていたというので、13歳のときに勘当され、播州網干(あぼし[現姫路市])の叔母のところにやられてしまいます。万屋を継いだのは、倹約(しまつ)で知られる甥っ子です。
養子になったこの甥っ子は変わっていて、嫁に焼き餅やきの女を望みました。そして、そのとおり焼き餅やきの娘をもらい、先代は隠居しました。跡取りがすこし浮かれて遊びはじめると、嫁は焼き餅をやいて騒ぎ立てるので、世間体が悪く、その行状もおさまります。これで家が万事おさまると、先代も喜んでいました。
ところが、万屋の老夫婦が亡くなると、いっぺんに様子が変わってきます。伊勢参りに出かけた嫁は、帰りに京大坂を見物し、それ以来すっかり派手好みになりました。亭主もからだの調子が悪いので養生したいといっては上方にのぼり、男色女色のふた道にふけって、金銀をまきちらすようになります。こうして、万屋の身代は一気に傾いていきます。
その後、万屋は両替屋をはじめるが、うまくいきません。信用もなくなり、次第に没落していきます。(巻5の5)
時勢の移り変わりもあったかもしれません。しかし、どうやら大金持ちの二代目、三代目というのは、カネ儲けに意義を見いださなくなってしまうようなのです。カネは儲けるより使うほうがおもしろいに決まっています。それはどう用心しても、商家にしのびこんでくる誘惑でした。
カネの世は移ろいやすく、富豪の家もいつまでもつづきません。
それが江戸時代の浮世でした。
豊後の府内(いまの大分市)にも万屋という富豪が実在しました。
その家督を継いだ三弥は、新田を開墾し、菜種を植えたところ、これが大成功して、大金持ちになりました。灯火に使われた菜種油は当時の大ヒット商品です。
ところが、この三弥、京都の春景色を見物にいったあたりから、だんだんと遊興の味を覚えるようになります。豊後に戻ってくるときには美しい妾を12人連れてきました。屋敷を新築して、ぜいたくのかぎりをつくし、冬の朝は優雅に雪をながめ、夏の夕涼みには多くの美女をはべらせて、扇で風を送らせるという日々。
店をまかせていた古参の手代が亡くなると、三弥のぜいたくはますますエスカレートします。これではおっつけ暮らしも立たなくなるだろうと周囲がやきもきしていたところ、案の定、ある年、収支に不足が生じ、それからしだいに穴が大きくなっていきました。そして、ついには罪をおかし、殿様からとがめられ、命まで失うことになった、と西鶴は書いています。
じっさい、豊後では、こういう事件があったようです。「永代蔵」の注には、万屋の3代目、守田山弥助は、藩主日根野吉明(ひねの・よしあきら)によって、正保4年(1647年)10月、密貿易や奢りのかどで、一族5人とともに誅されたとあります。(巻3の2)
いったい何があったのでしょう。その真相はわかりません。
幕藩体制は、商品世界の広がりになかば懐疑的だったといえるのではないでしょうか。
参勤交代がおこなわれ、武士が都市に集住する時代においては、武家政権を維持するには、年貢の米を正常に換金化することが欠かせませんでした。
しかし、それ以上に商品世界が広がることに、武家はむしろ懸念をいだいていたといえるでしょう。三井や鴻池、住友のように幕藩体制に密着する商人とちがい、カネの力によって自由に羽を広げようとするブルジョアは、何かにつけて取り締まろうという傾向が強かったのではないでしょうか。
西鶴を読んでいると、経済学でいう資本蓄積論とは別に資本解体論とでもいう項目を立てたほうがいいのではないかと思うくらいです。
西鶴の話(1)──商品世界ファイル(19) [商品世界ファイル]

井原西鶴(1642〜93)の『日本永代蔵』が出版されたのは元禄元年(1688年)のことです。それを暉峻康隆(てるおか・やすたか)の現代語訳で読んでみます。
「大福新長者教」というサブタイトルがついています。サブタイトルからすれば、長者すなわち金持ちになるための読本です。もっとも、この本を読んだからといって、金持ちになれるとは限りません。あくまでも惹句ですね。
全6巻30のエピソードからなっています。元禄時代の経済社会ルポといえるでしょう。一部仮名にしてあるところ(たとえば三井八郎右衛門を三井九郎右衛門にするなど)もありますが、店の名前もしっかりと記されていて、全部実話です。体系化されているわけではありません。1巻出すたびに評判を呼んで、書き足しているうちにそれが6巻になったという次第です。日本各地の富豪の由来と、時にその没落をえがくという手法は、当時の人にとっても興味津々の話題でした。
全部おカネにまつわる話です。おカネが人を動かす時代がはじまっていました。西鶴はそれを時にユーモラスに、時に憐れ深くえがいています。
おカネはあの世では役に立たないが、おカネがあればこの世でかなわぬことはまずない。残しておけば、子孫のためにもなる。だから、よく働いて、おカネをためよう。
西鶴は最初にそんなふうに書いています。このあたりの感覚はいまも変わらないですね。
江戸時代はまだ農業が中心(全人口のうち農民の割合が8割以上)とはいえ、それでも商業と流通の発達した時代です。大きな町も生まれ、商売が盛んになっていました。
当時、最大の商品は何といっても米です。幕府をはじめ各藩の財政は年貢によって支えられており、物納された米は大半が売却され、貨幣に代えられていました。その貨幣は大半が江戸藩邸で使われます。各藩の米を扱う鴻池や淀屋などの大商人が実質上、金融業者となり、大名にカネを貸すようになるのは必然でした。
運ばれた米は町で消費されます。なかでも、江戸、大坂、京都が3大消費地でした。もっとも、人の生活は米だけあれば足りるというものではありません。人がくらしていくには、衣食住それぞれの支えがなくてはならないはずです。
町では、それに応じて、さまざまな商品が生みだされ、貨幣を仲立ちとして、それらの商品が売り買いされることによって、生活が成り立つ仕組みができあがっていきます。こうした商品をつくりだす職人や、それを売る商人が増えて、流通する商品が多くなるにつれて、町は繁盛することになります。
そして、かつてはほぼ自給自足していた村が、こんどは町のために商品をつくるようになり、町の商品を買うようにもなって、貨幣経済が全国に行き渡り、商品世界が拡大していくわけです。
江戸時代には、そんな商品世界が広がりをみせようとしていました。
しかし、商品を売ったり買ったりするには、もちろんおカネが必要です。
江戸幕府が金・銀・銅の三貨からなる貨幣制度を整えたのは17世紀前半といわれます。
ただし、江戸時代を通じて、完全な通貨統合は実現できませんでした。金建て(単位は両)の江戸にたいし、大坂(上方)は銀建て(単位は貫)であり、両者のあいだには為替レートのようなものが発生しました。つまり、ひとつの国に金建てと銀建ての地域が併存していたわけです。
そのなごりは「ちんぎん」に賃金と賃銀の表記があることをみてもわかるでしょう。貨幣をカネというのも、金銀銅の三貨(3種の金属貨幣)を念頭においているからですね。
銭貨(庶民貨幣)としての寛永通宝が発行されはじめたのは寛永13年(1636年)のことです。これによって、中世を通じて世間で用いられていた皇朝銭[日本製]や永楽銭[中国製]、その他さまざまの銭貨は次第に排除されていきます。
あまり、ややこしい話はしたくないのですが、江戸幕府が成立することで、曲がりなりにも統一された貨幣制度がつくられ、それによって商業が盛んになって、商品世界がだんだんと広がっていくという構図をまずは思いえがいておけばよいでしょう。
でも、それは近世ではあっても近代ではありませんでした。資本主義も金融システムも未発達ですし、産業革命も生じていません。近代国家も誕生していませんでした。租税の基本は貨幣ではなく米でしたし、職人はいても近代のような労働者は誕生していません。資本と経営もまだ未分化の状態でした。
それでも商業は活発になっており、貨幣はなくてはならないものになっています。おカネがあれば何でも買える。しかも、そのおカネは貯めることもできる。その意味では、たしかに新しい時代がはじまっていたのです。
おカネが日本じゅうどこでも通用するようになったのも江戸時代の特徴です。しかし、それが集中する場所はおのずと決まっていました。
まず三都といわれた江戸、大坂、京都です。その周辺の淀や伏見や堺。それから中国・オランダとの窓口である長崎、さらには博多、敦賀、酒田、大津などの港町。これらの町が『日本永代蔵』の主な舞台です。
人の欲望はかぎりありません。だが、目の前にそれしかなければ、どこかで満足してしまうものです。実際、欲望の対象が現前していなければ、欲望がかきたてられるわけもありません。まだ高度な産業が発達せず、手工業が中心の時代には、生みだされる商品の種類や量もごくかぎられていました。それでも、商品の誘惑は大きかったでしょう。
それと並行して、貨幣の誘惑ももちろん大きかったのです。どれだけおカネをもっているかで、金持ちかそうでないかが分かれました。しかし、おカネはもっているだけでは、減りこそすれ、けっして増えていくことはありません。ものや人と結びついてこそ、おカネは生きてくるのです。
商品世界においては、おカネを増やしたいという欲求があるからこそ、それを生みだす元となる商品も次々と開発をうながされます。こうして何もかもが商品化されていくようになります。西鶴が直面したのはそういう時代でした。
といっても、江戸時代にカネになる商品はたかがしれています。先ほどもいったように、最大の商品は米です。幕府や諸藩は租税として集めた米を売っておカネに換え、武士は俸禄(実質の給金)をもらってくらしています。おカネが必要なのは庶民も同じです。おカネは貯まればしめたものですが、まずは必要なものを買うことに使われます。欲と色が、カネを稼ぐための最大の動機だということを西鶴は知っています。
そのころの商品を思い浮かべてみましょう。江戸時代は250年以上つづきますから、そのかんに商品の種類も量も大きく変化しました。元禄のころをえがいた「永代蔵」には、次のような品物がでてきます。
まず、食の関係では、コメを筆頭に野菜や豆、魚(とりわけ高級なのは鯛や伊勢エビ)、鯨(食用だけではないが)。ほかに茶や菓子(舶来の金平糖も)、胡椒。それに忘れてはならないのが塩、醤油、そして酒(焼酎、清酒など)ですね。その他もろもろ。煙草もいれていいでしょうか。
衣の関係では絹や木綿、糸、晒布、染めもの(材料としての紅花その他)、着物や帯、櫛など。
住の関係では木材をはじめとする建築資材、その他、紙や家具、焼き物、台所用品、油や蝋、薪、うるし、それに鼠取りや灰掻き、五徳などの金物も挙げられるでしょう。
さらに貨幣の原料ともなる金、銀、銅も重要です。長崎では糸や唐織、鮫皮、薬、諸道具などの高級品が輸入されていました。
「永代蔵」にはえがかれていませんが、江戸時代はたたら製鉄が完成した時代で、鉄が刀や鉄砲、大砲などの武器をはじめ、農具やさまざまな日常品に用いられていました。
以上のように西鶴はずいぶん多くの商品をとりあげています。そして、これらの商品は、単なるものではなく、すべて人(家)や場所、運搬、軍事などと結びついていました。生産面で、町や村、鉱山などの役割が重要だったのはいうまでもありません。そのいっぽう、町では遊郭や芝居小屋、茶屋、宿場、店、寺社などがにぎやかな消費の場を提供していました。馬や船、駕籠は運搬手段として欠かせません。そして、それらはすべてカネ次第の世界に包摂されていったのです。
西鶴のいた時代には、すでに商品世界が生まれていました。けっして農業一色の時代ではありません。商品のラインアップをみただけでも、当時の生活ぶりが浮かびあがってくるようです。そうした世界を西鶴は興味津々の目でみつめています。その視線は世俗的で快楽主義的だったといえるかもしれません。しかし、そこにはどこか仏教的な無常感のようなものもまとわりついています。
以上は前置きです。なお西鶴の話にはよく寺社の話がでてきます。商売はただ儲ければいいというのではなく、寺社や信心と密接に結びついていたといえるでしょう。
それでは『日本永代蔵』の世界に。
ブローデルをめぐって(10)──商品世界ファイル(18) [商品世界ファイル]
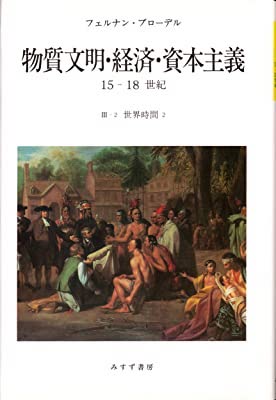
しめくくりとして触れたいのが産業革命についてです。
ブローデルは、ある推計にもとづいて1960年のドル換算評価で、18世紀における一人当たりGNPを、イギリスが150ないし190(1700年)、アメリカ大陸のイギリス植民地(のちの米国)が250ないし290(1710年)、フランスが170ないし200(1781〜90年)と推計しています。これにたいしインドは160ないし210(1800年)、日本は160(1750年)、中国は228(1800年)という数字をだしています。
1人あたりGNPに関しては、イギリス、アメリカ(イギリス植民地)、フランスと、インド、中国、日本はさほど変わらなかったことがわかります。それがなぜ19世紀に大きく変化して、西ヨーロッパと米国が優位を占め、インドや中国などが遅れをとっていくのでしょう。そして日本はなぜ急速にその遅れを取り戻していったのでしょうか。
その謎を、ブローデルは産業革命によって解き明かそうとしています。
産業革命は1750年代ないし1760年代にイギリスではじまって、現在もつづいている、とブローデルはいいます。さらに、産業革命は単なる経済的過程ではなく、生活のあらゆる分野とつながっているとも書いています。
それはとつぜんはじまったわけではありません。長い前段階があり、何度も失敗した前史がありました。
18世紀半ばから後半にかけ、イギリスで農業や商業、産業の面で何が起こっていたのかをみておきましょう。
まず農業についてみると、18世紀にはまだ農業は機械化されていません。半月形の鎌、長柄の鎌、殻竿(からざお)などが、農具として一般に用いられていました。機械が導入されるまでの農業の進歩は、耕作法や輪作、種の選択、牛馬の利用、収量を増大させる工夫によるものでした。
こうした農業改良は17世紀半ば以降に定着しました。加えてそのころから、農家は小麦栽培よりも牧畜に力を入れるようになります。それによって肥料がより多く供給され、小麦や大麦の収量が増大するという好循環が生じました。
1650年から1750年にかけ農業生産性は13%増加し、イギリスは小麦の輸出国になります。また、17世紀末から18世紀はじめにかけて、農村産業も発達しました。イングランドの各州で、レースや帽子、釘、紙などの製造産業が盛んになっていきます。
農業生産性の増大は、人口増を支えることになります。そのいっぽうで貧しい地方での手工業の発展は予備労働力を生みだしました。
イギリス農業の特徴は、領主体制が崩壊していたことです。大地主の貴族はみずからの土地を農地経営者(借地農)にゆだね、そこから地代を徴収し、加えて年金で生活することに甘んじていました。農地経営者は、大きな土地を運用し、賃金労働者を雇って、農業をいとなんでいました。
エンクロージャー(囲い込み)運動がさかんになると共有地は廃止され、大土地所有が進んでいきます。それが農業の効率化へとつながります。
イギリスでは、農業は早くから全国市場と結びついていました。農業は鉄工業の大きな需要先で、農家は鉄製の農具を数多く利用していました。
イギリスの人口は1700年には583万5000人、1790年には821万6000人、1850年には1800万人へと増加していきます。その間、出生率は上昇し、死亡率は低下していきました。
農村は豊かになり、都市は膨張し、産業従事者数が増えていきます。都市は活気に満ちていました。そのいっぽうで、貧困と悲惨さも際立っています。
産業革命を導いたのが技術だったことはまちがいありません。しかし、その技術も生産と結びつき、需要に支えられなければ、ほとんど空振りに終わってしまったでしょう。
その点、織物業ではめざましい進展がありました。杼(ひ)の開発もないがしろにできません。これによって織りのリズムが加速されたからです。
さらに1765年ごろに発明されたジェニー紡績機、1769年ごろのアークライトの水力機、1779年のクロンプトンによるミュール紡績機が大きな技術革新をもたらしました。これによってイギリスでは、紡績の速度が10倍になり、アンティル諸島(のちには北アメリカの南部植民地)やインドなどからの綿花輸入量も倍増しました。
冶金業についていうと、コークスによる溶鉱法は1709年に発明されていたもののあまり普及せず、18世紀半ばをすぎても、鉄は大半が木炭利用の高炉でつくられていました。コークスを使うほうが、生産費が高くついたからです。
しかし、鉄の需要が増えると、木炭の価格が上昇し、いっぽうで石炭価格が下落したため、コークスが広く使用されるようになりました。その分水嶺となったのが1775年です。その後、蒸気設備によって、高炉の大型化が可能になっていきます。
鉄が大量に生産されるようになると、機械の製作が容易になり、機械自体も堅牢になっていきました。橋などを建設する場合も、これまでの木材に代わって鉄が用いられるようになります。
そして、19世紀にはいると、汽車が出現するのです。
ブローデルは木綿革命を過小評価してはならないと主張しています。
木綿には長い歴史があります。17世紀にインドとの通商が本格化すると、ヨーロッパはインドの木綿製品に圧倒されることになりました。
自国の織物、とりわけ毛織物を守るために、ヨーロッパはインドの布地の輸入を禁止します。それでもインド木綿の人気には根強いものがありました。
そこでイギリスはインド製品の模倣に走ります。問題は同じくらい上手に、しかも安い値段で木綿の糸や布地をつくることでした。
インドの職人に太刀打ちするには、機械で対抗する以外に方法はありません。18世紀後半のアークライトとクランプトンの機械がそれを可能にしました。こうして、イギリスはインド布地の市場を制覇して、新たに巨大な市場を開拓することになります。
木綿の市場が国内、国外に広がるにつれて、生産は一気に増え、同時に価格も下がっていきました。利幅はむしろ減少していきます。それでも世界市場を得たことで、工場は大きな資本蓄積をすることができたのでした。
19世紀にはいると、木綿産業は大量の蒸気を利用するようになります。マンチェスターには工場が何百も建ち、巨大な煙突からは黒煙がたちのぼっていました。リヴァプールには、米国から原綿が運ばれてきます。
木綿にくらべると、羊毛産業の機械化はずっと遅れました。シェフィールドやバーミンガムの刃物業や金物業も同じです。
産業革命の影に隠れがちですが、18世紀後半のイギリスをもうひとつ特徴づけるのは通商革命だった、とブローデルは書いています。
輸出向けの産業が急速に拡大しました。イギリスが繁栄したのは、自国の島の外に商業帝国を築いたからです。イギリスの勢力はヨーロッパではかえって後退しましたが、インドやカナダ、アフリカ海岸では競争相手を押しのけ、圧倒的な勝利を収めました。独立後の米国とも関係は途絶えることがありませんでした。
国民市場、すなわち国内商業の拡大も無視できません。国内商業の割合は国外通商の2、3倍あったとみてよいでしょう。産業革命はこの活発な流通経済に直接支えられたものでした。
ロンドンを中心に都市が発達し、所得や利潤が増え、貨幣経済が活発になり、輸送手段が改良されたことが、国内商業の拡大を導きました。
国内流通を促進した要因は、何といっても沿岸航海路と河川航行路の確立にあります。河川はつながれて運河となり、炭田と都市を結ぶルートとなりました。新たな陸路もつくられました。
炭鉱の竪坑口から船着き場を結ぶ鉄路もでき、馬が荷車をひいて、そのうえを走るようになります。そして、ついにスティーヴンソンが1825年に蒸気機関車を完成させます。
産業革命は近代的成長、すなわち連続的成長をもたらす端緒となりました。19世紀において、物価は下降期と上昇期を経験しましたが、そのどちらの時期においても、経済は成長しつづけました。それ以前の歴史が、成長と停滞、後退や下落をくり返したのと対照的です。
産業革命はエネルギー革命でもありました。それが13世紀の水車のように、すぐに天井にぶつからず、ずっと持続したのは、エネルギー源が消滅することなく、新たに開発されつづけたからです。
さらに、ブローデルが注目するのが分業です。成長は新たな分業をつくりだし、社会と経済のかたちをつくりかえる、と論じています。
ヨーロッパで分業は当初、下請け外注システムのかたちをとりました。商人は農村の職人に製品を発注します。職人は羊毛や亜麻、木綿などの原料を商人から預かって、それを製品や半完成品に仕上げて、商人に手渡し、支払いを受けます。企業はこのシステムによって固定費を抑え、需要に応じて生産を調整することができました。
工場制手工業(マニュファクチュア)は、工場に労働力を集中させ、それによって規模の経済をはかろうというものでした。ブローデルは初期の段階では、工場の割合は少なく、まだ下請け外注システムが一般的だったと述べています。
産業革命は蒸気力にもとづく近代的な工場をもたらしましたが、その代表格である木綿産業でも、そうした工場が実際に動きはじめるのは1820年代になってからです。
しかし、何はともあれ、工場が動きはじめると、農村から町に人が集まってきます。最初は家族をまるごと雇うこともあったようです。つまり、家内作業所がそっくりそのまま工場へはいっていったわけです。
しかし、1820年代以降、自動式ミュール精紡機がつかわれるようになると、工場の内部では家族のまとまりが断ち切られ、それに代わって児童労働という新たな問題がでてきます。つまり大人は雇わなくても、子どもでじゅうぶん間に合ったわけです。それによって失業者が路上に放りだされ、賃金は崩落していくという問題が発生します。
貧しい農民は農村から遠く離れ、都会でつらい労働に耐え、長時間労働と苦しい生活を強いられるようになりました。資本家たちは、そんな労働者に冷ややかでした。そのため、19世紀前半から半ばにかけては、急進的な労働運動が発生することになります。
分業は同時に専門化でもあります。かつて卸売り商人は、商人であると同時に銀行家であり、保険業者であり、船主であり、実業家でもありました。かれらは多種多様な事業に携わるとともに、ときに下院に議席を有することもありました。
しかし、19世紀にはいるころから、新たなタイプの実業家や企業家が登場します。かれらは新技術を支配し、職長や労働者を掌握し、市場の知識を有して、その場その場に適した進路を判断しながら自社の生産を方向づける能力をもっていました。
こうした企業家が登場したのは、産業がこれまでにない規模に達していたからです。規模の巨大化は、資本主義の上層部においても、専門化と分業をうながすことになったのです。
近代化が進展するにつれ、産業に占める第1次産業部門の割合が収縮し、第2次、第3次部門の割合が増えてきます。いまでは労働人口の半ば以上が、第3次のサービス部門の仕事に従事するようになります。その仕事のどれもが専門化する方向を示しています。ブローデルは、何はともあれ産業革命が分業化と専門化を促すビッグバンになったととらえています。
さらにブローデルは産業革命がイギリスの歴史地理を変えてしまったことを指摘します。かつてのイングランドの豊かな地域では伝統産業が凋落し、これに反して北側の地域は数世代のうちに、おどろくほど近代的な地域に変貌しました。石炭の力が、北のバーミンガム、マンチェスター、リーズ、シェフィールドを一気に産業都市に変えていったのです。
金融も大きな発展を遂げます。1820年代のイギリスでは、イングランド銀行を中心に100行の都市銀行と650行の地方銀行があったといいます。これらの銀行は預金と貸し出しをおこなっていました。ロンドンには手形交換所や割引銀行がもうけられました。イングランド銀行発行の紙幣が国全体に広がります。株式取引所も活況を呈し、海外への投資もはじまります。
イギリスでは1770年ごろから1812年ごろまで物価が上昇しましたが、そのかん賃金は上昇しませんでした。そのため、1820年ごろまで、実質賃金は減少していきます。賃金事情が改善されるのは1820年ごろで、そのころ物価は下がっていました。奇跡がおこるのは1850年以降です。このときは物価が上昇し、賃金もそれに応じて上がっていきます。これによって連続的な経済成長がやっと軌道に乗ります。
近代化が達成されるために、何世代もの人びとが犠牲となりました。技術面の勝利と商業の優位、実業家と金融家の盛運のために、民衆がどれだけ重い代価を払ったのかを忘れてはならない、とブローデルは記しています。
とはいえ、「19世紀中葉にいたって、〈旧制度〉の成長に特有の[成長と後退をくり返す]リズムが消滅した」ことはたしかであって、それからは「人口、物価、GNP、賃金が同時に上昇するトレンド」がはじまりました。しかし、こうした連続的成長を可能にした長期の世紀トレンドは、1970年代に終わり、これからは長期にわたる危機がくると、ブローデルは予想しています。
本書『物質文明・経済・資本主義』が出版されたのは1979年のことです。それから40年以上がたって、世界はさらに大きく変わりました。
ブローデルが探求したのは、主に15世紀はじめから18世紀終わりまでの400年にわたる資本主義の歴史です。それは変貌に変貌を重ね、19世紀以降も、多くの方向転換を重ねてきました。そして、資本主義は現在にいたるまで変化しながらも、もとの姿を受け継いでいます。
いまも資本と国家とのあいだには綿密な連携関係が存在します。しかし、資本主義と文化や社会とはかならずしも折り合いがよいわけではありません。資本主義は人間の生き方を縛っていますが、それは理想の生き方とはほど遠いものです。環境や伝統、文化を破壊しつづけているともいえます。多くの経済格差や不平等、苦痛をもたらしているのも事実です。
しかし、ブローデルは、外部的な力によってならともかく、資本主義が〈内因性〉とでもいった劣化をきたして自分から崩壊するようなことはありえない、と断言します。システムとしての資本主義は、「危機を乗り越えて生き延びる確率がおおいに高い」とも述べています。
ブローデルは資本主義の欠陥を是正する方向として、レーニン流の全体主義的社会主義を否定します。資本を国家に入れ替えても、それは「資本の欠陥に国家の欠陥を加えるだけ」だと断言しています。そして、問題の解決は、政治的次元でも経済的次元でもなく、社会的次元にあると示唆して、本書の結びとしています。
国家の枠組みは残り、資本主義も存続するのでしょう。しかし、世界平和条約によってつながれた国家が公共国家となり、資本主義が公共性のルールにしたがうようになることが前提です。さらにいえば、ブローデルのいう社会的次元による解決とは、社会的共通資本の領域を拡大すること、そして、社会的問題を社会全体が受けとめ、社会的不平等を解消する努力をつづけることをさしているのではないでしょうか。いまはそんなふうに思います。
ブローデルをめぐって(9)──商品世界ファイル(17) [商品世界ファイル]

15世紀から18世紀にかけては、商業活動が活発になった時代です。都市には大商人がいて、その下に行商人や小売商人、雑貨商、穀物商などがいました。さらに、その周辺には外交員、仲買人、水夫、人足、仲仕、高利貸しなどがたむろっています。
大商人は卸売商兼金融業者として、大きな事業を手がけています。全世界を相手に富を築く大商人は、その下の商人たちとはまったく別の階級に属する上流人士でした。
資本はまだ生産の領域を支配していたわけではありません。プランテーションやマニュファクチュアはありましたが、資本は直接、事業を起こすのはまれで、いわば生産の領域を遠巻きにして、できあがった商品を市場に運ぶことによって利益を得ていました。資本主義への助走はすでにはじまっていますが、資本が商品(資本財および労働力)によって商品をつくりだす時代はまだ到来していません。
そのことは金融についてもいえます。金持ちは資金提供者として教皇庁や王侯、商人、船主にカネを貸し付けていました。17世紀にオランダでは資金を貸し付ける銀行も誕生します。しかし、全体として銀行は未発達で、おカネを預けたり振り替えたりするようなものはあっても、表だって資金を貸し付けてくれる金融機関はなかったのです。
それでも、商業が盛んになると、自然におカネが集まってくるような場所ができてきます。それが13世紀から15世紀にかけてのフィレンツェ、16世紀のジェノヴァ、そして17世紀のアムステルダムでした。
近世においては、遠隔地交易に多くの資金が投入されました。もちろん、近隣の小麦、羊毛、塩などの交易も盛んになっていました。しかし、遠隔地交易に乗り出す数少ない業者が、アメリカとアジアを股にかけ、絹や胡椒、香辛料、タバコ、コーヒー、砂糖、銀の延べ棒などを扱って、大きな利益を得ていたことは確かです。実際、商業ブルジョワジーは、遠隔地交易のなかから生まれてきます。
それでも、この時代はまだ金融システムがじゅうぶんに確立されていたとはいえません。金融システムがしっかりしてくるのは1694年にイギリスでイングランド銀行が設立されてからです。
貨幣は金銀の複本位制、あるいは金銀銅の三本位制がとられていました。16世紀半ばにアメリカから銀が大量に流入すると、金銀の比率は大きく変動します。ここでも優位な立場にあるのは大商人で、かれらは「黒い貨幣」(銅貨)と呼ばれていた小銭をすぐに流通に戻し、手元に価値の高い貨幣だけをとどめました。金貸しは貸し付けを銅貨でおこない、銀貨で返却を求めていました。
経済のかなめとなるのがインフレーションです。貨幣量の増加によりヨーロッパでは物価が上昇していきます。しかし、賃金は同じ比率では上昇しませんでした。そのため、金持ちはインフレーションで大きな被害をこうむるどころか、大いに潤っていました。
この時代、会社と呼ばれるものは、それほど多くありません。会社の起源は9世紀ないし10世紀にさかのぼります。ヴェネツイア人が地中海で一航海のためにだけ「海の結社」をつくったのが最初です。その後、ルッカやシエナ、フィレンツェで商人たちは会社をつくり、亜麻布や毛織物、香辛料、サフランなどを仕入れ、内陸交易をおこないました。
ドイツではヴェルザー家とフッガー家が大きな勢力を誇っていました。しかし、16世紀になると、それまでの同族会社に代わって、合資会社がヨーロッパ全域に広がっていきます。合資会社では、出資者が経営にかかわるものの、自分たちの出資分にしか責任を負わないで済むというメリットがありました。
そして、いよいよ最後に株式会社が登場します。出資者は資本の持ち分を所有し、会社の上げる利益を株式の持ち分に応じて得ることができました。イギリスでは16世紀にモスクワ会社が誕生しますが、これは株式会社です。それ以前からヴェネツィアやジェノヴァでも株式会社はあったといいます。
しかし、特許大商業会社を別とすれば、株式会社が急速に普及することはありませんでした。株主についても、どこかうさんくさい感じをまぬかれなかったのです。それでも18世紀半ばになると、海上保険会社や、運河会社、鉱山、水道会社などで、株式会社の形態が広がっていきます。
何といっても注目されたのは、特許会社としての株式会社です。この特許会社には、国家から遠隔交易を独り占めする特権が与えられていました。
最初に国家と会社を結びつけたのはヴェネツィアで、ヴェネツィアには17世紀以前から、こうした会社がありました。アメリカ大陸の発見後、スペインやポルトガルなども、国家と事業との結びつきを強めていきます。オランダとイギリスの大特許会社は、それを引き継いだものといえます。
特許会社にはかならず国家がからんでいますが、それは国家の財政を補助することが目的でした。特許会社は国家が与えてくれた独占権にたいする見返りを求められます。こうした特許会社の代表が、オランダ、イギリス、フランスで17世紀につくられた東インド会社です。
特許会社のなかで、東インド会社のみが成功をおさめたのは、「アジア商業がもっぱら奢侈という星の下にあった」からであり、そこにはアジア貿易の困難さにともなう「成功の地理学」があった、とブローデルは述べています。アジアとの交易によって、ヨーロッパには「胡椒、上質の香辛料、絹、インド更紗、中国の金、日本の銀、やがて茶、コーヒー、漆器、磁器」などがもたらされました。
こうした商業活動の活発化は、社会全体にも影響を与えていきます。
都市では、ブルジョア階級が誕生するとともに、貴族階級のブルジョア化がみられます。
18世紀のフランスではブルジョアが人口の8パーセントを占めていた、とブローデルはいいます。しかし、ブルジョアといっても上から下までさまざまで、そのランクはたえず入れ替わりました。上層のブルジョアは2パーセント足らずで、その数は上層の貴族とほぼ同じだったようです。ブルジョアの後裔は、官職を得て法服貴族となりたがりました。
都市や農村では、しょっちゅう一揆や暴動、騒動が起こっています。農民の反乱が勝利することはありませんでしたが、それでも農民は少しずつ自由を勝ち取っていきます。
労働者の騒動もありましたが、それが広がることはまれでした。労働者は安い賃金と失業のあいだで、身動きのとれない状態におかれていました。
資本家の勝手な振る舞いにたいし、労働者がストライキに立ち上がるのはとうぜんでした。リヨンでもアムステルダムでも、その他の産業中心地でも労働者は立ち上がり、粘り強く戦います。しかし、それは広がりをみせません。おそらく、その理由は労働者が別々の同業組合に属していたことと、そして、市当局と結びついている工場主が圧倒的な権力を有していたためです。当時はまだ労働組合の結成は禁止されていました。
さらに、都市には膨大な下層プロレタリアが存在しました。貧民、乞食、浮浪者の群れです。
都市でぎりぎりの生活をしている人びとは、雇用状況が悪化すれば、たちまち貧民となります。貧民にはまだ仕事がありますが、乞食や浮浪者となると、物乞いをしたり、残飯をあさったりして生きるのがせいいっぱいです。
18世紀になると、貧困者の数はさらに増えていきます。農村の囲い込み運動に加え、飢饉などによって、貧民が都市に流れこんできたからです。生き地獄から抜けだすのは容易ではありません。密造・密輸組織にはいったり、山賊、海賊、軍隊、召使い、下僕になったりするのはひとつの脱出口でした。
商業活動の活発化は都市人口の膨張をもたらしましたが、それはかならずしも社会全体の豊かさとは結びついていなかったのです。
近世になって変化したのは社会だけではありません。国家も大きく変化しました。国家は単なる統治機構ではなく、重商主義を推進する機関となっていました。重商主義の背景には、国家の富とは金銀の蓄積にほかならないという考え方があります。いずれにせよ、国家が経済を常に意識するようになることが近世の特徴です。
相次ぐ戦争によって、国家の支出はうなぎのぼりになりました。重商主義は、ある意味、戦争を支える経済戦略として採用されたともいえます。
とはいえ、この時代、国家の管理している貨幣は貴金属からなり、紙幣はまだつくられていません。行政機構もじゅうぶんに備わっているとはいえませんでした。軍隊そのものも人員不足でした。
国家のヒエラルキーで重要なのは、王の直臣、貴族、領主、都市、教会でした。国王は、領主のなかから、他にぬきんでて王という位を獲得した存在にすぎません。そのため国王は貴族たちとの縁を切るわけにはいきませんでした。そのころ、都市のブルジョアたちも、公職を買って、貴族に列するようになっていました。
近世にはいって、国家はヨーロッパ世界を動かす新しい力となっていきます。国家は資本主義を優遇し、それを援助するようになっています。しかし、いっぽうで、資本主義の躍進をさまたげる役割も果たしていた、とブローデルは指摘しています。
この時代に大きな力をふるっていたのが宗教です。
イスラム世界は商業文明を根幹としていました。
絹や米、サトウキビ、紙、綿などの産品、さらにはインド数字(アラビア数字)、失われていたギリシア科学、火薬、羅針盤などの技術は、イスラム世界を介してヨーロッパにもたらされたものです。
イスラム世界は、ジブラルタルから中国にまでひろがっていました。東インド会社ができるまでは、アジアの貴重な商品はすべてイスラム世界を経て、ヨーロッパに運ばれていたのです。
キリスト教と資本主義は当初、折り合いが悪く、とりわけ金利については、教会の側から激しい反感がありました。5%ないし6%以上の金利をとる高利貸しは禁止されていました。しかし、それが次第に緩んできて、経済活動にはリスクが伴う以上、ある程度の金利はやむを得ないという解釈が生まれます。
マックス・ウェーバーは16世紀以降、オランダやイギリスで商業資本主義が隆盛したのは、プロテスタンティズムの精神があったからだと唱えました。これにたいし、ブローデルは、ウェーバーの主張には論拠がないと批判しています。カルヴァンが登場するはるか前から、資本主義への門はとっくに開かれていたというわけです。
17世紀はじめまで資本主義の中心はローマ・カトリックのイタリアにおかれていました。アメリカ大陸を発見し、アジアへの航路を開いたのも、地中海ヨーロッパの国々(スペインとポルトガル)だったといいます。当時もハンザ同盟都市や、バルト海沿岸の交易はあったものの、北方の経済活動は概して立ち後れていました。
その後、経済の中心が北方に移動したことは事実です。宗教改革が北方諸国に一体性をもたらし、先進的な南方諸国に対抗する契機を与えたことはたしかでしょう。しかし、プロテスタンティズムの精神が資本主義の隆盛をもたらしたとするウェーバーの論理は牽強付会だ、とブローデルは述べています。
資本主義は新たな心性をもたらしました。それは、金銭の礼賛、時間の貴重さ、つつましく暮らすことの必要、などですが、もし資本主義的心性の起源を把握したいのなら、「中世のイタリア諸都市におもむき、そこにじっくり腰を据えること」以外にない、とブローデルは書いています。
いっぽう、アジアは日本を例外として資本主義の発達に遅れをとりました。
中国ではあまりにも中央集権的な国家が、市場経済と資本主義の発達を抑えてしまったのにたいし、日本では国家からある程度独立した経済的・社会的勢力がつくられており、それが資本主義的発展への余地を残したという見方もあります。しかし、それはあまりに単純な見方です。
ブローデルは徳川時代の日本において、商人階層が生き残り、資本を蓄積したこと、貨幣や為替手形の流通がおこなわれたこと、職人生産から初期的なマニュファクチュアが形成されたこと、市場経済が発達したこと、鎖国のもとでも中国や朝鮮、オランダとの交易がつづいたことなどを、明治維新後、日本が経済躍進を遂げた理由として挙げています。
イスラム世界やインドを含め、アジアでは資本主義の発達を妨げる何らかの要因があったことはたしかです。ブローデルの本では、それが何だったのかは、ひとつの大きな課題として残されました。
ブローデルをめぐって(8)──商品世界ファイル(16) [商品世界ファイル]

近世のヨーロッパでは産業は小規模なもので、農業と一体化していました。産業がとつぜん動きはじめるのは、農作業のできない冬になってからです。小麦の刈り取りなどがおこなわれる夏は、農業が忙しくなる季節です。
農民が産業に乗りだすのは貧しさからでした。領地がせまく、農業さえままならぬイタリアのルッカは、絹織物に活路を見いだしました。山地の住民は、土地の貧しさを補うために、麻加工の仕事をはじめました。スコットランド高地のやせた耕地で生きていけない農民は、鉱夫や織工になって糊口をしのぎました。
中部ヨーロッパでは、15世紀、鉱山の活動に大きな変化が生じました。フッガー家などの富裕な商人が鉱山をみずからの手に握ったのです。こうしてそれまでの自由な労働者は賃金労働者となったのです。資本投下は、生産量のめざましい増加をもたらしました。
しかし、フッガー家といえども単独で鉱山を引き受けるには、財力が不足していました。鉱山の背後にはつねに王侯がいて、国家はつねに鉱山事業に関与していました。それは貨幣の鋳造と関係しています。
16世紀にはいくつもの有名な鉱山が放棄されて、国家の手に渡りました。アメリカでの鉱山開発が、ヨーロッパの鉱山に大きな打撃を与えたのです。商人たちは鉱山の直接経営から手を引くようになります。それでも製品の販売や周辺の事業には引きつづきかかわっていました。
鉱山には労働力の集中を必要とします。すでに労働者の階層化が進行し、中間管理職も生まれています。労働者の頂点には商人の代理人である職場長、そしてその下に職工長という体制がつくられていました。
16世紀中葉以降、ヨーロッパは次第に鉱山開発から後退し、金属原料を国外に依存するようになります。
とりわけアメリカ大陸で、鉱山の直接開発がなされました。有名なのがボリビアのポトシ銀山です。山で採掘された銀鉱石は、ふもとで粉砕され、アマルガム法によって精練されました。大きな利益をふところにするのは、商業ネットワークを握っている大商人たちです。
大規模な設備を必要とする岩塩鉱は、大商人によって運営されていましたが、塩田は小企業による経営が一般的でした。鉄についても、鉱山と高炉、製鉄所は別々に運営されており、どれもさほど大きな規模ではありませんでした。鉄の大規模生産が可能になるのは18世紀になってからです。
石炭の採掘も小規模で、露天掘りが中心で、表層部の石炭を取るだけでした。ところが18世紀になると、状況が一変します。石炭の需要が一気に高まったのです。すると、本式の採掘が求められ、大資本が石炭に関心を示すようになりました。
産業活動が活発化するのは、18世紀にはいってからです。それまでイタリアとネーデルラントにかぎられていた産業が、ヨーロッパ全体に広がっていきます。
そのころの産業の主力は衣服と織物です。衣服は身を包むもので、なくてはならないものでした。カーテンや壁掛け、壁布などの織物は奢侈品で、民衆が織物を買えるようになるのは、18世紀に綿製品が登場してからです。
13世紀、14世紀には、イタリアの羊毛製品がもてはやされました。その後、16世紀にイタリアが最後の経済的繁栄を謳歌できたのは、絹のおかげでした。絹はやがてスイス、ドイツ、オランダ、イギリス、そしてとりわけフランスのリヨンへと広がっていきます。17世紀にはイギリスの上質な毛織物が登場します。
18世紀には木綿が新しい勝者となります。インドの更紗がヨーロッパを埋め尽くしました。そこで、ヨーロッパはインドを模倣し、木綿を織り、捺染する作業に挑戦することになります。18世紀後半には、さまざまな加工技法によって、絹とウールの混紡、麻と綿の混紡といった新しい織物が登場します。イギリスの産業革命では、木綿が大きな役割を果たすことになります。
資本主義を牽引したのは都市の商人ですが、かれらも職人の同業組合を無視するわけにいきませんでした。しかし、次第に大組合は大商人の手に移り、ついに問屋制度が生まれてきます。
商人が職人に原料と賃金の一部を前貸しし、生産者に仕事を発注するのが問屋制です。同業組合は徐々に崩壊し、商人のもとで、職人どうしが協同作業をする体制が生まれます。
商人が直接、生産を握っていない地域も残っていました。イギリスの地方の羊毛加工、フランス南部ラングドッグの釘製造、フランス北部トロワの麻加工などです。こうした自由生産地域の存在は、近くに市場や大市があることが前提になっていました。フランス南部の山間部、ジェヴォーダンでは、冬場になると農民たちが織機の前に座って、織物を仕上げ、それを近くの市に売りにいくのが通例となっていました。
前産業時代の産業は、家内手工業と問屋制が大部分ですが、そこにマニュファクチュアと工場が姿をあらわします。マニュファクチュアを手工業によるもの、工場を機械設備にもとづくものとするのが一般的な区別ですが、その区別はあいまいです。マニュファクチュアの規模にしても、ごく少人数のものから、大規模なものまでさまざまでした。
いずれにせよ、問屋制度の行きつく先がマニュファクチュアで、最終的な仕上げ作業がおこなわれる場所がマニュファクチュアだったと理解することができます。
最終工程で、比較的大きな設備を必要としたのは、仕上げ作業がもっともむずかしかったからです。しかし、それ以上にマニュファクチュアの最終目的は、最終的な製品を手中に収めること、さらには需要に合わせて生産を調整することだったといえるでしょう。
マニュファクチュアによってつくられる製品は、麻レースから革製品、陶磁器、毛織物、石鹸製造、鉄、ろうそく、絹製品、瓦、紙、板ガラス、ビロード、綿布にいたるまで、じつに多種多様でした。さらにいうと、マニュファクチュアは技術的進歩のモデルでもありました。国家は産業を保護するために、先進的なマニュファクチュアを支援しました。
17世紀、18世紀にかけて、マニュファクチュアでは資本の規模が大きくなっていきます。印刷、製糖、ビール醸造、毛織物のマニュファクチュアでも、高価な設備が必要となり、それなりの投資をしなくてはなりませんでした。
常に資金難がついてまわります。社会状況の悪化や、投資の失敗などにより、倒産も生じました。もちろん、危機を乗り切った勅許マニュファクチュアもあります。しかし、伝統的なマニュファクチュアの株式は、18世紀が進むにつれて、事業家ではなく「年金生活者」の貴族が所有するようになります。
利潤率の変動は激しく、予想を許しませんでした。工業生産のカーブは短期間に激しく上下し、長期的にみても、はじめ上昇したカーブが下降していきます。ひとつの産業の衰退は、他の産業の上昇と並行しています。
15世紀から18世紀にかけては、いかなる産業も、いつ急激に落ちこむかもしれない、きわめてあやうい基盤のうえに成り立っていた、とブローデルは記しています。
近世の商品世界について述べるには、そのころの輸送手段にも触れないわけにはいきません。
輸送と生産のつながりはだいじです。18世紀には輸送のスピードが上昇し、輸送量が格段に増えていきます。
この時代、すべての陸上輸送は、宿駅ごとの旅籠に依存していました。旅籠は商取引の中心であり、同時に運送業の取次も兼ねていました。
民間業者と公共運送業とのあいだには競争がありました。17世紀にはドイツとイタリアを結ぶ主要幹線道路に大規模な運送商会が出現します。その本拠地はスイスと南ドイツに置かれていました。アムステルダムやロンドンなどにも、大規模な運送業者がいたことはいうまでもありません。
河川輸送には、小舟や大型船、筏などが用いられていました。河川輸送の欠陥はスピードの遅さです。しかも、それは増水や風、凍結など川の気まぐれに左右されました。
ほかにもさまざまな障害がありました。川のあちこちに無数の通行税徴収所があることもやっかいでした。運河は合理的な解決法でしたが、閘門の多さが船の動きを遅くします。さらに気性の荒い水運業者をどう扱うかもめんどうな問題でした。
フランスやドイツにくらべると、イギリスでは輸送はよほど自由でした。石炭は海上輸送で課税されるだけで、道路や河川の輸送では何の障壁もありません。とはいえ輸送費はけっしてばかにならず、ニューカッスル炭はロンドンでは現地の5倍の価格になりました。
道路や河川にくらべ、海上輸送はより大規模で、その投資も巨額なものとなりました。中世ヨーロッパでは、船は数人の仲間のもちものでした。かれらは仲間で操舵手や船頭を雇い、自分たちの商品を積みこんで目的地に向かい、そこで商取引をおこないます。
15世紀末には、すでに大型貨物船が登場しています。船には一部の資金を出資する持ち分保有者や、食糧や道具類を供給する現物出資者、さらには抜け目のない投機家もかかわっていました。
海上輸送の発展につれて、造船会社や保険会社も誕生します。18世紀には、遠洋航海に多くの資本が注ぎこまれ、国もその事業にかかわりました。
保険で保護されているとはいえ、航海に危険はつきものです。遠距離交易は成功すれば大きな利益が舞いこみます。これにたいし、近距離輸送は競争が激しいために運賃が抑えられ、たいしてもうかりませんでした。
18世紀以降になると、海運業では、固定資本の割合が大きくなり、人間にたいする支出は減っていきます。造船はますます複雑なものとなり、船価は上昇しました。船長や航海士、操舵手の技倆もあがっていきます。いっぽうトン数あたりの乗組員の数は減少していきました。
概していうと、18世紀までの段階では、資本主義はまだ生産部門に仮住まいしているにすぎなかった、とブローデルは論じています。当時の資本家である大商人は、まだそれほど生産のなかに飛びこんではいなかったのです。資本が積極的に生産の領域を支配するのは産業革命以降です。
ブローデルをめぐって(7)──商品世界ファイル(15) [商品世界ファイル]

近世社会の特徴のひとつとして挙げられるのは、市場経済の広がりと、商人による商圏の拡大といってよいでしょう。
ブローデルはこんなふうに書いています。
たとえば、17世紀にフィレンツェとリヴォルノに本拠地を構えていたサミニアーティ商会は、地中海全域だけでなく、リヨン、アムステルダム、ロンドンにまで取引を広げ、香辛料や胡椒(こしょう)、絹などの特権的商品だけでなく、手形や金銭、貴金属も扱っていました。
16世紀にアウクスブルクに拠点をおいていたフッガー家やヴェルザー家は、ハンガリー、ボヘミア、アルプスに鉱山事業を展開する巨大な商人で、早い時期からスペインの王室と結びついていました。
そのような大規模な商人でなくても、たとえばドイツのニュルンベルクなどにも多くの商人がいて、中東、アフリカ、インド、アメリカとの商業活動を担っていました。しかし、アウクスブルクとニュルンベルクの経済は1570年に破綻し、その後はライプツィヒが商業の中心地となっていきます。
ヨーロッパの都市の特徴は、都市が地方空間を握っているだけではなく、国際空間をも掌握していることでした。15世紀から17世紀までの花形商品は胡椒ですが、それは次第に後退し、それに代わって、15世紀から18世紀にかけては、砂糖が急速なリズムで消費空間を広げていきます。
砂糖はほとんどサトウキビが原料です。ニューギニアを原産とするサトウキビは、インドからはじまって、地中海、大西洋、さらにアメリカへと移植されていきました。15世紀と16世紀、砂糖はまだ贅沢品でしたが、17世紀、18世紀になるとアメリカからヨーロッパに砂糖が大量に輸入されるようになります。18世紀になると、ヨーロッパでは砂糖はもはや珍しい商品ではなくなり、食料品店や菓子店のどこにでもある商品になっていました。
もうひとつの世界商品が貴金属です。
金や銀を産出するのは辺鄙な地でした。ブローデルは、金の産出地として、アジアではボルネオ、スマトラ、海南島、チベット、セレベスなどの名前を挙げています。アフリカではスーダンが金の産地として知られていました。中部ヨーロッパには銀鉱がありました。
新大陸ではインディオが砂金採集のため強制労働にかりだされていました。銀を産出した鉱山としては、ボリビアのポトシが有名です。ブラジルでもまだこの時代、砂金が出ていました。カリフォルニアにゴールドラッシュが巻き起こるのは、まだ先の19世紀半ばになってからです。
貴金属を受け入れ、それを貨幣としてさかんに流通させたのは、ヨーロッパの国ぐにでした。いっぽう、それを貯蔵したのが、インドと中国です。中国は金に貨幣の役割を与えず、もっぱら銀を貨幣としました。
ここからは、当時の世界貿易の流れが想像できます。中国の絹、陶磁器、茶、インドの高級綿織物、宝石、真珠はヨーロッパに流れ、中国とインドには、その代わりヨーロッパから新大陸産の貴金属がもたらされたのです。
ヨーロッパでは貴金属は主に貨幣として利用されています。しかし、ヨーロッパはアジアからいつまでも木綿製品や絹製品、香辛料、薬種、茶などを、一方的に輸入しているわけにはいきませんでした。そこで、レヴァントには毛織物を、中国にはインドの木綿とアヘンを送り、わずかながらも収支のバランスをとろうとしました。だが、それだけではとても間にあいません。ヨーロッパ全域にわたり、鉱業開発と工業化が推進されたのも、国際収支を改善しようとする努力の一環だった、とブローデルはみています。
16世紀以前からヨーロッパの国は重商主義政策をとっていました。その狙いは、貴金属の流出を防ぐことにありましたが、それ以上に強く望まれたのは貿易収支を黒字にすることでした。当時は、国家の富は貨幣の備蓄にほかならないという考え方が根強かったといえるでしょう。
たしかに貿易収支の慢性的赤字は、国の経済を構造的に悪化させます。実際、インドでは1760年以降、中国では1820年ないし1840年以降、慢性的な貿易赤字が生じるようになっていました。
いつの間に、インドや中国がヨーロッパにたいし貿易赤字になっていたのでしょう。16世紀以降、ヨーロッパ人はアジアに進出しますが、それはただちに古くからの貿易構造を変えたわけではありません。香辛料をはじめとするアジアの商品は、銀によってしか手に入りませんでした。
しかし、ヨーロッパの勢力は、次第にアジア内部にはいりこんでいきます。当初、インドの沿岸交易を担ったのはポルトガルです。その後、オランダ人はジャワ島に入植し、バタヴィアを建設しました。アジアはまだその時点では、貿易面でヨーロッパにたいし圧倒的な優位を保っていました。
インドの貿易収支は、1730年ごろから悪化しはじめます。ムガル帝国は崩壊しつつあり、経済もまた弱体化していました。1757年のプラッシーの戦いにより、イギリス東インド会社はベンガルを征服、金銀宝石を本国に持ち帰ります。インドは、そのとき以後、大生産・商業国という威信ある地位から、イギリス製品の買い手で原料の供給者という植民地の地位に転落していくことになります。
その運命はつづいて中国をも襲います。中国ではヨーロッパに輸出するため、茶の栽培農地を広げたため、綿が不足するようになっていました。そこで、綿をインドから輸入するようになります。1780年以降は、インド産のアヘンがはいってくるようになり、1820年ごろからは、貿易収支が赤字になっていきます。清朝の崩壊がはじまろうとしていました。
前に、近世の特徴は市場経済の広がりに求められると書きました。しかし、近代が近づくにつれ、市場経済をさらに発展させたのはヨーロッパで、それまで優位を保っていたアジアはむしろ後退していきます。いったい何があったのでしょうか。
ブローデルはそこに資本の働きをとらえています。資本が経済を動かす時代がはじまろうとしていました。
資本とは商品を動かしたり、つくりだしたりすることのできるおカネの力にほかなりません。それはその途中に耐久的な資本財(商店や作業場、道具、船など)をつくりだします。これは固定資本、すなわち商品をつくるための商品ともいえます。そして、何よりも重要なのは、資本が雇用(マルクス流にいえば商品化された労働力)を生みだしたことです。
昔の経済は固定資本の損耗が激しく、それが経済成長の阻害要因となっていました。家屋にしても、船舶、橋、灌漑用水路、あるいは道具や機械にしても、けっして長持ちしませんでした。火災もしばしば村や都市に大きな損害を与えています。経済技術構造がわずかな資本形成しか許さないとすれば、一昔前の資本主義が、大部分の投資を流通の領域に向けていたことはやむを得なかったのです。
とはいえ、16世紀末のイタリアのように、通貨の過剰に悩む地域もありました。カネは土地の購入や、田舎の別荘、華麗な建造物に向けられていました。華麗な文化の時代は、「イタリアが、その経済が消費することのできる資本財と金銭の量を超えて、もちすぎてしまった」ことの結果だった、とブローデルはいいます。あまったカネは消尽するほかありません。社会の脆弱さと利潤の低さが、資本主義の発達、ないし全面化をはばんでいました。
それでも、15世紀から18世紀にかけて、資本は流通から生産の領域に進出していきます。それが本格化するのは、19世紀以降の近代になってからですが、飛躍に向けての助走はすでにはじまっています。
われわれは近世のイメージとして、都市は消費で、農村は生産という構図を思い浮かべます。すると、資本が流通から生産の領域に進出するといった場合、生産の拠点である農村を資本が包摂すると考えるかもしれません。
しかし、それはそう簡単ではありませんでした。
商人が土地を買っても、その目的は貴族になるためでした。当時はまだ荘園制が保たれており、土地が資本主義的に利用されることはまずありません。しかも、土地は簡単には売り買いできませんでした。
農村は人口過密で、つねに窮乏と飢餓のぎりぎりの線上にあり、人間が多すぎることが生産性の向上を妨げていました。農民は生きていくのがやっとで、しかも不作の試練に耐え、さまざまな賦課租を払うために、休みなく働くことを強いられていたのです。
農民は世界のどこでも、貧窮と忍耐、不屈さのなかで生きていました。農民は生き延びるために、多くの副業をいとなんでいました。鉱夫や水夫、石切、行商、運送、日雇いなどの仕事にもついています。
そして、農民といっても、その状況は国や地域によってさまざまで、その身分も奴隷、農奴、自由保有農民、折半小作人、小作人とさまざまでした。
フランスでは13世紀に農奴解放の動きが広がり、15世紀に農民は土地に縛られなくなります。イギリスでは18世紀に囲い込み運動が発生し、農民は次第に都市にやってくるようになります。
とはいえ、荘園制は長くつづいたのです。農村には貴族の領地が広がっており、農民は領主に賦課租を収めねばなりませんでした。賦課租は、金銭、現物、労働(賦役)から成り立っていましたが、賦役は次第に金納に変わっていきます。
近世になると、貴族は領主権によって、さまざまな税を徴収し、時に土地を集中化し、折半小作地をつくることにも成功しています。農民は農奴でなくなり、自由に土地を離れることができるようになりますが、ほとんどの農民は、それまでどおり、領主のもつ土地を耕しつづけていました。
農民の生活は「生き延び、生殖し、みずからの務めを果たしつづけるだけ」のことであり、これにたいし、「つねに飢餓のおそれにさらされている世界において、領主たちは日のあたる側にいた」と、ブローデルは書いています。
この農村世界に資本主義はどのように入りこむことができたのでしょう。そこはまだ領主や地主が支配する世界でした。
資本主義が農村にはいるケースはまだまれです。たとえばジェノヴァの事業家は15世紀にシチリアでサトウキビの栽培をはじめています。ボルドーやブルゴーニュでは、17世紀から大規模なぶどう畑が広がるようになります。その畑を所有していたのは、都市の高等法院や僧院でした。
いっぽう、東ヨーロッパでは、16世紀に「第2次農奴制」ともいえる揺り戻しが発生します。農民はふたたび土地に結びつけられ、自由に移動できず、域外結婚もできなくなります。物納賦課と労力奉仕が強化されました。
じつはこの時代、東ヨーロッパは、西ヨーロッパの原料「植民地」になろうとしていたのです。東ヨーロッパで農民への負担が大きくなったのは、領主たちが、西ヨーロッパの大量需給にこたえようとしたためです。
農村はもはや自給自足の共同体ではなくなっていました。というのも領主たちが、領地の穀物や木材、家畜などを西ヨーロッパに積極的に売りに出していたからです。こうした農奴制の再現は、商業資本主義の影響によるものです。大地主はアムステルダムの商業資本主義の手先と化していました。
ポーランドの領主は、グダニスクの商人から支払いを受け、グダニスクの商人は、オランダ商人から前払いを受けるという関係にありました。つまり、荘園領主は資本のシステムに組みこまれていたわけです。とはいえ、それは資本が直接、生産にかかわっているわけではありませんでした。資本はあくまでも生産の外側にいて、その成果を待ち受けています。
それは「新大陸」のアメリカでも同じでした。アメリカでは多くの地域や島で、プランテーションがつくられていました。そこで商品の生産を支えていたのは、アフリカから連れてこられた黒人奴隷でした。
ブラジル東北部にサトウキビ畑が開かれたのは、1550年ごろのことです。農場には農園主の邸宅と奴隷小屋、砂糖圧搾場が付設されていました。君臨していたのは農園主ですが、最終的に砂糖の相場を握っていたのは、リスボンの卸売商人です。ヨーロッパの商業が、新大陸での生産と、旧大陸での販売を支配していたといえるでしょう。
カリブ海にまたがるアンティル諸島(キューバやハイチ)でサトウキビの栽培がはじまったのは17世紀半ばのことです。イギリス領ジャマイカでも18世紀半ばからサトウキビ農園がつくられるようになりました。
当時の記録によると、砂糖やコーヒー、藍、綿など植民地の産物はヨーロッパで高く売れたものの、コストがかかり、プランターにとっては、さほどもうからなかったといいます。ヨーロッパの大商人は前払いによって、プランターをしばり、植民地の産物を安く買いたたいていました。
イギリスの先進的農村で荘園が消滅し、近代的な土地所有関係が生まれるのは18世紀後半になってからです。貴族のもつ農村の地所は資本主義的借地農に賃貸され、賃金労働者が雇用されるようになります。
パリ周辺では、都市住民、すなわちブルジョアジーが、農民と貴族から土地を購入していました。しかし、こうした地所を経営していたのは地主ではなく、大借地農です。大借地農こそが、企業者であると同時に「村落世界の真の支配者」だった、とブローデルは書いています。
ヴェネツィアは15世紀はじめに内陸部に領土を広げ、農業国に変貌しました。とりわけ17世紀をすぎると、ヴェネツィアの財閥貴族は商業を見捨てて、農業経営の方向に舵を切ります。財閥貴族の所有する土地では、管理官の監督のもと、一種の農業マニュファクチャーが運営され、小麦、トウモロコシ、麻が栽培され、牛と羊が飼育されていました。
19世紀はじめ、ローマ近郊の広大な農地には、あらゆる地方からの労働者が集められていました。農作業は請負制で、多くの請負師の監督のもとでおこなわれました。労働者に食料を提供するのは農園主の役割でした。
19世紀のはじめにローマ周辺の土地を所有していたのは、領主たちと宗教団体です。しかし、どちらも土地の経営に手をだすことはなく、実際に農地を預かっていたのは大借地農です。その土地はさらに小借地農に下請けにだされていました。そこには、あらゆる地方から労働者が集められ、請負師の監督のもとで農作業がおこなわれていました。「これは資本主義の明らかな闖入である」と、ブローデルは書いています。
フィレンツェの財力によって、トスカーナの田園も大きく変貌しました。零細農民の農地は山間部に残るのみで、平野と丘の斜面はポデーレと呼ばれる折半小作地となり、そこでの収入は、地主と小作人によって折半されました。地主は農民の家の近くに別荘を所有しています。折半小作人は賃金労働者ではありません。オリーブオイルやワインなど、収益の上がる産品をつくることを余儀なくされていました。こうしてトスカーナでも、農業は次第に資本主義的な性格を帯びていくことになります。
しかし、ヨーロッパでも、こうした先進地域は例外でした。南イタリアやシチリアでは、貴族がますます権力を強め、再封建化を進めています。遅れていたのはアラゴンやスペイン南部、スコットランドやアイルランドも同じです。
17世紀後半から18世紀前半にかけ、フランスの領主貴族は地代を値上げしたり、境界を動かしたり、共有地を分割したりといった強硬策をとるようになります。これは伝統への復帰というより、資本主義の誘惑のもとで、かれらが大きな利潤を求めたためです。しかし、フランスではイギリスのように土地の資本主義的利用が進んでおらず、そのため、18世紀後半になると、こうした領主の反動にたいする異議申し立てが生じ、それが旧体制打破というスローガンとなって、大革命へとつながっていくことになります。
ブローデルをめぐって(6)──商品世界ファイル(14) [商品世界ファイル]

15世紀から18世紀にかけて、資本主義はまだ成熟しておらず、それが大きな力をもつのは、ようやく20世紀になってからだ、とブローデルは書いています。
それでも、市場経済の拡大とともに、近世において資本が大きな権力をもつようになるのはたしかです。権力といっても、それは直接的な政治権力ではなく、経済権力といってもよいでしょう。政治権力と経済権力が分離され、国家のもとに統合されるのが、近代の特徴といえるかもしれません。
ブローデルの『物質文明・経済・資本主義』は、第2巻の『交換のはたらき』にはいっています。ここでは交換の領域、すなわち市場(しじょう)が論じられます。
市(いち)の発生はそれこそ古代にさかのぼります。エジプトでもメソポタミアでも中国でも、はるか昔から市は存在しました。しかし、ブローデルが取りあげるのは、15世紀から18世紀における市の発展です。
都市では市からはじまって、市場(いちば)、商店が生まれます。イギリスやフランスで市が発展するのは16世紀後半からです。市は定期的に開かれ、次第に毎日開かれるようになって、それが市場となりました。パリでは、周辺の地域から魚介類や肉類、小麦、ワインが運ばれてきます。
その市場から独立するかたちで、商店も誕生します。パン職人、肉屋、靴職人、鍛冶屋、仕立屋などが店をだすようになります。さらに、自分ではものをつくらず、ほかから商品を仕入れて、ものを売るだけの商人もでてきます。金物商、薬局、質屋、両替商、宿屋、居酒屋なども登場します。
17世紀後半になると、商店は目をみはるほど増殖していきます。高級店は室内装飾をほどこし、ショーウインドウに商品を並べ立て、道行く人びとをひきつけます。
商店は街路を浸食し、ひとつの地区から他の地区へと進出していきました。すでに一種の消費社会が生まれようとしていた、とブローデルは書いています。
商店が躍進した最大の理由は、信用売買にありました。小売店は、顧客とりわけ裕福な顧客に掛け売りをしました。掛け売りをするというのは、一種、資本家の立場になるということであり、貸したカネを回収できない危険性もありました。とはいえ、信用貸しの連鎖こそが商業の基本だった、とブローデルは指摘しています。
市場が浸透していったのは都市だけではありません。近世のヨーロッパでは、人口の8割か9割かが農民で、農村社会はまだ自給自足状態にありました。そこに、ごくわずかの商品を背負った行商人たちが、続々と入っていきます。かれらは市場拡大の担い手でした。
18世紀になると、市場制度は完全に確立します。西洋がアジアにたいして優位を占めるようになったのは、直接、国家が市場を制御するのではなく、いわば合理的な市場制度が認められ、それが発展したからではないか、とブローデルはみています。
市場が発展すると、それを束ねる機構も必要になってきます。当初、その役割をはたしたのが大市で、ここには地域の都市や農村から多くの産品がもちこまれるとともに、多量の為替手形が決済され、負債が相殺されました。なかでも有名なのは、ジェノヴァ人が主宰したピアチェンツァの大市です。
ピアチェンツァの大市は16世紀末から17世紀初頭にかけて栄えましたが、その後、商業と金融の中心はアムステルダムへと移行していきます。アムステルダムの強みは、資本市場としての取引所を有していたことと、商品の流れ(アジアの胡椒、香辛料、バルト海沿岸の穀物その他)を把握していたことです。アムステルダムでは卸売業が発達し、倉庫が整備されていました。
アジアや大西洋の交易を掌握する国が勃興します。18世紀はイギリスの時代です。ロンドンでは、多数の倉庫をもつ卸売商人が大きな力をもつようになりました。トマス・グレシャムがロンドンに取引所をつくるのは16世紀後半ですが、それはのちに王立取引所となります。
1695年には王立取引所で、東インド会社やイングランド銀行の株も取引されていました。やがて、1700年ごろには王立取引所から分離されるかたちで、証券取引所が生まれました。
金属貨幣はつねに不足がちでした。そのため、為替手形が必要となり、さらに公債証書や銀行券、さらに紙幣が加わるようになるのですが、それを支えたのが銀行や証券取引所の信用でした。活発な市場経済は、そうした信用制度がなければ、とても無理だったでしょう。
ヨーロッパ以外でも、文明のあるところ市はありました。
イスラム世界では、イスタンブルでもバグダッドでもカイロでも、バザールでありとあらゆる商品が売られていました。
インドでも、あらゆる村に市があり、都市にも市と商店が密集していました。行商の人数も半端ではなく、鍛冶屋などの巡回職人が都市や村を回っています。
中国では村に市はなく、市があったのは町で、町の市は週に2、3回開かれていました。農民は市にでかけ、こまごまとした商品を買って村に帰ります。行商人や仲買人は、ひとつの市から別の市へと、たえず渡り歩いていました。
遠距離商業は大きな利益を生みだしました。アルメニア商人はペルシアとインドのあいだを行き来しており、時にチベットのラサや中国の国境まで足を延ばしていました。扱う商品は銀、金、宝石、ジャコウ、藍、毛織物、綿織物、ろうそく、茶などです。
この時代、ペルシャやイスタンブル、アストラハン、モスクワでもインド人商人の姿を見かけたといいます。インドではすべての集落に両替商を兼ねる銀行家がいました。インド人銀行家のなかには信じられないほどの金持ちがいて、運送も引き受け、織物の手工業生産にも携わっていました。
ブローデルは西洋と非西洋との隔たり(分岐)は、そう昔からではなく、遅い時期(18世紀末から19世紀はじめ)にはじまったのだと述べています。ヨーロッパとアジアでは商業が同じように発達していたのに、なぜヨーロッパがアジアを圧倒するようになったのかは、大きな研究テーマといえるでしょう。
近世になると、商業のルートは複雑な網の目のようになって、世界じゅうに張りめぐらされるようになります。しかし商品はすぐに貨幣と交換されるとはかぎりませんから、為替手形が用いられ、それ自体が取引の対象となっていきます。
初期の商業は、メディチ家にしてもフッガー家にしても一族経営が一般的で、多くの手代が使用されていました。商人の一族はそれぞれ対立したり協調したりしながら、商圏を築いていきます。アルメニア商人やユダヤ商人のネットワークも世界じゅうに広がっていきます。ポルトガル商人はスペイン領アメリカに勢力を伸ばしました。
ところで、ブローデルは、ここで商業剰余価値という、マルクスが無視した独特の概念を導入しています。商業剰余価値は、商品は移動するたびに、その価格が上昇していくという、ほぼ例外のない原則から生じます。
たとえば、1500年ごろ、ヴェネツィアの商人は銀貨や鏡、ガラス玉、毛織物などを船に積んで、アレクサンドリアに向かいました。これを売ったあと、商人はアレクサンドリアで、胡椒や香辛料、薬種を買って、ヴェネツィアに持ち帰ります。このプロセスではふたつの需要とふたつの供給があり、行きと帰りの環があり、その環が完結すると商人の活動は終了し、最終的にその商業剰余価値、すなわち利益が確定されることになります。
商品には輸送に要するコストがかかるというだけではありません。遠くに運ぶことによって利益が生じなければ、商売をする意味もなかったのです。
とはいえ、競争相手がいて、商品があまりに大量に入荷したり、持ち帰った商品の品質があまりよくなかったりしたときには、その商品が値崩れを起こし、商人のもくろみが失敗に終わることもありました。つまり、予見したとおりに商業剰余価値を実現するのは、容易ではなかったわけです。
ブローデルは供給と需要の関係についてもふれています。
商品交換の刺激となるのが、供給と需要の相関関係であることはいうまでもありません。このことも、往々にしてマルクスが軽視した点でした。
セビーリャの船は、イドリア(スロヴェニア)の水銀、ハンガリーの銅、北欧の建築用材、毛織物、綿・麻織物、植物油、小麦粉、ブドウ酒などを満載して、新世界へと向かいました。持ち帰るのはアメリカの鉱山で産出する銀の延べ棒です。
さまざまな商品のかたちで、スペインの輸出に投資した商人は、その見返りが銀で支払われることを期待していました。国王と国家の介在するその取引は、実際には略奪といってもいいほどの、著しい不平等交換で、ヨーロッパに圧倒的な利益をもたらしました。
遠方交易は巨大な富をもたらす可能性がありました。ヨーロッパの優位性は、地中海交易の発展をバネとして、アメリカとアジアへの交易路を開いたことにあったといえるでしょう。それが資本主義の勃興につながっていきます。
ここで、需要についていうと、人の欲求はかぎりなく、潜在的な需要は常に存在します。しかし、15世紀から18世紀にかけて、庶民の需要はその9割が食べることに向けられていました。わずかな賃金は、手から口へと、たちどころに食べ物に換えられていきます。
小麦、米、塩、木材、織物などは、根源的な需要であって、それを満たすためなら、人はいかなる労働も苦とはしませんでした。
奢侈品には流行がありましたが、それが激烈な欲求を呼びさましたのも事実です。ひと時代前の胡椒につづいて、近世は砂糖、リキュール、たばこ、茶、コーヒーなどがそうした商品でした。
15世紀末に、ヨーロッパの富裕な人びとは豪奢な毛織物を捨てて、絹織物に乗り換えたといわれます。絹は100年以上にわたって、イタリアに繁栄をもたらしました。17世紀の最後の四半世紀は、イギリス産の毛織物が流行し、そして18世紀にはいると、こんどはインドの更紗がもてはやされます。
需要に比べれば、供給は柔軟性を欠いています。この時代、経済の根幹は農業です。18世紀前半、イギリスでは農業生産性が飛躍的に増大しました。同じく1600年から1800年のあいだに、工業もまた少なくとも5倍の規模になった、とブローデルは推測しています。そして経済障壁の撤廃が流通をうながしたことも、生産を刺激する要因となりました。
ここでブローデルは、供給が需要をつくりだすというセーの法則についてもふれています。たしかに、商品を生産するとなると、その過程において金銭の分配が生じます。資本家は原料を買い付け、運送費を払い、労働者に賃金を支払わなければならないからです。すると、支払われた金銭は、購買のかたちで、市場にふたたび姿をみせます。つまり、供給が需要をつくりだしているわけです。
1930年代になって、ケインズはこのセーの法則を批判しました。供給の受益者が、即座に需要者としてマーケットに姿をあらわすわけではないと考えたのです。
15世紀から18世紀にかけては、下層階級ほど通貨の流通速度は速かったといえるでしょう。金銭はたちまち手から離れ、食べ物へと変わっていきました。この時代、労働者の賃金を決定するのは食料品価格であって、労働者はみずからが生産した手工業製品の消費者ではありませんでした。
この時代の企業家は、発注がなければ、事業を起こすことはありませんでした。無から新しい需要をつくりだそうという発想が生まれるのは、産業革命が起こり、商品の価格が安くなり、それが購買力を引きだすことができてからです。
15世紀から18世紀は、まだ商品は必要にもとづいてつくられており、そのかぎりにおいて、供給が需要をつくりだすというセーの法則はあてはまらなかった、とブローデルは論じています。
ブローデルをめぐって(5)──商品世界ファイル(13) [商品世界ファイル]

近世の物質文明の締めくくりとして、ブローデルは貨幣と都市について語ります。
貨幣は交換の道具であり、消費を支える道具でもあり、また消費・交換・生産をつなぐコードでもあるという言い方をしています。
古代にも貨幣はありました。しかし、15〜18世紀にいたっても、貨幣はまだ完成の域に達していませんでした。貨幣はどちらかというと新奇な存在で、まだいくつかの地域、分野にしか浸透していませんでした。
しかし、貨幣にはそれまでの生活スタイルを変える力をもっていました。その貨幣を供給していたのが国家です。そして、貨幣はいやおうなく日常生活のなかにはいりこんでいきます。
それぞれの地域にそれなりの貨幣制度がありますが、ここではやはり近世ヨーロッパに焦点を当てることにしましょう。善かれ悪しかれ、それが世界を引っぱっていったことはまちがいないからです。
近世のヨーロッパでは、貨幣が徐々に社会に浸透していました。金・銀・銅の金属貨幣があり、さらに前貸しや為替手形にいたる信用制度が発達していました。こうした金融制度はヨーロッパ域内にとどまらず、世界じゅうに網の目を広げようとしています。それを支えていたのは、アメリカ大陸から補給される大量の貴金属だったといえるでしょう。
金銀銅の貨幣はそれぞれの役割を果たしていました。金貨は王族貴族や大商人、教会がもっぱら用い、銀貨はふつうの取引に利用され、銅貨は貧乏人が日常品を購入するために使っていました。金と銀の比率は、その流入量によって、大きく変化しています。
ヨーロッパにおいて、当時、貨幣の問題はふたつでした。ひとつは貴金属が外に向かって流出していくこと、もうひとつは貴金属が貯めこまれて、社会から消えていくことでした。
金や銀はインド諸国や中国に流れていました。それはローマ帝国以来の構造で、ヨーロッパは絹や胡椒、香辛料、麻薬、真珠などの代価を支払うのに、金や銀をあてるほかなかったのです。
もう一つの小さな流れはバルト海経由のもので、西ヨーロッパは東ヨーロッパから小麦、木材、ライ麦、魚、皮革、毛皮を買い入れて、金属貨幣で支払いをすませていました。
貨幣が不足しがちだったのは、貴金属が貨幣のまま蓄蔵されたり、金銀の家具や装身具に変えられたりしたためです。さらに、16世紀末期から17世紀初頭にかけて創設された銀行が、貨幣の蓄蔵に輪をかけました。
金銀の交換比率が常に変動していたことも問題でした。国家はそれを固定しようとしましたが、どうしても無理がありました。
アメリカ大陸から貴金属が大量に流入すると、貨幣量が増大し、貨幣の流通が加速して、それが経済を刺激し、インフレが生じるようになります。ところが、そのいっぽうで、奇妙なことに、貨幣が不足するという現象が生じていました。
貨幣の不足を補うために、紙幣や手形が導入されるようになります。紙幣や手形は信用の道具です。信用は昔からある決済方法でした。ヨーロッパでは、為替手形は13世紀、銀行紙幣は17世紀半ばに登場します。
しかし、何といっても安定した紙幣発行に先鞭をつけたのは、1694年に設立されたイングランド銀行だといってよいでしょう。フランスでフランス銀行が設立されるのは1801年と遅れるますが、それはジョン・ロー(1671〜1729)によるミシシッピ計画の失敗がトラウマとなったからでした。
紙幣の発行は、その後の近代資本主義の発展に大きな影響をもたらします。
貨幣とは消費財を手に入れるための証書にほかならない、と定義したのはシュンペーターですが、貨幣はいわば世界の共通言語でもありました。
ブローデルはこう書いています。
〈外洋航海のように、あるいは印刷術のように、貨幣と信用とは技術である。それも、おのずから繁殖し、永続化する技術である。この両者は、単一かつ同一の言語なのであって、いかなる社会でも、それぞれの仕方でその言語を話しているから、あらゆる個人がその言語を習わざるを得ないのである。〉
こうして、貨幣という世界共通の言語は、次第に世界を席巻していくことになります。
貨幣は古代から存在しましたが、その点は都市も同じです。都市が生まれるとき、歴史がはじまる、とブローデルは書いています。それは分業と商業のはじまりであるだけではなく、文明と国家のはじまりをも意味しています。商品世界は貨幣と都市の成長を前提としているといってもよいでしょう。
中世末期のドイツには、3000の自治都市があり、その平均人口は400だったといいます。フランスでも18世紀初頭に人口900の小都市はざらにありました。これらの小都市は、太陽都市ともいうべき大都市の周囲にちらばっていました。
人口400以上を都市とするなら、イギリスの都市人口は1500年に全人口の10%、1700年に25%に達しています。イギリスにくらべれば、ロシアの都市化率は、きわめて低かったといわねばなりません。これにたいし、日本の都市人口の比率は1750年段階で22%でした。
しかし、都市は単独では生きていけず、農村が都市を支えなければなりませんでした。都市と農村は完全に分離されていたわけではありません。都市のなかにも菜園やブドウ畑が広がり、馬や豚が飼育されていました。また農村でも、蹄鉄工や鍛冶屋、車大工などの職人がおり、織物などもおこなわれていました。
都市は常に補充の新来者を求めます。たとえば、パリで筋肉労働に従事するのは地方出身者でした。かれらは自由と賃金を求めて、パリにやってきます。富裕な商人や有名な教授、建築家、画家なども集まってきます。
15世紀から18世紀にかけて、ほとんどの都市は、安全を守るため、城壁を築くようになりました。城壁がなかったのはイギリスと日本、それにそれ自体が島であるヴェネツィアくらいのものです。北京の城壁は、ヨーロッパ諸都市の城壁を凌駕していました。
都市にはそれぞれ存在理由がありましたが、どの都市にも例外なく市(いち)がありました。市は週ごと、あるいは日ごとに立ち、毎日の生活の糧を供給しました。大都市には多くの商品が流れこみ、その途中に宿駅や港が配置されています。
都市についてもうひとついえるのは、都市はそれぞれが文明の所産だということです。イスラム圏にはイスラムの都市のかたちがあり、中国には中国のかたちがあります。
西ヨーロッパの諸都市の特徴は「自由を導きの星としてきた」ことだ、とブローデルはいいます。領域国家にたいして、できるだけ自立を保とうとしてきたのです。貴族と有産市民、金持ちと貧乏人のあいだで争いはたえませんでしたが、それでも市民は自分たちの住む都市に愛着をもっていました。
西ヨーロッパでは、16世紀以降、大都市が生まれました。国家は首都を定め、首都の整備に力を注いでいます。その代表がロンドンとパリ、ナポリで、やがてアムステルダム、ウィーン、ミュンヘン、コペンハーゲン、サンクトペテルブルクなどが後につづきます。アメリカの都市はイギリスの植民地で、ずっと立ち後れていました。
以前から巨大な規模を誇っていたのが、中東とアジアの都市です。たとえば16世紀のイスタンブルの人口は70万、18世紀の北京の人口は300万でした。インドでは、王族の移動に伴い、都市は興隆したり没落したりしました。
ヨーロッパの都市とかたちが似ていたのは日本で、1609年の段階で江戸の人口は50万人、京都は40万人、大坂は30万人でした。日本の17世紀はフィレンツェ風の様相を帯びた町人の世紀だった、とブローデルは評しています。
1530年に3万だったアムステルダムの人口は、18世紀末に20万人に達しました。ここはユダヤ人移民やユグノー難民などの極貧者が住む町でもあります。
パリでは18世紀に市壁が取り壊され、ほうぼうで広場が整備されました。パリを支えていたのは国王と貴族、役人、金持ち、商人、聖職者、その他大群の民衆です。都市の富は快楽を引き寄せます。
汚らしくて豊かな、活気と陽気にあふれた町、ナポリの人口は18世紀末には50万で、ロンドン、パリ、マドリッドにつづくヨーロッパ第4の都市でした。貧民区が広がり、ここには10万人以上がつめこまれていました。この貧民大衆のうえに、貴族や聖職者、役人、裁判官などの特権階級からなる上流社会が鎮座していました。
サンクトペテルブルクは18世紀以降、ピョートル大帝の意思によって建設されました。中央にネヴァ川が流れる水面すれすれの土地は、しばしば洪水に見舞われましたが、エカテリーナ2世は大工事をおこなって、サンクトペテルブルクを堅固で美しく、しかも活気のある都市に変えていきます。
しかし、何といってもロンドンに触れなくてはなりません。
ロンドンは1666年の大火により荒廃しました。その後、行き当たりばったりで復興し、そのさい、多少の整備がなされています。商業の町にちがいありませんが、同時に王室に依存する町でもありました。その人口は1700年に70万、18世紀末に86万へと増加していきます。
ロンドンを支えていたのはテムズ川です。そのいくつもの埠頭には石炭やワイン、鮮魚、その他、数え切れないくらいの物資が運ばれてきました。テムズ川にはロンドン橋しかかかっていませんでしたが、橋の両側には商店が立ち並んでおり、南側には酒場と劇場、それに監獄が並んでいました。いっぽう北側にはセントポール教会とロンドン塔が立っていました。
17世紀から18世紀にかけて、ロンドンは同時に四方八方に伸びていきます。そのうち東部などの周辺街区はしだいにプロレタリア化し、アイルランドからの貧民や中部ヨーロッパ出身のユダヤ人も迫害を逃れてやってくるようになります。
ロンドンでは基本的な清潔や治安が確保できなくなっていました。火災や洪水の危険性もありました。食料補給も大きな問題でした。「すべてが数に、多すぎる人口に由来していた」と、ブローデルはいいます。
それでも、巨大都市には長所もありました。「巨大都市は近代国家によって作りだされたのだが、それと同程度に、巨大都市が近代国家を作りだした」とブローデルは書いています。
巨大都市は全国的市場をつくりだす原動力となったのです。
巨大都市が資本主義と近代文明の核心に位置していることはまちがいありません。都市に集まるのは虚妄の富にすぎない、とルソーは論じました。それが、ある程度真実であることをブローデルも認めています。しかし、資本、余剰が都市に蓄積されるとともに、都市化はますます進んでいくことになります。



